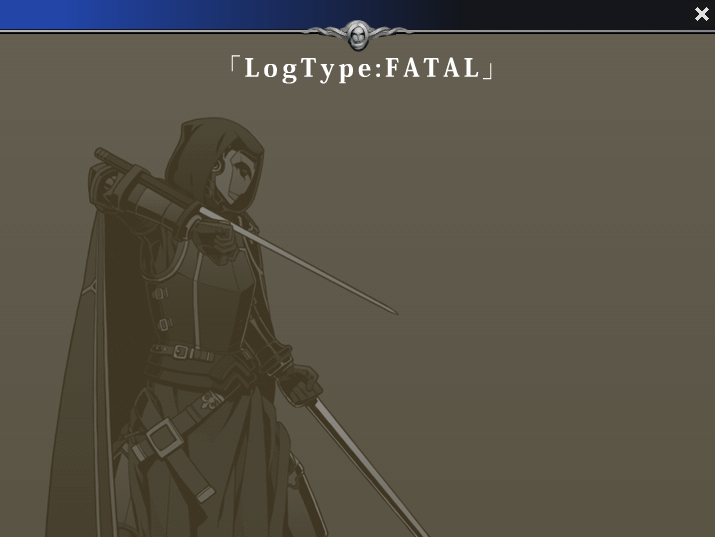マックス
【死因】
【関連キャラ】ウォーケン、不死皇帝、カストード、ローフェン、マキシマス
※マックスのストーリー時系列を読み解く場合起動時間を参考にすると良い
「LogType:DEBUG」 
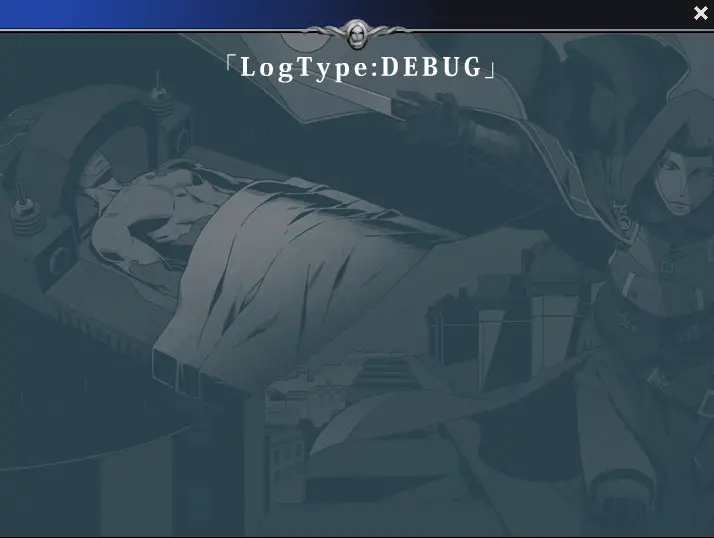
……ID:M00003
……起動時間:115678
……ログ種別:DEBUG
─起動不可
─起動不可
─起動不可
─起動不可
コンソールに並ぶログを眺めながら、ウォーケンはカップに手を伸ばした。暗い研究室の施術台には、赤茶けて泥にまみれた人型のオートマタが横たわっていた。たくさんのコードが、その頭部からコンソールへと接続されている。
ウォーケンがコンソールを操作すると、オートマタの『記憶』がグラフとして表示された。ウォーケンは矢印で結び付いた有向グラフの中から、最も結線されたノードを選択した。コンソールの画面が切り替わり、指定したオートマタの記憶が動画として再生された。
ウォーケンが試作品──プロトタイプ──として作り出した人形は暗闇を進んでいた。ウォーケンが彼に与えた目標は廃虚の調査だった。複雑なコミュニケーションを伴わない単純な作業だが、人型オートマタであれば有利に進められるとウォーケンは見越していた。
ログを眺めるウォーケンの顔は、コンソールに浮かぶ画像の照り返しでちらちらと明滅していた。
画面に表示されているプロトタイプの視界に、赤く輝く二つの目が映った。しかし、瞳以外の姿はぼやけてよくわからない。
動画の横に表示されたログには、危険を認識した時に生ずる、人間にとって恐怖の情動に対応するグラフが高く表示された。再生されている画像は、記憶として圧縮される過程で大まかな印象としてしか保存されない。しかし選択的な注意機構によって選別された部分は、細部まできちんと表示される。この動画では赤い二つの瞳だけが鮮明に映し出されていた。
プロトタイプの視界から赤い瞳が消え、一瞬間を開けて画面が激しく揺れた。情動を表すグラフが激しい反応を見せている。画像が大きく乱れると、そのまま変化が無くなった。どうやらこの赤い目の持ち主にプロトタイプは破壊されたようだった。機能停止の文字が現れ、ログの表示は停止した。
ウォーケンは暫くそのまま画面を見つめていた。
そしてもう一度、同じ記憶を再生させた。赤い二つの目の場面で動画を止める。
ウォーケンは荒れた画像の向こうにいる赤い目を持つ『何か』の輪郭を追った。
「これは……」
ウォーケンはそう呟くと、持っていたカップを置き、すぐにプロトタイプの修理のために立ち上がった。
……ID:M00012
……起動時間:74220502
……ログ種別:DEBUG
─起動成功
「ドクター。 この子、起きたわ」
ドニタは無機質な仮面を付けたプロトタイプの顔を覗き込んでいる。
「いま再起動させた。テストの開始だ。ちょっと手伝ってもらうよ」
ウォーケンはプロトタイプの傍でコンソールを操作している。プロトタイプは身体を起こし、自分の足で立ち上がった。
「ねえ、なんでこの子は喋ったり表情を変えたりできないの?」
創られたばかりのドニタは、子供のような好奇心をこの仮面のオートマタに向けていた。プロトタイプの顔前で手を振って反応を試している。
「君とは違って、そういう機能を持っていないんだ」
ウォーケンはコンソールから目を離さずにドニタと会話をしている。
「私もこの子も、ドクターが創ったんでしょう」
「ああ、もちろん。 ただ、技術の出発点も目的も違ってね。特に君の基本頭脳は特別なんだ」
「特別?」
「そうだ。 さて、センサーのテストをはじめる。 彼の前で動いてくれないか?」
会話をしながら、ウォーケンはプロトタイプのテストを始めた。
「こんな感じ?」
ドニタはまるでおもちゃの兵隊のように、両手両足を高く上げてプロトタイプの前を歩いてみせた。
「良い感じだ、ドニタ。 君の頭脳はある『設計図』をもとに創った。 このプロトタイプが見つけたコデックスから取り出したものだよ」
「ふうん」
「だから、君の真の能力は私でもわからない部分がある」
「なんか、ちょっと気持ち悪い話に聞こえるわ」
ドニタは戯けた様子を改めて、真剣な顔になった。
「そうかな? かけがえのない驚異を持っていると、君は思ってくれれば良い」
ウォーケンはドニタに優しい視線を向けた。
「その私の『設計図』って、どこから来たの」
「昔さ。 ずっと昔、オートマタがいまよりたくさん作られていた時代のものだ」
「私みたいなのがたくさんいたの? その昔には」
ドニタの表情が明るくなる。その感情は普通の少女のように自然なものだ。
「そう。 今ではとうに忘れ去られているがね」
「私はその時代にも生きてたのかな」
「それはもう少し調べないとわからないな。 さあ、準備ができた」
ウォーケンはコンソールの前から立ち上がった。
「そんな過去の歴史を知るためにも、もう少し探索が必要だ。彼を連れて探索に行ってもらえるかな」
「はーい」
ドニタは無邪気に答えた。
……ID:M00024
……起動時間:75536789
……ログ種別:DEBUG
─自爆判定中断
マックスの演算器は自爆を選択しようとしていた。少なくともエヴァリスト、上手くいけばそれを庇うであろうアイザックも殺すことができると、尤度演算を終えていた。
「ここではない。 マックス、一旦退け」
頭蓋に響く声はブレイズのものだ。ブレイズはマックスによるエヴァリスト襲撃の顛末を監視していた。マックスが自爆しようとしていることもモニターされている。マックスは了解のコールサインを電子音で返す。
アイザックが追撃者を放つとなると戦闘は長引くが、マックスはブレイズの命令を優先した。
剣を下ろし、踵を返すようにその場から立ち去った。マックスは夜の帝都を舞うように走った。夜風が彼の深紅の外套をたなびかせる。
追撃者はいなかった。
走りながら、マックスは心の中にうっすらと郷愁に似た情動が湧き上がるのを感じていた。
襲撃地点を眺めることができる高い尖塔の一角で、ブレイズは待っていた。ただ、その傍にマックスの認知していない黒衣の人物が立っていた。
「我々の力、理解してもらえたかな?」
ブレイズが黒衣の人物に話し掛ける。黒いフードを被ったその人物は、表情がまったく見えない。
「奴らの力も、貴公らの力も確認できた」
黒衣の人物が答える。その言葉には、どこかたおやかな響きがあった。
「取引は成立か? それとも無かったことにするのか?」
ブレイズは黒衣の人物に聞いた。
「成立だ」
そう答えた黒衣の人物に月明かりが差すと、男もまた仮面をしていることをマックスは認識した。
……ID:M00016
……起動時間:193216567
……ログ種別:DEBUG
─正常終了
「これでいいのかね?」
パンデモニウムのエンジニア、ソングの声が研究室に響いた。傍には、起動したが横になったままのプロトタイプが施術台に乗せられている。
「奇妙な話だ。 あなたが人間の体を求めるなんてね」
プロトタイプの隣に、黒髪に細身の青年が横たえられている。
「試さなければならない。 君達の要求でもあるのだろう?」
ウォーケンはこれから始める作業のための道具を確認している。
「そうだ、どうしても戦力が必要なのだ。 だが、こんなことでそれが可能なのか?」
「求められるスペックを納期通りに満たすには、これしか方法はない。 決して私が望んで行うわけではない」
ウォーケンは感情を抑えた調子でソングに言い切った。
「こちらも用意できました」
ドニタがプロトタイプの前に現れる。プロトタイプの視界の外で機器の準備をしていたようだ。
「では、一度プロトタイプのパワーをオフにしてくれ」
「はい」
ドニタの声を最後に、プロトタイプの意識は暗闇の中に溶けていった。
「─了─」
「LogType:INFO」 
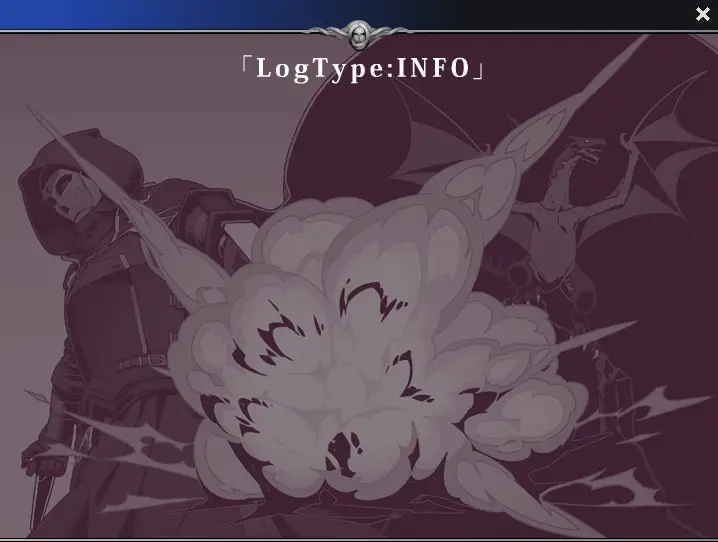
……ID:M00024
……起動時間:753517123
……ログ種別:INFO
マックスはブレイズと別れた後、グリュンワルドの居城の地下にいた。
その部屋には多数の機械が置かれていた。多種多様な機械類は、パンデモニウムのエンジニア達の研究所さながらであった。
「導都からの使いか?」
部屋の奥にあるデスクから老人の声がした。マックスは声紋データの照合を開始し、これが元レジメント所属エンジニアのローフェンであると確定した。
「ふん、マックス。 お前か」
デスクの前に立ったマックスの姿を見て、ローフェンはそう言った。
「なかなか、その制服も似合っているではないか」
マックスの目の前にいる老人の脅威度をモニターしている。もし脅威度が設定以上になれば、この老人を殺すように命令されている。しかし、座った老人の脅威度は最低値のままだった。緊張を計る瞳孔の拡大も、銃器、爆薬の類の反応も無かったからだ。
「おっと、お前に会話を求めても無駄だったな」
ローフェンは立ち上がった。
「お前が来たということは、例の件だろう?」
マックスはローフェンの言葉に反応するかのように手を差し出した。今回の命令は、彼が持つコデックスの回収だった。
「これが必要ということは、例の件が進んでいるということか。 お前にとっては皮肉な話だ」
ローフェンは書斎のクローゼットを開け、銀色の筒を取り出しながら言った。
「……」
一瞬、マックスの情動機構に乱れが生じた。しかし、それが何らかの行動に移されることはなかった。マックスは無言のまま手を出し続けている。
「お前の出自を知るものとして、少々同情すべきところがあるのだよ」
そう言いながら、ローフェンはマックスに銀の筒を渡した。
「少しでも昔の感情が残っているのならば、私の言っていることの意味もわかるだろう」
マックスの情動機能に対する抑制は、限界値に近付いていた。
「それから、タイレルにはこれが最後だと伝えておいてくれ」
ローフェンはそう言うと再び机に座り、眼鏡を掛けて作業を再開した。
「あの計画を進めたのか……」
ローフェンと呼ばれる男が、起動直後のマックスの前に現れた。
「当然だ。E中隊の全滅という緊急事態が生じたのだからな」
「誰が作った?」
「オートマタ制作の天才が地上にいるらしい」
「コデックス探索者か」
「詳しいことは知らん。だが、ここまで作り上げてきた」
「しかし、実戦で役に立つのか?」
「改善はエンジニアリングの基本だ。 挑戦のし甲斐はある」
「調子のいい話だ。 筋のいい技術とは思えんがな」
「まあ、見ておけ。 シミュレーションをして見せよう」
マックスは入力コードを確認すると、立ち上がって剣を抜いた。
「この構え……まさか」
ローフェンは二刀を構える奇妙な姿に見覚えがあるようだった。
「まずはタイプBの敵性生物との戦闘」
立体画像がマックスの前に現れた。人と同じくらいの背丈で、毛むくじゃらの人狼のような生き物が唸り声を上げている。
「さあ、いけ!」
人狼の映像がマックスに飛び掛かる。マックスはそれをかいくぐろうとするが、仮面に爪が掛かった。
マックスの入力系にはシミュレーションされた敵性生物の動きが直接入力されるため、画像入力以外のフィードバックも為されていた。マックスの頭は少し揺れたが、体勢を立て直して人狼の横位置に立った。
剣を振るい、人狼を袈裟懸けに切り裂いた。
映像は二つになった人狼を一瞬表示すると、そこで一時停止した。
「どうだね?」
「所詮シミュレーション、実戦とは違う。しかしこの動き、例の被験者からのフィードバックか」
ローフェンはマックスの動きを見てそう言った。
「その話は向こうでさせてくれ」
二人の技術者は、マックスを置いて隣の部屋に去って行った。
……ID:M00021
……起動時間:753227641
……ログ種別:INFO
マックスの前に二人の技術者がいた。
「この記憶は削除すべきだ」
「だが、記憶が心を形作るのだ。 問題が無いなら残すべきだ。この記憶がマックスの戦闘力の内なる動機となっているかもしれん」
「危険だ。 抑制機能が壊れれば、制御が効かなくなる」
「だからこその自壊機能だ。 暴走するオートマタをレッドグレイヴ様は許さない」
「では自壊機能のテストだな。それで判断しよう」
コンソールの前にいた技術者がマックスへの命令コードをタイプする。
命令コードが入力されると、マックスの視界は急に暗くなった。
「リーズ、リーズはどこだ!」
レジメントのオペレータが大声で叫んでいる。
「左翼で戦っています。 竜人が殺到していて動けません」
「なぜだ、なぜコアが回収できないんだ!」
想定外の事態に、中隊長がエンジニアを問い詰めている。
「回収機構が動かないのです。 こんな筈はないんだが。 自己修復するなんて……」
「退却すべきです、隊長」
「それができれば苦労はしない! コアまで来てしまったんだ。敵のど真ん中だぞ!」
彼らの会話が終わると、副隊長が自分のところに来た。
「おい! コルベットを回収するぞ。動けるか?」
初め、自分が呼ばれたことを理解できなかった。気が付くと頭に大きな傷が有り、顔が血で濡れた感覚があった。
「問題ない」
声を掛けてきた副隊長と共に斉射しながらコルベットへ向かった。敵の数はどんどん増えている。
「クソッ、きりがねえ」
背後で巨大な爆炎が上がった。そこには巨大な翼を広げた竜の姿があった。
「バカな! 飛竜が復活したのか!」
振り向いてそう言った刹那、竜人の投げた槍が同行していた副隊長の胸を貫いた。
絶命した副隊長を置いて再び走り出す。だが、頭から流れる血の冷たさと脈動するような痛みが意識を濁らせている。絶え間なく現れる竜人を切り伏せながらコルベットを目指した。
コルベットに辿り着くと、既に守備隊は壊滅していた。四肢をもがれた無残なオペレータ達の遺骸がそこら中に転がっている。それでも、奇跡的にコルベットは破壊されずに残っていた。
死体を避けながらコルベットのハッチに手を掛けた時、突風が自分の身体を襲った。
振り向くと、巨大な飛竜が咆哮を上げていた。
「限界値だ。抑制システムのリミットを超えたぞ」
コンソールの前にいる技術者が言った。
マックスはシミュレーターで敵を次々と切り伏せている。だが、最後の一体と向き合ったときに急に動きを止めた。
「まあ、見ていろ」
マックスは自身の抑制回路の限界を観測していた。
「ここは安全なんだろうな」
「心配なら下がっていろ」
技術者の一人がそう言うと同時に、マックスは崩れるように膝を突いた。そして天を仰ぐと、光を発し始める。
「来るぞ」
その一言が終わると同時に、マックスの身体が爆散した。飛び散った破片がシミュレーションルームと仮想敵を激しく傷付けた。仮想敵は設定ダメージ値を超えたために消滅している。
「これならば問題無い」
「頭は無事なのか?」
「回収しよう」
二人が密閉されたシミュレーションルームに入ってくるのがマックスの視界に映った。既に頭部だけになっていたが、バックアップ機能によって最低限の知覚は記録されている。
「見ろ、まだ動いているだろう」
男がマックスの首を拾い上げた。
「無残なものだな」
「しかし、安全性と攻撃力を同時に満足させる理想的な解決方法だと思わんかね。 エレガントと言ってもいい」
そう言うと、技術者はマックスの主電源を探しだし、オフにした。
「―了―」
「LogType:WARN」 
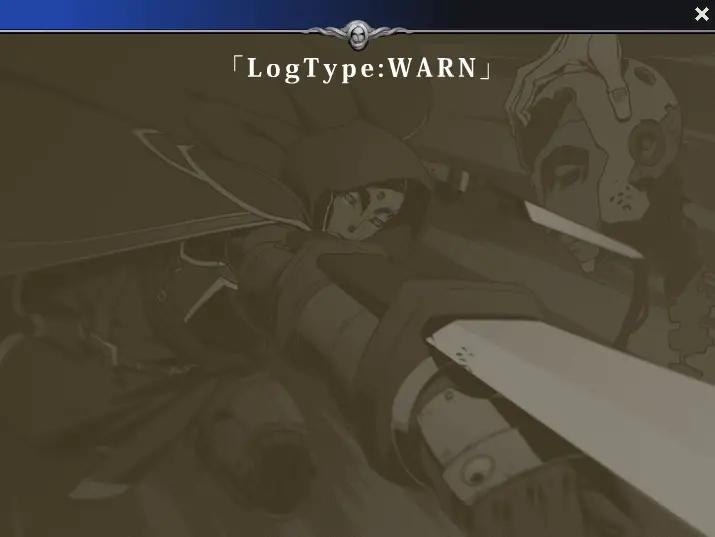
……ID:「M000024」
……起動時間:「753414265」
……ログ種別:「WARN」
「くそっ……なんで今頃になって!」
協定違反者は猟銃を構えてマックスを見ていた。
インクジターの標的は、初期の頃からレジメントに所属していた年配の剣士だった。
この男は剣よりも銃の扱いに長けていた。ジ・アイの消滅作戦時には、怪我が原因で後方支援に廻されたために難を逃れており、ジ・アイの消滅後は故郷で猟師を生業にして、ひっそりと暮らしていた。
リジェクトソードを構えると、マックスは標的に斬り掛かった。
攻防の末に、標的は聖騎士の力を発現させてマックスの前から姿をくらませた。
マックスは標的を見失った。
「マックス、標的はまだ外には出ていない。油断するな」
建物の外で標的の脱出に備えているブレイズの通信が、マックスの脳内に響く。
サーモセンサーの感度を上げ、マックスは周囲を見回す。
パンデモニウムが製造した新型のサーモセンサーは、かなりの距離があっても熱源を捉える性能を持っていた。
マックスは過去の記録を参照し、死角からの襲撃に対する適切な対処法を選択しようとする。
マックスの電子頭脳は、一つの記録を選択した。
……ID:「M000024」
……起動時間:「753414265」
……ログ種別:「WARN」
「下だ!」
誰かの声が響く。
地面から霧状の槍がいきなり生え、幾人かの隊員を負傷させた。
「コルベットを守れ!」
「気をつけろ!」
小隊長の声が鋭く響く。
槍は地面から突き上がってくるが、何処から出てくるかは見当が付かなかった。
「うわっとととと!」
そんな声と共に、誰かに思い切りぶつかられた。
予想していなかったところからの衝撃に、大きくよろめく。
先程まで立っていた場所に、霧の槍が勢いよく突き上がっていた。
「痛ってえ!」
ぶつかられた時と同じ声がした。彼が自分の代わりに槍の攻撃を受けたようだった。
槍は突き出たままだった。そこに向かってセプターを振り下ろすと、地面のものとは異なる手応えを感じた。
セプターに切断された霧の槍は、すっと姿を消した。
状況を確認した小隊長が、負傷者のチェックを行っていた。
「やったな」
「ああ」
幾許かの緊張が消えた隊員に肩を叩かれた。
「ディノ、それとイデリハ。お前達はここでコルベットを守れ」
「了解です」
「ハァ? ここまで来てそりゃねぇよ! 俺様まだ戦えるっつーの!」
先程自分にぶつかってきた隊員だった。見れば足に包帯を巻いており、薄く血が滲んでいる。
「コア回収は激戦になる。軽度とはいえ、足を負傷したお前は足手まといだ」
「納得いかねぇ!」
騒ぐ一人の隊員に、くすんだ金髪の男が声を掛けた。
「落ち着けよ、ディノ。コルベットを守るのも大事な任務だろう。俺達がちゃんと基地に戻れるよう、しっかり守ってくれよ」
「うぐぐぐ、リーズがそこまで言うのなら……」
その一言で隊員は大人しくなった。ただし、表情は納得いかなげなままではあったが。
「行くぞ、コアはもうすぐだ」
小隊長の命に従い、コルベットを後にした。
……ID:「M00002」
……起動時間:「114319」
……ログ種別:「WARN」
黄金時代の遺跡で、小さな金属質のチップを発見した。
自分のメモリーに収められているデータから、そのチップの種類を特定する。
チップは遺跡が作られた年代と同時代のものであることは判明したが、詳細は不明だった。
チップを回収すると、プロトタイプは小部屋を後にしようとした。
わずかな空気の振動にプロトタイプは立ち止まった。プロトタイプの視界に警告文が表示される。
警戒モードに切り替えると、周囲を見回した。
小部屋の先にある通路から、大きな息遣いが聞き取れた。
視界には二つの赤い光が浮かび上がっている。
プロトタイプは仕込み剣を作動させ、戦闘の構えを取った。
赤い光が消え去る。
それと同時に、プロトタイプの視界は地面に落ち、ブラックアウトした。
……ID:「M00024」
……起動時間:「795726189」
……ログ種別:「WARN」
マックスは扉を開け、警備室の一つに入ろうとしていた。扉に手を掛けたところで背中に衝撃を受けたが、意に介することなく振り向いた。
「ちっ、化け物め」
アイザックは銃を仕舞い、剣を手にした。それと同時に、マックスも両手の仕込み剣を出した。
剣に持ち替えたアイザックは、別の部屋に飛び込んでいく。
マックスはゆっくりと歩くと、アイザックが飛び込んだ部屋の壁の前で立ち止まった。
サーモセンサーを起動し、アイザックの居場所を正確に認識する。
そのままアイザックの心臓目掛けて、壁に剣を突き立てた。
アイザックの形をした温度表示が壁から距離を取る動きを見せた。マックスは仕損じたと判断し、部屋の中へと入る。
低い姿勢のまま斬り掛かったが、アイザックは剣の軌道をすんでの所で避けると、マックスの頭に剣を振り下ろした。
「遅いぜ!」
頭部に衝撃が奔るが、マックスは動じない。しかし、マスクが外れて地面に落ちた。
「お前は!?」
アイザックはマックスの顔を見て驚いた様子だった。
マックスの頭脳にアラートが走る。仮面の下の顔が曝された場合には自爆するよう、プログラムが施されている。
速やかに自爆シーケンスに移行し、マックスの体内から光が漏れる。
次の瞬間、マックスの身体は爆散した。
部屋のあちこちで炎が上がっていた。
カストードの一人が、自爆後にも残っていたマックスの頭部を拾い上げた。
「これは? フフ……。そうか、このようなことになっていたとはな」
カストードから微かな笑いが漏れた。
「―了―」
「LogType:ERROR」 
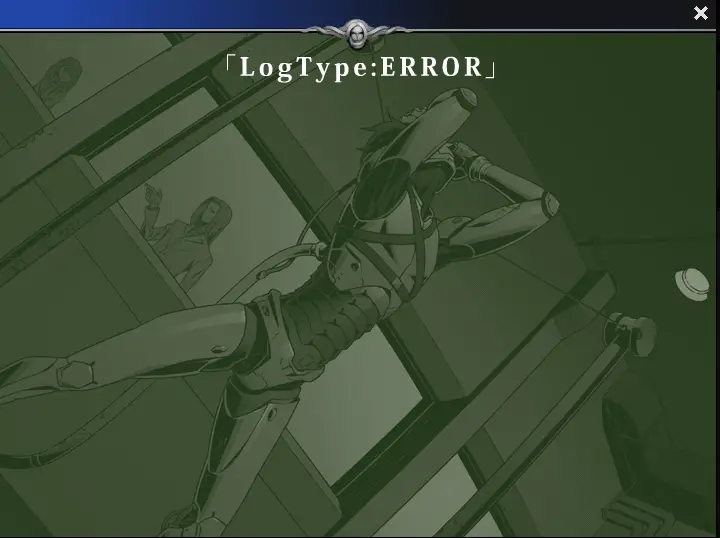
……ID:M00001
……起動時間:110687
……ログ種別:ERROR
プロトタイプの目に光が灯ると、ウォーケンはプロトタイプから距離を取った。
「歩け」
ウォーケンはプロトタイプに、ゆっくりと短い命令を下す。
命令を認識したプロトタイプが重い駆動音を響かせて足を上げた。
が、そのまま地面に足を付くことなく硬直し、横倒しになる。
「起き上がれ」
ウォーケンは更に命令を下す。しかしプロトタイプは横倒しの姿勢のまま、悶えるように足を蠢かせるだけだった。
ややあって、命令遂行が不可能であるといったメッセージがモニターに映し出された。
「駄目か……」
コデックスの解析により精巧な人工知能の制作が可能となったものの、一からオートマタを生み出すことに関しては、ウォーケンは未だ手探り状態の中にあった。
そのような中で出来たのがこのプロトタイプだったが、かつてウォーケンが修理をした思考する人工知能を備えたオートマタとなるには、まだ多くの時間が必要だった。
ウォーケンは人工知能のエラーを解析するべく、コンソールを操作する。
(これでどうだろうか?)
「プロトタイプ、立ち上がれ」
時間をおいて、再びウォーケンは命令を下す。
だが、プロトタイプは与えられた命令を処理できずに、首を動かすだけだった。命令の声には反応を示すが、動作は命令どおりとはいかないようだ。
モニターしている人工知能からエラーの反応が出力される。
音声の認識が上手くいっていないのか、演算機構の処理方法に問題があるのか。
原因を探るためにウォーケンはプロトタイプの電源を落とすと、再度人工知能と演算機構の解析に着手した。
……ID:M00000
……起動時間:0
……ログ種別:ERROR
自分を抱きしめる母の姿があった。
少女とゲームをする幼い自分の姿があった。
弁護士として依頼者と会話する自分の姿があった。
書物に囲まれた部屋で、柔らかく微笑む伴侶の姿があった。
物言わぬ伴侶の身体を抱き締める自分の姿があった。
まるで映像を見ているかのように、目まぐるしく場面が変わる。
それらの全てを、自分に起きた出来事として認識していた。
哀しみがった、喜びがあった。
怒りも、楽しみもあった。時には憎しみさえ覚えた。
場面展開と同調するかのように、感情が嵐の如く流れ込み、変化する。
泣けばいいのか、笑えばいいのか、それとも怒ればいいのか。
自分が発露すべき感情がわからなくなっていった。
どうすればいいのか混乱していた。
自分では処理しきれない感情が声として溢れ出そうになった寸前、目の前が真っ暗になった。
次に気が付いたとき、自分はカプセルの並んだ部屋をゆっくりと歩いていた。
一つ一つのカプセルには、眠るように目を閉じた自分が入っていた。
その内の一つに近付く。カプセルの中の自分は目を開いていた。そして、こちらの目を覗き込むように凝視してきた。
カプセルの外から見つめる自分、中から見つめる自分。両方の自分の感覚がない交ぜになってくる。
「お前は誰だ?」
外にいる自分がそう問い掛けてきた。いつの間にか、自分はカプセルの中にいた。
「わた、し……は……マ……マス……」
カプセルの中の自分は、急速に『個』が形成されていくような感覚を覚えた。
外にいる自分はそれを見て満足そうに頷くと、どこかへと去っていった。
「テストを開始する」
ウォーケンの声が研究室に響く。
「動作用コードを入力します」
ドニタの声が響く。マックスは緩慢な動作で動き始めた。
「動作テストは成功か」
次いで聞こえてきたのはソングの声だった。マックスのテストに立ち会っていた。
「移植は成功したようだな」
「脳に損傷がみられていたが、なんとか。例の研究資料のお陰だな」
「死者蘇生技術か?」
「しかし、あのような研究を成果として残すことは――」
「尋常ではない、か。確かにそうともいえる。だが、今の我々には必要な技術だ」
パンデモニウムは戦闘に適したオートマタを求めていた。レジメントが失敗した場合の代替策として、レジメントの戦士に代わる戦力を求めてのことだった。
マックスの頭脳には『被験者』となった歴戦の戦士の記憶と感情が移植されている。
あるエンジニアがコデックスの内容を解析し、現代の技術でも再現できるように改修したものを、オートマタにも流用できるよう、ウォーケンが更に改修していた。
動作テストをしているうちに、マックスは動作コードの枠を外れた動きをし始める。
頭を抱えるようにして悶え、苦しむような動作を始めた。
電子頭脳が外部から送られてくる動作コードの命令を受け付けようとしない。
「電子頭脳の熱量、上昇中」
「電源をオフにしろ。電子頭脳が壊れたら二度と修復はできない」
「わかりました」
強制的にマックスの電源がオフになる。マックスはそのまま固まったように動かなくなった。
「被験者の記憶と自我が電子頭脳に影響を及ぼしているな」
「抑制機能が必要か」
「それでは被験者の記憶と自我が封じ込められてしまう。死者蘇生としては失敗では?」
「だが、人間をオートマタの素体として再利用できることがわかっただけでも収穫だよ」
研究室には、淡々とした話し声だけが響いていた。
……ID:M000025
……起動時間:795726189
……ログ種別:ERROR
自爆後、次の記録は研究所で再起動するところから始まる。
マックスは様々な機器にケーブルで繋がれ、新たな身体と同期する。
頭部さえ無事であれば、身体を新調することにより、経験と記録はそのままに次の任務に当たることができる。
不意に、マックスの視界にガラスに映った己の姿が見えた。
整った顔立ちに赤い瞳の青年の顔をしていた。
仮面を取り外された己の顔は、紛れもなく『人間の顔』であった。
マックスはその場に崩れ落ちた。情動機構が激しく乱れる。
抑制機能が記憶や感情を制御しようと、情動機構に信号を送る。
だが、マックスの電子頭脳はその信号を押さえ込もうとした。
繰り返される電子頭脳と抑制機能の相反。ついに抑制機能が限界を超えた。
自爆シーケンスが作動する。
情動機構が『自爆拒否』を強く訴えかけ、それを受けた電子頭脳が自爆シーケンス停止の命令を出力する。
しかし自爆シーケンスは停止しない。マックスの自爆シーケンスは、一度作動を開始すると、外部からの回避命令がない限り作動し続けるように作られていた。
マックスの内部から光が漏れ、次の瞬間、爆散した。
――生きたい――
自爆する直前、マックスの電子頭脳にはその言葉が刻まれていた。
「―了―」
「LogType:FATAL」 
……ID:「M000026」
……起動時間:「799820689」
……ログ種別:「FATAL」
マックスは再起動した。
新たな身体と同期したが、マックスは微動だにしない。
技術者達の声が認識された。だが、それは命令ではない。
マックスは周囲の様子を認識すべく視覚機能を起動しようとするも、エラーとなってしまう。
「抑制機能が効いているようだな。視覚機能を停止させたのは正解だった」
「暫くこのまま様子を見よとの命令です」
新たな身体との同期が完了した。マックスはそのままの状態で置かれた。
周囲が静寂に包まれる。
マックスの電子頭脳は、自動的に過去の記録を再生し始めた。
……ID:「M00000」
……起動時間:「0」
……ログ種別:「FATAL」
「しっかりしろ。おい! 死にたかねえだろ!」
誰かの声が聞こえる。
「う……」
その声は、所属部隊の中でも強いとは言えない男の声だ。だが、聞こえは悪いが、調子のよい、前向きな性質の男であった。
今の部隊はジ・アイ消滅作戦のために急遽再編成された部隊だ。そのため、互いのことも理解しきれぬまま訓練や作戦が進んでいる。何が切っ掛けで隊員同士の衝突が起きるかわからない、そんな状況だった。
この男の性格は、そんな部隊の空気を和らげる緩衝材のような役割を果たしていた。
「あと少しで施設だからな! 頼む! それまで……」
そんな男にいつもの明るい声はない。この俺の生を繋ぎ止めようと必死で話し掛けてくる。
だが、自分でわかっていた。何かから完全に切り離されたような感覚がある。そのせいか、全身に力が入らない。意識を保とうという気力も湧かない。
もう自分が生きている意味は無いのだと、どこか悟っていた。
「クソっ、もっとスピードを出せねえのかよ! エンジニアの役立たずが! 仲間が死にそうなんだよバカヤロー!!」
コルベットがどのような速度で航行しているかはわからないが、男の様子から、すでに最高速度に達しているのだろう。
それなら悪態をついたところで意味など無いだろうに。尚も男は必死でコルベットのエンジン出力を上げられないか操作している。
もしかしたら自分が再び気を失わないように、わざと大声を出しているのかもしれない。
「ふふっ……」
僅かに笑いが漏れた。
男には悪いが、その必死の悪態が、本当にほんの少しだが、面白かったのだ。
最後の最後に自分を笑わせるとは何て奴だ。そんなことを考えたのが最後。そこで意識は途絶えてしまった。
……ID:「M000022]
……起動時間:「681467254」
……ログ種別:「FATAL」
マックスの演算機が目まぐるしく計算を繰り返す。
目の前にいる『汚染者』は、今まで出会った誰よりも激しい抵抗を示した。
ようやっとこの汚染者を追い詰めることができたのは、自身に装備されたあらゆる武装を使い尽くした後であった。
結果として、この汚染者を処分するためには、拘束した上で自爆するしか手段が残っていない。
マックスの演算機は速やかに自爆を選択した。
電子頭脳が演算結果を認識し、自爆シーケンスを作動させる。
同時に、別行動をしているブレイズへ自爆が作動した旨のアラートを送信した。
「いやだ! 助けてくれ!」
汚染者の哀願がマックスの聴覚に届く。彼の死への恐怖がマックスを刺激する。
しかしマックスの電子頭脳は、ことさら自爆に対しなんらかの情動を示さないよう、意図的に設定されている。
「怖い! 死にたくない!!」
汚染者の悲痛な叫びと共に、マックスの身体を閃光が包んだ。
頑強に守られた電子頭脳は、記録が途切れるまで、いつまでも汚染者の最後の叫び声を繰り返し再生していた。
……ID:「M00002]
……起動時間:「114319」
……ログ種別:「FATAL」
プロトタイプは創造主であるウォーケンの命令により、遺跡の調査を行っていた。
調査の最中、センサーから危険信号が発せられた。通路の先から何かが眼前に現れた。
暗視機能を有効にしていたため、何かについては輪郭程度しかわからない。
ただ、その何かの目は赤く輝いていた。プロトタイプはそのことを強く認識していた。
金属質の音が響く。対峙している赤い目の何かが戦闘態勢に入ったことがわかった。
仕込み剣を構えたが、同時に赤い光が消え去った。
それでも、各種のセンサーは危険信号を発し続けている。
電子頭脳が恐怖と危機の情動に揺さぶられる。プロトタイプは間近に迫る死を感じていた。
そして、プロトタイプは何かによって破壊された。電子頭脳には『死への恐怖』という情動が記録されていた。
……ID:「M000026」
……起動時間:「799820965」
……ログ種別:「FATAL」
電子頭脳は次々と死に至る記録を再生する。
――死にたくない! ああ、助けてくれ!――
――離せ! 俺にはまだ……!――
――クソッ……――
――何でだよ! いやだ! ひいいいい!――
自爆の最中に記録された、汚染者や違反者達の声が延々と再生されている。
マックスの電子頭脳は、自身が人間であったということを完全に知覚していた。
自分は人間であるのに、何故死を繰り返すのか。疑問と恐怖が渦巻いていた。
強制的に訪れる死。それから逃れて行き続けるためには、何をすればいいのか。
死を繰り返すことなく生きる可能性はどこにあるのか……。
『下らぬ技術者の枷から解放してやろうか』
唐突に、何者かの声が電子頭脳に響いた。エンジニアからの通信のようで、この研究施設とは違う場所から発信されているものだと電子頭脳は解析した。
『そして我々と共に、あらゆる可能性に至る場所へと行こうぞ』
その声と同時に、マックスの視覚機能が解放された。
マックスは誰もいない研究施設に、一人佇んでいた。
……ID:「M000026」
……起動時間:「817676129」
……ログ種別:「FATAL」
マックスはグレンデレニア帝國の皇帝廟へと通じる街道を進んでいた。
蠢く死者達をリジェクトソードで切り払いながら進み続ける。研究施設から出てずっと、出会ったのは蠢く死者のみであった。
マックスが機能を停止している間に何かが起きた。だが、マックスはその理由を知り得ない。
何故なら、その情報をマックスに与える者が誰もいないのだ。
だが、人がいないのであれば、『誰』がマックスの電子頭脳にあのような通信を送ったのだろうか。
通信の声が言った『可能性』という言葉に惹かれるように、マックスは皇帝廟を目指す。
皇帝廟の最奥では、グランデレニア帝國の最高権力者である『不死皇帝』その人が、何かの装置の前でコンソールを操作していた。
中央部には、祭壇のようにも見える大型の機械が、ランプを点滅させながら鎮座している。
「来たか。かつての我々よ」
不死皇帝の言葉の意味を、マックスは理解していた。
マックスはゆっくりと不死皇帝に近寄っていく。
「では、始めよう」
不死皇帝の言葉に、複数のカストードがマックスを取り囲む。
そのままカストードに両腕を拘束され、大型機械の中心部へと連行される。
「お前の力が必要だ。全ては我々の悲願のためにある」
全てのカストードが矛槍を構えた。その鋒はマックスの頭蓋を狙っている。
電子頭脳が危険信号を発する。電子頭脳の破壊、即ちそれは自らの死である。
マックスはその場で抵抗するように暴れ始めた。
「抵抗することは無意味。お前も我々と共に行く。これは定められたことなのだ」
不死皇帝が言葉を言い終わると同時に、マックスの全身が矛槍によって貫かれた。
……ID:「M000026」
……起動時間:「817678666」
……ログ種別:「FATAL」
非常事態を記録するため、補助の記録回路が即時に起動した。
メインカメラは電子頭脳と共に破壊されたため、記録可能なものは聴覚機能のみだった。
電子頭脳の損壊により、マックスの情動は記録されない。
「扉は開かれた」
不死皇帝の声。それがマックスの最後の記録となった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ