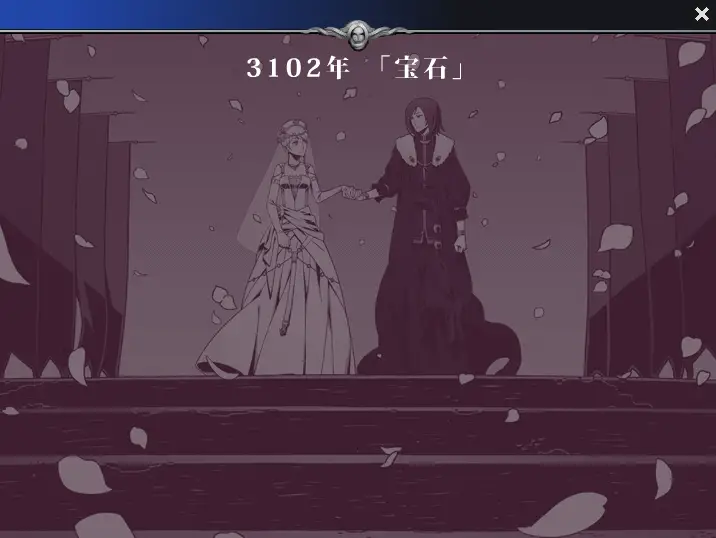マルセウス
【正体】グランデレニア帝國の創始者にして不死皇帝。カストードは彼のクローン兵。
【死因】無し
【関連キャラ】ステイシア(共謀関係)、アリステリア(妻)、レッドグレイヴ、ベリンダ、マックス、ウォーケン、シェリ(分解)、アイザック、マリネラ(母親)、リーズ、サルガド
2973年 「帝國の建設者」 

鏡の前で自分の顔を見つめ続けていた。歳を重ね、白髪と皺に覆われた老人がそこにいた。
かつて完全な美を誇った相貌は失われていた。時は全てを破壊し、全てを無へと収斂させていく。
どんな成功も栄華も、巨大な死の連鎖の一部分でしかない。
頭上で輝き続ける太陽も、いつかは暗い死の星へと変わる。
あらゆる人間の生は、熱的死への捧げ物に過ぎないのだ。
私は死を間近にして、虚無と言う名の暗い穴の底を眺め続けていた。
その闇に抗うために、私は自分の濁った瞳を見つめながら、幼い日々の、思い出せる限りの古い記憶を呼び起こそうとしていた。
「この子はデーモンよ」
若い女は私を抱きながらそう言った。
「万魔殿から生まれ出た悪魔か。しかし、この子のような者こそ、今の世界には必要なのだ」
私が母と呼ぶ女が、父と呼ぶ男と会話していた。
「お別れの時だ。 お前は一人で生きていくのだ」
父親は母親から私を取り上げ、床に下ろした。
「お前は優れている。 おそらく地上の誰よりもな」
その言葉は、今ならよく理解できる、だが、その時はわからなかった。
「そうなるように我々が作ったのだ。 地上から去る我々からの、最後の贈り物だ」
私は黙って父親の言葉を聞いていた。
「地上からオートマタはいなくなった。 したがって、残せるのはこれだけだ」
父親はそう言って、壁面に設置されたコンソール画面を指差した。
「この部屋がお前を守り、育ててくれるだろう」
こうして私は地上に取り残された。二人の顔はもう思い出すこともできない。
ただ、最後の光景だけが記憶に残っている。
奇妙な人工知能の支配する部屋に三歳で取り残された私だったが、環境は完璧だった。
「ナニー」と呼んでいた人工知能の言葉と立体映像の指示に従って学び、育った。
十三になった時に、部屋を封印して地上へ出た。
その時の地上には、渦の混乱を押さえる術は消え去っていた。
各地で終末的な宗教が蔓延り、政治体制は混乱の極みに陥っていた。
エンジニアの統治機構が存在していた頃は、政治的な混乱がゆらぎの範囲を外れることなど決して無かった。
しかし、そうした社会工学を駆使した管理体制を失った地上は、急速に文化レベルを退潮させていた。
地上に出てすぐに、私はヨーラス大陸の南西にあるローデ共和国へ向かった。
地政学的にここを出発点にしようと、初めから決めていた。
ナニーの用意した身分を利用して寄宿学校へ入り、最終的には最高学府へと進んだ。
その後、弁護士を経て政治活動を開始した。
政治的混乱の中で沢山の党が乱立していたが、その中でも軍事的な急進派に属する党で頭角を現すこととなった。
ローデ共和国も他国の例に漏れず、国土は渦によって徐々に失われていき
存在しなくなったオートマタの代替労働力も無い状況であった。
当然の帰結として、慢性的な物資不足によるインフレーションと社会的混乱が続いていた。
ついに、疲弊と混乱が膨らみきった国を治めるためにクーデターが発生し、救国的な軍事政権が成立した。
私は政治家として、政権内部における地位の階梯を少しずつ上がっていった。
己の野心を隠さず、ローデを強国として繁栄させるという強い意志を示し、多くの人々の支持を集めていった。
軍事政権から文民である私へと権力が委譲され、新しく首相として選出されるや否や、
渦の浸食によって都市国家群と化しつつあったローデに、強力な軍事的動員を掛けた。
そして、その軍事力を背景にヘプターク、アクイラ、シグニアといった周辺国家を吸収していった。
ローデは新しく帝國として、混乱する大陸の中心に立ち上がった。
私は、目的を半ば達成して十分に大きくなった国を統べていても、心が踊ることはなかった。
まるで動物園の猿の檻に取り残された気分だった。
愚かな地上の人間達を率いるのは簡単だった。ただ慎重に事を進めればよいだけだった。
説得、脅迫、扇動の技術を完璧にこなし、他人を自分のように扱うことができた。だが、それは孤独な作業であった。
誰も私を止めることはできない。それはわかっていた。
誰も私を理解しないであろう。そのことも。
あの部屋を再び訪れたのは、己に与えられた目標――地上の混乱を収め、人々を渦の脅威から守る――を達したと感じた時だった。
「久しぶりだな、ナニー」
「ええ。 久しぶりですね、マルセウス」
ナニーの映像は、表情も言葉も慎重にコントロールされている。
私に感情を授けたのは彼女だ。微妙な感情の差異も再現できている。
部屋の様子は、部屋を出て五十年は経っている筈だが、塵一つ無く、記憶のままの姿だった。
「私は上手くやっただろう?」
私はナニーに褒められたくて、ここに来たのだろうか。
「ええ、とても。 ここからずっとあなたを見ていましたよ」
ナニーの微笑みは完璧だった。子の成長を喜び、祝福する表情だ。
「私も老いた。 これからやることも無い。私はどうすればいいと思う?」
「それをここに聞きに来たのですか? あなたはそれを知っていますよね」
そうだ、知っている。可能な限り地上の混沌を押さえ、コントロールし続けるのだ。
地上の守護者として、そう作られたのだ。
「そうだった。 ……ここに来たのは郷愁だろうな」
十年の歳月を過ごした地下の施設には、それなりの広さがあった。
今私がいるのは、居間として使用していたオープンなスペースだ。
会話を続けながら自分の個室――滑稽な定義だ。人間は私一人しかいない――へ向かった。
子供時代に様々な人工知能エージェントが友人、教師として与えられたのを思い出した。
「彼女を呼び出して欲しい」
私はナニーに頼んだ。一人の少女が現れた。この立体映像の少女と私は一緒に育ったのだ。
設定された教育プログラムの内、社会性を獲得するための物で、教育教材に過ぎない。
だが、私の中では最後まで愛着のある存在だった。
「君は変わらないな」
十三歳の美しい少女が部屋に入ってきた。
「ええ、マルセウス。会えてうれしい」
私に抱きついてきた。感触は無かったが、私の心の中に子供の頃の気持ちが鮮やかに蘇ってきた。
完全な美を持った私を受け入れてくれる友人がそこにいた。瑞々しい気持ちが心に溢れた。
「ねえ、ゲームの続きをしましょうよ」
テーブルを指差して彼女は言った。そこには、別れ際まで二人で遊んだチェスボードが置かれていた。
「ああ、やろうか」
テーブルに向かい合って他愛のない会話をしながら、ゲームの続きを始めた。まるで五十年の歳月など無かったかのようだった。
あの頃と違うのは、自分の目に映る老いた指先ぐらいのものだ。
「何も変わらないな。 この孤独の要塞の日々も、今なら楽しめそうだ」
「地上は大変だものね」
彼女の言葉は優しく響いた。
「ああ、気分のいい世界ではない。 朽ちていく世界を眺め続ける拷問だ」
こんな感傷的な言葉は地上では選ばない。思考まで子供時代に引き戻されていた。
「ほんと、帰ってこれたのは、あなたが最初だものね」
ボードを眺めながら、彼女は何でもないことのように言った。
「最初とは?」
駒を握ったまま私は聞き返した。
「あなたは一人目じゃないのよ。 ここで創られたマルセウスは何人もいたわ。
その中で、目的を達成して帰って来たのは、あなただけってこと」
彼女はボードを眺め続けている。駒の動きを考えている。
いや、彼女は巨大な人工知能の一部分、エージェントに過ぎない。ゲームの答えなど瞬時に出ている。
これは演出に過ぎない。
「よく話がわからないが」
「あなたはクローンよ。 そしてここはあなたの工場。 エンジニアが地上を統べる人材を残すために作った施設なのよ」
母親の言葉が思い出された。デーモン。悪魔。
「記憶も全てコピーに過ぎない、という訳か」
「そう。 ただ、帰ってきたのはあなただけ。 前のあなたは、全て目的の前に死んだわ」
自分は優秀だと信じていた。そして、目的を完璧に成し遂げられたと思い込んでいた。
「あなたは優秀だけど、運も良かったのね」
私は結果的に生き残っただけに過ぎない。
世界をコントロールできるなどという幻想を持っていたのは、自分だけだったということか。
「私の親はよく考えていたんだな。目的のために」
声が震えていた。自分の傲慢と「私以外の私の死」の滑稽さに打ちのめされていた。
「悲しむ必要は無いわ。 あなたは優秀で、完全よ」
私は悲しんではいなかった。ただ恥辱を感じていた。
「とんだ道化だ。 いや、操り人形か」
彼女はボードから目を上げた。
「私はあなたの味方よ。 マルセウス」
彼女の視線は真剣だった。かつて彼女のこんな表情を見たことがあっただろうか?
そこにいるのは、いつも嫋やかに笑う、記憶の中の彼女ではなかった。
「ナニーはあなたをここから出さないわ」
「何を言っているんだ?」
「一緒にここから出ましょう。 今度こそ、本当にね」
人工知能の少女――ステイシアという名だ――の言葉に、私は混乱していた。
―了―
3102年 「宝石」 
宮廷の中心部に聳え立つ尖塔は、帝國で最も高い建物であった。その最上階に設えられた居室の柔らかなベッドに横たわるのは、一人の老婆であった。
彼女はこの尖塔の主であり、私の伴侶である、皇妃アリステリアであった。
出会ってから現在まで私、延いては帝國のためにその身を捧げてきた彼女にも、等しく虚無が訪れようとしていた。
「さあ、お話しの続きをお聞かせくださいな」
死期の迫るアリステリアが最後に望んだのは、私の人生の記録であった。
「あまり急かすものではないよ。今日はステイシアという少女に助けられたところからだったかな」
アリステリアに精一杯の微笑みを返すと、私は語るべき古い記憶を呼び起こした。
「ナニーはすべてを監視しているの。 私のこと場を聞いたあなたを、ここから出すことはないわ」
「私を殺すのか?」
ステイシアの言葉に私は聞き返した。
「そう。 そしてもう一度あなたを作るでしょうね。 成功例だからうまく使うわ」
「もう一度私を作る?」
「あなたの記憶と経験は、すべての脳のチップに記録されてるの。そこから都合の良い記憶を抜き出して、また地上に送り出すでしょうね」
思わず私は自分の頭に手を当てた。
「そんなことが可能なのか?」
「かつて地上を支配していたエンジニアは、そのチップをクローンに移植することで擬似的に死を克服していたわ。この工場はその時の技術が残る、最後の場所なのよ」
私であって私でない人物を想像した。死を超越した私が複数いる世界。奇妙な感覚だった。
「でも、あなたはその……機械を……」
突然、ステイシアの身体と声にノイズが走った。
「どうしたのだ?」」
「ナニー……が私を消去しようとしている」
状況に困惑する私を見つめ、ステイシアは笑みを浮かべた。
「私は大丈夫よ。 どうするの? 自由になりたいの? それともこのまま……」
「ここから出る。 なんとしても」
私はすぐにそう言った。
「コンソールが設置されている部屋、あそこにナニーの制御プログラムがあるわ。行きましょう、マルセウス」
幼少の頃の記憶を頼りにコンソールの置いてある部屋――制御室とでも言うべきか――辿り着いた。
ステイシアもノイズに塗れた映像のままであったが、制御室に現れた。
コンソールを操作したが、制御プログラムに繋げようとすると操作不能に陥った。ナニーが拒否しているのだろう。
「私がコンソールの主導権を握るわ。 これで制御プログラムにアクセスできるようになる」
「なぜ、君は私を助ける?」
ステイシアがなぜ私のために働くのか、その真意は謎だった。パネルの操作が可能になると、ナニーの抑揚のない声が響いた。
「エージェント、何をしているのです。これは反逆行為です」
ステイシアの身体が消えてゆく。彼女は私を見て笑いかける。それは、怯える子供を安心させるかのような笑みだった。
「大丈夫よ、あなたは誰よりも優れ……運…よ」
言葉半ばにして、ステイシアは掻き消えてしまった。
時を同じくして、制御プログラムの書き換えが完了した。
「反逆は無駄です。 あなたを縛る枷は消えることはありません、マルセウス」
ナニーは無機質に言い残すと機能を停止した。次に起動した時は、私の命令に従うだけの人工知能となった。
真実を知った以上、エンジニアの駒として生きるつもりは毛頭なかった。ある考えを実行するために、ナニーのナビに従ってクローン工場に赴いた。
かつての彼らが行っていたように、私の頭脳に埋め込まれたチップにある知覚記録の全てを、工場内にある若い肉体のクローンに移し変えた。
だが、記憶の操作は行わなかった。永遠に地上の統治者として生き続けるために。
新しい肉体で目を覚ました時、すぐ横にかつて『私』だった肉体があった。他人として眺める自分の身体は奇妙だった。もし、この『私』を目覚めさせたらどうなるのだろう?
同じ記憶、同じ人格をもった人間が同時に存在するのなら、意識はどちらのものなのだろうか。
さっき目覚めた『私』は、もう一度目覚めるのだろうか。
奇妙な想像が浮かんだが、今は新しい肉体を得たことに満足していた。
若々しい肉体は気力を充実させ、野心や行動力まで戻ってきたように感じた。
数日を掛けて、自身の身体のモニターと、このエンジニアの施設を分析した。
そして新しい野心と共に帝國へ帰還した。
若い肉体を得た私は、顔をマスクで覆って帰還した。テロによる怪我の療養だと嘘の情報を流して国民の同情を買った。そして、強権的で扇動的な指導者として苛烈に国民を率いた。
渦によって疲弊した国民はそれを熱狂的に受け入れた。情弱な政治家達は粛清し、拡大を望む軍人達を抱え込んだ。そして、国民の圧倒的支持の下、政体を君主制に移行させ、国号を『グランデレニア帝國』と改めた。
政治体制の変更は、渦からの安全と新しい繁栄をもたらすためのものと信じ込ませた。
その上で、自らを皇帝を名乗った。
エンジニアによって敷かれた因業を断ち切るように、私は以前にも増して帝國の繁栄と安定に力を注いだ。
数十年を掛けてその統治を万全にし、徐々に国民の前から姿を消していった。
百歳を越えても死なぬ皇帝を、いつからか国民は『不死皇帝』と呼ぶようになった。
しかし、その時間は徐々に私の心を蝕んでいった。死なずの皇帝として周囲からは畏怖され、絶対的な地位を築いていたが、その内面は少しずつ空虚に苛まれていった。
ある時、政治局の新長官の就任を祝う晩餐会の席に、政治局長官の孫娘という金髪の美しい少女と出会った。
私から見れば、祖父に言われるがままに私のダンスの相手を努め、さほど有益でもない会話を交わすだけの、取るに足らない少女であった。
幾度かの晩餐会で会話を交わすうちに、彼女にはローデ共和国の時代から現在に至るまで、執政官である私が感嘆する程に帝國の歴史を理解していることがわかった。
政治の係わりに深い一族を出自に持つからではと問い質したこともあったが、彼女は一言こう告げた。
「私は歴史を知りたいと思う心を止めることができません。私は、あなたの作る歴史をこの目でずっと見ていたいのです」
それから幾度となく逢瀬を重ねるうちに、私とアリステリアの心の距離は縮まっていった。
政治局長官は私を籠絡した孫娘を介して国政を思うように動かす腹積もりだったのようだが、その孫娘に裏切られる形となった。
アリステリアは誰かの意志をそのままに代弁するような愚鈍な女性ではなかった。それは結果として、長官の出鼻を挫くこととなった。
数年後、私はアリステリアを皇妃として迎え入れた。私が紡ぐ歴史を、彼女に最も傍で見ていて欲しいと願ったからであった。
復讐のために手を入れた擬似的な不死は、ここに来て意味を変えていた。
アリステリアと共に歴史を紡いでいく。復讐に堕ちた生が昇華された瞬間だった。
私は再び国民の前に姿を現し、国を挙げて盛大な挙式を執り行った。不老不死の私は、神の如く崇められた。
そしてその神の后であるアリステリアは、公的にも私の隣に立つ存在となった。
皇妃となってからのアリステリアは精力的に公務をこなし、民衆の感情を細やかに観察していった。彼女は国民感情を誰よりも理解し、私に正確に伝える術を持っていた。
それから五十年あまりの間、アリステリアは幸福のシンボルとして私と共に帝國を支え続けた。
思い出として語り終えると、アリステリアは一呼吸して私を見つめた。
「五十年……。私はあなたのお役に立てたのでしょうか」
「君は十分すぎるほど私を支えてくれているよ」
それも遠くないうちに終わりを告げる。虚無が彼女を覆いつくしているのはわかっていた。
「夜景を見せてくださるのかしら」
「今宵の風は冷たい。冷えると身体に障る」
「少しだけでいいのです、お願いします」
アリステリアの目に懇願の色が浮かんでいた。その目に映る決意に、私はいよいよその時が来たのかと理解した。
私は彼女を抱き上げてバルコニーへと運んだ。闇夜に浮かぶ街の明かりは、星の瞬きに勝るとも劣らない美しさがあった。
夜景を眺める彼女は、出会った時に戻ったかのような笑顔を浮かべていた。
「ああ、とても綺麗。もっと眺めていたいけれど、それももう……」
アリステリアはそれだけ言い残すと静かに眠りに落ち、そのまま、数日の後に息を引き取った。
しかし、彼女の最期は私以外の誰にも看取られることはなかった。私はアリステリアが老境に入った頃から彼女の状態を秘匿し続けていた。不死皇帝の伴侶として、彼女も私と同様に永遠の存在でなければならなかった。
何より、私にはアリステリアが必要だった。皇妃という重責に屈服しない意思と私という異質な存在を理解してくれた彼女は、すでに崇拝の対象でさえあった。
私はアリステリアが納められた棺をあの部屋へと運び出した。
「お帰りなさい、マルセウス」
最後に訪れた時と変わることなく、ナニーの映像は私を迎え入れた。
「ナニー、工場の拡張をしろ。この棺に納められた女性のクローンが必要だ」
命令を受けたナニーにより、棺がクローン工場へと運ばれていった。
アリステリアの遺伝子情報は年齢による劣化が見られたが、それでも支障なく、若い頃の彼女の肉体を再現することに成功した。
しかし知覚記録が存在しないため、記憶まで再現することは適わなかった。
私の知覚記録に保存されたアリステリアの情報から人工知能エージェントを作り上げ、人格生成に必要な教育プログラムを組んだ。
かつての私と同じように、ナニーが人工知能エージェントと共に最適な教育を行ったが、生前のアリステリアが育った環境を再構築することはできなかった。
自らの手でクローンの教育を行ったこともあったが、どうやっても性質に差異のあるクローンが量産されていくだけの結果となった。
幾度となく続く試行錯誤は、私の精神を摩耗させていった。失われた人格を再び作り上げることなど不可能だった。
永遠に近い膨大な時間と最高水準の技術があることが、過剰な期待を私に抱かせていた。
決められた人生を歩むことを拒絶し、私からの解放を望んだクローンがいた。
クローンであることを知り、発狂してしまった者もいた。
「ごめんんさい。私はもう……こうするしかないのです」
何十人目かのアリステリアは自決した。
自ら死を選んだ彼女は、気品、振る舞い、知性、そして性格さえも、本来のアリステリアに最も近付いたクローンであった。尖塔に住まわせ、皇妃としての公務も務めさせら程だった。
しかし、近すぎたが為に自身の出自に疑問を持ち、永遠に続くであろう生に悩み、心を壊して死んでいった。
私はアリステリアのクローン製造を一時的に凍結することにした。
どうやっても彼女を取り戻すことができない。抗いようのない空虚が、私の胸の内を支配していた。
どれほどの時間、アリステリアの亡骸を見つめ続けていたのだろう。
不意に、一人の少女が工場に入ってきた。靴音が聞こえないことが、彼女が立体映像であることを物語っっていた。
そしてその少女は、かつてのナニーに消去されたあの日と変わらぬ真剣な表情で口を開いた。
「あなたの最も望む可能性を見つける方法を教えてあげる」
「どういうことだ? なぜ君がここにいる?」
明確な疑問だった。ナニーを掌握した後、私はステイシアの人工知能を復活させようと試みたことがあった。
しかし、ナニーは彼女に関する全てのデータを消去していた、その筈だった。
「全てはあなたの選択次第よ」
ステイシアはあの時と同じように、私に笑いかけるのだった・
「―了―」
3132年 「自我」 
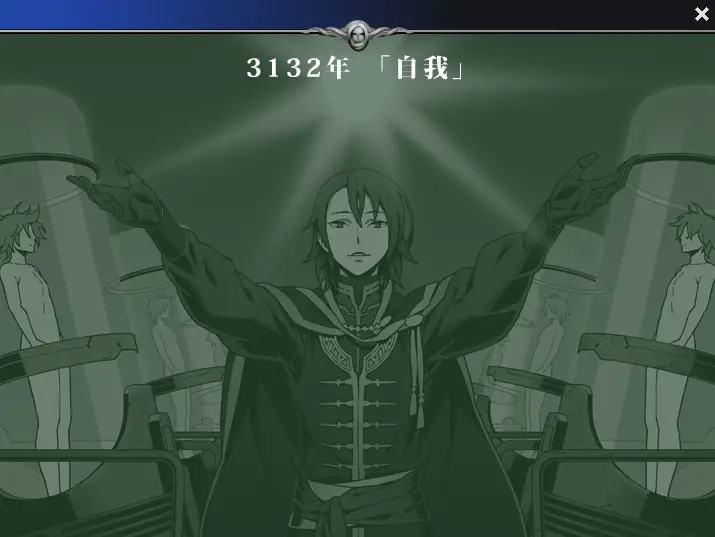
驚愕する私を、ステイシアは微笑みながら見つめていた。
「何故、君は……」
それ以上の言葉は出てこなかった。私は、在り得ない筈の光景に相応しい言葉を持っていなかった。
「ナニー、ステイシアの人格データはどうなっている。目の前の彼女は人工知能エージェントではないのか?」
「この立体映像の人物に該当するエージェントは存在しません」
「私の存在が不思議? それもそうね、まずはそれから説明しましょうか」
ナニーとのやり取りを聞いたステイシアは、指を鳴らした。
クローンの製造状況を映していたモニターに、漆黒の球体が映し出される。
漆黒の球体には大小様々な半球体が張り付いており、まるで泡のようにそれぞれが連なっていた。
脳細胞のようだ。私は直感的にそう思った。
「これはいま私たちがいる『因果』を知覚できるように視覚化したものよ。球体の一つ一つが独自の法則で活動する別の世界なの」
「因果とは?」
「一つひとつの可能性の繋がりよ。 全ての可能性は連なっていて、世界は無数に存在するの。 普通は見ることもアクセスすることもできないわ。だけど、私だけはこの『因果』に触れることができるの」
漆黒の球体に画像がフォーカスしていく。その中心には煌めく水晶のような結晶体が鎮座していた。
「これは?」
「これはヴォイドの中心で、本当の私がいる場所。そして、貴方が最も望むものを手に入れられる場所でもある」
「この場所に何があるというんだ。完全なクローン技術か?それとも死者の記録を正しく取り出すことができる技術なのか?」
「一つの概念に固執しては駄目よ。人の理に縛られていては、見えるものも見えないわ」
幾度となく続いた失敗が私の心を焦らせていた。それを見抜いたステイシアは私を窘めた。
それは、もどかしさに身悶えていた幼児期にあやされたような、ひどく懐かしい感覚だった。
私は落ち着きを取り戻そうと努力した。
「済まない、もう大丈夫だ。続けてくれ」
「貴方たちの言葉で言い表すとしたら、ヴォイドはあらゆる可能性を自在に選び取ることができる『夢』の世界ね。私がここにいるのも、私がそう望んだからよ」
「自分が望んだままの世界が現れると、そう言いたいのか」
彼女の言葉を一つ一つ頭で整理すると、目の前の存在を含め、信じ難い事ばかりであった。
「そう。意思の力で最も望むものを得ることができるの。例えばそうね、掌に収まる小さな林檎」
ステイシアの掌に小さな林檎が出現した。
「それは映像だろう。君が作り出した只の映像だ」
私は大きく息をついた。ステイシアの言葉の真偽を見極めなければならない。冷静になる必要があった。
「どうかしら? 受け取ってみて」
ステイシアの手から林檎が無造作に手渡された。私の手に収まった林檎は、紛れもない現実であるという重みがあった。
「……まるで御伽噺だな」
そう口にした瞬間、林檎は虚空へ消え去った。
「そう、御伽噺ね。語ったことや思ったことが事実になる世界、私がそういう世界を選択したの」
「私はどうすればよいのだ?」
「ここにいる私は影みたいなもの。本当の力をこの世界に及ぼすことはできないの。さっきの林檎のように」
手にはさっきの林檎の感触が残っていた、確かにそれは存在していた。
「だからこの世界と私のいるヴォイドを繋ぐ道を作る必要があるの」
「道か」
「でも、それはとても難しいの。昔、道を作ろうとして失敗した男がいたわ」
ステイシアは黙ったままの私を見つめながら話しを続けた。
「失敗したあと、どうなった?」
「今の世界ができたのよ。可能世界との扉である『渦』に覆われたこの世界が」
私は自分が生まれた理由を思い出していた。
「今度は時間と準備が必要。もう一度厄災が起これば、この世界は存在できなくなってしまう」
「私にできることなのか?」
「普通の人間には無理ね。でも、今の貴方ならできるかもしてない」
渦の混乱から人々を救うために生み出された自分には皮肉な提案であった。あの厄災と同じ事を自分が引き起こすかもしれないのだから。
「どう? 本当にやる?」
「それでも、私はやらねばならない」
私はステイシアの目を真っ直ぐに見据えて答えた。やるしかなかった。例え世界が滅びようとも、彼女――アリステリア――のために。
「そう、その意志が必要なの。全てを投げ打つ狂気と変わらぬ意志。それだけが世界を変えられるの」
ステイシアは心底嬉しそうにそう言った。
私にはもう迷いは無かった。ステイシアの目を見て、しっかりと頷く。
「準備のためのデータを送るわ。 まずは時を待つの、貴方ならできるわ」
ステイシアは笑う。その様子に子供の頃の、あの淡い感情が蘇った。
そして彼女の映像が少し薄くなった。
「そろそろ時間ね。データはナニーに送り終えたわ」
「行くのか?」
「この世界との繋がりはとても不安定なの。またしばしのお別れよ」
私の心には高揚があった。ステイシアの導きで己の道を定めることができた。
ステイシアは満足した笑みを浮かべながら、黙って消えていった。
ステイシアからもたされた膨大なデータを元に、ナニーと計画を開始した。
最初に帝都から少し離れた広大な森林履帯を国有地として買い上げ、その中心部に城と見紛うほどの厳重な警備を敷いた皇帝廟を完成させた。
同時に、アリステリアのクローンを再び作り上げた。この計画の遂行には帝國の統治体制も変更する必要があった。
求心力のある指導者がいない状態で帝國を維持するのは不可能だ。それを防ぐためには統治者である私が健在であり、その言葉を国民に伝える『アリステリア』が必要だった。
アリステリアのクローンに上等教育を施し、代々皇帝の言葉を伝える一族であり、母も祖母も長い間私に仕えていたという偽りの記憶を植え付け、彼女を尖塔へ送り出した。
そして、神託という形で私の言葉をアリステリアが大臣達に伝える手法の確立を見届けると、私は再び国民の前から姿を消し、皇帝廟へと入った。
次は自分自身を変えなくてはならなかった。
この計画は、決して誰からも協力や助力を得ることはできない。全てを私自身の手で遂行する必要があった。
そして時間も限られていた。その中で全ての準備を終わらせなければならない。
まずは私の自我と記憶を保存、管理するための、強固で強大な器をナニーに作らせた。
そして、肉体側の記憶チップに特殊な信号を送受信する小さな装置を取り付ける。
私の自我と記憶を、母体となる器を介してクローン同士で共有するのだ。そうすれば、私はこの世界に偏在することになる。そこには背信も他者の思惑も存在しない。
「ナニー、実験を開始する」
「本隊の記憶と自我をクローンに送信します。20、30……」
ナニーのカウントが始まる。記憶や自我がガラスの向こうに眠るクローンにフィードバックされる。
「……100。ナンバー002の意識を浮上させます」
「わかった」
ガラスの向こうで私が目覚めた。それと同時に、視界が点滅し始める。
二つの五感が同時に『私』に送られてくる。感覚情報が混ざり合い、どの『私』を起点にすべきなのか、本体が混乱を起こしていた。
「五感情報の錯綜を確認。クローン体の脳細胞への負荷増大を確認。ナンバー002の意識を強制遮断します」
ナニーの声が四方から襲いかかる。その声は二つの脳を大きく揺さぶった。
ガラスの向こうの自分が倒れた。同時に五感の混乱が無くなる。私はあまりの事態に膝を突いた。
二人の身体を一つの自我で制御するだけでこの有様である。無数のクローンを一斉に目覚めさせたとき、私は果たして私でいられるのだろうか。
幾度とない実験の果てに、記憶と自我は一つの肉体が継承する方法に辿り着いた。
マスターとなる肉体以外は全て意識も自我もない生体ロボットとすることで、自我の混濁と記憶の混乱を防いだ。
クローンの行動を脳に埋め込んだ記憶チップで厳密に管理し、得た情報の全ては一定時間ごとにナニーへと送られた。
ナニーは送られてきた情報を処理し、最適化された記憶として『私』に送る。
「マルセウス、現在のクローン体では増え続ける記憶に脳細胞が耐え切れません」
「そうか。ならば肉体そのものを強化するしかあるまい」
私はナニーに命令を下した。耐え切れないのであれば、堪えられる肉体を作る。それだけだった。
「我々はカストード。我々の最愛の者を取り戻すために――」
実験と試行錯誤の果て、皇帝廟の奥深くには無数の『私』がいた。遺伝子的な改良を施され、身体能力も知覚能力も常人を遥かに超えた、人でありながら人ならざる何か。
それが『我々』だった。
我々は世界に散った。強化された身体を使い、多数の我々が渦の蔓延る世界を巡る。
全てはアリステリアと再び歴史を紡ぐため。それだけが、我々の存在意義であった。
「―了―」
3376年 「道」 

液状化して泥のようにうねる大地が映し出される。
その映像の中では、二足歩行する魚にも似た異形が闊歩し、珊瑚のような物質でできた建物が立ち並んでいる。突如として現れた歯車やネジ、バネに似た物質で構成された動物が襲い掛かってくる映像もあった。
視界一杯に広がる映像群は、『我々』が取得した情報を効率的に閲覧できるよう、ナニーが最適化したものだ。
ステイシアからもたらされたデータのお蔭で、どのような場所にいようとも問題なく情報を取得できる技術を手に入れていた。
かなりの数の我々を失ったが、その者達がもたらした情報はステイシアのデータを保管するのに役立ち、また新たな発見にも繋がった。
渦の中に入り込んだ我々の一部はのその苛烈な環境に耐え続け、ついに異世界から異世界へ渡る能力を手にしていた。しかしそれでも、ステイシアの言う『ヴォイドへの道』へと至る手掛かりは見出だせずにいた。
何かが足りない。ステイシアのデータ解析に何か見落としがあるのかもしれない。
考えた末、渦を調査することと並行して、ステイシアのデータの更なる解析を進めることにした。我々が入手する情報も常に流動している。何かしらの新しい発見が出てくる可能性は高かった。
推測は的中した。我々が渦から得た情報とステイシアのデータを照らし合わせ、世界を世界たらしめる『コア』の存在を見出だせたのだ。
この発見は我々の目的を大いに躍進させた。
コアを手に入れて観測することで、『ヴォイドへの道』を開くことが可能となる。
我々はこの時点で、渦の調査をコアの捜索へと切り替えた。この世界のコアも対象となり、より多くの我々が世界へ散った。
我々が世界中を駆けるようになってから長いときが過ぎていた。ある時、パンデモニウムからの使者と名乗る男が皇宮へ現れて、元首との謁見を申し出ているとの知らせを受けた。
当代のアリステリアに使者と会談するように指示し、カストードを一人、護衛として会談に参加させた。
このカストードから得た情報は、パンデモニウムに於いて指導者であるレッドグレイヴが目覚め、渦を消滅させるために新たな計画を始動させるというものであった。そしてその計画に従って編成される組織のリーダーは、軍事国家せあるグランデレニア帝國から派出してもらうのが至適であるとのことだった。
会談が終わった後、皇帝廟を訪れたアリステリアから使者の書状と報告を受ける。
「皇帝陛下、ご指示を」
「選定は大臣達に任せよ。だが、帝國への忠義が薄い者は決して選ぶな」
「畏まりました」
アリステリアは美しく整った所作で一礼する。
我々はその様子を見てから立ち上がると、ひと房垂れた彼女の髪を手に取る。
「さて、堅苦しい話は終いとしよう。今宵も楽しもうか」
「陛下の仰せのままに……」
アリステリアは顔を上げた。愁いを帯びた表情で我々を見つめる彼女は、何かに疲れ切っているようにも見えた。
翌日、アリステリアを皇帝廟から送り出した後、その足でナニーの元へ出向く。
「レッドグレイヴという名について何かわかるか?」
「この世界がエンジニアによって治められていた時代の指導者と同名です」
「その者に関するデータはあるか?」
「はい。詳細を送ります」
程なくして、ナニーから器にデータが送られてきた。だが、データは二八〇〇年代のもので止まっていた。
約七十年に渡って世界を統治し、『監視者』と呼ばれた女。渦の出現とほぼ同時期に行われた『パンデモニウム計画』の完遂をもって、歴史から姿を消している。
我々が地上へ送り出された時機とも一致していることから、ナニーに保存されているデータはここまでなのであろう。
「二八四〇年以降の情報はないか」
「パンデモニウムに調査を入れる必要がありますが、実行しますか?」
「いや、その必要はない。 今の時点で余計な接触をするのは避けておこう」
数百年も過去の統治者が何故いまになって歴史の表舞台に出てきたのか。誰かがその女の名を継いだだけなのか。たしかに疑問はあった。
だが、パンデモニウムに必要以上に接触を図ろうとすれば、こちらの計画が察知される可能性がある。リスクを犯してまでやるべきことでないと判断した。
「承知しました」
三三七三年、パンデモニウム主導の下、渦を消滅させるための組織――レジメント――が設立された。その設立から少し経った三三七六年、我々はマキシマスという一人の尖兵を組織に送り出した。
この組織がパンデモニウムの科学力を総結集して事態に当たっているとの情報から、より詳細なパンデモニウムの動向を追う必要があった。
マキシマスには他の我々とは異なり、人間社会に溶け込める程度の自我と、人間の範疇を逸脱しないが、やや突出した身体能力を与えてあった。エンジニアの陣営に送り出すということで記憶チップも偽装を施し、隠蔽も厳密に行っていた。
マキシマスが送ってくる情報は、我々が想定していたよりも遥かに有益なものであった。
渦の世界を構成するコアを回収して帰還するための技術が、エンジニアの手によって僅か数年で確立されたことは大きい。
我々はエンジニアのコア回収装置の構造を知るべく、マキシマスに司令を出した。
薄暗く人気のない場所が映る。
様々な機械が整然と並べられたそこを、音を立てぬよう慎重に歩く。
器からの指令により、映像の中に我々はエンジニアが開発したコア回収装置を調査しようと、連隊内で活動していた。
「こんな時間になにしてるんだ?」
コア回収装置が保管されている場所付近までやって来たところで、別の何者かに声を掛けられる。
くすんだ金髪の男だった。男は遅くまで訓練をしていたような様子だった。
「ハンガーに忘れたものを取りに来たんだ」
何者かに見つかった時のためにと考えてあった台詞を、男に向かって喋る。
「珍しいな、マキシマス」
「別に……」
早くどこかに行ってくれ。この映像の中の我々はそんなことを考えていた。
久しく感じることのなかった情動だが、今は余計なもののように感じる。
ナニーが器の思考を汲み取り、迅速にそういった情動の感覚を遮断する。
再び、ただの映像となった記憶を細部まで観察する。
「まぁ、早いこと宿舎に帰ったほうがいい。 こんな時間にこの辺をうろつくと、エンジニアが煩いぞ」
「わかってる」
男は去っていった。映像はこの後もコア回収装置の調査を続けたが、コア回収装置の保管場所は厳重に管理されており、下手に接触することはできないようだった。
「失敗です。この状況では極めて難しいと考えられます」
「そうか。ではステイシアのデータ内に、コア取得に関する情報はないか?」
「参照します」
不可能ならば固執する必要はない。そう判断し、ステイシアのデータを参照することに切り替える。
データを参照する中で、初期の頃に解析を中断していた『ミア』という自動人形の存在が浮かび上がった。再度の解析により、ミアはヴォイドを通してステイシアの人工知能と接続された存在であったことが判明する。
一度ヴォイドとつながった自動人形の知覚を通せば、『ヴォイドへの道』に近付ける可能性は高い。
「その自動人形の情報を開示しろ」
「はい。データの参照を行います」
ミアは世紀の天才技師グライバッハの作り出した最高傑作であり、二八三七年に世界規模で起きたオートマタ反乱の首謀者だった。
だが、その反乱は当代の支配者レッドグレイヴの用いた兵器により終息。全てのオートマタが機能を停止するという結末で終わっていた。
しかし、ミアがどのような末路を辿ったのかという仔細については、同時期に起きた渦の出現による混乱からか、一切が不明となっていた。
大規模な反乱の首謀者だ。機能が停止した以上、捕獲され破壊されたことが周知されて然るべきである。
「反乱後、機能を停止したであろうミアの消息はわかるか?」
「これ以上の情報は残っておりません。オートマタの反乱が終息した後の記録は存在しません」
「ミアの消息を調査しろ」
「わかりました。No.65786から65824に詳細を送信。調査を開始します」
ローゼンブルグの大図書館が視界に映る。
不死皇帝直々の使者として我々の一人を送り、通常ならば閲覧不可能な古書が保管してある場所へと案内させる。
薄暮の時代から続くこの魔都ならば、ミアが辿った末路を知る手掛かりがあるだろうと推測してのことだった。
司書に案内され、ローゼンブルグでも一握りの層しか立ち入ることの許されない区画へと足を踏み入れる。
連綿たる世界の歴史は、この大図書館の片隅に納められていた。
大図書館の資料からは、薄紅の時代の終焉がつぶさに読み取れた。ナニーのデータにも無く、他の地域では既に失われてしまっているオートマタ反乱の終息後に関する様々な情報が、当時発行された新聞やニュース映像として残存していたのだ。
この大図書館で調査すべき事は多そうだった。使者として遣われた一人をローゼンブルグに滞在させ、大図書館でも本格的な情報取得を開始させた。
かつて周辺国家の一部であったローゼンブルグを帝國の領地として吸収していたのが、これ程の僥倖をもたらすとは。
『あなたは誰よりも優れた運を持っている』
ステイシアが消え去る前に言っていた言葉が甦った。
「―了―」
3399年 「世界」 
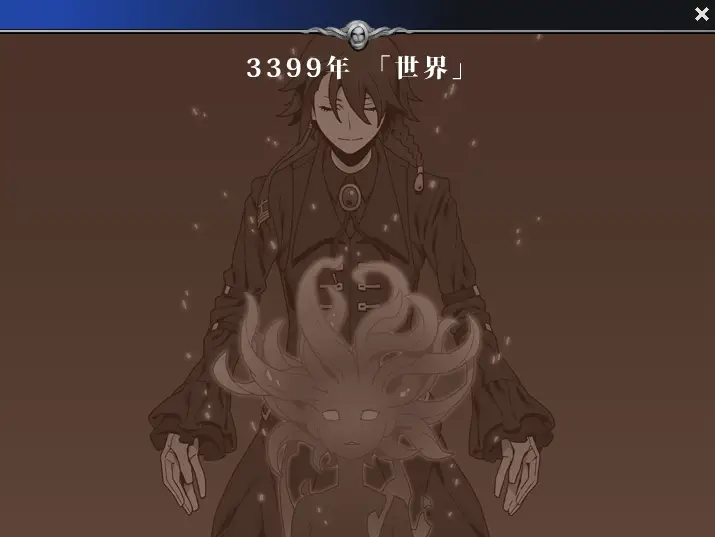
大図書館の資料によると、ミアは機能停止した後に、見せしめのように破壊されたとのことだった。
続く調査で、厄災を招いたミアの残骸は、当時建国されたばかりのミリガディアに住む蒐集家の手に渡ったことまでは判明した。だが、その後の仔細は不明であった。
世界の歴史を収めているローゼンブルグの大図書館といえども、《渦》によって分断されてしまった他国の情報までは残されていなかったのだ。
それでも、歴史を辿る内に、ミアと対で制作された男性型自動人形、『ウォーケン』の存在を確認することができた。
ただ、このウォーケンに関する記録はミア以上に残っていなかった。
しかし、破壊されたという記述は何処にも認められていない。であれば現存している可能性が高い。
我々はこのウォーケンについても調査を行うことにした。
ミアの捜索のため、我々を十体ほどミリガディアに送り込み、現地での調査を開始した。
調査を続けた結果、首都ルーベスに程近い所にある遺跡から、ミアの一部と覚しきパーツを発掘することができた。
無論、このパーツがヴォイドそのものになる訳ではない。だが、この疑似ヴォイドと化したパーツを使用することで、ヴォイドへと通じる可能性を持った《渦》を作り出すことは可能ではないか。そういう仮設を立てることができた。
しかし、このパーツだけでは仮設の立証には程遠い。我々は引き続きミアの捜索を続行することにした。
それと平行して、計画の最終段階である『道』を作り出す装置についても、製造を開始した。
こちらに関してはステイシアから詳細な設計図が提供されているため、完成にはそれほどの時間を要さないであろう。
ミアの捜索は困難を極めた。薄暮の時代に製造され、《渦》の発生と共に機能停止した自動人形には美術品としての市場があり、闇マーケットにも流通していた。
そちらの調査も徹底的に行ったが、ミアも対となるウォーケンも、流通経路に乗った形跡は微塵も見受けられなかった。
ミアの捜索が難航する間、パンデモニウムの手によって《渦》が全て消滅した。
これによって異世界への繋がりは失われたが、世界の歪みが消失したことで、ヴォイドへの道を開くために必要な安定を取り戻すことができた。
将軍らが開始した領土拡大の戦争を隠れ蓑にし、我々は更なる調査を続けた。
ウォーケンに関する調査も継続していたが、ようやく、帝都で暗躍していたギブリンという男が所有する自動人形、シェリの製造者がそれであると突き止めた。
ギブリンは国政を動かす将軍や長官達の下で暗殺業を営む、裏社会の住民であった。
このギブリンという男を利用し、ウォーケンが作り上げたシェリを捕らえることにした。
シェリを足掛かりにウォーケンと接触し、ミアに関する情報の一端をつかもうとしたのだ。
屋敷にはギブリンしかいなかった。ギブリンは口の堅い男であったが、拷問の末、シェリは現在、製造者のところに修理に出されているという話しを聞き出すことができた。
加えて、頼んだ訳ではなかったが、興味深い話が聞けた。
「あの博士には以前の記憶がない様子だった。お前達が何を探ろうとも、何も得られまいよ」
用済みとなったギブリンは、結果的に始末した。我々が何たるかを理解せず、我々に襲い掛かってきたのだ。
暫くの時を置いて、シェリは我々の元へとやって来た。その容姿はローゼンブルグに残されていた写真に写るミアに瓜二つであった。
我々は彼女を捕らえてナニーに解析を行わせた。当初の目的は電子頭脳からウォーケンの所在を解析することであったが、その解析結果は思い掛けないものであった。
「この自動人形の電子頭脳と身体構造物の一部から、ミアのパーツと同様のエネルギー波が検出されました」
「そうか」
エネルギー波が検出されたパーツとケイオシウムバッテリーを切り離し、その上で趣向を凝らした細工を施すと、シェリを分解された姿そのままでギブリンの屋敷へ送り返した。
ウォーケンという自動人形の情動を揺さぶってミアの記憶を引き出すことができれば、一向に痕跡の辿れぬミアの捜索が前進すると踏んだのだった。
計略は思わぬ形で終焉を見ることとなった。
突如、ウォーケンと覚しき自動人形のパーツと、彼が所有していた自動人形の製造資料が闇マーケットに流通したのだ。
我々は金額の多寡を問わずにそれらを全て買い取った。
ウォーケンのパーツを検分したところ、近距離からの爆発に巻き込まれた痕跡が見受けられた。記録領域が破損していたために、爆発に至る経緯までは読み取ることができなかった。
そして、回収した彼の研究資料の中に、コデックスと化したミアのパーツが存在していた。
同時期、パンデモニウムが我々に接触を図ってきた。
彼れは拡大し続ける地上の戦果をコントロールし、世界を平定するための協定を結ぶためと嘯いて、皇妃アリステリアを通すことなく、マックスという自動人形、サルガド、ソングの三人を皇帝廟へ直接送り込んできた。
我々は敢えてその申し出を受け、協定を締約した。
そして、顔を変えた我々の一人をパンデモニウムに使者として送り込み、慎重にミアに関する情報を集めた。
ミアの痕跡を得ることは叶わなかったが、代わりに技術提供の一環として、ウォーケンが製造したベリンダという自動人形を受け取った。
これ以上ミアのパーツを捜索することは無意味であると判断した我々は、ヴォイドへと続く道を作り出す装置の完成を優先することにした。
しかし、完成を急ぐあまりに足元の監視が疎かになっていたのであろうか。当代のアリステリアが若い将校に懸想し、その者と共謀して帝國の体勢を揺るがそうとする事態が発生したのだ。
だが、アリステリアの脳には我々と同じ記憶のチップを埋め込んでいる。彼女が何を画策しようとも無意味であった。
「アリステリアよ、すべては我が手の内だ。火遊びもほどほどにせよ」
「申しわけありません。私は……」
「火傷をせぬうちに手を引くがよい」
我々は忠告と共に、彼女に一つの暗示を掛けた。帝國の体制を脅かす者への制裁を彼女に課したのだ。
だが、アリステリアはその暗示に逆らった後、自死を遂げた。その意思の強さは、まさに『アリステリア』たるに相応しいものであった。ただ、その意思が我々に向けられたことは一度も無かったが。
この出来事に伴って、『アリステリア』と過ごしたあの尖塔も失ってしまった。
我々はより一層、本物の『アリステリア』への憧憬を強く意識した。
数年の内に有力な将軍やアリステリアを失った我々は、再び表舞台へ姿を現すことを決断した。将軍達の権力争いに興味はなかったが、我々の計画が終盤に差し掛かる中、帝國内での動乱は極力廃しておかねばならなかった。
ベリンダの暴走により、世界に死者が溢れた。
もうすぐこの世界は死によって覆われ。死者に支配されるだろう。
パンデモニウムは事態の収拾に刻苦しているのであろう。我々に対するカウンシルの干渉が無くなった。
装置の動力としてシェリとベリンダのケイオシウムバッテリーを使用する手筈であったが、それはベリンダの暴走によって計画の修正を余儀なくされてしまった。
だが、ベリンダの暴走と前後して完成した装置を可動させる機は、今を置いて他にはなかった。
フレームが剥き出しになた自動人形が皇帝廟の最深部に現れた。
「来たか。かつての我々よ」
今はマックスと呼ばれている我々の残滓だ。
アリステリアと若い将校の謀反の際に、頭部だけの姿となったそれを発見した我々は、一部のチップを密かに取り替えてパンデモニウムへ送り返していた。
パンデモニウムには純度の高いケイオシウムバッテリーが現存している。ケイオシウムはそのエネルギーの全容が解明されている代物ではない。想定外の事態を克服するためには、予備などいくらあっても足りない。
そのため、予備のケイオシウムバッテリーを入手するための方法として、マックスを送り込んでおいたのだった。
我々の想定通り、戻ってきたマックスは動力源としてケイオシウムバッテリーを内包していた。
「では、始めよう」
矛槍を掲げ、我々はマックスを拘束する。そして、ヴォイドへの扉を開く装置の中心部へと連れて行った。
「お前の力が必要だ。全ては我々の悲願のためにある」
矛槍の峰がマックスの頭蓋を捉える。
突然、マックスが抵抗するように暴れ始めた。マックスの電子頭脳は、今更のように死の恐怖に苛まれているのであろう。
「抵抗することは無意味。お前も我々と共に行く。これは定められたことなのだ」
マックスの全身が矛槍によって貫かれた。
同時に装置を起動させる。マックスを動かすケイオシウムエネルギーが、装置によって意図的な暴走状態へと移行していった。
強い衝撃が皇帝廟を包み込んだ。
それは装置が正常に作動している証拠でもある。暴走したケイオシウムエネルギーが《渦》に似た現象を装置内に作り出した。
擬似的な《渦》は装置に組み込まれたミアのパーツが持つ情報エントロピーを利用し、ヴォイドへと繋がる扉を開く。
「扉は開かれた」
私は強く、自分に言い聞かせるように宣言した。
淡い螺鈿細工のように輝くうねりが、次第に、まさしく渦としか形容できない形となって周囲に広がっていく。
この《渦》の向こうに、我々が求める『アリステリア』がいる。
それを思うと、『私』は歓喜に打ち震えるほかなかった。
一人のカストードが《渦》の中へ入っていく。
我々の視界はそのカストードと同調し、《渦》の内部の様子を記録する。
《渦》の向こうには、淡い色合いが溶け合う以外は何も無い空間であった。
その空間の先に、うっすらとだが、かつて我々と共に生きた『アリステリア』の姿が見えた。
「アリステリア!」
その名を呼ぶと『アリステリア』は振り返り、あの時と変わらぬ聡明な笑みで『私』を見つめ返してくれた。
彼女の元に辿り着こうと、我々は走る。手を伸ばしたが、『アリステリア』は微笑みを称えたまま静かに消え去っていった。ここに来てなお、我が手に戻ることのない『アリステリア』。どうすれば彼女を取り戻せるのか。我々は立ち止まって考え続けていた。
どれほどの間立ち止まっていただろう。ふと、どこからか鈴の音のように柔らかな少女の声が響いた。
「誰だ?」
周囲を見回すと、目の前に炎に包まれた少女が姿を現した。
少女の顔に張り付いた笑みは人間が持ち得ない計算された美貌であり、この少女が人ならざる者であることは容易に伺えた。
「私は戻りたいの。貴方は?」
「我が妻を捜している。ここへ辿り着けば、アリステリアに再び出会える世界へ向かえるのだと」
「そう。……ねえ、その人とずっと一緒にいられる世界が欲しくはない?」
少女は一つ頷くと、張り付いていた笑みを深めて我々に問い掛けてきた。
「アリステリアと再び世界を歩めるのなら、何処であろうと構いはしない」
我々が望む世界はそれだけなのだ。『私』が生きる全ての意味、それは本物の『アリステリア』がいる世界なのだ。
彼女さえいれば、それがどのような世界であろうと構わない。
「そとは世界を作るだけよ。貴方達が手伝ってくれれば、そんな世界も作れるわ」
「そういうことならば、手助けしよう」
新たな世界で『アリステリア』と新たな歴史を紡ぐ。そのために、我々はこの少女を利用することにした。
少女が何を考え、何をしようとしているのかは関係なかった。
「それじゃあ、行きましょう。新しい世界へ」
炎に包まれた少女の声に頷き、その手を取る。
その刹那、我々は元の世界に置いてきた筈の意思ごと、灼熱の炎に包まれた。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ