ミリアン
【死因】
【関連キャラ】
3373年 「胎動」 

戦いは無残に終わった。ミリアンの周りには異形の獣達の屍がある。すべて彼の手によって葬られたものだ。圧倒的な剣圧で破壊された獣達に、原型は残っていない。血生臭い空気が辺りを包んでいる。
小さな勝利の後には、ただ徒労感だけが残っていた。
廃墟に残って獣達を狩る日々。僅かな仲間達も少しずついなくなっていった。
渦から現れる獣達に限りはなかった。この廃墟となった故郷を取り戻すことなど不可能だと、頭では理解していた。
しかし、この戦いが無駄であったとしても、そこに戦い続ける意味はある、と信じていた。
ミリアンの家族はここで暮らし、渦の厄災に巻き込まれて死んでいった。自分だけ逃げるわけにはいかない、という想いがあった。
補給のために街に戻った。故郷からはかなりの距離があるが、そこで故郷の住民達と、難民として細々と暮らしていた。難民としての彼らは、この街の外周や、半ばスラムと化した城下町に、押し込められるようにして生活していた。元から住む住民達との間に軋轢はあったが、街の守備隊の連中がミリアン達を無下に扱うことは無かった。同情だけでなく、外の世界で自分達の代わりに化け物共を退治してくれる訳だから、実利もあった。
ミリアンは守備隊から許可をもらい、街の中へ入った。食糧の補給や、得られた戦利品――異界の獣の毛皮などは高く売れることもあった――を取引するには、こちらの方が効率いい。いつもの商店で食料を買おうとすると、店主が言った。
「悪いな。これ以上あんたらに物は売れないんだ。すまないな」
「そうか、いままでありがとう」
ミリアンはひどい扱いを受けたとは思わなかった。相手の立場を考えれば、仕方のないことだと思った。
「すまんな」
ばつの悪そうな顔をして、店主はもう一度あやまった。
店を後にしたミリアンは市場の露天商とも交渉したが、どの店でも冷たくあしらわれた。
そんな様子のミリアンに向かって、通りすがりの若い男達が毒突いてきた。
「難民風情が市内をうろちょろするな」
「疫病神め」
「おまえらに食わせるものなんてねえよ」
慣れっこになっていた嫌がらせの言葉だったが、徒労感と恥辱が合わさり、衝動を抑えるのに苦労した。
不穏な空気を感じたミリアンは、黙って人混みから去ろうとした。しかしその時、誰かが腐った果物を投げつけてきた。
結構な衝撃に、思わず剣に手が伸びた。
場内での武装は、守備隊のお目こぼしで許してもらっていた。ミリアンがしまったと感じたときには既に遅く、一斉に憎悪が自分へ向けられたのがわかった。
罵声と共に様々な物がミリアンに投げつけられる。
「こいつ、武器を手に取ったぞ」
「追い出せ!ここで暴れる気だ」
「守備隊は何をやってんだ」
ミリアンは市場から離れようとしたが、怒った群衆が自分を取り囲み始めていた。相手は一般人だ、自分が剣を振るえば簡単に納められるだろう。しかしそんなことをすれば、最後に破滅するのは、今は難民と呼ばれて蔑まされている同郷の仲間達だ。
「剣を取り上げろ」
「殺せ」
睨み合うことしかできないミリアンと民衆達。しばらく互いに牽制していたが、民衆の憎悪が収まることはなかった。
その時、守備隊の銃声が市場に響いた。
「どけ、どかんか!」
数人の武装した守備兵が市場に駆け付けてきた。
守備兵はミリアンを組み伏せようとする。ミリアンは抵抗せずに膝をついた。
「馬鹿者が。騒乱などを起こしおって!」
と、守備兵の指揮官が銃床でミリアンの顔を殴った。鮮血が辺りに飛び散る。
「この者は我々が逮捕した。みなとっとと立ち去れ。こいつの処理は我々に任せろ!」
指揮官が居丈高に周りに言いつけると、激昂していた市民達もしぶしぶと立ち去っていった。ミリアンへの憎悪は、この指揮官の態度に焦点をそらされた格好になった。
守備兵に引き摺られるようにして、ミリアンは営倉らしき場所に連れられてきた。
「さっきは手荒なことをして、すまなかったな」
指揮官はミリアンと顔見知りだった。鮮血で汚れた口を拭くようにと、タオルを手渡してきた。
「助かったよ」
守備兵が止めていなければ、民衆に殺されていただろう。ミリアンは抵抗するつもりは無かったが、かといって、命乞いをすることもできない男だった。
「お前らの街から来た難民の犯罪が増えていてね。みな苛立ってるんだ」
怒りも悲しみも無かった。ただ、諦観だけがあった。
「俺達は、この街から追い出されれば、故郷を取り戻すことができなくなる」
「ああ、わかってる。だがな、今の状況がそれを許さんのだ。悪いが武器を預からせてもらう。帰るときに返す」
ミリアンは黙って腰の剣を渡した。
死。その事が頭をよぎった。
街の外では仲間が待っている。皆が死ぬまで戦いを続けるのか。故郷と共に何もかもがこの地上から消えて無くなるまで。
「どうした、暗い顔だな」
黒いコートを羽織った老齢の男が声を掛けてきた。隣のテーブルに座って手招きをしている。
「こっちに来い」
そう言ってミリアンを呼びつけた。
風体はしっかりしており、この酒場には似つかわしくない。
「いろいろ古傷が痛んでな、そっちに行くのが億劫だ」
「誰だ」
「ワシはスターリング。これはおごりだ、とりあえず座れ」
ぶっきらぼうに酒瓶を差し出してきた。
「軍人か」
顔の傷や身なりから十分類推できた。
「長いこと帝國で働いていた者だ」
「帝國の軍人が、こんなところで何をしている?」
ミリアンは受け取った酒瓶を机に置き、向かい合う形で席に座った。
「お前に会いに来た。外で渦の化け物共と戦っているそうだな」
「ああ、故郷を取り戻すためだ」
「その戦いに勝ち目はあるのか?」
挑発するような言い方ではなかったが、スターリングの質問にミリアンは一瞬言い淀んだ。
「勝ち負けで戦っているわけじゃない。あの場所は俺の死に場所なんだ」
絞り出すようにミリアンは言った。
「惰弱な考えだ。目の前の本質から逃げてるだけだな」
スターリングはミリアンを突き放すように言った。
「お前に何がわかる」
「ああ、わからん。負けるための戦いなどな。戦いは勝利のため、価値のためにこそ命を捧げられるものだ」
「帝國ならそれも可能なんだろう。だが渦に飲み込まれた小さな街じゃ、そんなことは戯言みたいなもんだ」
「ワシも渦の脅威と戦ったさ。お前が生まれるずっと前にな。全て負け戦で撤退戦だった。逃げて逃げて逃げまくった。城を築き、鍵を掛けて引き籠もりもした。そして、こうして生き残った」
「それが誇りある戦いだったと言うのか?」
「ワシはこうして二本の足で立っている。たしかに、今じゃうまくは歩けなくなった。だがな、誇りも希望も失っていない」
「俺に説教しに来たのか?」
「いや、協力を頼みに来た」
グラスを傾け、酒をぐいとスターリングは飲んだ。随分と飲んでいるようだが、あまり態度に変化はない。
「それにしては、ずいぶんと腐してくれる」
「失ったお前の街を取り戻すことができるかもしれん。協力してくれるか?」
「戦う場所はどこでもいい。あの街を取り戻すことができるのなら」
「そうか、よかった」
スターリングは乾杯のグラスを掲げた。その老人の笑顔は少年のような力の満ちたものに、ミリアンは感じた。
「―了―」
3373年 「調査」 
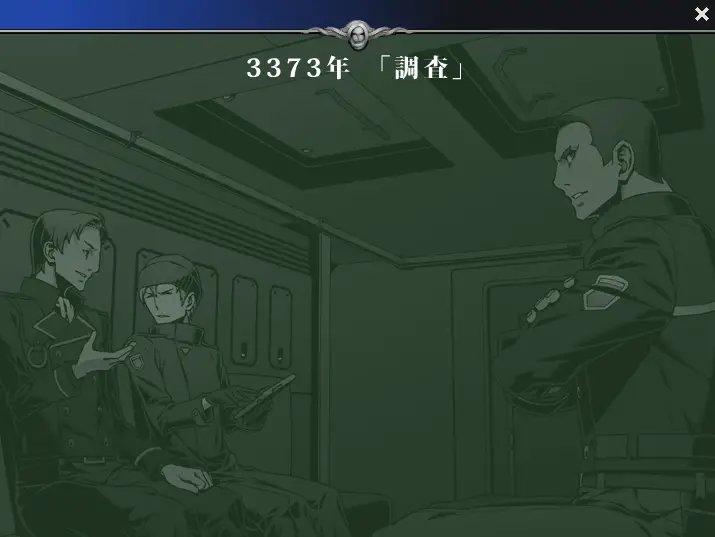
スターリングと共に『渦』へ立ち向かう組織に所属したミリアンに、忙しい日々が訪れた。
ミリアンは数人の仲間と共にこの組織に参加することにした。やって来たのは、故郷ダンカルクから600リーグ程離れた荒野だった。周りには渦がはびこり、荒れ果てた土地しかない。ただ、背後に山があり、エンジニアの作った巨大なウォードが四方に立てられていた。防御は完全に思えた。
「随分な場所にあるんだな」
スターリングが長い旅路を経てやって来たミリアンを迎えた。
「この場所を決めるのに相当な時間が掛かった。渦から離れても、兵站の維持ができなくても面倒だからな」
「エンジニアがうまくやってくれるんじゃないのか?」
「奴らは戦略家じゃない。ましてや戦術家でもない。この連隊のことを地上の開放のための軍ではなく、渦の科学的な調査隊だと考えている連中もいる始末だ」
スターリングはこの組織を単なる軍の基本単位として『連隊』と呼んでいた。後でわかったことだが、周りの皆も連隊――レジメント――としか呼ばないようだった。今、渦との戦争に挑んでいるのはこの連隊しか存在しないのだから、番号も名前も必要無いということらしい。
出来たてのホールにスターリングの男達が集められた。数は百人もいない、皆経験豊富な兵に見えた。女はもちろん、若い男すら殆いなかった。スターリングが設えられた壇上に上がり、声を発した。
「よく集まってくれた。今日が我が連隊の結成の日だ。諸君らの中には元軍人や傭兵、荒野を熟知した交易商、色々な出自の者がいる。しかし、皆が同じ目的を持って今ここにいる。 それは地上の解放だ。 諸君らは失われた我々の世界を取り戻すという大義のために集まってくれた男達だ」
さっと周りを見渡すだけで、何となく男達の出自がわかった。一つ目のグループはわかりやすい。スターリングが連れてきた帝國の兵士だ。階級章や所属がわかるようなものは着けていないが、一見して帝國のものとわかる軍服を着ており、規律正しい軍人らしさを全身から醸し出している。二つ目は傭兵や私兵上がり――これに自分も含まれるだろうが――、彼らは装備も服装もばらばらだが、体格や身なりは戦士として頼りになりそうな者達だ。そして三つ目、異質なグループが二十人程いる。色取り取りのスカーフをぶら下げ、ちょっとした道化か太古の物語の海賊の様な格好をした男達だ。彼らは危険な荒野を旅して交易を担う『嵐の乗り手〈ストームライダー〉』と呼ばれる男達の集団だった。
「酒はまだか!」
スターリングの話は終わっていなかったが、男達から声が上がった。主に傭兵上がりらしい男達からだ。
「話が長いぜ」
その声と共にグラスが壇上の袖に投げ込まれた。激高した帝國の軍人らしい男が大声を上げて振り返る。
「いい加減にせんか!大佐の訓辞はまだ途中だぞ!」
「うるせえ、とっとと酒にしろ!楽しいお話し合いはてめえらだけでやりやがれ、この腰抜け帝国兵が!」
「何だと!」
いきり立った帝国兵達と風体のだらしない傭兵上がりの男達や荒野の密輸人達、つまり、ホールにいたほぼ全員による大乱闘に発展した。
「よし、いいぞ!せいぜい楽しめ!」
スターリングは大乱闘のホールに向かって笑いながらそう大声で叫び、壇から降りた。
壇から降りたスターリングも酒樽から直接酒を汲み、飲んでいる。
「騒がしい連中を集めたな」
酒盛りと乱闘が続く。酒保商が集めた酒樽は逆さにされ、ありとあらゆるものが頭上を飛び交っている。
「なに、昔から胆力がある男というのは、馬鹿な騒ぎが好きなものよ」
ミリアンはスターリングの人となりが少しずつわかってきた。帝國の首都ファイドゥで廃兵院の長という閑職にいたが、兵士からの信望の厚さは折り紙付きの男だった。彼の連れてきた帝國の軍人達は、彼を大佐と呼んでいる。
「これから何をするんだ?」
「まずは訓練、そして渦の調査だ。とりあえずそこまではエンジニア達の計画に沿ってやる。奴らがスポンサーだからな。だが、実際の戦いではしっかりとこちらが手綱を握る」
「そうか、忙しくなるな」
そう語り合っている間も、足下に砕けたグラスの破片が飛んでくる。
「とりあえずの装備と施設、人は揃った。いよいよだよ」
スターリングは嬉しそうな顔をして酒を呷った。齢六十をとうに過ぎた老兵だが、その言葉と顔には若々しさがある。
ミリアンも同じ酒を呷った。呷り終えると同時に、一人の男が派手に転がりながら二人の間に突っ込んできた。
「て、てっめえ、やりやがったな!」
まるまると太った腹と髭面から傭兵と思われるその男は、体格のいい帝国兵に殴られて飛んできたのであろう。ミリアンは倒れた男を引き上げてやった。
「足にきてるな、そろそろやめておけ」
「放せ。俺に忠告なんぞ、百年早え」
太った男の正面には、拳を構えたままの帝国兵がステップを踏んでいる。
「ヘルムホルツ、紹介しておく。ミリアンだ。見ての通りの大丈夫だ。仲良くやってくれ。それとお前の相手になっている奴はヴィット。軍じゃ格闘術教官だった男だ」
少し酔った調子のスターリングが、ヘルツホルツと呼んだ太った男に周りの男達を紹介した。
「おうよ。ミリアン、てめえの相手はまた後でやってやる」
ヘルムホルツはそう言うと、ミリアンから酒杯を奪って口に含み、口中の血を濯ぐと床に吐き出した。そして低い姿勢のままヴィットに向かってタックルを仕掛けた。そのスピードは中々のもので、まるで跳ね回るボールの様だった。ヴィットとヘルムホルツは転がりながらホールの真ん中で組み合った。
「いいぞ、二人とも!」
スターリングは酒を片手に、その様子を見ながら笑っていた。
結団式の次の日から、男達は何事も無かった様に仕事を始めた。まず三〇人ずつのグループに再編して、A・B・Cの三つの中隊が作られた。
各中隊に六名程のエンジニアが合流して、調査小隊が組織される予定らしい。ミリアンはA中隊所属となった。それぞれの中隊毎に渦に関するブリーフィングが行われ、その後、ハンガーとグラウンド射撃場で訓練が開始された。
「おう、ミリアン。調子はどうだ?」
射撃訓練の途中、同じ中隊のヘルムホルツが声を掛けてきた。刺繍されたばかりの連隊の制服が全く似合っていない。そもそも鞠のような体型の男だ。一番大きいサイズの制服の袖を捲り、羽織るようにしてどうにか着ているといった感じだった。
「ひどい格好だな」
「うるせえ。生まれてこの方、制服なんぞ着たことがねえんだから、仕方ねえだろ。それに、他に着るものもねえしな」
「ヒゲぐらい剃ったらどうだ」
髪も髭も伸び放題であることが、さらに風采を上がらなくしていた。
「んなもん、めんどくせえだろうが」
馬鹿な話をしていると、射撃訓練の終わりを告げる声がした。
「射撃訓練なんか必要なものか。ここで教わるようなことじゃねえだろ」
次はハンガーでの操縦訓練だと、A中隊長のミルグラムが大声でそう告げた。
ハンガーには未だ組み立て途中らしき奇妙な機械が転がっていた。剥き出しのフレームに推進装置が取り付けられている以外は、一見、船のような姿形をしている。傍らに中年のエンジニアが立って説明を始めた。
「私は兵装エンジニアのダヴィル、この調査専用機『カッター』の開発責任者だ」
「まだ不格好だが、これを使って荒野の渦へ調査に行ってもらう」
「そして、操縦は君達タスクフォースの隊員にやってもらうことになる」
隣でその言葉を聞いたヘルムホルツが、指を鳴らしながら呟いた。
「そうそう、こーゆーのを待ってたぜ」
三ヶ月ほど掛けて一通りの訓練が終わった頃、最初の調査小隊の組み合わせが発表された。ミリアンは第四調査小隊で、帝國出身のハウスホッター、元ストームライダーのブルベイカー、顔見知りの元傭兵ヘルムホルツ、そして調査エンジニアのメルルが他のメンバーとなった。どうやら違うグループ出身者で小隊を組ませたようだ。
集まった第四調査小隊の前に、ミルグラムが立った。
「お前らのところは一人少ないが我慢してくれ。でかいのが二人いれば問題なかろう」
ミルグラムはミリアンとヘルムホルツを見て言った。
そして小隊長はハウスホッターだと告げられたが、その発表にヘルムホルツが噛み付いた。
「ふん、結局帝国兵のお偉いさんか。気に食わねえな」
「最初はこれでやらせてもらう。いずれ小隊の組み合わせは変わるし、適性を把握すれば役職も変わる」
ミルグラムは皆を見つめて言った。
「ヘルムホルツ、お前のカッターの操縦技術は中々らしいじゃないか。まずは腕で皆を助けてやってくれ」
「お、おう」
ミルグラムはスターリングが信頼している副官とも呼べる人物だった。隊員を纏める事には慣れている風だった。
調査隊は次々と目的地に向かって出発した。ミリアン達A中隊第四調査小隊は、三日目に出発となった。
「いよいよだぜ」
ヘルムホルツが操縦席で呟く。
「ああ、ドジを踏むなよ」
操縦席の後ろに陣取ったミリアンがそれに答えた。
「うるせえ。お前こそ、そのでかい頭をぶつけねえように、しっかりと掴まっておけ」
ミリアンとヘルムホルツの会話の向こうでは、ブルベイカーとメルルが今回の調査地域についての意見を交わしていた。
「この辺りの渦は季節によって荒れ方が変わる。 まずは西からのルートで様子を見る方がいい」
調査地域はマインシュタット山脈の南、旧サンダランド平原にある古い渦だった。
「何度か行ったことがあるのか?」
ミリアンがブルベイカーに訪ねた。ブルベイカーは痩身で窪んだ目が特徴の男だ。その姿はヘルムホルツと対象的だった。
「ああ、だがすぐ横を通り抜けただけだ。渦の活動が活発な時期にわざわざ近付いた事など無い」
ミリアンの質問にブルベイカーが答えた。
「出発するぜ、掴まんな」
ブルベイカーの答えに被さるようにヘルムホルツが言うと、カッターが浮遊した。そして加速度が後席の隊員達に加わり、皆、力を込めて椅子に深く座った。
巡航速度と高度を保つと、またメルルを中心に作戦の確認が始まった。誰もが初めての作戦であり、皆一様に緊張している。一通り作戦の確認が終ると、キャビンは沈黙に包まれた。
カッターのキャビンはそう広くない。渦に近付くまで一八時間、調査に四八時間から七二時間、帰還にまた一八時間、最低でも四から五日は掛かる調査に必要な武器と食料、水を積んでいるのだ。そして、カッターの大きさは最低限に切り詰められていた。
「なあ、ブルベイカー。なぜストームライダー達はレジメントの設立に加わったんだ?あんたらは外部の人間とは関わらないと聞いていたが」
荒野に生きる彼らも、元々は故郷のある普通の人間達だった。が、数百年の渦の混乱の中で生きる術として、城塞都市間の交易を担う存在となっていった。
「それはスターリングから聞いてくれ。俺達の口からは言えん」
「そうか」
「金だろ? 噂で聞いたぜ。ストームライダー達には俺達の三倍の契約金が支払われたって話じゃねえか」
ヘルムホルツが操縦席から話に加わった。
「金だけで自由人である俺達『乗り手』が『囚われ人』のお前らと関わることは無い」
彼らは自分達のことを自由人、都市に引き籠もった人間達を囚われ人と呼んでいた。
「へっ、何が囚われ人だ!お前らはいつも金、金、金じゃねえか」
ヘルムホルツはストームライダー達への差別心を隠そうともしない。小さな都市国家では、交易の担い手であるストームライダー達を、暴利を貪る商人、として嫌うことも多かった。
「やめるんだ、ヘルムホルツ」
ハウスホッターがヘルムホルツの無礼を諌めた。
「けっ、いい子ぶりやがって」
再びキャビンに沈黙が広がった。ミリアンは窮屈な席の中で目を閉じ、眠ることにした。
「―了―」
3373年 「未知」 

レジメントの施設を発ってから十五時間ほどが過ぎていた。このまま順当にいけば、あと数時間で旧サンダランド平原に到着する。
ミリアンはカッターの操縦をヘルムホルツに交代し、何度目かの仮眠を取っていた。
不自然に揺れるカッターからの振動で、ミリアンは目を覚ました。
「くそっ、蝿みたいにブンブンと目の前を飛び回りやがって……邪魔くせえ」
操縦席のヘルムホルツが悪態を吐いている。
「何があった?」
揺れるカッター内でメルルに尋ねる。
「適性生物だ。機体に体当たりしているようだな」
キャビンの脇にある小さな窓を覗くと、カッターの周りを歯を剥き出しにした異形が飛び回っていた。
骨格や翼は蝙蝠に似ているが、爪や顔から生えた針のような牙は、生身の人間だったら簡単に引き裂かれてしまうだろう。
重い衝撃音が機体に響いた。適性生物が激突したようだ。
「この機体は大丈夫だろうな?」
ハウスホッターがメルルに訪ねた。
「このサイズなら、おそらく問題は無い」
「おそらく?」
思わずミリアンが訪ね返した。
「確定的な情報が全てわかっているなら、調査隊など必要ないだろう」
メルルは状況を端末に打ち込む作業を続けながら言った。エンジニア独特の抑制的な口調だ。
その間にもまた、重い衝撃音がキャビンに響いた。
「ミリアン、お前に替わったほうがいいんじゃないか?」
ブルベイカーが言った言葉を、操縦席のヘルムホルツは聞き逃さなかった。
「聞こえたぞ!じゃあ、てめぇがやってみろってんだ!」
キャビンに振り向いて大声で叫び返す。
「おい、操縦に集中しろ」
ハウスホッターがたまらず仲裁する。
「ふん。なら、その役立たずなやせっぽちの口を押さえとけ!」
ヘルムホルツが怒鳴った。
「あいつの腕が落ちるなら誰の操縦でも落ちる。任せよう」
ミリアンは大きく揺れる機体の中で、周りのメンバーに言った。
途中何度か進路を調整したため、到着予定時刻には間に合わなかったが、カッターは調査ポイントへと辿り着いた。
カッターを大きな段差の影に着陸させると、メルルを中に残して、四人はカッターを背に庇うようにして立った。
周囲に魔物の姿は見えない。
一時的ではあるが多少の安全が確保されたところで、メルルが小型の障壁器を展開させた。これでカッターの半径3アルレ圏内の安全は強固なものとなる。
しばらくはここが、ミリアン達第四調査小隊の拠点となる。
ここから渦に近づき、周辺の情報を計測して帰還するのが、今回のミッション内容だ。
「何を調べるんだ」
ミリアンはメルルに聞いた。
「ケイオシウム濃度や環境、適性生物の分類、諸々だ」
計測器のチェックをしながらメルルは言った。
「この時期の渦は活動も活発だ、素早く済ませよう。渦の知覚では何が起こるかわからない」
「ずいぶんと弱気じゃねえか。ビビってんのかよ」
ヘルムホルツがブルベイカーに突っ掛かっていた。
「俺は馬鹿でも無謀でもないからな。我々は渦の流れを読み、渦の脅威を知ることで生きてきた。ぬくぬくと都市の壁に守られていたお前よりは、よく知っている」
「そうかいそうかい。じゃあ、せいぜい働けよ。俺達より貰ってるんだからな」
「報酬だけでこのレジメントに参加したわけではない」
「よく言うぜ」
「互いに争っても、誰の特にもならん」
殴り合わんばかりの調子の二人に、ミリアンが割って入った。
「こいつの肩を持つのかよ、ミリアン」
「怒りは魔物相手に取っておけって言ってるんだ。 ここで死にたいわけじゃあるまい」
ブルベイカーとヘルムホルツは互いに鋭い視線を交わすと、それぞれの持ち場に立った。
渦の周辺調査は苛酷なものになった。散発的に現れる魔物を相手にするため。五人は常に緊張状態にあった。
最初の内は相当数の悪態や軽口を吐いていたヘルムホルツですら、時間が経つにつれて口数が減っていった。
「あの高くなった岩場まで近づけるか?あそこから調査ドローンを送り込みたい」
メルルの提案にハウスホッターは隊員達を確認した。弾薬はまだ十分にあった。だが、緊張感からか、全員が疲労しているように見える。
「問題ないぜ。俺はまだまだやれる。臆病者のやせっぽちはどうかしらねえけどな」
乳白色の霧が奇妙な色合いに反射する渦の境界線が、不安定な明滅を繰り返していた。
「問題ないだろう。渦は少し落ち着いているようだ」
ブルベイカーはヘルムホルツの挑発を無視して答えた。
「問題ない」
ミリアンも答えた。疲労感は精神的なものだった。まだ行けると、正直に思った。
霧が少し晴れると、境界上にある岩場にメルルは観測装置を取り付けた。ドローンをコントロールする機械のようだ。
「これを送り込めれば、今回の調査は成功だ」
メルルにしては感情のこもった言葉だった。
ミリアン達は近辺で、魔物の出現を警戒するべく渦の中を注視していた。
最初はほんの僅かな違和感だった。呼吸するかのように収縮と拡大を繰り返す光の中に、何かが見えた。ミリアンは目を凝らして霧の中を注視する。
暗く輝く渦の中には、苔色をした凸凹の岩盤のようなものと、藍色をした細長いオブジェが見えた。その先には乳白色をした空間が広がっている。
苔色の岩盤が渦の中に拡がる大地だということに気付くのに、さほど時間は掛からなかった。その先に見えるのは空ということになるのだろうか。
奇妙な異界の姿だった。渦が異界との境界であることは散々教えられていた。だが、実際に向こう側を見るのは初めてだった。
ちらちらと現れては消えるその姿は、幻覚でも映像でもない。現実だった。霧と光、渦との境界に現れる悪夢の世界。
自分の故郷と家族を奪ったものの正体と、ミリアンは対峙していた。
「メルル、渦の動きがおかしい。そろそろ潮時だ」
ブルベイカーは渦の些細な変化も見逃さない。長い経験から向う側で何が起きて、次にこちら側で何が起きるのかを知っているのだ。
「いや、まだだ。あと一◯分」
メルルは目まぐるしく数値が変わる調査器の記録を、余すところなく取っていた。メルルは興奮しているようにも見えた。
「メルル、ブルベイカーの言うとおりだ。撤退するぞ」
「だめだ!」
メルルはハウスホッターの意見すら意に介さず、計測器の数値を見つめていた。
「……っ!」
メルルの腕に一瞬でとりついたその蔦を、ヘルムホルツは散弾で吹き飛ばした。
「後ろだ、気をつけろ!」
ブルベイカーがヘルムホルツに叫んだ。
咄嗟にその丸い身体を反転させ、襲いかかる蔦をショットガンで吹き飛ばした。
「礼は言っとくぜ」
「チームの為だ」
ブルベイカーとヘルムホルツはそう会話すると、次々と襲いかかってくる蔦との戦いを再開した。
ミリアンはメルルを掴むようにして守っている。触手のように伸びてくる蔦が、ミリアンを鞭のように襲った。銃剣で払おうとするが、相手の棘で肩口を切り裂かれた。
「コンソールが!」
「あとだ!」
次々と飛び出してくる蔦を銃剣で切り伏せ、調査隊は境界線から撤退を始めた。
岩場を転がるようにして下り、どうにか蔦の猛襲から逃れることができた。
「コンソールを回収しなければ……。これではここに来た意味が無い」
腕から血を流したままのメルルが言った。
「馬鹿を言うな、死んじまうぜ」
ヘルムホルツが反論した。
自然と、隊長であるハウスホッターに視線が集まった。
「ブルベイカー、どう思う?」
「回収するものの詳細を教えてくれ。俺一人なら上手くやれるかもしれん」
少しだけ考えた後、さっきの戦闘で無傷だったブルベイカーが言った。
「わかった、一時間だけ回収作業を行う。怪我の状態もある」
ハウスホッターはそう隊員達に告げた。
「無理はするなよ」
「バックアップに回ろう」
ヘルムホルツがブルベイカーに言った。ヘルムホルツも傷は殆ど無い。
「わかった。頼もう」
二人はメルルが指定した機器を取りに、また岩場を登っていった」
一時間が経ったが、二人は帰ってこなかった。
ハウスホッターは撤退の準備を始めた。
「待たないのか?」
ミリアンはハウスホッターに言った。
「これ以上の危険は冒せない。カッターまで戻るぞ」
ミリアンは意識を失いかけているメルルを起こし、傷付いていない方の肩を貸してあるき始めた。
その時、岩場の上から音が聞こえた。
三人は動きを止める。霧の向こうからはヘルムホルツとブルベイカーが下りてきた。
「こいつでいいのか」
ヘルムホルツがメルルの指定したコンソールを抱えあげてみせた。
「……そうだ。それでいい」
メルルは小さな声でそう言うと、意識を失った。ミリアンにメルルの重みが掛かってふらつきそうになったが、ハウスホッターが反対側から支えた。
「さあ、帰りの時間だ。油断するな」
ハウスホッターがそう言うと、調査達はカッターへ戻る道を進んだ。
帰還したミリアン達を迎えたのは、他の調査隊の疲弊した戦士やエンジニア達の姿だった。
規模の程度に差こそあったが、それぞれ埒外の現象に見舞われて、どうにかこうにか帰還してきたのだろう。
レジメントが立ち向かおうとしている渦は、あまりにも強大な存在であった。
それから幾度となく調査隊が組まれ、犠牲を出しながらも渦の研究は進んでいった。
エンジニア達から支給される装備品も改良され、初期の頃とは比べ物にならないほど利便性を増し、強力なものとなっていった。
しかし渦の正体があきらかになっていくことと比例するかのように、犠牲者も増え続けていた。
渦を消滅させるための理論が確立し、それを行うための装置が完成したのは、追加の隊員達がレジメントに入隊してすぐのことであった。
新しいセプターの取り扱いに関する一通りの説明が終了し、ミリアンは次のブリーフィングのためにハンガーへと向かっていた。
その途中に通りかかった射撃場では、新隊員達が訓練を行っていた。
渦消滅の主力とするべく新たに各地から集められた男達は、心なしか若い連中が多かった。
渦と戦う部隊の名は、少しずつだが大陸の各都市で話題になり始めていた。去る者が入れば、来る者もいる。
「ミリアン、もうすぐ新型コルベットの説明が始まるぞ。急いでくれ」
「ああ、すぐに向かう」
新兵の訓練終了を待たずして、ミリアン達A中隊が最初の渦消滅作戦に参加することになり、その前準備としてブリーフィングを重ねている。
ミリアンは訓練中の新隊員達を一瞥して、足早にハンガーへと向かっていった。
「―了―」
3376年 「光明」 
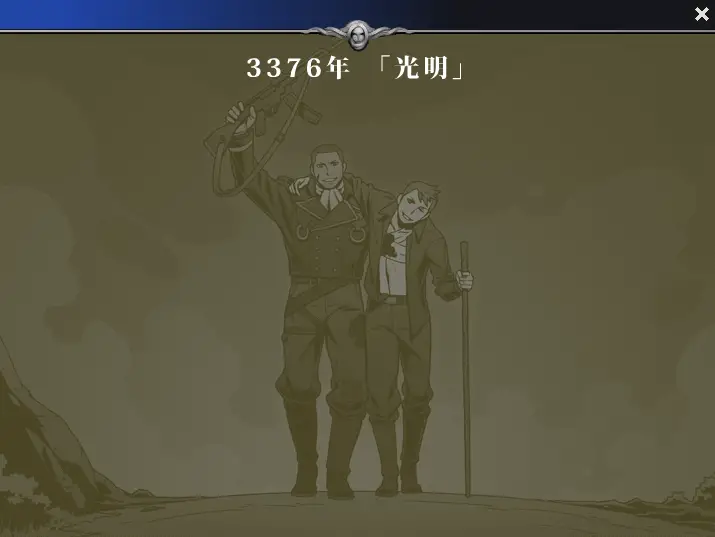
「これにより最終ブリーフィングを開始する」
作戦会議室にはA中隊に所属する全ての隊員と、他の中隊の隊長格が集まっていた。
エンジニアの用意した大型のモニターには渦周辺の様子が映し出されている。
「これが今回の作戦で攻略する渦の全容だ。規模はBクラス、敵性生物の脅威度はC。場所はレジメント施設から東へ300リーグ。旧オーネ山の麓となる」
A中隊付きのエンジニアであるラッカが、渦の説明を開始する。
世界で初めての渦を消滅させる作戦が開始される。その先陣を切るのはミリアン達A中隊だ。
作戦概要を聞いていたミリアンは自然と威儀を正した。それは他の隊員達も同様だった。
レジメントの隊員は、この日のために幾度とないブリーフィングと訓練を重ねてきた。今回の作戦が成功を納めれば、自分達がやっていることの正しさが証明され、世界を渦の脅威から救う光明が見える。
それを思えばこその緊張だった。
「どうした、緊張してるのか?」
「俺のセリフだろう、それは。お前こそ筋肉が震えてるぞ」
「馬鹿を言うな。こりゃ武者震いだ」
ヘルムホルツは戯けたように肩を竦めた。緊張の中にあってもいつも通りの態度が取れるこの男は、隊の中では貴重な存在である。
「まあいいさ。これが成功すれば俺達のやってきたことが徒労でないと証明できる」
「相変わらず真面目だな」
「かもしれん。さあ、もうすぐ作戦開始だ」
「ああ。頼りにしてるぜ、ミリアン」
ミリアン達は新型コルベットで、旧オーネ山へと近付いた。
新型コルベットが四機、コアを回収するための装備を乗せたアーセナルキャリアが一機という編成だった。
渦が近付いてくる。
「突入するぞ!」
通信が入り、ミルグラムの声が聞こえた。
ミリアン達は身構える。渦は調査作戦では何度も行ったが、戦闘が主目的で突入するのは今回が初めてである。
渦への突入と同時に、ミリアンは一瞬だけ船酔いのような気持ち悪さに襲われる。
「作戦展開位置への到達を確認、降下します」
操縦席のダニエルからの合図と共に、コルベットとアーセナルキャリアが降下する。
そこは風が強く吹き、灰色の砂が支配する不毛の砂漠だった。幸いにも日光になるものは出ておらず、熱で体力を奪われることは無さそうである。
コルベットから隊員達が降りると、ミルグラムが最終指示を出す。
A中隊全員が同一の行動を執るのは、ここまでであった。
「A3、A4小隊は予定通りここでコルベットの護衛を頼む。我々の帰還予定は四時間から五時間後だ」
ミルグラムはA中隊全員の顔を見回している。極度の緊張に置かれていないかを確認するためだ。
「異界では通信に制限がある。我々の帰還が予定時間を超過した場合は全滅したとみなし、速やかにここを脱出せよ」
ミルグラムの言葉に隊員達の表情が強張る。頭では理解しているものの、やはり緊張下で聞く言葉は重みが違う。
「では、出発するぞ!」
男達の雄叫びが異界に響き渡った。
ミリアンはA2小隊の小隊長としてアーセナルキャリアを護衛しながら、渦の中心であるケイオシウムコアのある場所へと向かっていった。
「70アルレ先に反応。コアと敵性生物です!」
A1小隊の索敵担当からアーセナルキャリアに通信が入る。ミリアン達はライフルの安全装置を外して身構える。A1小隊は斥候として先行しており、ミリアン達A2小隊の200アルレ程先を進んでいる。
渦を消滅させるために必要な工程は、全てアーセナルキャリアが握っている。
ミリアン達A2小隊の任務は、コア周辺の敵性生物やコア生物と呼ばれる魔物を狩り、アーセナルキャリアがコアを回収するまで打護衛することだ。
さほど経たぬ内に魔物の悲鳴が聞こえてくる。
「三時の方角に敵性生物の反応を確認!」
「迎撃しろ、こちらに近付けさせるな!」
敵性生物がアーセナルキャリアに向かって突進してくるのが見えた。距離を測って合図を出す。三時方向にいる隊員達が一斉にアサルトライフルを掃射する。
何とか第一陣を退けたが、間髪を入れずに第二陣が襲ってくる。
「撃て!一匹も逃すな!」
ミリアンもアサルトライフルで応戦する。ここでアーセナルキャリアが行動不能になれば、全てが無に終わる。
負傷者を出しながらも、どうにかして敵性生物を掃射した。
あとはA1小隊と合流し、コアを回収するだけだった。
A1小隊は、既にコアを守る敵性生物と交戦中であった。
「接敵!斉射!」
「ベゴーニャが負傷!衛生兵!」
隊員達の声が飛び交う中、ミリアン達A2小隊はライフルでA1小隊を援護する。
「A2小隊到着しました!」
ミリアンはミルグラムに駆け寄り、状況を報告する。
「アーセナルキャリアは?」
「上空の安全が確認できたので、50アルレ上空で待機しています」
「わかった。コアはすでに確保している。あとはここの敵性生物を掃射するだけだ」
「了解しました!」
どれくらい戦ったのだろうか。感覚が麻痺するほどの激戦であった。ライフルの弾は尽きかけ、セプターのエネルギー残量もあと僅かであった。
「コアの回収を確認。撤退するぞ!」
ミルグラムから合図が出された。ミリアンは額に浮いた汗を拭いながら周囲を確認する。そこには敵性生物の死体しかなかった。だが、こちらの負傷者も数え切れない。
それでも、コアを回収したという達成感がそこにあった。
「退路を確保した!この先には敵性生物の反応なし!」
「油断するなよ。必ず敵性生物が襲ってくると思え!」
ミルグラムの指示にはっとする。帰還途中に敵性生物に襲われないとは限らない。コルベットに残したA3、A4小隊も心配であった。
もしコルベットが破壊されていれば現世界への帰還は不可能になる。最後まで油断は禁物であった。
負傷者を庇いながら作戦展開位置まで戻ると、負傷したA3、A4小隊の面々がほっとしたような表情で出迎えた。
「お前達、随分とボロボロだな。何があった?」
「お前らが行って暫くしたら、狼みたいな姿の敵性生物が大群で襲ってきやがった」
「まあ全部掃討したがな。この通り、コルベットは無事だ。死者も出ていない」
A3小隊を執っていたヘルムホルツとブルベイカーの報告を受ける。
やはり、敵性生物は我々が『招かれざる客』であることを本能的に察知しているようだった。
「コルベットに搭乗しろ!帰還するぞ!」
結節点《ノード》を通り、見慣れた現世界の大地が姿を現した。
渦は最後尾のコルベットが現世界に姿を現したと同時に、揺らめきながら消えていった。
「やった……」
ミリアンは小さく呟いた。力の入らなかった拳に力が戻ってきたような気がした。
コルベット内のあちこちから感極まったような声が聞こえ、ついには大歓声となった。
ふと、ミリアンは家族の顔を思い出した。妻と子供が遠くから満面の笑みで手を振っている、そんな錯覚に囚われていた。
コルベットが施設に帰還すると、A中隊の面々はスターリング自らの出迎えを受けた。今回の渦の消滅に成功したことは、既に施設内に知れ渡っているようだった。
検疫を受けた後、A中隊には酒と食事が振る舞われた。最初の作戦を成功裏に納めたことを祝して、ささやかながらの宴が催されたのだった。
「なあ、ミリアン。お前、どうしてこの連隊に入ろうと思ったんだ」
ヘルムホルツが酒の勢いで聞いてきた。
「何だ?改めて。そういうお前はどうなんだ?」
「俺か?俺は新しい刺激が欲しかったんだ。ただの傭兵をやってるだけじゃ飽きちまってよ」
そう答えるヘルムホルツの目は遠くを見ていた。この男も何か他人には言えない事情を抱えているのかもしれない。
「ほら、次はお前の番だ」
「俺は家族のため、だな」
「家族か」
「あぁ……」
それ以上は答えることができなかった。家族がどうなったかについて、今は語りたくなかった。
連隊に来る前は故郷のみんなを守るために渦の魔物と戦っていた。その時から家族のことは意図的に考えないようにしていた。だが渦の消滅に成功した今、やっと家族のことを振り返ることができた。優しかった妻、生きていれば幼児期に入る子供、渦によって壊されたささやかな幸せ。
渦の消滅という確固たる事象が、どうすることもできなかった無力感を癒やしていくような気さえしていた。
「これで家族に対して胸を張れそうだ」
「そうだな。渦を消滅させることができた」
もう、あの時のような徒労感に苛まれることはない。
ミリアンはそう強く感じていた。
「―了―」
3387年 「家族」 
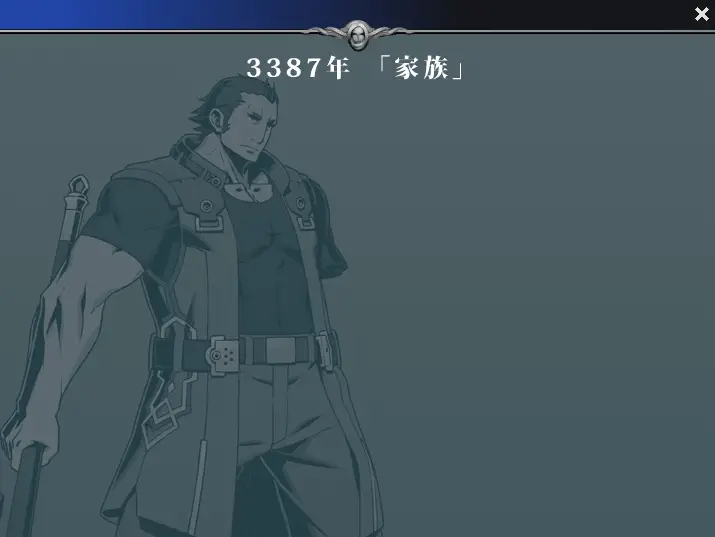
「ジ・アイ攻略作戦の凍結を解除する」
――連隊の精鋭で構成されたE中隊の全滅――。この最悪の結果を迎えた第一次ジ・アイ攻略作戦。一個中隊の壊滅という結果は、現状ではジ・アイ攻略の見込みが立たないとされ、打開策が見つかるまで作戦は凍結とされていた。
「ロッソ技官が一隻のみ帰還したE中隊のコルベットにあったデータを解析し、ジ・アイ専用のコア回収装置の理論を完成させた」
連隊付きエンジニアであるロッソが発表した『量子通信を応用した世界軸間でのコア回収同期装置』。これが実用に値するとパンデモニウムに認められ、ジ・アイの完全な消滅に目処が付いたのだった。
「ジ・アイは混沌を撒き散らす渦の中で、最も強大な結節点《ノード》である。綿密なシュミレーションの結果、ジ・アイのコアを回収すれば、他の渦も消滅することが判明した」
テクノクラートが作戦室のモニター上のジ・アイに大きなバツ印を表示させる。それに連動して、地図上の全ての渦にバツ印が付く。
「作戦プログラムは用意した。これを素に各中隊の役割を決定し、動的シミュレーションを実施せよ。攻略作戦開始は三三八九年風月七日。この日まで、専心して動的シミュレーションでの成功率上昇に努めてもらう」
作戦室のエンジニアが第二次ジ・アイ攻略作戦の概要と、各中隊が為すべき仕事を発表していく。
「スミス司令、この内容でよろしいですかな?」
「ああ、問題ない。皆もそれでいいな?」
テクノクラートの言葉に、スミスと呼ばれた男は神経質そうに頷いた。この頼りなさげな風貌の壮年の男性。これが現在の連隊総司令であった。
数年前、スターリングは連隊長の座を辞していた。
暫くの間は長年彼の副官的な立場であったミルグラムが連隊長代理となっていたが、それもパンデモニウムがスミスを着任させたことによって役目を終えた。
そして、そのミルグラムもスターリングを追い、連隊から去ってしまっていた。
新連隊長のスミスは南方にある都市国家で長年軍を率いてきたということだったが、今はエンジニアが多数を占める作戦室の提案にただ従うだけの男であった。
そのため、ミリアンを含む古参の隊員達には、彼はパンデモニウムの命令にただ首を縦に振るだけの傀儡のように見えていた。
「運が良ければ、再来年には故郷へ帰れるんだな」
「はは。ボード、お前は先走りすぎだ。まずは作戦の成功が第一だろう」
終わりが見えれば連隊が無くなった後の話も出てくる。それは当然のことだった。動的シミュレーションに関する会議後の雑談でも、祖のような会話をする隊員隊が増えていた。
「ミリアン中隊長は、渦が全部無くなった後はどうするんです?」
「ああ、そうだな……」
軽い雑談として話を振られたものの、ボードの言葉にミリアンは答えに詰まってしまった。
連隊に入隊して十五年近く。守れなかった家族への弔いを込め、ただひたすらに《渦》を消滅させることだけを考えてきた。
《渦》を消滅させた後のことなど、今の今まで考えたことはなかった。
ボードから話を振られて以降、ミリアンは未来に向けた会話をする隊員達から自然と避けるようになった。
家族を失って連隊に入隊してからのミリアンは、人生の全てを《渦》の消滅に捧げてきたといっても過言ではない。
仲間を失っても、多くの部下を失っても。それも只がむしゃらに突き進んできた。そんなミリアンにとって、未来を想像することは難しかった。
「浮かない顔をしているじゃないか」
人の多い場所を避けるように食堂の片隅で静かに食事をしていたミリアンに、ラームが声を掛けてきた。
ラームは連隊が再編された歳に、エンジニア側の増強要員として配属された人物だ。
エンジニアの中では鷹揚な性質で隊員達とのパイプ役も担っている。
「そう見えるか?」
「例の件のこともあるからね。仲間が罪を犯すのは見るに耐えんだろう。それは理解できる」
例の件とは、聖騎士の力を悪用する違反者の捕縛のことだろう。力を得れば、それに溺れる者が出るのは当然であった。とうとう都市に出て犯罪行為に手を染める者も現れたため、ミルグラムの主導で本格的に処罰が開始されたのが数年前のことだ。
ミリアンはミルグラムから業務を引き継ぎ、その違反者の捕縛を指揮していた。ラームはその違反者をパンデモニウムに送致する役目を担っている。
その為か、自然とラームと接する機会が増え、適度に雑談を交わす程度には交流があった。
「いや、昔から力に溺れる者は多かった」
ミリアンは溜息を吐く。連隊が発足した当初から、絶えずそういった者が現れていたのだ。
「そうらしいな。いくつか話を聞いたことがある。特に酷い話だと、モーガンという男が我々の開発した装備を奪取し、連隊から逃走したことがあるとか」
「貴方の耳にも入っていたか。もう随分昔の話だというのに……」
貴重な装備を奪取したということで、ストームライダーを中心とした捕縛部隊が編成されたほどの事件だった。
「《渦》に捕縛部隊が足止めされ、そのまま行方が知れなくなったのだったかな?」
「ああ。その事件に関してはもうどうにもならない。整理も終わっている」
彼らが何か事件を起こしていないかは気掛かりだったが、それも十年以上前の話なのだ。
「では、何か他の悩み事かね?」
「そんなところだ」
「ふむ。よければ話してみて欲しい。吐き出すだけでも、少しくらいは楽になるだろう」
ミリアンは目を瞬いた。いくら鷹揚で気さくであるとはいえ、他者に関心の薄いエンジニアが地上の人間に親身になるとは思えなかった。
だからこそだろうか、ミリアンは打ち明けてしまった。妻子を失った虚無感を《渦》を消滅させることで埋めてきたことを。それ故に未来を想像できない恐怖を。
「今まで敢えて何も考えずにやってきた。だから、先のことを想像できない」
「そういうことだったか。ならばどうだろう。私の研究室に来ないか?」
ミリアンの話を聞き終えたラームはゆっくり頷くと、小さな声でミリアンに囁いた。
「何故?」
「その悩みを解決する可能性が私の研究室にある、と言えばどうかね?」
ラームはそれだけ言うと、研究棟の方へと去っていった。
ミリアンはラームの研究室の扉を叩く。
今までならば胡散臭いを一蹴しただろう。だが、今のミリアンはこの纏わり付くような不安を抱えることに疲れ果てていた。この不安を取り除くことができるというのなら、縋ってみたい気持ちがあった。
研究室に入ると、ラームとロッソ、そして見知らぬ一人の女性が立っていた。女性の後ろには球体のドローンが浮遊している。
「やあ、ミリアン。よく来てくれた」
ラームと女性は笑顔でミリアンを出迎えた。ロッソだけは不機嫌そうな顔をしていた。
「この人はマルグリッド。我々の同志だ」
「マルグリットよ。ラームから話は聞いているわ」
「ラーム、ロッソ、これは一体?」
ミリアンは困惑する。ロッソがラームの研究室にいることは理解できる。だが連隊施設に部外者を入れるのは厳禁であり、エンジニアでも例外なく厳しいチェックが義務付けられている筈だ。
「彼女こそが、君の悩みを解決することができる可能性を持った者だ」
「だからと言って、部外者を施設に入れることはできないだろう。どうやって――」
「そんな瑣末なことを気にする必要は無い。こっちはとっとと本題に入りたいんだ」
ロッソが苛立ちを隠しもせずにラームを促す。
「はは、そういうことだ。では本題に入らせてもらうよ」
ラームはミリアンを見据える。その目にはいつもの鷹揚さは微塵も感じられない。
「ケイオシウムの力によって、渦が多重世界のあり得ない可能性を結び付けていることは知っているね?」
ミリアンは頷く。連隊に入った者ならば誰でも知っていることだ。
「だが、それはケイオシウムが持つ力の間違った使い方に過ぎない。暴走が招いた結果と言ってもいい」
「私達はケイオシウムが本来持つ、現実を書き換える力をコントロールするための研究を続けているの」
「現実を書き換えるだと……。そんな都合のいい話など、ある筈はない」
扉を叩いた当初こそ希望を持っていたミリアンだったが、ラームとマルグリッドの話はあまりにも現実から掛け離れていた。
「いいえ、事実よ。私という存在がそれを証明しているわ」
突然、マルグリッドの姿が掻き消え。ミリアンの背後に現れた。そしてミリアンが胸に下げていたドッグタグを取り外す。そしてそのドッグタグを持ったまま、今度はラームの執務机の前に現れてドッグタグをロッソに手渡す。
「信じられんだろうが、この女は研究中の事故でケイオシウムコアと融合している。身体こそ失っているが、このドローンを本体として実存している。何処に行くのも現れるのも自由自在って訳だ」
「私は一度死んで生まれ変わったのよ。そして融合したコアを使い、多元世界を行き来できるようになった」
「本当……なのか。そんなことが可能だなんて」
俄には信じられなかった。だが、目の前でこのような事象を見せ付けられては、彼らの話が事実であると認めなければならなかった。
「現実を見ろ。俺達は不可能と思われていた事象を乗り越えることができる」
ロッソは強い口調で言い切った。
「我々はジ・アイのコアを利用して、あらゆる可能性を見出だせる世界へ渡る。そのためには連隊からの協力者が必要だ。見返りは君が望む世界。魅力的な話だとは思わないか?」
「私達に協力してくれれば、貴方の望みを叶えられる。貴方の協力が必要なの、ミリアン」
一瞬だけ迷いが走った。だが《渦》が消えた後、平和になった世界で妻子と共に暮らせるという希望が、ミリアンの胸を照らしてしまった。
「……わかった、協力しよう。で、俺は何をすればいい?」
「契約成立ね。よろしく、ミリアン」
ミリアンは差し出されたマルグリッドの細い手を取った。映像だというが、握手を交わした感触が確かにあった。
マルグリッドのもたらした知識は、ミリアンに確かな希望を与えた。
彼女達に協力することで、失った妻子を取り戻すことができる。
そのためなら、連隊を売り渡すことなど造作もなかった。
竜人の塔の頂上にある吹き抜けで、ミリアンはベルンハルトと対峙していた。
「それと、そいつらを排除しろ」
ロッソの言葉に、ミリアンはベルンハルトへ銃口を向ける。
「悪いが、俺はロッソと行く所があってな」
「何故こんな真似を?」
ベルンハルトの言葉がミリアンの脳を通り抜けていく。長く共に戦ってきた部下であるが、今となっては瑣末なことであった。
「心配するな。 渦は無くなる。新しい世界が始まるんだ」
一瞬の攻防だった。ミリアンは片腕を失ったが、ベルンハルトをコアから遠ざけることに成功した。
そして、ミリアン達はジ・アイのコアに包まれ、ついに零地点へ渡ることに成功した。
零地点に渡ったミリアンは様々な可能性を目にした。そしてその可能性の中に、元気な妻子の姿があった。
だが、マルグリッドが言うには『航海士』がいなければその可能性を現実のものにすることはできないとのことだった。
ミリアンはマルグリッド達と共に航海士を探し続け、ついにミリガディアのスラムにいることを突き止めた。
かつて連隊の見習い隊士であったレオンを利用し、ラームの手引きで現世界に帰還した。
ミリアンはミリガディアのスラムでアーチボルトと対峙していた。
航海士の少年はアーチボルトと縁があるらしく、幾度もアーチボルトからの妨害を受けたが、深く詮索はしなかった。
かつては背中を預け合った仲間だが、失った妻子を取り戻す障害となるのであれば、殺してしまう以外の未知などありはしなかった。
死闘の最中、ミリアンとアーチボルトは少なくない言葉を交わす。
「どうしても理由が知りたい。 何故お前らはジェッドを追う? エンジニア共の意図は何だ?」
どちらにも引けぬ理由があった。だが、その理由の真の意味をどちらも語らなかった。
「エンジニアの連中にも派閥がある。その中でも、ケイオシウムの真の力を開放しようとしている」
「真の力?」
「現実を書き換える力だ。 その力があれば、人は無限の可能性の中から理想の状態を取り出すことができるようになる」
「馬鹿げた話だ」
「その能力、エンジニアの連中が言う『航海士――スーパーノート――』の力を、あの子だけが獲得できた」
「都合のいい話だ」
ミリアンは妻子と再開するために航海士の少年を得ようとし、アーチボルトは別の信念によって航海士の少年を守ろうとする。
「でかい図体をしているくせに怖じ気突くとはね。 あとはあの鼠一匹だけなのよ」
マルグリッドはアーチボルトを侮っているようだった。
「ミリアン、ここまで来たのだから、最後まで契約を果たしなさい。あなたの望みはすぐそこよ」
「ああ、わかっている」
ミリアンは地面に突き立てていた戦斧を抜き、アーチボルトが飛び退いた方向へ身体を向けた。
死闘の末、ミリアンはついに仰向けに倒れた。
アーチボルトも共に倒れた。あとはマルグリッドが上手くやるだろう。
「終わりなど無い……。俺達は……」
霞む視界に、零地点で垣間見た妻と娘の姿が映し出されていた。
妻子の表情はわからない。ただ目の前にいる、それだけしかわからなかった。
手を伸ばそうにも、そのような力さえ残っていなかった。
いつまでも差し伸べることができない手。妻と娘の姿が、ミリアンの意識と共に闇に呑まれていった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ