メリー
【死因】
【関連キャラ】ヴィルヘルム(憧れ)、ギュスターヴ、ルディア
「夢路」 

優しい光が降り注ぐテラス。そこではメリーと隣国の王子であり婚約者であるヴィルヘルムが、午後のひと時を過ごしていた。
「ハーブ園の視察はいかがでしたか?」
「よく育っていたよ」
「ああ、楽しみ。貴方の国のハーブで入れるお茶は、とても優しい味がしますから」
メリーは、小国ながら資源と自然が豊かな国の姫だった。威厳ある父王と優しい母、頼もしい女騎士であるルディアと共に、平和に暮らしていた。
しかしある時、北の大国が豊かな自然と鉱山欲しさに、王女であるメリーとの婚姻を求めてきた。
縁深い隣国の王子であるヴィルヘルムとの婚姻が決まっていたこともあり、メリーの父がそれを拒否したことから平和は崩れ始める。
資源を合法的に奪うことができないのであれば滅ぼしてしまえ。そう考えた大国の侵略を受けてしまったのだった。
国のシンボルであった瀟洒な城は、大国の軍隊によって瞬く間 炎に包まれた。
王と王妃は北の国に囚われてしまった。メリーはお付きの騎士であるルディアと共に、運よく逃れることができた。
逃げ延びた先で、メリーはルディアに問う。
「ルディア、私は国を救いたい。何か方法はないかしら?」
「まずは隣国に助けを求めましょう。ヴィルヘルム様ならきっとお力添えをしてくれるかと」
「でも、あの方たちを巻き込むわけには……」
「姫様。北の国は恐ろしい国です。我々の国を攻めただけで終わるとは思えません。隣国にも北の国の恐ろしさを知らせる必要があります」
ルディアに説得されたメリーは、隣国へ逃れるとヴィルヘルムに助けを求めた。
北の国の横暴に心を痛めていた隣国の王は、メリーから事情を聞くと、二人に食事と寝所を提供した。そして一つの道をメリーに示した。
「聖なる山に世界の理を知る賢者が住んでいる。だが、彼の者の力を借りるには姫自身が試練を乗り越えねばならないでしょう」
「国を救うためなら何でもできます。ルディアと共に聖なる山に向かいます」
メリーはルディアと隣国一腕が立つという仮面の騎士を伴い、聖なる山に出発した。
仮面の騎士は寡黙だった。メリーやルディアの会話に口を挟むことなく、ただ前を守るようにして進んでいた。
程なくして騎士の正体は明らかになった。道中で出くわした魔物の一撃で、騎士の仮面が飛ばされてしまったのだ。
「ヴィルヘルム様!?」
仮面の騎士の正体はヴィルヘルムだった。
ヴィルヘルムは手にした剣で魔物を打ち倒すと、悪戯がばれた子供のようにばつが悪そうな顔でメリーに向き合った。
「旅が終わるまで隠しておくつもりだったんだけどね」
「なぜ?王様が心配なさいます。早くご帰還くださいませ」
「将来の伴侶を放っておけないからね。父の承諾は得ているよ」
困惑するメリーの頭をヴィルヘルムが優しく撫でる。そんな二人の様子を、ルディアはニコニコと笑って見守っていた。
メリーは、ヴィルヘルム、ルディアと共に聖なる山を登って いった。
道中には賢者が人を遠ざけるために仕掛けた罠があったり魔物に襲われたりもしたが、三人で力を合わせて乗り越えていった。
「小国の姫、よくぞここまで辿り着いた。試練を乗り越えたお主に知恵を授けよう」
聖なる山に住む賢者は、少年と青年の間のような年頃に見える男だった。
「賢者よ、北の国から私たちの国を救う知恵をお貸しください」
「北の国は悪魔に支配された国。悪魔を倒すには東の海の神殿に眠る秘宝の力が必要だ」
「秘宝?」
「神殿に眠る秘宝には世界を正しい方向に導く力があるという。そして秘宝を手にすることができるのは、強い思いを持つ者に限られる」
賢者は大昔の文献に書かれていることを伝えた。
「秘宝を手に入れる道程は困難を極める。それでも行くか?」
「はい。私は国を、父と母を救いたいのです。賢者ギュスターヴ、知恵をお貸しいただきありがとうございました」
「吾も共に行こう。世界を導く秘宝と世界を導く姫を、この目で見届けたい」
賢者は杖を取り立ち上がった。こうして、国を救う旅に稀代の賢者ギュスターヴが加わった。
ギュスターヴの魔術と知恵は困難を乗り越える助けとなった。東の海の底にある神殿に入るのにも、ギュスターヴの知恵が役にたった。
秘宝を守るための罠や仕掛けを解除し、ついに神殿の奥深くに安置されていた秘宝に辿り着いた。
強い光で神殿の内部を照らしていたのは、複雑な多面体で構成された秘宝だった。
「姫よ、秘宝を手にするがいい。お主にはその資格がある」
メリーが手を伸ばすと、秘宝はメリーの手におさまった。
「これが秘宝……」
秘宝はメリーの手の中で淡い光を放っていた。
「おお。吾にもよく見せてくれ」
「ええ」
メリーはギュスターヴに秘宝を見せるべく、その手を差し出した。
「これこそ、吾が長い間求めていた秘宝。真に世界を動かす力をもつ、世界の要」
秘宝を手にしたギュスターヴは、突如高らかに嗤った。
「全ては吾の手の内よ。では、用済みの姫には消えてもらうとしようか」
ギュスターヴの杖が怪しく輝くと、一筋の閃光がメリーに向かって放たれた。
「姫様!」
メリーはルディアに突き飛ばされる。ルディアはメリーに代わってギュスターヴの術を受けた。
「ルディア!」
「ギュスターヴ!賢者である貴方がなぜ!?」
「賢者などと言われていたのは昔の話よ。この秘宝を手に入れるために、吾は長い年月を費やした」
「我々を騙したというのか!?」
ヴィルヘルムが剣でギュスターヴに斬り掛かるも、秘宝の力で弾かれてしまう。
「姫様……」
「ルディア、そんな……死なないで」
「どうか……いき……」
「雑魚が、煩いぞ」
再びギュスターヴの杖が光る。ルディアはそのまま物言わぬ灰と化した。
呆然となるメリー達を一瞥すると、ギュスターヴは黒い光の矢となって北の国の方角へと飛び去っていった。
悲しみに暮れるメリーとヴィルヘルムは、ルディアの最後の言葉を胸にして北の国へと向かった。
北の国は邪な秘宝の光に包まれており、あらゆる生物は死に絶え、魔物が闊歩する地獄のような場所となっていた。
メリーとヴィルヘルムは暗闇の中心へ急ぐ。そこは北の国王の居城だった。
玉座にはギュスターヴがいた。秘宝を手に持ち、魔物とも人ともつかない配下を従えていた。
「ふん、吾を追ってここまでやって来るとは、ご苦労なことだ」
「北の王はどうした!?」
「最初から北の王など居りはせんよ。居たとすれば、それは吾の分身だ」
ギュスターヴは配下を下がらせ、自らメリー達の前に立つ。
ヴィルヘルムが剣を抜いた。白銀の剣は、すでに何体もの魔物の血でくすんでいた。
「秘宝をどうするつもりだ」
「お主らに言ったところで、理解など得られる筈もなかろう。吾は無駄なことはしない主義でな」
「貴様!」
ヴィルヘルムがギュスターヴに向かって剣を振り抜いた。
ギュスターヴの杖が剣を受けると、そのままヴィルヘルムに向かって魔術を仕掛ける。
距離を取ろうとするギュスターヴ、肉薄するヴィルヘルム。
ヴィルヘルムの攻撃の手が緩むことはなかった。
ついにヴィルヘルムの剣がギュスターヴの手から秘宝を弾く。
メリーは急いで転がり落ちた秘宝を拾い上げた。
しかしそれと同時に、ギュスターヴの魔術がヴィルヘルムの腹部を貫いた。
「メリー……」
「ああ……そんな……ヴィルヘルム!」
ヴィルヘルムは秘宝を手にしたメリーを見つめて微笑むと、そのまま絶命した。
ヴィルヘルムの亡骸を抱きかかえたメリーは、静かに涙を流した。
「小賢しい真似をしてくれる。小娘、秘宝を吾に渡せ」
メリーは答えない。痺れを切らせたギュスターヴがメリーに向けて杖を振るう。
ギュスターヴの魔術がメリーを襲うが、秘宝の力がギュスターヴの術を寄せ付けなかった。
「……許さない」
メリーの冷たい声が、王座の間に響く。
メリーは強く祈った。秘宝はメリーの思いに感応し、赤黒い光を放ち始めた。
「ギュスターヴ様、ここは危険です」
配下の言葉はギュスターヴに届かなかった。
「これが秘宝……吾の望みを真に叶える鍵」
秘宝の光に魅入られたギュスターヴ。その目には赤黒く光る秘宝しか映っていなかった。
「全部、なくなってしまえ!」
メリーの目から涙がこぼれた。涙が秘宝を濡らしたその時、メリーを中心に赤黒い闇が世界を覆い尽くした。
一つの世界が終わりを告げた。人も、動物も、無機物も。闇は、 全てを飲み込んだ。
「この世界も違ったようですね」
何もない空虚な場所で、桃色の衣装を身に纏った幼いメリーは、溜息と共に呟いた。
目の前には淡く輝く多面体の結晶が浮かんでいる。
手をかざすと結晶はゆっくりと回転を始め、面ごとに様々な世界を映し出す。
「お兄さん……」
メリーの呟きに呼応するように、結晶体は煌めいていた。
「―了―」
3398年 「現」 
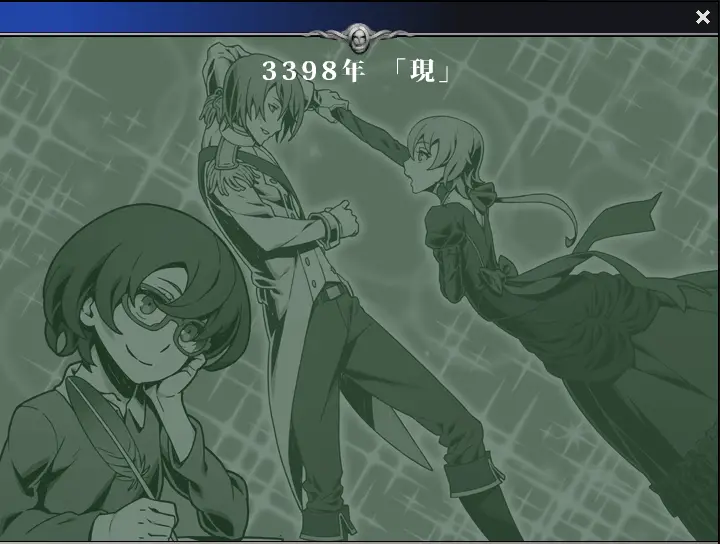
広げられたノートに向かって、メリーは一心不乱に文字を綴っていた。
カリカリという音が部屋に響く。
メリーの部屋は何の変哲もない子供部屋だ。小さなベッドと机、最低限の生活用品を入れるためのクローゼット、そして子供向けの小説や教本が入った小さな本棚。
違うところがあるとすれば、それは机の上に堆く積まれたノートだろう。
使い込んでボロボロになった物から手付かずの新品まで、綺麗に積み上げられている。
「メリー、そろそろ礼拝の時間よ」
部屋の扉を叩く音と僧侶の声が聞こえてくる。
その声にメリーは手を止め、ペンを置くと部屋の扉を開けた。
「皆が待っているわ、早く礼拝堂に行きなさい」
「はぁい」
メリーは書き掛けのノートを気にしながらも、礼拝堂へ向かった。
礼拝の最中、メリーは祭司の唱える文言を聞いてはいたが、心は別のところにあった。早くノートに続きを書かないと内容を忘れてしまう。そんなことばかりを考えていた。
礼拝が終わると、メリーは足早に自室に戻り、書き掛けのノートに向かって再び文字を綴り始めた。
どれくらいそうしていただろうか。日が暮れる頃に扉を叩く音でようやっとノートから視線を外す。
「メリー、部屋にいるの?」
メリーが部屋の扉を開けると、昼の礼拝の際に呼びに来た女性僧侶が心配そうに立っていた。
「イザベル先生?どうしたの?」
「ああよかった。姿を見かけなかったから、どこに行ったのかと思って」
「ううん、ずっと部屋にいたよ?」
「そう……。また書いていたの?」
イザベルと呼ばれた僧侶は、メリーの背後に見えるノートを見やる。
「うん!」
「今はどんなことを書いているの?見てもいい?」
「いいよ!」
メリーはニコニコと笑いながら、イザベルに書き終えたノートを差し出した。
ノートの中には少女の拙い字で、壮大な物語が綴られていた。
「これはいつの夢?」
「えーっと、一昨日から見てる夢だよ。私がお姫様で、お兄さんが王子様なの」
メリーは少し恥ずかしそうにしながらも、嬉しそうだった。
「そう、楽しそうな夢ね」
「それでね、いろんなところを冒険するの。今朝はね、海底にある大きな神殿に行ったんだよ」
今朝夢に見た情景がどんなに凄いものだったかを無邪気に語るメリーに、イザベルは困ったような笑みを浮かべながら相槌を打つしかできなかった。
メリーは半年ほど前に起きた凄惨な事件に巻き込まれてから、精神の均衡を崩している。彼女は夢に見たものをノートに書き綴ることで、辛うじて自身の心を保っていたのだった。
ある日、メリーは聖堂から少し離れた場所にある閑散とした植物園にいた。
人気の無いそこは昼間にも関わらず静まり返っており、酷く不気味であった。
少し前までは、植物園の所有者であるオハラという老人と、ヴィルヘルムと名乗る若い男が管理をしていた。しかし今は放置されており、メリーが一人で雑草同然となった草木を手入れしている。
「またここにいたのね。ここに来てはいけないと祭司様に言いつけられているでしょう?」
植物園の片隅で土の手入れをするメリーを見つけたイザベルが声を掛けた。
「ごめんなさい……。でも、お兄さんにここを頼むって言われてるし……」
メリーの言葉にイザベルは暗い顔をした。
彼女の言う『お兄さん』とは、オハラと共に植物園を管理していたヴィルヘルムのことだ。
この青年は数年前に大怪我を負って倒れていたところをメリーに発見され、聖堂によって保護された。そして怪我が治った後も、行く当てが無いということから、植物園の管理を手伝う住み込みの従業員として雇った経緯があった。
自分のことはあまり話さなかったが、心優しい人物であり、仕事も真面目にこなす青年であった。
だが、彼はメリーが精神を病む原因となった事件の際、行方不明となった。
事件の発見者であるオハラの言葉によれば、植物園の管理小屋におびただしい量の血が撒き散らされており、その中に鋭利な刃物で無数に貫かれた痕跡のある衣服が残されていた。そして、守られているかのように、その衣服に包まれた無傷のメリーが倒れていたのだという。
残されていた衣服は間違いなくヴィルヘルムがその日に着ていた物だったが、持ち主である彼の姿は忽然と消えていた。そして現在に至るまで彼は発見されておらず、生死も不明の状態であった。
不可思議で凄惨な事件だったが、容疑者はすぐに捕まった。だが、容疑者は犯行を否定し続けており、事件の真相究明は難航していた。
植物園は事件とオハラの高齢を理由に閉園され、今では寄りつく人もいない。
彼と共に事件に巻き込まれたメリーは衝撃的な場面を目撃してしまったせいか、事件の前後の記憶を失っていた。
そして精神的に不安定となった彼女は、ヴィルヘルムはどこか遠くへ旅に出ており、留守中の植物の面倒を頼まれた、という夢想を自分の中に作り上げていた。
そのため、度々聖堂を抜け出しては、この寂れた植物園に勝手に入り込んでしまうのだった。
「そうね。でも、もうお終いにしましょう」
「どうして?」
「祭司様の言いつけを破ってしまうのは、駄目なことでしょう?」
「でも、お兄さんがここを頼むって……」
メリーはイザベルの言葉に納得できず、植物園を訪れることを諦めようとしなかった。
「どうしてもここに来たいのなら、ちゃんと祭司様に相談なさい」
「祭司様がいいって仰れば、来てもいいの?」
「ええ、もちろん。だから、ちゃんと祭司様に相談するのよ」
「うん!」
イザベルは嬉しそうに頷くメリーを見て、ひっそりと重い溜め息を吐いた。
以前にもメリーに現実を教えた事はあった。しかしメリーはひどく狼狽し、しまいには聖堂を飛び出してしまった。その時は運よく聖ダリウス大聖堂の近くで保護されて事無きを得たが、次に同じような事があっても無事に保護されるとは限らない。間違ってスラムにでも入り込んでしまったら、今のメリーでは生きて帰ってくることは不可能だろう。
今のメリーは夢の内容をノートに綴りながら青年を待つことで、何とか精神の均衡を保っている。そこの部分に目を瞑れば、メリーは少しだけ夢見がちな普通の少女なのだ。
ヴィルヘルムの死も、夢を書き綴ることも、年単位の時が流れれば、メリーは少しずつ現実を受け入れてくれるだろう。そう考えた祭司とイザベルを含めた聖堂の僧侶達は、メリーに真実を隠し続けることにしたのだった。
「お兄さん、早く帰ってくるといいなぁ」
聖堂への帰り道、メリーは何も疑問に思うことなく、そんな言葉を口にした。
ヴィルヘルムのことを話すとき、メリーは一際無邪気に振る舞う。
「……そうね。彼が無事に旅を続けられるように、お祈りをしましょうね」
「そうする!」
イザベルの言葉に、メリーは無邪気に笑うのだった。
夕闇の中、蠢く死者の群れと異形達が、首都ルーベスで交戦していた。
異形達は圧倒的な腕力と念力とも言えるような不思議な力で死者の群れを薙ぎ払う。 対する死者の群れは、尋常ならざる頑強さで異形の力に耐え切っていた。
メリーはその様子を大聖堂の塔の上から見下ろしている。
暫くの間眺めていたが、羽根ペンと紙を虚空から呼び寄せると、慣れた手付きでその様子を紙へと綴った。
一通り戦場の様子を記録すると、羽根ペンと紙を虚空へと消す。
「探さなければ……」
メリーは小さく呟くと、塔から飛び降りた。
そのまま重力を無視したように宙を漂うと、戦場の真っ只中に降り立った。
泥と埃と血に汚れた戦場で、奇麗な桃色の衣装を身に纏うメリーの姿は奇矯だ。
だが、街を闊歩する死者の群れも異形達も、メリーに気付くことはなかった。
「―了―」
「抵抗」 

それは、三三九八年の終わりから続く、破滅への一本道だった。
商業都市プロヴィデンスを覆った死の瘴気は、各国の血の滲むような対策も虚しく、世界を包み込んでいったのである。
銃声が響く。
異形の集団と、白いフレームが剥き出しになった戦闘人形が激しい戦闘を繰り広げていた。
異形でも戦闘人形でもない町の人々は、突如として始まった戦闘に逃げ惑うしかなかった。
「こっちです!早く!」
そんな中、ぼろぼろの戦闘服とライフルを装備した一団が、逃げ惑う人々を誘導していた。
彼らの年齢構成は年端も行かない少女から老人までと、非常に広範であった。
「さあ、もう大丈夫です。これに乗って安全な街まで行きましょう」
「あ、あ……あぁ……」
呆然とする人々を、待機させていた機械馬の馬車に次々と乗せていく。
異形と戦闘人形はこちらの様子には関心が無いらしく、追ってくる気配は無い。
救出した人々と戦闘服の団体を乗せた馬車は、南方に向けて出発した。
グランデレニアとルビオナとの戦争は、死者の軍勢によっていずれをも勝者にすることなく終わりを告げ、二つの国家は死の世界に飲み込まれて滅亡した。
しかし、この大事変でさえも、新たな戦争の幕開けでしかなかった。
先の戦争で沈黙を保っていた宗教国家ミリガディアが、常軌を逸した力を持つ超人と呼ばれる存在を各国に送り込み、混乱する世界を統一しようと動き始めたのだ。
しかし、ミリガディアの目的はあくまでも超人が支配する世界を構築することである。ミリガディアの掲げる世界の実現に賛同し、超人化の儀式を受け入れなければ、救いの道は存在しない。
その状相に制止を求めたのが、空中に一大都市を築く導都パンデモニウムであった。
パンデモニウムは自分達こそが世界を管理、平定する者であると主張し、ミリガディアを排斥するために世界各地に戦闘人形を送り込んだ。
当然ながら、ミリガディアの超人達はこれに反抗する。
こうして、パンデモニウムとミリガディアとの、泥沼の戦争が始まったのだった。
「なあ、俺達は一体どこに連れて行かれるんだ?」
馬車の中で怪我の応急処置を受けていた男性が、治療を担当している少女に尋ねた。
「私達レジスタンスが拠点としている街です」
少女、メリーは笑顔で答えた。
「あの、噂に聞く要塞都市か?」
「はい。そこであれば、しばらくは安全に暮せます」
地上に残された人々にとって、ミリガディアもパンデモニウムも、どちらも等しく敵であった。
超人組織と化したミリガディアは言わずもがな、パンデモニウムも世界の管理平定を謳っておきながら、死者の軍勢に襲われて逃げ惑う人々を無視し、救助の手を差し伸べることはなかった。
残された人々は災厄を逃れるために南へ南へと向かい、そこで、かつて《渦》に対抗する連隊が使っていたという施設を発見し、拠点として街を築いた。
更に、パンデモニウムに見捨てられた地上派遣のエンジニア達と協同することで、施設を修理し、武装を整え、障壁を死者の軍勢に対して効力が発揮するよう改良するなど、単なる街ではなく要塞都市としての完成を見たのである。
『地上でただ一つの、人間が安全に暮せる街』の噂は口々に伝搬されていき、流入する人々の数はどんどんと増えていった。
そうして集まった人間達は、世界を自分達が安全に暮せるようにしたいと求めるようになり、自らを『レジスタンス』と呼称するようになった。
彼らはミリガディアとパンデモニウムの戦争を終わらせようと各地で奮闘しながら、人間の保護を同時に行っていた。
超人と異形、戦闘人形、死者の軍勢、それらが闊歩して人間を脅かしているのが今の現実だ。だが、この要塞都市は別世界であるかのように平穏で、その上で活気に溢れている。
死者の軍勢を寄せ付けない障壁の存在と、街の人々が精一杯の産業を行って生活を支えているお陰であった。
要塞都市に戻ったメリーは救出した人々と一緒に検疫を受け、そのままレジスタンスが本部としている建物で雑務をこなしていた。
「メリー、調査部から連絡だ。例の『お兄さん』らしい人が見つかったってよ」
メリーの所へやって来た壮年の団員がそう告げたとたん、メリーの表情は緊張で強張った。
「ほ、本当、ですか!?」
メリーには、戦争の混乱で離れ離れになってしまった、大事な『お兄さん』がいた。
その人物は戦火に包まれるミリガディアで、メリーのいた養護院の子供達を守るために異形に立ち向かい、行方不明となった。
メリーはレジスタンスに保護された後、その『お兄さん』を探し出すために救出チームに入り、各地を飛び回っていたのだ。
「ああ。ミリガディアの研究所に囚われてる人のリストに、お前さんの言う『お兄さん』の特徴に当てはまる人物がいるって話だ」
「研究所……」
その人物が『お兄さん』であるという保障はどこにもない。
「あの研究所は人間を使って何かの実験をしようとしてるって話だから、急いで救出チームを向かわせる予定だ」
「私も一緒に行きます!」
団員の言葉に、メリーはすぐさま救出チームに加わる意思を見せた。
「よし、わかった。出発は明朝だから、今日はもう帰宅して構わない。急いで準備してくれ」
「はい!」
調査チームの情報を元に辿り着いたのは、要塞都市の北東にある、かつてグランデレニア、インペローダ、ミリガディアの国境が交わる場所であった。
以前は三国の交易を担う都市が築かれていたが、ミリガディアに支配されてからはその機能を失っており、今では都市全体が研究施設として使われていた。
そして、ミリガディアの重要施設であると認識したパンデモニウムは絶え間なく戦闘人形をこの都市へ送り込み、間断なき戦闘を繰り広げていた。
メリー達レジスタンスは戦闘人形と異形との戦闘が激しくなる頃合を見計らい、研究施設に突入した。
幾度かは異形との交戦があったが、外の戦闘に戦力を割いている影響だろうか、さほど労することなく、人々が囚われている場所に辿り着いた。
その中に『お兄さん』の姿は見えず、メリーは落胆しながらも救出活動を続ける。
「ま……待ってくれ、別の部屋に、もう一人残されてるんだ」
最後の一人が弱弱しい声で、囚われている人物がもう一人いると告げた。
「わかりました、ありがとうございます!」
最後の一人を救出すべく、メリーは二人の団員と共に該当する部屋を探し出す。
その部屋は人々が囚われていた部屋の、更に奥にある部屋だった。
手術台の上に一人の男性が拘束されていた。
「お兄さん!」
その人物こそ、メリーがずっと探し続けていた『お兄さん』こと、ヴィルヘルムであった。
やはり、ヴィルヘルムはこの施設に囚われていたのだ。
やっと出会えた感動をぐっと押さえ、メリーは手術台に近付く。
そして、ヴィルヘルムの拘束を解こうとしたその時だった。
「あ! がっ……」
腹部が鈍く重い衝撃に襲われた。メリーの視界には、血に塗れた太い棘のような何かが自分を貫いているのが見えた。
何が起きたのかはわからなかったが、異形か超人の攻撃を受け、自分がここで死ぬのだということは理解できた。
一緒に行動していた二人の団員達も、尋常ならざる叫び声を上げた。彼らもメリーと同じように体を貫かれたのだろう。
ヴィルヘルムが目を見開くのが見えた。だが、彼の拘束は頑強で、腕の一本を動かすことすら叶わないようだった。
声さえ出せぬように拘束されている彼からは、唸り声のようなものしか聞こえない。
――ごめんなさい。――
声にならない声が喉を過ぎていく。
メリーの胸中を後悔が塗り潰していく。
ずっと探していた人が目の前にいるのに、助けられなかった。
――ごめんなさい。
もう一度声を出そうとしたが、それは血の塊となってヴィルヘルムに降り注ぐだけだった。
メリーは、空虚な世界の中で静かに涙を流していた。
たくさんの世界を覗き、その世界に降り立つことはできても、その世界に干渉することはできない。
そのことに気付いてからも、メリーは多様な世界を見続けた。
必ず何処かに『メリー』が叶えられなかった幸せな世界が存在すると信じていた。その世界を発見し、『メリー』のために観測することこそが、自身の使命であると確信していた。
「さあ、次の世界を観測しましょう」
結晶が煌めき、再び様々な世界を映し出す。結晶のそれぞれの面に異なる世界が映る。
それらの中から、『メリー』が生きる世界を見つけようとした次の瞬間だった。
多面体の一角、つまり一つの世界が白く目映い光に包まれた。
そして、白い光に包まれた面は二度と世界の姿を映すことなく、結晶から消えていった。
「またですの……?」
この場所は時間の流れが曖昧ではあるが、メリーの感覚で言うところの最近、こうやって白い光に包まれて消失する世界がいくつか現れ始めていた。
そうなってしまった世界は、過去の観測をすることさえもできなくなってしまう。
様々な要因、選択によって枝分かれした世界を消滅させるこの光を、メリーは酷く嫌悪していた。
『メリー』の幸せを探す自身にとって、この消失現象は見過ごせない。
今まで観測してきた世界は、確かに幸せな結末を迎えたとは言い難い。それでも、誰かにとっての幸せや決意、覚悟があったのだ。それを否定し、奪うことなどあっていい筈がない。
「多元世界を否定したい何かが存在するようですわね」
煌めく結晶を前に、メリーは静かに怒気を発するのだった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ