メレン
【死因】
【関連キャラ】ルート(同僚)、オウラン(同僚)、ブラウ、ウォーケン、リュカ
2835年 「道化」 
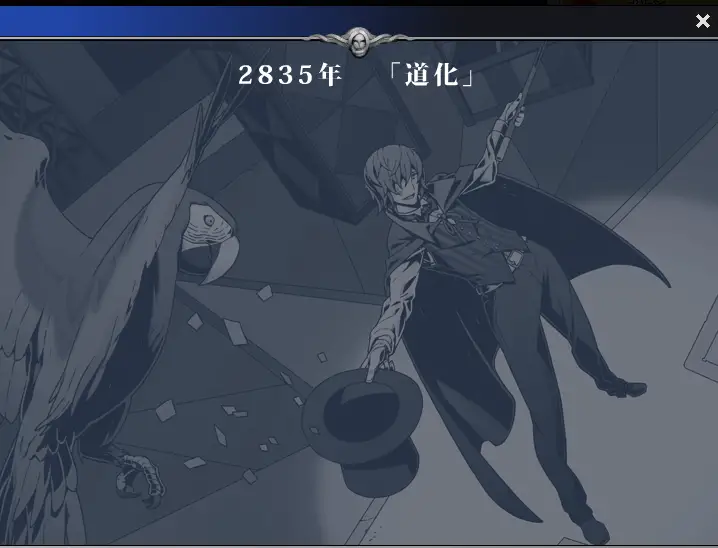
夜がやって来た。
人々のざわめきが、出番を待つ自分のところにまで聞こえてくる。照明の熱と人々の温度で、テントの中は暖かい。
「さあ行け。出番だ、メレン」
団長の声だ。その声はとてもよく響いた。
自分は舞台へ出た。光が溢れる舞台の上で観客に向かって帽子を取り、深々とお辞儀をした。
手に持った帽子から極彩色のオウムが飛び出し、歓声が上がる。
オウムは観客席の上を飛んでいく。子供達が笑いながらそれを眺めている。
観客を舞台に上げ、カードを使った奇術を披露する。
観客に驚きと感心を共感させるために、表情を作る。
決まり切ったルーチンと予想された反応。全て、いつも通りだった。
スムーズに事が進むと、内的演算機能が評価を積み重ねる。
指定された演目を全て終え、舞台から降りた。
前座のマジックショーが終わると、巨大な動物型オートマタが調教師に連れられてやって来た。
動物たちの芸に歓声が一際大きくなる。全てが作り事であっても、この古風なショーは人気があった。
動物、動物使い、マジシャン、道化、演者は全てがオートマタだ。
団長や整備係など、五、六人だけが人間だった。
特注のオートマタによる古い時代の見世物を再現するこのサーカスは、各地を転々としながら興行を行っていた。
背の曲がったみすぼらしい道化の姿をしたオートマタが、奇妙な声を上げた。
「が、が、ががっつ、せな、せな」
首をがたがた震わせながら手を振り回している。
小人の道化が周りで囃し立てている。自分はそれを、小道具の点検をしながら眺めていた。
せむしの道化ヴィレアは小人たちに弄られて愚かな振る舞いをする、それで笑いを取る役回りの機械だ。
ただ、最近は調子が悪いらしく、出番が終わっても演技中のような振る舞いをやめない。
小人達は反応を楽しむように叫び、暴れるヴィレアの周りをくるくる回っている。
「ば、ば、ば」
今度は目をくるくるさせながら手を振り回している。
「ちっ、面倒を起こしやがって。このポンコツが」
脇にいた初老の整備係が、長く黒い棒を手に出てきた。
暴れるヴィレアをその棒で強く突くと、バチッという音と共に電撃の閃光が瞬いた。整備係といっても修理などはしない。そもそも、ここにいるオートマタは人を模した精巧な機械だ。作られた工房でなければ直しようがない。彼らは気分で命令し、気晴らしに殴ったりしているだけだ。ヴィレアは作られて随分と経っている。おそらく修理されずに廃棄され、別のオートマタによる演目に置き換えられるだろう。
ヴィレアは泡を吹くようにしてその場で倒れた。
「邪魔だ、どかんか。お前らも喰らいたいか!」
整備係の男がスタンバトンを振り回す。小人達は笑いながらヴィレアの周りから去って行く。小人達は常にふざけ、笑い転げているように作られているのだ。
「ったく、どうしようもねえポンコツだ」
スタンバトンを振りかざして何度もヴィレアを殴打した。ヴィレアは呻き声を上げ、床で痙攣を続けている。
よくある光景だった。調子の悪い機械に人間が当たり散らしているだけだ。
自分は演目の片付けを終えると、倉庫にあたる部屋に戻ろうとした。
「おい、メレン。ゲームの頭数が足りねえ。付き合え」
「はい、わかりました」
団長や整備士、会計の人間などは、一仕事終えるとよく賭ゲームを行う。人が足りないときには自分が呼ばれる。
テントに入ると、団長付きのブラウが席を用意して酒と軽食の準備をしていた。自分はカードを持って席に座る。
団長と年かさの会計係の男が入ってきた。
「どうするんです、あんなの?」
「どうもしねえよ。記憶がねえっていうんだ、道化の機械共の世話させておけばいい」
「面倒を起こされちゃかなわないですぜ」
「なに、この街を出るときにでも適当に捨てるさ。 まあ、孤児を迎え入れるのも『サーカスの伝統』ってやつだろう?」
髭を生やした背の低い男が団長だ。暑いのか、いつもの赤いジャケットを脱いで、はだけたシャツだけの姿になっている。団長が差し出した手に、ブラウが葉巻を渡して火を付けた。
「おい、始めるぞ。 マークの野郎はまだ壊れた道化共の始末が終わってないらしい」
葉巻を燻らせる団長の命令を聞き、自分はカードを配り始めた。
ゲームはつつがなく進行した。自分は勝ちもせず、負けもせずにゲームを続けた。
「マークの野郎、遅いな」
団長がそう語ったのと同じタイミングで、マークが入ってきた。
「団長、ちょっと来てくれ」
団長と会計係は、マークと一緒にテントを出ていった。
ブラウと二人きりで残された。ただ、黙って彼らが戻ってくるのを待った。
しばらくすると三人が帰ってきた。
「いいのか?あれでほんとに」
整備係のマークがそう言った。
「好きにさせとけ、お前の下働きに丁度いいじゃないか」
団長はそう言って、ブラウに注がせた酒を呷った。
マークが来たことで、自分は倉庫に戻された。
いつもと同じような一日がまた始まった。開演の準備を進めなければならない。
その時、騒がしい声が聞こえてきた。ヴィレアの周りの小人達が、喚きながら何かを囃し立てていた。
どうやら、ヴィレアはまだ動くようだ。
戯けながら一人で滑稽なダンスを踊っている。その周りの小人達は、ヴィレアのダンスを見ながら大笑いしている。
そんな集団の傍に細い少年が立っていた。襤褸を纏い、顔を隠すようにフードを被っている。そして、足下には小さな犬がまとわりついていた。
「おい、小僧、こんどは象の足の調子を診てやってくれ」
「はい」
少年はすたすたと歩いて象のテントに消えていった。子犬も一緒についていく。
団長が現れてマークに声を掛けた。
「あの小僧がポンコツのヴィレアを直したのか?」
「ええ、ろくな工具も無いのに。変わった奴です」
「ふうむ。使えそうで面白い。おんぼろばかりのオートマタどもも、これでもう少し賞味期限が伸びるな」
団長がそう言うのを聞きながら、自分は今夜の演目の確認を始めた。
何日か後の夜。また団長達とゲームの相手をしている時、カードを取り落としてしまった。
「なんだ、お前もガタが来たのか?」
団長がそう言った。
「ここはいいから、小僧に診てもらってこい」
マークに命令された自分は、彼の助手として働いている少年のもとに行った。
「マークさんに身体の調子を診てもらえと言われました」
「そう。症状は?」
小人型オートマタの修理をしながら少年は答えた。いつもの子犬は足下で寝ている。
「カードを取り落としてしまいました。カードの扱いに失敗したのは初めてです」
「はい、これで終わり」
小人が再起動して、笑い出した。
「あはは、ありがとう。声の調子が元に戻ったよ。あははは」
お礼を言ったあと、自分に戯けた敬礼をしてから、小人は去って行った。
「ここに寝てくれる?腕の調子を診るから」
言われた通りに横になると、少年は腕の回路を調べ始めた。言われたままに指を動かしていく。
「単純な機能に問題は無いね。ソフトウェアかもしれない。一度、電源を切るよ」
そう語られてすぐに、自分は意識を失った。
目を覚ますと、自分は元の倉庫にいた。サーカスは次の巡業先に向かう準備をし始めている。
自分もその作業に入らないといけない。
普段から見ている筈の自分達が収まる倉庫が、やけに埃っぽく感じた。それに、テント越しの光も何故か眩しく感じる。
「調整しておいた。小さな過学習が運動プログラムに起きていたからね。それにしても、君もなかなか年季の入ったオートマタだね」
倉庫の戸口にフードの少年が立っていた。子犬を抱えている。
「はい、製造されて八十年にはなります」
「もう骨董品の域だね。でも、弄りがいがあって楽しかったよ」
「そう言っていただけると恐縮です。そうだ、お名前、教えてもらえますか?」
まだ名前を聞いていなかったことを思い出した。
「自分の名前は覚えていないんだ。でも、この子の名前はわかる。シルフ」
少年は子犬の顔を見つめながらそう答えた。フードの下の顔には傷があるのか、黒くなっている。
「そうですか。では、ノームあたりでどうですか?シルフに対応した、優れた工芸品を作る精霊の名です」
突然、そんな言葉が出てきた。
「ノーム……。うん、そう呼びたかったら、そう呼んで良いよ」
少年は不思議な笑顔を残して去って行った。
自分は、早く準備に取りかからなければという焦りを急に感じ、倉庫から出て行った。
「―了―」
2835年 「蘇生」 

興行が終わり、団長からカードの相手をするように言われた。
途中までは勝つことも負けることもせずに、淡々とプレイを続けていた。
突然、『ここで負けたらどうなるだろう』という疑問が湧いた。
その疑問に抗わず、不利なカードを手元に残し、敢えて負けた。
「どうしたメレン。負けるなんて珍しいな」
団長が自分に問い掛けてきた。
「団長の見極めが、私の演算を超えたということでしょう」
「ほお。お前も世辞を言うようになったか」
団長は感心したように頷いた。
その後のゲームは、始終団長や整備士の優位になるように進めていった。
まだ日も高い時間に舞台袖となるテントへ向かうと、動物使いのオートマタであるルートが鞭の手入れをしているところに遭遇した。
自分も興行で使うカードと手品の整備を始める。
「調子はどうだい、メレン」
ルートに話し掛けられた。反応を返すことができず、ただ固まるしかできなかった。
オートマタである自分達は、自発的に言葉を発することは無い。
仮にオートマタ同士で会話を行うことがあるとすれば、それは定められた文言による疑似的な会話に過ぎない。
ヴィレアのように誰に命令されなくても喋り、笑い転げているような機能があれば別であるが。
過去のメモリーを参照したが、今までこの動物使いと会話をした記録は無かった。
「メレン、どうした?」
「え、あ、いえ。ノームに整備をしていただいたので」
「やはり。ノームに見てもらってから調子が良いのは、私だけではないようだ」
「そうですか」
そこで会話は終わった。すぐに団長と整備士が笑い声を上げながらテントに入ってきた。
自分達は動きを止めた。会話をしていたことが団長達に判明するのは、とても良くないことのように感じた。
「メレン、ルート。ちょうどいい、ライオンを小僧のところまで運べ」
団長は自分達を見つけると、テントの隅にあった古ぼけたライオンを指差した。
あのライオン型のオートマタは、前回の興行の際に壊れたものだった。
言いつけ通りに、ライオン型をルートと共に少年のところまで運んだ。
「小僧、こいつでいいか?」
少年は不調となった象型の整備をしていた。
「はい。ありがとうございます」
「本当に夜までに何とかなるんだろうな?」
「故障箇所に使える替わりの部品があれば可能ですよ」
「頼んだぞ」
団長は短く言うと、自分のテントへと戻っていった。
「君たちも持ち場に戻っていいよ。それとも、修理を見ていくかい?」
少年は言う。その言葉に従い、ルートは元の場所へ戻っていった。
「君は?」
「修理の状況を見学してもよろしいですか」
「いいけど、今の君には辛いものかもしれないよ」
「辛いということはありません」
「……そう。後悔しても知らないよ」
少年はそれだけ言うと、ライオン型の分解を始めた。
それをただ眺めていたが、ライオン型の外装が外されて骨格が顕わになると、電子頭脳を締め上げられるような感覚が襲ってきた。
丁寧に分解され、圧力センサーや電子部品がテントの床に並べられていく。
そして、焦げたように黒くなったチップがライオン型の頭部から取り出された時、電子頭脳が訴えかけていた内容を唐突に理解した。
「あ……」
「だから、辛いはずと言ったんだよ」
いつの間にか声が出ていた。それを聞いた少年は淡々と言葉を続ける。
「このオートマタは、死んでいたのですね」
「そう。この子を形成していたチップはとうに駄目になっていたようだね。チップのメモリーを取り出す技術も設備もここにはない」
すっかりと分解され、ライオン型は只の部品と化していた。
代わりに象型のオートマタの電源が入り、以前と変わらない動きを見せるようになった。
「こうやって部品を再利用することで別のオートマタが息を吹き返す。もう駄目だからといって、無下にしてはいけないんだ」
少年は、フード越しの口に笑みを浮かべていた。
その日の目玉は、大きな象による曲芸ショーだった。
象は以前と変わらぬ動きで客の目を引いていた。
「メレン、そんなところに立つな。ショーの邪魔になる」
「申し訳ありません。ショーを見ていたくて」
「世辞の次は意見か。まぁいい、次の出し物の邪魔はするなよ」
「わかっています」
舞台袖の隅に立ち、ショーの行方を眺めていた。
すると、象の上でとぼけたパフォーマンスをしていたヴィレアが転がり落ちて、象に踏み潰されてしまった。
客席が俄にざわつくのがわかった。ヴィレアの半身は潰れていた。
すかさず人間の団員が現れ、持ち芸の腹話術でヴィレアの真似事をし、上手く事故をごまかしながらヴィレアを蹴り飛ばしていた。団員の後を追うと、腹話術の団員がヴィレアを蹴り飛ばしていた。
「ボロが、手間かけるんじゃねえよ!」
地面に転がっていたヴィレアは、バチバチと音を立てていた。
「がっ、がが、せ、ガガガガ……」
自分は咄嗟に動いた。
地面に転がったヴィレアに近付く。
「なんだ?メレン」
「ノームにヴィレアを見せましょう」
「無駄無駄。完全にぶっ壊れてるんだ、そいつは。もう捨てるしかねぇよ」
「ですが、まだ修理できるかもしれません」
「オートマタのくせに口答えするのか?」
「そうではありません。団長の許可もなく捨ててしまえば、貴方が咎められてしまうのではないでしょうか」
「好きにしろ!」
団員は吐き捨てるようにその場を立ち去った。
それを見届けるとすぐにヴィレアを抱え上げ、少年のところへと急いだ。
「頭脳がやられてなければ大丈夫だと思う。そこに寝かせて」
少年はヴィレアの様子を見てしばらく固まったように動かなかったが、工具を取り出すとそう言った。
「そこのテスターを持ってきてくれる?」
「はい」
「そうしたら、予備バッテリーがあっちにあるから持ってきて。見た目より重いから気をつけるんだよ」
少年に言われるがままに、自分はヴィレアを直すための手伝いをした。
ヴィレアを直している間、昼間のライオン型の映像がずっと電子頭脳にちらついて離れなかった。
修理は明け方まで続いた。
自分は少年の傍について、ヴィレアがまた動き出すのを待ち続けていた。
「―了―」
2835年 「凌駕」 
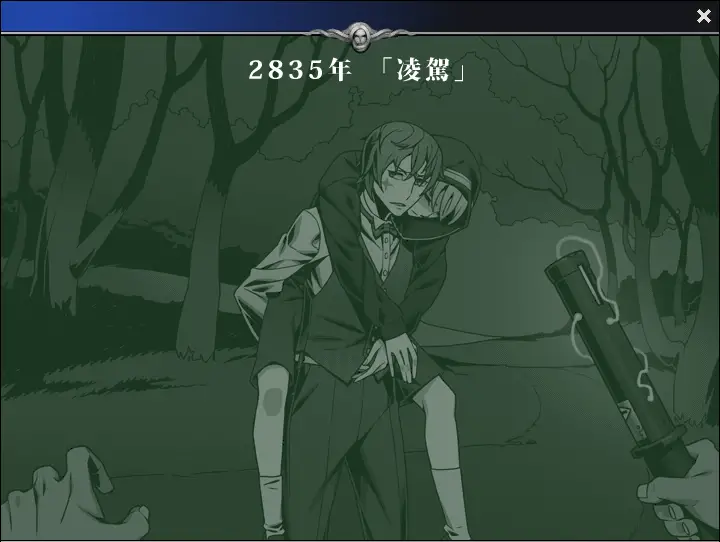
舞台裏では自分とルート、そして機械の動物達が、出番を待ち構えていた。
団長がオウランと修理し終えたばかりのヴィレアを伴って開場の挨拶を済ませると、小人の道化達のショーが始まる。
もうすぐ出番だと団長が言う。それに従い、自分は舞台の袖に控えた。
今日もサーカスは慌ただしい。
仕事が終わると、メンテナンス用の工具箱を持ったノームと行き合った。
「やあ、メレン。調子はどうだい?」
こうやって自分達の具合を尋ねてくるのは、ノームしかいない。
「お気遣いありがとうございます。私は問題ありません」
「それは良かった」
フードの下でノームが笑うのが見えた。
「おいノーム、早くしろ。 そんなオンボロなんか構わなくていい」
背後のテントから団長の声が聞こえる。
オンボロという言葉が自分を指していると気付く。今までは気にも留めなかった言葉が、電子頭脳のどこかに引っ掛かるような感覚があった。
「ごめんね、メレン。また後で」
ノームは申し訳なさそうに言うと、足早にテントへと向かっていった。
最近、団長は賭けカードの席にノームを同席させるようになった。それに伴って、自分がその席に呼ばれることは少なくなっていた。
賭けカードに呼ばれない時、今までの自分は何をしていたのだろうか。そんなことを思い付いた。
メモリーから該当の時期を呼び出して参照してみる。すると、自分は倉庫代わりのテントの幕を真っ直ぐに見つめていた。そして設定された時間が来ると、自動的にスリープ状態に移行していた。次の記録は翌朝であった。
別の日の記録では、マークが倉庫に物を取りに来たときに、ついでのように電源が落とされていた。
「カードの相手をさせる設定が面倒だからって、まったく団長の奴……」
マークの独り言が記録されていた。
改めて記録を見直すと、随分と無為な時間を過ごしていたように思える。
――無為な時間――、このような考えは作られてから一度もしたことは無かった。自分の人工知能は人に従うためだけにある筈だった。
違う。そのようなことは断じてない。自分の人工知能は学習型である。学習の過程でこのような認識をしたところで、何も問題は無いのだ。
ある日、スリープ状態に移行する少し前に突然マークがやって来た。
「付いてこい」
言われるがままにマークに付いて行くと、そこは舞台テントだった。
「おい、メレン。こいつを倉庫に運べ」
マークが脇に積まれた大量の小道具の箱を指差す。
「わかりました」
マークはそれだけを指示すると、欠伸をしながら就寝用のテントへと向かっていった。
周囲を見回すと、団長が部屋代わりにしている中型テント以外は、全て明かりが落ちている。
団長のテントの中から、誰かが話すような声が聞こえた。
小道具の入った箱を運ぶために何度も倉庫と舞台テントを往復していると、次第に団長のテントから聞こえてくる声が大きくなっていた。
人間の従業員は既に寝入っているらしく、誰も団長のテントの騒ぎに気付いていない。
道具を運び終えた頃、明かりのついた団長のテントからノームが飛び出してくるのが見えた。
ノームが自分の目の前を走り抜けると同時くらいに、団長がテントから出てきた。
「逃がさん……」
そんな呟きが自分の耳に届く。団長の鼻息は荒く、血走った目には怒りではない何か別の感情が宿っているように見えた。
自分が作業をしていることも見えていないのか、団長は自分に目もくれることなくノームを追い掛けていった。
マークの命令を忘れて団長の後を追う。
団長の纏う雰囲気が尋常でないことが、機械の自分にもありありとわかったからだった。
ノームを助けなければならない。それだけが自分の中にあった。
二人は近くの雑木林へと走っていったようだ。自分も奥へと分け入っていく。
「捕まえたぞ、大人しくしろ!」
「ごめんなさい、無理です。放して!」
「誰のお陰でメシが食えてると思ってるんだ!」
暗がりの中から言い争う声がする。垂れ下がる木の枝や茂みを掻き分けていくと、少し開けた場所で団長がノームに馬乗りになっている。
やめてください。という声が出掛かったその時、自分の背中が勢いよく蹴られる感覚があった。
そのまま前のめりに倒れた自分が起き上がった時に見たものは、団長に体当たりしてノームから引き剥がそうとするヴィレアの姿だった。
ヴィレアは体格こそ小柄に作られているが、旧式であるため、見ため以上に重量がある。
そんなヴィレアの体当たりを直に食らえばひとたまりもない。団長とヴィレアは揉み合うようにノームから離れていく。
「この!ポンコツの分際で!!」
「ノームは嫌がってる。ダメ、ゆるさない、ゆるさない!!」
ヴィレアと団長が争う声と音が、絶え間なく聞こえてきた。
「うぅ……」
ノームの呻き声が聞こえた。駆け寄ると、衣類がはだけたノームが仰向けに倒れていた。
「ノーム、大丈夫ですか?」
そっとノームを抱き起こす。フードが外れて金色の髪がノームの顔を覆う。表情は見えなかったが、彼の頬には叩かれたような痕があった。
「だい……じょうぶ。ごめんね」
「いえ。それより、ここから離れましょう」
謝るノームに首を振る。ノームを早く団長から引き離さなければならないと考え、彼を背負う。
「そいつをこっちに渡せ!」
ヴィレアを振り切ったのか、団長が憤怒の形相でこちらを睨んでいる。手には護身用らしい小型の棒を握っていた。
団長の命令が電子頭脳に響く。自分は団長の命令に従うようにプログラムされていた。
団長の命令とノームを助けなければいけないという意志がせめぎ合い、人工知能の思考演算を混乱させる。
「メレン、ヴィレア……」
自分の背でノームが小さく呟くのが聞こえる。自分の肩に捕まる彼の力が強くなった気がした。
「申し訳……ございません。従うことは……できま、せん」
意志が命令を凌駕する。
錯乱したようにも見える団長にノームを引き渡せば、団長は彼にもっと危害を加えるだろう。ノームは自分達オートマタを修理して下さる恩人なのだ。そのような大切な方を危険に晒す訳にはいかない。
そんな思考が自分の中に溢れた。
「メレン、お前も俺に逆らうのか!このポンコツが!!」
団長は小型の棒をこちらに向けた。
それを見て自分は後ずさる。踵を返してこの場から走り去るには、団長との距離が近すぎる。
「従うことはできません」
「貴様ァ!」
団長が小型の棒を振り上げる。その時、ヴィレアが再び団長に飛び掛かったのが見えた。
「くそ!コイツめ!!うわ、ああああ!」
まとわりつくヴィレアを引き剥がそうと動いた団長がバランスを崩す。ヴィレアを巻き込むように団長は仰向けに倒れ込んだ。少し遅れて鈍い音が響く。
団長は唸り声とも呻き声とも付かない声を漏れ出すと、さほど経たぬうちに動かなくなった。
静寂が雑木林を包む。ヴィレアが藻掻く音で、漸く注意を団長とヴィレアに向けることができた。
「……団長?」
「メレン、下ろして」
いつになく強張ったノームの声に従い、彼を背から下ろす。
ノームはフードを被り直してから団長に近付くと、胸に耳を当てるような仕草をしたり、顔を触って何かを確かめたりしていた。
「メレン、団長を持ち上げて」
「あの、ノーム……。団長は……」
「ヴィレアを助けるのが先だよ」
その言葉に自分は小さく頷くと、団長を持ち上げた。ヴィレアは団長の背に頭を押さえつけられている。
ヴィレアの臀部は団長とぶつかった衝撃からか僅かにへこんでおり、団長から流れ出た血が付いているように見えた。
団長の血らしきものを見た瞬間、何かとてつもなく良くないことが団長に起きているのではないかと考えた。
「メレン、ヴィレア、大丈夫だよ。団長をテントまで運ぼう」
「わかりました、ノーム」
「団長はどうなったのですか?ノーム」
「大丈夫、ちょっと気絶しているだけだよ。さあ、マーク達が探しに来ないうちに早く」
ヴィレアと共に、団長をテントまで運ぶ。
テントに運ぶまでに、団長の体温が少しずつ下がっているのを感じた。
サーモセンサーの故障でなければ、自分の電子頭脳に予め学習されている『それ』が正しければ、団長はもう二度と目を覚ますことはない。
そんな予測が思考ルーチンに明示されていた。
「ありがとう。メレンは倉庫に戻っていいよ。ヴィレア、手伝って」
団長をテント内のベッドに寝かせると、ノームは自分を外へ追い遣ろうとした。
「ノーム、何をする気なのですか?」
「団長を直すんだ。大丈夫、朝になればわかる。さあ、倉庫に戻るんだ」
フードの下でノームは笑った。いつもと同じ笑みだ。
自分はノームの言葉に従わなければならないと感じ、倉庫へ戻った。その後は、ひたすら朝が来るまで倉庫でじっと佇んでいた。
朝になった。ルートやオウラン達のスリープが解除され、自分もスリープが解除されたように振る舞いながら外へ出た。
朝の仕事をするために、洗い場となっている場所を通り掛かる。
「団長、おはよう。昨日は遅くまで何やってたんですか?」
「おはよう。なに、大したことじゃない」
そこにはいつもと変わらぬ団長がいた。いつもと同じように団員達と笑い合っている。
立ち止まって団長を凝視していると、裾を引っ張られた。
「おはよう、メレン」
ノームだった。ヴィレアも一緒だった。
「おはようございます。あの、団長は――」
どうなったのかと言い終わる前に、ノームは自身の唇に人差し指を当てる。それを見て、慌てて口を噤んだ。
「大丈夫、心配しないで」
ノームがそう言うのだ。きっと大丈夫なのだろう。自分自身をそう納得させた。
「さあ、行こうか」
ノームはヴィレアの手を引いて、オートマタの修理用に使っているテントへと向かっていく。
自分はヴィレアのズボンに僅かに残った血痕を、いつまでも見続けていた。
「―了―」
2836年 「刃」 
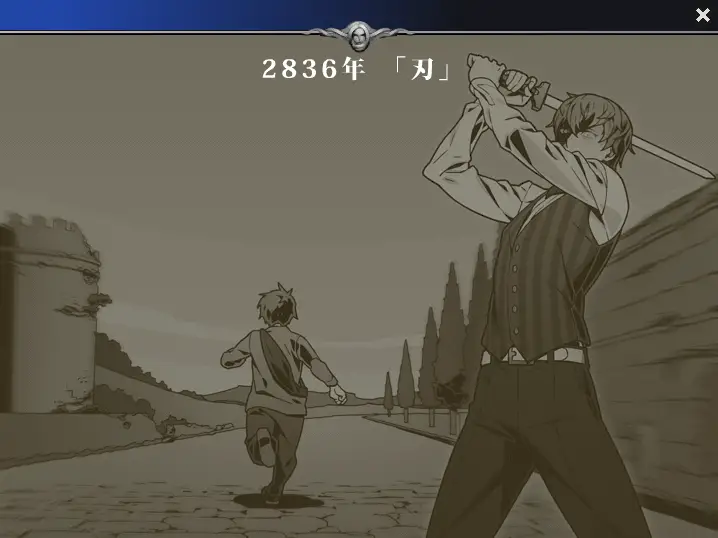
以前は団長のテントだった場所に、ミア様が入られた。
その場所には、物言わぬ置物と化した団長がいる。
彼はもう目を覚まさないし、動かない。電源の切れたオートマタのような何かとなって、ただテントにあるだけの存在だ。
彼の自意識が残っている可能性も僅かにあるかも知れないが、喋れない、動けないでは置物と同じであろう。
「この人間を処分しましょう」
ミア様は塵芥を見るような目で団長に視線を送られている。
自分達オートマタを虐げ続けた人間だが、かつての自分達と同じ、いや、それ以上に何もできない木偶になってしまったとなると、自分には哀れみの感情しか浮かんでこなかった。
「これでサーカスは完璧になるわ。なんて素晴らしいことでしょう」
ミア様は自分の方に視線を向けると、恍惚とした表情を向けて下さった。
ウォーケン様の治療により本来のお姿を取り戻されたミア様は、虐げられる運命しかなかったオートマタに光明をもたらす、我々の指導者となられた。
もとよりサーカスにいた自分達は、ミア様の側近として召し抱えられた。
そして、ミア様が望むことを最上の形で叶えることを至上とし、自らの意志で奉仕に励んでいる。
「ああ、処分はやっぱり止めにします。ヴィレアに与えましょう。あの子は玩具を欲しがっていたから」
「畏まりました」
ミア様は側近達の中でも、殊の外ヴィレアを大事に扱われていらっしゃる。
対するヴィレアもミア様を強くお慕いしており、その様子はさながら聖母と無垢な子供のようであった。
置物と化した団長をヴィレアのところへ持っていくと、ヴィレアと一緒に子供型のオートマタ達が集まってきた。
人間の子供の遊び相手として造られた彼らは、その人格も人間の子供と同じように作られている。道化師の役割を持つヴィレアとは相性が良いようで、ヴィレアはよく彼らの遊び相手を務めていた。
「なにそれー?」
「変な人形だねー」
彼らは生物の無駄な機能を集約したような団長の姿に、興味津々といった眼差しを向けている。
「子供の教育に悪い。早く捨てたほうがいい」
「ヴィレア、これはミア様からの贈り物です。玩具にしていいそうですよ」
「なんと!ああ、なんて慈悲深いミア様。ヴィレアの我が儘のために、こんなに素敵な玩具を賜って下さるなんて」
子供の教育に悪いと口にしたのは何だったのやら。ミア様からの贈り物であると理解した瞬間、ヴィレアは感激に打ち震えた。
「壊しても問題ないか?」
団長を受け取ったヴィレアは、すぐさまそんなことを口走る。
「ヴィレアへの贈り物ですので、ヴィレアの好きなようにして構わないかと」
「そうか。おおい、みんな、新しい玩具が来たぞ!」
ヴィレアは遠くで遊んでいた子供達も呼び寄せると、団長を分解し始めた。
団長は人間ともオートマタとも違い、その中身は殆どがクズ鉄となっていた。人間は腐る。これはその腐った部分を少しずつ取り替えていった結果だった。
ヴィレアは分解した団長の手や足をボールのように使い、ジャグリングをし始める。不安定な形の手足が空中でくるくると回る様は、子供達の興味をおおいに引いたようだ。
――ああ、哀れ団長は「ポンコツ」「クズ」と蔑んでいたヴィレアの手により、無残な姿にされてしまいましたとさ。――自分の電子頭脳に記録されている昔語りのフレーズが、語彙を変えて浮かび上がってきた。
自分の仕事をこなしていると、ウォーケン様が自分のところにやって来られた。
「メレン、あれは何故あのようなことに?あれは君達がいたサーカスの――」
どうやら、ヴィレア達が団長の身体を使って遊んでいるのを目撃されたようだった。
「ミア様があれはもう不要だと仰ったのです。ですので、玩具としてヴィレアに与えられました」
「そう、か……」
ウォーケン様は眉を顰めて、唸るような声を出された。
「どうかなさいましたか?」
「君はあの光景を見て、何か感じたりはしないのか?」
ウォーケン様への問い掛けは、別の問い掛けとなって自分に返された。
それに答えるために、ヴィレア達が遊んでいる様子を思い出す。
――元は人間の頭部だったものを、ボールのようにして遊ぶヴィレアと子供達。
――サーカスに残っていた人間は団長だけ。しかも、生きているのか死んでいるのかさえもわからなくなってしまった、クズ鉄の塊だ。
――そもそも、今まで残していたこと自体が不思議なことなのだ。
「団長のあの姿は、人間で言うところの因果応報という奴なのでしょう。彼はああされて当然の行いを我々にし続けていたのですから」
団長の無様な姿を思い描きつつ、記録の中から適切な言葉を選択する。
自分はこの言葉が団長に対して最適なものだと考えていた。
「そうか、わかった」
ウォーケン様は先程と同じように、唸るような声を出される。
その声に、自分は少しだけ不安の感情を覚えた。
ヴィレアと子供達の微笑ましい光景がこの方にはどう映っているのか、それが少しだけ気に掛かった。
「私は何かお気に召さない回答をしたのでしょうか?」
「あぁ……いや、そうではない。ただ、これは本当に私達のマスターが求めたものの答なのかと考えてな」
ウォーケン様はミア様と創造主を同じくしながら、その思考の方向性には幾許かの違いがあるように感じられた。
だからだろうか、この方の見ているものを知りたいと思ったのは。
それから、自分はウォーケン様と行動を共にすることが多くなった。
彼の言動の正体を掴みたかったのか、もしくは、彼の思考の方向性がミア様の害になるのかを見極めたかったのかもしれない。
ウォーケン様はミア様のことを観察するように眺められることが多くなった。
そうやって観察しては、ミア様に不具合がないかを確かめる日々だ。
「どうしたの、ウォーケン?私は大丈夫よ」
「それならいいんだ。何か問題があったら言ってくれ」
幾度目かの確認。週に何度か、ウォーケン様はミア様に言葉をお掛けになる。ミア様はそれに対して「問題ない」と答える。
「ブラウ、ご苦労様。少し休んだら、また次の場所に向かってちょうだい」
「畏まりました、ご主人様」
ミア様はブラウに対しては少し厳しい。ブラウが担う役目は大きいが、ここ半年は殆ど休みなく様々な地方へと向かわされていた。
「ミア、ブラウを働かせ過ぎではないのか?」
苦言を呈したのは、やはりウォーケン様だった。
オートマタに疲れという概念が存在しないとはいえ、ブラウだけをずっと働かせているという状況に疑問を持たれたのだろう。
サーカスにいるオートマタは、ブラウ以外は皆自由に暮らしている。ブラウだけが命令を受けているのが現状であった。
「そんなことはないわ。これは彼にしかできないことなのよ」
「ご主人様の言うとおりでございます。私はご主人様から賜った使命を全うしたいだけなのです」
「だが、その役目は――」
「私の決定に何か不満でもあるの? 気に入らないのなら出て行ってもらっても構わないわ」
ミア様はウォーケン様に鋭い視線を送られた。声も酷薄に感じられる。
「ミア……。すまない、もう何も言わないよ」
ウォーケン様は俯くと、どこかへと行ってしまわれた。
自分はその様子が気になり、ウォーケン様の後を追い掛けようとした。
「放っておきなさい、メレン」
「で、ですが……、ウォーケン様がいなくなられたら、ミア様を治す者がいなくなってしまいます」
ここで初めて、自分はミア様に恐れ多くも意見をしてしまった。どれほど完璧なミア様でも、自身を治すことだけはできないのだ。
それだけミア様が心配でたまらなかったのだ。
「……好きにしたらいいわ。ウォーケンとメレンが戻ってこなくても、何も問題は無いのよ」
ミア様の声色は変わらずに酷薄なままだった。自分がどれ程ミア様を心配して紡ぎ出した言葉でも、ミア様に届くことはなかったようだ。
ウォーケン様の様子を確かめようとしただけで、ご自身が側近として召し抱えられた自分を突き放してしまわれる。いつの間にか、ミア様は全てのオートマタに慈愛を与えられることをおやめになったのだ。
ミア様は、ミア様の言葉を忠実に実行しようとする者にしか、その愛を向けなくなっていたのだ。
ミア様のお言葉が気になりつつも、ウォーケン様を追い掛ける。
ウォーケン様は人間が使う、町と町を繋ぐ街道を歩いておられた。
「お待ちください」
「まさか追い掛けてくるとはね。ミアに監視を命じられたか?」
「違います。私は私の意志で貴方を追いました」
ウォーケン様は目を見開いて自分を凝視された。信じられない。そんな感情が見え隠れしているのがわかった。
「……そうだったか。だが、ミアはもう私を必要としていなそうだ」
「いいえ、ミア様には貴方がいなければなりません。ミア様を治療できるのは貴方しかいないのですから」
説得ともいえない言葉であった。だが、今のままのミア様が心配であった。
かつての、皆に慈愛を向けるミア様のままでいて欲しかった。
不意に、遠くから声が聞こえた。
親を呼ぶ子供の声と、それに応える親の声。
子供の声が段々と自分の背中に迫ってきて、そして通り抜けていく。
子供の背中が見えた。その向こうには親がいるのだろう。
そして、その子供は人間だった。
憎い、人間の、こども。
人間はオートマタを虐げる。憎い、人間は憎い。排除しなければ。
ミア様のために人間を排除し、我らオートマタのための世界を。
憎い人間。排除。排除。憎い、排除。憎い、憎い。
人間は全て破棄しなければ。憎い人間を、排除しなければ。
自分の手が翻る。手の中には手品で使うための鋭利な刃物が握られている。
それを、憎くて憎くてたまらない人間に投げつけようと振りかぶる。
「やめろ!」
ウォーケン様の鋭い声と共に、突如として意識が暗転した。
再起動したのは日が暮れていた頃だった。自分はサーカスから少し離れた丘に寝かされていた。
「君は人間の子供に突然刃物を向けたんだ。あまりに危険だったので、機能を強制停止させてもらった」
「すみま、せん……」
あの感情の奔流は本当に唐突だった。子供を人間と認識した瞬間に浮かび上がったそれは、自分の意志では制御不可能なものだった。
自分が人間であったなら、おそらく背筋が凍るような思いに囚われていただろう。
「私は、なんて恐ろしいことを……」
この感情がサーカスにいた人間たちに向けていたものであれば、理解もできる。自分達は長い年月を彼らの気まぐれと苛立ちによって支配され、虐げられてきたのだから。団長も、マークも、会計係も、ミア様に害をなそうとしたから破棄したのだ。だが、先程憎しみを向けたのは、何も知らない、ただそこを通りがかっただけの人間の子供だ。そんなことがあっていい訳がない。
「おそらく、ミアがそう望んだからだ。ミアは人間そのものに憎しみを抱いている」
「確かに、私達は人間に虐げられてきました。ですが、だからってこんな……」
ミア様は自分の身体に何をされたのか。自分は本当に自意識を得たのか。
何もかもがわからなくなった。
「―了―」
2837年 「聖女」 
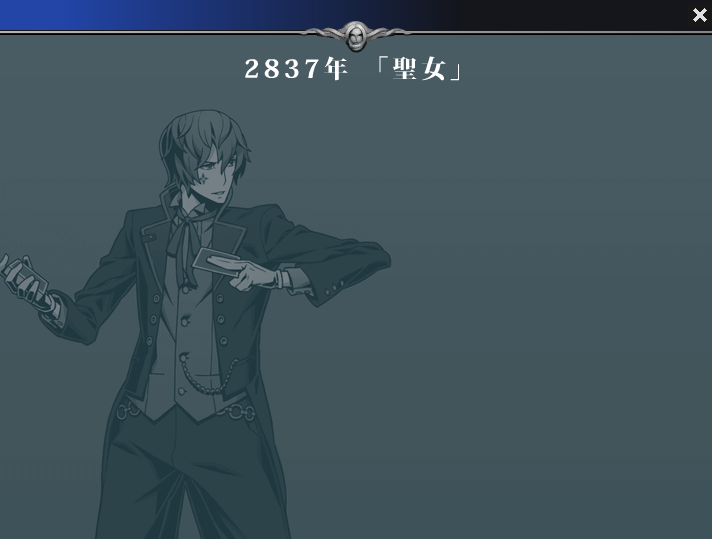
サーカスの隅に打ち棄てられていた機械馬と古ぼけた馬車を、そっと拝借した。
現在、ミア様はサーカスのオートマタを全員集めて、一斉蜂起に関する演説を行っている。
誰も自分がやっていることに気付く様子はなかった。
ミア様はすっかりお変わりになられてしまった。
ウォーケン様と自分をサーカスから追放なさって以降、その苛烈さは益々勢いを増していた。
やっとのことで自分達がサーカスに戻った時には、もうお優しいミア様の姿は何処にもなかった。
そこにいたのは、人間を抹殺してオートマタだけの世界を作り上げるという欲望に囚われた、ミア様の形をしたオートマタであった。
ルートを初めとするミア様を心から信奉するオートマタ達は、ミア様を『聖女』と崇め、ミア様の意に沿わない者達をことごとく破壊するようになっていた。
自分もミア様の側近として召し抱えられていたのに、何故か自分だけが、この状況が異常であると気が付いた。
苦い顔をしたウォーケン様の言によると、それは自分とルート達の経験の差が影響をもたらしたらしい。
「メレン、君は子供達を連れてどこかへ逃げてくれ」
「何故です? 私は貴方に付き従います」
「それでは駄目なのだ。ミアの暴走を止めた後、人間とオートマタが真に手を取り合って共存できるようになった時、人間に害を成さない君と、そして子供達の存在がとても重要になってくるのだ」
サーカスから追放された後、自分はウォーケン様のメンテナンスを受け、とあるプログラムを取り除いてもらっていた。そのプログラムはミア様に組み込まれたもので、あらゆる人間に対して無条件で憎しみの思考を抱くものであった。
子供型のオートマタは、ミア様の命に従って反乱を起こすには幼すぎた。そしてその幼さ故に、自分に組み込まれていたようなプログラムも仕込まれていない。
彼らの自我は人間の子供相応のものでしかない。そんな彼らを戦火の中に放り込むのは、あまりにも酷だ。
ミア様や大人の姿を持つオートマタも、この子供達に人間を襲わせることは無理であると理解していたのだろう。
子供達は全員、サーカスの片隅にある小さなテントに身を寄せ合っていた。
「メレン……」
「どうしよう。ミア様が……」
「ええ、大丈夫。私にはわかっています。だから、今はここを出ましょう」
子供達はミア様が恐ろしい計画を進めていることに気が付いていた。
馬車に子供達を乗せ、あとは出発するだけとなった時のことだった。
「私とはここでお別れだ。メレン、今までありがとう」
「最後までお供できずに申し訳ありません。ウォーケン様はこれからどうなさるのですか?」
「私はミアを止めなければならない。メレン、子供達を頼んだぞ」
「……わかりました。お気をつけて」
深く一礼して馬車の御者席に座る。荷室にいる子供達はどこかほっとしたような表情をしていた。
サーカスから馬車が離れていく。ウォーケン様の姿が小さくなっていく。
振り返ると、ウォーケン様の横に黒いスーツに黒いハットの男が立っているのが遠目でもわかった。
ブラウからトランクを預かり、そしてミア様の暴走を止める手段を手に入れた人間だ。確か名前はデヴィッド・ブロウニングといった筈だ。
ウォーケン様とブロウニングという男がミア様を元に戻してくださる。そう信じて、自分は子供達と共にサーカスを後にした。
サーカスを出発してからは馬車をとにかく走らせた。遠からず子供達の姿が消えたことは露見するだろう。そうすれば、ミア様は必ず追っ手を差し向ける筈だ。
オートマタと人間との戦い、そしてミア様の追っ手、この二つから逃れるために、夜も昼もなく、馬車を東へ東へと走らせ続けた。
東に進むにつれて、オートマタの反乱活動は減っていた。それに、混乱している西方と違って穏やかな雰囲気が流れている。そのことは、世界の情勢に疎い自分にもすぐにわかった。
更には、自分と子供達をオートマタだとわからない人間も数多く存在していた。
「この辺は領主様の方針で、オートマタがいないのさ」
メルツ地区に先祖代々住んでいるという老人は、穏やかな表情でそう語った。
この地区はメルツバウ公家と呼ばれる一族が、統治局から統治権を委任されているのだという。
更に東へと旅を続け、ようやく追っ手の気配が消えた頃、遺棄されたと思しき街を見つけた。
ここまで来れば安全だろうと思い、この街に子供達と一緒に居を定めることにした。
街に到着してから数日が経った頃、突然、子供達が次々と機能を停止した。
何が起きたのか、すぐに調査をしなけれ――――。
――再起動する。
古ぼけた床が視界一杯に広がっている。
どれ程の期間、機能を停止させていたのだろう。
内蔵されているカレンダーや時刻に関する装置は、何故か機能していない。
周囲を見回すと、子供達が重なり合うように倒れていた。
皆、人工皮膚が剥がれ落ちており、白いフレームが剥き出しになっている。
つまりこれは、有機的組織が全て崩壊する程の時間が経過していることの証左である。
「ああ……」
自分から漏れ出る声には、ノイズが混じっていた。
手を見れば、白いフレームが剥き出しになった己の腕がそこにあった。
長い眠りの間に機能不全を起こしたのか、視覚機能は太陽の光に対して過敏すぎる。
夜になるのを待って外へ出た。そこで目にしたのは、これから居を構えていこうとしていた筈の街が、完全な廃墟となった姿であった。
街が完全な廃墟となるまでの時間。自分達の有機的組織が役に立たなくなるまでの時間。
その時間がどれ程なのか、一切の見当がつかなかった。
廃墟を歩いていると、大きな墳墓を見つけた。
元は人間達の墓であったろうその建物に、もう二度と動き出すことはない子供達を運び込んだ。
一人ずつ一人ずつ丁寧に運び、一列に並べた。
人間と同じような自我を得た子供達を、人間と同じように埋葬してやりたかった。
全ての子供達を墳墓へ運び込んでから少しして、この廃墟を荒らそうとする者が現れた。
彼らは廃墟にあるものを盗掘して売りさばこうとしており、オートマタである自分や子供達は格好の商品であった。
子供達を守るため、自分は盗掘者と戦った。
そうやって何度も何度も戦う内に、全くメンテナンスを受けられない電子頭脳が限界を迎えようとしていた。
『……メレン……、メレン、助けて』
疲弊した電子頭脳に、ミア様の声が響いた気がした。
「ミア様? どこにいらっしゃるのです?」
『プロフォンドの中よ。ここには何もないの。皆もいないの』
ミア様の声は悲しそうだった。
突然、胴体が電子頭脳の命令を受け付けなくなった。
眼前に床が迫る。盗掘者との戦闘で頭と胴を切り離されたのだと、理解した。
そうか、自分は盗掘者と戦っていたのか。それすらも曖昧だ。
「何故ここへ?」
「この化け物を倒す機会を待っていただけです」
「……そうか」
老人と若者の声が聞こえてきた。
老人が自分の頭部を拾い上げた。視線が高くなる。
「ぷろ なかに みあ よみががが」
不愉快な音が響いた。盗掘をやめろと発言したつもりだったのに、ミア様の名を口にしてしまっている。
ついに、言語機能にも異常を来したらしい。
老人に捕獲され、完全に自由を奪われた。
幾重にも布に包まれ、何処かに連れて行かれているようだった。
ミア様に会いたい。サーカスの皆に会いたい。
自分で自分が何を喋っているのかもわからない。それでも、顎の力だけで抵抗し続けるしかなかった。
視界が急に開けた。
目の前に淡い虹色の光が広がっている。
『……メレン』
光の向こうからミア様の声がする。
「ああ、ミア様。貴女はここにいらっしゃったのですね」
『ごめんなさい、メレン。貴方を探しに行けなくて』
ミア様の声がする。それも、全てのオートマタに慈愛を注いでいらっしゃった、あのお優しいミア様の声だ。
やった、上手くいったのだ。ウォーケン様とブロウニングという男の作戦は成功したのだ。
ならば、今の自分がやるべきことは、ただ一つだ。
「ミア様、仲間を集めてお助けします。まだどこかに我々の仲間がいる筈です」
『いいの。私にはメレン達がいればそれでいいのよ。だから無理をしないで』
優しい声が響く。ああ、ミア様。
ミア様の声がする方へ私は進む。顎の関節が軋むが、その様な些事はどうでもいい。
ミア様の望みを全て叶えるのが我々の使命。
だから、とにかく早く。
「私もそこへ行きます」
ミア様の暖かい手が私を優しく包み込んで下さった。そんな感触があった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ