リンナエウス
3390年 「環境」 
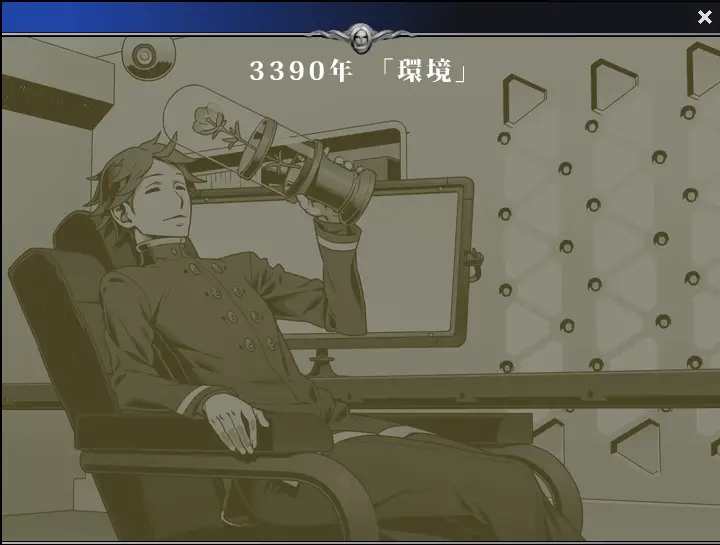
青い空に白い雲。輝く太陽。爽やかな風が吹き抜ける丘の上。
不思議な匂いがする鮮やかな花々。柔らかい土の温かさ。
それらは今でも忘れない。
モニターにはデジタル化された地上の地図が所狭しと映し出されていた。
リンナエウスがコンソールを操作すると地図がズームし、空気中に含まれる物質、地中温度、土に含まれる物質、毒素などの数値データが表示される。
しかし、そのデータの日付は現在よりも幾分か古いものであった。
「この地域の調査担当って、ドレッセル技官だったよねぇ?」
モニターの日付を指しながら、リンナエウスは横のデスクでデータ整理をしていた助手のペトルスに尋ねた。
「はい。そうです」
「ドレッセル技官から何か連絡は?」
「いえ……。調査報告は昨年の雨月十五日を最後に途絶えています」
口籠もる助手のエンジニアに、リンナエウスは小さく溜め息をついた。
「そう。統制局からの通達でこちらからの連絡はできないし。困ったねぇ」
レジメントへの派遣以外にも、幾人かのエンジニアが環境調査のために地上へ送られており、彼等の調査報告は逐一更新されていた。
しかしジ・アイが消滅して間もなく、統制局は地上へ派遣されているエンジニアとの連絡は全て当局を通すようにとの通達を出した。
この通達のために、地上の状況を細かく知る必要がある者は困惑の最中にあった。《渦》の消滅により、地上環境の変化には著しいものがある。それを統制局は理解していながら環境改善の研究を行うエンジニア達の行動を制限したのだ。
特に、その部門に関しての最先端を行くリンナエウスには大きな痛手だった。
「どうしますか?最悪の場合、こちらから通信を行うことも考慮しなければと思いますが」
「まあ、統制局が突拍子もなく研究を制限するのは儘あることだからねぇ。私達はおとなしくして、いまできる範囲の研究を続けるしかないよ」
「そうは仰いますが、このままでは研究自体が停滞してしまいます」
「統制局に逆らっても良いことはないよ。君もパストラスのハワード所長のようにはなりたくないでしょう?」
リンナエウスは焦るペトルスに、戯けた調子で言ってのけた。
「も、申し訳ありません」
かつてケイオシウム研究を巡って起きた大粛清。その時、ケイオシウム研究の第一人者であるテクノクラートが処罰対象となった。
そのテクノクラート、ハワードはリンナエウスの遠戚に当たる人物だった。そのせいか、リンナエウスは大粛清の時に起きた混乱をつい最近のことのように思い出すことがあった。
「別に謝る必要はないよ。あの人は研究に一途過ぎただけ。まあ、そこがいい所でもあったけれどねぇ」
それだけ言うと、リンナエウスはモニターに向き直った。
それから暫くして、統制局は複数の研究所に対して再編と統合の通達を出した。
理由としては、レジメントに派遣されていたエンジニアが多数殉職したことによる人員整理であるとのことだった。
リンナエウスの所属していた研究所は解体の対象となっており、所属するエンジニアには異動辞令が出されていた。
「ペトルス技官、バリオン研究所への異動おめでとう。栄転だねぇ」
研究データを整理していたリンナエウスが、部屋に入ってきたペトルスに掛けた第一声だった。
「私は納得がいきません。何故私がバリオンへ行って、貴方の異動先が未定なのですか!」
ペトルスは憤慨した様子で異動辞令が入ったポータブルデバイスを睨んでいた。
「君の実力が認められたってことでしょう?」
「貴方は上級技官でしょう。なのにどうして……」
リンナエウスは憤慨したままのペトルスを見て笑う。
「君は私に毒され過ぎちゃったのかねぇ。駄目だよ、栄光あるバリオン研究所の一員になるんだから、もっとエンジニアらしく振る舞わなきゃ」
「私には貴方の言っていることが理解できかねます」
「それでいいんだよ。私の研究は異端だし、それに、そもそも君はデータ管理の適正を見込んだだけの補充要員だったんだし」
「リンナエウス上級技官は、私のことをその程度であると仰るのですか?」
「うん。だから私の事は放っておいて」
「貴方という人は……」
それ以上の会話は無かった。それでもペトルスは最後の作業として、誰が見ても分析しやすいようにデータを纏め上げた。
「これからどうしようかなぁ」
自宅へ向かう車の中で、リンナエウスは大きく息を吐いた。
リンナエウスの異動先が未定というのは建前であった。彼の予定異動先は既に通知されていたが、そこは現在に比べると全く自由のきかない研究所であったため、異動への返答を先延ばしにしているだけである。
ペトルスには黙っていたが、リンナエウスを取り巻く環境は良くも悪くも酷く極端であった。
リンナエウスはパンデモニウムが浮上する以前から続く高名な一族の直系血族であり、指導者層となるべく高等プログラムも受けていた。遺伝子スクリーニングもほぼ最良の結果であるし、旧体制下ほどではないにせよ、ある程度自由に恵まれた地位に就けることが約束されている筈だった。
だが、大粛清の際に処罰対象となったハワードの存在が、リンナエウスの一族に暗い影を落としていた。
ハワードの家系が傍系であったのが幸いして厳重な監視こそ免れているものの、統制局からの厳しい目に晒されていた。
自宅に到着すると、生活サポートドローンがリンナエウスを出迎えた。杖とドローンに介助されながら、ゆっくりと自宅の廊下を歩く。
リンナエウスは先天性の疾患により、右足に異常を持って生まれてきた。パンデモニウムの医療技術でも完治できなかったため、歩行に不自由が残っていた。
「荷物の整理はできてる?」
「現在60%程度となっております」
「わかった。引き続き進めておいて」
「承知いたしました」
自室のデスクに座ると、硬化ガラスケースを手に取る。中には一輪の青い花が飾られていた。
何の理由でかは忘れたが、幼い頃、父親に連れられて降りた地上で見つけたものだ。もう何十年も前の切り花ではあったが、パンデモニウムの物質保存技術で半永久的に保存されている。
リンナエウスはかつて見た地上の美しさに心を奪われ、それを地上に取り戻すべく、『地上の環境改善』を研究テーマとして選択した。
ガラスケースの花はその象徴といえた。だが、統制局の思惑によってその研究が暗礁に乗り上げつつあった。
このまま自由がきかなくなるのなら、いっそ現地調査の名目で地上に降りてしまおうか。理由なんて後付でどうとでもできる。そのように考えてドローンに荷物の整理を命じるほど、リンナエウスは思い詰めていた。
「レナート様、お客様がお見えです」
どれほどの間花を見つめていたのだろうか。ドローンの音声ではっと我に返る。
「誰が来たの?」
「オルグレンと仰っておいでです」
「わかった。客間に通しておいて」
「承知しました」
あまり人に会いたい気分ではなかったが、古くからの知り合いであれば無碍にする訳にもいかなかった。
「どうしたんだい急に?連絡もなしに尋ねてくるなんて珍しいねぇ」
オルグレンは長い付き合いのあるエンジニアだ。医療技術の才能に恵まれ、リンナエウスに先んじてテクノクラートの資格を得ている。
「研究所の異動について未確定と聞いた。何が起きている?」
「そのことか。統制局に逆らうような真似はしたくないけど、今の研究が続けられなくなるのも困る、というところかなぁ」
「異動先では満足に研究ができないということか」
「そうだねぇ。勝手に調査したけれど、あの研究所には私の分野に使えるような設備は無いようだからねぇ」
「足りない設備はいずれ増設すると聞いているが?」
「今回の件でいくつの研究所が解体されると思っているの。設備増設の予算なんてものが出るとは考えにくいよ」
オルグレンはリンナエウスの言葉に、考えるように沈黙した。
「実は、今回直接尋ねたのには訳がある」
オルグレンはややあって口を開くと、ポータブルデバイスに一つの令状を表示した。
「本来なら他人に見せるものではないが、これを見て欲しい」
その令状は、新設される研究所の所長就任の辞令であった。
他にもその研究所に異動となるエンジニアのリストがあったが、リンナエウスはそのリストに見知った名前があることに気が付いた。
誰も彼も、突出した能力を持ってはいるが『異端』と分類されるような研究を行っているエンジニアばかりだった。
「ずいぶんと思い切った人員だね、これは」
「上はこの研究所をレジメント派遣と同じような名目の研究所にするつもりのようだ」
「なるほどねぇ。で、私にこれを見せた理由は?」
オルグレンの言葉によって統制局の意図は掴めた。要は厄介者の烙印を押されたエンジニア達を一つの研究所で管理しようというところなのだろう。
別々の研究所を監視するよりは、一箇所に纏めておいた方が労力も少なくて済む。その程度はリンナエウスにも想像が付いた。
「貴方が今の辞令を決めかねているのなら、私と共にこの研究所の共同設立者とならないか?私が所長で、貴方が副所長だ」
「統制局にはどう説明するつもりだい? 保留状態ではあるけれど、私は既に異動先が決まっている身だよ?」
「厄介な研究所の所長に任ぜられる見返りとして、私には役付きの人員選択権が認められている。だからこうして交渉している」
「ふむ……。共同設立者となることで、私に生じる利益は何かなぁ?」
厄介者の受け皿となる研究所である。何が起こるかは想像できない。
「副所長の職務と引き換えだが、共同設立者としての権利が生じる。自由な研究活動の保証だ」
「少し考えさせてくれるかな……」
リンナエウスは慎重になっていた。オルグレンのことを信頼していない訳ではない、ただ、少しだけ冷静になって心の準備をする時間が必要だと感じていた。
「もちろんだ。だが、返答は早い方がいい」
「わかった。早めに連絡するよ」
オルグレンは私用の連絡先を置いて、リンナエウスの自宅を後にした。
彼を見送ったリンナエウスは、自室に戻って考えた。
これはチャンスではなかろうか。オルグレンに付いて副所長となれば、ある程度の自由は保障される。その代わりに副所長としての職務が発生するが、それでも、このまま統制局の通達に 従うよりかは先が見えるのではないだろうか。
翌朝、リンナエウスはオルグレンに渡された連絡先に通信を入れた。
「あぁ、オルグレン?昨日の件だけど、引き受けるよぉ」
デスクに置かれたガラスケース、その中で青い花が揺れていた。
「―了―」
3390年 「狐」 

《渦》による被害が最も酷かったインペローダ領サラン州。かつてそこにあった自然を復活させるための調査。
リンナエウスはその責任者として、地上改善を主要研究とする複数のエンジニアと共に地上へ出向していた。
オルグレンの要請を受けたリンナエウスは、レプトン研究所に副所長として入所し、地上の環境改善に関する研究を続けている。環境改善の第一人者であるリンナエウスが出向の責任者となるのは順当であった。
ライブラリアンが発掘したかつての自然分布図やインペローダの古い風景写真などと照らし合わせ、どういった改善が適しているかを調査する。
それがリンナエウスの仕事である。
《渦》の影響がなくなった地上の調査は、驚くほどスムーズに進んだ。
かつて《渦》がこの世界に存在した頃、何人ものエンジニアが地上調査に送り出されたが、得られた成果はごく僅かであった。
それが今は、調査をすればするだけ成果が出てくる。
《渦》が人類をどれほど脅かしていたのか、リンナエウスはその事実に改めて震えた。
「おや?」
リンナエウスが調査クリッパーでジ・アイの跡地周辺に赴いたときのことだ。
そこには、怪我を負った一匹の野生動物が横たわっていた。
このような不毛の大地に動物がいるということ自体、非常に珍しい。
別の場所から餌を探して迷い込んだのか、それとも群れから追い出されて彷徨っているのか。いずれの理由も区別は付きかねた。
だが、野生動物がこの地にいるという事実自体が、貴重なサンプルである。
「あの狐を保護しようかぁ」
「生態系調査のサンプルですね」
「うん。それに怪我を治して野生に帰せば、この個体がここでの新たな生態系発展のきっかけになる可能性もあるからねぇ」
「わかりました。保護用の檻を用意します」
こうして、一匹の狐がリンナエウスの研究棟へと保護された。
リンナエウスが保護した狐は、非常に大人しい個体であった。
怪我を負っているということもあるが、基本的に部屋の中でじっとして養生していた。実際に保護をしたリンナエウス以外の者が部屋に近付くこともなかったためか、噛み付いたり暴れたりといった危険なこともなかった。
地上管理局にも、この貴重な野生動物の保護に関する中間報告を済ませておいた。
野生動物の保護報告から数日後のことだった。
調査用クリッパーから送られてくるデータを閲覧していると、 部下の技師から通信が入る。
「地上管理局から、保護した野生生物の処分に関する通達が来ています」
「不毛の地であるサラン州に生物がいることがどれほど貴重なのか、地上管理局はわかってないのかなぁ」
「リンナエウス上級技官の仰るとおりではありますが……」
「いいよ、地上管理局には私から説明するから、連絡を待てって言っておいて」
「わかりました」
通信が切れると、リンナエウスは地上管理局にどう言って納得してもらうか考えつつ、データ閲覧を再開した。
「地上環境の改善の目安となる野生動物を保護しただけであり、処分通達は受け入れかねます」
「どんな毒を保持しているかもわからないものを保護するなど──」
「寄生虫や病原体の検査は完了しています。特に人体に影響はないと報告済みでしょう」
「そもそも、野蛮な地上の生物に干渉するなど、規約違反だ」
地上管理局員は強めの口調で規約を持ち出した。この言葉を言われると大概のエンジニアが萎縮することを知った上での言葉だ。
「技術提供エンジニアが地上に出向するのとは訳が違います。我々の調査は《渦》が原因で荒廃した地上環境を改善するための調査です」
「だが、調査項目に野生動物の保護といったものは含まれていない。研究棟に持ち込んだ地上のものは、全て処分すべきだ」
「地上で発見したものは全てが貴重なサンプルです。ましてや生物をこちらの都合で処分するなど。摂理としてあってはならない」
地上管理局員は無言になった。その隙を逃さず リンナエウスは畳み掛けるように言葉を続ける。
「地上の環境改善は統制局からの勅命です。地上管理局の判断だけで処分不処分が決められるとお思いですか?」
長い沈黙があった。
「……わかった。通達は撤回しよう。だが、くれぐれもその動物の毒をパンデモニウムに持ち込まないように」
地上管理局員は苦々しい顔でそう言うと、通信を切った。
リンナエウスは通信が切れたことを確認すると、大きく溜息を吐いた。
統制局は地上平定や地上環境の改善を謳っているものの、各局はエンジニアの専門的な意見や現場の報告を無碍に扱うことが多々あった。
最高指導者レッドグレイヴが復活してからというもの、こういった強硬姿勢をとる局員は多い。交友のあるエンジニアや中央統括センターに勤める親族からも、各局の高圧的な行動を何度も漏れ聞いていた。
レッドグレイヴは薄暮の時代において、類稀なる政治手腕をもって世界を改善し、発展させてきた人物であるのは確かなのだろう。だが、今のレッドグレイヴは、高圧的でエンジニア達の研究を蔑ろにするような各局を咎める動きを見せない。
加えて、見せしめのように処刑された遠戚の存在もあって、リンナエウスは彼女の統治にかなり懐疑的な視線を送っていた。
とはいえ、そんな発言を口にすれば自分がどのような処罰を受けるかは明白なため、この思いを誰かに漏らすことはなかったが。
インペローダでの調査は、例の狐を保護したこと以外は大きな問題が起こることもなく、つつがなく終了した。
明朝には予定通りパンデモニウムから迎えの飛行艇がやって来る。
狐に関してはこのまま野生に帰すつもりであった。
最初に保護した時点で処分が言い渡されるような状況では、この狐を生きたサンプルとしてパンデモニウムに持ち帰ることは不可能であった。
その日の夕方、リンナエウスは狐のいる部屋を訪れた。傷はすっかり癒え、野生に帰るリハビリの結果も申し分ない。
「私がパンデモニウムに帰る前に怪我が治ってよかったよぉ」
狐は、話し掛けるリンナエウスをじっと見つめていた。
「さて、明日には君を解放できるよ。今まで窮屈な思いをさせてごめんねぇ」
それだけを言うと、リンナエウスは狐のいる部屋をあとにした。
翌朝に備えて眠っていたリンナエウスは、腹に鈍い衝撃を受けて目を覚ました。
誰かが腹の上に馬乗りになっていることはわかったものの、暗くて自分の状況を正確に把握できないままでいた。
口は布か何かで塞がれて、声を上げようとすることはできな い。
「暴れるな。今からいくつか質問する。素直に答えれば殺さない」
女の声が上から降って来る。
「イエスなら首を縦に、ノーなら横に振れ。わかったか」
声は小さいが、鋭くリンナエウスの耳に届いた。わかったの意思表示をするために首を縦に振る。
「お前はハワード・リンネという男の親類で間違いはないな?」
ハワードという名称に、リンナエウスは眉を顰めた。
この女は何故、二十年ほど前に処刑された遠戚の名を知っているのか。
「答えろ!ハワード・リンネは親類か?」
口に宛がわれた布に力が込められる。これ以上力を込められると窒息の可能性もあった。
慌ててリンナエウスは首を縦に振る。
「ハワードが処刑されたあと、遺品の美術品を受け取ったな?」
彼女が言う遺品とは、ハワードの家族から渡されたもののことだろう。
ハワードは、一族がパンデモニウムが浮上する以前から所有していた美術品を管理していた。これらの美術品は協定監視局による検閲を経て、最終的に一族の直系であるリンナエウスに譲渡された。
古くから一族に伝わる価値のある美術品ということなので、譲渡されてからは家で大切に保管している。
だが、この女はどうしてそのようなことまで知っているのか。再度首を縦に振り、女の次の言葉を待った。
「それを私に寄越せ。あれにはハワードの研究の全てが隠されている」
今度こそリンナエウスは驚くしかなかった。
ハワードの研究。即ち、当時の最先端を行っていたケイオシウム研究。
その研究の全てが、検閲され問題ないとされた美術品に隠されているなんて、誰が想像できるだろうか。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ