リーズ
【死因】
【関連キャラ】マックス(マキシマス)、ディノ、イデリハ、ミリアン、ルディア
3376年 「怒り」 
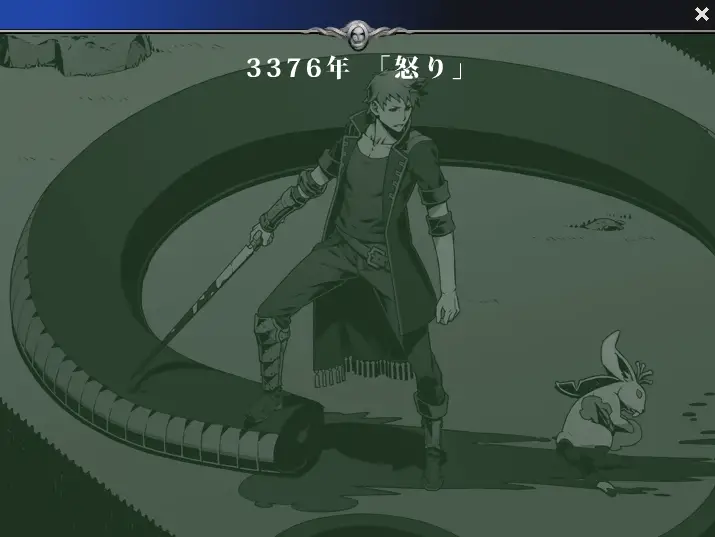
「こんなことやってても、いつか皆やられちまうんだ。人間の住む街はどんどん減ってきてる。俺たちの街だって、渦が来て……」
グリッドがぶつぶつと独り言のように文句を言った。いつもの恐怖を紛らわすための儀式だと思って、他のメンバーは聞き流していた。
「黙れよ。あんたの泣き言なんか、聞きたくねえよ」
グリッドの泣き言をリーズが断ち切った。
カナーンの守備隊は『魔物』見たという住民の報告を受け、街を囲む城壁を越えた、街道からも離れた森を探索していた。
メンバーは二十人程で、様々な年齢の男達の集団だった。
「リーズ、ガキのお前はわかっちゃいねえんだ。ずっとずっと前から人間は減り続けてるんだ。俺が子供の頃は隣街のメルギスへだって行けたが、今はどうだ?メルギスの街自体が渦に飲み込まれちまった」
グリッドはリーズに向かって早口で捲し立てた。
他の守備隊のメンバーはこの男の愚痴にうんざりだったが、魔物と戦わなければいけない、という緊張からか、敢えて誰も止めに入らなかった。
「ここに来るまでに難民達を見ただろ。城壁にへばりつくように生きてる奴ら。あれがメルギスの住民さ。少しずつ魔物に喰われていってるんだ。哀れなもんだ」
「黙れって言ったぜ、おっさん」
リーズは足を止めてグリッドの胸倉を掴んだ。グリッドの背はリーズよりだいぶ低く、胸倉を掴まれるとつま先立ちになっていた。
「は、離せ。小僧が」
「哀れなのはあんただよ。少しは口を閉じてまっすぐ歩け」
投げるようにしてリーズが手を離すと、グリッドは無様に地面にころがった。
「ば、馬鹿野郎、粋がりやがって。お前の親父だって……」
「それ以上言ったら、お前を先に殺すぞ」
リーズが剣に手を掛けた
「おい、やめろ。構うな。怖いんだよ、こいつは」
副長格のバックがリーズを止めた。
「こんな奴、連れてこなきゃよかったんだ」
リーズはバックに従って隊列に戻った。
リーズは若くしてこの守備隊に入った。いまは十八だが、十代の前半からずっと戦っている。
元々守備隊を率いていたのは彼の父親だった。街を守るために、守備隊として魔物が近付くのを防いできた。しかし二年前の戦いで大怪我を負い、隊長を退いた。今は悪くなった足をかばいながら、細々と暮らしている。
そんな悲劇を目の前にしても、リーズが守備隊を辞めることはなかった。
自分の目の前で父親が襲われたが、それを助けたのもリーズだった。瀕死の父親を一人で救い出し、その後も前線に立ち続けた。
そんなこともあり、リーズは若いながらも守備隊で一目置かれていた。
恐怖を知らないのではないか、と囁かれることもあったが、リーズ自身、恐怖を感じていない訳ではなかった。自分の前で父親が襲われた時、心底恐ろしかった。
しかしそれ以上に、自分の中に魔物に対する怒りが沸いた。
恐怖より怒り。
リーズを駆り立てるのは、その感情だった。
そんなリーズを父親は、しばしばきつく諌めることがあった。
「怒りをコントロールしろ、押さえろとは言わん。自分が怒りに駆られていることを意識し続けろ」
自分の怒りを制御すること。
グリッドの苛立たしい態度に切れた後、リーズはそんな父親の言葉をもう一度思い出していた。
隊列が止まり、部隊に緊張が走った。合図があり、部隊は訓練通りに展開を始める。指を差し、見つけた魔物の位置を確認し合う。
魔物には色々な種類がある。守備隊では全く敵わない強力な生物が出てくればどうしようもないが、そうでなければ、逃がさずに倒さなければならない。
そうしなければ、渦の化け物共は増え続け、街を飲み込むだろう。
「蛇だ」
誰かの声がした。
15アルレ《約20メートル》はあるかという巨大な蛇だ。ただ、蛇と言っても地上にいるような顔つきではない。十対もある目をぎらぎらと輝かせる、悪夢のような化け物だった。しかし、倒せないわけではない。
皆で慎重に敵を囲む。逃がす訳にはいかない。
隊長の合図と共に銃声が響く。しかし蛇の動作は速い。
鎌首を高く持ち上げたかと思うと、素早くその尻尾で部隊を薙ぎ払う。途端に銃声が止んだ。
蛇の尻尾に吹き飛ばされた男達が呻き声を上げる。怯んだ隊員は体勢を立て直そうとするのに精一杯となっていた。
再び鎌首を持ち上げて辺りを睥睨する蛇に、皆が恐怖していた。
蛇は口を開けて、舌なめずりをした。
この空間、この瞬間、恐怖が辺りを支配するのをリーズは感じた。しかしそれに囚われることなく、リーズは蛇の前に飛び出した。
呆気にとられる部隊員の前で、リーズは蛇の首を切り落とした。
驚くべき剣技だったが、それよりも、一瞬で相手の懐に飛び込む胆力こそ、リーズが凡百の男でないことの証左だった。
部隊から歓声が上がる。
「よくやった、リーズ」
隊長から声を掛けられる。
「なに、皆があの化け物の注意を引きつけてくれたからさ」
本心ではなかったが、部隊の士気を挫かないために、リーズはあえてそう言った。
部隊は街に戻った。化け物を倒したことで、ちょっとした凱旋騒ぎになっていた。
リーズはそんな騒ぎから距離を置きつつも、一応参加していた。
「俺は銃を構えてよ、バババっとあの大蛇を撃ちまくったのよ、そしたら蛇の野郎、しっぽを巻いて逃げだしやがってよ。そこへリーズがトドメを刺したって訳よ」
すっかり上機嫌になったグリッドが、隣に座った酒場の女に自慢話をしている。
「やれやれ。グリッドの野郎、後ろのほうで縮こまってたくせにな」
副長のバックが、カウンターの端にいたリーズの傍に来て言った。
「まあ、言うだけならタダだ」
「しかしリーズ、すまなかったな。お前にばかり手を煩わせて」
最近の出撃では、リーズの腕で隊が救われることが多かった。
「別に構わない、親父もやってきたことだ」
「親父さんも、それはいい戦士だった。だがリーズ、お前には驚かされてばかりだ」
バックとリーズの父親とは、若い頃からの友人だった。このカナーンの街で生活し、街を守ってきた。生業は別に持っていたが、街を守るためにずいぶんと修羅場をくぐってきた男だった。
「ずっと、このままいけると思うか?」
バックが尋ねた。
「どういう意味だ?」
「最近、魔物が街道近くに現れる回数が増えてきてる。渦自体が近くに現れたという話は聞かないが、渦からあふれた化け物どもがこの街に迫ってきてるんだろう」
「そうだな。これからは油断できなくなる」
「ああ。もっと守備隊は増強しなきゃならない。いまの人数と能力じゃ、冗談みたいなもんさ」
「協力するよ」
リーズも今の守備隊の能力には疑問があったので、同意した。
「でもな、俺の本音を言えば、このままじゃこの街は守れないと思ってる」
バックは目を伏せて自分のグラスを眺めている。
「グリッドの愚痴もな、あれはあれで真実をついてるんだ」
「俺はそうは思わないよ。親父もあんたも、この街を守ってきた。これからだって大丈夫だ」
リーズは冷たい炭酸水の入ったグラスをあおった。酒は好きではなかった。怒りをコントロールできなくなるんじゃないか、という不安からだった。
「順番なのさ。段々と人間の住める街は少なくなってきてる。これは確かだ。洪水に沈む街みたいなもんさ。高台にある家はなかなか沈まない。しかし水かさが増せば、その高台だって沈む」
「俺はそうは思わない」
「渦はな、今まで一個だって消滅してないんだ。水かさは増し続けてる」
「だからって、黙って溺れ死んだりはしないぜ。俺は」
バックのらしからぬ態度と言葉に、自分の中にざわついた気持ちを持ち始めていた。
「そう、黙って死ぬことはない。この街でな。リーズ、お前は若いんだからな」
バックの言葉の意味がとれずに、リーズは眉を顰めた。
「アバロンから来たっていう隊商がいただろう」
アバロンは大国ルビオナの首都であり、この大陸で最も繁栄している都市のひとつだ。
「その中に変わった男がいてな。俺達守備隊にわざわざ会いに来た、というんで話したんだ。俺より歳を食っていたが、そいつは、グランデレニア帝國の元兵士だが、今はとある組織の一員だって言うんだ」
バックの話し方は熱を帯びていた。
「なんでも、その組織は渦自体を攻撃、消滅させる部隊で、勇士を集めてるって話をし始めた。隊長はそんな話を一笑に付して追い返したんだが、俺は興味があって続きを聞いてみたんだ」
バックの言葉をリーズは黙って聞いていた。
「エンジニア達がわざわざ地上に降りてきて作った部隊らしい。それに、もう少しで渦を消滅させることができるところだって言うんだ。ただ、戦いに長けた人材を集めるのに苦労してるらしい。まあ、当たり前の話だがね。生きるためにぎりぎりの戦いをしてる奴らに、そんな雲をつかむような話に乗れっていうのが無理な話だ」
バックは一息ついて改めて言った。
「でもな、俺はそいつの話、信じられるような気がしたんだ。いや、信じたいって思ったのかもしれん」
また間を置いて、バックはリーズを見つめ直した。
「初めて水が引くかもしれない、ってね」
バックの話が見えてきた。
「リーズ。お前、行ってみないか」
「突拍子もない話だな」
リーズの心のざわめきは、別の感情を表し始めていた。
「ああ。でも、もし本当なら、この街を救うにはその方法しかないって思うんだ」
「でも、親父はなんて言うかな」
「悪いが、親父さんには俺が先に話した。俺と同じ考えだったよ。長い間一緒に戦ってきたんだ。今の状況が袋小路だって話はずっとしてたんだ」
リーズが迷っているように見えたのか、バックは続けた。
「お前には才覚がある、リーズ。特別なんだ。 お前はこの酒場にいる連中とは違うものを持ってる」
隊員達は皆、酔い、歌い、騒いでいる。緊張の裏返しの開放感に浸っていた。
「自分じゃわからないね」
「俺は運命だのなんだのは信じちゃいない。でもな、この巡り合わせには何かあるって、そう思ったんだ」
「で、行くならどうすればいいんだ」
バックの熱を帯びた調子とは対照的に、落ち着いてリーズは答えた。
「行く気になったのか?」
「決めちゃいない。でも、悪くない話だって思っただけさ」
「その男は、まだベルの宿屋にいる。お前ならきっと認めてもらえる。明日会いに行こう」
バックは破願すると、また酒をあおった。
「若くて経験もある。すばらしい人材だ」
組織の男はヘイゲンと名乗った。リーズを一目見て気に入った様子だった。
「さっそく本隊に向かってもらおう。連絡は先につけておく。心配せずに行ってくれ」
書面に何かを記入しながら、ヘイゲンは言った。
「次の西に向かう隊商とソースバーグまで行くんだ。そこの支部から本隊に送り出してもらえ」
ルビオナ王国銀行保証の小切手を一枚、直ぐに切った。続いてもう一枚、金額を記入した小切手を切った。
「これは経費とは別の契約金だ」
金の為に行くのではなかったが、断る理由も無いので、リーズはそれを受け取った。
かなりの金額だったが、特に興味は持たなかった。親父が受け取ってくれればがと、ぼんやり思った。
西に向かう隊商が出発するまで三日程あったが、リーズはまるで普段通りに暮らした。
父親には旅立つことを告げたが、深く問われることはなかった。
「隊長にはバックがうまく話をつけるってさ」
「ああ、俺からも言っておく」
母親を幼い頃に亡くしてから、二人きりで暮らしてきた。戦い方も生き方も、全て父親に教わってきた。
今の父親は、失った足をかばいながら鍛冶屋を手伝っている。食べるには困らないだろう。
守備隊の長だった父親はリーズの誇りだった。そしてその地位を失っていても、リーズにとってはずっと大切な父親だった。
会話は得意でない二人だったが、互いを理解していた。
旅立ちの日になった。
父親は小切手を受け取らないだろうと思って、黙って机の中に隠しておいた。いつか見つけてくれればいい。
玄関先で、荷物を持ったリーズを父親は見送った。まるで、ちょっとした旅に出るかのような、何気ない別れだった。
「行くよ」
「ああ、うまくやってこい」
「もちろん」
それだけ言葉を交わすと、隊商の待つ城門へと向かった。
二度と会えないだろうと思ったが、リーズは振り向かなかった。
「―了―」
3377年 「門」 

レジメント基地のメインゲートを抜けた後、リーズは検疫を受けるために装備を外し、コルベットから降りた。
「今回はよくやったな、リーズ。報告書、なるべく早くな」
降り際に小隊長のベルキンから声を掛けられる。
リーズがレジメントに来てから十ヶ月程が過ぎていた。作戦参加回数は、既に二十回に達しようとしていた。
コア攻略は今回を入れて三回目だった。そして、また帰ってくることができた。
リーズは検疫班が遺体を下ろしているのを眺めていた。死体袋からは血が滴り落ちている。袋に綻びがあるようで、千切れた腕が地面にころがり出た。マスクをしている検疫作業員はそれに気が付かない。リーズはその腕を拾い上げて死体袋の上に乗せた。死んだ仲間の腕は、思ったより軽く感じた。
その瞬間、リーズは自分が今回も生き残ったのだということを、実感として受け取った。あの質の悪い夢のような『渦』から戻ってこれたのだと。死と自分の距離が、今ここにいる限りは離れている、と。
「必死の思いでやっと帰ってこれたと思ったら、この仕打ちか。エンジニア共の潔癖には付き合いきれねえな」
装備を外しながらローレンスが声を掛けてきた。リーズより一年早くレジメントに参加した、荒野出身の二十台後半の男だ。
二人とも検疫施設に歩き始めた。このレジメントの基地には、もしものために備えられた障壁器の内側に、施設と切り離される形で検疫施設が設けられていた。寄生型の生物や疫病などのチェックをエンジニア達が行う施設だ。
「確かにな」
多くの隊員達はこの検疫作業を疎んじていた。元々荒野に住んでいた者、生活圏を脅かす異界の怪物との戦いを続けてきた者達は、そんなものを気にして生きてはこなかった。検疫の項目は多岐に渡るので、施設に戻るのに一日近くここに留め置かれることになる。施設からはマスクと防護服を装備したエンジニア達がぞろぞろと出てきて、コルベットの除染と装備の回収を行っている。隊員たちは対照的に、戦闘服を渡した後、下着だけになって除染室に向かった。
「ったく、びびりすぎだぜ。酒と柔らかいベッドをお預けにされてる俺らの身にもなれって話だぜ」
ローレンスのぼやきをリーズは聞き流した。
「どうした、さすがに疲れたか?」
まだ、あの腕の重さの感触が残っていた。
「ああ、そんなとこだ」
リーズはそう言って、シャワー室に足を進めた。
所属するE中隊で行う簡単な追悼式が、基地に帰投してから三日目に行われた。霊園と呼ばれる施設の一区画には、既にたくさんのモニュメントが並んでいる。新しい六つが、今回の作戦で追加されることになった。
連隊長であるスターリング、リーズの所属するE中隊の幹部と作戦に参加した隊員、エンジニアが式に参加していた。隊員の中には怪我を負っている者も多い。
霊園のモニュメントの前に、遺骨が収められた銀色の長方形の箱が並べられている。ただし、実際に火葬された遺骨が入っているのは、遺体を持ち帰ることのできた二箱だけだった。
日々の作戦、戦闘の中で犠牲は出続ける。昨日まで笑って話していた男が、今日にはこの世界からいなくなる。街中での戦いなどとは比べられない日々だ。
リーズは仲間を悼む演説を聴いていると、急にここにいるのが場違いな気がしてきた。渦の近くで死に物狂いに戦っている時が現実で、今いるここは、何か幻であるような気分になっていた。
式典が終わった時、中隊長のヴィットに声を掛けられた。
「リーズ、あとで司令室まで来てくれ」
司令室では、さっきの式典での礼服を着替えたスターリングが待っていた。隣には中隊長のヴィットが立っている。
「今回の作戦の戦闘詳報、読ませてもらった」
スターリングの手元には報告書がある。
「クラスCの適性生物を、一回の出撃で六体か。 驚異的だな」
クラスCは人間の二倍はあるサイズの怪物のことだ。
「一年足らずでこの成果だ。底知れんよ」
下から覗き込むような形で、スターリングはリーズを見ている。
「いえ、チームの協力があったからこそです。自分の手柄だとは思っていません」
リーズは本心からそう思っていた。別に特別なことは何も無いと。気負いも無かった。ただ、戦いの中にいる方が、より現実感があった。
「謙遜だな。新しく入った者が活躍するのはいいことだ」
「で、今日呼んだのは、ちょっとした依頼がエンジニア側からあってな。若い優秀な隊員をモニターしたいと言っている」
「モニターとは?」
「さあな。彼らが言うには、こうしてコア攻略の戦果が上がっている中で、より効率を上げるために優秀な人材を見極めたい、ということらしい。それを新兵の選抜やトレーニングに生かすということだ」
「リーズ、どうだ。協力してくれるか?」
「作戦に影響はありますか?」
「たいしたものではあるまい」
「問題ありません」
リーズは即答した。
「ではヴィット、悪いがリーズをエンジニアのモニタリング対象にする。うまく調整してやってくれ」
スターリングは机に目を戻し、別の仕事に戻った。リーズはヴィットと共に司令室を出た。
「どうした?気が向かないなら、無理をしなくてもいいぞ」
ヴィットはリーズの落ち着かない様子を気にしていた。
「別に、先程の話のことではありません」
「疲れてるのか?」
「いえ。次の作戦、いつですかね」
「お前らは帰ったばかりで、補充もこれからだ。しばらくは休め」
「基地にいても、何もすることがないのは苦手です」
「休むのも作戦の一部だ。次の戦いに備えてな。お前は若い。自分なりのやり方をみつけろ。トレーニングでも遊びでもな」
ヴィットは四十代のベテラン兵士だ。格闘教官をやっていたというその分厚い身体は、人を威圧する感覚を放っている。
「わかりました」
「今度トレーニング室に来い、みっちり鍛えてやるぞ」
「考えておきます」
そう言って、リーズと中隊長は別れた。
一週間程経った後、リーズはエンジニアに呼ばれて検査を受けていた。身体機能の記録を取るということで、様々な器具をつけてシミュレーションを行わされた。
トレーニング施設を一時的に封鎖し、エンジニアが選抜したメンバーが一〇名程集められていた。基準はわからないが、秀でたメンバーのようだった。中には同じE中隊のクラウス、同時期に入隊した、今はA中隊にいるマキシマスといった、よく見知った顔もいた。
「久しぶりだな、マキシマス」
「ああ」
訓練の途中でリーズは声を掛けた。同じ訓練期間の間、よくパートナーとなった男だった。帝國出身で端正な顔立ちで、他の隊員達とはかなり異なる男だった。中隊が別になってからは特に話す事もなかったが、そもそも互いの戦果などを語り合う間柄という訳ではない。だが射撃、剣といった戦闘技術の高さはよく知っていたので、このモニタリングプログラムに呼ばれたことに不思議は無かった。
「A中隊はどうだ?慣れたか」
「特に問題はない」
「相変わらずだな。その態度じゃ、小隊でも持て余されてるんじゃないのか?」
マキシマスは特に口数の少ない男だった。リーズも多くを語る方ではないが、マキシマスは必要最低限のことしか口をきかない男だ。ただ、同期で年齢も近く、態度は変わり者でも悪くは思っていなかった。また、マキシマスもリーズと一番会話を交わしていた。
次のプログラムの準備のために、エンジニアが訓練場の機械を設置し直している。
その時、小さな爆発音が訓練場に届いたかと思うと、警報が基地に流れた。
「緊急事態。検疫地区で事故。コード16。警備部担当班は西第二ゲート前に集まってください」
エンジニア達の顔がさっと変わり、何か話し合っている。
「なんだ、コード16ってのは?」
「防護服を着て退避しろ、という意味だ。エンジニアの符号だ」
マキシマスの解説が終わるより先に、リーズは立ち上がった
「今日の帰還予定はE中隊の第一と第二小隊の筈だ。俺はゲートに向かう」
リーズは何が起こったかを情報交換している隊員達を尻目に、検疫地区へのゲートへ向かった。
検疫地区は高く厚い塀で主要施設と区切られている。そして中央に巨大な鋼鉄製のゲートがある。基地の警備には、専門の兵士もいるが、非常時の対応は輪番で隊員達にも割り振られていた。
「リーズ、来たのか」
警備室の前にはE中隊の面々が集まっていた。小隊長のベルキンに声を掛けられた。
「ああ。状況は?中隊長達は?」
「わからん。帰還したコルベットに近付いた検疫官がやられたらしい」
「そして二機の内、一機が爆発を起こした」
同じE中隊のメンバーが横から解説を入れる。
ゲートの警備室のモニターには、二機のコルベットが映っていた。一機のハッチからは煙が出ている。
「よく見えないな。上にあがろう」
「ああ、行こう」
集まったベルキン達E中隊の隊員は、屏へと上がった。ゲートを含む屏は分厚く、上部にはライトや機銃が取り付けられている。既に警備担当の隊員が検疫地区の中に乗り込んでいる。
モニターでは状況がわからなかったが、何人かの検疫官がまだ生きているようだった。
「おい、あいつらを助けに行かないのか!?」
隊員から声が上がる。
「今から武装した警備隊が行く。もう少しだ」
警備担当の隊員が更新しながら答えた。すぐにゲートが開く音がして、警備隊がコルベットへ近付いていく。六人の武装した隊員だ。
その時、煙の出ていないコルベットのハッチが開き、人影が見えた。
次の瞬間、武装した隊員達が血飛沫を上げて倒れていった。残りの三人がゲートに逃げ戻ろうとしたところ、また同じように倒れた。
「何が起きたんだ!?」
隊員達に疑問の声が上がる
「あれはヴィット中隊長だぞ!」
燃えているコルベットの白煙の向こうに、ちらちらと人影が見えた。体格から、確かにヴィット中隊長のように見える。漂う白煙で把握しづらい状況に、隊員達は苛立っていた。
「俺が行く」
リーズはそう言って欄干に足を掛けると、屏を飛び降りた。屏の高さは三アルレ以上ある。皆が声を掛けるよりも早く、リーズは宙を舞った。
「なんて野郎だ……」
事も無げに地面に降り、低い姿勢のままコルベットに向かうリーズを見て、ベルキンは呟いた。
武装していなくても、警備兵がやられたのを見ても、リーズに躊躇は無かった。戦いがそこにある。倒すべきものが目の前にある。考えるより前に飛び込んでいた。
そして、リーズにだけ見えていたものがあった。コルベットから降りてきたヴィット中隊長は『一人』ではなかった。
そっと回り込むようにしてリーズはヴィット中隊長に近付く。途中で倒れた警備兵からセプターを取った。セプターはレジメントの標準装備である伸縮式の長剣だ。
煙に紛れるようにして近付いたリーズだったが、その煙が風で飛ばされ、視界が開けた。
次の瞬間、衝撃がリーズを襲った。警備兵を倒した、あの見えない衝撃だ。
「くっ」
しかしリーズはその衝撃で倒れることはなかった。セプターによってその攻撃を受け流していた。
そして開けた視界で、ヴィット中隊長の姿をしっかりと確認した。
リーズの目に映ったヴィット中隊長の姿は、人外のものであった。背から透明な長い触手が後光のように蠢き、背景を歪めている。ヴィット中隊長の顔は灰色になっており、目は黄色く、焦点も定まっていない。
「取り憑かれちまったのか……」
そう呟くと、剣先を中段に構えて次の攻撃に備えた。
透明に見える触手を確認するには、微妙な屈折だけが頼りだ。普通の人間には、遠くからでは何が起きているのか全くわからない。
攻撃を躱し続けるリーズに、ヴィット中隊長はにじり寄っていった。その間もリーズは勝機を伺っていた。ヴィット中隊長はまだ生きている。知覚や行動は乗っ取られているとしても、確かに歩き、生きている。リーズは彼を救う方法を思案していた。
にじり寄られながらも、リーズは距離を保ちつつ位置を変えていった。
そして、燃えているコルベットの裏に走り込んだ。裏に隠れるように回り込むと、今度はコルベットの縁に手を掛け、上に飛び乗った。流線型のコルベットの上部ではあったが、バランスを崩すことなく軽々と立った。
間髪を入れず、ヴィット中隊長の真後ろへと跳躍した。そして着地と同時に、真横に一閃の一撃を加えた。
透明な瘤として隊長の背中に取り憑いていたその『もの』は二つに裂け、地面に落ちた。すると、まるで糸の切れた操り人形の様に、ヴィット中隊長は地面に倒れた。
リーズはヴィット中隊長の息がまだある事を確認した後、帰還したコルベットの中を確認した。
一機はヴィット中隊長が乗っていた第一小隊のものだ。中に動く者はいなかった。
もう一機の、煙を出したコルベットの中も確認する。中は銃痕と血糊、千切れ撒き散らされた身体の一部の所為で、まるで何かの生き物の臓腑の様相であった。
おそらく、あの『もの』が、生き残った隊員達と争ったのだろう。
奥を確認するためにハッチへ頭を入れようとしたその瞬間、『もの』がリーズの首を目掛けて飛んできた。
しかし、リーズはその攻撃を潜るように躱すと、剣の一閃で斬り伏せた。
生きているものの気配は、それで全て消え失せた。
煙を出し続けるコルベットから離れるために、リーズはヴィット中隊長を背負ってゲートに向かった。
少しすると、同じE中隊の仲間がこちらに向かって走ってくるのが見えた。
「─了─」
3378年 「異界との繋がり」 

レジメントの施設から北に500リーグ程の場所にあるモルグ渓谷。この一帯を覆う大規模な《渦》攻略作戦のブリーフィングに、リーズは参加していた。
施設の中でも一際大きい作戦会議室にはA中隊とE中隊の全隊員が一同に集まっており、作戦の規模の大きさが測れた。
その中でも、リーズのいるE1小隊とマキシマスのいるA2小隊は、コア制圧の中心部隊を任されていた。
ブリーフィングが終了して各自が次の予定行動へと向かう中、リーズは数ヶ月前にE中隊長になったベルキンに呼び止められた。
「リーズ、今度の作戦も頼りにしているからな」
「自分の仕事をやるだけさ」
自分の力を過信するつもりはないが、こうやって持ち上げられることに悪い気はしなかった。
何より、自信たっぷりに答えることが隊の士気維持に繋がることを、リーズは理解していた。
「リーズ、敵性生物がコアを取り囲んだ!急ぐぞ!」
ローレンスから怒号が飛ぶ、リーズはコア周辺を守る敵性生物の一体を真っ二つに切り裂き、他の隊員達に続いた。
コアは敵性生物の集落らしき場所の中央に掲げられており、その周辺を黒い霧のようなものに包まれた大型の敵性生物が、何体も見張るようにして守っていた。
「……あ、ああ!」
リーズは少し間をあけてローレンスに返事を返す。渦中央部への突入直後から断続的に襲ってくる頭痛が、リーズを悩ませていた。
渦へ突入するときの環境変化でこういう症状に陥ることはままあったが、休息を挟み、薬を飲んでなお症状が続くということは初めてだった。
今はコア攻略の真っ最中だ。不安要素は排除しておきたかったが、そう簡単にはいかないようであった。
「大丈夫か!?」
「問題ない、行くぞ」
「こちらグレン!ハリスンがやられました!」
「くそっ、遺体は回収できそうか!」
「できるものならやっています!!」
各所から隊員の安否や状況を確認する声が聞こえてくる。リーズも時々それに答えながら敵性生物を屠り、コアに近付いていく。
A2小隊も別の進路から合流し、コア周辺の敵性生物を減らしつつあった。
「コアはどうなっている!」
「最初に確認された場所から動いていません!」
「一気に突破して確保するぞ!続け!」
各小隊長から指示が飛ぶ。リーズは最前線で敵性生物と対峙した。この群れを突破すればコアは目の前であった。
リーズはライフルで敵性生物の動きを鈍らせると、セプターを構えて切り込んでいく。頭痛は散発的にくるものの、この程度なら何とかなるだろうと予想ができた。
リーズが倒した敵性生物の屍を乗り越えて、E1小隊の半数とマキシマスらA2小隊がコアの周囲を確保した。
「調子が悪いのなら下がっていろ」
「大したことは無い。余計な心配だ」
「そうか」
いつもと違うリーズの様子に気付いたのか、マキシマスが珍しく声を掛けてきた。この激戦の中にあってなお、彼は落ち着いて作戦を遂行していた。
リーズはコアに近づく敵性生物をライフルで掃討する。
頭痛は治まってきたが、今度は視界に歪みが生じてきた。敵性生物とオペレーターの区別が付き易いのは幸いだったが、危険であることに変わりはない。
コア周囲の敵性生物とは完全に立場が逆転していた。先程までコアを守る側だった敵性生物は、今度はコアを取り返そうとリーズ達に近付いてくる。
これらを掃討すれば、あとは20アルレ上空に待機するアーセナルキャリアがコアを確保するだけだった。
しかし敵性生物も必死だった。幾人かのオペレーターが敵性生物により負傷、あるいは殺された。敵性生物の猛攻により、リーズ達は徐々に防戦一方となっていく。
「前に出る!コアに奴らを近付けさせるなよ!」
リーズはコアからほんの少し距離を取ると、群がる敵性生物を相手取った。コアから離れると、視界の歪みは少し減った。
「これなら!」
近寄る敵性生物を片っ端から打ち抜き、切り伏せた。
リーズは完全に敵の動きを見切っていた。敵の動きが遅くなっていくような感覚があり、敵の攻撃を先読みできるようになっていく。
同時に、視界の歪みは世界を二重に映していた。ずれて映る世界では、敵性生物が放った炎の矢が全てを燃やし、その世界にあるリーズの腕や剣を燃やしていた。
「くそっ!」
リーズは立て続けに起きる不調に苛立ちを隠せなくなっていた。二重に映る世界は、この極限状態では酷く邪魔なものであった。
眼前の敵に集中すれば、却火の世界に囚われずに対峙できたが、煩わしいことに変わりはないのだ。
「しまった!」
そして、その苛立ちが隙を生んだ。背後から襲い掛かる一際大きな敵性生物に対応しきれなかった。
すんでのところで気が付きセプターで応戦するものの、肩に強い衝撃が伝わった。リーズの肩から炎が噴き出す。敵性生物の持つ、炎を纏った武器による着火だった。
二重に着込んだ防護ベストにより熱は感じないが、体中に燃え移るのも時間の問題であろう。そしてそれは先程、ずれた世界で見えた自分の状況と同じであった。
「こんなところで!」
まだやることがある筈だ、こんなところで死ぬ気はリーズには無かった。
死に場所くらいは自分で選ぶ、ここは死ぬべき場所ではない。
そう思いながら炎に包まれた防護ベストを脱ぐと、それを敵性生物に投げ付けた。
投げ付けられたベストに敵性生物が怯んだ隙に、その懐に飛び込んだ。その時、二重に見えていた世界と眼前の視界が重なり合った。
リーズの視界がクリアになる。それと同時にセプターから炎が噴出した。セプターを最大まで伸ばすと、炎を纏ったその剣先で敵性生物の首を刎ねた。
周辺の敵性生物が動揺したのがわかった。治まることのない炎を見て、リーズは笑みを浮かべる。
原理は不明だが、この力はここで使うべきものだ。本能がそう告げていた。
「全部、燃やし尽くしてやる」
リーズはセプターに纏った炎を操り、敵性生物を次々と倒していった。
コアを無事に確保した中隊がモルグ渓谷から帰還すると、リーズ達生き残った面々は、検疫作業と併せて身体の精密検査をすることとなった。
リーズが使用した不思議めいた炎の力がエンジニア達の耳に入り、詳細な検査を求められたためだった。
「ただでさえ疲れてるのに、そりゃないぜ。なぁ、リーズ」
「そうだな」
除染室に向かう傍ら、ローレンスにやや力なくリーズは答える。
頭痛や視界の歪みは渦から脱出した直後に綺麗に無くなっていたが、施設に帰還してから気が抜けたのか、全身が疲労感に襲われていた。
「それにしても凄かったな。ありゃなんだ? 新しいセプターでもエンジニアに融通してもらったのか? モニタリングとやらに参加すればいいのか?」
嬉々としてあの力のことを聞き出そうとするローレンスが、今ばかりは少々煩わしかった。
「いや、特別なものは何もない」
「本当かぁ?」
どこまでも疑ってくるローレンスに辟易するも、すぐに除染と検査が始まり、会話どころではなくなった。
精密検査が終わり、やっと自室に戻れた数日後、リーズはエンジニア達の研究施設に呼び出された。
病院の診察室のような場所にいたのは、フォレットと名乗るエンジニアだった。ケイオシウムの専門家であるという。
「君の身体に重大な問題が見つかった
重大という割に各フォレットの言葉から緊張や深刻さは感じられなかった。
リーズはいくつかの数値が書かれた、同じような二枚の紙を見せられた。
「これは?」
「君とマキシマスの身体検査の結果だ。年齢や身体能力を加味し、総合的に君と最も近い数値が出るのか彼だ」
そう言われて検査結果を見比べる。専門的な単語が多く、半分程しか理解できなかったが、ある一点がマキシマスよりも高い数値で書かれているのを見つけた。
「他のオペレーターに比べ、君のケイオシウム汚染濃度が高いことが判明した」
「ケイオシウム汚染ですか?」
「そうだ。脳の、特に頭頂葉と後頭葉に汚染の影響が見られる。問診で君が回答した視界の歪み、別の世界が見えたことは、このことが原因だと想定される」
「なぜ俺だけ汚染濃度が高いのですか? それと、歪みとの関係は?」
「渦を構成するコアはケイオシウムエネルギーの塊だ。コア周辺にいる時間が長い程、高濃度のケイオシウムに曝されることになる。心当たりは?」
リーズはここ半年で参加した作戦を思い出す。
作戦参加回数は以前と変わらぬものの、コア制圧部隊の中心人物として据えられ、幾度となく成功させてきていた。
「コア攻略作戦への参加回数が増えています」
「断定はできないが、要因として考えられるのはそこだろう。詳細を解明するには更に詳しい検査が必要だ」
「何か悪い影響がある、ということですか?」
「周囲へ汚染を拡大させたり、君の健康を脅かしたりするものではない。だが、すでに君には別の世界が見えるといった影響が出ている」
「作戦行動に支障が出た場合の対策はありますか?」
「これは初めてのケースだ。対策はこれからする。君はこれから定期的に検査を受け、場合によっては検証作業にも参加してもらう」
「長い間拘束されると」
「次の汚染被害を防ぐためにも必要なことだ」
どうやらエンジニアにとって、自分達レジメントの隊員は実験動物と同じようなものらしい。
エンジニアに身体を弄くられるくらいなら、渦の中で戦っていた方が遥かにマシだ。
リーズはそう思いながら、研究施設を後にした。
「―了―」
3380年 「聖騎士」 
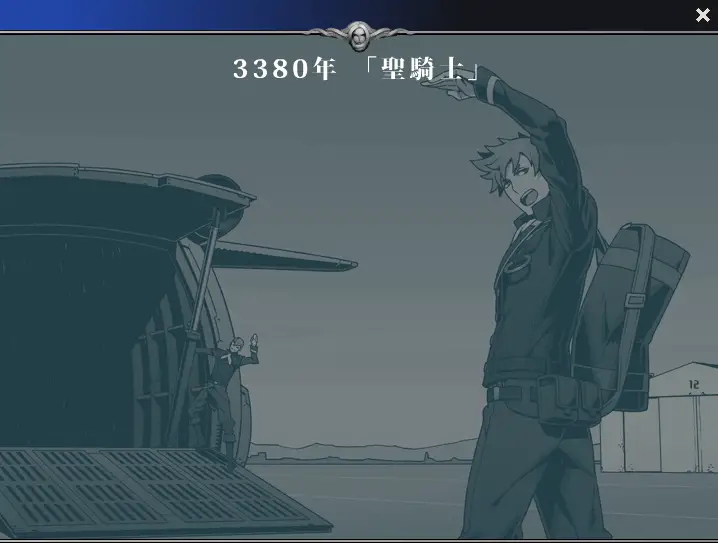
身体のあちこちに電極のようなものが取り付けられていた。
身じろぎもできない状態のまま何かの数値を計測されている間は、とても暇だった。欠伸や眠気と戦いながら、じっと時間が過ぎるのをリーズは待っていた。
「よし、もういいぞ」
連隊司令部直々の命令ということもあり、渋々といった思いながらも検査を受け続けているが、この検査に時間を取られることはとても煩わしかった。
「リーズ、お疲れー!」
検査を終えて特殊訓練施設に戻ると、ディノが手を振って出迎えた。
周囲を見ると、他の面々は訓練用セプターによる一対一の模擬戦を行っていた。
「元気だな、ディノ」
「模擬戦の相手にあぶれちまってよ、お前が来るまで待機だって言われてなー」
「はは、俺はお前以外がよかったよ」
口を尖らせるディノを冗談であしらうと、用意されていた訓練用セプターを手に取る。
ディノはリーズと同期に入隊したストームライダー出身の隊員で、共にモニタリングに参加している。
「よっしゃー、どっからでもこーい!」
待たされていた鬱憤からか、張り切って訓練用セプターを振り回すディノ。それを見て、リーズは思わず苦笑する。
「セプターがすっぽ抜けても知らんぞ」
幾度も訓練を重ねたにも関わらず、ディノの構えはなっていなかった。それに訓練用とはいえ、セプターを大振りに振り回すのは危険極まりない。
模擬戦が始まってすぐ、ディノは大上段に構えた格好そのままに斬り掛かってきた。
あまりにも読みやすい行動に一瞬呆気に取られたが、冷静に大振りの一撃をいなし、足払いを掛けてディノのバランスを崩す。そのままディノは尻餅をついた。あっけない模擬戦だった。
正直なところ、ディノは誰の目から見ても『弱い』部類に入る戦士であった。訓練であぶれた理由も、リーズには察しが付いていた。
だが、ディノは入隊して間もなく参加した渦攻略作戦において、小隊が壊滅状態に陥りながらも、コアを回収して帰還した実績があった。
モニタリングへの参加は、その驚異的な生還が認められた結果といえる。エンジニアはディノの強靭な肉体に注目したとの話を耳にしていた。
「くっそー」
「……交代しよう」
尻餅をついたディノの後ろからイデリハがやって来た。一緒に模擬戦をしていたらしいローレンスの姿も見える。
イデリハもリーズと同期の隊員だ。A中隊のマキシマスに負けず劣らず口数が少ないため、出身が東方であるというくらいしか知らなかった。
「ええー、せっかくリーズと戦えるチャンスだってのに」
「この後モニタリングがあ……るだろう?」
「リーズの全力はそっちで見られるんだから、模擬戦は俺とやろうぜ」
「ああそっか。その時でもいいんだもんな。よし、リーズ、勝負はおあずけだぜ!」
「あ、あぁ」
勝負も何もと思ったが、言葉を濁すことでリーズはごまかした。
リーズの能力が解明されていくにつれて、エンジニアが課すモニタリングプログラムも様相を変えていった。
若年の者ほどケイオシウム汚染の影響を受けやすく、能力が発現しやすい傾向にあることも判明した。追加入隊した隊員においては、十代から二十代前半の若者はモニタリングへの参加を義務付けられるようになっていた。
モニタリングでは様々な機器を身に着けたシミュレーションの他、渦内での戦闘を想定した実戦訓練などが行われている。これは、極度の緊張状態に身を置くことによって個人の生存本能や闘争本能を刺激し、リーズのような特殊な力を開眼しやすくするためのものであった。
「リーズ、撃て」
「了解」
訓練場に作られた障害物の影から、リーズは合図と共にアーチボルトに向けて閃光弾を撃つ。敵性生物が放つ火球を想定したこの弾には、着弾すると小さな爆発が起きるよう、特殊な火薬が込められていた。
アーチボルトに向けて放たれた閃光弾は、発射されて間もなく空中で爆発四散した。
その向こうには、エンジニアから支給されたハンドガンタイプの銃を構えたアーチボルトの姿があった。
「命中率99.8%。驚異的だな」
「やはり、これも聖騎士の力か」
隣で計測を行っているエンジニア達が淡々と言う。
リーズが持つ異界から炎を呼び寄せる能力や、アーチボルトの奇跡とも言える射撃能力を、エンジニア達は『聖騎士の力』と呼称するようになっていた。
この単語を聞く度に、リーズは背中がむず痒くなるような感覚に襲われた。
世界を救うという大義名分はあるものの、血と土埃と汗に塗れた自分達の姿を『聖騎士』と評するなど、何かの悪い冗談であろうと思っていた。
射撃シミュレーションが終了すると、今度は近接戦闘のモニタリングが始まる。
リーズはベルンハルトとフリードリヒの二人を一度に相手取っている。
額に電極のような計器を貼り付けての戦闘は滑稽なものに見えたが、これでケイオシウム汚染がどのように聖騎士の力に影響するのかを計測すると聞いていた。
幾度も繰り返される擬似戦闘。計測データは積み重なり、次第に信頼の置けるものになっていく。
解析が進む中、リーズも自分の能力を適切に制御する方法を身に付けていった。
ある時、施設の大ホールにレジメント全ての隊員が集められた。
スターリングを初めとする司令部の緊張した雰囲気に、隊員達は何が起きるのかと身構えていた。
「諸君、忙しい中、集まってもらってありがとう」
スターリングの挨拶もそこそこに、エンジニアが登壇して正面のモニターにジ・アイと思しき渦の映像を映し出した。
「度重なる調査の結果、近々ジ・アイの活動が低下することが判明した」
モニターに次々と映し出されるジ・アイの様子に、隊員達はざわつく。
エンジニアは早口で、ジ・アイの活動低下期間が間もなく訪れること、この期間であれば現在のレジメントの装備でも突入が可能であること、などを説明した。
そして、ジ・アイが消滅すれば全ての渦が消滅するということも。
「よって、E中隊を再編し、これを中心としたジ・アイ攻略作戦を実施する」
隊員達は騒然となった。
「各員の所属先は追って説明する。以上だ、解散」
それからは慌しい日々が続いた。ジ・アイ攻略に関するミーティングが何度も行われ、平行してE中隊が再編された。
再編されたE中隊は、モニタリングプログラムに参加していた隊員の中でも特に熟練した面々によって構成された。A中隊のエースともいえる立場にあったマキシマスや、D中隊で長く小隊長を務めていたダニエルなどが加わり、E中隊の戦力は大幅に増強された。
「ちっ、俺らだけで十分だってのに」
「司令部もわかってねぇよな」
マキシマスやダニエルなど、ジ・アイ攻略の要となるべく新たに配属された隊員は、元々のE中隊隊員達から敬遠されていた。
同じE中隊内で争いを起こすような真似こそ無かったが、数値といった形で優劣の差を見せつけられることは、正直のところいい気はしない。
「そう言うな。俺達は司令部から信頼されてる。だからこそジ・アイの攻略を任されたんだ」
「しかしなあ、リーズ」
「俺達は選ばれたんだ、何も気負うことはないさ」
リーズはこういうとき、努めて明るめの調子で会話をするようにしていた。チーム内での確執は、必ず大事故に繋がることを理解していた。
そして、その調整役ができるのは自分だけであるということも自覚していた。
「うーん、リーズがそう言うのなら、そうなのかもな」
「そうそう。俺様達でぱぱっとジ・アイのコアを回収すればいいだけなんだぜ、簡単簡単」
補足なのかフォローなのか、ディノも会話に混じってくる。
「お前が言うと、できるものもできそうにないんだよ!」
「ひっでぇなぁ」
いつの間にか、不機嫌な顔をしていた隊員達の表情が、少しだけ和らいでいた。
ジ・アイ攻略作戦の実施が迫っていた頃、新規開発された武器の実地試験のため、E4小隊が別の渦攻略作戦に参加した。試験とはいえ渦の攻略である、死傷も当然ながら起こり得る。
「救護班、急げ!」
「イデリハ!ロブ!くそ、大丈夫か!」
「すま……ない……」
E4小隊が乗っていたコルベットが煙を上げて不時着していた。渦から脱出した直後に結節点《ノード》で待ち構えていた敵性生物の攻撃を受けたのだ。
コルベットに乗っていた隊員達は酷く負傷しており、すぐに医療棟へと運ばれていった。
イデリハを含め重傷者が多数出たE4小隊は、ジ・アイ攻略に向けて人員を総入れ替えせざるを得なくなった。
コルベットの前にE中隊の面々が集まっていた。ジ・アイへ向けて出発する時刻が迫っている。
イデリハ達E4小隊に所属していた隊員達の復帰は叶わなかった。
しかし、この時期を逃せばジ・アイは再び活性期に入る。そうなれば次に突入できるチャンスがいつ来るのかは不明であった。
「これで、俺達の戦いも終わるんだな」
普段はディノと軽口を叩き合うようなローレンスも、眉間に皺を寄せている。
ディノに至っては極度に緊張しているらしく、いつものお調子者ぶりはどこへやら。E2小隊の面々と真剣に最終確認を行っていた。
「全力を尽くすだけだ」
「お互い生きて帰ろうぜ。イデリハ達E4の連中のためにも」
「ああ、そうだな……」
「頼りにしてるぞ、リーズ」
ローレンスの言葉に、リーズは静かに領いた。
ふと、マキシマスを見る。マキシマスはいつもと変わらぬ様子に見えた。
リーズにはそれが頼もしくもあったが、同時に、薄気味悪いものを感じていた。
視界を覆い尽くす程の巨大な渦がコルベットの窓から見える。
淡い虹色に輝きながら回転するそれこそが、地上に《渦》を蔓延らせた元凶、『ジ・アイ』であった。
ジ・アイが近付くにつれ、リーズを昂揚と恐怖がない交ぜになったような感覚が支配する。
人類の存亡が掛かった長い戦いがこれで終わる。いや、自分達が終わらせるのだ。その端緒にいることを思えば、恐怖なんていくらでも見て見ぬ振りができる。
リーズは思考の全てをそれで埋め尽くす。
「やってやる」
聖騎士の力を発現したオペレーターに支給される特別なセプター。リーズはそれをじっと見つめると、力強く握り締めた。
「―了―」
3381年 「強き者」 
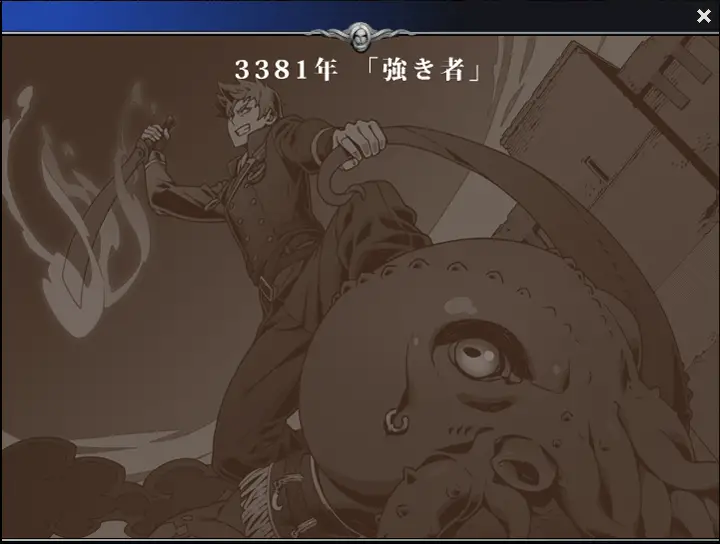
飛竜が崩れ落ちていく。激戦でぼろぼろになった隊員達から歓声が上がる。
「コア回収装置、起動します!」
エンジニアがアーセナルキャリアに搭載されているコア回収装置を作動させた。
「E1小隊とE2小隊は竜人の殲滅!残りはアーセナルキャリアを守れ!」
生き残った竜人達がコアに殺到してくるのを、リーズとディノの小隊が阻む。コア確保時の激戦により、二つの小隊を合わせても一個小隊程度の隊員しか残っていなかった。
コアの回収が始まった。これであと数分もしないうちに退路確保の指示が出る。それを励みにリーズ達は死に物狂いで竜人達を屠っていく。
だが、いつまでたっても指示が聞こえてこない。リーズはディノの援護を受けながら、増える一方の竜人を焼き払い続けた。
「くそっ、まだか!コアはどうなってる!」
「もう持ち堪えられんぞ!」
隊員達の必死な声が戦場を飛び交う。コアの様子を伺おうにも、竜人が多すぎて確認すら覚束ない。
「なぜだ、なぜコアが回収できないんだ!」
想定外の事態に、ベルキンがエンジニアに詰め寄る声がする。
「回収機構が働かないのです。こんな筈はないんだが。自己修復するなんて……」
怒りと焦燥が入り交じる異様な雰囲気に包まれる中、巨大な爆炎と共に再び飛竜が翼を広げた。
「馬鹿な!飛竜が復活したのか!」
復活した飛竜がアーセナルキャリアに迫る。コアを奪還しようと襲い来る竜人の数が多すぎて、リーズはベルキン達の援護に向かうことができない。それどころか、E1小隊とE2小隊は リーズとディノが辛うじて生き残っているだけだった。
「アーセナルキャリアを放棄しろ!」
「できるわけがない!」
大きな衝撃音と爆風を轟かせながら飛翔していく飛竜の姿がリーズ達の目に映る。その鋭い鉤爪には、アーセナルキャリアが引っ掛かるようにぶら下がっていた。
もはやコアの回収が不可能なのは一目瞭然だった。
作戦は失敗。それどころか生還することさえ難しい状況である。
「くそっ、撤退だ!コルベットへ撤収するぞ!」
誰かの声がした。ベルキンの声のようにも聞こえたため、リーズとディノは領き合うと手榴弾を同時に投げた。爆音が上がる。竜人達がそれに怯んだ隙に、リーズとディノはコルベットに向かって駆け出した。
追い縋る竜人達を振り切ってコルベットに辿り着く。守備隊は壊滅していたが、奇跡的に二機のコルベットが残っていた。
コルベットの周囲には竜人も味方もいない。ダニエルが竜人と相打ちになって絶命しているのを確認した。
「おい、リーズ!マキシマスだ!」
ディノが片方のコルベット内部で気絶しているマキシマスを発見した。頭部を負傷しており、早く治療を施さねば危険な状態であることが伺えた。
「発進させよう、急げ!」
ディノがコルベットを発進させる。コルベットが地面から離れたその時だった。必死にコルベットのところまでやって来たローレンスが竜人に囲まれているのが見えた。
「ディノ、マキシマスを頼む」
「は?リーズ、おい待て!どこ行く気だ!」
「ローレンスを助ける。コルベットはもう一つ残ってるし、何とかなるさ」
リーズはそれだけを言うとコルベットから飛び降りた。生き残りがいるのなら助けなければという思いがあった。
まだコルベットは一機残っている。ならばローレンスを助け、彼と共に帰還することができるだろう。遠ざかるエンジン音を背に、リーズはローレンスのいる場所へと駆け出した。
周囲の竜人を炎で焼き払う。ローレンスは竜人の攻撃を受けていたが、どうにか自力で行動できる様子だった。
「この馬鹿野郎!どうして戻ってきた!」
「コルベットはもう一機残ってる。生きて帰るぞ!」
罵声を浴びせてくるローレンスを一喝すると、リーズはローレンスを連れて残ったコルベットへ向かう。
だが、そこへ凄まじい咆哮と共に飛竜が飛来してきた。ローレンスは飛竜の鉤爪の餌食となって虚空に放り投げられ、竜人の集団の中へと落ちていった。
「ローレンス!くそっ!」
リーズは壊れかけたセプターを手に飛竜と対峙する。飛竜の口が開く。リーズは反射的にセプターを介して炎を呼び出し、飛竜に向かって斬り掛かっていった。
飛竜の業火とリーズの劫火がぶつかる。双方の炎がうねりを上げながら周囲を焼いていく。
全身が炎に焼かれ、酷い痛みに襲われた。それがリーズの最後の感覚だった。
適度に弾力があり、不思議な感触のするベッドのような場所にリーズは寝かされていた。
生きている。目覚めたリーズが初めに感じたのはそれだった。
ローレンスが殺され、飛竜と再び戦闘に入ったところまでは覚えていた。しかし、そこから先の記憶が不確かだった。
飛竜はどうなったのか。ディノ達は助かったのか。そんなことが頭を巡る。
「目が覚めたか。私の言葉がわかるか?」
声が聞こえた。
そちらの方に顔を向けると、リーズと同じか少し下くらいの年齢の、小柄な女性が立っていた。
「あ、あぁ……」
とにかく状況を把握しなければと起き上がろうとしたが、全身に痛みが走る。
「ああ、まだ動けるような状態じゃないぞ。ちょっと待っててくれ」
女性は手早くリーズを寝かせると、足早に誰かを呼びに出て行った。
間もなくして、全身が甲虫のような甲殻に覆われている生物が二体、部屋の中に入ってきた。
二足歩行をしているものの、どう見ても人間とは思えなかった。しかし、彼等が自分を襲ってくるような気配は無い。
彼等は目覚めたリーズを見ると、ギシギシと甲殻を鳴らして何かのやり取りをしている様子だったが、ややあってリーズに向き直る。
「目が覚めたか。強き者よ」
やや言葉に詰まりがあるものの、リーズが理解できる言語で彼等は喋りだした。
「俺は、一体……」
「大きな火傷を負って我らの国に落ちてきた。この国は異世界からよく物が落ちてくる」
自分の身体を見てみると、動かした箇所から痛みが走る。全身の様子はよく確認できないが、怪我をしていることは本当のようだ。
「しばらくは傷を治すのに専念するといい」
甲殻の者はそれだけを言うと、立ち去っていった。
「彼等は私達の言葉に不慣れなんだ。私が代わりに説明するよ」
そう言って、女性はルディアという名前を名乗ると、自分達が置かれている状況を説明し始めた。
――ルディアはリーズと同じように《渦》からこの世界へ漂着し、この世界の住民である甲殻の者達に助けられたこと。
――言葉が通じることから、おそらくリーズとルディアは同じ世界の住民であること。
――この世界には異世界からの物がよく漂着するが、生きた生物がやって来ることはとても珍しいこと。
――そんな奇跡のような存在である自分達を『異世界からやってきた強き者』と呼び、救世主のような扱いをしているということ。
――そして、彼等の国は争いによって疲弊しており、それを救うのが自分達であると言われていること。
「急にこんなことを言われても困るよな」
「そう、だな……」
苦笑するルディアに、リーズは歯切れの悪い言葉を返した。
夢の中にいるような感覚なのは否めない。その所為か、ディノ達は助かったのか。これが現実だったとしても元の世界に戻ることができるのか。どうして生き残ってしまったのか。そんなことを考えていた。
「怪我を治すついでに、これからどうしたいかを考えてもいいと思う。私もここで世話になりながら、元の世界に戻る方法を探しているんだ」
ルディアはそう言うと部屋を出て行った。リーズが考えを纏めるのに配慮してくれたようにも見えた。
リーズは怪我を治す傍らでルディアと情報を共有し、元の世界に帰る方法を模索していくことにした。
同年代の女性と話すのは本当に久しぶりだったが、同じ世界から来たということが確認できたおかげか、信頼関係ができるまでにそう時間は掛からなかった。
この世界の医療技術は元の世界よりも発達しているらしく、自身が思うよりも早く怪我が治っていった。動けるようになると少しずつ連隊式の訓練を再開し、腕の立つ剣士でもあったルディアに相手をしてもらうことで、鈍った身体の状態を徐々に戻していった。
この世界を救う者とは言われていたが、甲殻の者達はリーズとルディアをできるだけ争いから遠ざけようとしていた。
「大事な役目がある者を、おいそれと前線に出すわけにはいかない」
甲殻の者達はそれを繰り返すだけだった。だがある時、ついに国を守る壁が襲撃を受けてしまう事態が発生した。
今度ばかりは手助けして欲しい。甲殻の者達は懇願してきた。急かす彼等に促されて建物の外に出る。外には戦車のようなものが待機していた。
「もう一人の強き者は先に行っている。強き者よ、早く」
戦車らしきものに乗せられる。前窓から赤い空と、彼等の国を守っているらしい壁が煙を上げているのが見えた。
彼等の国を守る壁に到着すると、甲殻の者達が蛸や烏賊を思わせる触手を持った二足歩行の海洋生物に襲われていた。
リーズの背丈より二回り程大きな海洋生物は、ハンマー状の武器を用いて甲殻の者達を攻撃している。甲殻の者達も氷玉状のものを発射する兵器で応戦していたが、応戦し切れていない様子だった。
海洋生物の一方的な蹂躙かと思えたが、抵抗する甲殻の者達の中にルディアがおり、彼女が敵に一歩も引けを取らない戦いをしているのが目に入る。
「あれか」
「どうか救いを」
甲殻の者の手には剣があった。
「これは?」
「強き者に捧げるために作られた剣。もう一人の強き者も同じ物を持っている」
一瞬だけ、彼等に加勢してよいものかと逡巡した。だが、異世界で野垂れ死んでいただろう自分を救ってくれたのは、確かに彼等なのだと考える。
リーズは甲殻の者から剣を受け取ると、感触を確かめるように一振りした。同時に、セプターと同じように炎が刀身を覆う。初めて握ったとは思えない程、この剣はリーズの手に馴染んだ。加えて、セプターと同じように炎を扱えるのはリーズにとって幸いだった。
「おお、強き者よ……」
「助けてもらった恩は返さないとな。そうしないと気が済まないだけだ」
リーズは感激に甲殻を震わせているらしい甲殻の者を一瞥すると、海洋生物に向かって突進していった。
「加勢する!」
「来てくれたか!」
「まずはこいつらを片付けるぞ」
「わかった」
リーズが戦線に加わると状況は一変した。海洋生物は炎に弱く、リーズの炎に為す術もなく焼き殺されていった。
目の前の敵を片っ端から倒していくと、一際大型で身に付けている装飾品も豪奢な海洋生物が現れた。
巨大な海洋生物の唸り声に、前線でリーズ達と共に戦っていた甲殻の者達が怯えたように後退る。
「どうやら親玉のお出ましらしいな」
ルディアは剣を一振りして海洋生物の体液を払い落とす。
「あれを倒せばいいんだな?」
巨大な海洋生物は大きさに比例して動きが緩慢だった。だが、その分一撃の破壊力が凄まじいであろうことは容易に想像される。
「私が囮になる。その隙にあなたの炎を叩き込んでくれ」
「わかった。無理はするなよ」
ルディアの身体を黒い靄のようなものが包むと、一瞬にして海洋生物の眼前に移動して斬り掛かり、即座に離脱する。それを何度も繰り返した。
巨大な海洋生物は目の前をうろつくルディアを追う。その隙にリーズは海洋生物の背後に回り込むと、炎を纏わせた剣を海洋生物の頭部らしき箇所に突き刺した。
決着は一瞬だった。配下の海洋生物と同じように、巨大な海洋生物は炎に包まれて燃えていった。暫く藻掻いていたが、身に付けていた装飾品と骨のような残骸だけがそこに残った。
その様子を見た配下の海洋生物は、蜘蛛の子を散らすように逃げていった。
戦闘が終わり、リーズとルディアは英雄の如き歓待を受けた。
「海洋の王を滅したことで、長い戦いがついに終わりを迎えた。強き者達よ、我らの世界を救ってくれたことに感謝する」
そう言いながら、甲殻の者の長は丁寧に装飾された箱を持ち出した。箱の中には七色に淡く輝く宝石のようなものが鎮座している。
「これは世界を渡る宝珠。これをあなた方に献上する。この宝珠は闇に反応しやすいため、平和でなければ使えない。救世主が世界を救うまで封印しておく必要があった」
リーズとルディアは顔を見合わせた。長の『世界を渡る』という言葉が確かなら、これを使えば元の世界に帰還できるということだ。
歓待が終わった翌日、リーズとルディアは宝珠を使うことを決めた。元の世界へ戻りたい気持ちは同じであった。
旅の支度を整えた二人は祭壇で宝珠を掲げる。宝珠は《渦》のような紋様を虚空に生み出した。
「元の世界を強く思い描くのだ」
長の言葉通り、リーズは連隊の仲間達のことを思い浮かべた。ディノとマキシマスは生きて帰れただろうか、イデリハは怪我が治っただろうか。父は元気でやっているだろうか。
そんなことを考えていると、吸い込まれるような衝撃がリーズを包み込んだ。
気が付くと、リーズは暗闇の中に放り出されていた。上下左右が把握できず、動くこともままならない。
ルディアの名を呼ぶが、応えはない。代わりに空間のどこかから、男とも女ともつかない不可思議な声が響く。
「私がお前を呼んだのだ」
「どこにいる?お前は誰だ」
空間の所為なのか、突如頭痛に襲われる。その痛みは炎の力を初めて発現した時とそっくりだった。
次いで全身を飛竜に焼かれた時の激しい痛みが走る。リーズは堪らずのた打ち回る。
「選択せよ。ただ死に行くか、世界を変えるか」
不可思議な声と共に全身の痛みが治まっていき、次第に暗闇に包まれていた視界が開けていった。
リーズの眼前にはモノクロームの世界が拡がり、そこに石造りの大きな館があった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ