レタ
「珠」 
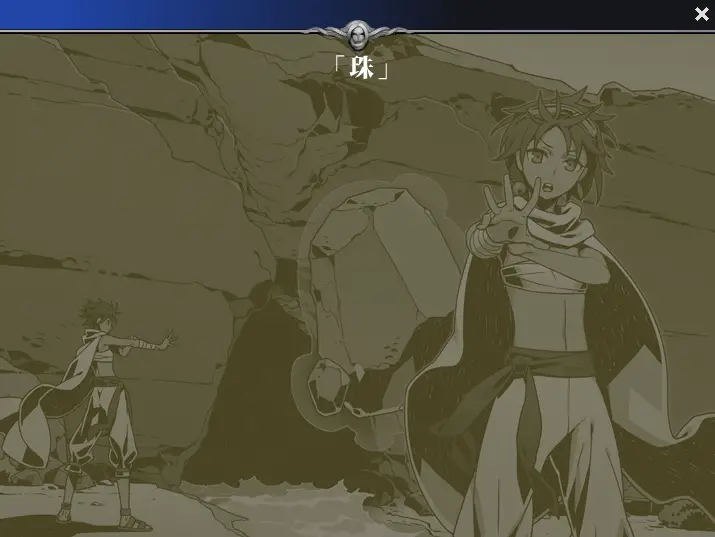
深紅色の砂漠の先に見えるオアシスに向けて、レタは歩いていた。
砂漠には風が吹き付けており、レタはフードとマスクで砂が侵入してくるのを防いでいた。
「レタ、大丈夫か?」
レタと同じようにフードとマスクを被った女、ホロムゥがレタの方を振り返る。
心配そうなホロムゥの声色に、レタは努めて明るい声で答えた。
「ちょっとだるいけど、平気」
レタは不調であることを隠さなかった。ホロムゥは非常に鋭い勘をしている。隠してもすぐ に露見してしまうことを、レタは理解していた。
「そうか。もうすぐ町だ、それまで我慢してくれ」
砂漠のオアシスにある町は静まり返っていた。丸い建築物や屋台のようなものは見えるが、人が外に出ている様子がない。
「昼間だからかな?」
レタは感じたままに言葉を発した。
前に訪れたオアシスの町は、同じような時間でも活気があった。
「それにしても、静かすぎるな」
人の気配はそこかしこにあるのに、誰一人として外を出歩いていない。
ホロムゥは周囲を見回すと、屋台のような所へと歩いていく。
屋台には紫色をした果実や、 白い葉を持つ野菜のようなものが並べられていた。
ホロムゥが屋台に近づくと、額から一本の角を生やした小柄な人型が姿を表した。
人型は皺くちゃの顔で怪訝そうにホロムゥを見ると、レタには理解できない言葉で話し掛けてくる。その言葉を受け、ホロムゥも同じ言語で会話をする。
彼女は自身の発明品によって異界の言葉を理解し、異界の住民とコミュニケーションを取ることができる。その発明品を持たないレタは会話に参加できない。
言葉が理解できないレタは、近くの日陰に座って休むことにした。屋台の店主とホロムゥはかなり長い会話をしているようだった。
ぼんやりとしていると、屋台に置かれていた果実をいくつか買い入れたホロムゥが、レタの元へ戻ってきた。
「少し先に旅人用の宿があるそうだ。行くぞ」
「はあい」
宿に向かうと、先程の屋台の店主と同じような姿の人型に出迎えられた。
砂漠の砂を玄関口で払い落とすと、建物の中に案内される。中はひんやりとしており、麻布のようなカーペットが敷かれていた。寝室と思しき場所にはクッションが敷き詰められていて、自由に寝転がれるようになっていた。
人型がお辞儀をして去ると、レタとホロムゥはフードとマスクを脱いだ。
レタとホロムゥの外見はぱっと見似ているが、明らかな差異がある。
ホロムゥには眉のように見える一対の複眼があり、臀部からはペタペタとした手触りの尻尾 のようなものが生えていた。
レタは褐色の肌をしているものの、複眼も尻尾も無い。二人は似たような二足歩行型の姿形ではあるが、全く異なる種族であった。
「ふへへ」
ベッドではないにしろ、久しぶりに柔らかなクッションで寝られると思ったレタは、顔をほころばせる。
レタがクッションに埋もれて幸せを噛み締めていると、宿の主が顔を覗かせに来た。主の後ろには二本の角を生やした人型がいた。
「レタ、留守番を頼む」
ホロムゥは二人の人型を見ると立ち上がり、彼らと一緒に何処かへと行った。
種族こそ違うが、レタとホロムゥは共に自分のいた世界へ戻るための手段を探して旅をしている。
レタは《渦》による災害で別の世界に転移し、故郷に帰るために放浪していたところでホロムゥと出会った。放浪中に目覚めた不思議な力でホロムゥを助けたことが切っ掛けで、共に旅をするようになったのだった。
ホロムゥは様々な世界を渡り歩く学者だ。かつて実験中の事故で別の世界に飛ばされ、それ以来自分の世界に戻るために必要な物質を探して旅をしていると聞いていた。
ややあってホロムゥが戻ってくる。
「どうだった?」
「やはり町の北にある洞窟に、それらしいものがあるらしい」
「当たりかな?」
「どうかな?数週間前に大きな岩で洞窟が塞がれたらしく、その岩のせいで町の連中も困っているらしいから……」
「行ってみないとわからないか」
「ああ。とりあえず体もう、陽が落ちたら出発だ」
宿を出て、この町の中心だという泉の近くを通る。泉の水は殆ど溜まっていない。
北の川から水が流れ込んではいるが、その量は少なく、この泉を満たせるとは到底思えな い。
この僅かな水を無駄遣いしないために、住民はなるべく外に出ることを控えていたのだ。陽に当たって体力や水分を消耗するのを防ぐためだと、ホロムゥはレタに説明する。
レタとホロムゥは僅かに流れる川を辿り、北へ向かう。
暫く歩いていくと、赤い岩だらけの山が見えてきた。更に進むと、大きな岩の隙間から少しずつ水が漏れ出ている場所に辿り着いた。
町の人が岩を破砕しようと頑張った痕跡も見つかった。
「ああー、これは確かに……」
「予想より大きいな。レタ、動かせるか?」
「んー、これくらいなら簡単かな」
そう言いながら、レタは岩の前に立つ。
「おい、岩の前に立つな。中の水量次第では流されてしまうぞ」
「あ、そっか。そうだね」
ホロムゥに言われ、岩の横に立つ。
「持ち上げる時は少しずつ持ち上げるんだ。隙間から徐々に水を逃がせ」
レタは手をかざして意識を岩に向ける。
これがレタの持つ不思議な力だった。原理は自身でもわからないが、どんな物体でも持ち上げたり引き寄せたりすることが自在にできる。
ホロムゥによれば念動力の一種だろうということだったが、レタにとっては『便利な能力』 程度の認識しかない。
黒い波動のようなものがレタの手から放出されると、岩がゆっくりと動き出す。
岩が浮き上がり、隙間から押し留められていた水が勢いよく出てくる。
「そこで止めろ。ひとしきり中の水を放出したい。支えていられるか?」
「任せて」
勢いよく流れ出てきた水が、次第に静かな川のようになっていく。
「もういいかな?」
「大丈夫そうだ。その岩はどこか邪魔にならないところに放っておこう」
レタは手を動かすと、岩を平らな砂地へと置く。転がる様子が見られないことを確認して、洞窟の中へと入った。
洞窟の中は水が充満していた影響か、ひんやりと湿っていた。危険な生物も生息しておらず、難なく最奥に辿り着く。
最奥には淡い青色に輝く球体が、岩の台座に鎮座していた。珠からは止め処なく水が溢れており、この珠に不思議な力があることは一目瞭然であった。
「これが町の人が言ってたやつかな」
「そうだな」
ホロムゥは背負っていたバックパックから小さな四面体を取り出す。所々が虹色に輝くそれを珠に近づけると、淡い光が漏れ出した。
光が珠を隅々まで照らすと、四面体の輝きが赤一色に変化した。
「違うか……」
「そうなの?」
「ああ。ケイオシウム結晶と性質は似ているが、構造が全く違う」
「とすると、この水はどこから……」
「水を運ぶことに限定されているが、この結晶自体が別の世界に繋がっている可能性が高い」
珠は確かに不思議な力を持っていた。珠からは尽きることなく清らかな水が湧き出ている。
「そうなんだ。……じゃあ、これはこのままここに?」
「これが無ければあの町は滅びる。ケイオシウム結晶でない以上、そっとしておくのがいいだろう」
ホロムゥはそう言うと、四面体をバックパックにしまった。
この珠は目当てのものではなかった。再び目的のものを探すために旅立たなければならない。
「一度あの町に戻ろう」
「そうだね。水がちゃんと通ったかも気になるし」
町は復活した水の流れによって歓喜に包まれていた。
ホロムゥが町の人に、岩をどかしたことと自分達はもう旅立つことを告げる。
町の者達は感謝の意を込めて、レタ達が持てるだけの食料と水を渡した。
食料と水を手に入れたレタとホロムゥは町を去った。
二人は再び紅い砂漠を歩く。視線の先に、黒い何かが風と共に揺らめいた。
「次は見つかるかな?」
黒い何かを見つけたレタは、期待を込めた眼差しでホロムゥに問う。
「どうだろうな。だが、見つけなければ」
「そうだね」
紅い砂漠の向こうに見える黒い何か。その先に見える世界が何処なのかはわからない。
それでも、レタ達は歩みを止めない。その先に目的のものがあるかもしれない。その可能性だけを頼りに進む。
黒い何かはレタ達をゆっくりと包み込むと、風に溶けるように彼女達と共に消え去った。
「―了―」
「黒の大地」 

黒い霧が晴れた先には、薄紫の光が降り注ぐ漆黒の大地があった。
その大地に勢いよく一歩を踏み出した瞬間、レタの身体がふわりと浮き上がる。
「わ!わ!!」
レタはそのまま腰の高さほど浮き上がり、ゆっくりと下降して大地に足を着けた。
「ふーむ……、今までとは物理法則が違う世界のようだな」
レタの様子を見たホロムゥが一つ領いた。
「気をつけて動かないと、危ないかな?」
「いや、そこまで気にする必要はないだろう。そうだ、幅跳びする感覚で地面を蹴ってごらん。移動がかなり楽になる筈だ」
「ヘー……」
ホロムゥの言葉を聞きながら、レタは走る体勢で勢いよく地面を蹴った。
レタの身体が軽く浮き上がり、一蹴りの勢いのまま、ホロムゥから二アルレ程の距離を移動できた。
レタの後をホロムゥが歩いて追い掛けてくる。
「どうだ?」
「凄い!これ楽しい!」
こういった物理法則は初めての体験であり、レタは気分が高揚していた。
「だが、何かに触れるときは慎重にな。今までの我々の感覚で触れると、思わぬ事故が起こるかもしれん」
「はーい」
「さて、ひとまずは町を探すとしようか」
「街道か、もしくは見晴らしのいい高台なんかが見つかるといいんだけどね」
二人は黒い大地を歩き始める。情報を収集するには、その世界の知的生命体を見つけ出すのが一番早いのだ。
しばらく歩いてみるも、代わり映えのしない景色だけが続く。
真っ直ぐに歩いているが、丘の形が少し変わる程度で、目立つような草木や岩、構造物といったものは一切見当たらない。
レタは同じ場所を延々と歩かされているかのような感覚に囚われていた。
「なんか、どこをどう歩いてきたのかわからなくなりそう」
「こうも殺風景ではな。おそらく、何も無いのはここら一帯だけだとは思うのだが」
「茂みどころか、花も木も無いもんねー」
「だからといって、休憩以外で立ち止まるのは愚策だろう。出た場所が悪かったと思うしかないな」
「そーだねー……」
二人は無言で歩き続けた。あまりにも殺風景ではあるが、この世界に辿り着いてから、まださほどの時間は経っていない。
地面の下から危険生物が這い出てくる可能性もある。何が起きるかわからない以上、警戒を怠る訳にもいかなかった。
更に歩を進めていくと、前方が何やら騒がしい。魔物のような獣の声と、レタには聞き取れない言語で何かを叫んでいる声が聞こえる。
近付いていくと、少し離れた丘の下に荷台があり、その持ち主らしき者達が虎と鰐を掛け合わせたような大小の生物に襲われているようだった。
荷台の持ち主達は、レタの世界で言うところの狸のような顔を持つ二足歩行型の生命体だった。言語と道具を使っているところから、この世界の人間に相当する生命体なのだろう。
「あれ、は」
「囲まれてる!どうしよう?」
「助けよう。知的生命体の可能性がある以上、情報収集の手段を失うわけにはいかない」
「わかった!先に行ってる」
レタは背負っていた荷物を地面に降ろすと、武器である長物を手に取る。
このような場合、様々な機械を持ち歩くホロムゥと一緒に向かうのでは時間が掛かりすぎる。小柄で敏捷なレタが先行して牽制し、強力な銃器を持つホロムゥが後方で支援に回るのが大体の役回りとなっていた。
「気をつけろ」
ホロムゥの言葉を背にレタは駆け出す。地面を蹴って飛ぶ加減を覚えていたのが早速役に立つ。
そしてその勢いのまま、今にも荷台の持ち主に襲いかかろうとしていた小型生物の一匹を切り飛ばした。
突然の第三者による介入に驚いたのか、荷台の持ち主達が何事かを叫ぶ。
しかし、ホロムゥのように翻訳装置を持っていないレタでは、彼らの言葉を理解することはできない。
そんなレタにできるのは、襲い来る小型生物をもう一匹切り伏せて、敵ではないことを示すことだけだった。
狸顔の者達は小型生物を攻撃するレタの姿に、少なくとも敵意は無いと判断したのだろう。
急いで荷台を襲う群れの討伐に戻った。
彼らは手の平から不思議な文様を出現させ、それを介して何かの物体を銃弾のように射出している。狸顔達の様子を見たレタは、群れの掃討に集中することにした。
襲い掛かってきた小型生物を長物で叩き落す。攻撃の隙にレタ目掛けて飛び掛ってきた小型生物がいたが、その顎がレタに届くより前に、勢いよく吹っ飛んでいった。
「大事ないか?」
「ありがと」
すぐ後ろでホロムゥが銃を構えていた。
「さっさと殲滅してしまおう。大型の方を頼む」
「群れのリーダーっぽいしね」
襲い来る小型生物を切り払い、レタは真っ直ぐに大型生物の方へと走る。
大型生物もレタに気付いたのか、咆哮を上げてレタに向かって跳躍する。
「よ、っと……」
この世界では俊敏に動けることも手伝い、レタはいつも以上の立ち回りを見せる。
大型生物の跳躍を回避し、距離を置いた。
レタはその距離を目測すると、大型生物が自分の方へと引き寄せられる姿をイメージする。
目の前に、この大地以上に黒い色をした、球体のようなものが出現した。
「来い」
レタは小さく呟く。その声に引き寄せられるように、大型生物が首を引っ張られるようにして引き寄せられる。
長物を構え、レタは少しだけ立ち位置をずらして大型生物を迎え撃つ。やはり物理的な法則が変化しているらしく、引き寄せるスピードはいつも以上である。
レタの長物の切っ先が大型生物の顔に突き刺さり、そのまま一気に喉まで切り裂いた。
レタは返り血を浴びる前に大きく跳躍してその場を離れると、ホロムゥのところへ駆け寄 る。
ホロムゥとレタ達の奮闘もあり、群れは完全に壊滅状態にあった。
「お疲れ様」
「ホロムゥもお疲れ様」
「さて……」
群れを全滅させたことを確認すると、ホロムゥは荷台の持ち主に近付く。
助けたことを切っ掛けに、町への道を尋ねるなどの交渉をするためだ。
ホロムゥと狸顔のリーダー格が二言三言を話し、戻ってくる。
「町まで乗せて行ってくれるそうだ。ここから半日ほど掛かるらしいが」
「ほんと?」
「ああ。それと、町で改めて礼をしたいらしい。理由はわからんが、積荷がとても大事なものだったんだろう」
「いい人たち、なのかな?」
「だったらいいんだがな」
幌の掛かった荷台に空間を作ってもらい、二人はそこに座った。
御者台に座る者が何かの合図を出す。すると、二人を軽い浮遊感が包み込んだ。
この荷台は何らかの技術で浮遊し、低空を飛行するものらしい。荷台を引っ張る馬や驢馬に相当する動物がいないのも領けた。
半日ほど飛行すると、緩やかな山道の下に、幾何学的な文様を描く円形の街並みが見えてき た。
町が描いている文様は、先ほど狸顔達が群れを攻撃してきた時に出現したものにとても似ている。
「不思議な感じ。あの人たちがさっき攻撃する時にも使ってたし、何かの力を呼び出すための文様なのかな?」
「おそらくそうだろう。科学的なものか、それとも呪いなのか、その辺はわからんがな」
「力の発生源とか、あるのかな?」
「どうだろう?とにかく、行ってみなければ何もわからんよ」
「それもそうだね、気を引き締めなきゃ」
異世界の知的生命体との本格的な交流を前に、レタは居住まいを何となく正した。
何が原因で敵対してしまうかもわからない。習慣の違いによる行動で、一瞬にして不利な状況に陥ってしまうかもしれない。
会話による交渉はホロムゥが全てやっているが、自分の行動一つでその交渉を台無しにしてしまう可能性だってある。
それを考えると、自然と緊張が走るのだった。
「今回も上手くやれるといいな……」
レタは一人、近い未来の行動を考えて呟くのだった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ