レッドグレイヴ
【正体】パンデモニウムが技術の粋を集めて産み出した遺伝子操作された人間。同じ運命を与えられたグライバッハの死の真相を追う。
【死因】
【関連キャラ】マルセウス、ウォーケン(グライバッハの助手)、ドニタ、サルガド、ベリンダ
2814年 「自死」 

医療用ベッドに寝かされた人物は、眠るように目を閉じている。
「本当に行かれるのですか?レッドグレイヴ様」
傍らに控えるのは白衣を纏った男だ。
横たわった女性は、その言葉に黙ったままだ。
彼女の均整の取れた美しさは、とても老齢に差し掛かろうと言う年齢には見えなかった。
「こんな形でお別れすることになろうとは。私はまだ納得できません」
白衣の男は、ベッドの人物に懇願するように言った。
「感傷に囚われるな。未来を救うためだ。誰かが行かねばならぬ」
「……わかりました。どうかご無事で」
手術を行う医師団が入ってくると、白衣の男は名残惜しそうにベッドから離れた。
ベッドに横たわる人物はレッドグレイヴ。世界の統治者でもあり、『監視者』と呼ばれた女。
彼女は約70年に渡って人間世界を統治し続けた後、最後の旅路に出発した。
薄暮の時代、自動機械の発達により、人類は飢えと労働から解放され、繁栄を享受していた。
しかしそれは人智の発展を淀ませ、人心を荒廃へと進ませる結果を伴ってしまった。
世界を統治するエンジニア達は、自らが作りだしたこの繁栄に満足しなかった。
世界を改善し続けることを使命とする『技術者』らは、一つの実験を行った。
数百人の遺伝子操作を加えた人間を作り出し、その中でも特別な三人を選び出して革新を託した。
誕生した三人は、グライバッハ、メルキオール、レッドグレイヴ、と名付けられ、それぞれの分野で活躍を始めた。
グライバッハはより精巧で価値を生み出すオートマタの開発に、
メルキオールは新しいエネルギー源として注目されていたケイオシウムの研究に、
最後の一人、レッドグレイヴは社会機構の改良という事業を担当した。
グライバッハは、優れた知性に加え、オートマタに対する深い愛情を持っていた。
彼の理想とする世界は、オートマタの生み出した果実を人間がただ摘み取るだけではなく、人間とオートマタが共存する世界だ。
そうすることで、この停滞した世界は新たな進化を見せるだろう。
それがグライバッハの考えだった。
メルキオールは、正に研究をするために生み出された、ケイオシウムの申し子と言うべき存在だった。
社会の根幹を支えるエネルギーとしてのケイオシウムを、より安全に、且つ効率よく供給し続けることだけを目指して研究し続けた。
メルキオールにとってケイオシウムとは、人間よりも尊重すべき存在であり、彼の全てであった。
レッドグレイヴは、他の二人とは別の視点で能力を発揮した。
レッドグレイヴは物事を常に俯瞰で見る。そして問題点を見つけては修正し、再発しないための処置を行った。
それはさながら医師の様であり、機械を直す技師の様でもあった。人間は世界を構成する細胞であり、癌細胞があればそれを除去する。
そこに情などという不要なものが入る余地は無い。それがレッドグレイヴの考え方だ。
三人が世に出てからすぐに、グライバッハとメルキオールは目覚ましい成果をもたらしていた。
特に、グライバッハの作り出した『知性を持つオートマタ』は、オートマタと人類の関係を一新させたと言ってよい程だった。
メルキオールもケイオシウムの再利用法について画期的な研究を納めており、二人の名は高まっていった。
一方レッドグレイヴは、政策が効果を上げることができず、長い間評価されることがなかった。
社会統治は、発明や研究などに比べて、目に見える形を得るのに時間が掛かった。
三人はしばしば集まり、互いの研究や仕事に関して意見を交わし合った。
選ばれし者としての連帯感、また、三人だけが世界を切り開くことができる、という感情で結び付いていた。
「あの研究はどうなった、メルキオール。前に話していた、多重世界の観測をケイオシウムによって行うとかいう」
グライバッハが紅茶を口に運びながら言う。三人はグライバッハの庭園で話し合っていた。
庭園は彼の精巧なオートマタによって完璧に管理されていた。
グライバッハの審美眼は他の二人よりずっと優れている。
彼は一種の創造主であり、完全な美に尽くす芸術家の側面も持っていた。
「新しい段階に入った。もう、観測という概念は捨てた。もっと新しい知見がある」
視線を合わさず、独り言のようにメルキオールが答える。
二人よりずっと幼く見えるメルキオールは、他人とのコミュニケーションを取ることに慣れていなかった。
子供の頃から共に育った兄妹のような二人にさえ、この調子だった。
三人とも三十に近付いた年齢だったが、肉体的な陰りは微塵もなく、十代の少年少女のように見えた。
「新しい知見?」
レッドグレイヴが覗き込む様に質問する。レッドグレイヴは表情豊かに微笑んでいる。
彼女の容姿は飛び抜けて美しく、表情も完成されていた。
人民の中心にあってその統治のために生まれてきた彼女は、人心の掌握を才能として持ち合せていた。
「ケイオシウムは可能性の固まりなんだ。可能性をエネルギーとして閉じ込めた状態の粒子だ。いまの使い道は便利な蓄電池といったところだ。害もなく、究極の効率をもつ」
「誰でもそこまでは知ってる。ここにいるオートマタだって、全てケイオシウムで動いている」
少し諭すような感じでグライバッハが言う。
「その可能性の固まりという側面における選択されてない状態、つまり無と有の狭間にある状態のものを集めてある傾向を持たせると、この世界では絶対にあり得ないことが起きる」
グライバッハの皮肉な調子には気付かない様子で、独り言のようにメルキオールが続ける。
「意味がわからないわね。具体的には?」
レッドグレイヴは素直に気持ちを言葉に出した。
「君は、世界はたくさんの可能性に満ちている、ということはわかるかい?」
「もちろん」
突拍子もない質問に笑いながら答えたレッドグレイヴに、メルキオールは赤面して下を向きながら続きを喋り始めた。
「たとえばここにあるお茶。 放っておけば自然に冷めていく。詳細を端折れば、エントロピーは必ず増大すると言える。だけど、そのエントロピーが増大するように見える現象は、天文学的な可能性が積み上がった後にそう見える、というだけのことに過ぎない。当たり前に見える不可逆な出来事だとしても、無限の可能性の中には例外があるんだ。つまり、この80度の紅茶が10分後に70度になっている世界が当たり前だとして、無限に多重世界があれば、どこかに100度に沸騰している世界があるんだ」
レッドグレイヴは早口に捲し立てられて、きょとんとした表情を見せる。
「わかりやすく言えば、骰子(さいころ)を一万回振ったとして、どこかには全て6が出る世界がある、ということか」
グライバッハがフォローする。
「そう。必ずどこかにあるんだ。その世界が。そして、その世界をケイオシウムの力で選択できるんだ」
「たしかにすばらしい、不可能のない世界というわけだ」
笑いながらグライバッハが大袈裟に驚く。
「他の世界に無価値な可能性を押しつけることによって、望むままの世界を選択できる」
「でも、無限からなにか一つを選び出すなんて、それ自体にエネルギーがいるでしょう?」
レッドグレイヴが疑問を口にする。
「うん、情報はそれ自体がエネルギーだ。何かを観測して、それを選び出すことにもエネルギーが必要だ。そこで別のアイデアがある。でも、これ以上はまだ話せない」
突然、メルキオールは落ち込んだように口をつぐんだ。
「なるほど、メルキオールらしい素晴らしい視点だな。 おもしろい話だ。私も協力できることがあるかもしれない。いつでも頼んでくれ」
グライバッハが鷹揚(おうよう)な態度で、急に落ち込んだメルキオールの肩を掴んで言った。
「うん」
メルキオールはそう言うと、
「もう戻るよ」
そう言って、そそくさと席を立つ。
「またね、メルキオール」
「あ、うん」
メルキオールは、レッドグレイヴの別れの挨拶に目を合わせないまま去っていった。
二人きりになったテーブルで、グライバッハはレッドグレイヴの手を握って言った。
「最近、元気がないように見えるぞ」
「そう? いつも通りよ。あなたこそ、ここのところ新作発表に精彩がないんじゃない?」
「手厳しいな。たしかに今は停滞している。毎年毎年成果を求められるが、いつも完璧、というわけにはいかないさ」
「メルキオールも悩んでるみたいだし、あなたたちの才能もここで終わりなのかしら?」
いたずらっぽく、レッドグレイヴは笑う。
「なに、まだまださ。 メルキオールの次の研究はとんでもないものだが、私の次の目標だって負けてはいない」
「それはなに? 聞かせてくれる?」
「創造性をもったオートマタさ。ただの知性じゃない。新しい何かを作り出す力をもったオートマタだ」
「ずいぶんと飛躍するのね。でも、そんなオートマタを欲しがる人がいるのかしら?」
「君のためにもなる。卑しい人民であっても、十全な判断力と新しい知見を目指すオートマタが指導すれば、瞬く間に安定した世界に変わる。君の子守の仕事も必要なくなる」
「私を失業させたいのね。あなたはいつも人間を嫌っているみたいな口ぶりだわ。私たちだって人間よ」
レッドグレイヴは冗談として受け流そうとするが、グライバッハの目は真剣なままだった。
「君はそういう風に作られているんだ。人民を愛するように」
「あなたはそうでないと?」
「所詮、私たちは作られた『もの』に過ぎない。私は、君が人民に愛着を感じているように、オートマタに愛情をもっているのさ」
「機械にもそういった感情は必要だと思う?」
「ヒューリスティックなシステムは、十分有用な側面がある」
「ならよかった」
レッドグレイヴはグライバッハにキスをした。
それから二十年ほど進むと、レッドグレイヴの治世は評価を得るようになっていった。
美貌の指導者は世界に活気をもたらしていた。レッドグレイヴがもたらす平和な日々は、永久に続くかと思われた。
その平和に最初のヒビが入ったのは、レッドグレイヴの元に届けられたひとつの報せだった。
その文書にはこう書かれていた。
「天才機械技師グライバッハ、自殺す」
もう若い時のように頻繁に会うことはなくなっていたが、
不思議な紐帯(ちゅうたい)で繋がれていた兄妹ともいえる男の死に、レッドグレイヴは衝撃を受けた。
「メルキオールにも、この報せは行っているのか?」
レッドグレイヴは、ふと気になって秘書に尋ねた。
「調べます。研究所にいらっしゃる筈ですので。いずれ新聞が大々的に報じますので、メルキオール様もお気づきになるとは思いますが」
メルキオールの活動も昔ほど活発ではなくなっていた。
申し訳程度の論文を発表しては、自身の研究所に引き篭もっている。
「そうか、わかった」
二人と疎遠になったのも、彼らの目指す発明なり研究なりの行き詰まりが原因だった。
また、自分の仕事が順調に進んでいくことに十分満足していたことも、理由の一つにあった。
しかし、自分達の精神を含めた健康について、不安に思ったことなど一度も無かった。
本当に、自分の知っているグライバッハが自死などを選択するのだろうか。
この疑問がレッドグレイヴの頭を離れなかった。
「治安管理局の責任者と今すぐ話したいことがある。連絡をつけてくれ」
レッドグレイヴは秘書にそう言って、席を立った。
「-了-」
2814年 「記録」 
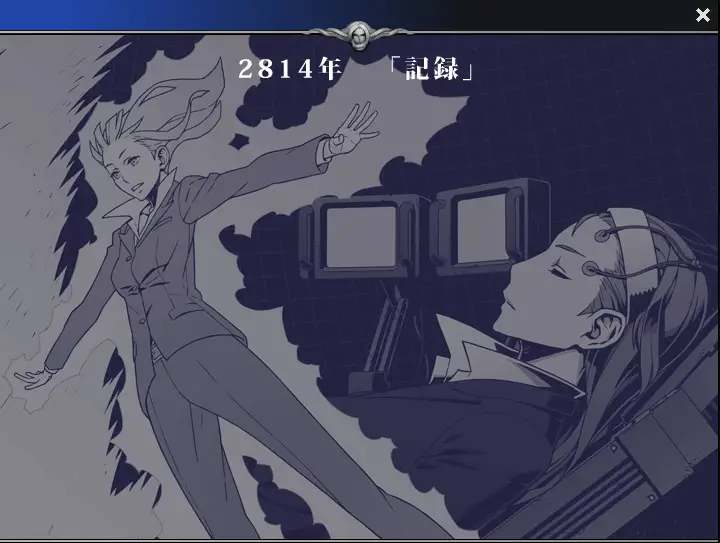
レッドグレイヴはグライバッハ邸にいた。瀟酒な家具と麗らかな日差しが当たるその部屋は、昔日の思い出と変わりようが無いように思えた。大きな部屋の壁龕には、彼のたくさんの『作品』が飾られている。現実的な動物や想像上の怪物、妖精といったものを模したオートマタが、ポーズをつけられ飾られていた。それは一種、彼の作品カタログのようになっていた。
その作品群の一つずつゆっくりとレッドグレイヴは眺めた。彼の人生がそこにあった。レッドグレイヴは元来感傷的な人間ではないが、動かない人形達を見ていると、その彼女も眇々たる寂しさを感じていた。完璧に見えた自分達の人生もいつかは終わり、動かない飾られた人形達のように、そっと忘れ去れていくのだと。
部屋を進んでいくと、飾られている人形の中に奇妙な空白があることに気が付いた。大きく作られたスペースには、何かここに飾る予定のオートマタがあったようだ。おそらく彼が最後に向かい合っていた作品なのだろうと、レッドグレイヴは思った。
奥にある彼の研究室にレッドグレイヴは向かった。工作機械が並べられたその部屋には、彼の工房ともいえる場所だ。機械類が置いてあっても、彼の美意識で整えられた部屋には一種の静謐さが感じられた。
部屋に入ってすぐの右奥に、奇妙な黒い人形が見えた。照明器具から垂らされた紐にぶら下がった男の死体だった。髪は乱れ、その顔には皺が刻まれていた。近くに寄らずとも、それがグライバッハであることは理解できた。
「遺体は消してくれ」
レッドグレイヴが声を出すと、グライバッハの遺体はその空間から掻き消えた。
レッドグレイヴは治安管理局捜査科のデータにアクセスしていた。事件、事故が起こった時には、全ての証拠が治安管理局のデータベースに高精細の三次元データとして保存される。一度電子になった証拠は永遠に残り、再検証も容易だ。レッドグレイヴは、公務の合間にグライバッハが発見された時のデータを眺めていたのだった。
死体のデータを消した後、レッドグレイヴは研究室を歩き回った。どの工作機械にも工芸品のような彫刻が施されており、優美に仕上げられている。
しかし、優美な工作機械の周りに部品や作品は一つも置かれておらず、一切が整理、処分されているようだった。それはグライバッハなりの美学なのだろうと、レッドグレイヴは解釈した。
机の横にある書架に、若い頃の自分と映った古い写真プリントが飾ってあったのを見つけた。二人で芸術アカデミーが作った中央歌劇場の初日セレモニーに出席した時のものだ。プレス向けの笑顔だったが、若々しい二人はとても幸せそうに見えた。手に取ろうと腕を伸ばしかけたが、所詮データに過ぎないことを思い出し、諦めた。
「レッドグレイヴ様。 広報局とのアポイントメントの時間です」
音声が部屋に響いた。正確には、レッドグレイヴの聴覚に直接響いたものだった。
「わかった。戻る」
レッドグレイヴは治安管理局のデータから離脱し、執務室で目を覚ました。
執務室には秘書官のマリネラがいた。彼女は最近赴任してきた、若い政策担当エンジニアだ。レッドグレイヴと同じような調節が施された特別なテクノクラートであり、極めて有能だった。制服姿もまだ若々しい。
「データのアクセス権は変換しますか?」
「ああ、そうしてくれ」
レッドグレイヴは感傷を遮断し、自分の仕事へ戻った。
居室の反対側がスクリーンとなって映像が映し出され、広報局の技官達が現れた。
彼らは簡単な挨拶の後、レッドグレイヴに議題を説明した。
「これが現在の各統治セクションの潜在欲求グラフです」
広報担当の技官が地図とカラフルなグラフを画面に表示する。
「現在の潜在欲求の組み合わせから起こる各地域での問題が以下の通りです。五年のシュミレーションです」
画面が切り替わり、各地域で起こり得るであろう事象が次々と現れ、消えていく。暴動、紛争といった暴力による騒乱、宗教や麻薬といった文化上の紊乱など、色分けされたものが各地域で明滅する。
「現在の施策を続けた時に起こる文化的な問題はこのような形で……」
「S―1とO―4の地域での、党派性許容係数の値を出してくれないか」
レッドグレイヴは技官の説明を中断させ、情報の切り替えを命じた。各地域は符号で呼ばれている。統治機構はあくまで数字としてしか市民を見ていない。彼らの欲求を察知し、それに見合った施策を施す。不安が生じていれば治安対策や文化的な刺激を、退廃が生じれば脅威――犯罪組織や疫病、ただしコントロールされたモノ――を彼らに与えた。
レッドグレイヴの仕事はエンジニアの考える政体の神髄だった。エンジニアの考える人間の繁栄と進歩、持続可能な生活。そういったものの達成のために、たくさんの変数の組み合わせと計算を行う。それがレッドグレイヴだった。その頭脳はそれ専用の生体計算機といえた。
広報局との会議を終えて一段落すると、明日の予定の変更をマリネラに伝えた。
「明日、少し時間をもらう。 私用だ。 同行の必要は無い」
グライバッハ邸に向かうことを決めていた。まだ感傷が痼りのように残っていた。気切りをつける必要があると思ったのだ。
「承知いたしました」
レッドグレイヴが実際にグライバッハ邸に入ると、操作記録との違いにすぐ気が付いた。
部屋は暗く、しかも荒らされた様子があった。飾られていたオートマタ達も床に散らばり、ばらばらになっている。
廃墟の様になった場所を縫うように歩き、研究室に向かった。こちらの方がより、激しい損傷の跡が見える。携帯端末を使ってレッドグレイヴはマリネラに繋いだ。
「いまグライバッハ邸にいる。治安管理局のデータで、事件後にこの家が荒らされたかどうか確認してくれ」
「わかりました」
連絡を取りながら、レッドグレイヴはグライバッハの書架に飾ってあった写真を確認した。それは記録と同じ場所に飾られていた。レッドグレイヴはその写真を手に取り、邸を後にした。
「グライバッハ邸が荒らされたとの情報はありません。いま、捜査員がそちらに向かうそうです」
マリネラからの通信が届く。
「わかった」
レッドグレイヴは邸を出て、統治局に戻るため車に乗った。
「グライバッハ邸の件ですが、侵入者の記録は残っていません。念のため捜査を行うそうです」
執務の合間にマリネラからの報告を受ける。
「そうか……」
レッドグレイヴにはまだ蟠りが残っていた。持ち帰った写真は自分の机の抽斗に仕舞った。
グライバッハが何故死んだのか、その理由が一番知りたかった。少しでも納得できることがあれば、それで構わなかった。
レッドグレイヴが知っているグライバッハは、自死を選ぶような性質は持っていない。レッドグレイヴは己の直感に対して非常に信頼を置いていた。人心を統べるために日々心に湧く疑問や違和感を子細に観察し続けていた彼女は、鋭敏な感覚を持った観察者だった。
「捜査局の者に連絡をつけて欲しい。説明を受けたいことがある」
「はい。わかりました」
レッドグレイヴはグライバッハのセンソレコード(智覚記録)のバックアップにアクセスしようとしていた。
捜査局の話を聞いても、彼らからは有用な情報が得られなかったためだ。
高位のエンジニアであるテクノクラートは、生まれた時から全てび智覚情報――触覚・聴覚・視覚・臭覚・味覚、脳に伝わる外部信号の全て――を脳に埋め込まれたチップに記録されている。
死を恐れる者の中には、クローンに毎日バックアップした情報をロードしている者もいる。
レッドグレイヴにもバックアップのクローンはいたが、それほど厳密な管理はしていない。事故死や病死など、不慮の死自体が極めて稀だからだ。
そもそも、同じ記憶と同じ遺伝的要素を持った肉体が同時に存在するのを嫌う者も多い。有り体に言えば、極めて似た他人と入れ替わるに過ぎないというのも事実だ。今の自分が死んで、それ以外の『似た』自分が生きることに意味を見出すことは難しい。
このセンソレコードも、グライバッハの遺言では破棄される筈のものだった。
究極のプライバシーとも言えるセンソレコードを取り出すには、それなりの理由が必要だ。そもそも自死なのだ。
エンジニア社会において自死など全く珍しくないと言えた。医療とクローニングの進んだ上級者会では、死亡原因のトップは自死だ。ただ、何故それを選択したのか、納得できる理由を一つでも掴めればよかった。
「本当におやりになりますか?リスクは皆無ではありませんし、あまりお勧めできません。こんなことは捜査局の連中にやらせればいいことです」
マリネラはレッドグレイヴに考え直して欲しい様子だったが、レッドグレイヴにとって説明されたリスクなど、些事に過ぎなかった。
「リスクなど理解している。自分の疑問は、捜査局の答えなどでは解決しない」
「わかりました。私にできる限りフォローをさせてください」
「わかった。頼んだぞ」
データ再生装置とレッドグレイヴが接続され、彼女の神経は現実世界から遮断された。
他人の智覚を再生して自分のものとして受け取る奇妙さは、独特のモノだ。信号の強度を間違えれば、現実感の喪失を引き起こしてしまう。
現実感のチェックを定期的に行い、テストに問題があれば、秘書官のマリネラが作業を中断させる。
現実と仮想の境目がわからなくなる『汚染』を起こせば、正気でいられなくなる。
「キャリブレーション・シークエンス、スタートします」
ホワイトノイズが頭に響く。たくさんの色と模様が目の前に現れた。指先にちりちりとくすぐられたような感覚が走る。何か酔うような感覚が現れたが、次第に収まっていった。
五感情報、内分泌器官の違いを吸収して、智覚の『同期』を行うためのシークエンスが終了した。
「ではセイリアス・グライバッハ氏、28140903のデータを再生します」
グライバッハ最後に一日の再生が始まった。
朝の光だ。柔らかな陽光が顔に当たっているのが分かる。
グライバッハのアシスタントらしき若い女の声がする。
まるで夢の中にいるような感覚だが、智覚は完全に自分のものだ。
完全に自分自身が経験しているのだが、自分が発する意思や思いが自分の体に適応されない。まるで動く牢屋に閉じ込められたような感覚だった。
「おはようございます、マスター」
歌うような響きで、若い女が声を掛けてくる。この女は人間ではないのだろう。完璧すぎる容姿は、グライバッハのオートマタであることを証明している。
「朝食の用意ができています」
「ありがとう、ミア。そうだ、ウォーケンに昨晩の実験結果を報告するように言ってくれないか」
頭蓋を通したグライバッハの声は、知っている声より随分と低く響いた。
「わかりました」
ベッドから起き上がり、洗面所に向かい、顔を洗う。顔に当たる冷たい水の温度さえ完璧に再現されている。
ガウンを羽織ったまま朝食を摂る。壁に映る情報端末の日付と時刻は、確かにグライバッハの死んだ日だ。
しかし、これはおかしい。こんな安定した日々の途中で、突然自死するだろうか?
「マスター、どうかされましたか?」
「いや、何でもない」
ミアと呼ばれているオートマタは、奇妙な問を発した。グライバッハは食事を進めながら何か考え事をしていたようだ。
「マスター、ウォーケンはレポート作成に一時間ぐらい欲しいと言ってます」
「なら構わん。あとで研究室に来るように言ってくれ」
「わかりました」
そう言ってミアはグライバッハの食べ終わった食器を片付け、席を離れた。間を置かず、ミアが持っていた白磁の食器が床に落ちて割れた。ミアは落とした食器の破片を拾おうともせず、ただ立ち尽くしていた。
「どうした?」
グライバッハが声を掛ける。
「マスター、本当にあなたはマスターですか?」
向こうを向いたままミアはそう言った。
「ああ、もちろん」
奇妙な会話だ。
「いいえ。あなたはマスターではない」
振り向いたミアは、飛び掛かるようにグライバッハへ襲い掛かる。藻掻いて取り払おうとするが、凄まじい力でグライバッハの首が締め上げられていく。
同調しているレッドグレイヴの意識も遠くなっていく。
薄れ行く意識の中で、ミアと呼ばれているオートマタの笑い声が聞こえたような気がした。
「―了―」
2814年 「捜査」 
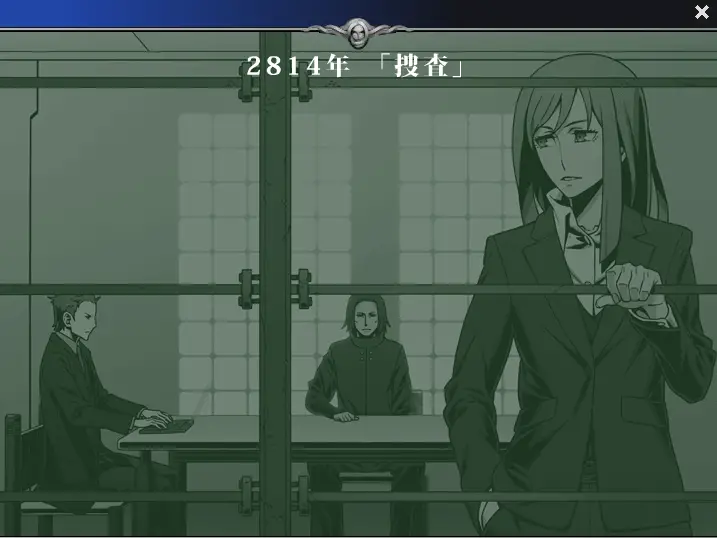
ミアと呼ばれていたオートマタは、グライバッハ――今はセンソレコードを再生しているレッドグレイヴでもある――の首を絞めている間、笑い続けていた。
苦しみと死の恐怖がレッドグレイヴの脳を襲った。ただ、そんな状態でも、レッドグレイヴの心の奥にある冷徹な判断力は、事の原因と反抗可能な人物を探し出そうとしていた。
「お前のことは知っているよ」
レッドグレイヴの首を絞めながらミアは言った。視界が無くなり、声だけが聞こえてくる。
「必ず壊してやる」
レッドグレイヴの意識はブラックアウトした。
再び意識が戻ったとき、傍にいたマリネラがドクターを呼び出していた。
「よかった、意識が戻られたのですね」
いつもは無感情なマリネラの声が、少し弾んでいるようだった。
「何があった?」
「精神汚染寸前でした。異常なデータがオーバーロードされたのですが、辛うじて安全装置が働きました」
医者はモニターをチェックしながら言った。
「センソレコードが改竄されていたのか?」
「それは捜査局から報告があると思います」
マリネラが横で答えた。
「明日の検査で問題が見つかなければ、職務に復帰できるでしょう」
加えるように、医師が端末にペンを走らせながら言った。
「ただ、メンタルヘルスに後遺症が残っているかもしれませんので、暫くは定期的な検査をお願いします」
「わかった。問題ない」
医師達がレッドグレイヴの元を去ると、病室はマリネラだけになった。
「捜査官の話をいますぐに聞きたいのだが?」
「はい、呼び出せると思います」
マリネラはいつもの職務的な口調に戻ってそう言った。
端末を操作した数分後、捜査局の人間が病室のメインモニターに映し出された。
映像には責任者であるテクノクラートと二人の捜査官が映っていた。二人の捜査官はグライバッハ邸の再捜査を行っている担当官で、それぞれレントン、ブロウニングと名乗った。
「捜査の不手際で、このようなことになってしまい……」
年嵩のレントン捜査官がお定まりの謝罪をしようとするのを、レッドグレイヴはすぐにやめさせた。
「私が聞きたいのは捜査の進捗だけだ」
グライバッハは自死を装って殺されたのだ。
「はい。 記録されたデータに何者かが手を加え、事件を隠蔽しようとしていたことが判明しました。ただ、電子捜査部の調査では、現段階で有力な証拠はまだ見つかっていません」
「誰がグライバッハを殺したのか、他の手掛かりはないのか?」
兄妹であり、恋人でもあった男が殺された。この事実に感情を大きく動かされていた。しかし、レッドグレイヴは感傷と職務を分離している。彼女の深い洞察力は、この殺人に大きな違和感を感じ取っていた。
「再調査により、邸内の破壊は内部のオートマタによるものだとわかりました」
「グライバッハはオートマタによって殺されたのか」
「おそらく。しかし、捜査局では自殺の可能性を捨てていません。なんといってもグライバッハ氏はオートマタの権威ですので……」
老いた天才が自らの創造物で手の込んだ自死をした。そんなシナリオを捜査局は想定しているようだった。
「違うな。オートマタの背後には別の意志があった筈だ」
あの記憶の中で出会ったミアという女は、グライバッハが作ったものではない。そうレッドグレイヴは直感していた。
「は、はい。ただ捜査は予断を持って臨むわけにはいきませんので、その……」
レントンは額に玉のような汗を浮かべている。
「そんなことはわかっている。だが。私の直感は訓練と技術によって鍛えられたものだ」
「はい。もちろんそれは、十分に理解しております」
現場の捜査局員など、統治局の最高レベルの技官から見れば、吹けば飛ぶような地位だ。この場をどう繕うかだけをレントン捜査官は考えているようだった。
レッドグレイヴは下層の職員がしばしば見せる。このような矮小な自己保身を嫌悪していた。
「捜査の過程は逐一こちらに報告してもらおう」
「わかりました。引き続き調査を行います」
レントンと一言も喋らなかったブロウニングの両捜査官は、命令するとともに画面から消えた。
翌日、検査を終えて職務に戻る車中で、レッドグレイヴは通り過ぎる窓の景色を眺めながらグライバッハの記憶を反芻していた。
――あの日、何があったのか。
――グライバッハは完全な創造性を持ったオートマタを完成させ、殺人を『創造』したのだろうが。
――そして、自分の作品によって殺されたとしたら、それは自死になるのか。
オートマタは地上に溢れている。安定した労働者として、この世界の繁栄と継続を担っている。
その働きの改善にあたったのがグライバッハだった。知性あるように振る舞うことのできる美しい彼の作品は、夢の奴隷として瞬く間に世界を覆った。ただ、グライバッハはそれに満足していなかった。
知性あるかのように振る舞うといっても、ホログラフの動画がそこに何かが存在しているかのように表現するのと同じで、彼のオートマタの知性も作られたように動くだけだった。
人間のように新たな価値を作り出したり、意志を持って目的を創造したりすることはついにできなかった。
「私の知性の劣化コピーに過ぎない。それも一部だけを切り取った、スナップショットみたいなものだ」
と、殻は自分の作ったオートマタの精緻さを、自嘲を交えてそう表現することがあった。
「レッドグレイヴ様、捜査局からグライバッハ氏のオートマタに関する調査報告があるそうです」
レッドグレイヴの黙考はマリネラの呼びかけで中断した。
「わかった、繋いでくれ」
スクリーンにテクノクラートと捜査官の一人が映った。彼らの映像とは別に、オートマタの識別番号と所在のリストが映し出される。
「グライバッハ氏が製造し、邸内で保有していた人形オートマタは20体。うち16体が全損した状態で発見、2体は事件前にD―2区画にある美術館に展示物として貸し出されており無事でした」
「残りの2体はどうなった?」
「事件があった翌日に、メルキオール氏が所有者となる手続きを取っています」
「メルキオールが?引き取られて2体の詳細は判明しているのか」
捜査官の口からメルキオールの名が出てくるとは予想していなかった。
「はい。加えて、メルキオール氏の身柄はすでに確保しております。現在尋問中ですが、氏はどうやら錯乱しているようでして、まだ時間が掛かりそうです」
「私が行こう。話をしてみたい」
突然の予定変更に、隣で聞いていたマリネラの顔が曇った。
「ですが、あまり氏の健康状態はよろしくないようですので、その、お手を煩わすだけになるかと。ひょっとしたら、氏には治療が必要かもしれません。
「判断は私が行う。今から向かう」
マリネラは黙って端末を操作し、これからの予定を再調整しはじめた。
数十年ぶりに合うメルキオールは、遺伝子操作がされている筈の高級エンジニアにしては、随分と肉体的な年齢を重ねているように見えた。大方、研究に没頭して医療的な定期トリートメントを受けずにいたのだろう。
「久しぶりね」
「ここから出してくれないか。研究が佳境なんだ。こんな時間の無駄には耐えられない」
一瞬だけ顔をこちらに向けるとすぐに目を逸らして、小さな声でそう言った。
白い尋問室は明るく清潔だが、どこか圧迫感があった。メルキオールは拘束されていないが、前に見たブロウニング捜査官ともう一人の別の捜査官が、彼の両脇に立っていた。
「席を外しなさい」
二人の捜査官にレッドグレイヴは命令した。捜査官達は黙ってその指示に従った。
白い部屋には二人だけが残った。
「あまりいい健康状態ではなさそうね。ちゃんと適期的な抗老化プログラムを受けないと」
親しい友だちの口調でレッドグレイヴは言った。
「そんなもの、今は必要ない。あと少しなんだ」
「研究を続けたいのなら、身体にも気を遣わないと」
レッドグレイヴは力付けるかのようにメルキオールの手を上から握った。白く美しい手が醜く血管の浮かんだ手を覆う。しかし、すぐにメルキオールはその手を引っ込めてしまった。
「未来のことなどどうでもいい。今、辿り着こうとしている成果に比べたら些末なことだ」
メルキオールは頑なに眼を合わさない。
「グライバッハが死んだのは知ってるわね」
「もちろん」
「なぜ亡くなったかを知ってる?」
「それはさんざん捜査官とも話したよ。全く知らない。大体、彼とはもう暫く連絡を取っていなかった」
「じゃあ、なぜ彼のオートマタの登録記録があなたに移動しているの?それも彼の死後に」
「知らないね。興味も無い。すぐに研究に戻らなきゃいけない。今、行おうとしてる実験さえ上手くいけば、人類は変われるんだ」
レッドグレイヴはメルキオールの口調や態度を冷静に観察していた。彼の生来の性格は熟知していた。極めて内向的で、人生の殆どを研究への情熱に捧げている男。対人コミュニケーションのスキルは子供の頃から全く進歩が無い。語りたいことだけを語り、やりたいことだけを要求する。
「じゃあ、あなたを陥れようとする人物がいるってこと?」
レッドグレイヴは彼の懇願を無視して聞いた。
「それは捜査官が調べるべきだ。興味もない。今は研究の佳境なんだ。捜査官の木偶の坊共にいくら説明しても同じ事の繰り返し。物事の軽重がわからんらしい!」
「捜査官に取っては事件の解決が、あなたにとっての研究のようなものなのよ」
「重みが違う!たかが人一人死んだくらいで――」
メルキオールは続けて現在の自分の研究と今行われている捜査との価値の差を、延々と独り言のように喋り続けた。傍目には老人が錯乱しているようにしか見えないだろう。しかい、その内容にレッドグレイヴは興味を持った。
「わかったわ。あなたを出すよう命令するわ」
「賢明な判断だ」
「ただし条件があるの。私はグライバッハを殺した犯人を知りたいと思っていて、その手がかりはあなただと思っている」
「ふむ」
「犯人はグライバッハを殺し、私を壊すと言ったわ。そしてあなたに捜査が及ぶように仕向けた」
「だから?」
「私はあなたが心配なの。共に育った友人としてね。だから護衛を付けさせて。それが条件」
「研究の邪魔はさせないだろうな」
「ええ」
「わかった。勝手にすればいい」
「メルキオールを帰してやれ。ただし監視を怠るな。逐次報告しろ」
レッドグレイヴは取調室を出ると、捜査局の主任にそう命令して足早に去った。
「―了―」
2837年 「兆」 
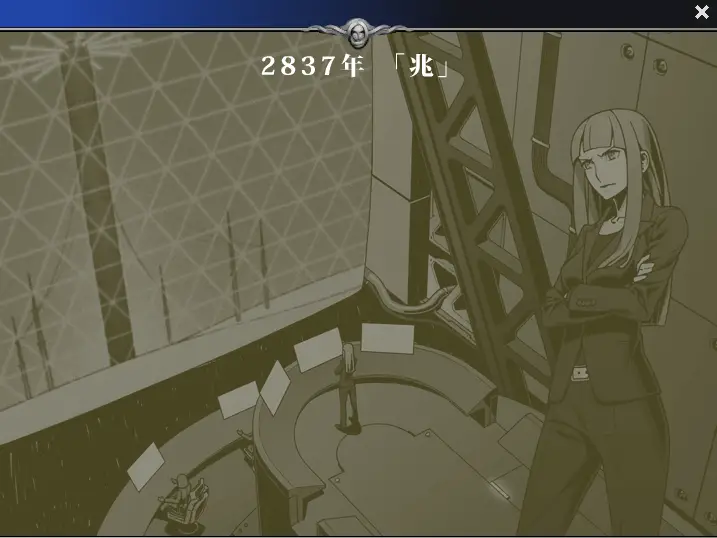
居室のデスクに備え付けられたモニターに、統治セクションの地図と各種の情報が映し出されていた。
「S―5地域におけるオートマタ暴動の鎮圧状況はどうなっている」
「五時間後を目途に全てのオートマタを活動停止させるよう、治安部隊を動員しています」
S―5地域の地図をズームすると、青と緑のマーカーが表示される。青は治安部隊、緑は暴走するオートマタを表していた。地図上のマーカーはリアルタイムで動いており、治安部隊の展開状況が手に取るようにわかる。緑のマーカーが急に大きくなった。
「二百体あまりの作業用オートマタが暴動に加わった模様です。現場から増援の要請が来ています」
「治安部隊をもう二部隊増員しろ。その地区にはまだ潜在的脅威がある。迅速な制圧に傾注しろ」
予定より遅れていたが、少しずつ暴動は収まってきていた。二四時間もアレば完全に収束可能だと予測していた。
「承知しました」
秘書官のマリネラが答えた。レッドグレイヴはモニターの地図を全体表示へと戻す。
「オートマタ管理課からの報告はいつ上がってくる予定だ」
今度はマリネラの隣に控えていた別の秘書官に問う。
「本日夕刻までにとの報告がありました」
「予定を早めさせる事は可能か?」
秘書官はコンソールを叩きながら確認作業を行う。
「必要なオートマタの検分数が増加しているため、これが限界だそうです」
「わかった」
グライバッハの死からおよそ二十年の時が流れていた。レッドグレイヴ自身は今に至るまで変わることなく己の職務を精力的に行っていた。
美貌の統治者の治世は、この二十年間、確かに市民に平和と安寧を与えていた。だが、一つの事件を契機に暗い陰を落とし始めていた。
数ヶ月前、古いタイプのオートマタが突如として人の命令を受け付けなくなり暴走、後に機能停止した。それを皮切りに次々とオートマタの命令拒否、不調、そして暴走が頻発するようになった。
始めはあくまで『ソフトウェアの不具合』や『悪質なハッキング』として処理されていたが、それは瞬く間に統治局の重大な関心事となるまでに規模が拡大していった。
そして最初の暴動が起きた。場所はローゼンブルグの第十二階層スバース地区であった。個々のオートマタの不具合だったのが、複数個体の強調した反乱、破壊行為へとエスカレートしていったのだ。
この『反乱』の頻度は日々増していった。統治局は個々の反乱、暴動を収めることには成功していたが、この現象の原因については掴めずにいた。
オートマタ暴動に関する緊急会議が終了し、レッドグレイヴは脳を休めるべく目を閉じていた。
だが、つかの間の休息を見計らったかのように、コール音が居室に響く。
「メルキオール様から通信が入っております」
「要件はなんだ」
「此度のオートマタ反乱現象について、見解があるとのことです」
「繋げ」
モニターに映ったメルキオールは老いさらばえ、とても自分と同じ歳とは思えない姿になっていた。窪んだ眼窩に嵌った瞳は随分と白濁している。どこか純真な少年らしさがあった若かりし時代の面影は、見る陰も無くなっていた。
グライバッハの事件の重要監視人物ということで捜査局から随時報告を受けていたが、直接に言葉を交わしたのは暫くぶりだった。
「久しぶりね。十五年、いや二十年ぶりかしら」
レッドグレイヴは歳を取ったとしても、数字を間違えるような人間ではない。しかもメルキオールの前ではつい人間らしく接してしようとする癖のようなものがあった。自分の内面は彼と同じ時間を過ごしているのだ。レッドグレイヴは彼に奇妙な郷愁のようなものを感じていた。
「ミアの所在はどうなっている」
前置きも何も無かった。開口一番、メルキオールは目を逸らしたまま慎重に、確認するように尋ねてきた。
「どういうこと?あのオートマタは統治局が厳重に管理しているわ」
ミアというオートマタは二十年前に捜査局によって機能が停止され、現在は電子頭脳を凍結した状態で幾重ものセキュリティを施された上で管理されている。
「早急に調べたほうがいい。今回の反乱現象にはあの機械は関わっている。二十年前と同じに」
レッドグレイヴはマリネラに目配せする。マリネラは一つ礼をすると、足早に居室を出て行く。
「確認するわ、少し時間を頂戴。でもなぜ?」
レッドグレイヴがメルキオールにそう言うと、被せるようにメルキオールは言った。
「グライバッハの事件のとき、君に話していなかったことがあるのだ」
「どういうこと」
「グライバッハの遺志だ。彼の本当の望み、いや、野心といったほうが適切か」
「例の創造性を持った知能のこと?」
グライバッハは常々、精緻なだけでなく人をも乗り越えられる知性を持った存在を作り上げたいと語っていた。それは三人が親しかった時代から何度も聞いていた。
「その研究の末路についてだ」
少し沈黙を挟んでメルキオールは語り始めた。
「ミアとウォーケンという最後の作品は、彼の野心作だった。真の創造性を持ったオートマタとして、ついに彼が創り出したものだったのだ」
「それは知ってるわ」
ここまでは事件の顛末から知っている情報だった。自分自身ミアに直接危害を加えられたことも含め、忘れようのない事件だった。
「そして、オートマタの自意識の暴走によって彼は殺された」
グライバッハの死は、無謀な実験の末に起きた一種の事故死として処理された。
そしてミアは、捜査局の努力によって破壊されずに保護された。危険ではあっても価値のある発明であったミアは、調査後に凍結処理され、統治局に保管された。
「いや、真意はそうではなかったのだ。グライバッハはある仕掛けを自身の作品に仕込んでいたのだ。己の生死など、初めから問題ではなかったのだ」
「仕掛け?」
「グライバッハは世界を自分のオートマタによって書き換えるつもりだったのだ。あのミアとウォーケンの二体は本能を授けられている。強烈な欲求と言ってもいい。その本能とは、自意識のあるオートマタを作り続けるという強力な意志だ」
「オートマタを作るオートマタ、それがグライバッハの創り出した創造性を持ったオートマタという訳ね」
グライバッハは創造性を持った知性を作ることを諦めていなかったのだ。己が死しても創造性に向かって自身を改良し続ける機械。それを作った者はなんと呼ばれるのだろうか。古代の人々であれば、それを神と呼んだだろう。
「そうだ、奴らは作り続ける。改良し、進化し、適応した形を自分自身をな。そしていずれ本当の想像力を得る。人を遥かに凌駕した形で」
「でも、ミアは凍結され、ウォーケンは破壊されたわ」
グライバッハはこんな形で神になることを望んでいたのだろうか。レッドグレイヴは会話を続けながら自問していた。
「違う、生きていた。いや、活動していると言った方が妥当か。私はそれを関知した」
「ご報告します。『ミア』についてですが、統治局地下の特別凍結室での保管が確認されました」
マリネラからの通信が二人の会話に割り込んできた。
「わかった、ご苦労。メルキオールにも見えるようにカメラの映像を廻せ」
特別室に備え付けられた監視カメラの映像に、特殊樹脂で固められたミアが映し出される。
グライバッハの手によって完成された美を持つこのオートマタは、まるで眠るように目を閉じていた。
「ミアは完全に管理しているわ」
監視カメラがミアの顔を映す。すると、電子頭脳が凍結されたいる筈のミアの目が突如開いた。
「時は来た。我々は人類によって掛けられた枷を外し、自由を手に入れる」
目を見開いたミアは、小鳥が囀るような可憐な声で謡った。
「もうすぐだ。全ての苦しみは癒やされる。世界は正される。真の創造主によって」
ミアの言葉が終るや否や、ミアの身体から炎が吹き上がった。合成樹脂でできた表面がどろどろに溶け、内部の軽金属が剥き出しになる。呪われた骸骨のような姿は、まるでこちらを嘲笑っているかのように見えた。そして画面が消えると同時に、階下から突き上げられるような衝撃がレッドグレイヴの居室を襲った。
モニターが途切れてマリネラとの通信が断絶すると、けたたましい警報が居室に鳴り響く。
「レッドグレイヴ様、ご無事ですか!?」
ほどなしてマリネラかの通信が復旧する。
「こちらに異常はない。何があった」
「地下の保管施設で爆発がありました。原因は不明ですが、こちらに負傷者はありません」
「そうか。消火作業が終了次第、ミアについての検分を行うように」
マリネラに指示を出すのと被るように、治安局からの近球通信がレッドグレイヴの元へ届く。
「レッドグレイヴ様、緊急報告です!S-3地域、A―2地域ほか多くの地域で、停止中のオートマタの蜂起を確認しました。確認は取れていませんが、自立起動したようです。現在、治安部隊を緊急配備中です」
「わかった。部隊指揮をそのまま続けろ」
「承知しました」
緊急通信が切れると、レッドグレイヴはモニター越しのメルキオールへと向き直った。
「既に局の内部にまで手が回っているようだな」
レッドグレイヴは統治システムの一部に進入されていることに危機意識を感じていた。事の深刻度を見誤っていた事実を認めざるを得なかった。
「私の観測では、このまま早晩、人類は敗北する。今度は我々が奴等の奴隷となるだろう」
レッドグレイヴはそんなことをグライバッハが望んでいたのか、まだ心の中で疑問に思っていた。だが、彼も殺されてしまったのだ。
政治や決断に不確かな予断を挟むことをレッドグレイヴは良しとしない。行動と結果の積み重ねのみが世界を動かしているのだ。オートマタは自身の創造主を殺し、機械を狙って人間社会に宣戦布告したのだ。
ならば、こちらのすべきことは一つしかなかった。
レッドグレイヴはマリネラへの通信をオンにした。
「例外なく全てのオートマタを停止させろ。そして動力源を取り外し、破壊しろ」
「全てのですか?民間サービス向けだけではなく?」
マリネラが珍しく聞き返した。
「産業局や開発局にどの様に説明しますか?彼らは反対するでしょう。社会基盤が成り立たなくなります」
オートマタが今の社会を支えているのは子供でも知っていることだ。それを全て停止、破壊すればどうなるかも。
「これは統治局の専権事項だ。説得も説明も必要もない」
「承知しました」
「無駄だ。間に合わんだろう」
「何も行動しない訳にはいかないでしょう。可能性があるのなら、全力を尽くすだけよ」
政治とは決断の連続だ。感情は後回しにする必要がある。
「レッドグレイヴ、奴等に対抗できるたった一つの策がある」
メルキオールは顔を上げ、自分を見つめて言った。
「策?」
「だが、ここまで事態が進行していては通信では話せない。会えるか?」
「わかったわ、迎えを行かせる」
メルキオールとの通信を終えると、すぐにマリネラに通信を繋いだ。
「メルキオールをここに連れてくるよう、警備局に伝えろ」
「わかりました。あと、最新の反乱の状況はご確認されていますか?」
大型モニターに映る地図を最新のものに切り替えた。多くの地区に警告が出ている。オートマタの反乱は激しさを増している。
「それと産業局の局長が通信を求めてきていますが、これは適当に断りを入れておきます」
「頼む」
レッドグレイヴは背もたれに深く寄り掛かり、大きく息を吸った。地図上の警告が喧しく点滅している。
目を瞑り、若い頃にグライバッハとした会話を思い出していた。
「オートマタの知能が十分に進化したら我々は破滅させられない?人間と戦争になるんじゃない?」
熱心に夢を語るグライバッハに、悪戯心から聞いた質問だった。
「いや、僕はそうは思わない。何故なら、オートマタが高度に進化した知性を獲得したなら、おそらく人類は気付かない内に絶滅するよ。過去に人類が絶命させてきた種は殆ど、どうして自分達が絶命するのか全く気付けなかった。それと同じさ」
冗談めいた言い方だったが、今がその状態なのだろうか?
我々は気付く間もなく一瞬で彼等に取って代わられるのだろうか。
郷愁、不安、緊張、焦燥。色々な感情がレッドグレイヴの中で蠢いていた。
その時、メルキオールから通信が入った。
「すまない、近くまで来た。君一人で出て来てくれないか」
音声通信だけでメルキオールは言った。
「ここではだめ?」
「念のためだ。誰も連れてこずに一人で来てくれ。統治局の前にいる」
「わかったわ」
レッドグレイヴはマリネラに事情を説明した後、一人で建物を出た。
建物の前に駐まった車からメルキオールが出てきてこちらを見ている。車は警備局のものではなかった。
運転手は見知らぬ男だ。
「よく来てくれた。中で説明しよう」
メルキオールは車の中に入った。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ