ヴィルヘルム
【死因】
【関連キャラ】グリュンワルド(上官)、メリー、ユーリカ(拷問)
3394年 「残光」 
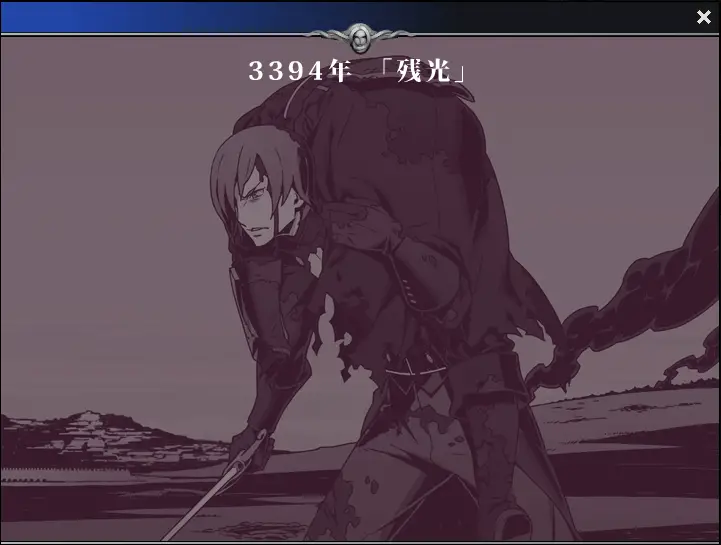
夜が明けた。空は白み、陽の光がトレイド永久要塞を照らし始める。
要塞に陣取るルビオナ王国軍及び傘下の連合軍兵士達には、緊張しながらもある程度の余裕があった。
そんな中、ヴィルヘルムはロンズブラウ軍の陣地で今回の作戦内容を再確認していた。
「何だ、あれは……」
誰の呟きだったかはわからない。ただ、巨大な機影が見えた。
それが帝國軍の擁する巨大戦艦ガレオンであると認識する間もなく、要塞に轟音が響いた。
一瞬の出来事だった。ガレオンの砲撃によりルビオナ王国軍が駐留していた陣地の一部が餌食となり、瓦礫を残すのみとなった。
兵士達は艦棲のように吹き飛び、硝煙と血の臭いが周辺を支配する。
恐怖に乱れた統制は更なる被害を呼んだ。帝國兵の突撃に対応できなかった王国軍は、手の打ちようもないまま蹂躙された。
「殿下、このままでは我が軍にも甚大な被害が」
ヴィルヘルムは事態を重く見てグリュンワルドに指示を仰いだ。ロンズブラウ軍は直接の砲火に曝されていないために統制を保っていたが、兵士達の間には恐怖と動揺が走っていた。
「全軍に後退を指示しろ。あの化け物から離れて、機を伺う」
「了解しました!」
「グリュンワルドの指示を集結させていた兵士に伝える。ヴィルヘルムよりも年若い彼等の顔は、やはり強張っていた。
ヴィルヘルムにトレイド永久要塞に派兵する部隊を率いる命令が下ったのは、つい数ヶ月前のことだった。
要塞に出兵する部隊は、大将であるグリュンワルドを含めても、ヴィルヘルムが最年長であった。
ロンズブラウ王国内では『王国軍、いまだ勢い衰えず』と報じられているが、幾度にも重なる派兵によって兵は疲弊している。
よって今回のトレイド永久要塞への派兵は、年若い体力のある若年兵が集められた。
ヴィルヘルムを含め、上層にあまり関与していない人間はそう聞かされていた。
「君がいる部隊は、苛酷な戦場でも必ず生きて戻ると聞いている」
「私だけの力ではありません。隊長や部隊の連携があってこそだと思っています」
「謙遜するな。此度の活躍も期待している。グリュンワルド王子殿下に粗相のないようにな」
「はっ」
様々な考慮からヴィルヘルムは昇進し、『トレイド永久要塞派遣部隊大隊長』という、周囲も当人も困惑するような、大仰な肩書きを与えられたのだった。
巨大戦艦に火柱が上がるのが見えた。ルビオナ王国軍の装甲猟兵による大火力攻勢だった。
「今だ!突撃せよ!」
グリュンワルドの命令が下った。大将自らガレオンが墜落するであろう地点に向かい、先陣を切って突撃していく。
グリュンワルドが駆け抜けた後に残るのは、首から血を噴出して痙攣していたり、心臓を一突きで貫かれたりした帝國兵の死体だった。
返り血で深紅に染まったマントを見失わないようにしながら、ヴィルヘルムも後に続いた。
「急げ、殿下をお守りしろ!」
戦場で鬼神の如く戦うグリュンワルドを見るのは、これが初めてだった。
恐ろしい王子、薄気味悪い黒太子。そう影で噂されていることはヴィルヘルムも知っていた。
風のように戦う彼の姿は確かに恐ろしかったが、同時に見蕩れたくなるような、奇妙な清々しさがあった。少なくともヴィルヘルムにはそう見えた。
ガレオンの甲板では、王国軍と帝國軍が入り乱れていた。
戦いの中心に異様な女性がいた。指揮杖を持って白い軍服を鮮血に染めた、美しいがどこか不気味な女将軍だった。
グリュンワルドがその女将軍に向かって駆けていく。ヴィルヘルムはグリュンワルドに襲い掛かろうとする帝國兵を切り伏せていた。
何人の帝國兵を切り捨てただろうか。ヴィルヘルム自身も返り血や怪我で血塗れになっていた。 振り返ると、グリュンワルドが女将軍を刺し貫いていた。
勝負はあった。
生き残っている王国軍、ロンズブラウ軍の兵士から、歓喜とも一つかないどよめきが上がった。
――ビチャリ。
そのどよめきは、突然発せられた不快な音により強制的に中断された。
「さあ、死者達。お前達の手で、さらなる死を生み出しなさい!」
ヴィルヘルムの目に映ったのは、緑色の体液を滴らせる女将軍の、喜びとも叫びとも受け取れる声を上げる姿だった。
その女将軍の姿を遮るように、首と胴が千切れかけた死体が起き上がる。身に着けているものは王国軍の兵装だった。
ぐちゃり、ぐちゃりと、濡れた音があちこちから発せられる。
「化け物だ!」
「う、うわああああああ!!」
一瞬にして、歓喜の場が地獄と化した。
戦場は混乱を極めた。死人となった兵士は敵も味方も関係なく生者に襲い掛かった。
統率など取れる筈もない。恐慌状態に陥った兵士達が死者から逃れるべく退却していく。
だが逃げる先でも死者が復活し、為す術もなく喰われていった。ヴィルヘルムも逃げる兵士達の波に呑まれ、ガレオンの甲板を走らざるを得なかった。
不意に背後から笑い声が聞こえた。それがグリュンワルドの声だと気付くのに、さして時間は掛からなかった。
奇妙な清々しさの正体は快楽であるのだと、ヴィルヘルムは気付いてしまった。
「死者どもよ、ただの肉塊へ戻れ」
凄まじい剣圧で死者達が吹き飛んでいく。しかし直後に轟いた爆音と共に、グリュンワルドは甲板から弾き飛ばされていった。
ヴィルヘルムの身体は咄嗟に動いていた。どれだけ恐ろしかろうと、自国の王子をその場に打ち捨てていける筈がなかった。
グリュンワルドの笑い声と言葉が耳に残っていた。ヴィルヘルムはその幻聴を振り切って駆ける。
死者を切り捨て、生者の波に揉まれながらも、どうにか地面に 降りることに成功した。
地上にも死の波が迫っていた。新たに製造された死者達は、鼠算式にその数を増やしていく。
トレイド永久要塞が死者に埋め尽くされるのは、時間の問題だった。
地面に打ち付けられたグリュンワルドの姿は、惨いものだった。
利き手は肘先が千切れ、死者に喰われた場所からは内臓がはみ出し、それもまた喰い千切られていた。端正な顔も顎の周辺で醜く潰れ、辛うじて呼吸だけをしているような有様だった。
ヴィルヘルムは自身より大柄のグリュンワルドを抱え上げると、背後に迫る死者の軍勢から逃れるべく、必死で足を動かした。
ロンズブラウ軍陣地に程近い場所まで進んだところで、後詰めに控えていた小隊となんとか合流することができた。
「大隊長!殿下は……」
死者に喰われて凄惨な姿を曝すグリュンワルドを一瞥した兵士が、青い顔でヴィルヘルムを見た。
「まだ生きておられる。衛生兵のところへお運びしろ。俺はここで死者達を食い止める」
「大隊長、ですがこれでは――」
「我々は配下として、殿下をなんとしてでもロンズブラウ王国に護送する義務がある!わかったら行け!」
「り、了解です!」
兵士にグリュンワルドを任せた後、その場に残ったヴィルヘルムは必死で剣を振るった。死人の動きはひどく鈍かった。
それでも、死人はまるで更なる犠牲者を求めるように、後から後から出てきた。
帝國兵も王国兵も、ロンズブラウ王国の兵士さえもが死人と化していた。
死人の一体に喰いつかれる。動きが鈍ったところを次々と襲い掛かられた。
ヴィルヘルムは死人の山に埋もれていった。光が遮られたが、自分の身に起こっている事は音と感覚だけで理解できた。
身体の肉が奪われていく。肋骨と脛骨が音を立てて削られていく感覚がある。死人の骨や歯が全身に突き立てられ、穴の開いた箇所から内臓や肉が引き摺り出される音がした。
血が吸られていく。頭蓋骨が音を立てながら喰い破られたのがわかった。大脳に何かが触れたのだろうか、反射的な嘔吐に襲われたが、吐いたのは血の塊だった。
ヴィルヘルムはそれでも抵抗していた。
感覚の残る右腕を振るうと、死人の一部が断絶されて光が漏れた。その隙間から見えたのは、グリュンワルドを背負って山道を下るロンズブラウ兵の姿だった。
まだ駄目だ。ここでもし自分が事切れれば、次は必死で逃げる兵士とグリュンワルドが呑まれてしまう。
そう考えると、残っていた心臓が強く脈動した。脈動と同時に、ヴィルヘルムの全身から吸い尽くされた筈の血液が大量に噴出する。
残っていた右腕を振るって死人の肉を掴む。すると、ヴィルヘルムが掴んだところから死人の肉が崩れていった。
それはヴィルヘルムに触れていた死人に伝播していった。次々と死人が崩れ去っていくのに合わせて、ヴィルヘルムの出血が止まる。
死人が生者だった頃の生命力の残滓を吸い上げている、ヴィルヘルムははっきりとそれを感じ取った。
蠢く死人の山が楔を失ったように崩れ去る。
ヴィルヘルムは残された肉と臓物と血でできた汚泥の中に、一人倒れ伏していた。
「ぐ……おぉ……」
岬き声を上げながら、ヴィルヘルムは覚束ない感覚の中、流れ出る血とこぼれる肉を引き摺りながら山の急斜面を転がり落ちた。
土地勘のないヴィルヘルムは、自分が何処にいるかわからなかった。
だが身体の大部分を失い、内臓や骨はおろか脳髄さえ露出しながらも生き続けるこの姿を、誰かに見られることだけは避けねばならなかった。
大部分の感覚は麻痺していた。神経も断裂しているのかもしれない。ヴィルヘルムに動く力は残っていなかった。
どのくらいの時間が経ったのか。虚ろな意識でどこか遠くを見ていると、不意に全身を鋭く強い痛みが走った。
麻痺していた感覚が急速に戻ってくる。傷口の脈動がはっきりとわかる。残った肉が少しずつ再生していくのを自覚する。小さな音を立てながら骨が形を取り戻していくのが感じられる。
ぼやける目を凝らして内臓を失った腹部を見ると、残った内臓のかけらが蠢き、新たに内臓を作り出していくのが見えた。
「やはり、これでも俺は……」
言葉を言い終わらぬ内に、全ての思考を遮断する程の痛みと疲労がヴィルヘルムを襲う。
そのまま、ヴィルヘルムの意識は闇に呑まれていった。
「―了―」
3394年 「指嗾」 
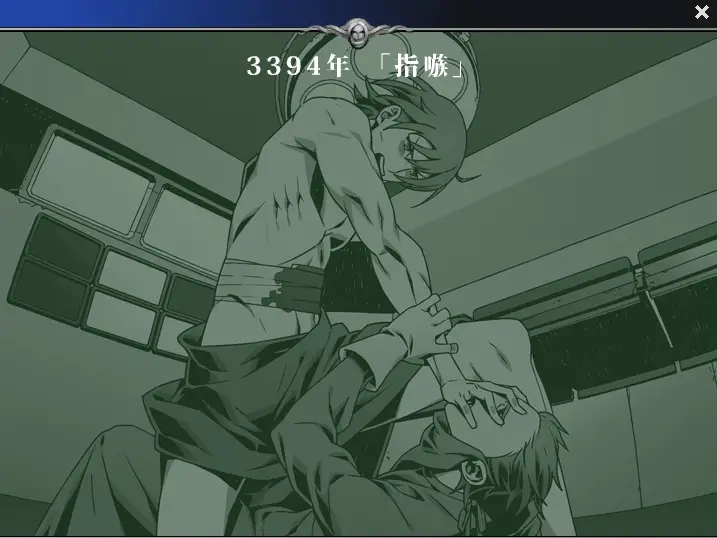
気が付くと、両手両足を鎖で縛られていた。
辛うじて動く頭を動かして周囲を見回す。どうやら冷たいコンクリートの床と壁に囲まれた牢屋のようだ。小さな窓に取り付けられた鉄格子の外を見やる。明かりの数が少ないようで、目を凝らしても先は伺えない。
大掛かりな身体再生を行った後は、確実に何日も眠り続ける。その間は何をされても目を覚ますことはない。ましてや身体の半分以上を失った上での再生だ。一体どれ程眠っていたのか見当もつかなかった。
「お目覚めですか」
感情が籠もっていない女の声が響く。ランプに照らされた女は冷たい目でヴィルヘルムを見ていた。
何故。どうして。そのような疑問ばかりがヴィルヘルムの頭を駆け巡る。
女には見覚えがあった。古い記憶から、この女がユーリカと呼ばれていたことを思い出す。そして、とても危険な組織の構成員であるということも。
ヴィルヘルムはユーリカが属する組織で『偉大なる首領を蘇らせるための鍵』だと言われ、研究者達に身体を弄り回された過去があった。
あからさまに死ぬような目には遭わなかったものの、昼も夜も関係なく、想定しうる限りのあらゆる傷害を負わされた。
十数年前の悪夢がヴィルヘルムの中に蘇る。
「そんな……」
「生きているとは予想外でしたね。報告を聞いたときは驚愕しました」
「もう俺は用済みだろう。何故こんな……」
「ええ。あの時は確かに用済みでした。でも、生きているのなら話は別です」
ユーリカは目を細める。光の宿っていないその目から、過去に組織から受けた仕打ちを連想させられた。
「これから俺をどうするつもりだ?」
「化け物がそれを知る必要はありません」
それだけを言うと、ユーリカはヴィルヘルムに背を向けてどこかへと去っていった。
それから間もなく、ヴィルヘルムは組織の研究者達に拘束され、消毒液の臭いが充満する部屋に運ばれた。
手足は樹脂のようなもので手術台に固定され、身動きが取れない。
目の前の研究者達は皆、どこか嬉々とした表情でヴィルヘルムを眺めている。
「お前らの首領は戻ってきたんだろう、もう俺は必要ないはずだ……」
「せっかく面白い実験材料が戻ってきたんだ。この機を逃すわけがないだろう」
「全ては善き世界のためだ」
「化け物が世界の礎となるんだぞ?感謝はされど、憎まれる筋合いはない」
研究者達は喜びの表情を隠すことなく、口々に言う。
皮膚を切り裂き、骨を砕き、心臓さえ取り出しても再生するヴィルヘルムは、格好の研究材料でしかない。
研究者達はヴィルヘルムを『人間』として見てなどいない。彼らにとってヴィルヘルムは、どれだけ過酷な実験を繰り返しても無限に再生する『生きた玩具』であった。
「が……うぐ……」
ヴィルヘルムは低い呻き声を上げる。
腹部と頭部に移植された何かの植物が、ヴィルヘルムを養分にして根を張っていた。
痛みを抑える薬物を投与されてはいたが、常人より遥かに早く薬の効果が切れるヴィルヘルムには、あまり意味を成さなかった。
ただひたすら痛みに耐えてやり過ごす。ヴィルヘルムにはそれしか方法がなかった。
「再生能力に変化は見受けられん。 植物の遺伝子構造も検査したが、そちらにも変異なしだ」
「養分にはなれど、影響はないか」
「どうする?」
「植物を切除し、別の実験に切り替える。植物が駄目だとすると、次は昆虫だな」
「そうだな。これの再生を待って、次の実験に取り掛かろう」
気絶することもできず、ヴィルヘルムは研究者達の言葉を虚ろな表情で聞いていた。
終わらない実験、終わらない痛み、終わらない苦しみ。
「もう、嫌だ……」
このまま精神が壊れてしまえばどれ程楽だろうか。そんなことを思いながら、為すがままにされていた。
「ほう、言葉を喋る余裕があったか。おい、あれを使うぞ」
「あれか?あれはまだ臨床の段階ではないぞ。脳に強い作用がある」
「だからこそだ。どうせ薬で発狂したところで、暫くすれば元に戻るんだ。かつての実験で実証済みだよ」
研究者の言葉で、自分が何度も正気を失っていたことを初めて知った。その前後のことは全く記憶にない。己の異常さは心にも及んでいたのだ。別に心が壊れなかったわけではない、ただ身体と同じように、心も再生しただけだったのだ。
「なら問題ないな。すぐに始めよう」
まだ苦しみが続く。それも、正気のまま死んだ方がましのような苦しみが。ヴィルヘルムは絶望するしかなかった。
脳に強い作用があるという薬物が投与されてさほど経たぬ内に酩酊し、そのまま意識が途絶えた。
気が付くと、最初にいた牢屋の中で手と首に鎖が繋がれた状態で転がされていた。
「ぐ……うう……」
腹部が痛い。その箇所を見ると、菌が入らないように最低限の処置だけが施された腹が見えた。包帯から滲む鮮やかな血が、まだ再生の途中であることを窺わせた。
ヴィルヘルムは牢屋の中で深い溜め息を吐いた。
少しでも再生が遅くなればどこかへ放逐されないだろうか。そんなことを考える。
ふと、死者の軍勢から助かった時のことを思い出した。あの時は、ここで倒れる訳にはいかないと思っていた。あれは自らの強い意思だった。
もしやと思い、ヴィルヘルムは自分の腕に思い切り歯を突き立てた。痛みが走るも、そのまま食い千切らん勢いで皮膚を破る。
血の味が口腔内に拡がったところで腕から口を離す。くっきりと歯の形に傷付いた腕に意識を集中させ、その傷が治っていく過程をイメージする。ややあって、自身が認識しているよりも 早く傷は治った。腹部に付けられた保護布を剥ぎ取って傷口を見てみるが、そちらはあまり変化がない。むしろ、再生する速度はかなり落ちている。
やはり、とヴィルヘルムは思う。この異常な能力を自分の意志で操れるようになりかけていると、確信めいたものを感じた。
ヴィルヘルムは組織からの脱出を決意した。過去のように傷の治りが遅くなっても、捨て置かれる可能性は低い。このままこの場所でいつ終わるともわからない状況を受け入れることはできなかった。
程なくして、その機会はやって来た。
「今日はずいぶんと耐えるな」
「よし、もう少し深く抉ることにしよう。前に植え付けた昆虫の卵探しだ」
二人の研究員は、必死で痛みに耐えながら機会を伺うヴィルヘルムを嘲笑うかのように、腹部をメスで切り裂く。
実験が終わって拘束が解かれるまでは何としても耐えなければ、という一心で、ヴィルヘルムは気絶しないように歯を食いしばる。
「見つからんな」
「幼虫の姿もない。排出されたのか?もしそうなら観察が必要だな」
研究員達は口々に言いながら、ヴィルヘルムの穴の開いた腹部に簡単な保護布を当てるだけの処置をする。
「もう一度卵を植え付けて、今度は皮膚が再生しないようにする必要がありそうだ」
「再生を阻害する薬を開発しなければな」
次の実験への好奇を隠すことなく会話する研究員の一人が、 ヴィルヘルムの拘束を解く。その際に、ヴィルヘルムはその研究員にしがみつくようにして倒れ込んだ。
「おい、何をしている」
「急に倒れ込んできたんだ。」
「気をつけろ」
様子を見やった研究員の視線が外れたその瞬間、ヴィルヘルムはしがみついた研究員の生命力を吸い上げる感覚をイメージした。
「あ、がが……い、痛い、痛い痛い痛い痛い!!!は、腹、腹がああああああ!」
研究員の腹部から血が噴出し、悲鳴が上がる。同時に、ヴィルヘルムは自分の腹部の痛みが消えていくのを感じた。研究員は突然発生した痛みに転げ回り、実験台にぶつかった。二人揃って床に倒れこむ。
「ば、化け物め、何をした!」
もう一人の研究員は手元にあったメスや道具を手当たり次第ヴィルヘルムに投げつけた。悲鳴を上げていた研究員は痛みのあまり気を失ったらしく、痙攣を繰り返している。
ヴィルヘルムは道具が身体に当たるのにも構わず、もう一人の研究員の顔を掴んだ。そして、先程と同じように生命力を吸い上げる。
「ひ……やめ……!」
「殺しは、しない……。俺は、逃げられればそれでいい」
研究員達が動かなくなったのを確認すると、その衣服を奪い、実験室から休憩室に繋がる扉を開けた。休憩室は静かだった。誰かが入ってくる様子はない。視界に入った窓から外を覗くと、建物のすぐ傍を川が流れていた。
川の深さはわからない。だが逃げ道はここしかない。多少浅くて着水に失敗したところで、骨折程度ならすぐに回復するのはわかりきっている。
一時の痛みと、脱出に失敗した後に続く拷問の如き痛みとどちらが良いか。
躊躇うようなことではなかった。迷うことなく前者を選んだヴィルヘルムは窓を開ける。
そこで実験室の方が俄かに騒がしくなる。他の研究員達が異変に気付いたようだ。 幸い、窓は人一人程度ならば潜り抜けられる大きさであった。ヴィルヘルムは急いで窓から身を乗り出すと、その勢いのまま川へ向かって飛び込んだ。
幸い、川はそれなりの深さがあり、そこそこ強い流れがある箇所だった。
ヴィルヘルムは水面から顔を出すと、泳ぎ始めた。研究員達の生命力を吸ったせいか、身体が驚く程に軽いのも助けになった。
とにかくあの実験施設から離れなければ。川の流れに合わせるように、ヴィルヘルムはひたすら下流を目指した。
「―了―」
「変異」 
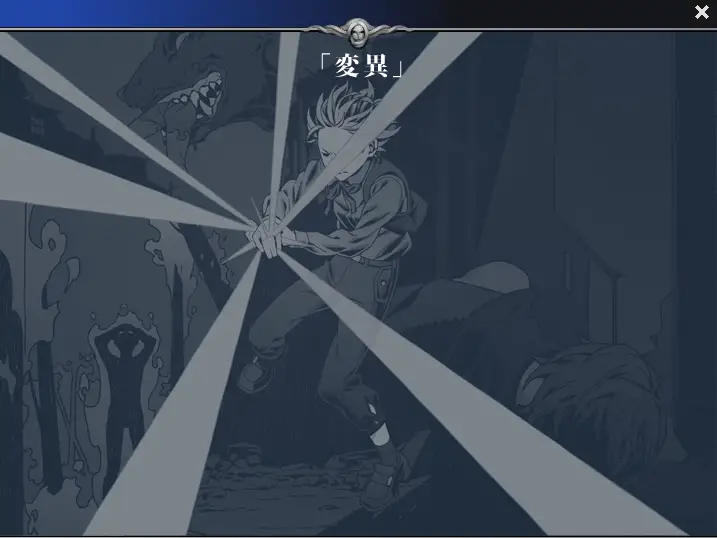
石造りの街並みは無残に崩壊していた。
この街に住む人間は誰も、突如広場に現れた黒く昏い『何か』を理解することができなかった。
その『何か』は荒れ狂う嵐のように街を破壊し、浸食するように広がっていった。
ヴィルヘルムは家族と共に、その『何か』から街の住民を逃がしていた。
彼の家は守人の家系であり、土地に災いが起きた時は率先して人々の救助に当たる役目があった。
『何か』の浸食は留まるところを知らない。
街の人々を救助し終えて自分達が脱出しようとした時には、もう遅かった。
ヴィルヘルムの家族に黒く昏い「何か』が迫る。もう助からないのだと覚悟した。身体が動かない。迫り来る死の匂いを感じ取りながら、ヴィルヘルムは目を閉じた。
その時だった。父親がヴィルヘルムの手を取った。
「お前に、希望を……」
「父さん?」
言葉の意味はわからない。だが、大切なものが自分に託されたことだけはわかった。
石のようなものを握った感触があった。その瞬間、ヴィルヘルムの身体を均熱が襲った。全ての骨肉を焼き尽くさんとするその熱に、ヴィルヘルムは意識を手放した。
ヴィルヘルムは一人、荒野を歩いていた。
今がいつで、どうしてこんな場所にいるのか。そもそもどうやってこの場所まで来たのか、意識がはっきりするまでどうやって生活していたのか。何故自分だけが助かったのか。
ヴィルヘルムには何もわからない。生き残ってしまったという罪悪感だけが、ヴィルヘルムの胸中にあった。そんな彼を嘲笑うかのように、災厄が次々と襲い掛かってきた。
ある時は山林の火災に巻き込まれた。魔物が山に火を放ったらしい。
野生の動物と一緒に逃げ惑う内に、火に飲み込まれた。焼かれていく感触は確かにあったし、全てが熱に飲まれていくのを感じていた。
気が付くと、水辺で倒れていたらしいところを、近辺で暮らしていた猟師に助けられた。
またある時は、魔物に追われていた運び屋に、魔物を欺くための囮にされた。
「悪いな、ボウズ。俺達を待ってる仲間がいるんだ」
必死の抵抗も虚しく魔物に蹂躙された。筈だったが、またしても気が付くと無傷で荒野に取り残されていた。
「何で、俺は……」
そんな目に遭ってどうして生きているのか。何もかもがわからなかった。
当てもなく彷徨った末に辿り着いたのは、どこかの国のスラム街だった。自分の身体が普通ではないと自覚したのは、この頃だった。
すれ違った時にちょっと肩が当たってしまった。ただそれだけのことだったのに、その相手に目をつけられた。ヴィルヘルムがぼんやりとした顔をしていたのも、彼らの目を引いたのかもしれない。
「あぁ?何だてめえ」
「すみま……せん……」
謝るヴィルヘルムを彼らは許さなかった。日頃の苛立ちを解消するかのように、ヴィルヘルムをひたすら殴り、蹴った。
抵抗する力など無かった。ただただ、彼らの気が治まるのを待つしかなかった。
そうする内に、強烈な一撃が後頭部を襲う。ヴィルヘルムは岬き声を一つ上げて、完全に動かなくなった。
「アニキ、コイツ動かなくなっちまいましたよ」
「ほっとけ。死体が一つ増えたところで、誰も気にしやしねえよ」
そんな声が遠くから聞こえたような気がしたが、意識は遠のいていくだけだった。
目を覚ました時にはすでに朝だった。路地の片隅に打ち捨てられていたヴィルヘルムは、起き上がることもせずにぼんやりと 地面を眺めていた。
そこに、ヴィルヘルムを痛めつけた男達が通り掛かった。
「何だ、お前……。昨日あれだけ痛めつけたのに……」
「……アニキ、こいつおかしいぜ!」
男達はヴィルヘルムが無傷であることに気が付いた。自分達が負わせた怪我が綺麗に治っている。その事実に青ざめた。
「お、おい、逃げるぞ。こいつは化け物だ!」
自分としては意識が闇に包まれ、次に意識を取り戻した時には傷が癒えていた。それしかわからない。自分がどれ程の怪我をしたか知る人物もいないため、何が起きたか知りようがなかったのだ。
傷が癒える速さが常人とは違うのだ。どのようなことになっても死ぬことはないのだ。そう認識したのはこの時だった。
何があっても死なない。そのことを自覚したヴィルヘルムは、スラムから再び荒野に飛び出した。人の目がある場所は怖かった。化け物と言われることを恐れた。
荒野を彷徨っている内に、ヴィルヘルムは魔物に襲われた。臓腑も脳髄も肉も、全て魔物にくれてやるつもりだった。
どうせ、また気が付いたら無傷なのだろうという絶望がちらついたが、すぐに激痛でそんな思考も奪われた。
「おい、誰か倒れてるぞ!」
「ひどい怪我だ!とにかく聖堂へ運べ!」
人の声が聞こえて意識が微かに浮上した。やはり助かってしまった、そんな絶望感だけがあった。
次に目が覚めると、ヴィルヘルムは薄暗い部屋で拘束着を着せられて、動けない状態で寝かされていた。
「目覚めましたか」
無表情の女が目の前に立っていた。彼女はヴィルヘルムを冷たく見下ろしている。
「ここは……」
「それを知る必要はありません。あなたは今から、我らの首領を救うための礎となるのですから」
「何を……」
「光栄に思いなさい。神を救うための贄となることを」
何もわからぬヴィルヘルムを待ち受けていたのは、今までの災厄さえ生温いと思わせる程のものだった。
白衣の男達はヴィルヘルムを徹底的に害した。肉も、臓腑も、脳細胞も、ありとあらゆる箇所が何度も切り取られ、何度も擂り潰された。あらゆる物を溶かす液体に首から下を全身浸けられた。全てが凍り付くような場所に放置された。魔物と一緒に閉じ込められた艦の中で、ただ食われていく様を観察されたこともあった。
それでも再生し、生き続けるヴィルヘルムに、白衣の男達は目の色を変えて研究していた。死なない細胞、死なない化け物。彼らはそう口にしながら、ヴィルヘルムの身体が持つ神秘に取り憑かれていった。
ヴィルヘルムは痛みで気絶し、痛みで目を覚ますことが恒常化しつつあった。酷い時には臓腑や脳髄を削られている最中に意識を取り戻すことさえあった。
精神も折れる寸前であった。むしろその程度で留まっていること自体が奇跡だった。
後にこれは間違いだと知るのだが、この時のヴィルヘルムにそれを知るような余裕も、知らせるような人物もいなかった。
しかし、身体は限界を迎えつつあった。傷の再生速度が落ちていった。傷付けられた身体は、数日が経過しても回復の兆しを見せなくなった。
「再生能力が落ちているな」
「さすがに限度があるか。どうする?」
「ユーリカ様に指示を仰ごう。ギュスターヴ様の再生はすでに開始されている」
朦朧とする意識の中、そのような会話が聞こえてきた。
それから暫くの後、ヴィルヘルムは何処とも知れない場所に廃棄された。
正確には、気が付いたら塵捨て場のような場所に放逐されていたと言うべきか。
流れる血と臓腑の欠片を、ヴィルヘルムはぼんやりと見つめていた。
彼らによって傷付けられた身体は再生する兆しを見せない。感覚は完全に麻痺し、痛みがあるのかないのか、何処が傷付いているのか。その程度のこともわからなかった。
何故目を覚ましたのだろう。あのまま自覚なく死んでいればよかったのに。
そんなことを思いながら、明るくなりつつある空を見上げていた。
何故このような酷い目に遭い続けながらも、苦痛と共に生きなければならないのか。そのことをヴィルヘルムは考える。
あの時、黒く昏い『何か』から一人だけ助かってしまったことに対する罰なのかもしれない。
守人の家に生まれながら、何一つ守れなかったことに対する罪なのかもしれない。
でも、それももう終わりだ。再生することのない身体を見遣って、漠然とそう思った。
やっと家族のところへ行ける。やっと苦しみから解放される。そんなことを思いながら目を閉じた。
「――さん!」
誰かが呼ぶ声が聞こえた。
重く重くのし掛かる瞼を無理矢理こじ開けると、一人の少女がヴィルヘルムを心配そうに見つめていた。
先程まで自分の視界を満たしていた明るい空は無い。目の前に 広がるのは草木の緑。
どうやら過去の夢を見ていたようだと、ぼんやりとする頭でヴィルヘルムは思った。
「お兄さん、大丈夫!?」
「き、 み……は……」
「待ってて、いま誰か呼んで来るから!」
少女の足音が遠ざかっていった。
「―了―」
3396年 「仔」 
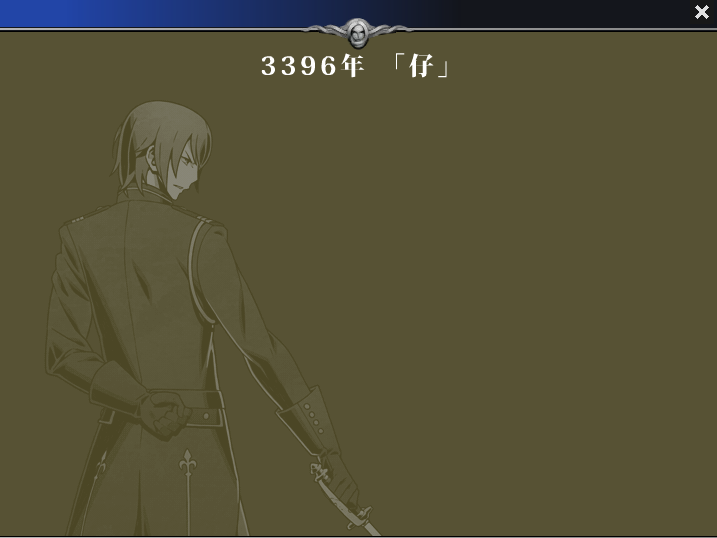
真新しい軍服に、苦楽を共にした軍学校の同期達。厳しい面差しの上官が訓示を述べている。
ヴィルヘルムの意識はロンズブラウ軍に入隊した頃の夢を見ていた。
組織からゴミ同然に捨てられたヴィルヘルムは、魔物か何かの手によって運ばれていった。
そこで魔物の餌になる筈だったヴィルヘルムを助けたのは、周辺の魔物討伐に派遣されていたロンズブラウの軍隊であった。
ロンズブラウに保護されたヴィルヘルムは、隊を率いていたルドガー・クルトという初老の男性に引き取られ、療養することとなった。
長きに亘る凄惨な実験の弊害なのか、ヴィルヘルムの身体は常人と同じ程度にまで修復速度を落としていたが、逆にそのお陰で、誰からも不審がられることはなかった。
間もなくヴィルヘルムの傷は癒えた。療養中に得た知識によって、自身の故郷はおそらく《渦》に亡ぼされたのだろうという考えに行き着き、今後の身の振り方について悩むようになった。
「これからどうするつもりだね?」
「わかりません。故郷は《渦》によって滅んでしまいましたし……」
「ふむ。行く当てが無いのなら、我々の軍に入隊してみるのはどうかな?」
悩んでいたヴィルヘルムに、ルドガーは再び手を差し伸べた。
「軍隊、ですか?今まで従軍の経験は無いのですが……」
「もちろん、無理にとは言わん」
詳細を聞けば、ロンズブラウ軍は《渦》から這い出てくる魔物から国と国民を守るために、常に兵を求めているのだとか。
「でも、何もしないよりはいいかもしれません。わかりました。入隊しようと思います」
少し悩んだ末、ヴィルヘルムはルドガーの提案に領いた。
再び放浪したとしても、あの組織にまた捕まってしまうかもしれない。そのような危険があるのなら、ロンズブラウ軍に入る方が未来があると考えたのだ。
「とはいえ、いきなり従軍させる訳にもいかんな。確か王立の軍学校はまだ生徒を募集していた筈だ。まずはそこで勉強してみてはどうだ?」
「勉強もさせてもらえるんですか?」
「もちろん。こんな時勢とはいえ、学はあるに越したことはない」
「ありがとうございます!」
ヴィルヘルムは正式にルドガーの養子となり、ロンズブラウ王国の軍学校へと入学した。
ここまで親身になってくれたルドガーのためにも、勉学はもちろん、しっかりと従軍できるような資質を備えなければならない。
ただ、いまは他人と何も変わらない身体能力だが、いつ身体に宿る忌まわしい力が戻るかわからない。再び力が戻ったときに周囲に悟られぬよう、なるべく傷を負わないように強くなることを自身に課した。
そうした努力もあり、主席とまではいかないものの、ヴィルヘルムは好成績を収めた上で軍への入隊を果たした。
従軍してから約十年。《渦》の魔物による所属部隊の危機などがあったものの、災厄に見舞われていたかつてとは比べ物にならない程に安定した日々が続いた。
だが、その日々もルビオナ連合国とグランデレニア帝國の戦争が始まり、トレイド永久要塞に派兵されたことで終わりを告げたのであった。
ヴィルヘルムの目に見知らぬ木目の天井が映りこんだ。
「う……」
動く範囲で首を動かすと、サイドボードや花瓶に飾られた花が目に入る。
首を動かすと同時に、複数人の足音と声が耳に届く。
「大丈夫かな、あの人」
「目を覚ましてくれるとよいのだけれど……」
少女と大人の女性の声だった。少女の声は、一度目を覚ましたときに聞いた声によく似ていた。
ヴィルヘルムが目覚めたことに気付いた周囲は、彼に慌ただしくなった。 町医者が呼ばれて軽い身体検査が行われ、今の身体の状態を聞かされた。 実験と呼ぶにはあまりにもおぞましい行為の痕跡が治りきらなかったらしい。幾重にも腹部に巻かれた包帯が、傷の重篤さを物語っていた。
無意識に力をコントロールしているのか、それとも実験の後遺症か。かつてロンズブラウ軍にいたときと同様に、傷の修復の速さは医者に違和感を覚えさせない程度に抑えられているようだ。
「まあ、全治六ヶ月といったところでしょうな。とはいえ、若いからもう少し早いかもしれませんが」
「そうですか。ありがとうございます」
怪我を負って倒れていた自分を発見したという少女、メリーが足繁く見舞いに訪れる中、ヴィルヘルムはゆっくりと傷を癒していった。
「お兄さん、今日の具合はどう?」
「だいぶいいよ」
身体を修復する力をコントロールできるようになっているのか、力を意識的に使わないようにすれば、医者の見たて通りの治癒時間で治っていった。
「ロンズブラウ、ですか……」
意識を取り戻したヴィルヘルムは、町医者が来る前に自身の身分を語ると、真っ先に現在の故郷ともいえるロンズブラウへの帰還を口にした。
しかし、聖堂の僧侶であるイザベルは困ったような、気の毒がるような表情をした。
「ロンズブラウで何か起こったのですか?」
「あの国は二年前から内乱が続いているんです。故郷に戻りたいというお気持ちはわかるのですが、その……、正直なところ おやめになった方がよいのではと思います」
二年前といえば、トレイド永久要塞へグリュンワルドと共に出兵した時期である。あの凄惨なトレイドでの戦いから二年もの時が経っていることにも驚いたが、ロンズブラウが内乱状態にあることにも驚愕を隠せない。
「内乱?詳しくお聞かせ願えますか?」
「ごめんなさい。私達も詳しいことはわからないのです。この辺りに届くニュースでは、王政が崩壊した結果の内乱であると しか……」
老齢のロンズブラウ国王の容態が芳しくないということは、トレイドに出兵する以前から噂程度には耳にしていた。
王位継承権を持つグリュンワルドが助かることなく死亡、そして近い時期に王も崩御したのであろうか。であれば、規模の大きな混乱が起きてもおかしくはない。
だが、そもそも国の運営は国王が信頼する重臣達の手によって行われていた筈だ。王が存在しなくとも、すぐに王政が崩壊して内乱が続くような状況に陥るとは思えない。
「何故そんなことに……」
ヴィルヘルムの疑問は尽きない。だが、イザベルはその問いに答えられるだけの話を持ちえていなかった。
「ロンズブラウで内乱が起きてからは、ミリガディアやインペローダからロンズブラウ方面に出る連絡船は運行されていません」
「そう、ですか……」
「ルビオナとグランデレニアの戦争も酷くなる一方です。ですので、余程の理由がなければそちら方面への出国も叶わないのが現状です」
申し訳ないと言わんばかりの顔で、イザベルは話を続ける。
「内乱が収まってロンズブラウへの連絡船が再開されるか、もしくは戦争が終結するまでミリガディアに留まられるのが一番いいと思います」 「……わかりました。ありがとうございます」
現状、ロンズブラウに帰る手段は万に一つも無いに等しい。
そういうことならば、とヴィルヘルムは納得せざるを得なかった。
だが、同時に困ったことになってしまったのも事実であった。
国に戻れないのならミリガディアで生活をする他ない。だが、働き口や住居はどうすればいいのか。
聖堂が自分のような難民を受け入れる場所であるとは説明された。とはいえ、しばらくこの国に留まる以上は、きちんと働いて生活せねばならない。
働き口を探したいというヴィルヘルムに、聖堂は近場の植物園を紹介した。
この植物園はオハラという老人が一人で管理しており、若い働き手を求めているとのことであった。
オハラの植物園に住み込みで働き始めたヴィルヘルムは、とても真面目に働いた。
老齢のオハラでは難しい力仕事を手始めに、植物の世話の仕方なども意欲的に学んでいった。
働くならばやれる限りのことをしようというのもあったが、ロンズブラウに戻ったときに困らないようにという思惑もあった。
「お兄さん、こんにちは!」
「やあ、メリー。今日の勉強は終わったのかい?」
「うん! 今日は何をするの?」
「今日はこの種を袋に詰めるんだ」
週に三度、聖堂が主催する子供向けの勉強会が終わった頃に、 聖堂からメリーが植物園の手伝いにやって来る。
メリーは自分を発見してくれただけでなく、意識が戻ってからも献身的な看病をしてくれた恩人だ。ヴィルヘルムは彼女を子供だからと無碍に扱うことはせず、兄のように接した。
オハラに許可をもらい、ヴィルヘルムの指導の下で簡単な手伝いをするメリーは、ヴィルヘルムに同調するかのように真面目に手伝っていた。
「ああしている姿を見ると、仲の良い兄妹のようですね」
「そうですねえ。彼は真面目だし、とてもよく働いてくれる。メリーが手伝ってくれることも、他の子供達へのよい見本になっています」
「いやあほんと。彼さえよければ、いつまでもここで働いてもらいたいものです」
オハラとヴィルヘルムを保護した聖堂の者達は、真面目なヴィルヘルムの働きぶりを見て朗らかに笑った。
植物園での労働は、ヴィルヘルムに従軍していた頃とは違う充足をもたらした。 そんな中で、ヴィルヘルムはハーブや薬草の栽培に殊のほか興味を惹かれた。
薬草類は特に管理が面倒だからとあまり栽培はされていなかったが、ヴィルヘルムは他の植物の管理を疎かにしないという条件の下、メリーにも手伝ってもらいながらそれらの栽培量を少しずつ増やしていった。
ロンズブラウ軍に従軍してからは《渦》の魔物の討伐に忙しく、《渦》が無くなってからは戦争へ駆り出された。
様々なことがヴィルヘルムの身に起き続けていたのだ。こんな風に争いも無く、そして生産性の高い作業に従事したのは初めてである。
ゆっくりと植物やハーブを栽培する時間は、ヴィルヘルムの心に確かな平穏をもたらしていた。
(いずれロンズブラウに戻った時に、今の経験を生かして植物園を経営するのもいいかもしれない。)
そんな未来を思い描きながら、ヴィルヘルムは植物の世話に没頭するのだった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ