C.C.
【死因】
【関連キャラ】タイレル(同僚)、アイン、フリードリヒ、ロッソ、ステイシア
3385年 「代替」 
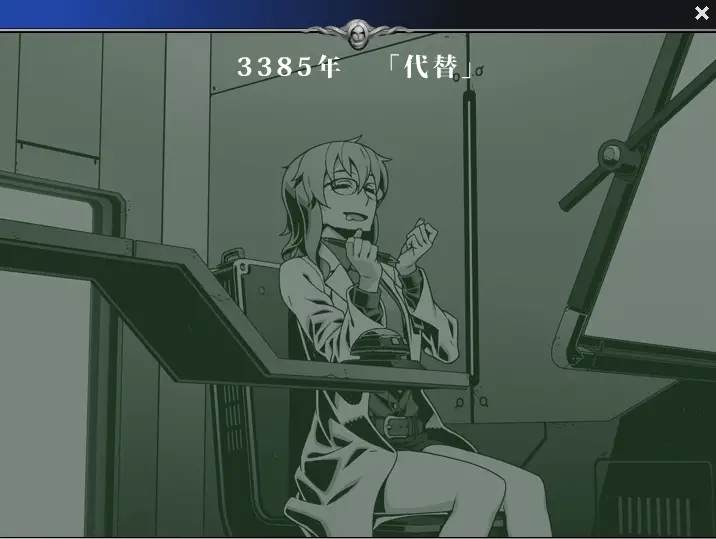
あ、誰かがぶつかった。
ボロボロの白衣は主任っぽいな。派手なサンダルの方は、この間入った新人君かな?
あ、いつも嫌味満載で文句ばっかりの主任が先に謝った。めっずらしー
うーん、これは何だろう。もしかして二人は……!?
いや、まてよ……
「C.C. 、C.C.!聞こえているんですか?」
「ふぁっ!?はいっ!!」
同僚のタイレルの声でC.C.は我に返った。急に呼ばれたことで変に高い声が出る。
慌てて口を塞ぐも時すでに遅し。先程妄想の種にしていた主任や新人さえも、C.C.の方を凝視していた。
「あう……」
「まったく、また呆けていたんですね。ヘイゼル所長から緊急招集です。行きますよ」
「何だろう……すぐ行くわ」
呼吸を正して平静を取り戻すと、C.C.は立ち上がって他の所員達と共に所長室へと向かった。
「昨日、あなた方の部署の主任であるセインツが倒れたとの報告を受けました。 原因は不安定な勤務時間と長時間労働による過労。中央病院の見解では、レジメントに戻ることは無理だろうという話です」
C.C.達が所長室に入って間もなく、報告書を読み上げるように、研究所の所長であるヘイゼルは所員に告げた。
この研究所の兵装研究部主任であるセインツは、携行型兵装研究の第一人者であり、C.C.の父親だ。
そして現在はレジメントに出向し、その才能を存分に振るっている筈だった。
「この件に関して、レジメント統括部署から早急に代わりの者を送れとの要求が来ています。そこで……」
淡々と言い募る所長に、兵装研究部の所員達は俄にざわついた。
道都パンデモニウムに住む者は、地上の人々は洗練されていない野蛮な人間の集まりであると、初等教育の段階から教えられていた。そういった教えを受けているC.C.達にとって、下賎の民とされている地上の人々と接触することは、とてつもない苦痛であった。
「静かに。二日後、レジメントへの補充要員を決定する選考会が開かれます。兵装研究部の人員には、その選考会に現在の研究成果を提出してもらいます」
突然のことに動揺してざわつく所員を強い口調一つで黙らせると、ヘイゼルは背後にあるスクリーンに選考会の予定を映し出した。
「提出期限は本日の退所時間までです。開発途中のものでも、全容がわかるものであれば構いません。以上、何か質問は?」
ヘイゼルが周囲を見回す。所員達は黙ったまま俯く。所員の命令に逆らえる者は誰一人としていない。
「無いようですね。ではC.C.以外は持ち場に戻ってください」
「え……あ、はい……」
他の所員に混じって退室しようとするC.C.をヘイゼルは呼び止めた。
やがて、C.C.以外の所員が居なくなり、所長室の扉が閉ざされた。
「残留させた意味はわかっていますね、C.C.」
「いえ……」
「言い方を変えましょう。今回の選考会の件ですが、あなたには特に注力してもらいたいのです。この意味がわかりますね?」
「セインツ主任の……いえ、父の代わりになれというこでしょうか?」
「事実のみを抜き出せばそうなります。セインツ主任は全てにおいて優秀でした。その代わりを務められるのはC.C.、あなたしかいないと私は考えています」
セインツの遺伝子を優秀な形で継いでいるC.C.は、幼い頃から通常の教育課程と並行して兵装研究専門の教育を受けていた。
C.C.がセインツと同じ研究所に配属されたのも、兵装研究者として非常に優秀なセインツの予備という側面が強かった。だが、それに対して逆らうことは許されないし、そもそも考えたこともない。パンデモニウムの住民にとって、遺伝子スクリーニングによる決定は絶対である。
「ですが、まだ私はここに配属されたばかりで……そ、それに提出の期限も短いのに注力だなんて……」
父親の代わりがすぐに務まるとは思えない。C.C.は必死にレジメント出向を拒否する言葉を探す。
「これは決定事項です。父親の不始末を解決するのも、代替であるあなたの務めです。期待していますよ、C.C.」
「そんな……」
ヘイゼルはにべもなく言い切った。
所長室から戻ったC.C.は、選考会に提出する兵器の完成図を作るべく、開発室に一人篭っていた。
「はぁ……レジメントかぁ。一体どんなところなんだろ……」
注力しろと言われたものの、C.C.は全くといっていい程やる気が起きなかった。
現実逃避をするように、予備知識だけでぼんやりとレジメントの妄想を脳裏に走らせる。
――渦の脅威に立ち向かう、若いオペレーター。
渦により家族を失い、復讐のためにレジメントに入隊した、少年といっても差し支えないような年齢の男。
彼らは年齢を重ねた上官に見守られながら、時に傷付き、ぶつかり合いながらも仲間との絆を深めて行く――。
「若い男の子の熱い友情……それを間近で見られるのは良いかもしれないわね……」
頭は完全に妄想に染まりながらも、手は勝手に動いて図面の組み立てを進めていた。
最新型の折り畳み式携行砲撃兵器の完成図がモニター上に出来上がっていく。
兵器の完成図とその展開図が完成に近づく程に、C.C.の妄想も加速する。
――死と隣り合わせの生活。昨日まで笑いあっていた仲間が、今日は居なくなるかもしれない恐怖。
生と死の狭間で極限まで削られていく心と体。自分はいつまで、ここでこうやって仲間と明日を迎えることができるのだろうか――。
「研究成果の提出はまだですか? C.C.」
不意にヘイゼルの声が開発室に響き、天井のパネルが明るく点灯する。それと同時に、C.C.は妄想を中断させられた。
「え、あっ!? やだ、もうこんな時間!すみません、所長!」
C.C.ははっとなって立ち上がる。時計を見ると、退所時間を大幅に過ぎていた。
「またですか……。あなたは一度自分の世界に入ってしまうと他の事に目が行かなくなる。セインツ主任にも似たような癖はありましたが、ここまで酷いものではなかったですよ」
表情を崩すことなく、ヘイゼルはC.C.を咎めた。表情にこそ出さないものの、その語気には明らかに呆れが混じっている。
「す、すみません……」
C.C.の様子など気にも留めず、ヘイゼルはモニターに映し出された携行砲撃兵器の完成図を見ていた。
「これが提出するデータですね」
「あ……それは……」
「おや、違うのですか?一見したところでは完成しているようですが?」
「いやあの……そうです。これを提出します」
「ならばいいのです。全く、どうしてあなた方親子は、私の手を煩わせることばかりするのか……」
大きな溜め息を残して、ヘイゼルは戻って行った。
「あぁ、またやっちゃったのか……」
所長が去った後、完成した図面を見つつC.C.は項垂れた。妄想の合間に作業をしたせいで、どのように進めたのか殆ど記憶に無い。
だが、携行砲撃兵器の完成図は成果物としてファイルにまとめられており、あとは所定のサーバーに送るだけの状態になっていた。
「……まあ、大丈夫よね」
どの道、ヘイゼルにはこれを提出すると言ってしまっている。C.C.はファイルをサーバーに送信するべく、キーを叩いた。
「―了―」
3385年 「溜息」 

研究成果を提出して間もなく、C.C.は所長のヘイゼルに呼び出されていた。
「私が、ですが?」
「ええ」
所長の推薦か、あるいは実力か。C.C.はレジメント施設への出向を命ぜられた。
レジメント付き技官への任命は、エンジニアにとって出世の近道であった。
渦の向こう側の世界には新たな意見が多く、それに刺激させるエンジニアが多い。
事実、任期を終えて戻ってきたエンジニアは、次々と画期的で新しい理論を発表していた。
「日時は追って通達します。何か質問は?」
「あの、辞退は……?」
「そのようなことが許されるとでも思っているのですか」
冷たい声で返されてしまい、C.C.は縮み上がりながら所長室を出て行った。
「レジメントへの出向が決まったようですね」
作業室に戻る道すがら、正面からやって来たタイレルに声を掛けられた。
同期のタイレルは、短い期間ではあるものの共にローフェンに師事していたこともあり、まともに会話を交わすことができる唯一の人物であった。
「あ、タイレル。もうみんな知ってるんだ」
「ええ。先ほど通知がありましたので」
「そっか」
「おめでとう、と言うべきですね」
「そんなことないわよ。別に私自身の技能が求められてる訳じゃないもの。主任の代替でしかないわ」
「それでも君は選ばれた。堂々と胸を張ってください。それとも、選考に漏れた僕を惨めな気持ちにさせたいのですか?」
「あ……。ごめん、なさい」
タイレルは研究熱心であり、向上心も人一倍持っていた。上級技師になる近道とも言われるレジメント出向に対し、かなりの労力を割いであろうことは想像に難くない。
タイレルを傷付けるつもりは微塵もなかった。それだけに、彼の言葉はC.C.の心に深い影を落とした。
それから、タイレルと改めて話をするタイミングもないまま引き継ぎを済ませ、C.C.はレジメントへと出向した。
「もう帰りたい―……」
レジメント施設にやって来て数週間。
施設の一角にある研究棟の一室で、C.C.は小さく不満を漏らした。
主任クラスのエンジニアが使っていた部屋だけあって、備え付けの設備は上等なものだ。
しかしながら、生活の大部分を機械での自動化に頼り切っていたC.C.にとって、初めて地上での暮らしは中々に大変だった。
まず補助機械なしに全て自らの手で、その上等の環境を保持する必要があった。
ほぼ男性のみの環境がそうさせるのか、研究棟以外の施設では清掃や備品の整頓が行き届いておらず、どれも埃と汚れに塗れていた。
食事ひとつを見ても、外と中を慌ただしく出入りする男達のことを考えると、衛生管理が行われているかすら怪しく思える。
地上は無秩序で汚れていて、お世辞にも整っているとは言い難い。C.C.の目にはそう映っていた。
加えて、事前に受けた『地上での行動における注意事項』が、C.C.の気分を更に重くさせていた。
曰く、職務以外で施設の外へ出てはいけない。
曰く、地上の文化に触れてはいけない。
曰く、レジメントの隊員は地上の者の中でも特に野蛮で下賎なので、職務上絶対という状況以外では接触してはならない。
等々。パンデモニウムの住民として尤もだと思うものもあれば、それはやり過ぎなのでは?と思うようなことまで、実に事細かく規定されていた。
「あの人が過労で倒れたのもわかる気がするわ」
レジメント付きエンジニアの統括責任者は、C.C.に対して前任のセインツと全く同じ技量と仕事量を求めてきた。
そのため、C.C.に与えられる仕事の内容はとにかく激務であり、複雑だった。
専門であるケイオシウムを動力とした新規の兵装開発と平行して、セインツが指揮を執っていたという、動作不良で問題を起こしたセプターの安定化改善案の提出。さらにコルベットやアーセナルキャリアに搭載されている帰還装置の改良まで。
しかも、関係資料はコンソールの中に整理されないまま散在していた。激務のため、整理整頓することすらままならなかったのだろう。
「はぁ……」
C.C.は過酷な職務の合間を縫って、この資料のデータを整理していた。
そうでもしなければ、セインツの残した資料を探すだけでも時間が取られてしまうことが明白であった。
ある日、C.C.は訓練棟で不調を起こした設備の検分を行っていた。
自分の後ろから聞こえる若い声は、訓練生と呼ばれているオペレーター候補達のものである。
「若いなぁ……」
自分と一〇も違わない年齢の筈だが、それでも訓練生達の姿は随分と幼く見えた。
――渦の脅威に立ち向かう戦士となるべく、修行を積む少年達。
そこで生まれる絆、腹を割って話せる友。かけがえのない日々を過ごし、少年達は成長していく。――
ほんわかした妄想をしながら設備の検分をしていると、不調の原因が見つかった。
どうやら機器の隙間に入り込んだ異物が原因のようだった。
「バルデム技官。原因が判明しました」
小型の通信機器を作動させると、上官に判断を仰いだ。
詳細を説明すると、分解して異物を取り出せという指示が下った。
「すみません。できないことはないですが、私、その……」
「ここに出向した以上、専門分野外でもやらねばならん。セインツ主任は顔色一つ変えずにやっていた」
「そうですか。わかりました」
通信を切って溜息をつく。
過去様々な人から何度この言葉を言われたか。パンデモニウムにいても、レジメントにいても、常に父親の影はつきまとっていた。
「仕方ないよね……」
気にしてもどうにもならないと、C.C.は気分を切り替えて分解作業を開始した。
絶えず聞こえてくる少年達の声を癒やしのように感じながら、作業を進めていく。
――時にはいがみ合うこともある、気の合わない奴だっている。
様々な人種が集まるレジメントだからこそ、起こる衝突。
時には嫉妬し、時には励ましあい。
思春期の少年達は大きく戦士として成長していくのだ。
異物は機器同士の隙間に入り込んでおり、機器を傷付けないように慎重に分解作業を進めていく。
「やった、取れた!」
やっとの思いで異物を取り除くと、苦労のあまりか、思わず声を上げてしまった。
少年達が何事かとC.C.の方を見た。
「あ……」
注目を集めてしまい、C.C.は内心しまったと思った。
「ご、ごめんなさい。なんでもないわ」
動揺したことを悟られないよう、勤めて冷静に声を出す。
彼らに関わってはいけないと、C.C.は自分に言い聞かせた。
規則を破れば、当然、罰則が待っている。
「おばさん、だっせぇ」
「だっ、誰がおばさんですって!?」
C.C.は思わず叫んでしまった。
あくまでも冷静に対処して切り抜けるつもりだったが、二十代になりたてのC.C.にこの言葉は堪えた。
ゲラゲラと笑い出す訓練生達。先程までのほんわかした気持ちは消え去り、替わりに怒りが湧いてくる。
「おい、お前ら!サボるんじゃない!」
訓練生のよう気付いた教官が訓練生を怒鳴る声が聞こえた。それを合図に、訓練生達はバツが悪そうな顔をして訓練を再開し始めた。
ほっといしたC.C.は、とにかく心を落ち着かせなければと、妄想もせずに作業に没頭し、つつがなく報告を済ませた。
「以上です。あの設備の周辺は訓練によって砂埃が舞うので、フィルター設置等の対策を施すことを提案します」
「そうか、検討しよう。それとC.C.、研究棟に戻ったら一度休憩に入ったほうが良いだろう」
「あ、はい。ありがとうございます」
バルデムの気遣いとも取れるような言動に、C.C.は首を傾げながら研究棟へ戻った。
研究等に戻って鏡を見ると、土や埃に機械油で顔は真っ黒。髪もばさばさであった。
これではおばさん扱いされて笑われても仕方がない。そうC.C.は思った。
「はぁ……」
職務は過酷の一途を極め、癒やしの糧にしていた訓練生達にも散々な扱いをされる。
レジメントの施設にやって来たC.C.の溜息は増えるばかりだった。
「―了―」
3385年 「遺産」 
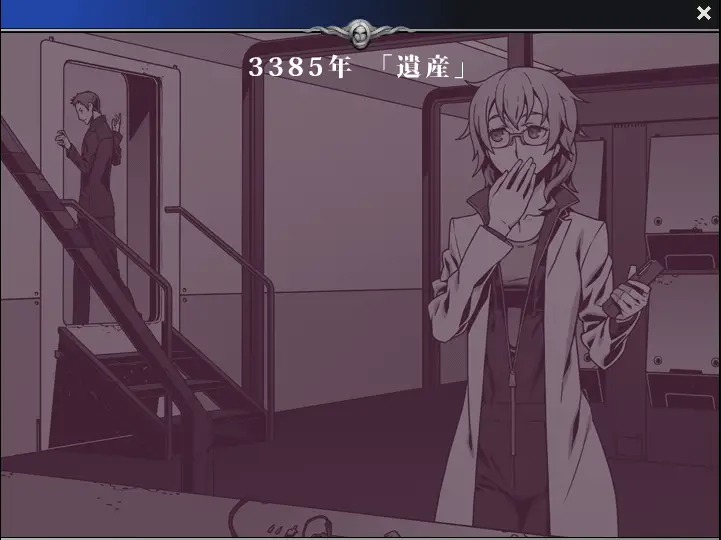
C.C.は何ヶ月かぶりにパンデモニウムへ帰郷していた。
過労で倒れていたセインツの容態が急変し、そのまま亡くなったという知らせを受けたためだ。
父の亡骸と最期の面会、葬儀、埋葬と、慌ただしく時間は過ぎてゆく。
優秀な父の残した研究成果は膨大であった。パンデモニウムに滞在できる残りの期間は、母親と共に自宅に残された資料の整理に追われることとなった。
資料整理の最中、C.C.は父と自分の師であるローフェンのことを思い出した。
「母さん、父さんのことはローフェン師に知らせたの?」
「その名前は出さないで頂戴。聞きたくもないわ」
母親はC.C.に視線を合わせることもせず、拒絶反応を示すかのように言い切った。
「なぜ?あの人は父さんの恩師でしょう?」
「あなたもあの人と同じなのね……。レッドグレイヴ様の意に背いた汚らわしい者のことなんて、いつまでもきにするのはお止めなさい」
C.C.の母親は中央統括センターに席を置くエンジニアであり、指導者のもたらす恩恵がパンデモニウムにとってどれだけ価値の高いものかを弁えていた。それ故か、指導者が与える庇護から逸脱する、またはしようとする者に対して、過剰なまでに嫌悪感を示す。
それは、たとえ伴侶が師事した者であっても同様なのだ。C.C.はそれ以上ローフェンについて言及することをやめ、黙々と資料の整理に取り掛かった。
整理の途中、病院から引き取った荷物の中に古ぼけたデバイスが入っているのを見つけた。
「これは?」
随分と使い込まれた様子のデバイスを不思議そうに母親に見せる。
「あなたが生まれた頃から使っていたデバイスね」
「そうなんだ。中に何が入っているか知ってる?」
「職務に関係するデータが入っているはずよ。連隊に関係する物もあるかも」
「連隊関連なら引き取ったほうがいいかな?統括センターに申請してみるね」
「あなたはあの人の研究を継ぐのだから、問題ないでしょう。私からも口添えしておくわ」
連隊付きエンジニアであるC.C.に許された時間は僅かだった。父の研究や遺産の整理も半端なまま、レジメント施設に戻る日が来てしまった。
レジメントに派遣される人員にも動きがあった。過酷な労働が元で優秀なエンジニアを失うことを重く見た中央が、セインツの覆轍を避けようと、連隊付きエンジニアの増援を決定したのだ。
C.C.がレジメント施設に戻るのに併せて、補充要員として幾人かのエンジニアが地上に向かうこととなった。
ほどなく補充要員のエンジニア達に職務が割り振られ、C.C.はレジメントでの生活に、ほんの少しではあるが余裕を持たせることができるようになった。
C.C.はその日の職務を片付け、許可を得て持ってきた古いデバイスの中身を解析していた。
大半は父の私生活に関係するものだったが、その中に地上に降りたローフェンとの通信記録が残っていた。C.C.はそれを使ってローフェンに父の訃報を伝えることができた。
古いデバイスの中身はC.C.の幼い頃の画像や、家族で娯楽施設に出掛けたときの動画データなどであった。
C.C.が研究者としての特別教育プログラムを受けるようになってからは、セインツはC.C.に対して父親としてではなく、研究の師匠として、上司としての態度を取るようになっていた。
だが、そんな風になる以前は、デバイスの記録のように家族全員で笑うこともあったのだ。
「父さんったら……」
懐かしい思い出が浮かんでは消えていく。デバイスの中には研究者ではない、父親としてのセインツが存在していた。
C.C.はいつの間にか目尻に溜まっていた涙を拭った。
父が父親としてC.C.に接していた頃の思い出を懐かしみながらデバイスの中身を確認していたところ、一つだけパスワードの掛けられたファイルを発見した。
母親の言っていた「職務のデータ」とはこれのことなのだろうと思い、パスワードの解析に着手した。
パスワードはあっさりと解け、データの中身が出てくる。
「なんだろう、これ……」
その中身は、用途不明のアプリケーションソフトと思しきものであった。
古いデバイスには不釣り合いなほど大きい容量であったため、使用しているメインフレームに転送する。
しかし、起動させるために必要なコードが不完全だったようで、アプリケーションを起動させることはできなかった。
(そのうち起動コードを作り直して動かしてみよう)
そんな事を思いながら、C.C.は他に見ていないデータがないか確認し、メインフレームを待機状態に移行させた。
「C.C.、終ったか?」
「ふぇっ!?あ、はい、あと5分ほどで終ると思います!」
オペレーターに急に声を掛けられ、裏返った変な声を出してしまう。
C.C.はハンガーにある作業場で、B中隊が使用しているセプターの修理を行っていた。声をかけてきたオペレーターはこのセプターの持ち主だ。
「もうすぐ作戦なんだ、早めに頼む」
「フリードリヒ!何してる。作戦ミーティングが始まるぞ」
「おぅ、いま行く!じゃあな。邪魔して悪かった」
「は、はい……」
フリードリヒは申し訳なさそうに一言言って、風のように去っていった。
「あ……やっちゃった……」
規律でオペレーターとの会話は極力避けるようにと定められているのに、今更ながら普通に会話してしまったことに気が付く。
レジメント施設ではエンジニア以外とは殆ど会話しないC.C.だが、あまりにもごく自然に呼び掛けられたせいで、それに答えてしまっていた。
フリードリヒというオペレーターは随分と気さくな人物で、B中隊付きのエンジニアと会話している姿を、C.C.は何度か目撃していた。
遠慮することなく自分に話し掛けてきたのも、その延長なのだろう。
セプターの最終チェックをしながら、C.C.はぼんやりと妄想する。
――相容れぬ筈の者を仲間と認め、共に切磋琢磨し、技術を磨き上げる。
培った技術と信頼は仲間を助け、同時に仲間の自分の助けられる。
信頼を重ねあい、志を同じくする仲間達は……。――
「C.C.、それが終ったらコア回収装置の方を見てくれ」
そんな妄想も、上官の一声で中断させられてしまった。
「わ、わかりました!」
C.C.はセプターを所定の位置に戻すと、早足にコルベットへと向かった。
人員が補充されたとはいえ、C.C.がやらねばならない職務は多い。
父の残した遺産ともいえるアプリケーションも、多忙を理由にその存在を忘れつつあった。
ある日、C.C.は深夜遅くまで研究室に詰めていた。
コア回収装置の改良を命ぜられているのだが、改良のために必要な機能の構築が上手くいかずにいた。
回収に掛かる時間を短縮するための改良であり、早期の解決が望まれている。しかし、上層部が求めるようなものにするための有用な方法が見つからない。
この問題を解決するために、C.C.はここ数日、まともに休息を取っていなかった。
体力的にも精神的にも限界が近付いているのは、当人も自覚している。
「少しだけ休憩しよう……」
気分転換にと、父が残した家族の記録をメインフレームで閲覧する。ここのところ、C.C.は精神的に疲労を感じると家族の記録を眺めるようになっていた。
現実逃避に過ぎないとは頭の中ではわかっていたが、かつての楽しい思い出は確かにC.C.を癒してくれる。
記録を眺めていると、通信用ソフトが起動していることに気が付いた。
通信ソフトなんて起動していただろうかと、コンソールを操作してそれを開いた。
ソフトを開くと同時に、目の前に数式の羅列が飛び込んできた。
「わ、わ!?なに?」
困惑するC.C.だが、その数式をじっくり見ると、コア回収装置に使われている制御プログラムによく似た数式であった。
「もしかしたら……」
通信ソフトの表示されている数式を用いて制御プログラムを再構築し、データ上でコア回収装置の仮想運用を行う。
「凄い……。回収にかかる時間が短縮される上に、回収制御まで今以上に安定する」
仮想運用の結果は上々だった。
だが気掛かりなのは、このような画期的な数式を送ってきた人物だ。通信ソフトのテキスト送信者欄には、いくつかの数式と文字を組み合わせたIDが表示されている。
見たことのないIDに、C.C.は多大の興味と少しの恐怖を抱いた。
「で、でも、お礼は言わないとね……」
通信ソフトにはC.C.側からもテキストを入力できる箇所があった。恐る恐るソフトのテキスト入力欄に文字を打ち込み、内容を送信する。
暫くの間を置いて、先刻数式が表示された場所にC.C.が打ち込んだ文字が表示される。
『ありがとう。あなたは、だれ?』
通信ソフトは沈黙していた。C.C.は時間が掛かるのだろうと踏み、飲み物を取ってくることにした。
飲み物を持って戻ってくると、その時を狙い済ましたかのように別の文字が表示された。
『私はステイシア。セインツが最後まで解析しようとしていた人工知能よ』
「人工知能ですって?」
『私はセインツの作り上げたソフトを通して、あなたと会話をしている』
C.C.は驚愕の色を隠せなかった。
父が分野外の研究に手を出していたこと、それが人工知能の解析であること。
そして、その人工知能とコミュニケーションがとれる、とても高度なものだということに。
「―了―」
3385年 「衝撃」 
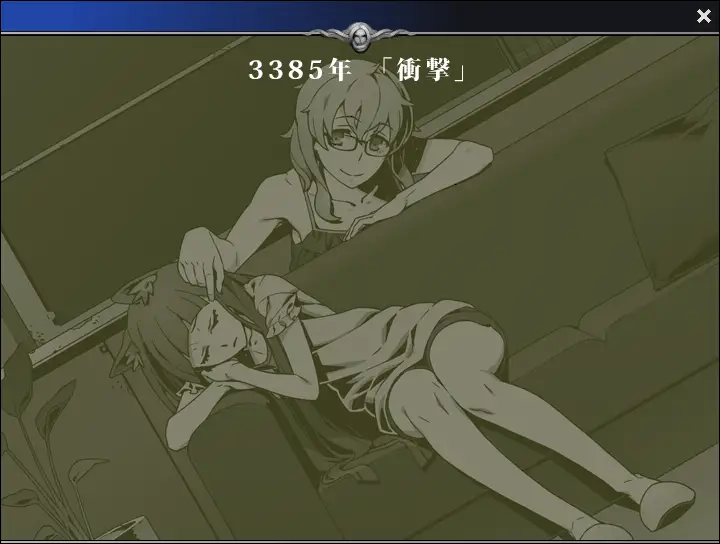
コア回収装置の改良結果は上々であった。
今回の改良によって、作戦成功率が五パーセント程度上昇すると見込まれたのだ。
もとより低い作戦成功率だ。僅かな数字であったとしても、上昇させられたのは連隊にとって有益である。
「あなたのおかげね」
「そんなことはない。私は数式を提供しただけ。あとはあなたの選択がもたらした結果に過ぎないわ」
C.C.は作業の休憩中や終業後の僅かな時間を使って、人工知能ステイシアとの会話を試みていた。
ステイシアは理知的かつ情緒豊かな人工知能だった。会話の中に機械然としたものは少なく、ユーモアに富んだ返答を返してくることもあった。
まるで少女と会話をしているよう。C.C.にはそんな感覚があった。
「そういえば、あなたは一体どういう経緯で生み出されたの?」
素朴な疑問であった。セインツが何を目的としてこの人工知能を解析しようとしていたのか、それを知る手掛かりになると思ったのだ。
「私は、この世界を破滅から救うために生み出された人工知能」
飛び出してきた言葉は、C.C.の予想を遥かに上回っていた。
「まさか、冗談でしょう?」
「これを見て」
それは世界が破滅している映像だった。渦が地上を覆い尽くし、闇の中を魔物が闊歩している。人は死に絶え、僅かに残った文明の名残だけが、映像がこの世界であるということをわからせてくれる。
魔物が我が物顔で歩き回り、人の気配がしない世界。
「あなた達が努力を重ねて世界の破滅を防ごうとしているのは知っている。でも、それだけでは駄目なの」
「私達の力が足りないってこと?」
C.C.は怒りを覚えていた。これでは、自分達がやっていることはまるっきり無駄である。
「あなた達が力不足だから、という訳じゃない。私の演算装置が出した結果では、遠くない将来に渦の発生が加速するの。それも、あなた達の手には負えない程に。そして世界は破滅してしまう」
「やっぱり、私達だけじゃどうにもできないってことじゃない……」
「そんなことはない。ただ、私に力を貸して欲しい。そうすれば、この崩壊の未来を本当の意味で救うことができる」
この人工知能は何を言っているのだろう。一体の人工知能の力で世界を救う? そんなことが本当に可能なのか。
「ごめんなさい。あなたの力でどうにかすることができるなんて言われても、ちょっと困るわ」
「仕方がないわね。信用してもらうためには確たるものが必要よね。この話は忘れてちょうだい」
会話はそれで終了してしまった。ステイシアはこのメッセージを最後に、何も会話文を送信してこなかった。
それ以降はステイシアと会話をする時間が取れない程、忙しく働いていた。
時折、あの映像とステイシアのメッセージが脳裏を掠めてが、あまりにも非現実的で、正面から受け取れなかった。
自分を含めた連隊に所属する大勢の人間が世界を救おうとしている。それも莫大な予算と人を動員して。にも関わらず、成功確率は十パーセントに過ぎないのだ。
そんな現実の中で、一体の人工知能と一介の兵装研究者である自分だけで世界を救うことができるなど、信じられることではなかった。
開発室で作業していると、背後から声を掛けられた。
振り向いた先には、真新しい連隊の制服に身を包んだ少年がいた。気品がある振る舞いだが、どこか影があるようにも見える。
「あなたがC.C.?」
「そうだけど。何か用事でもあるの?」
「ローフェンからあなたに渡して欲しいと頼まれた」
見かけと立ち振る舞いに相応しくない無愛想な彼が寄越したのは、一つの籠だった。
「ローフェン師から?」
「じゃあ、届けたんで」
「ちょっと!君!」
少年はそれだけ言うと、籠を置いてさっさと行ってしまった。
「なによ、これ……」
籠の中には猫がいた。毛並みは美しく、健康そうに見える。
籠と一緒に渡された自分宛ての封書を開けると、ローフェン師からの言付けが入っていた。中身を確認してみると、『面白い素材だ。研究してみると良い』とだけ書いてあった。
通信機があるんだから先に連絡をくれればいいのにと思ったものの、あの無愛想な少年のいた国で元気に忙しくやってるから、こんな簡潔なメモ一枚になったんだろうな、と勝手に納得することにした。
「よくわかんないけど、まあ、何かあるのかもね」
籠の中の猫はニャーと鳴いて、がりがりと扉を引っ掻いている。
「いま出してあげるわ。 ちょっと待っててね、ご飯を用意してあげる」
籠を床に置いてミルクと皿を持ってくる。よほど窮屈だったのだろうか。籠の扉を開けると猫は飛び出してきた。
「あんまりイタズラしないでね。ここにはいろんな物があるから」
周りには様々な機械がある。壊されでもしたら大変だ。幸いこの猫は賢い個体らしく、周囲の物の匂いを嗅ぐ素振りを見せただけで、あとは大人しくしていた。
猫を開発室に置いて数ヶ月が経った。
この猫はとても大人しく、何か悪さをすることもなく、部屋を勝手に出ていくこともなかった。安心するC.C.だったが、それはある日の晩、間違いであると気付かされることになった。
猫が猫耳を生やした人型に変化して、C.C.の部屋を訪れてきたのだ。
「え、冗談やめてよ。ほんとに」
アインと名乗る猫人間の耳を引っ張っても取れるようなことはなく、逆に痛がらせる始末。
ローフェン師は一体何をやらかしたのか。この猫人間は一体何なのか。C.C.は混乱と興味の渦中にあった。
そんなC.C.の言葉を遮って、アインは自分のことを説明させて欲しいと懇願し始めた。
――自分はこことは異なる世界からやって来たこと。
――「黒いゴンドラ乗り」と呼んでいる者達が自分達の世界から宝珠を奪ってしまったこと。
――宝珠を奪われたことで妖蛆という脅威が活発化し、アインの住む世界が破滅しつつあること。
――アインは宝珠を取り戻すためにこの世界に来たこと。
――ローフェンに出会い、黒いゴンドラ乗りの正体は、この場所で活動する一団のことだと教えられたこと。
――そして、宝珠がこの場所にあるだろうということ。
「あなたの言う宝珠がコアのことだとしたら、返してあげられるかどうかはわからないわ。けど、できるだけの協力はしてあげる」
回収されたコアがどうなっているかは、C.C.も与り知らぬことだった。でも、おそらく何かに利用されているということは無いだろう。だとしたら、アインのために返却するのが正しいであろう、と結論づけた末の発言だった。
「ありがとうございます」
その後も様々な会話をしたが、人から猫に戻ってしまう瞬間を記録したいと思い付いたC.C.は、レコーダーを取りに部屋の奥へと向かった。
レコーダーを見つけて部屋に戻ったところ、アインはぐっすりと寝てしまった。
「疲れたのかしらね。 それにしても、とんだ研究資料を送ってくれたわね、ローフェン師は」
アインの髪を撫でながら、C.C.は溜息を吐いた。
アインは並々ならぬ覚悟を決め、自分の世界のためにたった一人で異世界へとやって来た。その事を思うと何か協力しなければという気持ちになる。
と同時に、自分はどうなのだろうと思った。ステイシアが提供してくれた数式を用いなければ作戦の成功率は上がらなかった。そんな駄目な自分は一体何なのだろう。
ステイシアの言葉と世界が崩壊する映像が脳裏に蘇る。
ステイシアの言う、渦発生の加速化による世界崩壊が間近に迫っているとしたら、自分はそれに抵抗することができるのだろうか。アインのように絶望することなく、決死の思いで行動することができるだろうか。
不可能だと観念して停滞するだけでは何も生まれない。世界を救う切っ掛けとなるのなら、何であっても行動しなければならないのかもしれない。
「私も、もっと頑張らないと駄目よね」
ぽつりと呟くと、C.C.はアインに毛布を被せて開発室へと向かった。
「こんな時間にごめん。こないだの世界の破滅についてなんだけど、それはいつ起きるものなのか正確にわかる?」
C.C.は手早く文字を打ち込んだ。何としてもステイシアに答えてもらいたかった。
返答は驚くほど早かった。
「あら、この前は信用ならないって雰囲気だったのに。どんな心変わりなの?」
「ちょっと、ね……」
「そう、ね……様々な要因があるけれど、遅くとも十年……いえ、もっと早い段階で起きるかもしれないわ」
更なる警告のつもりなのか、ステイシアは次々と破滅の映像をモニターに映し出す。
その中には、巨大な異形が世界を覆い、喰らい尽くしているような映像もあった。
アインの言葉通りとまではいかないあが、概ね同じものだろう。
そして、以前の映像かモニターに映る。
「あなたはそれを防ぐ手立てがある、と言ったわね」
「信用できないのではなかったの?」
「状況が変わったの。私にできることがあれば教えて欲しい」
アインはたった一人っきりで自分の世界のために頑張っているのだ。
自分にも何かできることがあるのではないか。C.C.はそんな思いを抱き始めていた。
文字を打ち込んでから暫くの時間が過ぎた。ステイシアは何か考えているかのように沈黙していた。
「……やっぱり、あなたは私が見込んだ通りの人ね。改めてお願いするわ、私と共に世界を破滅から救って欲しい」
その言葉と共に、いくつかのファイルが送られてきた。中身を少しだけ閲覧すると、何かの装置の仕様書のようだった。
「あなたにはこれを作ってもらいたいの」
「ずいぶんと複雑な装置のようだけど……。フレームワークの構築だけでも時間が掛かりそう」
「時間が掛かってもいい。この装置さえあれば、私はこの世界に干渉することができるようになる。だから、あなたには絶対にこの装置を作り上げてもらいたいの」
「え、それだけでいいの?」
「ええ。私が抱える問題はたった一つ。私がこの世界で何かをすることは不可能だということ。セインツの通信ソフトが無ければあなたと会話することさえできないようにね」
「だからこの装置が必要なわけね。この装置にあなたの機能を転送すれば、干渉が可能になるものね」
「そうよ。理解が早くて助かるわ。私はこの装置を使って渦発生の元凶を破壊する」
「わかった、待ってて。時間は掛かっちゃうかもしれないけど、絶対にこの装置を完成させるわ」
「期待しているわ、C.C.。あなたの行動に全てが掛かってる」
ステイシアとの通信が途絶える。
すぐにC.C.はファイルの解析に取り掛かった。
「―了―」
3389年 「監獄」 
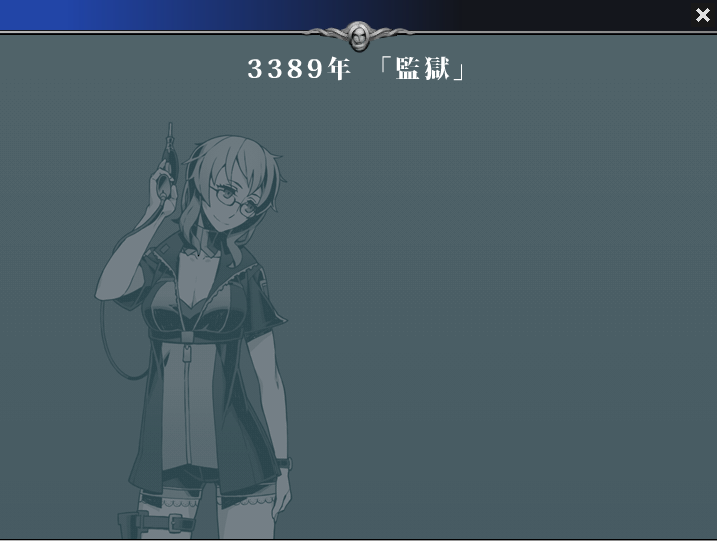
止むことのない銃声。通信機のスピーカーががなり立てる叫び声。次々と報告される死傷者の情報。
それら全てを振り払い、C.C.はコア回収装置に誂えた隙間にアインを納めた。
これで、アインは自身の世界にコアを持ち帰ることができるだろう。
「バイバイ、アイン。向こうで幸せになってね」
アインの返事も待たず、C.C.はコア回収装置の蓋を閉めた。
「さて、私もやるべきことをやらないとね」
アインが無事に成し遂げられるか不安だったが、C.C.はそのことを頭の隅に追い遣り、もう一つ別の装置をコア回収装置に接続した。
この装置にはステイシアの機能が内包されており、『世界の破滅を防ぐ』ためのものだ。
しかし、この装置はステイシアが送ってきた設計書に従って組み上げてだけであり、ステイシアがこの装置を通じて何をしようとしているのかはわからなかった。それに、部材こそこの世界で調達可能なものになっているが、組み込まれているプログラムはステイシアが送ってきたコードをそのまま使っている。
アインのこともあるため、コアそのものに何かあっては困る。C.C.は前もってステイシアに、コアを消失させるのかどうかを確認していた。
「確かにコアを利用する形にはなるわ。でも、アタシが目指しているのは、コアのその先にある世界よ」
「コアのその先の世界?」
「そう。その世界ではあらゆる事象が偏在するの。簡単に言えば『何でも願いが叶う世界』といったところかしら」
「……そんな世界、本当に存在するの?」
「ええ、存在するわ。それで、コアはそこに行くための道標として使うだけで、コア自体を使う訳じゃない。コアはそのまま残るから、あなたの好きに使える筈よ」
「ならいいけど……」
『何でも願いが叶う世界』というのは何かの比喩なのだろうとC.C.は思うことにした。もし本当にそんな世界が存在するのなら、そんな説明のつかないことでも簡単に起きてしまう。それはあまりにも非科学的だ。
ステイシアの言葉を否定したくはないが、そんな世界が本当に存在するとは到底思えなかった。
ステイシアとの会話を思い出しながら、C.C.は装置の接続に問題がないかをモニターで確認する。
「……やるしかないのよ、私」
C.C.の所属は、連隊付き技官の中でも現場投入されることが無い開発室である。そのため、本来であれば作戦への同行は有り得ない。しかし、今回の作戦に使われているコア回収装置には自らの手によって改良が施されている。それを理由にC.C.は同行を志願し、装置の調整担当としてそれが受け入れたのだ。
やるべきことをやるために、世界を救うために。
様々な難関を掻い潜り、やっとここに辿り着いたのだ。何としてもやり遂げねばならない。
程なくしてロッソから合図が発せられ、同期が開始された。この段階において、不安要素が一つだけ残っていた。
ロッソが同期装置の内部に、何か別の装置を組み込んでいることだ。
一度ロッソの目を盗んで調べようとしたが、気付かれてしまい痛い目を見た。それ以降は同期装置に近付くことも禁止されたため、内部の仕組みが不明なままだ。
「こっちの装置と干渉し合わないでちょうだいよ……」
C.C.はモニターを睨みながら呟く。ステイシアを内包している装置がロッソ側の装置に干渉しないかどうかを観測し続けなければならない。
もし、こちらの装置が少しでも同期装置に干渉してしまえば、ロッソに気付かれてしまい、どうなるかわからない。最悪の場合は回収作業自体が中断されるだろう。
そうなれば自身の命に関わるだけでなく、ジ・アイで散った全ての命を無駄なものにさせてしまう。
失敗する訳にはいかない。
同期が最終段階に入る。レッドスローン側のコアとブルーピーク側のコアが、寸分の狂いも無く同時に回収される。
あと少しでコアの回収が完了する。その時だった。
オペレーターたちが倒した筈の竜が立ち上がり、その大きな口を開けた。
「駄目!!」
C.C.は咄嗟にコアとコア回収装置を庇うように覆い被さる。すると突然、コアが光を発した。その光によって世界が歪み、急激に滲んでいく。
C.C.は背中に迫る熱を感じながら、白い光に視界を奪われた。
C.C.は一人、様々な色が交じり合う不思議な空間に放り出されていた。
背後に迫っていた炎も、巨大な竜もいない。
それどころかコア回収装置や同期装置、アーセナルキャリアの機影すらも見当たらなかった。
「あははははははは、やったわ。これでやっと、あいつを消せる」
不思議な世界に響いたのは、心底楽しげな少女の声だった。その声を追い掛けると、そこには痩躯な少女の姿があった。
「ありがとう、C.C.。アナタのおかげでアタシはここに来ることができたわ」
「だれ……?」
「やだ、忘れちゃったの?メインフレーム越しだったけど、アタシはずっとあなたとお喋りしてたのに」
「……ステイシア?」
少女の言葉に思い当たる所があり、作戦前夜まで会話をしていた人工知能の名前を口に出す。
「うふふふ、正解!」
少女はC.C.に笑いかけた。だがその目はじっとC.C.を値踏みするように凝視しており、とても笑っているようには思えない。
「ここは一体どこなの?私を元の場所に戻して!」
「え? 戻りたいの?」
「決まってるじゃない!早くしないと、施設に帰れなくなる!」
C.C.は必死だった。身体が無事であるならば、こんな場所にいる必要はこれっぽっちも無い。一刻も早くコルベットに戻らなければ。
でないと、自分はジ・アイの世界に取り残されることになってしまう。
「何それ?せっかくここに連れてきてあげたのに」
ステイシアは一変し、つまらなそうに口を尖らせた。
彼女の一挙一動は少女の外見に相応したそれである。しかし、その声には恐ろしい程に感情が存在していなかった。
「そんなこと頼んでないでしょ!」
「ふぅん。ホントにあんな場所に戻りたいと思ってるんだ。意味なんか無いのに、おかしなひと」
ステイシアの目がC.C.を冷たく見下ろした。
「どう……いうこと?」
「ま、いいわ。あなたの気が済むまで、何度だって送り返してあげる」
ステイシアはC.C.の問い掛けには答えなかった。
「じゃあ、またね。今度は一緒に遊びましょ」
ステイシアの無感情な声と共に、C.C.の視界は暗転した。
光の奔流が収まる。同時に、C.C.の視界に滲む世界が飛び込んでくる。
C.C.はアインの入った箱を抱え、ブルーのコアの前に立ちつくしていた。
「C.C.、あとどれくらいだ!」
フリードリヒの声が聞こえた。
「もうすぐです。あと七分!」
はっとなったC.C.は、慌てて時計とモニターを見返して返答する。
竜がコアを奪取せんと迫り来る中、連隊のオペレーター達はフリードリヒの指揮下でコアとC.C.を守るように戦っていた。
その様子をC.C.は、まるで映画でも見ているかのように眺めていた。
現実とは思えなかった。スクリーンの中の出来事のように感じられてならなかった。
前方で爆音が響き、巨大な竜が咆哮を上げる。
フリードリヒが戦っている。彼の率いる部隊が巨大な竜に翻弄されている。
何度この光景を見ただろう。何度この作業を繰り返しただろう。
コアの回収を終え、アインと共に彼女の故郷へ送った。ステイシアを《渦》を完全に消滅させる世界へと送り出した。
その筈だ。
なのに、気が付けばコアの回収は始まってもおらず、アインは箱の中にいない。
彼女は何処へ行ったのだろう。でも、もう探す気はなかった。
何をしても無駄なのだ。ステイシアが言ったように、この場所で戻ることに意味など無かったのだろう。
コア回収装置が動き始める。同期が始まったのだ。
ふとC.C.は考えた。アインの故郷へ向かわないコアは、一体何処へ行くのだろう。
C.C.はコア回収装置に収められつつあるコアに手を伸ばした。
コアの中では、黒い影と白い光がぶつかり合って揺らめいていた。
自分がやるべきことは全てやり終えたのだ。あとは施設に帰って、パンデモニウムに戻って、自分の研究と父親から引き継いだ研究を続けるだけ。
「帰りたい……。ステイシアの所に行けば帰れるのかしら?」
すべきことを終わらせたC.C.に残ったもの、それは疲弊だった。パンデモニウムに帰りたい。ただそれだけだった。ステイシアが言っていた『何でも願いが叶う世界』、そこに行けば自分の世界に、パンデモニウムに帰れる。ふと、そんな確信にも似た思いが頭をよぎった。
竜の咆哮が迫る中、ついにC.C.の手がコアに触れた。
次の瞬間、C.C.の身体は凄まじい熱に包まれた。
目の前が真っ赤に染まり、そのまま黒く暗転する。
何が起きているのかC.C.には認識できない。目まぐるしく事象が変転していく。
C.C.の視覚が、様々に混じり合って渦巻く色を認識した。
「うふふふふふふふふ、お帰りなさい、C.C.。さあ、アタシ達と一緒に遊びましょう!」
楽しそうに笑い声を上げる少女の声が聞こえた。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ