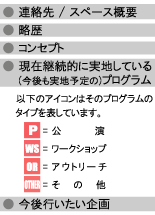『ニュータウン入口』プレビューII準備公演
または私はいかにして心配するのをやめニュータウンを愛し土地の購入をきめたか
(写真左より)上村聡・佐藤拓道・南波典子・田中夢
photo:有賀傑
遊園地再生事業団 演劇公演 『ニュータウン入口』
開催日:プレビューI リーディング公演 2007年4月20日~4月22日
プレビューII 準備公演 2007年6月29日~7月1日
本公演:2007年9月21日~9月30日
会場:森下スタジオ(プレビュー公演)、シアタートラム(本公演)
主催:遊園地再生事業団
作・演出:宮沢章夫
森下スタジオを新作創作の活動拠点とし、創作途中で試演を発表しながら本公演に向けて作品を練り上げる。 プレビュー公演では、出来る限り公演後に観客とのディスカッションを実施し、作品のフィードバックに役立てる。共催事業として森下スタジオを提供。
以下、宮沢氏による企画内容およびプロットを掲載。
「集団/戯曲/身体」 連続的なワークインプログレスの不合理な試み
ひとつの舞台作品を上演する手続きには、これといって正しい決まりがあるわけではない。もちろん、舞台を作るには初期の準備段階からステージマネージメント(あるいは「制作」と呼ばれる作業領域)の必要性は高いが、ここではもっぱら、舞台そのもの、舞台上で表現される一連の作業のことを、「手続き」として考える。
たとえば、「舞台の作り方」や「演出の方法」といった種類の書物にはその方法が丁寧に解説されているかもしれないが、それが正しいと一概に言えないのは、そうした「正解」を作ってしまったところで、「正解」が、「表現」そのものに、どのように反映するか確実なことはわからないからだ。いかに「正解」が示す方法で舞台が創作されたからといって表現の質はなにも保証されない。あたりまえとされるような方法ではなく、またべつの「作り方」を創出することが、表現そのものを変化させる。むしろ、「作り方」そのものが表現になるのが、現代演劇と考えていいし、それは、「言葉」から「身体」へという現在性、あるいは、「ドラマ」から「パフォーマンス」へというこの時代が要請する表現のあり方とも一致する。なぜなら、演劇を作るにあたって、まずはじめにあるのは、身体そのものだからだ。
おそらく、「劇団」と一般的に呼ばれる舞台を作る集団の意味とは、この過程の連続性にあると想像できる。長い時間の集団創作によって集団の持つ表現力をより高めることに本来の目的があるからだ。基礎的な訓練からはじまり、それを応用して統一された表現を育て、舞台としての成果を生み出す。だが、いまこの国の「劇団」の多くはそれとは異なるあり方をしていないだろうか。舞台を作るためには「劇団」がなくてはならないという無反省な位置から単なる集団となったとき、「集団性」の弊害は、「個」の確立をはばみ、集団を構成する者らにとっては単に寄りかかるだけの場所になってはいないか。そうした無反省な集団から新鮮なものが生まれてこないのは、チェルフィッチュやポツドールをはじめ、いまの若い世代の演劇の成果の多くが、過去の「劇団」の形態とは異なる姿から生まれているのを見ればあきらかだ。
では、集団創作の方法は、それ自体、否定されるべきものだろうか。そもそも演劇というカテゴリーが集団的な営みである以上、集団創作から表現を切り離すことはできないとするなら、過去とは訣別した「集団創作のまた異なる試み」が求められるのは必然である。その中心にあるのは、「考えることの運動性」であり、ピーター・ブルックがかつて語った「退廃演劇」は、その「運動性」を失ったとき自明のものとして出現するにちがいない。単なる個人的な才能や力量だけでは、退廃から免れることはできず、才能や力量にも限界があるのもまた、これまでの多くの例に見られる通りだ。人は退廃する。成功しても、失敗しても。運動性を失ったとき、人は誰もがまるでそれが当然であったかのように退廃するし、そこから免れるためにも、いかに運動性を持続できるかが問われ、「個人的な才能や力量」に依拠しない集団的な創作の方法が、ここにおいてさらに試されることになるだろう。
遊園地再生事業団がその作業の方法として、いくら「ワークインプログレス方式」を採用しても、それが絶対的な正しさとしてあるのではない。これは、これとして、ひとつの試みである。ここでの「ワークインプログレス方式」とは、本公演にあたる舞台を上演するまでに、可能な限り時間を使い、その過程を何回かに分けて外部に発表することだ。
まず第一回のワークインプログレスは「リーディング公演」である。それは字義通り、戯曲の読みのことだが、ここで読まれる「戯曲」が最終形ではないのは、「テキスト(=言葉)」の次元でそうであるのと同時に、「表現」の次元においても最終形を示すものではないのを意味する。戯曲は単に素材かもしれない。もちろん、遊園地再生事業団は、宮沢の書く戯曲を上演するのを目的としているのが前提だが、戯曲を「書かれたもの」として擁護しつつ、けれど、本公演に向けてそこからいかに遠ざかり、身体的な表現へと昇華させるかは、いま演劇の表現において当然の課題としてある。べつの言い方をすれば、戯曲は書かれなければならないが、戯曲の言葉によって舞台が支配される過去の演劇の構造から遠ざかることを意味する。まず戯曲を読むことで、劇のアウトラインを示したのち、次に、第二回のワークインプログレスに進むとすれば、その課題は、「身体」になるのは必然だろう。「言葉」から「身体」への展開は、すでに述べたように、戯曲によって舞台が支配されないことを意味する以上、過去の演劇のような、どのように戯曲を再現するかという、あたりまえのように考えられてきた演出の方法とは異なる姿になるのと同時に、演出家という「個人の才能と力量」によって、戯曲を「個性的」に解釈し、それを元にいかにも「個性的」に表現したり、あるいは解体するような試みでもない。そこに集団的な創作が本来的に持っているであろう力が出現するのと同時に、いかに、身体から発する表現の魅力が、戯曲(=言葉)を可能な限り強度を備えたものとして舞台に具現できるかが試される。だから、リーディングというひとつのワークインプログレスを経て次に公開されるのは、言葉をより身体化し、いかに豊かにできるかを、様々な身体表現を探ることの積み重ねによって試す、ワークインプログレスだ。
おそらく、この国の古典芸能を踏襲しているのだろう「稽古」という用語は、いまでは、いかにも古めかしく感じるが、だからといってほかに思いあたる適当な言葉がないので、あえてそれを使えば、「稽古場」はここにおいて、透明なビーカーのように開かれているのを意味する。連続的なワークインプログレスは、いわば外部に開かれた研究室である。そしてこの一連の作業が持つきわめて不合理な時間の使い方は、演劇がもともと内包しているはずの、「不合理」という名前の美徳のことである。
『ニュータウン入口』
そこではとても美しい生活が約束されている。いま若い夫婦が不動産業者に案内されてこのニュータウンに来た。
たしかにそこはとてもいい街だ。安全な生活に住民は満足しているし、幸福感に充たされ、清潔に計画された土地で人々は快適な暮らしを送っている。そして、住民たちだけではなく、この国の誰もが記憶している「ニュータウンのある事件」がテレビで報道されても、住民たちにとっては見知らぬ土地の特別な出来事に過ぎなかった。自分の幸福とは関係がない。テレビのワイドショーで語られる程度の遠い物語だ。
なにもゆがみはない。生活に暗さはない。明るく計画された住区だ。合理的に造成された街路や、街路を装飾する樹木は、町に潤いをあたえる。新聞の折り込み広告にあるような、様々な種類の情報として流される、嘘のように飾られた住宅の絵や映像が、その町ではまさに実現しているようだった。住民はその土地を愛していた。これはニュータウンの住民たちによる、ニュータウン礼賛の物語だ。
若い夫婦はそこに土地を買うのだろうか。
ただ彼らが知らないのは、この宅地の下にある地層にこめられた歴史だっただろう。幸福感と礼賛に埋め尽くされた物語が忘れているのは、地層にこめられた歴史だ。一見すると、あらたに計画され造成された土地には歴史がないかのように見えるが、それというのも、住民たちにとってそもそもそこがどんな土地だったかという想像はまったくないからだ。かつてそこは森だった。森には動物もいたかもしれないが、もっと特別な力が棲んでいた。森から流れていたというあの風はいまどこに封じ込められてしまったのだろう。人を揺り動かすあの神秘的な力は。
ニュータウンの開発で土地が掘り返されたとき、土のなかから封じ込められたものが人々の前に姿を現す。
美しく計画されるはずの土地から小さな石が見つかる。
土に蓄積された歴史と、太古からの時間が、その石には封じ込められている。石が見つめてきた時間はどんな姿をしていただろう。石の放つ奇妙な力によって人々の生活は少しずつ、そしてゆっくりゆがんでゆくが、若い夫婦にはそれがわからない。住民たちも気づかない。自分たちの生活の危うさを石が語りだそうとしていることなど誰も知らない。けれど誰もが幸福だ。気づかないことによって幸福だ。幸福はいつまでも続くと誰もが信じて疑わなかった。
だが、それに最初に気がつくのは子供たちだ。石の力に素早く感応し、過去からの声に耳を澄ます。若い夫婦にはその声が届かない。ニュータウンは礼賛されるべきだ。つまらない否定や悲観などここでは語るに値しない。だから夫婦は決意する。
私はいかにして心配するのをやめニュータウンを愛し土地の購入を決めたか。
けれど、石の奇妙な力によってあきらかになる土地の本来の姿を見つめるとき、現在と過去、未来と太古、時間が織りなす物語が、石を通じてここから動き出す。
2007年7月吉日
作・演出 宮沢章夫

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結解除
凍結解除 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ