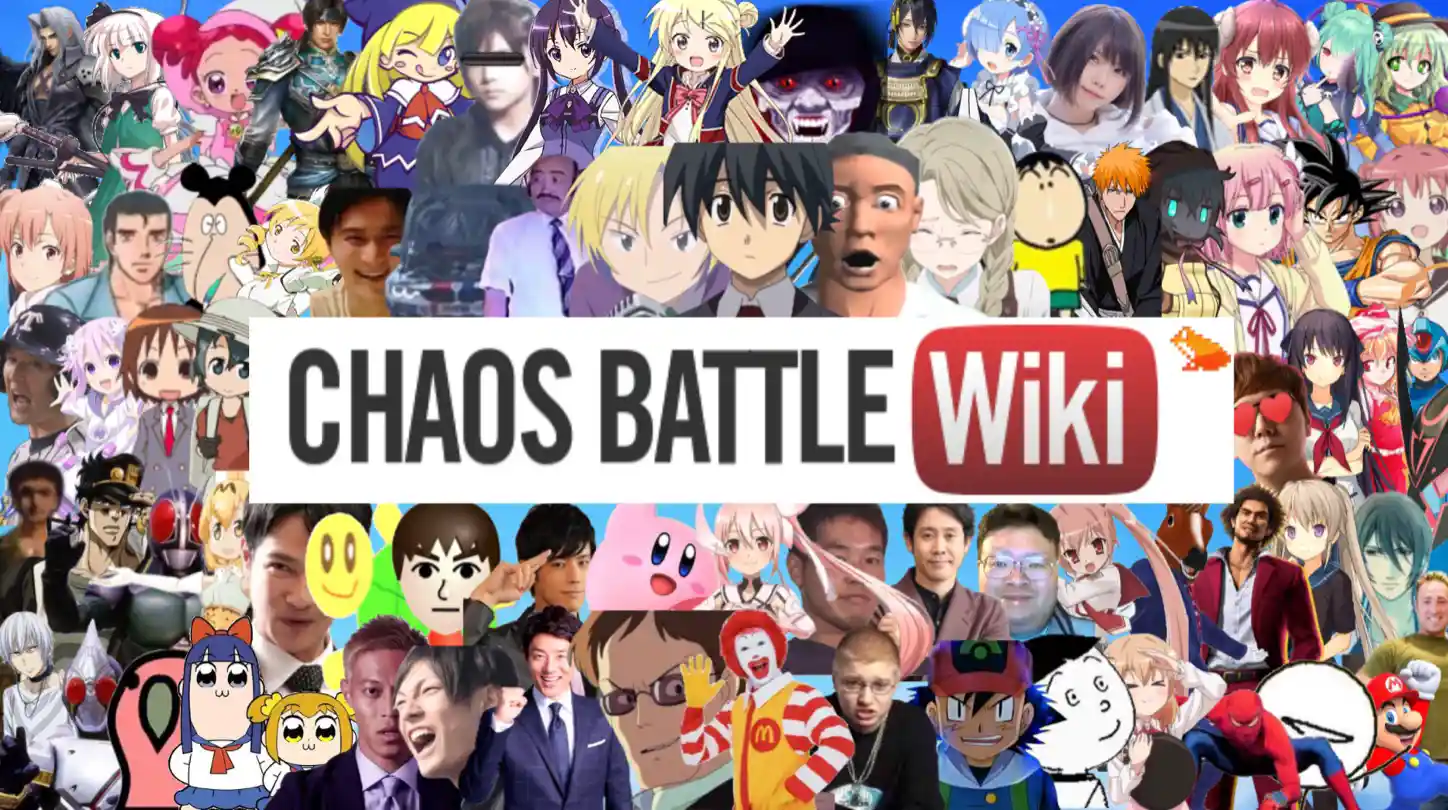日本国有鉄道の近郊型電車。
概要
1985年、東海道線に登場。軽量ステンレス製車体や構造の簡便なボルスタレス台車、サイリスタチョッパ制御より簡便かつ安価に回生ブレーキが使用可能で抵抗制御を基本とした界磁添加励磁制御、応答性の高い電気指令式ブレーキ、簡易的なモニタ装置等、省エネルギーや保守費用低減に配意した新機軸を採用した。これらは「次期近郊形電車」を念頭に開発されたシステムで、このシステムは民営化後のJR新型車両にも多数採用されている。尚このシステムは211系の同期、205系が先に導入している。
車両スペック
1ユニットあたりの力行性能の向上により、電動車比率を下げ、2M3T編成で25‰までの勾配でも通常の使用が可能であり、新製コストや運用コストの低減を狙った設計とした。これにより、2M3T編成でも113系・115系の2M2T編成と同等かそれ以上の走行性能を持つ。
3ドア20m車体だが、113系、115系等と比べて若干ドア位置を車端に寄せ、ドアそのものも113系等の2900mmから2950mmとした。
車内座席は0・1000番台がセミクロスシート、2000・3000・5000・6000番台は混雑に対応したロングシートとなる。
番台別解説
国鉄時代には首都圏と名古屋地区で計258両製造し、国鉄分割民営化時にはJR東日本、JR東海にそれぞれ引き継がれた。分割民営化後もJR東日本、JR東海、JR西日本が引き続き製造し、計569両が製造され、総計では827両が製造された。
0・2000番台
基本形式。東海道線向けの暖地仕様車で、0番台はセミクロスシート、2000番台は制御車のトイレ対向部を除きロングシートとなっている。東京地区には0・2000番台、名古屋地区には0番台が投入された。
東京地区
国鉄時代は、東海道線東京口用のグリーン車2両組込の0番台10両基本編成*16本と2000番台5両付属編成*25本の計85両が製造され、田町電車区(後の田町車両センター)に配置された。1986年3月3日のダイヤ改正から営業運転を開始した。
グリーン車は従来1両にトイレ・洗面所と専務車掌室を装備することが通例であったが、本系列ではトイレと洗面所のみ装備のサロ211形と専務車掌室のみ装備のサロ210形とに分けて製造し、これを組合せており、定員が増加している。シートピッチはこれまで通り970mmとしたが、車体が従来より広くなったので、通路幅600mmを確保したまま座席幅を475mmに広げ*3、背もたれはフリーストップ式とし、傾斜角度も従来よりやや大きくした。
導入当初、東海道線の東京駅~平塚駅間以外では喫煙が可能であったため、ロングシート車を含む各車両(除く禁煙車)に灰皿を設けていた。後の禁煙区間の拡大にともない、グリーン車を含め全車禁煙となり灰皿は撤去された。*4
JR東日本では、1988年度から1991年度までに基本編成8本と付属編成9本の計125両を増備した。従来、ロングシート車(2000番台)は付属編成のみであったが、基本編成もロングシートの2000番台車とされた。国鉄製造分と比較し、JR東日本の増備車(2000番台のN21・N56編成以降)では、車内の荷棚を金網式からパイプ式に変更、速度向上に対応したヨーダンパを装備する等の変更点がある。
グリーン車も定員増加を図るため、2階建のサロ213・212形とされた。*5
名古屋地区
1986年11月ダイヤ改正時に、名古屋地区において117系を6両編成から4両編成化して東海道線快速の増発が実施された。この際、増発分の車両不足を補うため0番台4両編成*62本が川崎重工業で製造された。
登場当初は東京地区用と異なり、先頭車の電気連結器と自動解結装置が非設置*7で、外装は東海地区のイメージカラーとした青色の帯に白のピンストライプを入れた独自カラーであった。その後、同車を引継いだJR東海のコーポレートカラーがオレンジ色となったことから、1988年に他車と同じ湘南色帯に改められた。これと同時期に電気連結器と自動解結装置も設置されている。
民営化後の増備が後述のロングシート車である5000番台車に移行したことから、JR東海が所有する211系では8両のみセミクロスシート車となっている。
1000・3000番台
東北本線*8と高崎線の使用に配慮した寒地仕様車。1000番台はセミクロスシート車、3000番台はロングシート車で、ともにスノープラウ、耐雪ブレーキ、半自動ドア、レールヒーターなどの耐寒耐雪装備がなされている。1986年2月18日から営業運転を開始。
普通車のみの5両編成*9。国鉄時代には1000番台11本、3000番台22本の計165両が製造され、民営化後は東海道線用と同様にロングシートの3000番台のみが1991年までに40本増備されている。
1000番台が全車両新前橋電車区(現・高崎車両センター)で、3000番台は当初クモハ211形・モハ210形・クハ210形の車番3001~3046が新前橋電車区、3047~3062が小山電車区(現・小山車両センター)配置であったが、2000年からE231系が小山電車区に新製配置になったことにより、同年12月に新前橋区に配置が集約されている(その後一部が幕張車両センターに転出)。
0・2000番台と同様に2008年秋頃よりモケット地をすおう色から青緑色に交換している他、順次PS33E形シングルアーム式パンタグラフへの取り替えおよび増設(一部)が行われた。
房総地区
2006年3月、JR東日本は宇都宮線・高崎線の上野駅発着列車のグリーン車連結率を100%にすることに伴い、グリーン車組み込みは10両基本編成17本が組成されることとなり、3000番台34本を使用して行われた。これに付属編成分として17本が残されたため、残る110両(5両×22本)分をE231系の投入によって捻出。これらの編成のうち70両(5両×14本)は、海岸線沿いを走行し塩害による腐食などが進んでいる房総地区各線の113系の置換え用として、幕張車両センターに転用することになった。残りの40両は、宇都宮線・高崎線の輸送力増強分に振り向けられた。
転用編成は、前面種別表示器をLEDから幕式への復元(一部)と、車体帯色を変更した上で大宮総合車両センターなどから2006年8月以降順次出場した。車体色は房総色とされた。編成番号はマリ401~414と付番され、2006年10月21日から運用を開始した。半自動ドアスイッチは残されたままであり、2006年からは千葉駅・蘇我駅を除き、駅での停車時間が5分以上ある場合に、扉横の半自動ドアスイッチの通年使用が行われていた。
長野地区
2013年3月16日のダイヤ改正より、長野支社管内で営業運転を開始すると発表された。2012年6月以降、元幕張車両センター所属および元高崎車両センター所属の一部車両が長野総合車両センターへ転属し、2013年3月15日にはダイヤ改正に先駆けて大糸線で営業運転に投入された。2014年3月以降の運用範囲は中央本線・篠ノ井線・信越本線・飯田線へ、2014年6月以降は中央本線立川駅まで運用を拡大している。
車体カラー帯を長野地区の115系・E127系100番台に合わせた長野色に変更し、先頭車の前位寄り台車に車輪の空転を防止するセラミック噴射装置「ミュージェット」を取り付け。6両編成に対し先頭車両に搭載の自動解結装置を撤去。保安装置変更、狭小トンネル断面に対応したパンタグラフへの交換といった改造が行われた。
2021年の途中から、3000番台のN314編成のクハ210-3048・N315編成のクモハ211-3049の前面種別表示器を白地・黒文字・ルビなしの幕式へ、N316編成のクハ210-3050の前面種別表示器がLEDに交換されている。
N314編成のクモハ211-3048・クハ210-3048とN315編成のクモハ211-3049・クハ210-3049の前面種別表示器をN301~N305・N331~N339編成と同等の表示幕へ再度交換された。
5000・6000番台
1988年に登場し、1991年までに242両が製造された。2M3Tを基本とするJR東日本の0・2000番台などとは異なり、4両 (Mc-M'-T-Tc'=2M2T) または3両 (Mc-M'-Tc'=2M1T) を基本とする電動車比率の高い編成となっている。
名古屋・静岡都市圏で使用されることから、ラッシュ対策のため、座席はオールロングシートとし、当初はトイレをすべて省略した。また室内からの展望に配慮して、先に登場していた213系?と同じく前面貫通扉と運転室助士席側の窓を下方に拡大した。
主電動機の冷却ファン形状を変更したことにより車内の静粛性を高めたほか、座席は0・2000番台などに比べてクッション材を厚く、奥行きを深く変更したことで座り心地の向上を図っている。網棚はパイプ棚となっている。電気連結器・自動解結装置の装備に伴い、ジャンパ連結器が省略されたことから、前頭部のスカート形状が0番台と異なる。また各車両両端4つのドアにはドア締切表示灯が設置され長時間停車時などドアカット時に表示する。車外放送用スピーカーも設置している。
スーパーサルーンゆめじ
JR西日本ではジョイフルトレイン「スーパーサルーンゆめじ」用として2両のみ211系を導入している。ホンマに211系なんか…?
1988年4月10日の本四備讃線茶屋町駅~宇多津駅間*10の開業時に新製され、快速「マリンライナー」用のグリーン車クロ212形と同構造の3両編成であった。車体帯はピンクと青で、3両編成1本(中間車のクロ212-1001は213系に区分される) が在籍していた。
快速「マリンライナー」用の電動車は1M方式の213系であるが、この編成を含むパノラマ車は車体強度確保のため普通鋼製車体となった。編成を組むクロ212形は1000番台。
1988年度グッドデザイン商品(現在のグッドデザイン賞)に選定された。
改造
JR東日本
後述の転用改造により0番台グリーン車4形式が改造された。
211系0番台から転用されたグリーン車は当時のペアのまま寒冷地仕様への改造が施工され、原番号+1000番台に改番された。扉脇の半自動スイッチを設置。
また置換え及び転用により113系2階建グリーン車の2形式が211系へ改造編入された。
車両の引き通し線を211系とするため、室内1階の床板を取り外して車内配線をすべて取り替え、車掌室に表示設定器を新設、一般配電盤を交換、行先表示器と車側灯をLED式に更新、ブレーキ装置を電磁直通式から電気指令式に取り替える等、大掛かりな改造が行われた。*11
高崎車両センター所属の車両でも2008年10月頃から一部の編成でパンタグラフが2基に増設された。なお、これらの編成に関しては全てシングルアーム式のPS33E形に交換されている。
2007年11月から房総地区の一部編成でパンタグラフを2基に増設する改造が行われた。増設されたパンタグラフはシングルアーム式のPS35C形となっており、前後で異なる形態となった。*12
JR東日本所属車は、前述のグリーン車置き換え(東海道線用)および組み込み(宇都宮線・高崎線用)が終了してから、乗務員室(クモハ・クハ)にデジタル無線対応工事が順次施工された。
JR東海
優先席の設置、転落防止幌の取り付け、全車両ドアチャイムの設置、車椅子スペース設置(名古屋方・車掌の立つ位置の前)、パンタグラフへの取替、東海道本線への313系?増備により120km/hに対応した速度計への交換、吊り革の客用扉付近への増設、ATS-PT取り付け、排障器(スカート)の延長、方向幕の交換等を行った。
台車へのヨーダンパ設置やブレーキの増圧対応工事のほか、側面行先表示器も311系と同様の列車種別幕と行先幕を別個にした方式のものに変更された。
置き換え等
東日本地区
田町車両センター・高崎車両センターの211系はE233系3000番台によって置き換えが進められた。*13
田町車両センター所属車は2012年4月23日に、高崎車両センター所属車についてもE233系3000番台を投入して置き換えを進め、2013年3月15日に宇都宮線上野口の定期運用を終了し2014年3月14日をもって高崎線での定期運用も終了。置き換えられた車両のうち、グリーン車は2014年12月までに全廃。電動車・制御車は長野地区や高崎地区に転用されている。
宇都宮線小金井駅~黒磯駅間での5両編成での運用は、2013年8月24日から運用を開始した205系600番台*14に置き換えられ2014年3月24日に運用終了した。宇都宮線と両毛線の直通列車2往復のうち、宇都宮線小山駅~黒磯駅間の1往復の運用は2017年3月3日、小山駅~宇都宮駅間の1往復の運用は2019年3月16日のダイヤ改正で廃止され、3ドア車両(烏山線直通列車は除く)の定期運用は消滅した。
東海地区、名古屋地区
JR東海では2022年から本形式置き換えのため315系の導入が開始されており、2025年度までに全車引退が予定されている。2022年3月に神領車両区の編成は順次廃車となっている。
記録はお早めに。
西日本地区
2003年9月30日まで快速「マリンライナー」として岡山駅 - 高松駅間で使用されていたが、2003年10月1日に快速「マリンライナー」が213系から223系5000番台およびJR四国5000系に置換えられ、213系(クロ212形0番台と1000番台を含む)および「ゆめじ」編成による快速「マリンライナー」の運用が終了した。
2010年3月7日に岡山駅 - 大野浦駅間で実施されたさよなら運転「ファイナルラン さよなら!スーパーサルーンゆめじ号」での運用をもって営業運転を終了し、6月30日付で廃車。
現在の運用
- 両毛線/上越線/吾妻線/信越線*15
- 信越本線*16/篠ノ井線/中央本線*17/大糸線*18/飯田線*19/富士急行線*20
- 中央本線*21/関西本線*22/愛知環状鉄道線*23
- 東海道本線*24/御殿場線/身延線*25
余談
- 瀬戸大橋線の「ゆめじ」編成は瀬戸大橋線開業時に当時の皇太子・皇太子妃夫妻を乗せて走行した実績がある。
- 高崎車両センターの211系は行き先表示器のLED化が進められたが、A36編成は現在も行き先表示器が方向幕式。
- 2024年に静岡地区SS2、SS3、SS7、SS8、SS11の計5編成が三岐鉄道に譲渡された。三岐線で運用する。既存の西武鉄道からの譲渡車は置き換えとみられる。
- プラレールで製品化される際に車体は211系専用の新規金型になる予定だったが、強度orコストの関係で新規金型は見送られ、205系と同じ車体に変更された。
↓
証拠ツイート
別角度
カオスバトルでは
初出は恐らくムスカ大佐破壊神。
技
- MT61形界磁添加励磁制御
- 警笛(※未使用)
- ドア閉