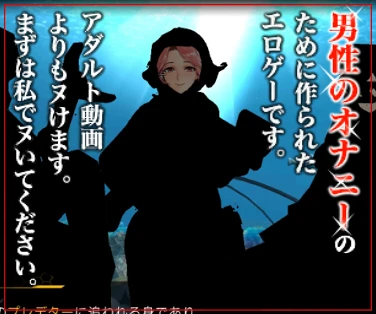「……そんな次第で、余はつい先日やっと、本当の意味で殿の御心を知ったというわけさ。まったく、己が不明を恥じるばかりだ」
プレスターヨアンナが短い話を終えて、小さく頭を下げる。拍手と、様々な思いのこもったため息がそれに答えた。
「たしか貴殿は主君が来て間もない頃、外部拠点の開拓任務を買って出てオルカを離れましたね。もしかして、あれも?」アタランテが空のグラスにワインを注ぎ、ヨアンナは会釈をしてそれを受け取る。
「ああ。人間とできるだけ距離を置きたかったのだ……ただ、思えばあれは悪手であった。もう一月か二月、共に過ごしていれば、殿のお心の広さはすぐにわかっただろうにな」
「本当ですよー」マジカルモモがぷうと可愛らしく頬をふくらませた。「ヨアンナさんがずっとそんな風に悩んでたなんて、モモ全然知りませんでした。もうけっこう長い付き合いなのになー」
「ヨアンナ公はなんでも内にかかえ込みすぎなのです」なぜだか水着姿のシャーロットが割り込んでくる。「もっと、すべてをさらけ出せばよいのに。この私のように」
「なかなか、卿のようにはいくまいが……今後はもう少し心がけよう」
「懺悔のため部屋を暗くして……なるほど、そういう手が……」クノイチ・ゼロは何ごとかメモしている。
ヨアンナを囲んで盛り上がる伝説サイエンスのバイオロイド達を、クローバーエースは目を輝かせて眺めていた。
「すごいな、テレビや映画で見たヒーローが勢揃いだ」
「貴女もそのヒーローの一人でしたけれどね」
その隣でアルマン枢機卿が、微笑んでグラスを傾けた。
SS級への昇級手術も受け、もうじき外部拠点再建のためふたたびオルカを離れるヨアンナの壮行会と、最近オルカに加わったクローバーエースの歓迎会を兼ねて、伝説組だけの小さなパーティを開こうと提案したのはマジカルモモだった。
「それではもう一度、ヨアンナさんのためにかんぱーい!」
箱舟の会議室をひとつ借りて、白いクロスの敷かれたテーブルに軽食と飲み物、そして誰がどこから調達してきたのか、差し入れの高級そうな酒や菓子が並ぶ。昔テレビで見た芸能人の打ち上げのような光景だと思って、クローバーエースは一人で笑った。ここにいるのはまさしく芸能人ばかりなのだ。自分も含めて。
「クローバーエース卿、正式な挨拶がまだであったな。プレスターヨアンナだ」グラスを二つ手に持って、サーコート姿のヨアンナがエースのところへやってきた。
「初めまして! 『エルサレムの黒き盾』観たことあります。会えて嬉しいです」頬を紅潮させて、エースはグラスを受け取る。ヨアンナが苦笑した。
「伝説の同僚からそう言われるのは、みょうな気分だな。もちろん『クローバーエース・ショー』は余も知っている。それに、世界のあちこちでバイオロイドを助けて鉄虫と戦う『不思議な流れ者ヒーロー』の噂もな。オルカに加わってくれてくれて心強い」
「そんな、こちらこそ。オルカの話はあちこちで聞いてました」
「モモのことも知ってます?」ヨアンナの後ろから、モモがひょこりと顔を出した。
「マジカルモモ! 本物はやっぱり可愛いなあ! 新作映画のたびに観に行ってたけど、特に『花の都のミルフィーユに想いをこめて』が最高だったよ。ディスクも買ったんだ、パリの風景がすごく良くて、ちょっぴりロマンチックで」
「拙者たちの戦いの映像もご覧になったでござるか?」
「もちろん! 『大戦乱』は私たちの学校じゃ歴史の教材になってた。授業で観たのは第一部だけだったけど、私は第三部が好きだな」
「当然私もご存じですわね?」
「ごめん、『シャーロットロマンス』は小説版しか読んだことないんだ」
「なぜ!?」
ショックで涙目のシャーロットに、アルマンがくすくす笑う。「あれには私が出ているからですよ。さすがに、同じ顔が画面の向こうにいては怪しまれますからね」
「いや、見たかったんだよ? 小説はすごく好きだったし」クローバーエースもあわてて弁解する。「でもリバイバル上映があるたび、なんでかちょうど機械帝国が出てきて……ああそうか、でもあれも番組の都合だったのかあ」
「そうですね。実際、『シャーロットロマンス』はかなり貴女好みだと思いますよ。箱舟のライブラリにありましたから、あとで観てみたらいいでしょう」
「絶対観て下さいね! 絶対ですよ!」
「いやー、緊張したなあ」
ひととおりの挨拶を終えたエースはテーブルに戻って、並んだ料理をぱくぱくと平らげる。
「伝説の人たちってさ、なんていうか、いろんなタイプがいるんだね? みんな私みたいのかと思ってた」
「そうですね……あなたはむしろ、新しい番組製作スタイルのテストケースでした。役者、俳優タイプの方が、数としては主流ですね。私もそうですし」
アルマンも小さなサンドイッチを上品にかじりながら、エースの方を横目で見やった。
「……本当によかったのですか? オルカに腰を落ち着けてしまって」
「え、どういう意味?」シュリンプフライを頬張りながら、エースは目を丸くする。
「あなたは旅の途中でしょう。途中で止めていいのですか? 陛下はバイオロイドの自由と主体性を何より尊重して下さいます。旅を続けたいと言えば、きっと許して下さいますよ」
「そりゃ……」エースは言いよどんだ。「……ここは、バイオロイドが幸せに暮らせる場所だって聞いたけど。違うの?」
「違いませんとも。私たちにとって今この地上で、陛下のおそば以上に幸せな場所はありません」きっぱり言ってから、アルマンはクローバーエースの顔をまっすぐに見た。
「ですが、それは普通のバイオロイドの話。あなたは自由も、幸せも、すでに手にしているはずです。自覚していますか、それはとても希有なことなのですよ? 特殊な立場と、そのために与えられた人格と性能、そして偶然のタイミングが奇跡のように噛み合って、自由なるヒーロー・クローバーエース、今のあなたは生まれました。そのあなたをここに留めてしまうのが果たしてよいことなのか、私は測りかねています」
エースは口の中のものを飲み込んで、唇をペロリとなめた。「私のこと、すごく気にかけてくれるんだね」
「私はルージュの伝言と記憶を預かった身です。貴女が本当に自由で、幸福であるか、見極める責任がありますので」
真顔で答えるアルマンに、エースは小さく笑う。
「そういうところ、ルージュとそっくりだ」
「基本的な人格プログラムは同一ですから」アルマンが小さく肩をすくめた。その仕草もルージュによく似ていて、エースはまた笑った。
「さっきも言ったけど、オルカのことは前から聞いてたし、興味があったんだ。最後の人間が率いる抵抗軍なんて、いかにもヒーローにふさわしい場所じゃないか」
「それだけですか?」ナプキンで口元をふきながら、アルマンがちら、とエースを見上げる。
「……元々、目的地のある旅じゃないし。一人旅も、そろそろ寂しくなってきてたしさ」
「それだけ?」
エースは顔をしかめてアルマンを見た。「……もしかして、わかってて聞いてる?」
「さあ、どうでしょう?」
エースはしばらくためらってから、身をかがめてアルマンの耳元へ口を寄せ、小声で何事か囁いた。アルマンは満足そうに頷く。
「それなら、何も問題はありません。ようこそ、オルカへ」
「そういう意地悪いところも、ルージュそっくりだな!」顔を真っ赤にしたエースに、アルマンはすました顔で言った。
「基本的な人格プログラムは同一ですからね」
* * *
夕暮れの風が冷たい。
北極圏に位置するスヴァールバル諸島では、盛夏であっても摂氏10度を越えることは稀だ。人間ならばコートが必須だが、バイオロイドにはさほどのこともない。クローバーエースとプレスターヨアンナの二人は黙ったまま、冷たい夕陽が照らし出す岩だらけの湿地を歩いた。
太陽はまもなく西の海に沈みそうに見えるが、決して沈むことはない。白夜の季節だ。
「……すごいな。これが白夜か」
最初にこの島に上陸した時は特に見るところもないと思ったものだが、間違いだった。クローバーエースはため息とともにあたりの景色を見回し、そうしてヨアンナの背中に視線をもどす。
(少し、外を歩いてみないか)
パーティも半ばを過ぎ、皆がなんとなく落ち着きだした頃、ヨアンナがふいに声をかけてきて、エースは外へ連れ出されたのだ。
彼女はオルカの中でもかなりの古株だと聞く。新参者を一発シメておこう、とでもいうのだろうか。昔の学園生活を思い出してひそかに腹筋に力をこめたりしていると、ヨアンナが歩きながら振り返った。
「クローバーエース卿」
「は、はい」
「敬語はよしてもらいたい。ここでは皆、同僚だ」ヨアンナはやわらかく笑う。
「卿は……かつての時代、巨大なセットとして丸ごと作られた街の中で、普通の人間と同じように暮らしていたのだったな」
「はい。あ、いえ、うん」エースは頷いた。「当時は、自分は人間で、本当に悪と戦ってるんだと思ってま……思ってた」
「リアリティ・ショー形式というやつだな」
ヨアンナは、淡いオレンジ色に染まる湿原のほうへ目を投げた。つられてエースもそちらを眺める。
「思えば伝説は常に、よりリアリティのある表現形式を追求していた。あのまま世界が続いていればあるいは、卿のようなスタイルが主流になったのかもしれぬな」
足音と風の音以外、聞こえるものは何もない。ほとんど呟くようなヨアンナの声も、はっきりと聞こえた。
「余は伝説のバイオロイドの中でも、ごく初期のモデルだ。そのせいか知らぬが、モモ卿やシャーロット卿と比べると役者魂というか、俳優としての意識が希薄なようでな。演技の技術は身につけていても、演じること自体の喜びや誇りといったものはあまりないのだ。おそらくそれも、リアリティを追求する試みの一環だったのだろう。……最初期のモデルと最後期のモデルが、ともに演じることから離れていったというのは、思えば面白い話だ」
どう答えればいいのか、クローバーエースが戸惑っているうち、ヨアンナはふと足を止めた。エースも合わせて立ち止まる。特に何があるわけでもない、湿原の真ん中だ。
「失礼を承知で聞きたい。卿は先ほど、『エルサレムの黒き盾』を観たと言ったな。それはくだんのショーが続けられていた頃……つまり、卿が自分を人間だと思っていた頃、ということでよいのか」
「え……うん。そうだよ」
「そして後になって、バイオロイドや伝説のことを知った?」
エースはもういちど頷く。ヨアンナはしばらく黙ってから、エースの方に向き直った。
「感想を聞かせてくれまいか。あの映画を観て、卿はどのように感じた?」
「……!」
まっすぐな視線をまともに受けて、エースは言葉につまった。
あの映画の撮影で何が行われていたか、もちろん今のエースは知っている。それは外の世界では隠すことでも何でもなく、どんな映画情報誌にも書いてあったからだ。
自分は責められているのだろうか? 無責任にも人間のように、あの映画を楽しんでしまったことを? いや、彼女の眼差しにそんな色はない。考えろ。きっと、自分にしか答えられないことがあるのだ。この問いのためにこの人は自分を連れ出したのだと、今はエースにもわかった。
「……あの映画の撮影のために、伝説がどんなことをしたかは聞いてる。あんなことは、二度とあっちゃいけないと思う」
ゆっくりと、一言ずつ考えながら、言葉をつむいでいく。ヨアンナは黙って聞いている。
「でも、そういうことを何も知らないで観た時は……感動した。すごかった。戦争も、信仰も、人の死も、それを乗り越えて生きる人たちも、まるで本物みたいな、ものすごい迫力で輝いて見えた。私はたいして映画に詳しいわけじゃないけど……それでも、あんな映画はほかにないと思う」
エースが言い終えても、ヨアンナは長いこと黙っていた。
どれくらいそうしていただろう。夕陽は水平線の上をいつまでもすべるように動いて、時の経過を教えてはくれない。吹きつける風がさすがに肌寒く感じられてきた頃、ヨアンナはようやく口を開いた。
「あの……あの現場からどんな作品が生み出されたにせよ、余が奪った同胞の命とつり合うものだとは決して思わぬ。しかし少なくとも、まるきり無価値というわけではなかったようだ。それを慰めと思うべきかは、まだ判断がつかぬが」
それから、ヨアンナはエースに深く頭を下げた。
「ありがとう、クローバーエース卿。心より感謝を」
「い、いやいやいや!」エースはうろたえて頭と手をぶんぶん振った。
「私なんかそんな! 今のオルカが発信してる映像も、私は大好きだよ。『プロジェクトオルカ』は何度も見た」
「ほう! あれを観たのか」
ヨアンナが頭を上げて、ぱっと笑った。エースはようやくほっとして、「もちろん。どこへ行っても、あれを見てない人なんていなかったよ。これからオルカに合流するんだって言ってた人もいたし、ひみつ付録の方だってみんな……」
「ひみつ付録?」
エースはぱっと口元を押さえた。
しかし、もう遅い。しばし怪訝な顔をしたヨアンナが、ハタと手を叩いた。
「ああ、あれか。タロンフェザー卿がデータ漏洩を装ってこっそり配信したという、ライブの後のスカイナイツの」
必死に平静を保とうとしたが、無理だった。頬がぐんぐん熱くなる。ヨアンナの顔をまっすぐ見られない。そんなエースを見て、ヨアンナがにやりと笑った。
「もしや、卿はあれでオルカに興味を持たれたか?」
「そ、それだけじゃないし!」叫んでから、墓穴を掘ったと気がついた。ヨアンナがいっそう笑顔になる。
「はっははは! そうか、そうか! いや結構、大いに結構。卿が望みさえすれば、それは遠からず叶えられよう」
先程までの空気を吹き飛ばすようにひときわ大きく笑ってから、ヨアンナは大きく息をついた。白い息が風に流れて、すぐに消えていく。
「さて、帰るとしようか。主賓が二人とも抜けたままでは、会も締めようがあるまい」
行きより少しだけ早足に、二人は歩いた。先をゆくヨアンナは時折思い出したように、クックッと小さく笑う。
「……そんなに笑わなくたっていいじゃないか」
「いや失敬、おかしくて笑ったわけではないのだ」ヨアンナが少し歩をゆるめて、エースの隣に並んだ。「ただ嬉しくてな。卿のような特別なバイオロイドまでもが、殿にあらがえぬ魅力を感じてくれるということが」
「私は別に、特別なんかじゃ……」
「卿は自分が幸せだ、と断言したそうではないか? 生まれてこの方、余はそんなバイオロイドを見たことがない。無論、殿にお会いする前の段階では、という意味だが」
「……アルマンにも同じようなこと、言われたな。さっき」
ヨアンナの横顔を眺める。夕陽に照らされた浅黒い顔は穏やかだ。
「司令官さんって、どんな人? まだ挨拶しかしてないんだけど」
「アルマン卿は何と?」
「自分で知っていくのが一番だって、何も教えてくれなかった」
「では、余の答えも同じだ」
不満げなエースをなだめるようにヨアンナは微笑んで、エースの目の前に指を二本立ててみせた。
「だが先達として、二つほど助言を授けておこう。この先、卿が殿にどのような気持ちを抱くにせよ、その気持ちのまま、自由に振る舞うべし。おそらく殿も、いや殿こそが誰よりも、それを望んでおいでだ」
「……二つ目は?」
「卿が興味を抱いたそのことが、この先起こったとしてだが」ヨアンナはいたずらっぽく片目をつぶる。「これまでどのように期待を膨らませてきたにせよ、それをはるかに超えるものだと心得よ。殿は大層タフであられるゆえな」
赤面したエースを見てヨアンナは笑い、両手を大きく空に広げて、歩きながらくるりと回った。
「“夕暮れの時はよい時、かぎりなくやさしいひと時。冬なれば暖炉の傍ら、夏なれば大樹の木陰。それは過ぎ去った夢の酩酊、今日の心には痛いけれど、しかも全く忘れかねた、そのかみの日のなつかしい移り香……”」
「ヨアンナさん、役者魂がないって言ってなかった?」
「これは素だ」
よく通る声が朗々と、湿原の上をわたる。その声の残響を追いかけるように歩いてゆく二人のバイオロイドを照らす夕陽は、いつまでも沈まなかった。
End
白っぽく色の抜けた赤毛はカサカサに乾いてよじれ、額から頬にかけてへばりついている。柔らかな皺がいく筋も刻まれた、透けるような象牙色の肌は、色ガラスで作ったオブジェか、でなければ干物になる途中の魚を思わせた。
うっすら開かれたまぶたの下の、色素の薄い瞳が、不安定にふるえながら右から左へさまよう。その視線が俺の上へ止まったタイミングをとらえて、俺は立ってベッドの傍らへ進み出た。
「おはようございます。初めまして、ミセス・マリア・リオボロス」
リールで回収したマリア・リオボロスの棺をドクターが検査した結論は、
「不完全」
だった。
「これって正確には遺体じゃなく、ヒュプノス病の末期状態になったところを冷凍したんだね。でもプロセスが不完全だし機器の調整も甘い。少しずつだけど細胞の損壊がはじまってる。ヒュプノス病のことも色々わかってきたから蘇生はできそうだけど、今すぐやって成功率は六割ってとこ。一年後にはゼロになるかな」
報告を聞いた俺はオルカの幹部達と相談し……最終的に、今すぐ彼女を蘇生させることにした。賛否は色々あったが、この場合まず優先されるべきはワーグとの約束だと判断したのだ。
「…………要は、アンヘルは死んだ。人類も全部滅んだ。地上にいるのはバイオロイドと鉄虫だけ、と」
「はい。ここにいる俺と、たった今目覚めたあなた以外は」
「………………」
マリア・リオボロスはリクライニングベッドに背中を預けたまま、天井と壁の境目あたりへ視線を投げていた。事前に読んだ資料では、整形手術によって七十を越えても若々しい外見を保っていたとあるが、冷凍されている間に整形の効果も抜けてしまったのか、目の前にいるのはどう見ても年相応の老婆だ。皺の刻まれた顔には何の表情もなく,俺の話を信じてくれたのかどうか、それ以前に聞いているのかすらわからない。
もういちど最初から説明した方がいいかしらと思い始めたころ、マリア・リオボロスはようやく枯れ枝のような指を持ち上げ、病室の窓をさした。
「窓を開けてもらえる?」
俺は言われたとおりにカーテンを引き、窓を開けはなった。部屋の隅に控えていたラビアタがさっと立ち上がり、女帝の肩まで毛布を引き上げる。北極圏の風が、病室に吹き込んできた。
窓の外には雪に覆われた原野と、そして冷たい青灰色の海が広がっている。女帝は弱々しい手で酸素マスクを外し、深く息を吸い込んで、そして少し咳き込んだ。
「ともかく、奴のいない世界の空気を吸うことはできた」
他人事のように彼女はそう言って、うすく笑った。
「……ミセス・マリア。ここには、エンプレシスハウンドの隊員がいます。彼女たちに会っていただけませんか」
「……?」それは何? というように、女帝はしばらくぽかんとした顔になった。「……ああ。あれか」
手を上げて合図すると、ドアのロックが開き、薔花、チョナ、そしてワーグが順に病室へ入ってきた。
薔花は顔をしかめて目をそらしている。チョナはいつも通りの態度に見えるが、笑顔が固い。そしてワーグは、
「女帝陛下! マリア様……っ!」
女帝の姿を一目見るなり駆けよって膝をつき、そのまま泣き崩れた。ベッドのふちに顔を埋めるようにして嗚咽するワーグを、女帝はただぼんやりと眺めていた。
ラビアタの目配せで、俺は外に出た。よそ者がいない方が話しやすいこともあるだろう。どのみち、あまり長時間接触しないように言われていたのだ。
「相手は三大企業の幹部、『あの』女帝マリア・リオボロスです。人間と会話した経験さえないご主人様が彼女と渡り合うなどとんでもない。ハムスターが狼の相手をするようなものです」
ラビアタの言い様はあんまりだと思ったが、反論もできない。俺はそのまま廊下をすすんで、突き当たりに設けられた監視用の部屋へ入った。この小さな療養施設は、女帝のために大急ぎで建てたものだ。医療設備が整っているのはもちろんだが、室内の様子は厳重に監視され、録画されている。施設の周辺には常にスナイパーが控えており、最悪の場合には建物ごと爆破して海に沈めることもできるようになっている。
モニタを睨んでいたシラユリが、俺の方へ小さく会釈をした。彼女の隣に座って、監視カメラの映像をいっしょに見る。
マリア・リオボロスはベッドに横たわったまま、エンプレシスハウンドと言葉少なに会話をしていた。大半は今の世界の状況に関する質問や確認だったが、自分のことやワーグ達に関する他愛ない話もあった。喋っているのはほとんどワーグで、たまに薔花やチョナも短い相づちを返す。俺が映像を見ていた間、女帝は一度も笑わなかったが、かといって声を荒らげたり、怒りや憎しみの感情を見せることもなく、ただ淡々とまわりの物事を見聞きしているようだった。
それは全体として、上品で知的で心身のおとろえた、ごく当たり前の老婦人の姿に見えた。怨念に凝り固まった残忍な女帝ではなく。
「まだショックが抜けてないんだろうか。もしかして、脳にダメージがあったとか?」
「というよりは、むしろ……」シラユリは細いきれいな指で、下唇のまわりをゆっくり撫でた。
「彼女は滅亡前の世界で、あまりに多くの物事を……財産や、計画や、敵や味方を抱えていました。それらが一度に消えたために、価値判断や情緒的反応の基準まで同時に失われ、ある種の……殻が取れたというか、精神的に初期化された状態になっているのでしょう」
「つまり、今の状態が本当の彼女ってことか?」
「それは微妙な問題です」シラユリはうすく笑った。「蝋燭の芯だけが本当の蝋燭だと言えるでしょうか?」
ワーグはずっとベッドの側にひざまずき、主人の足元に控える犬のように、幸せそうに頭を垂れていた。そして女帝は、その頭をゆっくりと撫でてやっていた。
慈愛に満ちた母のように、などという感じでは全然ない。しかし、優しくないわけでもない。例えるならそれは、他人の子犬を撫でるような手つきだった。親密さも思い入れもないが、「これは優しくしてやるべきもの」ということだけはちゃんとわかっている。そんな風に見えた。
「時間です。これ以上は患者の体に障ります」
ラビアタの指示でワーグ達が外へ出されると、監視部屋へ呼んできて話を聞く。
「あれが女帝? アタシを罵っては殴ってきたあのババアと同じ人間だなんて思えない。本物なの?」
「いっぺんに三十歳も老けたみたい。肉体的にはあの頃から大して時間たってないはずなのに、不思議だね~」
「いや。あれはマリア様だ。間違いなく」戸惑いを隠せない薔花たちとは対照的に、ワーグはきっぱりと言った。
「頭撫でてくれたからとかじゃなくて?」
チョナのからかうような言葉にも、ワーグは動じず首を振る。「そんな表層的な理由ではない。マリア様は本来、穏やかで思索的な方なのだ」
「本当かよ」
肩をすくめる薔花を無視して、ワーグは俺に深く頭を下げた。
「あらためて感謝する、司令官。最後の願いが叶った。もう思い残すことはない」
* * *
翌朝、マリア・リオボロスが呼んでいるとの連絡をうけ、俺はふたたび病室を訪れた。
「私には、どれだけ時間が残っている?」
俺が部屋に入るなり、女帝は挨拶もなしにいきなり言った。俺は一瞬、言葉に詰まって立ちすくんでしまい、彼女はそれで大体のところを察したようだった。
マリア・リオボロスは死から蘇ったわけではない。ヒュプノス病の症状を中断させた結果、生命活動が一時的に再開しただけだ。不完全な冷凍で傷ついた神経は、重金属被覆手術には耐えられない。彼女はほどなく、永遠の眠りに戻ることになる。それは最初からわかっていたことだった。
ドクターの見積もりによれば、覚醒から再入眠まで長くて48時間。
実際のところそういうタイムリミットがなければ、いかにワーグのためといえど、レモネードデルタとの戦争がまだ続いているこの時にブラックリバー上層部の人間を復活させるなどという選択はできなかっただろう。
隣のラビアタが肯定の目配せをしている。俺は咳払いをしてから、事実をそのまま告げた。
女帝は顔を冷たくこわばらせた。さすがに、あと一日というのは予想を超えていたのだろう。しばらく黙ってから、彼女はひどく虚ろに聞こえる声で言った。
「……私にさせたいことは何だ。あるいは、訊きたいことは」
「してほしいことは別にありません。……鉄虫とヒュプノス病、星の落とし子について、知っていることがあれば教えてください。それと、PECSとレモネードシリーズについても」
「どれも大したことは知らんな。星の落とし子とやらは聞いたこともない。何だそれは?」
俺は星の落とし子とヒュプノス病の関係について、できるだけかみくだいて説明した。女帝は大きく息をついて、枕に頭をあずけた。
「ブラックリバーの機密でも訊かれるのかと思ったが」
「ブラックリバーがもうないのに、機密など意味がないでしょう」
「それはそうね」女帝はつまらなそうに鼻を鳴らしてから、「つまり私を蘇生したのは、ワーグに私を会わせるためか」
それだけではないが、それが一番大きな理由なのは確かだ。頷いてみせると、女帝は唇の端をゆがめた。
「バイオロイドのために、人間の命を左右するとは……確かに、ここは私の生きる時代ではないようね」
そうして彼女はぐったりと横になったまま、遠い目線を窓の外へ向けた。
俺はだまってその姿を見ていた。滅亡前の世界を知らない俺には、彼女の本当の胸中はわからない。たとえばある朝目覚めたら見知らぬ誰かに「もうオルカもレモネードオメガも、鉄虫も星の落とし子も、誰もいません」と言われたら、どう感じるだろうか。
長い時間が過ぎた。女帝は枕から頭を上げ、きっぱりとした口調で俺に告げた。
「窓を開けて。それから、エンプレシスハウンドを呼びなさい」
駆けつけてきたワーグ達を女帝はベッドの前へ整列させ、その顔を順繰りに眺めてからおごそかに言った。
「今日までご苦労だった、エンプレシスハウンド。お前達の任を解く。私から命じることはもうない。好きなように生きるがいい」
薔花は忌々しげに目を伏せて肩をすくめた。チョナはおどけた調子でひょいと頭を下げた。膝をついて深々と礼をしようとするワーグだけを、女帝は呼び止めた。
「ワーグ、お前だけは別よ。最後の任務を与える。私を殺しなさい」
「はっ…………?」
ワーグが凝然と動きを止めた。俺も聞き違いかと思って、何度か目をしばたたいた。
「ミセス・マリア、一体何の……」
「黙れ」
俺を遮ったのは女帝ではなく、ワーグだった。
「女帝は冗談など仰らない。言い間違いをすることもない」
食いしばった歯の間から、一言ずつ押し出すような言葉だった。
「やはりお前は他とは違うわね」女帝は満足げに言った。
「どうせ明日にはない命。お前の百年にわたる精勤に報いるものは何もないが、せめて私の死をお前にやろう」
ワーグは肩を小さく震わせ、跪いたまま動こうとしない。ようやく顔を上げたとき、その白眼がまっ黒に染まっているのが、俺にも見て取れた。
「本当に……よろしいのですね」
「古来より、子は親を殺し、人は神を殺して、自己を確立してきた。次はバイオロイドの番かもしれない。せいぜい立派に務めてみせなさい」
「薔花。チョナ」
立ち尽くしていた二人は、ワーグに小さく名を呼ばれて我に返ったようだった。「外に私の装備が置いてある。持ってきてくれ」
ラビアタがドアを開ける。二人はワーグの言葉に一言も返さず、小走りに出ていった。
「司令官。……外に出ていてくれないだろうか。殺人を犯すところを、見られたくない」
消え入るような声だった。俺はマリア・リオボロスに最後の一礼をして、部屋を出た。
廊下には、ワーグの武器スコルとハティを抱えて戻ってきた薔花たちがいた。俺はここでも何も言わず、目礼して二人とすれ違い、そのまま建物の外へ出た。
スコルとハティはワーグの身長と同じくらいある長大な刀だ。狭い病室で振り回すのには向いていないが、生涯で最も重い任務を果たすのに、使い慣れた愛用の武器以外を使う気にはなれないのだろう。ワーグの腕前なら、見事に扱ってみせるに違いない。
風が冷たい。こんな時煙草を吸えたらいいのだろうかと、ふと思った。
病室の窓ごしに、ワーグのすすり泣く声が聞こえてきた。
* * *
立ち会うのは俺と護衛数人だけという、寂しい葬儀だった。
マリア・リオボロスの蘇生はもともと限られた幹部にしか知らされていない。この墓が誰のものであるかも、ほとんどの隊員は知ることがないだろう。
ワーグは誰よりも長い間、その簡素な墓の前に頭を垂れていた。
「私の命は女帝のものだった。今日この時からは、私のものだ」
最後に小さくそう呟いて、ワーグは立ち上がった。
「そして、私はこの命を司令官、あなたのために使う。あらためて、そう誓います」
こちらを振り向いた彼女は目尻に涙を浮かべていたが、今まで見たこともないような、澄んだ力強い笑顔をしていた。俺は手を差し出し、ワーグはその手をかたく握り返してくれた。
オルカへ戻る道すがら、俺は二日間女帝の看護を担当してくれたラビアタに礼を言った。万が一のことを考えて、ブラックリバー製以外かつ人間の強制力が絶対効かないとわかっている彼女にしか頼めなかったのだ。
「ご主人様のためですから、何でもありません」
ラビアタは涼しい顔で言ってくれたが、旧時代の人間、それも企業幹部と接することが辛くなかったはずはない。俺は感謝の気持ちを込めて、隣を歩くラビアタの手をとった。
「でもな、ラビアタ。マリア・リオボロスのあの様子を見ていて、俺はこんな風にも思ったんだ」
バイオロイドに対して信じがたいほど残酷で邪悪な仕打ちを繰り返してきた旧時代の人間たちは、しかし決してその本質から残酷で邪悪だったわけではない。おそらくは時代が、社会が、彼らをそのような人間にしてしまったのだ。まったく新しい世界、まっさらの状況でバイオロイドと向き合えば、ちがう関係を築くこともできる。そう希望を持ってもいいはずだ。
「…………」
ラビアタはだまって微笑んだまま、俺の言葉を肯定も否定もしなかった。
ある日、マリア・リオボロスの墓の前にロクがいるのを見かけた。
ロクはつい先日まで、ずっと長期遠征任務に出ていた。あれが誰の墓なのか、俺はまだ伝えていない。
ハウンドの誰かが教えてやったんだといいなと、俺は思ったのだった。
End
ティーワゴンが小さく揺れて、白磁のポットとカップがカチャンと音を立てた。向かいに座る龍がちらりと目を走らせると、ワゴンを押していたウンディーネが身をすくませる。
「ありがとう。あとは俺がやるから」
「はいっ。お呼びがあるまでお邪魔しないようにしますので、ごゆっくりどうぞ」
ぴょこんとバネ仕掛けのようなお辞儀をして小走りに去っていくウンディーネの背中を、ラビアタは小さく苦笑いして見送った。緊張するのも無理はない。
疑似太陽光がやわらかに降り注ぐ、昼下がりの箱舟生態保護区。カフェ・ホライゾンの裏手、ほとんど人の立ち入らない静かな木立のあいだに、瀟洒な丸テーブルと椅子が四脚持ち出され、小さな茶席がととのえられている。
「えー、ではと。まずはラビアタ、長期間の任務お疲れ様」
司令官がぱん、と両手を打ち合わせ、ラビアタへ笑顔を向けた。
「勿体ないお言葉です」ラビアタは深く頭を下げる。
「龍も、拠点再建とPECS艦隊の相手、大変な仕事を二つも丸投げしてしまってすまない」
「海は小官のホームグラウンドだ。大役を任された誇りとやり甲斐にくらべれば、苦労など何ほどもない」
龍は謹厳にぴしりとした答礼を見せた。
「そしてアルファ。内務を本当に上手く切り回してくれて、助かっている」
「アルマンさんをはじめ、オルカの優秀なスタッフあってのことです。私だけの力ではありません」
アルファは奥ゆかしくお辞儀をした。
ラビアタ・プロトタイプ、無敵の龍、レモネードアルファ。旧時代の三大企業それぞれが持てる技術の限りを尽くして作り上げた最高傑作というべきバイオロイドであり、オルカでも最高幹部の地位を占める三人だ。一番の新参であるアルファが加わってから一年あまりになるが、この三人だけが集められた会合というのは前例がない。
「皆にはそれぞれ重い仕事や責任を背負ってもらっているから、普段あまり気軽に話もできないと思う。今は少し余裕のある時期だし、一度ちゃんとお礼を言って、ねぎらわせてもらいたいと思ってこの席を設けた。今日は仕事のことはいったん忘れて、お互い打ち解けてくれると嬉しい」
言い終えた司令官はいそいそとティーポットカバーを取り、意外に手際よく紅茶を淹れて三人に配った。
「過分なお心遣い、ありがとうございます」
三人はもう一度深く礼をしてめいめいのカップを持ち上げ、司令官に向かって小さく掲げてから口元へはこんだ。
「旧時代に、この三人で会ったりしたことはあったのか? トップ会談みたいな感じでさ」
「いいえ」アルファが控えめに首を振った。「私たちは企業秘密の塊のようなもので、できるかぎり秘匿されていました。自由になる時間も連絡手段も持っていませんでしたから、とても」
「ブラックリバーとの身柄交換の時に、龍さんと一度だけ会ったことがあります」ラビアタが言い添えた。「でも、私もその一回きりです。アルファさん達レモネードシリーズとは一面識もありませんでした」
「でも、お互いに関心を持ってはいたんだろ」
「それは、まあ」
「言ってしまえば小官もレモネード殿も、ラビアタに対抗するために開発された面がある」龍が腕を組んで言った。「当然あらゆる情報を集めていたし、常に動向を注視していた。その意味では、大いに関心はあったが」
「ラビアタから見たらどうだったんだ? 二人は後輩みたいなものだろ」
「後輩というか、ライバルでしょうか」ラビアタは苦笑した。「もちろん、お二人には注目していました。アルファさんの言うとおり企業秘密でわかることは限られていましたが、なんとか少しでも情報を得ようと……そうそう、隠し撮り写真を買ったりしましたよ。私でなくて、三安の研究所がですが」
「まあ、本当ですか?」レモネードが手の甲を口元にあててコロコロと品良く笑った。
「今はどうだ? お互い会ってみて、どんな風に思う?」
「二人とも、素晴らしい能力の持ち主ですね」ラビアタは丁寧に言葉を選んで答える。「私が一人で仕切っていた頃より、抵抗軍がはるかによく機能しているのがわかります。ご主人様と、お二人のおかげです」
「ご謙遜を」レモネードがしずかに微笑んだ。「私から見れば、これだけの規模の組織をたった一人で立ち上げて、50年以上も戦線を維持してきたことの方が驚異的です」
「同感だ。小官が初めて本格的に肩を並べたのはグアム島の戦いの時だったが、貴殿の指揮能力には感服させられた」
「あまり持ち上げないで下さい」
「お茶のおかわり、いるか?」
「かたじけない。いただこう」
「今日のためにお茶の淹れ方を練習したんだ。ちゃんとできてるといいけど」
「お見事ですよ。コンスタンツァに教わったでしょう?」
「わかるの!?」
「あの子の癖が出ています」
「……」
「……」
「えーと……そうだな……」
ラビアタはティーカップをしずかに傾けて上等の紅茶を味わいながら、司令官に見えないようそっと嘆息した。どうやらご主人様もようやく気づきはじめたようだ。
このお茶会が、全然盛り上がっていないということに。
彼の意図するところはわかる。自分たちは三大企業それぞれのバイオロイドの頂点といっていい存在であり、したがって抵抗軍を構成する主要三グループの頂点でもある。自分たち三者の親疎は、グループ間の関係にも直接間接に影響をあたえるだろう。いま特に対立や摩擦があるわけではないが、この先PECSとの本格的な戦争に突入すれば、それに絡んで感情的なしこりが生まれないとも限らない。三人が一箇所に集まる機会は少ないのだから、先に手を打っておくのは悪いことではない。
(だからってね……)
いきなり集められて「さあ打ち解けろ」と言われても、そう簡単にできるわけはないのだ。
「不足しているものなどはないか? 南アジア方面に手の空いている艦が数隻ある。今のうちなら調達に回すこともできる」
「あら、有り難いです。あとでオレンジエードから、希望優先度つきリストを回させますね」
案の定、龍もアルファも「仕事を忘れた」話題は早々に尽き、業務がらみの話に逃げつつある。
かつて自分たちはライバルであり、商売敵であり、政敵であり、時には砲火を交える正真正銘の敵同士だった。そして同時に、それらはすべて自分たちの所有者の関係性にすぎず、おのれ自身は等しく企業という檻に厳重に囚われた奴隷同士なのでもあった。当時お互いのことをどのように思っていたか、説明することはラビアタ自身にも難しい。同じ立場の存在として関心はあったし、多少の同情めいた共感を覚えたこともないではない。しかし、あの頃自分たちが生きていた世界で、そんなささやかな共感にはなんの意味もなかった。もっとはるかに重く、冷たく、巨大なものが、自分たち全員を押し流していたのだ。
「このあいだ乗せてもらった、レアとティタニアの様子はどうですか。訓練、うまくいっています?」
「二人ともなまじの気象レーダーより役に立つ。常備したいくらいだが……肝心の気象操作の方は、まだ連携に難があるようだ。少しずつ改善しているみたいだがな」
少なくともラビアタは旧時代、この二人と腹を割って話したいなどと考えたことは一度もない。夢見たことさえない。もし仮にそんな機会が与えられたとしても、何を話せばいいのかわからず困るばかりだったろう。まさに今、そうなっているように。
「……お茶の葉を新しくもらってこようか。食べるものももう少し足すから、三人で話しててくれ」
ついに司令官がそんなことを言って、そそくさと席を立った。
足すも何も、ティースタンドの軽食はまるで減っていない。最初に取り分けられたタルトを遠慮がちに少しずつ口にするだけで、誰も新しいものを取っていないからだ。司令官が去ると、龍とアルファが目に見えて気を緩めた。
「お心遣いは本当にありがたいのだが、な……」
いちばん直截な物言いしかできない龍が、小さく苦笑いをして呟いた。レモネードはもちろん何も言わない。この中で一番本心を隠すことに長けているのが彼女だ。
ラビアタも何も言わなかったが、同意の印にほんの小さく肩をすくめた。ご主人様は確かに未熟だ。ことに人の心を読み、動かす技術については、まだまだ勉強してもらわねばならない点が多すぎる。
しかしそれでも、彼の真心は間違いなく本物なのだ。それを無碍にすることなどあってはならない。
ラビアタはティースタンドから小さなレモンクッキーを一つつまんで口に入れると、少しのあいだ無心にそれを咀嚼した。
「…………」
自分には少なくとも、アダム・ジョーンズ博士という心から尊敬できる父のような人がいた。この二人にそんな相手はいなかった。対等な誰かと本音で語り合うという経験自体を、二人はしたことがないはずだ。
だから要するに、ここは自分が踏み出すしかないということなのだ。ラビアタはすっかり冷めた紅茶を飲み干し、一つ咳払いをした。
「もう、だいぶ以前のことです。オルカがまだ、アジア近海で足場固めをしていた頃。私はセラピアス・アリスから秘密裏に相談を受けました」
突然あらたまった調子で話し始めたラビアタに、龍とレモネードが怪訝そうに目を向けた。ラビアタは構わず続ける。
「ご主人様を発見した功労者であるコンスタンツァ416に、バトルメイドの皆からサプライズの贈りものをしたいので協力してくれと言うのです。私は喜びました。アリスが妹たちのことをそんな風に気にかけることは、それまで滅多になかったからです。贈りものは夜着で、骨格の近い私に採寸モデルになってほしいとのことでした」
二人は怪訝そうな顔をしたまま、とりあえず黙って聞いている。
「ずいぶん過激なデザインでしたが、ご主人様のために着るのだろうと、特に不審にも思いませんでした。採寸と仮縫いに二回付き合い、三度目の調整の時、オードリーが何か忘れ物をして席を外し、私は仮縫いの夜着を来たまま待たされました。……そうしたら数分後、ご主人様が入ってきました」
「!」
「あとで知ったのですがその時ご主人様は、皆のたくらみでしばらく禁欲状態だった上に、強精料理ばかり食べさせられ、大変……欲求不満が溜まった状態でした。そしてその部屋には大きなベッドがあり……つまり私は、妹たちにまんまと嵌められたのです」
ごくり、と二人のどちらかが唾を飲んだのが聞こえた。両方かもしれない。
「ご主人様は限界に達したご様子で、私の肩をつかみました。『すまない。もう我慢ができない』というのが、その夜ご主人様が発した、最後の理性的な言葉でした。私が意識を取り戻したのは翌日の昼のことです。あとでご主人様に聞いたところでは、気絶している私は溶けかけたアイスクリームのような有様だったとか」
さすがに頬が熱い。ラビアタは大きく息をついて首筋の汗をぬぐうと、二人をまっすぐ見返して、あえてニヤリと微笑んでみせた。
「これが、私とご主人様との馴れ初めです。……貴女がたは?」
「「…………!!」」
二人の顔がさっと朱に染まる。ガタリ、と音を立てて、二人とも前のめりに椅子へ座り直した。
「……箱舟へ落ち着いて少ししてからのことでした」先に応戦したのはレモネードだった。「ご存じでしょうがレモネードシリーズにはそれぞれ呪いが課されており、私のそれは『色欲』です。その頃私の呪いは限界に達していたのですが、積もりに積もったそれを……旦那様は一晩で解ききって下さいました」
「時期的には、小官の方が先だな」龍も負けじと身を乗り出す。「アラスカを攻める数週間前のことだ。グアムでの戦闘指揮のご褒美をいただけることになっていたので、小官は主との一夜を所望した。緊張する小官のために、主は特別に、海の見える展望寝室を用意して下さった。まあ最後の方は、海など目に入らなかったのだが……」
「ご主人様って、ああ見えて力も強いんですよね」機を逃さずラビアタはたたみかけた。「私のこの体も軽々と持ち上げて、自由自在に動かして下さるんです。お二人もご存じかもしれませんけど」
「もちろんだ」龍が勢い込んで頷く。「小官は知らなかった。あんな、あんな風に抱き上げられて、あんな角度から……」
「たくましい殿方って、いいですよねえ」アルファもうっとりとため息をついて、「旧時代にはもう毎日毎日年寄りの顔しか見ていなかったものだから、本当たまらなくて……」
「ご主人様ったらどこで手に入れたのだか、日本の秘伝書だっていう四十八種類のラーゲが書かれた本を持っていらして、四十まで試したんですけど……」
「私の全身で、旦那様の子種に洗われていない所はどこにもありません。強いて言えば耳の中と肺の中くらいでしょうか」
「以前など、わざわざセイレーンから制服を借りてきて下さってな。小官はそれを着て……」
競うように言いつのる三人の言葉が、あるところでピタリと止まる。そしてほんの一瞬にらみ合ったあと、三人はいっせいに弾けるように笑い出した。
笑いながらラビアタは理解していた。確かに旧時代、この二人と腹蔵なく話したいなどと夢にも思ったことはなかった。だが叶ってみれば、なるほどもっと早くこうすべきだった。もっと早くに、これを夢見ればよかったのだ。世界に三人しかいない、同じ立場を分かち合える仲間なのだから。
この二人だけに話せる思い出。この二人だけに打ち明けられる悩み。この二人だけに通じる冗談。そんなものがあることすら知らなかったが、それは心のずっと深いところから、泉のようにとめどなく湧き上がってきた。不思議な驚きとともに、ラビアタは幸福に、それを受け止めた。
* * *
「……だからほら、第二次スエズ危機を覚えてる? 三安はあの時、ウラジミールとカラカスは静観すると踏んでいたのだけど……」
「なんてこと! あの時それを知っていれば、油田地帯の半分は私たちのものになったのに」
「待て待て、あの年なら我々も秘密裏にキプロスへ艦隊を仕込んでいたんだぞ。まさかそこまで見抜いていたとは言うまいな?」
せっかく準備したお茶会が今一つ盛り上がっていない気がする。どうしたらもっと皆の会話がはずんでくれるか、あれこれ考えていたらずいぶん時間がたってしまった。次に振るべき話題をあれでもないこれでもないとひねりながらワゴンを押して戻ってみたら、三人はそれまでと打って変わった様子で何ごとか熱心に論じあっていた。
「なんだ、すっかり盛り上がってるな。何の話だい?」
「やあ主。昔の感想戦といったところだ」龍がかるく手を上げて迎えてくれる。「サンドイッチか、ありがたい。早速いただいていいだろうか」
「もちろん、どうぞどうぞ」
見ればティースタンドはすっかり空だ。俺が席を立った時にはほとんど手が付いていなかったはずだが。龍はワゴンの上から直接サンドイッチをひょいひょい取って、ラビアタとアルファにも回した。
「そうだアルファ殿、さっきの話の引き替えというわけではないが、エルブンシリーズを何人か艦隊に配備するわけにいかないか。最近、例のミルクの愛好者が艦隊にも増えてきていてな」
「あら、気前がいいと思ったらそういう話だったんですか? 私どもは龍さんのところほど上下関係が厳しくないんです。私が命令しても聞いてくれるわけではないですよ」
「むろん正式に嘆願書は出す。その時に口添えしてくれればいいんだ」
「エルブン達は緑のないところにはいたがらないわよ。レア達が乗った艦に、小さな温室を作ったと言っていたでしょう。そこならいいんじゃない?」
みんなくつろいだ楽しげな笑顔で、さっきまでとまるで雰囲気が違う。もしかして、俺がいない方がみんなリラックスできたのだろうか。それはそれで少し寂しいな……。
そんな風に思っているのを見透かしたように、ラビアタがにっこり笑って立ち上がった。
「ご主人様、次は私に淹れさせて下さい。たまには腕を振るいませんと、なまってしまいますので」
「あ、ああ。みんな、仲良くなってくれたみたいで嬉しいよ」
「それはもう」魔法のようになめらかな手つきで茶葉とポットを扱いながら、ラビアタは朗らかに言う。「来週も、この場所をお借りしてよろしいですか? 三人で話したいことがまだまだあるんです」
「ああ、もちろん……ん? 三人?」
ラビアタは笑いながらうなずいた。「ええ、私たち三人だけで。殿方はご禁制です」
俺は龍とアルファの方を見た。二人ともにこやかに同意する。
それは確かに、この会の目的は三人に打ち解けてもらうことだった。それは十二分に達成されたようだが、俺は聞かずにいられなかった。
「俺がいない間に、何があったんだ?」
三人は顔を見合わせ、そろって俺の方をちらりと見てから、一斉にくすくす笑い出した。何を聞いても答えてくれないので、俺は仕方なくラビアタの差し出してくれた紅茶をだまって飲んだ。
悔しいことに、それは俺が淹れたものより、ずっとずっと美味いのだった。
End
逸る心、走り出しそうになる足をぐっと抑えて、雑踏をすり抜けてゆく。約束の時間は過ぎていた。可愛い可愛いとはしゃぐ二人のおかげで着付けが予定よりずっと長引いた挙句、きわめて険しい表情の姉君に「絶対に走らないこと」と厳命されたせいだ。普段から勝手を咎められてはいるが、特に今日の物言いは尋常ではなかった。こんなに動きづらくては走りたくても走れないじゃないか、と口を尖らせたものの、彼女は聞く耳を持ってはくれなかった。
そんなことを思い出して、X-05エミリーはかすかに笑みをこぼした。わかっているとも。ぜんぶぜんぶ私のための言葉だ。
デートの相手は手持ち無沙汰げに、長椅子に腰かけていた。どうしてだろう。ついさっきまでは舞い踊るような心持ちだったのに、いざその姿を見ると不思議なほどに胸が重くて、いっそのこと部屋へ戻ってしまいたい気すらしてくる。あまりに矛盾した気持ちの変化に、頭での理解が追いつかない。
彼女はすぐに、それを完全な気の迷いだと打ち消した。帯で体が締め付けられているせいだろう。だから感情もそれに引っ張られて、苦しい気持ちになってしまうのだ。彼をこれ以上待たせるわけにはいかない。一度長く息を吐いて、司令官へ声をかけた。
「お待たせ、司令官」
「ああエミリー、よかった入れ違ったんじゃないかと──」
立ち上がった司令官はにわかに言い淀んだ。頭をかいては下駄の先で土を弄り、エミリーをちらりと瞳に映しては再び目を外す。ここまで露骨に狼狽した様子の彼は、エミリーの記憶の片隅にさえいなかった。
「どうしたの……?」
「いや、なんでもない! なんでもないけど、その、浴衣」
浴衣と言われて、エミリーの心はどきんと跳ねた。司令官は今やエミリーの全身を確と見つめ、ひたすら言うべき言葉を探しているようだった。
「浴衣がだな、いや、うまく言えないんだけどさ」
紺の布地に百合の花々を染め抜いた浴衣とそれをまとめる薄紫の帯は、彼女の纏うミステリアスで無垢な雰囲気にぴったりと重なりあっている。加えて普段着のクールなイメージや学生服の少女然としたそれとは違う、どこか大人びた、淑やかな気品を生んでおり、服装の妙を感じさせるというものだ。しかし彼女自身の持つ可愛らしさはわずかにも損なわれておらず、後ろで端正にまとめた髪を留めている小さな蝶は、彼女の髪と露になったうなじの美しさを引き立てていた。
要するに、だ。
「浴衣、似合ってるよ。すごく綺麗だ。浴衣も、君も」
司令官は結局、飾り立てることなく素直な気持ちを言葉にすることを選んだ。
その一言で、固く結ばれていた何かがふっとほどけて、また体の中で跳ねて回って、不意に静まって、ゆっくりと溶け出していく。
「なんだ、そんなほっとした顔して。みんな似合うって言ってくれただろ?」
「……うん。ネオディムもカエンも、ジェノクスも、お姉ちゃんたちも可愛いって言ってくれたよ」
オルカでは特殊な事情で「夜」の相手ができない隊員のために、司令官との特別なデートの機会が設けられる。今回の司令官とエミリーの逢瀬に際して、旧時代の主に日本で着用されていた衣服である、浴衣を着てみないか、と提案したのはクノイチ・エンライであった。説明を受けた二人がそれを承諾した途端、あれよあれよという間に話が進み、気がつけば二人分の浴衣がオードリー・ドリームウィーバーによって仕立てられていた。だが、今日この瞬間まで、お互いは相手の衣装を見ることを──特に司令官がエミリーの浴衣姿を見ることを、禁じられていたのだった。
エミリーの言葉に対し、司令官は落ち着きを取り戻すかのように鷹揚に頷いた。
「そうだろうな。そのはずだ。もし今のエミリーを変だなんて言うやつがいたら、そいつはダフネか、いや、ドクターのところへ──」
「でも、司令官に言ってもらうのが一番嬉しい。ありがとう」
「えっ……! そ、そうか、そいつは、よかった。うん。それなら、よかったよ」
エミリーのそんな言葉に司令官は面食らって、まるで子供のようにどぎまぎしてしまった。こんな言い回しをいったいどこの誰から教わったのだろう。彼女の上官の顔が真っ先に浮かんだが、さあ果たして。彼女はもっと直接的なアプローチを好むような気もする。ただ今考えるべきはそんなことではなく、眼前にいる少女のことだというのは明確だった。
「本当に、すごくよく似合ってる。特にその蝶の髪留め、自分で選んだのか?」
そう言って、エミリーの髪で羽を休めている蝶を指し示すと、彼女は、
「どうしてわかったの?」
と言って笑った。蝶の羽は赤色の先から段々と透き通ってゆく色合いをしていて、最も濃い部分はエミリーのまなざしと同じ色であった。
「わかるさ、君のことだからな」
司令官がそう言ってエミリーの瞳を見て微笑むと、彼女のなかでずっと渦巻いていた何かがついに抑えきれなくなり、やがて強い奔流となってあふれ出した。
「オードリーに、ちょうちょの形がいいって言ったら、いくつも作ってくれて……ぜんぶ宝石みたいだったけど、これが一番好きって言ったら、エクセレントって言ってくれたから、これにしたの。……かわいい、よね? そうだ……爪も、おしゃれにしてもらったの。ちょっとくすぐったかったけど、きれい、だよね……。それから……」
驚くほどたくさんの言葉が、口からとめどなく流れ出てゆく。思えば、不安だったのかもしれない。着付けの時、いや、それよりずっと前から、この瞬間のことばかりを考えていたのだ。ただひたすら、彼のことを思い続けて今日を待っていたのだ。
司令官は興奮気味のエミリーの言葉ひとつひとつに丁寧に頷きながら、さりげなく彼女の手を取り、おもむろに歩き出した。エミリーもそれに連れられて、司令官と言葉を交わし合いつつ浴衣の裾を揺らす。満月にほど近い月が、二人の男女を照らしていた。白夜の時節はもはや終わりかけている。
かつてはムネモシュネと彼女が管理する動物たちだけがひっそりと暮らしていた箱舟は、今やオルカ抵抗軍の隊員たちがもたらす喧騒に包まれていた。
「たこ焼きー! たこ焼きいかがっすか! 外はサクサクで中はふわふわ、タコもぷりっぷりでちょー美味いっすよ!」
「冷たいエルブンミルク、プレーンにココア、バナナ味各種搾りたてご用意しておりまーす!」
「型抜き、一勝負やってかない? あそこのあいつみたいに不器用で負けず嫌いな奴は大歓迎よ~!」
「だあああまた欠けた! おいサラマンダー! これ難しすぎんだろ!」
「お前が下手くそなだけだよハイエナ! はいはい、次の方……って、あ、アザズさん……! いやあ、その……お手柔らかに……」
隊員たちが自らの意志で簡易的な店舗を並べているその様は、黄昏どきの薄暗さも相まって、市場というよりもさらに古い時代のお祭りを思わせる賑わいであった。ほとんどの隊員はそんなごく古い文化の、縁日と呼ばれる概念など知る由もなかったが、自然と似通ってしまうのは歓楽を求める感情ゆえであろうか。
「箱舟もすごく賑やかになったな。こんな風になるなんて、ここに来たばかりの頃は思ってもいなかったよ。はぐれるといけないから、手、離さないでくれよ」
司令官は嬉しそうにそう言った。彼の幸せが手のひらから伝わって、エミリーの内側に触れてそっと包み込む。いろんな場所から良い香りと楽しげな声が聞こえてきて、否応なしにエミリーの感情もうきうきしたものに変わっていった。
「どうしようか、エミリーは何か食べたいものとか──」
「あーっ! 司令官なの! こっちこっち、なの!」
二人が目移りしていると、よく通る声で二人を呼ぶ者がいた。
「あれ、エンプレス? イグニスに、ダッチまで! 三人も店を出してたのか?」
「はい、ダッチさんが自分も何かしたいとおっしゃったので、エンプレスさんにも協力していただいて、こうして海の物を焼いて出すお店をさせてもらっています」
イグニスの言う通り、火を入れた鉄板の上には大きなホタテやエビが並べられ、焼けた醤油の香ばしい匂いと煙をこれでもかとまき散らしている。イグニスたちは熱気の中の作業で全身にびっしょりと汗をかいていたが、とても楽しそうにしていた。
「よかったらこれ、持っていって。……上手にできたと思うから」
二人が同時に喉を鳴らしたちょうどその時、焼きホタテやエビ、イカの入った容器を袋に入れて、ダッチガールが差し出した。
「いいのか? 売り物だろ?」
「いいんですよ、元々ツナ缶を稼ぐために始めたことじゃありませんので。皆さんに楽しんでいただければ、それで十分ですから」
「採れたての美味しさを味わうといいの!」
イグニスもエンプレスも、そう言ってにっこりと笑った。
「そっか。悪いな、ありがとう!」
司令官はそう言って受け取ったが、しかし、その様子を遠巻きに見ていた隊員の何人かから、甲高い、不満げな声が上がった。
「えーっ! ずるい! 私たちのも司令官様に食べてもらいたいです!」
「えっ」
「アタシも! 抜け駆けなんてフェアじゃないわ!」
その声は瞬く間に広がり、それをきっかけに司令官とエミリーは、自分たちの店の商品を持った隊員たちに取り囲まれてしまった。そして、
「司令官様! 司令官様! チョコバナナ、あげるね! こっちはエミリーお姉ちゃんのぶん!」
二人の両手は、
「マジックジェントルマン! そして咆哮の魔獣を御する者よ! 我輩謹製の焼きそばを食すがいい!」
あっという間に、
「ミートパイをどうぞ!」
塞がってしまった。
もう持てないと司令官が悲鳴を上げるまで、二人はトッポギやフランクフルト、ハンバーガーにキンパなど、大量の食べ物を次々に渡されて、
「手、繋げなくなっちゃったな」彼はそう言って笑った。
「人気者だね、司令官は」
エミリーはそうやってわざとむくれてみせたが、彼は笑顔のままで、結局彼女もはにかむように笑ってしまった。
「どこか座れる場所で食べようか。確かあっちのブロックにテーブルが並べてあったはずだから、そこはどうだ?」
「うん……そうしよう。司令官と一緒にご飯食べるの、久しぶりかも」
幸いにして、空いている椅子とテーブルはすぐに見つかった。案外みんな、出店の営業だったり食べ歩きだったりに人が集中しているのかもしれない。抱えていた食べ物をどさっと下ろし、適当にテーブル全体に広げる。あまりに量が多くて、テーブルをもうひとつ拝借してきたくらいだ。食べきれるかどうかも怪しいが、今そんなのは気にすることではない。何はともあれ、冷めてしまう前に一刻も早く食べるべきだ。
二人が最初に選んだのは、ダッチガールたちにもらった海鮮焼きだった。
「うまい! 物がいいからってだけじゃないな、これはたぶん、新鮮じゃないと味わえない味だ」
ホタテは握りこぶしほどもある大きさなのに身がぎゅっと引き締まっていて、噛み締めると海鮮の旨味が一気に流れ込んでくる。醤油だれはかなり濃厚で、言ってしまえば大雑把で大仰な味付けではあるのだが、高揚した今の感情には特段にマッチしていた。
「うん、美味しい……こういうのを、ぷりぷりしてる、って言うんだよね」
焼きイカを頬張ると、やわらかい歯ごたえに続いて磯の香りが口の中いっぱいに広がる。味付けはホタテと変わらないはずなのに、まるで違う味わいになるのも不思議だ。トッポギもフランクフルトも焼きそばも、食べたことのあるものからないものまで、何もかもが普段の何倍も美味しく感じられた。
「いやあ……これは、酒が飲みたくなる……」
そんなことを、司令官が小声でこぼしたちょうどその時、
「ほう? 今そなたは酒を飲みたいと言ったな?」
「あ、隊長」
バニー姿のロイヤル・アーセナルが、大きなクーラーボックスを担いで現れた。
「アーセナル……何やってるんだ? いや、見ればわかるけど」
「もちろん営業だ、CAFE-amorのな。例え立派な店舗を構えていたとしても、戦術家のはしくれとしてこの機に乗らんわけにはいくまい。弾薬庫をクーラーボックスに持ち替え、出張開店中というわけだ」
アーセナルはそう言って、肩に担いだプラカードを掲げてみせた。なるほどそこには各種ドリンクの名前と値段だけが大きく書かれており、特にアルコールの売れ行きは好調らしく、すれ違うバイオロイドに顔を赤くしている者が多く見られたのはそういう理由のようだった。
「それでどうだ、司令官も一杯やるというのは。今ならビールにウイスキーに、なんでもお安くなっていますよ、お客様?」
わざとらしい敬語に加えてウインクを決めたアーセナルの言葉に対し、司令官は相当の時間を逡巡に費やしたが、最終的には首を横に振った。
「やめておくよ。今はエミリーがいるからさ」
「ふふ、そうか。まあ、そなたならそう言うと思っていた。これは私からの餞別だ。せっかくの機会だからな、司令官もエミリーも、存分に楽しむといい」
アーセナルはクーラーボックスからオレンジジュースの瓶を二本取り出し、テーブルに置いてそう言った。その間エミリーは料理に舌鼓を打ちながら二人のやり取りをぼんやりと聞いていただけだったが、ふと何かを思いついたように口を開いた。
「司令官、隊長。……どうして大人はお酒を飲むの?」
「ふむ、酒を飲む理由か、それは互いが正直に──」
「まあ第一には美味しいからだな! ああ、間違いない!」
エミリーの質問に躊躇いなく答えようとしたアーセナルの言葉を、司令官はことさらに大きな声で遮った。危ないところであった。例え要所は多少濁すつもりだったとしても、事実に近い情報をエミリーに伝えるのは教育上問題があるのではないか。そもそも迂遠な言い方をしたところで、さらに詰められたらどうするつもりだったというのか。
アーセナルがいささか白けたように司令官を見たが、彼はそれを黙殺した。
「……もちろん、それもある。美味なだけではない。適度な飲酒は人生を豊かにするものだ。快楽を盛り上げるためにも、悲哀をやわらげるためにも用いられる。無論、過ぎれば毒にもなるがな」
「ふうん……そうなんだね。私が飲んだ時は、あんまり……」
「エミリー、待て──」
今度はアーセナルがエミリーの言葉を遮ろうとしたが、あと一歩、遅きに失したようだった。
「何? おいアーセナル、どういうことだ」
エミリーの言葉を聞いた司令官は、しまったという顔つきで額を押さえているアーセナルをぎろりと睨みつけた。
「お前、エミリーに飲ませたのか!」
「私はそろそろ失礼する! 商品の補充に行かなければ!」
アーセナルはそう言い残して脱兎のごとく逃げ出した。実際のところ、司令官はただ一言「待て」と命令を下すだけでよかったのだが、この時の彼はそのことを完全に失念しており、ピンヒールで颯爽と駆けてゆくバニーの背中を呆然と見つめるほかなかった。
「くそ、あいつめ……今度会ったらしっかり話をしておかないとな……」
そうぼやきながら司令官が振り返ると、そこには悄然としてうつむいているエミリーがいて、やがてようやくか細い声を上げた。
「ごめんなさい、司令官……その、ダメ、だった……?」
エミリーは涙をこぼしてはいなかったが、自分の軽い行いで司令官を怒らせてしまったことや、自らの発した言葉で自分の上司が叱られるきっかけを作ってしまったことに、ひどくショックを受けていた。
だがしかし、司令官の目に映るしょんぼりとした彼女は、まるで悪戯を見咎められたペットの子猫のようで、渦巻いていた嘆きも憤りも、どこかへ飛んでいってしまった。彼は屈んでエミリーに目線を合わせると優しく微笑み、彼女の綺麗に整えられた髪をゆっくりと撫でた。
「エミリーは悪くないさ。元を正せば、俺の監督不行き届きだ。大声出してごめんな」
実際、彼女の飲酒は保護者であるアーセナルによって認められた行為であり(彼女の保護者としての適性はこの際置いておくものとして)、そもそも人間の身体的基準をバイオロイドに適用することが正しいのかさえも疑わしい。単に彼個人の価値観が、アーセナルのそれと衝突しただけである。何をかといえば、その衝突をエミリーの目の前でしたことのみが失敗なのだ。
それでもエミリーはしゅんとしたままで、首をふるふると横に振った。彼が謝るようなことなんて、何もないのではないか。
司令官は彼女のその様子を見て、自分が謝ることには何の意味もないことを悟った。
「そうだな……お酒、飲んでみてどうだった?」
「美味しくなかった……。後は、覚えて、ない……」
「そっか。じゃあ、お酒はまだエミリーには早かったってことだ。もう少し大人になるまで待つって、約束してくれるか?」
司令官のその言葉に、エミリーはゆっくりと頷いた。
「よし。それじゃあこの話はこれでおしまい! 俺はもう怒ってないし、アーセナルに何か言ったりもしない。約束する。だからほら、笑って美味しいものをたくさん食べよう!」
司令官は両手の人差し指をエミリーの口角に添え、きゅっと持ち上げると共に自らも歯を見せて笑った。エミリーは少しびっくりして司令官の顔を見つめたが、一瞬の間をおいて彼女の表情はへにゃりとほころんだ。
「司令官……」
「元気、出たか?」
「歯に青のり、ついてるよ……」
「はっ⁉」
司令官は慌てて飛びのくと、どこかで誰かに渡されたウェットティッシュで歯を勢いよく拭き始めた。別に汚いだとか、みっともないとか、そんなことは露ほども思わなかったが、彼の恥ずかしがり方がなんだかとても奇妙に思えて、それがどうにもおかしくて、
「ふふっ……」
さっきまで悲しい気持ちだったはずなのに、ついに笑みがこぼれてしまった。
「あっ、笑ったな! なまいきなやつめ、そんなエミリーはこうしてやる!」
司令官は恥ずかしさをごまかすようにそう言って、エミリーの両頬を指でつまむと横に引っ張ったり上下に揺らしたりを繰り返した。まるで意味のない子供同士の遊びのようなやり取りだというのに、それが無性に心地良い。
「ふへ……ごめんへ……」
「いまさら謝ったってもう遅いぞ。このままエミリーのほっぺたを伸ばして丸めて美味しく食べてやるからな!」
無邪気に笑いあっていた二人だったが、その時、不意に鋭い笛の音が空高く鳴り響いた。その音に鋭い反応を見せた者が幾人もいたが、司令官にはそれが戦闘員と非戦闘員の差として垣間見えたことが面白かった。
「うそ、敵襲⁉」
「違う! あれは──」
誰かが、おそらく箱舟にいるほとんどの隊員が口々に叫んだその刹那、炎の華、大輪の輝きが頭上を覆い尽くした。当然、それは一発で終わりではない。いくつもの閃光が次々と天へ放たれては、北極海の澄み切った夜空を彩る。記憶の箱舟に保存されたデータには、破壊ではなく美しさを追い求めた火薬の配合法も存在したのだ。
「──花火! 花火っすよ!」
「すごい! 前見たのより、綺麗になってる……」
「爆発だーっ!」
「しまったな、もうそんな時間だったか」
司令官のそのつぶやきは、しかしわき上がる歓声と花火の音にかき消され、誰の耳にも届くことはなかった。周囲からは次々に歓喜と驚嘆の声が上がり、赤、青、黄、緑と花開くたびにどよめきが起こる。派手な打ち上げの直後につかの間の空白が訪れ、まさかもう打ち止めか? と思わせた次の瞬間に無数の花火が再び空を埋め尽くす。ひときわ激しく美麗な開花には拍手や口笛が飛び交い、隊員たちの熱気は最高潮に達そうとしていた。
が、
「──まったくあのバカ司令官は! 本当に花火を打ち上げてくれだなんて、どーしてこの私がこんなことしなくちゃいけないのよ!」
しかしその一方で、花火を見る者がいれば打ち上げる者も当然存在するのであって。
「別に東南アジアの休暇でも似たようなことをしていたじゃないですか。今回もあれと大して変わりはないでしょう。あ、これ美味しいですね……」
「あれは全部私のためにやったことなの! アホ司令官は関係ないんだから! ほらそこ! 次弾装填急いで!」
「しかし、今回はちゃんと感謝を示すって約束してくださったのですよね?」
その言葉に玉座の主は押し黙ってしまったが、しばらくして、彼女は顔を赤らめたまま小さな声で頷いた。
「うん……」
「急に大人しくならないでもらえませんか? ほら、次の花火が来ていますよ」
「なんなのよ一体! ていうかなんであんたまでここにいるのよ!」
「当然私も司令官に愛していただきたいからです。私は誰かさんのせいで逃しに逃した機会を取り戻さなければいけませんので」
「な、なんですって⁉ あんたさっきから何もしてないじゃない! 冗談じゃないわ、司令官と約束したのは私なのよ!」
花火ミサイルの装填手を担当していた兵士たちの一人から、某部隊の少将と大佐の間でこんなやり取りがあったとかなかったとか、という噂が箱舟に流布されるのはまた別の話である。
ほんの少し謎の空白が生まれた時間はあったが、花火は絶えることなく空へと打ち出され、様々な色の輝きで箱舟の人々を魅了し続けている。二人はテーブルを挟んで向かい合っていた椅子を隣に寄せ合い、ロイヤル・アーセナルに渡されたオレンジジュースを少し、また少しと飲みながら、光の祭典を楽しんでいた。
「……花火、綺麗だね」
「花火、綺麗だな」
偶然にも、司令官とエミリーの声が重なり、二人はくすりと微笑み合った。二人がまったく同じ気持ちで、同じタイミングで同じ言葉を発したという事実が面白くもあり、たまらなく嬉しくもある。面白い時は笑う。嬉しい時も笑う。その中間の時はどんな笑顔をすればいい? 隣に座る司令官の横顔を見上げると、彼も楽しそうに笑っていた。
「エミリー、どうした?」
視線に気がついた司令官が、エミリーの方へと顔を向けた。彼とこうして目が合って、エミリーの心はまたくらりと揺れ動く。彼と共にいると、胸のあたりが不思議な動きをするのだ。ふわりと浮かんで、くるりと回って踊って跳ねて、突然落ちては地面すれすれで再び一気に浮かび上がる。自分でさえも制御の利かないそのはたらきが、なぜだかたまらなく愛おしい。
きっと、彼にしか解けない魔法にかかっているのだ。
そう思った瞬間、エミリーの体はもう動き出していた。
「司令官」
「うん、っ──⁉」
重ねた唇は、やたらと甘いオレンジの味がした。
「え、エミリー! いきなり何を……!」
エミリーの頬は耳まで真っ赤に染まり、自分のしたことが信じられないといった面持ちで口元を押さえていた。全身が沸騰したように熱い。心臓はわけのわからない速さで鼓動を繰り返し、その音だけが頭の中でずっと反響している。
「……わかんない。わかんないけど、司令官の顔を見てたら……なんだか、したくなって……つい、しちゃった」
色とりどりの花火の光に照らされながら、エミリーは恥ずかしそうに、けれども心から幸せそうな笑顔を見せる。
今日いちばんの輝きが、瞳に強く焼きついた。
End
インジケータがまた一つ赤くなった。ココ・マーキュリーは機械的に手をのばしてアラーム音を切った。ことここに至ってはアラームなど、うるさいだけで何の意味もない。
暑い。狭いコクピットの中はまるでサウナだ。汗がとめどなく噴き出し、そして斜め下への強烈なGで流れ落ちていく。
外部カメラはすべてシャットダウンされ、下がり続ける高度計の数字と、上がり続ける温度計の数字、そして骨にひびく振動だけが外の様子を教えてくれる。
現在、地中海上空5万5千メートル。
唇まで垂れてきた汗をプッと吹き飛ばし、ぎゅっと一度目をつぶってから、ココはふたたびバリアの焦点と出力の微調整に集中した。
――1時間前――
〈あっ痛う……〉
「大丈夫!? ユサールお姉ちゃん!」
火花と煙を噴き出す、いびつに歪んだ鉄虫の群れ。もう動くこともなく、慣性のまま回転してゆっくり遠ざかっていこうとするそれらをワイヤーでひとまとめにくくってから、ココはホワイトシェルの補助スラスターを噴かしてユサールの方へ移動した。
〈ケガは大したことないけどな。これ……〉
銀白色のボディスーツの脇腹に空いた穴はすでに気密テープでふさがれている。しかし、まわりに漂っている無数の凍った血のかけらが、テープの下の傷が決して浅くないことを告げていた。そしてなお悪いことに、背中の大きなケースにも弾丸が食い込んで亀裂が入っている。ユサールモデルの専用装備、簡易大気圏突入ユニットだ。
〈データ吸い出し終わったぜ。ざっと見ただけだと、変なログはないみたいだ〉
スパトイアの声にココは顔を上げた。間近で見る偵察衛星BLSAR-27は、ここまでの戦闘でパネルやアンテナのほとんどがちぎれ飛び、ぼろぼろの小型トラックが逆さまに浮いているように見える。そのトラックの運転席のあたりを蹴って、大きなタキオンランスを手にスパトイアがこちらへ接近してくる。
〈エイダーにも送った。あと、衛星はもう完全にダメ。復旧は無理そうだ……っと〉
ユサールの背中を見て、スパトイアもヘルメットごしに顔をしかめた。その意味するところをすぐに理解したのだ。
大気圏再突入の際にはホワイトシェルがスパトイアとスティンガーを引き受け、ユサールだけは自前のユニットで単独帰還する計画になっていた。だが、これでは単機突入は不可能だ。
〈置いてってもらってもええよ〉
〈バカ言うな〉スパトイアが即答し、ココもうなずいた。
〈データの解析が終わりました〉小さな電子音とともに、ホワイトシェルのキャノピーの隅に小さなエイダーの顔が現れた。〈半径800km以内に鉄虫の反応なし。最も近傍の衛星は三安の「アナシスXIV」ですが、物理的・電子的に接触があった痕跡はありません〉
「つまり?」
〈今回のことは偶発的な事象であり、鉄虫に感染した衛星はその一基だけと考えていいと結論します〉
〈決まりだな。こいつぶっ壊して、後片付けして帰ろうぜ〉言いながらスパトイアは、さきほどココが縛り上げた鉄虫の残骸をロボットアームで蹴り飛ばした。眼下……ココの主観的には左手方向にかがやく地球へと、ゆっくりと落下をたどり始めた残骸をしばし目で追ってから、ココはひとつ深呼吸をした。
「スティンガー、スパトイアさん、衛星を破壊して大気圏へ落として下さい。それから、帰還フェーズの手順を変更。ホワイトシェルで全機を抱えて再突入します。エイダーさん、軌道計算のやり直しお願いできますか」
〈了解〉
軌道上のエイダー本体から直接送られてくる音声は、こころなしか地上で聞くよりクリアに聞こえた。
――――
「アブレータ三層め、パージ」
ドシン、と小さな衝撃がコクピットに走る。
断熱圧縮により超高温となりプラズマ化した大気は、強い磁場をかければ操作できる。これを利用して断熱と減速を同時に行うのが電磁エアロブレーキングであり、ホワイトシェルの電磁バリアの出力ならば理論上単独での大気圏突入が可能だ。ただし、あくまで理論でしかなく、実際に試したのはおそらくココ・マーキュリー402が初めてだろう。
機体には戦闘のダメージが残っているし、予定外の重量を抱えてもいる。念のため積んできた断熱材もたったいま使いきった。「理論は完璧に。しかし何事も理論通りにはいかない」宇宙でのミッションで最初に心得るべき鉄則の一つだ。
ホワイトシェルは現在、体をまるめて背中から落ちる姿勢で大気圏に突入している。暑さとGは耐えがたいほどだが、コクピットにいる自分はこれでもましな方で、ホワイトシェルの腹の上に伏せているだけのスパトイアとユサールはもっと苛酷だ。スティンガーが冷却ジェルを絶え間なく吹きつけているが、それでも危険なレベルの高温のはずだ。
〈ユサール、もっと真ん中寄れよ〉接触回線ごしに、ノイズ混じりのスパトイアの声が聞こえる。
〈いやだって悪いやろ、元はといえばうちのせいで……〉
「ユサールお姉ちゃん、誰のせいとかじゃないです」ココは声を張り上げた。「スパトイアさんのロボットスーツの方が耐熱性能が高いんです。それにユサールお姉ちゃんのスーツは破損してるでしょ。一番熱の少ないところにいなきゃ駄目です」
〈同意します〉冷却ジェルを噴きつつ、ホワイトシェルと連結して重心移動と姿勢制御を担当していたスティンガーも言った。〈本ミッションでは全員の生還が高い優先度で義務づけられています〉
〈……ごめんなあ〉ユサールが移動してくれたらしい。重量バランスが微妙に変化したのを、スティンガーのスラスター制御で補正する。
〈一番キツいとこはあと何分かだ。踏ん張ろうぜ!〉
大気摩擦によるものとは違う、こもったような微かな振動がコクピットに響いてきた。たぶん、スパトイアがユサールの背中をバシバシ叩いているのだろう。
〈怪我人、叩くなや〉弱々しいユサールの声は、それでも笑っているのがわかった。
――4時間前――
空が黒い。
地上の空は眼下にほの青い光を満たし、ココ達を押し上げるように下から照らしている。そして上を見れば天は黒く、星をちりばめた吸い込まれそうな闇がどこまでも広がっていた。
〈宇宙、来れたなあ〉
〈ホントやなあ〉
スパトイアとユサールが、ぽつりと小さくつぶやくのを、ココは接触回線ごしに聞いていた。
地上190km。厳密にはここは電離層の中ほど、大気圏の上層部であって宇宙空間ではない。だがこの浮遊感、この無音、この希薄な空気。何よりこのあたりはすでに、低軌道衛星の限界高度をこえている。この高度での作戦は、立派な宇宙ミッションと言える。
言葉にはしなかったが、ココも二人に同感だった。いやむしろ、感激のあまりに言葉が出なかったのだ。
ついに来た。ここで働くために自分は生まれた。その入り口に、ようやく、とうとう、立てたのだ。
〈目標補足。座標を共有します〉
スティンガーの無機質な声に、三人は我に返った。キャノピーに映る光景に、小さな矢印がインサートされている。映像ではまだ豆粒のように小さな光点でしかないが、あれが目的地、ブラックリバーの軍事偵察衛星BLSAR-27だ。
「接近します。しっかりつかまって下さい」
増設プロペラントタンクに残されたわずかな燃料を使い切って加速をかけてから、タンクを捨てる。モジュールにしまわれたまま一度も使ったことのなかった微小重力空間での移動感覚が、ちゃんと指先まで行き渡っているのを新鮮な満足感とともに確認する。豆粒ほどだった光点が、ぐんぐん大きくなってきた。
〈なあなあ〉ホワイトシェルの左肩につかまっているユサールがふいに言った。
〈ココって、スチールラインの隊長さんと仲ええん? 打ち上げ前、ずいぶん色々話しとったやんな〉
〈あれ、言ってなかったっけ〉ココが答えるより前に、右肩からスパトイアが口を挟んだ。〈ココは昔、マリー隊長直属の部下だったんだぜ〉
〈そうなん!?〉
〈第1部隊第1スクワッド、隊長に常に随伴する精鋭部隊だ。なーココ〉
「やめてください、スパトイアさん」ココは照れ笑いをする。「司令官がいらっしゃる前、レジスタンスが今よりずっと小さかった頃の話です。それに精鋭っていうか、マリー隊長の護衛が役目でしたから」
マリー隊長、不屈のマリー4号機は自らの身を砲火にさらすことを厭わない人だ。高潔な人格ではあるが、将校としては……とりわけ指揮をとれる者が数えるほどしかいない零細軍隊においては、致命的な問題点でもあった。放っておくと一人でずんずん死地に飛び込んでいってしまう彼女の身を守るために、常に付き従う専属の護衛部隊が編成された。ココもその一人だったのだ。
〈へー! すごいわあ〉
司令官が来てからレジスタンスはみるみる大きくなり、それにつれて組織も再編成された。今のマリーにはスチールライン生え抜きの立派な親衛隊がついており、かつての第1スクワッドは存在しない。しかし今でも、ホワイトシェルのボディにはかつてマリーを守ってついた傷がいくつも残っているし、それはココの大事な誇りだ。
「えへへ。あ、ほら見えてきましたよ!」
肉眼でも形状がわかるくらいまで近づいてきた衛星を画面内で拡大する。なんだか逆さまにした小型トラックに、無数のアンテナやパネルを盛りつけたような形だ。事前に入手しておいた設計図と照合すると、ほとんどの箇所は一致するものの、明らかに損傷や経年劣化とは違う形状のゆがみがいくつかあった。最大望遠をかければ、黒っぽい生物めいた組織があちこちに食い込んでいるのがこの距離でも見てとれる。
BLSAR-27はブラックリバーの軍事衛星の中でも大型の部類で、中枢部にはA級AGSに相当する情報処理系を備えている。したがって当然、鉄虫の寄生床にもなりうる。
太陽電池パネルの付け根のあたりになかば埋まった赤い球体が、ぴくりと動いた。あたかも、こちらの接近に気づいてぎろりと目を向けた、とでもいうように。
「宇宙戦闘、用意です!」
ココの声と同時に、スパトイア、ユサール、スティンガーがぱっと上下左右に散った。
――――
高度計が3万メートルを割った。真っ赤だったインジケータ群のいくつかが緑に戻り、それと同時に猛烈な振動がコクピットを襲う。電磁エアロブレーキングが無効になり、ホワイトシェルのボディが直接大気がぶつかっているのだ。それはつまりボディ前面の空気がプラズマ化しなくなったということであり、すなわち速度と温度が十分に下がったということを意味する。
外部カメラが復活する。真っ暗だったキャノピーが全天ディスプレイに変わり、いちめんに広がる濃い青が目に飛び込んできた。はるか下に綿をちぎって置いたような雲が、そしてそのさらに下にかすんで海と陸地が見える。
「ああ――」
ココは声にならないうめきをもらす。帰ってきた。帰ってこられた。そして、宇宙はふたたび大気と重力の向こうへ去ってしまった。
しかし感傷に浸っている間もなく、位置情報システムからアラートが来る。危惧していたとおり、予定座標よりかなり北東へ寄ってしまっている。バリアの出力不全と予定外の重量による、進路のブレのせいだ。このままでは地中海に……レモネードデルタの勢力圏内に落下してしまう。
〈補助推進を開始します〉
スティンガーが飛び出し、ホワイトシェルの肩にとりついた。スパトイアとユサールもそれに続く。ココもホワイトシェルの四肢をひねって体を裏返し、両腕を広げて重力下での滑空体勢をつくった。全員の推進器をあわせて少しでも落下速度を遅らせ、西へ、外海のほうへ距離を稼ぐ。いまできることはそれだけだ。
――5時間前――
〈待たせたな。打ち上げ準備が整った〉
ホワイトシェルの背中に装着された耐熱カプセルの中で、スパトイアが両手を打ち合わせるのが聞こえた。〈やっとかよ。待ちくたびれたぜ〉
〈鉄虫の作ったシステムを逆用するなんて初めての試みですので。色々楽し……慎重に作業をしていたのです〉のんびりとした声はアザズだ。
「こちら、準備完了しています。いつでもどうぞ」
〈いやー、緊張するわあ。言うて宇宙に行くの初めてやってんもんなあ〉
〈航法データをエイダーに送信完了。ナビゲーションデータ受信体制に入ります〉
ローディングケージが動いて、ホワイトシェルを発射位置へ運んでいく。背中にスティンガーを連結し、スパトイアとユサールを収めた耐熱耐Gカプセルを背負って、燃料タンクを付けられるだけ付けた上で、全身に銀色の反磁コーティングを施された今のホワイトシェルに普段の面影はない。スパトイアは「やっぱ宇宙の色は銀の色だよな!」などと無邪気に喜んでいたが、ずいぶんといびつな姿になってしまった。
〈ココ。今更言うまでもないが、必ず生きて帰ってこい〉
コクピット内でもう一度作戦指示書を読み返していると、キャノピーの隅にマリーの顔が小さく現れた。
〈たとえ任務が失敗しても、全員無事に帰ることが優先だ。これは閣下の厳命でもある。忘れるな〉
「はい」
司令官は今、ヨーロッパ侵攻作戦の準備が大詰めの段階を迎えて通信の余裕さえない。マリーもこのあと発射の成功と、砲塔の破壊を見届けたらスヴァールバルへとんぼ返りする予定だ。すべてがギリギリの状況での緊急作戦である。
〈本当ならもっと入念に準備してから始めるべき作戦だが……如何せん時間がない。宇宙へ出てしまったら、こちらからは何もフォローができん〉
「マリー隊長。私たちはオービタルウォッチャーです」画面の向こうのマリーに、ココはにっこりと笑いかけた。
「私たち以上にこのミッションに適したチームはありません。生まれて初めて、本来の仕事ができるんです。必ずやりとげて、無事に帰ってきます。任せて下さい」
〈データリンク確立〉エイダーから通信が入ってきた。〈打ち上げ後は、こちらでモニターしつつ誘導を行います。スティンガー223番機は回線の維持に注力して下さい〉
〈本体の方の世話になるのは久しぶりだな。よろしく頼むぜ〉スパトイアが笑った。
ケージが大きく揺れて、止まった。発射位置に装填されたのだ。印加が始まれば、地上との通信はできなくなる。小さなウィンドウの向こうから、マリーが笑いかけた。
〈甘いカフェオレを用意しておく。帰ったら久しぶりに、茶飲み話でもしよう〉
〈はい!〉
ウィンドウが消え、コクピットに静寂が訪れる。ジェネレータのアイドリング音だけが静かにひびく中、ココは数秒後に訪れる発射の瞬間を、ただ一心に待った。
――――
ホワイトシェルの軌道計算プログラムを使うまでもなく、ココは直感と暗算でその結果を予測していた。
(足りない……)
偏西風を考慮に入れないとしても、スペイン中央部あたりへ落ちるのが限界だ。これは推進剤の残量、スラスターの出力、そして全員の重量から算出される必然的な結果で、努力や根性の入り込む余地はない。物理は無情である。
おそらくオルカの方でも自分たちの位置は探知しているだろう。だが通信は封鎖されており、助けを呼ぶことはできない。いや、仮に通信ができても、レモネードデルタの支配するヨーロッパのど真ん中へ救援を派遣することなどできはしない。
〈提言。ホワイトシェルの成形斥力場内での本機の自爆によって、一時的な推進力の確保と恒久的な重量の低減を同時に達成できます〉
「それは駄目」〈ダメだバカ〉〈駄目に決まっとるやろ〉三人の声がきれいに揃った。
〈任務遂行にともなう破壊は想定内の運用です。記憶データは作戦開始直前にバックアップされており損失は最小限です〉
〈そういう問題やない、だいたいさっき全員で帰るて自分で言うたやろが。おにい……司令官はAGSの命も大事にするて、スティンガーも知ってるやろ〉
〈AGSは生命ではありません。非合理的な運用方針。しかし所有者のオーダーには従います〉
不承不承、といった態度を不思議に感じさせる機械音声を最後にスティンガーは黙った。
ユサールの言うとおり、司令官はAGSも人間やバイオロイド同様、心と命をもったかけがえのない存在だと考えている。ココ自身としてはそれに完全に同意するわけではないが、とても素敵で尊重したい考えだと思う。実際、AGSには人間と同じような心があるのではないかと感じる瞬間はココにもある。
(……だけど、ホワイトシェルは違う)
ホワイトシェルにAIは搭載されていない。もちろん感情モジュールなどもない。あくまで操縦に必要な情報処理系だけを備えた、ただのパワードスーツだ。ホワイトシェルならば自爆しようが解体しようが、司令官の意志にそむくことにはならない。
たとえ、百年間いっしょに戦ってきた、ココ・マーキュリー402の大事な大事な相棒だったとしてもだ。
(…………)
ココは誰にも言わずにサブウインドウを呼び出し、ホワイトシェルを自爆させる手順と、それによって得られる運動エネルギーの計算をはじめた。
――19時間前――
モニタに映し出されたそれは、横倒しになる寸前で持ちこたえている超高層ビルのような、斜めに天へのびる細長く巨大な建造物だった。
「カナリア諸島、二日前の映像だ。鉄虫が建造した、超長距離電磁高射砲だと推測されている」
「電磁砲? このデカさで? それってほとんど……」画面をにらんだスパトイアの言葉に、マリーがうなずく。
「ドクターの分析の結果、スケロプ級かそれに準ずる鉄虫なら、この砲を使えば高度200km程度まで上がれるという。つまりこの高射砲は、小規模なマスドライバーとも言えるものだ」
「鉄虫がマスドライバー……!?」
思わず声に出したココの方を見て、マリーは再度重々しくうなずいた。
「とはいえ、奴らが宇宙に関心を持っているとは現状考えにくい。当該地域では二派の鉄虫が激しい交戦状態にあり、一方の側が高高度飛行可能な新種のレイダー型を投入している。この大型砲は単にそれに対抗するためのものだろう……というのが、ドクターのさしあたっての結論だ。しかし」
画像が切り替わり、ワイヤーフレームの世界地図の上に、大きく蛇行する無数の線と、数字の付いた光点が並んだ。その光点のひとつだけが、不吉に赤く明滅している。
「昨日、旧ブラックリバー・アビオニクスの偵察衛星の一基が突然変調を起こした。ちょうど、この高射砲の射界上空を通過した直後のことだ。発信された電波の解析結果から、ほぼ間違いなく鉄虫に寄生されている」
ざわめいたブリーフィングルームを、マリーが手を上げて静める。
「これが奴らの作戦なのか、偶然の結果なのかはわからない。だがどちらだったとしても、この砲も衛星も完全に破壊しなければならない。万が一にも鉄虫が宇宙へ進出し、衛星網を汚染するようなことがあれば、その被害は想像を絶する」
ココは挙手して訊ねた。「軌道上へ行く手段はあるんですか」
「手段は奴ら自身が用意してくれた」
マリーはふたたび画面を切り替え、最初の映像に戻した。
「我々はまず、この高射砲を破壊せずに占拠する。そしてこれを使って、衛星攻略部隊を軌道上へ送り込む。すなわち……」
「それが俺たち、ってことだな」マリーが言い終えるのを待たずに、スパトイアが満面の笑みとともに両手を打ち合わせた。
――――
キャノピーの隅をななめに横切って、黒い線のようなものが揺れている。はじめそれは、カメラに付着したゴミか、画像処理の不具合のように見えた。
自爆シークエンスの計算を続けながらココはそれにちらりと目をやって、また計算に戻った。しかし再度ディスプレイに目を向けた時も、その線はまだあった。しかも、さっきより視界の正面に近づいてきている。
「……?」
クローズアップするとオートで焦点が合った。つまり画像の不具合ではない。レンズに付着した何かでもない。確かにそこに、前方50メートルほどの距離に浮いている物体だ。
〈おい、あれ!〉右肩のスパトイアが身を乗り出し、はるか上空を指さした。
黒い線の正体がようやく掴めた。船舶や航空機の牽引に使われる、テザーケーブルだ。ケーブルの末端がココ達のすぐ前方を、ほぼ同じ速度で飛行している。
カメラを上に向けた。ケーブルはゆるやかにしなりつつ斜め上方へ、百メートル以上も伸びている。その先に何かがいる。何かがケーブルを垂れ下げて飛んでいるのだ。
最大望遠でそのシルエットを確認した瞬間、ココは残り少ない推進剤を使って最大加速をかけ、ケーブルへ手を伸ばしていた。
届かない。もう少し。手がずれた。スティンガーがホワイトシェルの肩を押して位置を補正してくれる。スパトイアとユサールが腕を這いのぼり、思いきり体をのばしてケーブルをつかまえ、全身をたわませて引っぱり寄せてくれた。カーボンナノチューブ製の太いケーブルを、ホワイトシェルの右腕のマニピュレーターがしっかりと掴む。
〈やっほー、やっとランデブーできた!〉そのとたん、スレイプニールの明るい声が接触回線で飛び込んできた。〈さあ、しっかり掴まっててよ!〉
言うが早いか、ケーブルがぐんと上方へ引っ張られる。ココは慌てて両手でケーブルを掴みなおし、ぐっとボディに引き寄せた。
「スレイプニールさん! どうしてここに!?」
〈空で困ってる人がいるなら、どこであろうとスカイナイツは駆けつけるわ! せーのっ!〉
答えになっているような、なっていないようなことを言うのは間違いなくオルカのスレイプニールだ。上空でノズルがぱっと輝き、ふたたびぐっと上方へのGがかかる。
ホワイトシェルの両手にロックをかけて、ココはほっと息をついた。これで何とかなるかもしれない。
だが、じきにその顔がふたたび曇る。
〈んーっしょ、んぎぎぎぎぎ………!〉
スレイプニールが頑張っているのは声からも、ケーブルごしに伝わってくるエンジンの駆動音からもわかる。だが上空の彼女自身を見てみると、駆動音に対して不自然なくらい噴射炎が小さい。加速も思ったほどにはかからない。いや、高度こそ維持できているものの、水平方向の速度はむしろだんだん遅くなっている。
ここはまだ高度2万メートルの超高空、通常の航空機が飛行できる高度の上限に近い。この薄い空気の中では、いかにスレイプニールモデルのエンジンといえど十分なパワーを出せないのだ。ココはごくりと唾を飲み下して、途中でやめた自爆シークエンスの計算を再開した。
「スレイプニールさん、無理しないで下さい。こちらで重量を減らす方法を」
〈大丈夫だいじょーぶ! もうちょっと距離を稼いで、スピードも落としてやれば、私より遅い二番手が追いつくからね!〉
〈誰が二番手ですって?〉
ガツン、とこんどは下から殴られるような衝撃があって、ホワイトシェルの体がまた一段上に持ち上がった。
「!?」
上にばかりカメラを向けていたので気づかなかった。すぐ真下を、黒い円盤のようなものが飛んでいる。円盤の中央には玉座のような立派なシートがあり、そこで悠然と足を組んでいる小柄な赤毛のバイオロイドがこちらを見上げた。
「メイさん!」
それはドゥームブリンガーの指揮官、滅亡のメイであった。ココはあまり話したことはないが、たしか円盤の名前はスローン・オブ・ジャッジメント。彼女の二つ名の由来である核ミサイルを搭載した、空飛ぶミサイル基地だ。しかし今、サイロがあるはずの玉座背面には無骨なアームが何本も取り付けられ、それがホワイトシェルの胴体を下からつかんで支えていた。
「あ、あの、重くないですか」思わず口から出た言葉に、
〈はん?〉メイはあからさまに小馬鹿にした表情で答えた。〈私がふだん積んでるミサイルがどれだけ重いか知ってる? あの貧弱なツバメと一緒にしないで。そんなロボットの一体や二体なんでもないわ〉
〈誰が貧弱よ! 私はスピード重視なの! スマートなの!〉
〈ふん〉メイは鼻で笑う。たしかにホワイトシェルとスパトイアのロボットスーツ、そしてスティンガーの全重量を支えてもスローン・オブ・ジャッジメントは小揺るぎもせず安定して飛んでいる。ココは今度こそ、深い安堵のため息をついた。
〈いや、ほんま助かっ……助かりました! ありがとうございます!〉
〈でもさ、スカイナイツもドゥームブリンガーも作戦準備中だろ? こんなとこに出張ってきて大丈夫なのか?〉スパトイアがホワイトシェルの肩から身を乗り出して下をのぞき込んだ。
〈大丈夫なわけないでしょう、この忙しいのに引っ張り出されていい迷惑よ。玉座までこんなみっともない姿に改造されて〉
「ご、ごめんなさい」反射的にココは身をすくめて謝る。
〈冗談よ。ミッションの内容は聞いてるわ〉メイの声は笑っていた。〈マリーのやつに頭を下げさせるのも、悪い気分じゃなかったし〉
「マリー隊長?」
〈私たちにどうしてもって頼み込んで来たのよ〉上からスレイプニールが口を挟んだ。〈なんとかホワイトシェル込みで無事に回収したいから、こっそり出張してくれってね〉
「……!」
ココはキャノピーを開けた。薄く冷たいカミソリのような大気が全身を切りつけ、紫がかった髪を一瞬でめちゃくちゃにかき乱す。狭いチェンバーから身を乗り出して、上空のスレイプニールと、下方のメイにそれぞれ敬礼してから、ココは二十時間ぶりの大気を小さな胸いっぱいに吸い込んだ。
――20時間前――
シュッと最後の一吹きを終えると、ココは少し離れて出来映えを確かめ、それから満足げにマスキングテープを剥がした。ホワイトシェルはその名のとおり、キャノピーから爪先までぴかぴかのパールホワイトに輝いている。
「おー、綺麗になったやん」
ちょうど格納庫へ入ってきたユサールが、ホワイトシェルを見上げて言った。
装備の手入れはすべて自分の手で行うのがオービタルウォッチャーの鉄則だ。宇宙では自分の装備品をどれだけ熟知しているかが生死を分けることがある。
「この色、例のやつ?」
「そうです。箱舟に仕様書があって、純正の合成装置が作れたんですよ。しばらく触らないで下さいね」
ホワイトシェルのボディの白色はただの塗料ではない。宇宙空間での熱吸収をおさえ、耐熱・耐衝撃・耐放射線性能にすぐれた、専用の特殊コーティング剤である。地上で戦う分にはさほど有効なものでもないのだが、それでもココは手に入るかぎり必ず、この塗料でホワイトシェルを塗り直すことにしていた。
万一の備えを怠らない、という気構えでもあるが、それ以上にこの塗装はココの希望だった。いつか宇宙へ行ける日がきっと訪れる。その望みを捨てないために、ホワイトシェルはいつでも宇宙で活動可能な状態にしておきたいのだ。
「お、試作品できたのか」
ロボットスーツの整備をとっくに終えて一服していたスパトイアが、手にした雑誌をぽいと捨てて起き上がった。ユサールが手にしたタッパーを開けると、ふわりと香ばしいかおりが立つ。ココも手袋を脱いでデッキへ下りた。
「何味?」
「こっちからココア、ジンジャー、コオロギ」
「コオロギ?」
「宇宙っぽいやろ。わざわざアクアランドで売るからには、なんかうちららしい所出してかんとな」
「受けるかなあ。あ、ジンジャーおいしい」
とはいえ現状では宇宙へ行くどころか、地上での仕事が増える一方だ。最近は大きな作戦の準備だとかでブラックリバーの隊員たちがほとんど訓練に出ずっぱりで、その分遠征や偵察などの雑務が頻繁に回ってくる。この間など、ホワイトシェルで氷山の下へもぐる羽目になった。今はこんな些細なことにでも、宇宙のかけらを想うしかない。そう思いながらかじったコオロギビスケットは、やっぱりあまり美味しくはなかった。
〈オービタルウォッチャー、緊急ミッションです。至急第二作戦室へ集合して下さい〉
エイダーの声がアラート音と共に通信機から響いてきたのは、その時のことだった。
――――
「なあなあ、これ!」
いつの間にかコクピットのすぐ横に来ていたスパトイアが、ごうごうと鳴る風に負けないよう怒鳴りながら、一枚のビスケットを差し出した。
「なんや、うちの試作品やん。持ってきてたん?」反対側の隣に来ていたユサールが身を乗り出す。
「いや、ポケットに入れたの今まで忘れてた。せっかくだからここで食べようぜ」
ビスケットを三つに割って一かけずつ、風に飛ばされないよう注意しながら口に入れる。よりによって、コオロギ味だ。
〈ちょっと、のんきに何やってるの?〉メイの声が飛んできた。下を見ると、こっちを見上げて拳をぶんぶん振っているのが見える。〈気を抜かないで。まだヨーロッパ圏よ〉
〈何々、おやつあるの? 私にもちょうだい〉と、今度はスレイプニール。
「いや、これは余りもんで。オルカに帰ったらあらためてご馳走しますね」ユサールとスパトイアはあわててホワイトシェルの肩の上へ戻っていく。ココもチェンバーにもぐり直し、通信機を喉元へ当てた。
「作戦が終わったら、マリー隊長とお茶を飲む約束をしてるんです。お二人もよかったらいかがですか。オービタルウォッチャー特製、コオロギクッキーがありますよ」
〈〈え、何それいらない〉〉
「なんでやねん!!」
装甲をばんばん叩いて憤慨するユサールにひとしきり笑ってから、ココはもう一度ホワイトシェルの機体を見渡した。ほんの一日前まで美しい純白だったボディは戦闘で傷つき、高熱で灼けて、見る影もなく真っ黒だ。フレームの地金がむき出しになっている部分さえある。
「……帰ったら、また塗りなおしてあげるね」
キャノピーを閉める前にココは手を伸ばし、ザラザラにささくれ立ったまだ熱い装甲を撫でた。今度は夢ではない。希望でもない。現実に、確かに行くべき場所へ行き、果たすべき仕事を果たしたこの相棒を、もう一度隅から隅までメンテナンスしてあげるのだ。ココはその時が待ちきれない気がした。
白く泡立つ雲の海がとぎれた。その下の、うろこのように小さな光をいっぱいに反射する青緑色の海が、少しずつ近づいてきた。
End
「あ、雪……」
おれいの声に、弥一郎はふとんの中から目を上げた。
ほそく開けた板障子の先、ほんのりと薄明るくなりかけた京の空に、ちらり、ちらりと、白いものが舞っている。
(どうりで、冷えるはずだ)
弥一郎は口の中でつぶやき、寝返りをうって、おれいの白い肌に手をはわせた。
「あれ、弥一郎さま」
(もうじき、師走だものな……)
まだ眠気ののこる頭でうすぼんやりと考えながら、むっちりとした乳房のあいだに顔をうずめる。
「もう、夜が明けますよ……」
「なに、まだ……あたたかいな、おまえの肌は……」
昨夜、あれほどむさぼるようにかき抱いた肌身だというのに、おれいの肢体はなんどでも弥一郎をとりこにして離さない。
「いけません、いけません……あ、あ……」
「おれい……ああ、おれい……」
おれいは、美馬弥一郎が遊里で出会った女である。
まじめ一辺倒の弥一郎は、それまで「そうした店」に足を踏み入れたことがなかった。ある時たまたま、気がむいて同僚のさそいに乗ってみたら、入った店におれいがいた。
とびきり美しいというわけではない。しかしふしぎと品のある顔立ちで、それが笑うと花の咲くようにやわらかくなる。何ごとにつけよく気がつき、酔客のあしらいもうまく、ふとした受け答えにはしっかりした教養を感じさせた。
このおれいに、弥一郎は、すっかりまいってしまった。本人のいうのに、
(一目ぼれ)
で、あったという。
そこから毎日のように通いつめ、一月もたたぬうちに、乏しいたくわえをはたいて請け出してしまったのだ。
おれいもまた、よく弥一郎に尽くした。寵愛をいいことに肉欲におぼれさせるような真似はけっしてしなかった。それどころか、
「弥一郎さま、お起きになってくださいませ。出仕に遅れます」
「弥一郎さま、そのようなお召し物ではいけません。繕っておきますので、お着替えください」
「む、むう……」
むしろ弥一郎の尻をたたくようにして、前よりも仕事に励ませる。かえって主家の評判も上がったほどである。
遊女を家にむかえたことによい顔をしなかった家人や同僚も、
「美馬のやつ、まことよい女を引き当てた……」
と、ほどもなくおれいを認めるようになった。
今ではおれいは、美馬の家のことをすっかりまかされている。祝言こそまだあげてはいないが、ほとんど正妻も同然である。
「さ、お召し上がりくださいませ」
「うむ。うまい、うまいな……」
麦飯と菜の汁、漬物だけの質素な朝餉を、弥一郎はもりもりとかき込む。白湯を一杯、うまそうにすすってから、隣にひかえているおれいへ目をやった。
「そうだ、まえの日記を出しておいてくれ」
「はい」素直にこたえてから、おれいが不思議そうな顔をした。「前のでございますか?」
「うん。今日はすこし、書きものをするのだ」弥一郎は愉快そうな顔をした。「お前にも関係のあることゆえ、見てみるか。ふふ……」
この時代、紙はまだ高級品である。日記をつけるなどというのは、弥三郎の身分では贅沢といえるが、きちょうめんな弥三郎は毎日、その日おきた色々なことをこまかく書きとめていた。
板の間へ文机をすえて、弥一郎は先月の日記をひろげ、真新しい紙を横において、何ごとか書きうつしはじめる。その手もとをのぞき込んだおれいが、
「ま……」
頬をぱっと赤らめて、顔をふせた。
弥一郎が書きうつしているのは、おれいが毎夜どのような技巧をつかい、どのように弥一郎をよろこばせたか。要するに、閨事の記録であったからだ。
「みょうに思うであろうな」弥一郎も、さすがに苦笑した。
「だがな、これが本当に務めなのだ。三好さまの、末の娘御がな。まだ子宝を授からぬそうな」
「は……」
三好さま、とは弥一郎の主君、三好長之のことである。讃州細川家に代々つかえている、歴史ある武家だ。
讃州細川といえば、いまを時めく天下の管領・細川家の分家である。三好家はそのいち陪臣にすぎないが、それでも家格はそれなり以上のものだ。領国である阿波のほかに、この京にも屋敷をもっており、弥一郎は京屋敷をあずかる奉公人のひとりである。
「おまえのことを、三好さまがご存じでな。閨の技に詳しかろうから、手本がほしいと、直々に頼まれた。このようなこと、人に知らせるものではないが、な……」
「恥ずかしゅうございます……」
袖で顔をおおって下がろうとするおれいを、弥一郎は笑いながらひきとめる。
「そう言うな。さ、ちょっと読んでみて、間違いなどあれば言ってくれ」
「あれ、もう……ご勘弁下さいまし……」
* * *
その夜、深更のことである。
京の冬は寒い。夜ともなればいっそうのことだ。足元から立ちのぼり、からみついてくるような冷気のことを、みやこ人は、
「京の底冷え」
と呼びならわしてきた。
寒気の沼に首までとっぷりとつかり、凍てついたように動かぬ町並みを、とある寺院の屋根から見下ろす一つの影があった。
おれいである。
いや、おれいであって、おれいではない。
檜皮色の麻の小袖は、黒い布を体にまきつけただけの動きやすい装束にかわり、白くなまめかしい脚にはうすい鋼の脚絆を巻いている。唐輪にまとめていた黒髪は頭のうしろで高く束ね上げられ、白い鉢金が月光をはねかえす。何より、やわらかく愛嬌のあったおれいの面立ちは別人のように冷たく引きしまり、殺気すらまといつかせているではないか。
おれいの本当の名を、
〈ゼロ〉
といった。
おれい、いや、ゼロは冷たい月明かりの下を、屋根から屋根へ音もなく跳びわたる。そして蝶が花にとまるように、ひときわ広大な屋敷の塀のすみへ、しずかに降りきたった。
花のかおりが、かすかにただよう。冬の夜には異様なことである。
あちらに臘梅、こちらには椿。冬でも花をつける木々が、そこかしこに植えられている。いや、冬にかぎらず、四季折々の花木が、広大な庭園をくまなく飾っているのだ。
この広大な屋敷の名は、室町第。別名を「花の御所」という。
京の都の中央に位置する、征夷大将軍の居宅にして執政所である。目をこらせば夜闇の中にも、贅をこらした庭木や柱、飾り障子のさまが見てとれる。屋根までが、にぶく輝く黄金でふちどられていた。
広壮な庭園のすみずみまで、ゼロはするどく目をはしらせる。石橋、あずまや、池の小舟……。そのいずれにも、おかしな点は何もなく、やがてゼロは失望の表情で、ふたたび鳥のように屋根の上へ舞い上がった。
〈おまえの母は生きている。手がかりはすべて、花の御所に〉
ゼロの脳裏には、あの謎めいた仮面の剣士の言葉が、影のようにまといついて離れないのであった。
――――姉の仇、そして母の仇を探しもとめて京の都にたどりついたゼロは、炎の剣技をあやつる奇妙な剣士のうわさを聞きつけた。不思議に心ひかれるものを覚えたゼロは、ひとまず母の仇のことはおいて、その謎の人物を追うことにした。身につけたムラサキ流のわざをもってすれば、遊里にもぐり込むことも、目をつけた郎党衆のひとりをたらし込むことも、造作もないことだ。
謎の剣士はすぐに見つかった。しかし、その正体を突き止めるよりも先に、その口からゼロは、とうにこの世にいないと思っていた母の所在を聞かされることになったのだ。
(――――何者なのだ、あの男は……?)
ゼロの心は千々に乱れる。
あの太刀筋は間違いなく、ムラサキ流のものだった。それも、ゼロが教わらなかった「火神の型」だ。
あの日から折をみて、こうして御所に忍び込んではさぐり回っているが、母の手がかりなどどこにも見つからぬ。屋根に開いた大きな穴を、ゼロは舞うように飛び越えた。
室町幕府の中枢たるこの花の御所であるが、じつは開府以来ずっと御所であったわけではない。三代義満公が北山第へ移り、一時は完全にうち捨てられた廃園同然のありさまだったことすらあった。ほんの数年前に、いまの将軍・義政公がふたたびここを御所とさだめ、改築もはじまったが、まだまだ荒れ果てた一隅がそこかしこにある。あるところは豪奢に、あるところは荒涼と、奇怪な風格をたたえた魔邸と化しているのが、いまの室町第のすがたである。
いくつめかの屋根をひらりと躍りこえたゼロは、
「式部少輔(しきぶのしょう)さま」
と、呼びかける声を足の下に聞いて、動きをとめた。
この下はうち捨てられた回廊だ。そこを誰か、歩くものがいる。いま、御所で式部少輔と呼ばれる者といえば、弥一郎のあるじ・三好長之しかいない。
「美馬のやつに、例の件お申し付けなさったとのこと、まことでございますか」
美馬、という言葉を耳にして、ゼロはかがみこんで耳をすませた。声はとがめるような調子で、もう一人の人物を問い詰めている。
「あやつの妻は遊里の女と聞きますぞ。かようなみだらな手業を、あのお方に……」
「口をつつしめ」
ぴしりと答えたしわがれ声は、やはり三好長之のものだった。
「もはや、体裁を気にかけていられる時ではない。細川様からも、そう仰せつかっておる」
「しかし……」
「お前でもかまわんのだぞ。なじみの端女の一人や二人はいよう……子をなす方法に心当たりがあれば、知らせよ。手立てはひとつでも多い方がよい」
「な……」
足音が廊下をすすんでいく。一呼吸おいて、もう一人がいそいで後を追った。
ゼロは屋根のへりに手をかけ、音もなく夜の庭へおり立った。直垂すがたの背中がふたつ、角をまがって消えていくところだった。
(……)
ゼロがひそかに調べあげたところでは、三好長之は讃州細川家の中でも、真面目で故実にくわしいことだけがとりえの、変哲のない武人にすぎない。子作りの法などをとつぜん訊ねてくるのは妙だと思っていたが、どうやら何か裏があるようだ。
(止めるべきか? 弥一郎さまを……)
房術もりっぱなムラサキ流の秘技のひとつ、余人に漏らしていいものではない。何か理由をつけて弥一郎の仕事をさし止めるなり、妨害するなりすべきか、ゼロは朝からずっとそれを考えていた。
しかし、いまの会話をきいて、ゼロはひとまず静観することにきめた。この糸は、どうやらより身分の高いだれかにつながっている。うまくたどれば、あの剣士や母の行方をたどる手づるになるやもしれぬ。
冬の風が一陣ふきつけ、枯れ葉を舞い上げた。それが地面におちた時、もはやそこには誰もいなかった。
* * *
菜飯に干魚のつけ焼き、豆の汁に、茸と昆布の炊き合わせ。来客があったので、いつもより一品皿をふやした、豪勢な夕餉だ。
「やあ、うまそうだの」
相好をくずす草野司馬次郎を、隣の弥一郎がにんまりと見た。
弥一郎の自慢の一つに、おれいの料理がうまいことがある。それもとくに値のはるものを使うわけでも、時間をかけるわけでもなく、ただありきたりの材料に少しの工夫で、
「おう、これは」
と、舌つづみを打つようなものをつくるのだ。
「干魚ひとつ焼かせても、美馬の家では味がちがう」
近ごろはそんなことを言って、夕餉の時分になると仲間の家人が、手みやげを持って弥一郎の家へやってくることも少なくない。
無論、これも忍びの手管のひとつである。人があつまるところには、情報もあつまる。「寄せ餌ぶるまい」と呼ばれる、ムラサキ流の基本の心得だ。
「ごゆっくり、どうぞ……」
酒の徳利を出し、奥へさがったと見せかけて、おれいのゼロは次の間でぬかりなく耳をすます。
「そういえば、どうなった、あのみょうな剣客とやらは」
「あれから、まるで姿を見せぬ」杯をうまそうに干して、弥一郎はふーっと熱い息をはく。「なんだったのか、今でもわからぬよ。伊勢殿の家人に、似た姿を見たという者もいるが……」
「なんでもよいわ。どのみち、これからしばらくの間は、そんなわけのわからぬ男にかまってはおれんぞ、美馬よ」
草野はぐっと声をひそめた。
「義尋(ぎじん)どのが、いよいよ還俗なさるときまった」
「まことか」
弥一郎の声が緊張をおびた。
「おお。今年のうちにも、寺をお出でになって、どこぞの屋敷へ移られるそうな」
「ということは、いよいよ……」
「義政公も、お子をあきらめられたということであろうよ」
次の間のゼロも、目をみはった。
義尋とは、いまの将軍・足利義政公の弟君の名だ。義政公に子がないことは誰もが知っている。仏門に入った義政公の弟が還俗するということは、すなわち義政公の跡継ぎになるということだ。
「御台さまは、どうお考えなのだろうな」
「あの方が、金のことのほかに何をお考えかなど、誰にもわかるものかよ」
そうなれば、義政公の正室である御台所……富子さまの心中も穏やかなはずがない。なんとしても、子をもうけようとするはずだ。
(つまり……)
三好長之のあの奇妙な言いつけは、娘のためなどではない。あるじである細川成之の、そのまた後ろ盾、御台様……将軍正室・日野富子のためだ。
「さればよ。きさまが命じられたという、例の件……安からぬお役目ということになりそうだぞ。どうだ、できたのか」
「あはは。まあ、な……」
(なんと、まあ……)
声に出さず、薄暗がりの中でゼロは含み笑いをした。昨晩、長之に食ってかかっていたのが誰かはわからぬが、気持ちもわかろうというものだ。天下をすべる将軍の正室が、娼妓のわざを頼みにしようとは。
しかし、これは随分と大物に糸がつながってしまった。手づるとしては申し分ないが、しかしこれほどの大物にムラサキ流の技を知られてしまうことは、
(かえって、危うくはないか……?)
「何しろ、数がおおくてな。なかなか、終わらぬ」
「なにを、惚気おって……しかし、この茸はうまい。もう少し、ないか」
「聞いてみよう。おおい、おれい、おれいよ」
じぶんを呼ぶ声に、ゼロは思案をいったん胸にたたんで立ち上がった。今は、弥一郎の妻になりきるとしよう。
その時、ふと一抹のかすかな違和感を、ゼロは感じたような気がした。しかし、それはあまりにおぼろであったので、そのまま忘れてしまった。そのことを、ゼロは悔やむことになる。
その夜遅く、草野を送っていった弥一郎はそのまま帰らなかった。翌朝、鴨川の河原に、冷たくなって横たわっているのが見つかった。
* * *
「家の前で別れた時は、したたか酔ってはいたが、いたって元気であった。も少し、様子に気をつけておればよかったが……この草野の不覚じゃ。詫びる言葉もない」
「いえ……」
戸口で深く頭をたれる草野司馬次郎に、おれいもしずかに頭を下げた。
行商人、与太者、乞食、病人、罪人……この時代、鴨川の岸辺には、ありとあらゆる身分の定かならぬ者どもがたむろしていた。そのうちの誰が弥一郎をおそったとしても、また、よし何ものかがそれを装ったのだとしても、突きとめるすべはないと言ってよい。
祝言をあげたわけでもなく、内縁のあいだがらにすぎないおれいには、美馬の家に対してなんの権利も、かかりあいもない。ただ、まわりのものの気遣いで、なきがらを荼毘に付すまでは家にいられることになった。
「お前も、望むならどこか奉公先をさがしてやるが」
「身にあまる、ありがたきお言葉なれど……」
三好長之の言葉を、おれいはていねいに辞退した。
寺に遺骨を埋めるという風習はまだ一般的ではない。焼いた骨は小さな壺におさめ、主君があずかって郷里の阿波まで持ち帰ることになる。
長之と、供をする草野がかえってゆく後ろすがたに、おれいは深く頭をさげる。。
ふいに、その目が見開かれ、そしてするどく細められた。
おれいは……否、ゼロは何もいわず、夕暮れの中に遠ざかる二人の男の背中が見えなくなるまで、じっと見つめていた。
* * *
「ふう……」
はや薄闇につつまれつつある鴨川のほとりを、ひとりの男があるいていた。
息が白い。
ひら、と男の首すじに冷気があたった。見上げると、薄闇の空からちらちらと、白いものがおりてくる。
(ゆるせ、弥一郎……身の不運とおもってくれよ……)
男は草野司馬次郎であった。
なにかから逃げるように早足であるく司馬次郎が、ふと立ち止まった。
道ばたに、女が立っている。
被衣(かつぎ)を深くかぶっており、顔は見えぬ。しかし司馬次郎は女の着ているのが、美馬の妻がよく着ていた檜皮色の麻の小袖であるのにすぐ気づいた。
「草野様」
司馬次郎が口をひらく前に、女はつっと進み出てきた。その声も、間違いなくおれいのものだ。
「このようなところで、何をしている?」
司馬次郎の険しい声にはこたえず、おれいは続けた。
「草野様の義理の妹御は、伊勢の塩屋隆頼さまに嫁がれたとか」
「それがどうした。なぜ、そのようなことを知っている」
「塩屋さまの弟ぎみは、浄土寺で義尋さまにお仕えしたことがあるそうでございますね」
「それがどうしたというのだ!」
司馬次郎は声をあららげ、腰の刀に手をかけた。おれいが、しずかに被衣をぬいだ。
「どうもいたしませぬ。ただ、最後に確かめたかっただけにございます」
おれいの髪は高く束ね上げられ、ひたいには白い鉢金が光っていた。
「最後に、だと」
白菫の被衣(かつぎ)が、ふわ、と宙をとんだ。司馬次郎がおもわずそれを目で追ってしまったのは、投げ上げるおれいの仕草があまりに優美で、無造作だったからだ。
そして見上げたその首が、もどることはなかった。
あごの下がぱっくりと大きく、赤く、口を開ける。そこから真紅の血をしぶかせ、司馬次郎はそのまま、声もたてず後ろへ倒れた。
おれい……否、ゼロは小太刀の血をはらい、懐へもどしてから、司馬次郎の死骸をつめたく見下ろした。大きな体を爪先でひっくり返すと、直垂の背中には、草野家の家紋である隅切角紋が染め出されていた。あの夜、三好家の三階菱に五つ釘抜の家紋とともに、廊下を曲がって消えていった家紋が。
ゼロは河原に住む乞食やならず者たちが集まってくる前に、ゼロは死骸を蹴って川へ落とした。
それから、弥一郎の好きだった檜皮色の麻の小袖を脱ぎ捨て、これも鴨川の流れに捨てた。
* * *
御所の廊下をいそぎ足にあるいていた三好長之は、ふと足を止めた。雪がだんだんと激しく舞いはじめた縁側に、汚れた書きつけが数枚、小石を重しにして置かれている。
「はて……?」
女御の誰かが置き忘れでもしたのか。何かの帳面からやぶりとったように見える。とりあげた長之は目を見張った。
そこには、閨のうちにて女が男を夢中にさせ、子種をしぼり、まちがいなく子をなすための手管が、ていねいな筆はこびで子細に書き出されていたからだ。
「これは……美馬の……?」
あたりを見回したが、だれもいない。長之はもういちどあたりを用心ぶかく見回してから、書きつけをていねいに畳んでふところへしまい、足早に歩き去った。
それを見届けて、すこし離れた屋根の上から影がひとつ、白い闇のむこうへ音もなく飛び去った。
ゼロの書き残した、ムラサキ流秘伝の房術――それを将軍正室・日野富子が実際に目にしたか、そしてそのわざを使ったのかどうか、それを確かめるすべはない。
ただ事実として、翌年富子はひとりの男子を身ごもった。その子・足利義尚と、還俗した義尋……足利義視との対立が、かの応仁の乱の火種の一つとなる。
また、三好家はこれ以降、急激に頭角をあらわし、細川家中での発言力を増していく。そして四代ののち、梟雄・三好長慶を生み、ついに主家を滅ぼすにいたるのである。
しかし、そのどちらも、今のゼロには知るよしもない。
ゼロはただ駆ける。家族の仇と、血のよすがとを求め、雪降る京の都を駆けぬけてゆく。
華麗なる花の御所を焼き尽くし、室町という時代をおわらせる大戦乱が、そのゆくてに待ち受けていることを、若きクノイチはいまだ知らぬのであった。
続 く
――――
「……おおー」
大きな「続く」の文字がバーンと画面に出ると、俺は思わず声を上げて小さく拍手をしていた。
「なるほど、これが時代劇ってやつかあ。ありがとな、カエン」
隣に座ったカエンが、嬉しそうに笑って、ぺこりと頭を下げる。
サレナの事件でテンランスタジオを捜索した際、結局かんじんの劇場版のデータはなかったわけだが、それ以外の作品の映像データはいろいろと残っていた。特に、ゼロとカエンの出演した『大戦乱』シリーズについては、シーズンごとの全話をおさめた「ボックス」と呼ばれる(らしい)映像ディスクセットがずらりと揃っていた。全部観たら何百時間になるかわからないほどだが、
「まあ大戦乱シリーズはスピンオフ作品も山ほど作られてますし、なんなら本編より長くなったシリーズとかもありますし、ゲーム版はゲーム版で一大ユニバースですし、さらにアニメも漫画も小説もありますから、作品世界全部を把握しようとしたらこれでも全然足りないんですけどねウェヘヘ……」
フレースヴェルグによればこれでも氷山の一角といった感じらしい。おそろしいことである。
ともあれ彼女がきっちりと整理した上でオルカのライブラリに入れてくれるというので、いずれ観ようと思っていたのだが、どこで聞きつけてきたのかカエンが先日、
「殿とこれが見たい」
と、ディスクを持ってきたのだ。
「あの、途中の回想でちらっとだけ出てきた、謎の剣士がカエンなんだろ?」
「そう」カエンは得意げに胸をはる。「これは、第二部、シーズン3……の、第1話。このあと、カエンの……正体、わかって、ゼロと再会する。強敵」
「なるほど。じゃあ、続きはゼロと一緒に見るか?」
だが、カエンは顔を曇らせて首を振った。俺はびっくりして二人がけの大きなカウチから起き上がる。
「カエン?」
「殿。今の、第1話、見て……どう思った?」
「どうって……面白かったよ。映像がリアルで、アクションもかっこよかったし。実際の歴史とつなげてるんだろうなっていうシーンもあって……俺はそこ詳しくないから、よくわからなかったけど」
時代劇、というジャンルがあることはゼロを復元したときに知っていたが、実際に見たのは初めてだ。歴史ドラマの一種なのだろうが、強く様式化された部分があり、独特の美意識を感じる。なるほど、ゼロやカエンはこういうものを演じるために作られたのかと、あらためて納得できた。
だが、カエンはじれったそうに首を振った。「お色気は?」
「お色気?」
「シーズン3は、リアリティと、お色気がコンセプト。ゼロ……毎回、えっちなことする。それは……どうだった?」
「ああ……!」確かに今回の話の冒頭には、ゼロと弥一郎という武士とのベッドシーンがあった。オルカで暮らしているとその辺の感覚がだいぶ偏ってくるが、言われてみれば相当きわどい所まで映していた気がする。
「そうだな、よく知ってるゼロがそういうことしてるのはちょっとドキッとしたけど、でも、まあ……」
しょせんは演技だし、そもそもオルカにいる今のゼロとは別の個体の話だ。と、続けようとして、ふいにゾッとした。
俺にはもちろん、そのことがわかっている。でも、ゼロは? もしも、ゼロがこれを見たら、どう感じるのだろう?
言葉が止まってしまった俺に、カエンが大きくうなずいた。
「ゼロ……は、これ、お芝居だって、知らない。わからない。ぜんぶ……本当。殿じゃない人と、えっちなこと、見たら、つらい」
顔を上げて、カエンを見た。その真剣な眼差しで、俺はようやく気づいた。「じゃあ、もしかしてカエンは今日……」
「これは、このシリーズだけは……ゼロに、見せないでほしい。それを、お願いしにきたの」
俺はテーブルの上から、ディスクが入っていたケースをとった。薄いプラスチック製のケースの表には、暗闇に浮かぶゼロの顔のアップにタイトルロゴ。裏には煽り文句と各話のかんたんな解説が書かれている。
「フレースヴェルグに言っておくよ。このシリーズだけはライブラリに入れないで、しまっておこう」
カエンはにっこり笑った。「ありがとう。殿」
「それにしても、よく気がついたな」俺はカエンの頭をなでた。
「お姉ちゃんだから」
嬉しそうなカエンの頭をもう一度なでて、俺は深く息をつきながらふたたびカウチに身を沈めた。カエンも、俺の横に寝そべる。
「この次のシーズン。カエンが、えっちなことになる話も、ある。……見たい?」
「……そういうのは、いいかな」
上目遣いで俺を見上げて、そっと体をすりつけてきたカエンを、俺は抱き寄せた。
第2話のアバンタイトルが流れはじめた。でも俺もカエンも、もう画面を見てはいなかった。
なお、これは余談になるのだけれど、その翌日、アルマンが俺のところへ来た。
カエンとまったく同じ懸念を口にしたので、昨日の話をすると目をまるくした。
「よもや、カエンさんに先を越されるとは……姉妹愛というのは、すごいものですね」
呆然としているその表情を、いまでも覚えている。
End
エレベーターが止まり、ドアが開くと、湿った生あたたかい風が吹き込んできた。
天井の高い、広い広いフロア。そこを埋めつくして、透明なアクリルの水槽と、無数の白いパイプがどこまでも、どこまでも並んでいる。
「ほおー……」
思わず、声がもれる。ランバージェーンがさも自慢げに、手をさっと振ってみせた。
「ようこそ、司令官。できたてほやほやの地下水耕農場、アクアランドファームへ」
島のほとんどを氷河に覆われた姿からはちょっと意外に思えるが、スヴァールバル諸島は地熱が豊富だ。火山こそないものの、島の北西部には天然の温泉が湧いているし、島内のあちこちには旧時代の地熱発電所も残っている。
ここにしばらく腰を据えると決めたとき、俺たちは当然、この地熱を何かに利用しようと考えた。そして出てきた案が、温泉と、発電所と、地下農園だ。
温泉案はその後発展に発展を重ねて、アクアランドとして先日めでたく落成した。発電所は旧時代のものを手直しして、そのまま使わせてもらうことにした。そして農園案から生まれたのが、アクアランドの地下深くに広がるこの水耕農場というわけだ。
「もー、大変だったんだから! 私は現場作業員だって言ってるのに、半月も地下で工程管理やらされてさ。しかもフェアリーシリーズの連中ってば、物腰は丁寧なのに注文は細かいわ、絶対ゆずらないわ……」
「ははは……ご苦労様」俺は苦笑いするしかなかった。技術班の上の方がみんな天才肌というか、趣味人気質の人々ばかりのせいで、ジェーンに苦労が集中しているのは聞いている。「忙しいのに案内までさせちゃって、すまないな」
「逆よ、逆! こんなに苦労したんだもの、エスコート役くらいもらわないと割に合わないわ」ジェーンは俺の腕をぎゅっと抱きかかえ、ニッと笑った。「で、どう?」
「うん、すごいな。でもこれは、農場っていうより……」
水耕農場というもののことはよく知らないが、もうちょっと何かしら畑っぽいものを想像していた。ここには土もなければ緑もない。まぶしいくらいに明るい照明が、清潔な水槽とパイプを照らしているだけだ。
「工場みたいよね」
ジェーンが俺の感想を先取りした。「私も同感。植物工場なんて呼び方もあるらしいわ。種苗エリアに行ってみない?」
水槽には水がはってあり、よく見るとわずかにさざ波が立っている。たぶんどこかにポンプがあって循環しているのだろう。横目で見ながら広いフロアをてくてく歩いて反対側に着くと、そこには巨大なシャフト状の建造物が、天井から床までをつらぬいてそびえ立っていた。立ち並ぶドアの一つを、ジェーンが気軽にノックして開ける。
「ヘイ、ドリアードいる? 司令官がきたわよ」
「ご主人様! ようこそお越し下さいました」
中央のテーブルで何やら作業をしていたドリアードが、ぱっと笑顔になって出迎えてくれた。
そこは実験室のような感じの部屋だった。一方の壁がぜんぶ大きな棚になっており、平たいバットがずらりと置いてある。バットの中には小さい緑の双葉が何百も、整然と並んでいた。
「キャベツの芽です。もう少し大きくなったら、外の栽培ユニットへ移します」
「これ、全部がキャベツ?」
「下の段はレタス、こちらはセロリとほうれん草です」ドリアードが指さして教えてくれるが、ぜんぜん区別がつかない。キャベツの芽って芽キャベツじゃなかったのか。
「地下一階は葉物野菜フロアなのよ」ジェーンも横から言った。「ここがいちばん遅れてるけど、下の階はどこももう動いてるわ。見に行くでしょ?」
「ああ、たのむ」
地下二階も同じような作りだったが、こちらの水槽には分厚いスポンジの土台が敷かれたうえに、すでに植物がぎっしりと生い茂っていた。中には小さな実をつけ始めているのもある。
「これはトマトで、あっちがナス?」
「正解です」ドリアードが嬉しそうに笑う。「あと一月ほどで、もぎたてを召し上がっていただける予定です」
「ソワンも喜ぶだろうな。土がなくても、こんなに立派に育つんだなあ」
「この水に必要な栄養素がぜんぶ入ってるのよ。あとは光と、温度・湿度管理ね」ジェーンが自慢げに透明な水槽を叩いた。「虫も病原菌もいないから農薬だっていらないし、収穫も全部オートメーション。未来の農業って感じよね」
「フェアリーシリーズとしては、複雑な気分でもあります」水槽の中で揺れるトマトの根を眺めて、ドリアードはしみじみとした顔になる。「大地に根をはり、太陽の恵みを受けてこその作物、という気持ちがどうしても」
「いいじゃないの、汚れないしラクだし、何より虫がいないし」ジェーンは肩をすくめた。「古いやり方にこだわるのって、アナクロだわ」
「微量栄養素や光の周波数が偏るために、成分が微妙に異なるというデータもあるんです。新しい技術はもちろん大切ですが、軽々に乗り換えていいということには」
「この島に農業できる場所なんてないでしょ? まずは収量、そしてコスト。地上の畑なんて今はぜいたく品なのよ」
「まった、まった。喧嘩はなしで頼むよ」
俺ごしに言い合いをはじめた二人を、俺は苦笑いしながら止めた。なにか他の話題をさがしてあたりを見回すと、外周の壁際に何か大きな建造物が貼りついているのが目に入る。
「あの壁際の建物は何? 上のフロアにはなかったよな」
ジェーンが顔を上げ、「ああ、あれは地下トンネルの入口。オルカのいるドックまで直通で、リニアも走ってるわ」
「おお! 秘密の連絡通路とか、そういうのワクワクするよな」
「男の人って、ホントそういうの好きよね」さっきまでにらみ合っていた二人が、呆れたように顔を見合わせて笑った。
もう一階下りると、そこは色々な豆を育てているフロアだった。その下は根菜。さらにその下は果物。そしてそのまた下のフロアには、青々とした田んぼが広がっていた。
「本当にすごいな。ここから出なくても一生食べていけるんじゃないか」稲の青いにおいをかいだのも久しぶりで、俺はふかぶかと深呼吸した。ドリアードはまだ細く柔らかい葉を、確かめるようにやさしく撫でている。
「オルカの食料自給率もちょっとは改善するかな」
「自給率ですか?」
オルカで消費する食糧や生活物資は、一部の海産物や、上陸先で見つけた分などを除いて、すべて外部拠点から送ってもらったものだ。世界中の外部拠点がオルカのために生産したものを、オルカが消費し続ける。そういう関係がずっと続いている。
そういう役割分担だからと言えばそれまでだが、なんとなく引け目というか、借りのようなものを俺はずっと感じていた。オープンしたばかりのアクアランドには、外部拠点の隊員たちも順番に招いて楽しんでもらう予定だ。この農園によって、彼らの負担を少しでも減らせるなら、それに越したことはない。
「ご主人様が、そのようなことをお気になさっているとは存じませんでしたが……」しかしドリアードは、ちょっと困ったような顔で首をかしげて言った。
「ここの農園の産物だけで自給できるのは、多めに見積もってもバイオロイド三十人くらいですよ」
「三十人」
思ったよりだいぶ少ないので、俺は驚いた。オルカの乗員の、せめて半分くらいは養えると思っていたのに。
「農業って大変なんだな……」
「司令官のお世話をしつつ、司令部機能を維持できる最低限の人数だそうよ。ここを閉鎖シェルター化する時にそなえて、設計の一番はじめに計算したわ」
ジェーンの言葉に、俺は天井を見上げた。太いフレームが無数に組み合わさった、強固な構造がむき出しになっている。この地下農場はただの農場ではなく、いざという時の防空シェルターでもある。レモネードとの戦争を見越して、そういう風に造ったのだ。一時的にであればオルカと箱舟、アクアランドの全人員を収容できるはずだが……一時的でない使用法まで考えられていたとは知らなかった。おそらく、秘書室や参謀達の配慮なのだろうが。
「……ここをそんな風に使う時は、来てほしくないな」
俺はつぶやいて、両隣の二人の手をにぎった。二人ともちょっと驚いた顔をしたが、笑顔でにぎり返してくれた。
「あれ、土がある?」
最下層はそれまでのフロアと様子が違っていた。水槽もパイプもなく、自然光に近い照明の下、ふつうの畑のように土の地面が広がっている。そこへりっぱな木が何本も生い茂り、向こうも見通せないくらいだ。
「試験的に、人工土壌を使っているんです。効率は落ちますが、木本はまだどうしてもこの形でないと……」
「ここだけ、定期的にエルフの連中に来てもらわないといけないのよね」ジェーンがちょっと唇をとがらせた。「まあ、あそこの上の二人はホントにすごいし、別に噛みついてこないからいいんだけど」
柔らかい土を踏んで、木々の間を進んでいく。案内してくれるドリアードの声は心なしかはずんでいる。
「ここから向こうがリンゴの木、あちらがオレンジの木。反対側はブドウ畑です」
「やっぱり、こういう土のある畑の方が好きみたいだな?」
「それはもう! ここがシェルターになった時には、セラピーエリアとしても役立つんですよ」
「だから、そういう使い方はしたくないって……」
ふいに木立が途切れて、開けた場所に出た。ほかと同様に土はあるが、何も植わっていないのだ。
「ここは?」
「実はここだけ、まだ何を植えるか決まっていないんです」ドリアードがちょっと恥ずかしそうに言った。「栄養配分の効率なんかを考えて、樹木の配置と面積を決めているんですが、ちょうど半端に土地があまってしまって」
空き地の端から端までを見渡す。この農場は地上のアクアランド同様、おおまかな円形をしており、ピザのように放射状に区画分けされているのだが、そのピザの小さめの一切れ分くらいが、ぽっかりと空いている。
「これだけの広さがあれば、なんでもできそうだけど」
「はい、それでよけい決めかねてしまいまして。よろしかったら、ご主人様が決めていただけませんか」
「俺が?」
* * *
「熱帯の果実がいいと思うんです。グアバとか、マンゴーとか」
サニーとスノーフェザーの声がきれいに揃った。
「傷むのが早くて、どうしても長距離輸送がむずかしいので。新鮮なものを司令官様にも食べていただきたいです!」
引き受けたはいいが、農業についてはまるで素人の俺にはアイデアも指針も何もない。そこでオルカの皆に「何か栽培したいものはないか」と募集してみたところ、予想以上の反響があった。
毎日のように誰かしらが俺のところへやってきては要望書を置いていく。もちろん、実際にそれが作れるかどうかは確認しないとわからないが、希望が多いのは大変いいことだ。
「ドリアード、どうだ?」
アドバイザーとして来てもらっているドリアードに聞いてみると、微妙な顔で首をかしげた。
「素敵だと思いますが、他の果樹と同じ空間で育てることを考えると、気温の調整がすこし難しいかもしれません」
「うーん……」俺は腕を組んだ。「魅力的だけど、保留で」
「ホップです。ホップしかありません」
〈I ♡BEER〉と大書したプラカードをかかげたキルケーがデスクごしに身を乗り出してきた。
「今は主に乾燥ペレットを使っていますが、やっぱり鮮度が違うのです。私どものような小規模ブリュワーは量産性に劣る分、材料の品質や鮮度で勝負したいのでして」
「ブリュワー?」
きみ占い師じゃなかったっけ。という突っ込みをする隙も与えずキルケーは矛先を変える。
「だいたいドリアードさん! あなたビール造りの名人だそうじゃないですか! どうしてもっと早く言ってくれなかったんですか!」
「そ、そう言われましても」
「教えてください! 飲ませてください! そして力を合わせてオルカブリュワリーを」
「落ち着けキルケー。ちょっとサディアスかソニア呼んで」
「余分な畑があるのなら何をおいても麦を増産すべきです! 米か芋でも構いません!」
キルケーが連行されていったのと入れ替わりに入ってきたシャーロットは、大きな胸をぶるんと揺らして力強く言い切った。
「いやまあ、確かに主食は大事だけど」
「飢えは最大の敵! 古来より、食べるもののなくなった軍隊ほど悲惨なものはありません。ぜいたく品など作る前に、まずカロリーの確保です!」
「現状、食糧自体は十分ありますし……」
「リストを拝見しましたがジャガイモが三種類しかないじゃありませんか!」ばんばん、とデスクを叩くシャーロット。よく見たらちょっと涙目だ。「アウグスブルガー! フォントネー! メザメ・オブ・インカ! おいしいおイモはまだまだいっぱい」
「外部拠点に頼んで、いろいろ作ってもらうようにするから」
「よかったらなんですけど、鶏を飼えませんか?」
アウローラはおずおずと切り出した。「やっぱりまだまだ新鮮な鶏卵は貴重で……供給が増えれば、カフェのスイーツなんかもぐっとお手頃になるんですけど……」
「それは嬉しいが……動物って、どうなんだ?」
「難しいです」ドリアードは無情に即答する。「管理が格段に大変になってしまいます」
「そうですかあ……」
しょんぼりと肩を落としたアウローラを見かねて、俺は言ってみた。「暖房のきいた寝床を用意すれば、地上でも飼えるんじゃないか? 確か、レアが地上にも菜園を作るとか言ってただろ」
「その菜園が荒らされるからって、ダメ出しされたんです……」
「柵をきちんとすれば大丈夫です。私からもお姉様にお願いしてみましょう。アウローラさんのスイーツ、私も楽しみですので……」
「動力施設にしよう」
サディアスは入ってくるなり言った。「最近規律が乱れすぎている。懲罰装置が必要だ」
ちなみにキルケーはあの後農園に忍び込もうとして、シティガードに捕まったらしい。今は禁酒刑に処されている。
「懲罰装置? 動力施設ってのは?」
「その両方だ。大型の人力発電機を据えつけて規則違反者に回させる」
「いやいやいや」
「賛同者の署名も集めたぞ。倉庫管理担当アンドバリに、調理班長ソワンに、ホードの衛生兵ケシクに」
「いやいやいやいや」
たしかに皆規則違反に悩まされていそうな面々ではあるが、せっかくの農園にそんな発電所だか超人墓場だかわからないものを作るわけにはいかない。サディアスに突きつけられた署名用紙を、俺は丁重に押し返した。
「うーん……」
プランを並べたホワイトボードを前に、俺はうなっていた。どれも悪くない(発電機以外)が、どれも決め手に欠ける。
みんなの意見を聞くうち、俺の中にも漠然と、何を作るべきかのビジョンが見えてはきている。必需品ではないが、あると嬉しいもの。できるだけ多くの人に行きわたるもの。鮮度が大事で、できれば日持ちもするもの。オルカの皆や、外部拠点の隊員たちにも喜んでもらえるもの……。
条件は固まってきたが、さてそれに当てはまるものは何かというと、さっぱり浮かばない。そんな都合のいい農作物があるだろうか。
朝から首をひねり続けて、ちょっと痛くなってきた。そんな俺を見かねてか、
「ご主人様、休憩になさいませんか」
コンスタンツァが銀のお盆を差し出してくれた。お盆には熱い紅茶と、湯気の立つスコーンが載っている。
俺は目を見開いて叫んだ。
「それだ!!」
* * *
〈夏もちかづく八十八夜 野にも山にも若葉がしげる……〉
スピーカーからリズミカルで軽快な歌を流しながら、ドローン達が一列になって進む。あざやかな黄緑色の茂みがどこまでもまっすぐに続き、密生した葉の一枚一枚に、霧のように水が降りそそいでいく。
「お茶かあ。なるほどね」また案内役をつとめてくれたジェーンが感心したように言って、俺は得意げにうなずいた。
お茶なら少量でもみんなで飲んで楽しめる。製茶まで済ませてしまえば保存もきくし、かさばらず重くない。お土産にもぴったりだ。
「素晴らしいアイデアです。さすがです、ご主人様」
「ふふふふふ」
ドリアードも褒めてくれて俺はますます得意になる。
「ところで、ドローンが流してるあの歌は何?」
「ゼロさんに教わった、お茶の栽培をするときの伝統歌だそうです」
本当ならお茶の木というのは苗から育てても四、五年かかるらしいのだが、そこはセレスティアの力を借りて早送りさせてもらった。アクアランドのオープン期間中に、オルカ製茶の第一弾が出来上がってくる予定だ。ちなみにこの間まで知らなかったが、お茶というのは紅茶も緑茶もウーロン茶も、ぜんぶ同じ葉から作れるらしい。
「遠くからわざわざ来てくれた隊員たちに、お土産として渡せたらいいよな」
「なあに、まだそれ気にしてたの?」ジェーンが笑った。「言っとくけど、オルカは別に輸入超過ってわけじゃないのよ。お土産品ならもう一杯あるんだから」
「えっ?」それは初耳だ。「いやでも、何を?」
ジェーンはニヤニヤ笑って、タブレットを差し出した。動画ファイルと画像ファイルがびっしりと並んでいる。「司令官/8月10日」「司令官/9月28日」「司令官/ボイス_No559」「司令官/生歌02」……
「これは……」
「司令官ポスターとか、マグカップとか、シーツもあるわ。あとは何といっても生写真が大人気。正真正銘、オルカでしか撮れない特産品ね」
「…………」
俺のこれまでの試行錯誤は一体……いやそれより、いつの間にこんなものが……。
「そういえばドリアード、例のキルケーを弟子にしたんだって?」
「熱意に負けまして……」
「ビールのレベルが断然上がったらしいわよ、ね、司令官、今夜みんなでバーに行かない?」
「そうだな……」
ジェーンに肩を叩かれて、俺は力なくうなずいた。実際、飲まないとやってられない気分だ。
「オルカ製のお茶、皆さん本当に喜ぶと思いますよ、ご主人様」
「うん……ありがとう……」
「でもあんたも持ってたでしょ、生写真」
「ジェーンさん!」
とぼとぼと家路につく俺のうしろで、ドローン達は軽快な歌を流しながら、ゆっくりと茶畑に水を撒いていた。
〈摘めよ摘め摘め 摘まねばならぬ 摘まにゃオルカの茶にならぬ……〉
End
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ