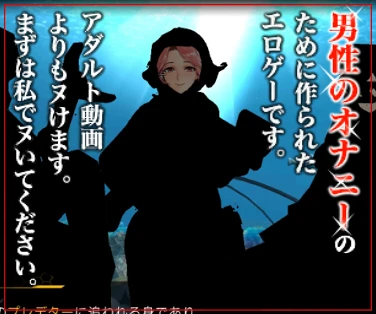おいしそうな匂いがただよってきたのに惹かれてフラフラと厨房へ入ると、そこには魔王がいた。
「あ……モモ…さん。どうも……」
床まで届くほど長いバサバサの(と見えるよう慎重に髪質をととのえた)髪。ゆたかに起伏する白い肢体を申しわけ程度に覆う、きわどい黒の戦闘コスチューム。
攻めた出で立ちに似合わぬ気弱げな笑顔で、大魔王ポックルはぺこりと会釈すると、抱えた皿ごと厨房のすみのテーブルの、さらにすみっこへそそくさと移動した。
「あー、夜のつまみ食いですか? 女優なのに、いーけないんだー」
おいしそうな匂いはその皿からしている。厨房の無断使用を咎められると思っていたのだろう。モモがにっと笑ってみせると、怯えをふくんだ表情がふっと緩んだ。
「い、今はもう公演とかないからいいんです。ちょっとお腹がすいて……あの、よかったら、一緒にどう…ですか?」
「えへへ、ぜひぜひです」
耐熱ガラス皿の中には黄金色の、少し焦げ目のついた、ふわふわした何か。大きなスプーンですくって口に入れると、モモの顔がぱっと輝いた。
「おいしーい! これ、ツナ缶?」
「はい。えっと……ツナ缶に、マヨネーズと玉ねぎを混ぜて、オーブンで焼いたんです」
焼けたマヨネーズの香ばしい油と酸味、ツナの肉汁、刻んだ玉ねぎの歯ごたえが、噛むたび口の中いっぱいに広がる。気がつくとモモは二匙目を口に運んでいた。
「んんー、罪の味……でもお料理できるんですね、ポックルさん。すごい」
「お料理っていうほどのものじゃないけど、これだけ知ってるんです……昔どこかで、誰かに教わったのを覚えてて」
「昔って、ソワンさんとかに?」
「いえその、もっとずっと昔に……あの、前の私が。アップデートの時に混ざって……そういうこと、ありません?」
「あ、あーあーあー…。ありますね」
バイオロイドが製造過程でプリインストールされる一般常識や基本的知識のデータセットは、定期的にアップデートされる。その更新用データは、すでに稼働している同型機の経験データをもとに作られることが多い。データ形式の親和性などからいって、それが一番効率がいいからだ。
もちろん雑多な個的経験などは除去され、精製されたコア情報だけが使われるわけだが、ごく稀に何かのはずみで特定の個体の記憶の断片が消えずにまぎれ込むことがある。そうしたものは、いわばある世代以降の同型機全員に共通の、おぼろげな思い出のようなものになる。
「白兎ちゃんとは最近どうですか? うまくやれてます?」
「はい!」ぱっとポックルの顔が明るくなる。「この間、二人でショッピングモール跡までお散歩したんですよ。マジカルピンクムーンライトを飾りつけたいからって、小物を探しに」
「あー、それはいいことですね。白兎ちゃん、あんなに可愛いのに服のセンスとかひどいですからね……」
「ドクターさんとスカディーさんが、記憶は残したまま現実認識だけを追加インストールする方法を探してくれてるんですけど、やっぱり難しいみたいで。でも、もう今のままの白兎でもいいかなって思ってます」
少し困ったように、ほんわかと笑ってみせるポックル。大魔王という恐ろしげな肩書きとは裏腹に、彼女にはこういう表情が本当によく似合う。争いを好まない、おとなしい人なのだ。
伝説サイエンスのバイオロイドの中でも「エンターヴィランズ」シリーズに所属する、いわゆる悪役のバイオロイドは、演じる役柄と素の自分自身とがはっきり分かれた子が多い。まあ邪悪な大魔王やら狡猾な枢機卿やらが、実際にその通りの性格だったら舞台にならないだろう。これでいざカメラが回ると、子供が泣き出すほど恐ろしげな魔王を見事に演じきるからすごい。
「でも、配給だけじゃなくて、バイオロイドが自由に使っていい分の食材があるなんて、すごいです。社長はいい方ですね」
「そうでしょーそうでしょー。自慢の司令官様ですよ!」
「ほんとに、オルカは夢みたいな所です。まるで『マジカル英雄大戦まつり』の時みたい……」
「英雄大戦まつり! 懐かしいなー…」
「マジカル英雄大戦まつり」とは、伝説サイエンスで何シーズンかに一度開催される大型イベントだ。イベント専用に用意されたより強大な敵が現れ、ヒロインとヴィランが善悪の垣根を越え手を組む、という展開がお決まりで、お互い殺し合っていた敵と味方の演者達が、この時だけは肩を並べ、共に戦うことができた。
いま、司令官の下にすべてのバイオロイドが一丸となって、世界を取り戻すために戦っている。そこには脚本の都合も、視聴率もない。本当は憎くもなんともないのに、誰かのために殺さなくてはいけない敵もいない。
戦い自体は過酷だ。だけどそれはどれだけ幸せな、満ち足りた戦いであることか。その幸せを本当の意味で味わえるのは自分たち伝説製のバイオロイドだけかもしれないと、モモは時々そんなふうに思うことがある。
焼きツナマヨを頬張りながら、うっすら涙さえにじませているポックルを見れば、彼女も同じように感じているのだろうと思えた。
「モモ、一度ポックルさんとこうしてゆっくりお話してみたかったんですよ」
「そ、そうなんですか、ありがとう」ポックルは照れたように髪をなでる。「でも、どうして?」
「どうしてでしょうね? モモも昔、どこかのモモがそんな風に思った記憶が残ってるのかも」
鉄虫が世界を侵食し始めてからは、伝説サイエンスも興行どころではなくなり、アリーナは幕を下ろした。モモやポックル、シャーロットなど主演級の役者達は、その戦闘能力を買われて鉄虫との戦争に動員され、軍事用バイオロイドにも劣らぬ活躍を見せたという。
もしかして、とモモは思う。滅びゆく世界で鉄虫と戦っていたモモやポックル達も、アリーナでお互いに殺し合っていた時よりは幸福だったのかもしれない。何の慰めにもならないけれど。
「あらあら、香ばしい匂いがするから何かと思えば、同僚のつまみ食いを見つけてしまいました」
「ぎゃっ、アルマンさん!」
「ぎゃっとは何ですか、品のない」
「アルマンさんもどうですか? ポックルさん秘伝のお夜食メニューですよー」
「こんな時間に、そんなカロリーの高いものを……」
言いながらもすすすと入ってくる赤いドレスのバイオロイドを、モモは朗らかに笑って迎える。
マジカルモモはいつだって人々の夢を背負って戦ってきた。だが背負う夢がこれほど優しく、気高く、暖かかったことはかつてなかった。
この夢があるかぎり、この仲間達がいるかぎり、モモはどこまでも戦える。そんな確信があった。
End
「……それでね、アルマンさんがこれはトーストに合いそうですねって言った、まさにそのタイミングでちょうど社長がトーストを持って厨房に入ってきたの! もう、みんな大喜び! モモさんなんか目をハートにして、『惚れなおすってこういうことなんですね』とか言っちゃってね」
「焼きツナマヨというの、そんなに美味しいのか? 今度、私にも作ってくれ」
オルカの一室。大きなテーブルにお茶と、松餅と、分解されたチェーンソーの部品を広げて、ポックル大魔王と魔法少女マジカル白兎は話に花を咲かせていた。
先日のクリスマスパーティの際発見されたショッピングモール跡に、豊富なアクセサリショップがあるという報告があった。それを聞きつけた白兎が、愛用の武器マジカルピンクムーンライトを可愛く飾りつけたいと言い出し、そこはかとない不安を感じたポックルが同行を申し出たのが数日前。首尾よく様々なデコパーツを仕入れてきたものの、白兎が、
「長年使ってくたびれてきたし、せっかくだから飾り付ける前に久々に分解してちゃんとオーバーホールをしてやりたい」
というので、なりゆきでこうしてお茶会がてら付き合っている。
超電磁モーターのシャフトの歪みを点検するポックルの横で、チェーンソーのブレードを一枚一枚ていねいに目立てしていた白兎が、さもいいアイデアが閃いたという風にパッと顔を上げた。
「なあ、このブレードに一つ一つ、うさぎの顔をデコるのはどうだろう? こう、ここのところに顔を置いて、ブレードがうさぎの前歯に見えるようにするんだ」
「あー、えっと……ブ、ブレードは高速で回転するんだから、見えないんじゃないかな。それに、斬った時に壊れちゃったらもったいないよ」
「む、そうか……」
手伝っている目的の半分は、白兎のデコレーションがあらぬ方へ暴走するのを止めるためだ。
何しろ白兎の美的センスときたら、婉曲に言って非常に個性的な代物だ。共にオルカに合流してしばらくした頃、パンツ一枚に赤いフード付きケープという壮絶な出で立ちを「よりウサギの特徴を取り入れてみた」と得意満面で着てきた白兎を見て、ポックルはこの子は放っておいては駄目だと確信した。
かつての世界でも、今の世界でも、それなりに長い付き合いになるが、白兎にこんな一面があるとはついぞ知らなかった。あのありとあらゆる部分が足りていないマジカルポックルの衣装すら、彼女は曇りなき笑顔で「似合っている」と言い切ったのだ(まあ社長には「ある意味大いにアリ」と言ってもらえたので、あれはあれで気に入ってはいるのだが)。
「ジェントルマンは赤と紫のジュエル、どっちが好きかな?」
「うーん、どっちが好きっていうことはないと思うけど、白兎の衣装は紫だから、合わせた方がいいんじゃ?」
「なるほど、そうしよう」
白兎の面倒を見ることは、ポックル自身のリハビリにも役立っている。何度もポックルの命を奪いかけ、一時は見るだけで身がすくんでいたこのマジカルピンクムーンライトにも、こうして抵抗なく触れるようになった。
「そういえばこの間、女神アタランテに会った。あの方もジェントルマンに従っていたんだな」ヤスリを細かく動かしながら、白兎がふと言った。
「え? あ、うん、そうそう」
「銃士シャーロットも、プレスターヨアンナもいる。それどころか、鋼の守護者ランパリオンまで! 異なる世界を繋ぐゲートが開いたに違いない。マジカル英雄大戦で倒したはずの異次元魔神がまた現れたんだろうか。ポックルはどう思う?」
「あーいえ、えっと、そういうわけじゃないけど……でも、同じくらい恐ろしい、正体不明の敵が鉄虫の背後にいる、みたい?」
「そうだな……これだけの魔法少女と勇者が揃って、まだ悪を滅ぼせずにいるなんて信じられない。きっと、恐ろしく絶望的な戦いなのだろうな」
「うん……」
白兎は自分だけでなく、伝説の他のバイオロイド達の演目についても、劇ではなく本物だと信じている。アルマン枢機卿とばったり出くわした時は肝を冷やしたが、幸い彼女は空気を読んでアドリブで話を合わせることにかけては伝説でも指折りの名手なので、「ジェントルマンの人柄に触れて改心した」ということにして事なきを得た。
しかし現実認識が不完全でも、今の世界がどのような有様で、オルカがいかに困難な戦いをしているかということは、彼女も鋭敏に感じ取っている。もともと、勘の悪い子ではないのだ。そして、いかに絶望的な戦いであろうとも、それで心が折れるような子でもない。
モモは言っていた。伝説のバイオロイドにとって、この戦いは過酷ではあっても満ち足りた戦いだと。この戦いなら、自分たちはどこまでも胸を張って戦えると。
とうてい勝てないような敵。奇跡が起きなければつかめないような勝利。モモや白兎たちは何度失敗しても決して諦めず、そこへ手を伸ばし続けた。そうして数知れぬ犠牲の果てに、最後には必ずつかみ取ってきた。ポックルはそのことを誰よりも身にしみて知っている。
彼女たちは正義の意味を知っている。希望を捨てないことが、自分たちが正しいと心から信じられることが、人をどれだけ強くするか知っている。それが魔法少女だ。それが正義の味方だ。
ただの役者に過ぎない自分たちが、この果てない戦いに参加した意味がもしもあるのなら、それはそういう所なのかもしれないと、ポックルも時々考えるようになった。
「よし! 終わった」
白兎が満足げな声とともにヤスリを置いた。チェーンに植え込まれた数百本のブレードが、一つ残らずピカピカに光っている。やっぱりちょっと怖い。
「ありがとう、ポックル。組み立ては自分でやるから、一休みしてくれ」
「うん」お言葉に甘えてポックルはフィルターを掃除していたブラシを置き、手を拭いて松餅をつまむ。「これからもがんばろうね、白兎」
「もちろんだ。これでいっそうジェントルマンの力になれる」
鼻息荒く組み立てにかかる白兎。それを見守るポックルの笑顔は柔らかかった。
「ところでポックル、この前、夜にマジカルポックルに変身して歩いていたのは何だったんだ? ジェントルマンに呼ばれない限り立ち入り禁止とかいうエリアにいたな」
「えっ!? いや…それは…あの…えーっと……白兎も、そのうちわかるよ」
「?」
End
「レプリコン2136より本隊。第8分隊は予定地点に到達。重傷1名、軽傷3名。戦闘続行は可能」
「ノーム803より本隊。鉄虫残党は予定ルートよりやや北寄りを逃走中。追撃の可否を求む」
次々に入ってくる報告を聞きながら、脳内に描き出された戦場マップにそのつど調整を加える。指揮官級バイオロイドの卓越した演算能力が、現実とほとんど変わらない精度で戦況を予測し、取れる選択肢に応じたあるべき未来を絞り込んでいく。選択肢が10個ほどまで減った時点で、不屈のマリーはその中の一つを選び出し……0.04秒後、それを捨ててまた別の一つを選んで、それを最終決定とした。
「深追いはするな。第8分隊はまもなく合流する増援の到着を待って再編成、逃走する鉄虫がエリアから離脱するまで監視。負傷者は帰還させよ。離脱の確認をもって戦況終了とする」
一呼吸おいて、通信モジュールへもう一言。
「我々の勝利だ」
わっという歓声が通信回線を満たす。鉄虫がエリアから完全に去るまで気を抜かないよう第8分隊に釘を刺してから、マリー自身も集中のモードを一段階下げる。残敵の確認と警戒に抜かりなく目を配る傍ら、精神の片隅で今日の戦闘の総括と内省をはじめる。
と、後ろから肩をたたかれた。
「お疲れ様、というやつだな」
すらりとした長身に栗色の髪をなびかせる、美しくも剽悍なバイオロイドが、代用コーヒーの入った紙コップをマリーの方に差し出していた。
「我々は一足先に帰投する。構わないな」
「ああ、後片付けはこちらでやる。……わざわざ挨拶に寄るとは、珍しいな?」
「帰る前にコーヒーを一杯飲みたかったんだ」
彼女――マリーと同じ指揮官級バイオロイド・迅速のカーンは、疲労のにじむ、しかし満足げな笑みをうすく浮かべて、紙コップの中身を一息にあおった。
カーン率いるアンガー・オブ・ホードは、マリー達の到着に先立って鉄虫の攪乱と足止めに昨晩から奮戦していた。人一倍タフな彼女が疲労を見せているということは、その部下達はヘトヘトに疲れ切っていることだろう。
「トレーラーを一台回すから使うがいい。ついでに負傷兵を連れ帰ってくれると助かる」
「そうさせてもらおう。……負傷兵か。ふふ」
「何か?」マリーも熱いコーヒーをすする。簡易野戦指揮キットにコーヒーメーカーを必備させたのは、彼女のささやかな贅沢だ。
「いや。我々は死ななくなったな、と考えていた」
「!」
マリーはコップから唇を離してカーンの方を見た。それは肩を叩かれる直前まで、まさに彼女自身が考えていたことだったからだ。
司令官を戴いてからというもの、鉄虫との戦いは連戦連勝だ。単純に戦闘命令を発してもらえるという利便性と、人間の主を得て士気が上がっているという精神的なメリットもあるが、それ以上に彼は確かな指揮能力を持っている。彼が戦略レベルで全体を統率してくれるおかげで、マリーやカーンら指揮官級ユニットは前線指揮に専念でき、そのことがまた戦闘効率を高めている。劇的に、という言葉でもまだ足りないくらいに、戦いは様変わりした。
それ自体は大いに喜ぶべきことだ。ただ一人生き残った人類が彼のような男性であったという僥倖には感謝しかない。しかしマリーは彼の指揮下で戦う時、未だにわずかな戸惑いと違和感を拭いきれずにいた。
「閣下は兵士の死を好まない。あと一手、一割の損耗を覚悟すれば完全な勝利を手にできるという時、閣下は決して駒を進めない」
「不満か?」
「不満ではない。ただ……慣れない」
かつてマリーが戦っていた世界では、それはほとんどありうべからざる思考だった。マリーが仕えていた人間の将校達は、一割どころか五割、十割の損耗さえ勝利のためなら平然と許容したものだ。バイオロイドとはそういうもので(加えて言うならブラウニーもそういう奴だった)、マリーはそれを当然の前提として経験を積み、戦術を磨いてきた。もちろん彼女自身としては部下を死なせたくないと願っていたが、その願いは主人の命令と天秤にかけられるようなものではなかった。
人類が姿を消し、鉄虫とバイオロイドだけの戦いになってからは、マリーは自分自身の理念に従って兵達を指揮することができた。そのかわり、戦況ははるかに厳しくなり、それまでとは別の意味で、犠牲を前提としない戦いなどはできなくなった。
「私は生み出されて以来ずっと、百年以上もの間、それを当然のこととして戦ってきた。私ほど多くの味方を死なせたバイオロイドは誰もいまい。今になって、突然そうしなくてもいいと言われると……何というか、混乱する。咄嗟の時に対応が遅れることがある。今日も何度か、そういうことがあった」
「それで勝った上に戦死者もいないのだから、立派なものさ」カーンはあっけらかんと笑う。「第一、人間の気まぐれな命令に振り回されることなど慣れっこだろう。特に私やお前はな」
「……閣下のご意志を、気まぐれなどと呼びたくはない」
「なんだ。結局気に入っているんじゃないか」
知らず不機嫌な顔になったマリーを見て、カーンはまた笑った。
実際、司令官をどう思えばいいのか、マリーの中ではいまだに定まりきっていない。それが問題なのだ。
ただ一人の主人であり、優秀な指揮官だ。マリーがどれだけ願っても手が届かなかった理想を実現してくれた人物でもあり、そしてそれだけに、自分がこれまで歩んできた道をすべて否定されてしまったような、そんな気分にさせられる相手でもある。すべてを差し出して仕えたくもある。すべてをぶちまけて怒鳴りたくもある。
「閣下はまるで……そう、まるで、我々の命が人命と同じであると考えているように見える」
そんなはずはないのに。自分に言い聞かせるようにマリーは言って、最後のコーヒーを飲み干した。
「ま、あまり考えすぎるな」
カーンは空になった紙コップを放り投げた。それは正確な放物線を描いて、ディスポーザーに吸い込まれていく。難しいことではない。初歩的な弾道プログラムを入れているバイオロイドなら誰でもできる。
「代用コーヒーの味も随分よくなった。物事は良い方に変わることもあるものさ」
「……そうだな」
苦笑して手を振ると、カーンは長身をひらりと翻して去っていった。マリーはその背中を見送ると、通信回線に意識を戻す。その眼差しからはもう、迷いや悩みはきれいにぬぐい去られていた。
マリーが司令官に抱く感情がはっきりと定まるのはもう少し先のこと。
生体再建ポッドに入った司令官が、華奢ながら引き締まった肢体をもつ十代前半の少年の姿で出てきた時であった。
End
キルケー? キルケー、起きてるか?
まだ戻ってこれないか……そんなに枕を噛んだままでは破けてしまうぞ。
尻の力も少し抜け。ほら、ちょっとくらい漏らしても構わないから。
少しやり過ぎたかな。ラビアタやアリスだったらもう二セットか三セットでようやく失神なんだが、ちょっとオルカ基準に慣れすぎて感覚がズレてきてるかもしれないな。
夢うつつでも構わないから、聞いてくれ。
ハロウィンパークの件だが……アルマンの懸念は、間違いではない。
今回ほど、記憶がなくてよかったと思ったことはないよ。
俺が旧人類の悪性と、少なくともその一部と無縁でいられるのは、単に「そういうものに触れた経験がないから」という、幸運の結果にすぎない。決して、俺が旧人類よりも善い人間だからじゃない。
俺がかつての時代に生きて、その常識の中で暮らしていたら、他の連中と同じようなことをしていたかもしれん。逆にそういう連中だって、今の俺のような状況に置かれれば、自分たちがどれほど異常で残酷なことをしていたか、誰だって気づいて目が覚めるのかもしれん。
つまりな、何が言いたいかというと……俺をあまり、持ち上げないでくれ。それと、旧人類を、あまり嫌わないでやってほしいんだよ。
「……私は、かつてのお客様方を嫌ってなどいませんよ?」
起きてたの!?
「それに、司令官様が敬うに値しない方だとも思っていません。たとえどんな時代に生まれていようと、あなたは優しい心と、強い意志を持つお方だったはずです……」
キルケー……
「もちろん、たくましいコレも……」
キルケー?
「……悲しい思いも沢山しましたが、それは私の背負った役目。誰かを恨む気持ちなどありません。今こうしていられるのですから、私は幸せです。
ですから…………私を何度もいじめたコレで、私をもっともっと、幸せにしてくださいね? 司令官様?」
…………任せておけ。
ここからはノンストップで行くからな。今のうちに水分補給を忘れるなよ。
「これならどうかな。フォーチュンお姉ちゃん、信号いった?」
「うん、うん、……うーん、駄目ね。さっきまでと変わらないわ」
昼下がりのオルカ艦橋。司令官が珍しく午睡をとっている隙をついて、ドクターとフォーチュンの二人はブリッジ中央にある艦長のコンソールをバラバラに分解し、いじくり回していた。
目的は指揮通信システムの改良である。
司令官が分隊を直接指揮する時に使っている通信装置は、かつての世界で強化人間がバイオロイド部隊を指揮する時に使われていた脳量子通信デバイスをフォーチュンが改造したものだ。
分隊全員の視覚・聴覚・体感覚情報を統合・抽象化して人間側の感覚野に直接投影し、まるで自分自身が低空から戦場を俯瞰しているような感覚で指揮を出すことができる。距離や遮蔽物の影響をほぼ受けず、理論上傍受やハッキングも不可能という優れものだが、一つだけ重大な欠点がある。人間の脳波とバイオロイドの脳波を強引にハーモナイズする副作用として、同型機のバイオロイドを区別できないのだ。
たとえばブラウニー五人からなる分隊を指揮しようとすると、全員に同一のコマンドしか送れない。それだけならまだしも、五人分の知覚情報が一人分のそれとしてフィードバックされてくるため、人間側の脳に深刻な見当識障害が発生する。司令官が実際に試してみた結果、一分もしないうちにげえげえ吐いてぶっ倒れる羽目になり、以後司令官が直接指揮する分隊は一体ずつ異なるタイプで編成する、というのが鉄則になった。
「ちょっと、まだなの? 司令官そろそろ起きてくるわよ」
「どうだ、目処は立ちそうか」
二人がうんうん唸っている艦橋へ、さらにもう二人のバイオロイドが入ってきた。一人は小柄な体躯に燃えるような赤毛、もう一人はそれと対照的にすらりとした長身と氷のようなプラチナブロンド。ドゥームブリンガーを率いる滅亡のメイと、シスターズ・オブ・ヴァルハラを率いる鉄血のレオナだ。
オルカの空陸の柱と言っていい大部隊を束ねる二人にとって、司令官直轄分隊の編成制限はことに深刻な問題である。マリーとも連名で、以前から技術部には何度も改善要請が出されていた。
「爆撃は面でするものよ。ジニヤーみたいなのが一人でヒラヒラ飛び回ってたって何にもならないじゃない。このままじゃ、いつまでたっても私達の真価を発揮できないわ」
「そう無闇に急かすものではない。とはいえ、一斉投入してこそ意味のある戦力というものはある。現状では周辺の支援部隊として運用しているが、やはり即応力と殲滅力が段違いだ。解決できるものなら早急に解決したい」
ニュアンスこそ違え、早く早くと急かしてくる指揮官級二人にげんなりするドクター。だいたい昔から軍人という連中は、技術者の苦労などわかっちゃいないのだ。フォーチュンも大きな胸に手を置いてため息をついている。
「お姉さんだって万能じゃないのよ~。司令官の安全にも配慮しないとだし、あまり急いでもいい結果は出ないわ」
「まあ一応、原因は大体わかったし、改造プランがないこともないんだけどね」
「解決法ができてるの!? 早く言いなさいよ!」メイが気色ばむ。
「できてはいるんだけど、こっちはこっちで別の副作用があるんだよ。しかも、バイオロイド側に影響が出るやつ」
「多少の副作用など我慢してもいい。具体的には何が?」
レオナも距離を詰めてくる。二組の巨乳が眼前に迫ってきて、ドクターは半歩引いた。関係ないがブラックリバーの指揮官級バイオロイドはなぜみんな揃ってコートを肩に羽織っているのだろうか。
「つまりねえ」ドクターは陽電子スパナの柄で頭をコリコリかく。「問題は五人のバイオロイドと一人の人間が、一様にハーモナイズしてることなんだよ」
二人ともピンときていないようなので続ける。「だから、これまでみたいに五機いっぺんにじゃなく、隊長機を軸にして、他の四機を枝につなげる形で接続すればたぶん大丈夫だと思うんだけど」
「そんな単純なことでいいの?」メイが目を丸くする。「なら、すぐにでもやりなさいよ。副作用ってのは何なのよ?」
「うん、隊長機は今より深くお兄ちゃんと繋がることになるから、思考内容も伝わっちゃう可能性が高いんだよね」
「思考内容?」けげんな顔をするレオナ。
「全部じゃないんだけど、とっさに浮かんだ考えとかね。特にお兄ちゃん自身にかかわる思考、たとえばお兄ちゃんをどう思ってるかとか、お兄ちゃんにどうしてほしいかとか、そういうのは全部筒抜けになっちゃうはず」
「「え゙」」
メイとレオナの表情が固まった。数秒間の静寂の後、目だけを動かしてお互いを見交わす。何かはわからないが、その瞬間に雄弁な情報交換がなされたのは、ドクターにも感じとれた。
「まあ、今のところはそれだけだから、あとは何度か試験プログラムを走らせて安全性を確かめたうえで、お兄ちゃんにも協力してもらえば……」
「わかったわ確かにそれは見過ごせない副作用のようね」メイが妙に早口でドクターの言葉を遮った。「別の方法を引き続き検討してちょうだい。別の方法を」
「急がなくてもいい。ことは司令官の身にもかかわることだ。時間がかかっても構わないから、慎重の上にも慎重にな」
レオナもなぜか微妙に目を泳がせながら早口で言う。
そうして二人はなぜか少し顔を赤らめて、そそくさと艦橋から出て行った。
「……どうしたんだろ、二人とも? あんなに急かしてたのに」
「さあ、どうしたのかしらね」
困ったように笑っているフォーチュン。ドクターはひたすら首をかしげるばかりだった。
その後なぜか、ブラックリバー組からの通信システム改善要求はぴたりと止んだ。ドクターとフォーチュンは引き続き、暇なときに通信システムをいじっているが、決定的な打開策は見つかっていない。
司令官は今日も、同じ型のバイオロイドは一機ずつだけという厳格なルールの下に編成された部隊を指揮して、鉄虫たちを駆逐している。
End
サイクロプスプリンセスの朝は早い。
背中をつつむ眷属の体温と、おなかをしっかりと抱き留めてくれているたくましい腕の感触。その二つを確かめて、プリンセスは今日も幸せな気分で目を覚ます。
「ふあーあ……おはよう、LRL」
眷属がいつまでたってもプリンセスの真名を覚えないのが不満だが、闇を統べるプリンセスは寛大なのでそれくらいは大目に見ることにしている。
朝ご飯はトーストとオレンジジュースに、たっぷりのツナサラダ。
料理大会以来、料理の腕を振るいたがる必滅者が増えた。鉄虫を駆逐し、安定して農業を始められる土地も増えたおかげで、オルカの食事は味も量もぐんぐんレベルアップしている。ツナ缶はおいしいが、ツナ缶をおいしく料理したものはもっとおいしい。プリンセスは大変満足している。
朝食を終えたら日課の体操をして、それから読書の時間だ。
「その時、闇のドラゴン零式が長き眠りから目覚め、光のバハムートアルティメットと一億年にわたる宿命の決着をつけるべく……」
プリンセス自らが朗読してやっているというのに、ダッチもフェンリルも、アルヴィスまで退屈そうな顔をしている。ハチコに至ってはすやすやと寝息をたてている始末。かつて全世界を暗黒の信徒に変えた、この竜殺マガジンの物語の真価がわからないとは、まったく必滅者の愚かさは度しがたい。
「あら、まだこんな所にいたの、LRL? あなたも今日出撃じゃない。もうすぐブリーフィングルームに集合よ」
「あ、はーい」
今日はお昼に出撃任務が入っているのだった。必滅者らにもようやくこのプリンセスの持つ闇の力のすごさが理解できてきたらしい。仕方ないので力を貸してやることにする。
「右翼、遅れているぞ! 走れ!」
「はい!」
『LRL、ビッグチックにビーム照射! 効果を確認したら続いて後方のチックランチャーに、妨害を切らすな!』
「は、はい!」
「敵部隊後退しつつあり、ですが後方より敵第二陣! LRL、十秒足止めできる?」
「やってみる!」
戦いは怖い。
鉄虫は容赦なく襲ってくるし、いつも優しいコンスタンツァもマリーも、別人のように厳しい顔で指示を飛ばしてくる。通信機から聞こえる眷属の声だって、いつものように優しくはない。はじめは怖くてつらいだけだったが、厳しいのはみんなが自分を一人前の戦力として扱っているからだということがだんだんわかってきて、それからは前よりもっと頑張れるようになった。
「二時の方向より敵増援、スナイパー三機! 近づけさせるな!」
「了解! LRL、私とあんたでやるよ!」
「う、うむ!」
エターナルビームで動きの止まったチックスナイパーにインフェルノミサイルが突き刺さり、それで戦闘は終わった。
「イェイ!」
グリフォンと手のひら同士をパン!と打ち合わせる。
直後、いつも意地悪なあのグリフォンと、まるで友達みたいにハイタッチをしてしまったのがなんだか恥ずかしくて決まり悪い気持ちになったが、ちらっと見てみるとグリフォンも同じように決まり悪そうな顔をしているので、お互い様と思うことにした。
「みんな、お疲れ様。装備預かるから、怪我した人はあっちね」
帰ってくると、補給と整備。今日は戦闘が多かったのと、コンスタンツァが出撃していたので、バトルメイドのお姉ちゃん達が手伝っている。
ラビアタお姉ちゃんの指示で、エターナルビームを出す左目は、とくに念入りにメンテナンスしてもらうことになっている。レーザー検眼鏡でチェックして、専用のナノマシン入り目薬をさして、クリームをすりこんで、保護用パッドを貼った眼帯をつける。
そこまでしなくても大丈夫なのに、とプリンセスは思う。生体ビームユニットはとても頑丈だ。メンテなど一度も受けられず、ツナ缶を一週間おきに一缶ずつと、たまに降る雨水のほかには何も食べるものがない暮らしがずっと続いても、左目がとうとう光らなくなるまでに、20年もかかったのだ。
「だから点検するのですよ。あなたが、二度とそんな暮らしをしなくていいように」
いつもおっかない目つきで睨んでくる(理由はよくわからないけど多分、ここ最近プリンセスが毎晩眷属といっしょに寝ているせいだと思う)アリスが、今だけはふしぎに優しい顔で、再生クリームを目元にすりこんでくれながらそんなことを言った。
メンテを終えると、もう夕方近くになっていた。お昼寝するには遅すぎるし、どうしようかと思っていたら、眷属が声をかけてきた。
「明敏なる司令官閣下、この私に子守をしろと仰るのですか」
「ひぅ……」
黒くて大きな威圧感のあるAGSが、身をかがめるようにプリンセスを見下ろして、さも馬鹿にしたような合成音声を出す。こわい。
このロクというAGSといっしょに夜間哨戒に出るはずのシルフィードが、昼の戦闘で負傷してしまった。幸いロクはバイオロイド一体くらいなら背中に乗せて飛べるので、夜目の利くLRLに代役を頼みたい。という、眷属じきじきの依頼である。
「この子はただの子供じゃない。飛べばわかる」
眷属に自信ありげにそんなことを言われては、断るわけにはいかなかった。
おっかなびっくり出動してから十分後。
「わはー! 速い高いすごーい!!」
ロクの背に乗って夕暮れの空を駆けるプリンセスはすっかり夢中になっていた。
空を飛ぶのなんて、いつだったかグリフォンに無理矢理ぶら下げられた時以来だ。ロクはグリフォンより断然速いし、乗り心地も悪くない。よく見れば黒い翼も、あちこちとがっている恐ろしげな姿も、サイクロプスプリンセスの乗騎としていかにもふさわしいではないか。
「ふはははは、漆黒の翼を使役して闇を駆ける深淵の姫、それこそが余である!」
「意味不明なことを言っていないで、周囲を見張りなさいバイオロイド。私は子供を乗せて飛ぶための安全係数の計算にいつもよりメモリを取られているのです」
「子供じゃない! サイクロプスプリンセス!」
言い返しながらもあたりに鉄虫の気配がないか見回すプリンセス。その視界、水平線近くに、見覚えのある地形と見覚えのある建物が映った。
「……あ」
「どうしましたか、バイオロイド? 鉄虫ですか?」
急に黙ったプリンセスを警戒してロクが速度を落とす。プリンセスが見ている方向に気づくと、
「灯台ですね。確か司令官がおいでになる前、オルカはあの岬の地下にあるドックに長く秘匿されていたとか」
「……うん。あの灯台に、ずっと余はいたの」
そうだった。補給と海流の関係で、あの島の近くを通るのだと、艦内ニュースで数日前に流れていたのを、プリンセスは思い出した。
記憶があふれてくる。灯台守のおじさんのこと。おじさんが動かなくなった時のこと。それからの長い長い月日のこと。
「……あの……あそこに、少し、下りてもらってもいい?」
「何の意味が? 今は戦略的に重要な場所ではないと聞いていますが」
「うん……」
灯台のすぐ裏手に、土が小さく盛り上がった場所があり、傍らに木の板が立ててある。ラビアタに出会った時、人間が死んだ時はこうするのだと教えてくれたのだ。あの時植えた花は、もう枯れてわからなくなってしまったけれど、かわりに草が生い茂り、こんもりとした緑の塚になっていた。
両手を額の前で合わせて、そっと膝をついて頭を下げる。ずっとここにくるのを避けていた。ラビアタの命令で、旧アジトから逃げてこの灯台で待機していた時にも、怖くてここに来ることはできなかった。
「そうか。お前も墓守だったのですね、バイオロイド」
ひざまずくプリンセスのすこし後ろに立っていたロクが、突然そんなことを言った。
「バイオロイド。お前の認識名、『LRL』の意味は何ですか」
「サイ……」真名で呼んでくれと言いかけて、プリンセスは止めた。そういうことを聞かれているのではない気がしたからだ。
「……ロング・レンジ・ライト」
「ほう。お前の名前は、お前の機能の名前なのですね」ロクは言った。「とても美しい。合理的だ」
自分の名前をそんな風にほめられたのは初めてだった。おじさんの眠るこの場所で、そんな風に言ってもらえたのがなんだか嬉しかった。
もしかして、慰めてくれたのかな?とも思ったが、プリンセスにはよくわからなかった。
帰る頃には、すっかり日が落ちて夜になっていた。ロクの背中で、プリンセスは眼帯を外した。あの頃と同じ、いやもっと明るい一条の光が、闇夜を貫いてまっすぐに伸びていった。
夕食はヴァルハラの皆が腕を振るった赤いシチュー(名前は覚えられなかった)と揚げパン。夜間哨戒をがんばったご褒美に、眷属がチョコバーを一本おまけにつけてくれた。お昼は出撃前にレーションをかじっただけだったので、おいしさもひとしおだ。
お腹いっぱいになって、シャワーも歯みがきも終えて、プリンセスは幸せな気分で眠りにつく。もちろん、眷属に背中からぎゅっと抱きしめてもらってだ。
夢を見ることがある。
昨日は誰も来なかったけど、今日も誰も来なかったけれど、あすは、明日こそは誰か来てくれるかもしれない。そう自分に言い聞かせて、もう動かなくなってしまった左目をむりに閉じてベッドに入る夢。
何度も何度も読んですり切れてしまった漫画の本のページを、破かないようにそおっとめくっていたら、ページの継ぎ目に涙をこぼして、ちぎれてしまった夢。
とうとう灯台の扉をノックする誰かが現れて、嬉しくて迎えに飛び出したら、何もかも夢だった夢。
ラビアタに拾われ、レジスタンスに加わったばかりの頃は、そんな夢を見て夜中に目を覚ますことが何度もあった。起きている時にさえ、時々夢がやってくることがあった。そういう時は悲しさと苦しさと安堵がいっぺんに襲ってきて、どうしようもなくなってわんわん泣いた。
21分隊に配属され、仲間ができてからは、夢を見る回数はだんだん減っていった。司令官がやってきてからはますます減り、最近では夜中に飛び起きることもない。一人で寝るのが平気になる日も、もう遠くないだろう。
……実際、そうでなければまずいのだ。アリス以外にも、LRLを見る目が日に日に怖くなっていくお姉ちゃん達は結構いる。はやく眷属の夜の時間を解放してやらないと、彼女達が何をするかわからない。
でもまあ、それはまだ少しだけ先のこと。今夜はまだ、眷属のあたたかくて力強い腕につつんでもらっていればいい。
おなかに回された腕を小さな手でさすりながら、サイクロプスプリンセスは安らかな眠りに落ちていく。
過去ではなく、明日を夢に見ながら。
End
「ククククク……愚かで無力なドラゴンの騎士よ。この六魔星のひとり、〈鮮血のアルマン〉の無限血界の中で死んでいくがいい」
「いいえ、そうはいきません、鮮血の魔星よ! この奏剣オーベルチューレが私の手にあるかぎり、〈虚無〉の力には屈しない!」
シャーロットが手にした剣を力強く振ると、その切っ先から水しぶきのように金色の輝きが飛び散る。
三方をつつむ深紅色のカーテンが真っ二つに切り裂かれ、舞台にさっと光が差し込んで、観客席から歓声が上がった。むふー、と鼻息を吹かんばかりに得意満面のシャーロットを見て、アルマン枢機卿は観客席から見えない方の肩をそっとすくめた。
きっかけは一月ほど前のこと。
「ア゛ル゛マ゛ン゛~~~~!!」
涙と鼻水をズルズル垂らしたシャーロットが、図書室で優雅に読書を楽しんでいたアルマンに抱きついてきたのが始まりだった。
ハロウィンパークの騒動で、人間達がそこでしてきたことと、それによってダッチガールが負った心の傷を知ったシャーロットは深く落ち込んだ。
最近はそこからもようやく立ち直ったと思っていたが、折悪しく今度はどこからかLRLの生い立ちを聞かされたらしい。
見た目は幼い子供の彼女が、実は滅亡前の時代から生きているオルカ最年長組の一人であり、その小さな体に見合わぬ過酷な半生を送ってきたことは、アルマンも聞き知っていた。もちろん気の毒には思うが、あの時代、あの世界には無数にあった悲劇の一つにすぎないとも言える。
「あんな……あんな、たった一人で、孤独に、ずっと……私っ、わたくし、もう……!」
しかし、この馬鹿で放埒で淫乱で、そして子供好きで底抜けに善良な銃士隊長は、そんな風に割り切っては考えられないようだった。
「あの子達に何か、何かしてあげたくて……このままでは私、陛下との夜伽も落ち着いて楽しめません……」
ハンカチで盛大に鼻をかみ、すすり上げながら言うシャーロット。夜伽はさておき、何かしてあげたいという気持ちはわからないでもない。
「とはいえ、ですねえ」アルマンは頬に指を当てて首をかしげる。「ダッチさんもLRLさんも、今は別に不幸せではないと思いますよ? 仲間もいるし、陛下もいらっしゃるし、ご飯もお腹いっぱい食べているし。殊更してあげることと言っても……」
ない頭をうんうん捻っていたシャーロットがぱっと顔を上げて、「お話の読み聞かせとか!」
「モモさんがすでに毎週朗読会をやっていて、大人気ですね。貴方、彼女より上手に読めまして?」
「うう……」
しょんぼりとうなだれるシャーロット。と、そこへ本をかかえた陛下が入ってきた。借り出していた本を返しに来たのだろう。
陛下は人間にしては珍しく、データベースでなく紙の書籍を読むことを好む。アルマンが図書室に常駐するようになったのも、彼がしばしばここを訪れるから、という理由が大きい。
「へい゛が~~~」
そして当たり前のように陛下にも泣きつきにいくシャーロット。あの直截さはちょっと羨ましくもある。
彼女から話を聞いた陛下はしばし考えて、
「劇なんか、どうだ」
「劇、ですか……?」
「本当の演劇だ。案外、やったことがないんじゃないか?」
「!?……」
それは確かに、今のこの身が劇場に立ったことはないが。俳優バイオロイドとして生み出され、数千回におよぶ様々な公演の経験がプリインストールされているこの自分に向かって「本当の演劇をやったことがない」とは何事かと一瞬カッとなったが、すぐに気がついた。陛下が言っているのはそういうことではない。
「それはつまり……」
アルマンの問いかけに、陛下は我が意を得たり、というように深くうなずいた。
方針が決まれば、後は早かった。
LRLの愛読書である竜殺マガジンを借りてきて読み込み、アルマンのライブラリに蓄えてある膨大な脚本データベースからテイストの近い話を探して翻案する。
独特な言葉遣いのセンスに多少戸惑ったが、晦渋な固有名詞の根底にあるいくつかのキーフレーバーを押さえてしまえば、調子を合わせるのはそれほど難しくない。アルマンが相手をしてきた観客の中には、こういう「こじらせた」性格の子供達も結構いたのだ。どうしてもつかめない所は陛下に頼った。
フォーチュンに手伝ってもらって大道具小道具をつくり、スカディーに声をかけてプログラムを組んでもらう。二人とも子供好きなので、協力は二つ返事で得られた。
エキストラには暇そうなグレムリンとウェアウルフを何人か引っ張ってきた。馬鹿だがセリフと振り付けだけは抜群に飲み込みが早いシャーロットは心配ないとして、他の出演者にはそれなりにきちんとした読み合わせと練習が必要だ。並行して演出、照明、音楽のプランも考えなくては。頭の中の、長いこと使っていなかった回路がフル回転する心地よい緊張感をアルマンは味わっていた。
「奏剣よ、我が歌声に乗り、闇の終わりを示せ! ノクテュルヌ・ド・ロワゾオ・ブルー!」
「ぐわあああああ! ま、まさか貴様が……光と闇の血を引く者だったとはな……だが一人では死なん、貴様も……道連れだ……!!」
満身創痍のアルマンがシャーロットに飛びつくと同時に、まがまがしい閃光が走り、舞台が爆炎に包まれる。観客が固唾を呑んで見守る中、青いマントがひらめき、輝く剣を手にシャーロットが炎の中から現れると、パイプ椅子を並べた観客席は力一杯の拍手と歓声で満たされた。
爆炎エフェクトにまぎれてこっそり抜け出し、舞台袖でBGMのボリュームを調整していたアルマンに、舞台を下りたシャーロットが全力で飛びついてきた。
「アルマン! ああ、なんて素晴らしいの。どれだけ斬っても、戦っても、誰も傷つかない。舞台を下りれば皆で笑っていられるなんて! こんな演劇を考え出すなんて、あなたは天才ですわ!」
「私が考えたわけではないのよ、シャーロット。ずっと昔、バイオロイドが生まれるより前の演劇は、こういうものだったの」
頭より大きい肉球二つに激突されてちょっとクラクラしたが、アルマンはどうにか答える。
トレーニングルームの精巧な半実体ホログラフに、シャーロットの剣の腕前と、アルマンが緻密に練り上げた殺陣が加われば、本物の戦いにしか見えない迫力ある戦闘シーンを演出することはたやすい。炎や雷、血しぶきだって自由自在だ。陛下が発案し、アルマンが準備した「本当の演劇」とはすなわち、戦闘まで含めたすべてが演技であるような劇のことだった。
「最前列にいたLRLちゃんとダッチちゃん達を見た? あの笑顔! ああ、私は! ああいう顔が!! 見たかったのですわ!!!」
「ええ、そうね。……本当に、そうね」
テンションが絶頂に達して感極まっているシャーロットほどではないが、アルマンもまた深い驚きと喜びに打たれていた。
演じる楽しみ、舞台に立つ喜びとは、こういうものだったのか。過去に製造されたどのアルマンも知らなかった経験を、今自分はしているのかもしれない。
「さ、行きますわよ」アルマンの手をシャーロットが取った。
「えっ、どこへ?」
「決まっているでしょう、カーテンコールですわ! 私とあなたが並んでカーテンコールを受けるなんて、滅多にないことよ!」
ぐいぐいと舞台へ引っ張られ、戸惑いとうれしさが半々の頭で、アルマンは考えていた。
さて、これだけ人気が出たからには、続編の構想も練らなくては。次はマジカルモモにも協力してもらって、ストーリーにもさらなる展開を……。
かくて、シャーロットの鼻水と思いつきから始まった創作劇「時のドラゴンと歌う剣」第一回公演は大成功に終わった。
大人気を受けて本作はシリーズ化し、やがて伝説組全員とそれ以外の相当数の面々を巻き込んだ一大ロングランとなる。それにライバル心を燃やしたモモも新しい魔法少女シリーズを立ち上げ、さらに助っ人として参加するうちに演じる楽しさに目覚めた他企業組による第三勢力も勃興してきて、オルカ演劇界は戦国時代を迎えるのだが、それはもう少し先の話である。
End
自分と同じ顔が血まみれになってくるくる回りながら吹っ飛んでくる。
もう何度も見慣れた光景で、今更心は動かない。ブラウニー388は地面に体を投げ出して、爆風と破片と同僚の死体をよけた。
ともかく被害は出た。少々犠牲が大きくなってしまったが、これでやっと他の奴らが動けるようになる。
「作戦開始。撃て!」
388の声で、僚機のブラウニー達が一斉に射撃を開始する。マンモス相手に、しかも足元や兵装しか狙えない制圧射撃でどれほどの効果があるとも思えなかったが、何もしないよりはマシだ。ブラウニー388は僚機達の背中を順に叩いて後ろへ下がり、前線を抜け出すと簡易指揮所へ戻った。
「全分隊交戦開始したッス」
「ご苦労。飲むか」
差し出されたマグカップを左手で受け取るのもずいぶん慣れた。医療物資が慢性的に不足している現状、この右腕の肘から先はもう戻るまい。
「にが」
「新兵はどうだ」
「全然ッス。相変わらずあの赤ん坊ども、何があっても撃たれるまで攻撃しないッスよ。何のためにブラウニーやってんだか」
「今回も進歩なしか……」マリーも代用コーヒーをすすって渋い顔をした。
ラビアタ・プロトタイプの率いるレジスタンスに加わって一番変わったことは、バイオロイド生産設備を使えるようになったことだ。それまで減る一方だった戦力を新たに補充できるようになったのは大きな進歩ではあったが、新しく生まれたバイオロイド達は、鉄虫を積極的に攻撃できないという思いもよらない欠点を抱えていた。
ラビアタによれば、本物の人間を見たことのない彼女達は、鉄虫と人間を区別する基準を持たないのだという。覚醒前の刷り込みの設定を調整したりして試しているものの、今なお解決の兆しは見えない。
「やはり、人間の命令者がいないとどうにもならんのかもしれんな。ラビアタはそちらの捜索にも戦力を割きたいと言っている」
「そんなん見つかるわけないじゃないッスか」388は大げさに鼻を鳴らした。「三安のメイドなんかにでかい顔させることないんスよ。一度隊長からガツンと言ってやらないと」
「そう悪く言うものじゃない。私もお前も、彼女に命を救われた身だろうが」
「そうッスけどね……」
鉄虫の方から攻撃され、何らかの被害が出れば、「危険な人間」と認識して制圧行動に入ることはできる。見敵吶喊がモットーのブラウニータイプとしては不本意なことはなはだしい戦い方だが、それしかできないのだから仕方ない。できるだけ有利な状況で敵の第一撃をさそい、少ない被害で戦闘が始まるよう状況をコントロールするのが、今のブラウニー388の重要な役目だ。
人類がまだいた頃から生き残っている兵士は、スチールラインにもう数えるほどしかいない。レッドフードが真っ先に全滅し、その次にイフリートが消えた。シルキーもノームも、最後の生き残りが何年も前に死んだ。
ブラウニー388が、鉄虫との最初の戦いで死ななかったのは単なる運だった。二度目の戦いも、三度目もそうだった。五度目の戦いからは、どうすれば戦果を上げつつ生き延びられるかを考えて動けるようになった。戦いを重ねるたび、生き延びるのは上手くなっていき、いつしかそのノウハウを仲間に教えられるほどになっていた。だが教えた連中も、それ以外の連中も、皆死んでしまった。
気がつけばスチールラインで388より長く生きているのは、不屈のマリー隊長ただ一人になっていた。彼女が388を副官に任命した時、文句を言う者は誰もいなかった。
副官用のヘッドセットを叩くと、マリーが見ている戦術マップが388の視覚にも投影される。
「これ、第7と18分隊、死ぬッスね」
「ああ」マリーは眉一つ動かさずに言った。「だが彼らの戦いが7分稼いでくれる。その時間で東側を固める」
いつものことだが敵の数は多く、味方の戦力は少ない。おまけにこちらは先制攻撃ができないハンデまでかかえている。戦いがいかに勝つかではなく、誰を犠牲にして何を得るかという残酷な差引勘定の問題になってからもう長い。味方を死地へ追いやりながら飲むコーヒーは苦い。
「砂糖ないッスか。それか紅茶」
「あるわけなかろう」
「ですよねー……隊長、ロイヤルミルクティーって知ってるッスか?」
「名前はな。飲んだことはない」
「美味いんスよ。甘くていい匂いで。昔、トモの何番だったかな、本場イギリスにいたっていう奴が」
388はふいに言葉を止めた。
周囲が静かだ。静かすぎる。
指揮所の周りには直衛隊を配置してある。もし敵がここまで迫ってきたなら彼らが戦闘に入るはずだが、何も物音はしない。考えられる理由は二つ。ただ単に何も起きていないか、あるいは。
視覚のすみに出しっぱなしにしておいた戦術マップで、直衛隊を示すアイコンが一つ、音もなく消えた。
ブラウニーとマリーが飛び退くのと、簡易指揮所の天幕を引き裂いてそいつが降ってくるのがほぼ同時だった。
血管めいた真っ赤な筋の浮いた、生白く波打つ腕。甲殻類の肢のようにせわしなく蠢き続ける副腕。長く伸びた舌のような口棘。「トリックスター」という名が付けられるのはもっと後のことで、この時はマリーもブラウニーも初めて見る連結体だった。
繰り出される長い爪を、サブマシンガンの銃身で受ける。一撃受けただけでへし曲がったマシンガンを放り捨て、二挺目を乱射しながら後ずさる。マリーの操る四基の浮遊砲台が一斉にレーザー狙撃を開始するが、大して効いているように見えない。
こいつはやばい。ブラウニータイプは総じて警戒心や恐怖心をあまり抱かない性格だが、それでも388の頭の中では全力で警鐘が鳴っていた。マンモス、ハーヴェスター、ストーカー、ヤバい鉄虫は色々いるが、こいつはその中でも別格だ。今ここで勝てる相手ではない。
象牙色の爪が、異様になめらかな動きでヌルリと胸元へ迫ってくる。避けられない、と直感的に理解して全身が粟立つ。
「後退だ。部隊を東の崖まで退がらせろ!」
マリーの背中が視界を遮った。
それは一瞬の判断だった。ブラウニーよりは指揮官級の堅牢なボディの方が、攻撃をしのげる可能性は高い。撤退の指揮だけなら388でもできる。
二人とも生き残る可能性が最も高い選択肢を、最も重要な瞬間に間違いなく見極められる指揮官級の演算能力と、どんなに可能性が細くとも躊躇なくそこへ手を伸ばしてしまう不屈のマリーの人格あればこその行動だった。
そして、ブラウニー388はそれを予想していたから、マリーを押しのけて前に出ることができた。
「388!?」
「逆ッス」
ブラウニー388は覚えている。四度目の戦いで、388が生き残ったのは実力ではないし、運でもない。撤退のしんがりを務めた388の小隊が全滅しかけた時、マリー隊長が単身援軍に来てくれたのだ。
あの時も、全員生き延びる可能性はそれが一番高かったのだろう。だが可能性は可能性でしかなく、結果として388達の小隊は生き延び、そして不屈のマリー7号は死んだ。ブラウニー388はそのことを決して忘れない。
だから388は決めていたのだ。次に同じことが起きたら、今度こそは自分が隊長を守って死ぬのだ。その逆になど絶対させないと。
鉄虫のクソ野郎の長い爪が肩をえぐった。問題ない、右はどうせ動かない腕だ。
せまい指揮所の中は自分の手のひらの上のようによく知っている。予備のマシンガンと拳銃が一挺。ブーツに自決用の爆薬。デスクの下にナイフと予備マガジン、コーヒーサーバーの横には大型バッテリーもある。これだけあれば、うまく使えば1分は稼げる。
三撃目で眼をやられて、そのあとのことはよくわからなかった。ただマリーの浮遊砲台が立てるパチパチという電磁音が遠ざかっていくのを聞いて、
(よかった)
と思ったのが、388の最後の思考だった。
「おはようございます、マリー隊長。紅茶ですか? 珍しいですね」
早朝、司令官の朝食の用意でラウンジに来たコンスタンツァは、先客のテーブルにあるティーカップを見て少し驚いた。彼女は根っからのコーヒー党だとばかり思っていたのに。
「ああ、今日はな。そういう日なんだ……前から、そうしたくはあったんだが」
どこか遠くを見るような穏やかな目つきで、しかしそれほどうまくもなさそうに、マリーはカップを傾けている。
「ビスケットでも持ってきましょうか。紅茶に合いますよ」
「いや、いい……あ、待ってくれ。ロイヤルミルクティーというものの淹れ方を知っているか?」
「もちろんです。お飲みになりますか?」
「いや、自分で淹れられるようになりたい。教えてもらえないか」
「喜んで。べつに難しくありませんよ」
みょうに緊張したマリーの面持ちが可笑しくて、コンスタンツァはくすくす笑いながらキッチンへ案内する。
今日がマリーにとってどういう意味を持つのか知る由もないが、少なくとも去年の今日も一昨年の今日も、のんびり紅茶など飲んでいられなかったのは確かだ。優秀なメイドであるコンスタンツァは余計なことを訊かなかった。
「まず、ミルクパンに……」
End
「なるほどな。イギリスではこんな風にして紅茶を飲むのか」
「……ロイヤルミルクティーは日本の飲み方ですよ?」
「そうなのか!?…………あいつも所詮ブラウニーだったか……」
「?」
「ではでは」
「今日も一日」
「「お疲れ様でした~」」
オルカ最下層。動力室と電池室にはさまれた、滅多に人が来ることのない一角の、そのまた片隅の小さな部屋に、小さな小さなバーがある。
薄暗い照明の下、狭いカウンターをはさんで、今夜もグラスを傾ける二人のバイオロイドがいた。
「くはー……! この一杯のために働いてるって感じ……!」
「さささ、おかわりぐーっとぐーっと」
「おっとっとっとー」
司令官にお酒を飲ませてはならない、というコンスタンツァの方針で敷かれたオルカ禁酒令が、「酒の入った司令官もそれはそれで悪くない」というウェアウルフら一部バイオロイドの強い反対によって緩和された。
その日のうちに、オルカ最下層の使われていない小部屋をミニバーに改装したのがキルケー。その夜のうちにバーに居着いたのが、彼女の呑み仲間のコネクターユミである。
「いや実際、今日も私がんばったー。新しい土地に来るたび、出かけてってアンテナ立てて電波拾って……あのチョコレート工場だかなんだかで、司令官様が直接指揮できるのだって私のおかげなんれすよー。そこのところ、わかってんのかなーあの人達いー!」
「大丈夫大丈夫~。みんなユミさんに感謝してますよう」
「ほーんとーかなー」
二杯目のビールをきゅーっと空けて、ぽっと赤くなった目元で幸せそうに息を吐くユミ。一方のキルケーはブランデー(密造品)をストレートでやっている。同じ酒飲み同士でも、酒との付き合い方はそれぞれに違う。
「でもいいのれーす。一日働いて帰ってくると、司令官様が『今日もお疲れ様』って言ってくれるのれす。それだけで明日も頑張れるのれす。ふへへへへ」
ユミの酒は、要するに独り者のサラリーマンが自宅で晩酌するのに近い。一日の疲れを癒やす、自分へのささやかなご褒美であり、飲むのは大抵ビール。味には大してこだわらないし、それほど酒に強いわけでもない。今夜もすでに呂律が怪しくなっている。
「いいなあ~。私なんか戦闘以外でお役に立てることなんてありませんから、出撃班に入ってない時はお客様のお目にとまる機会もなくて」
キルケーは酒豪である。もともと酔客の相手も想定して作られているのに加え、孤独を紛らわすために酒造りに没頭していた時期があり、舌も腕も内臓も一流だ。バーの棚にぎっしり並ぶボトルのいくつかには、彼女自身が丹精こめて作った酒が詰められている。
「キルケーさんはお酒が作れるじゃないれすか。前から言ってるけど、オルカ酒造部作りましょうようー」
「ビールやマッコリくらいは部屋の醸造釜でなんとか作れますけど、他はさすがに艦内ではね~。そのためにオルカを下りるのは本末転倒ですし」
「むうー。ワイン飲みたい。日本酒も飲みたい」
三杯目のビールをちびちび舐めながら、ユミがスツールの下で足を振り回す。
キルケーの自家製コレクションを別とすれば、オルカにある酒類はウイスキーやブランデーなどの度数の強い蒸留酒ばかりである。人類滅亡から百年以上を経て、まだ飲める状態で残っている酒はそういうものしかないからだ。
ごくごく稀に、奇跡的な保存状態が保たれて超ビンテージと化したワインなどが見つかることもあるが、そうした逸品は当然司令官のためにソワンが慎重に保管することになるので、ユミ達の口には入らない。
「でもお客様なら、お願いしたら分けてくれるかもしれませんよ~? 夜のおつとめの時に、こう甘~くおねだりを」
「ういっ」
途端に表情がこわばるユミ。色事の話になると、彼女は学生のようにうぶだ。さすがにはっきりとは訊いていないが、どうもいまだに司令官とベッドを共にしたこともないらしい。
もとからそういう人格設定なのか、長年の孤独な勤務でそんな風になってしまったのかは知らないが、そういう所がみょうに可愛くてキルケーはついからかってしまう。
「わー、わー、私はあれだ、仕事一筋のクールなシティウーマンれすしー? そういうのはコンプライアンス的にどうかなーって。キ、キルケーさんがおねだりすればいいらないれすか! そいで私にもおすそわけしてくらさい」
「私は無理です~。お客様にそういうことはもうしないって決めましたので」
「『もう』?」
「こっちの話です~」
「だいたい何れすかあのスケロプって奴はあー。素早いし固いし保護無視してくるし、日本人ならもうちょっと遠慮ってものをれすね」
「スケロプって日本人なんですか?」
「カブキがあるじゃないれすか、スケロプゆかりの江戸桜って」
「はあ」
愚痴の内容が支離滅裂になり。
「はあ~。お客様、好き……」
「わかるぅ。しゅきー」
「胸板とか本当いいんですよねえ~。シャツの前を開けて、裸の胸にもたれかかってお酒飲みたい……」
「おかえりなさいって言ってほしい……」
のろけが壊れたレコードのごとく同じフレーズを繰り返すだけになってくると、そろそろ潮時である。
「キルケーさあん」
「はいはい~」
「私ね……こんらふーに、仕事終わりにお友達とお酒のんだりできるの、初めてなんれすよ。ずっと、ずーっと、憧れてたんれすよ……」
「ユミさん、そのお話三度目ですよ~」
キルケーはクスクスと笑う。「でも私もです~。人間様のお酒の相手は何度もしましたけど、お友達と同じ目線でお酒を飲むなんて初めて。楽しいですよね~。お酒って、こんなに美味しいものだったんですね~」
「キルケーさんも、その話五回目れすよー……あれ六回目……?」
二人の酒は決まってこの話題で終わる。ユミの目がどろんと濁って焦点が合わなくなり、キルケーも体が前後左右にゆらゆらと揺れ始める。これでもう少しすると、ユミがこっくりこっくり船をこぎ始めるのが看板の合図だ。
が、今日はそこへドタバタという足音が近づいてきた。
「ラッキー、まだ開いてた! 水割り! ジョッキで!!」
「あたしビール!」
「あたしも! あとツナ缶開けちゃうっす!」
ウェアウルフとブラウニーが数名、慌ただしく駆け込んでくる。
一気に騒がしくなった店内に、キルケーはやれやれと笑ってスツールに座り直し、後ろの棚に手を伸ばす。
「ウィスキーでいいですね? ビールは今日の分、あとちょっとで終わりですよ~」
「マジか! じゃあなくなる前に私にもビール」
「えー! あたしの分がなくなるじゃないすか!」
「うるさーい! 前から思ってましたけろウェアウルフさん、あらたはもっと大人の飲み方とゆーもろを!」
「おわっ、いたのかユミさん! もうベロンベロンじゃねえの」
小一時間もすれば、レプリコンかブラックキャメルがやって来て、まとめて叱って連れ帰ってくれる。ユミには悪いがそれまでくらいの間は、この騒がしさも悪くない。賑やかな酒も、静かな酒も、キルケーはどちらも好きだ。
明日は誰が来てくれるかしら。ジョッキに水とロックアイスを注ぎながら、キルケーはニコニコと考えていた。今日より明日が楽しみだなんて、この百年間一度もなかったことなのだ。
End
一昨日からはじめたタマネギの植え替えがようやく終わって一息ついているところへ、聞き慣れたエンジン音が響いてきた。
褐色の頬を流れ落ちる汗をぬぐって。見上げたプレスターヨアンナは怪訝な顔をする。
よく晴れた空をこちらへ降下してくるのはいつも見るエクスプレス76の大型コンテナだが、もう一つ、見慣れない長方形のコンテナが並んで降りてくる。
「なるほど、ここがヨアンナ島か。牧歌的でいい所だな」
コンテナの上からひらりと降り立ったのは、艶やかな栗色の長髪をなびかせ、長大な対物ライフルを軽々とかかえた長身のバイオロイドだった。
「ロイヤル・アーセナル卿! どうしてここに?」
「やあ、直接にははじめまして、プレスターヨアンナ。今日は荷物がずいぶん多いと聞いてな、手伝いだ」
コンコン、と背後に着陸したフローティング・アーモリーを手の甲で叩いてみせるアーセナル。「こいつを空にしてきた。あまり繊細にはできていないが、運べる重量はちょっとしたものだぞ」
「いや、それはそうだろうが」ヨアンナは隣でコンテナの展開をはじめているエクスプレスを見やる。「生活物資の運搬など、キャノニアの隊長にさせる仕事ではなかろうに」
「私もそう言ったんだけど……」
「実を言えば、外に出る仕事なら何でもよかったんだ。ここのところ書類仕事と会議ばかり続いて、退屈でな」
カラカラとアーセナルが笑う。つられてヨアンナも笑った。
「なるほど、そういうことならゆっくりしていってくれ。オルカでは食べられないものも色々あるぞ」
「――――美味い! ただのアップル・ジュースがこれほど美味いとはな」
グラスの中身を一息に飲み干して、アーセナルは感じ入ったようにハアッと長い息を吐いた。
「鮮度が違うとも。プレッツェルとベリーもよければどうぞ。朝摘みだ」
みずみずしい漿果を二つ、三つつまんで口に放り込み、アーセナルは満足げな鼻息をもらす。
「これで美味いワインがあれば言うことはないな」
「卿も皆と同じことを言う。醸造所はまだ計画中だ」ヨアンナは苦笑する。
「この間加わったというキルケー卿は酒造りの心得があるそうだが」
「心得どころか、自分の部屋で酒を造ってバーを開店した。興味は持つだろうが、司令官のそばを離れる気はないようだし、希少なモデルだからな。当分この島に来ることはなさそうだ」
「それは残念」
議長室の大きな窓からは、居住区の町並みを一望することができる。焼きたてのプレッツェルをかじりながら、アーセナルは窓際に立って活気のある大通りを見下ろした。
「先程、町中を少し見せてもらった。……これだけ住宅があるのに、どの家にも表札がないな?」
「タグコードを地図情報に埋め込んでおけば、目で見る表札は必要ないからな。たまに趣味で出している者もいるぞ」
「町の規模の割に、荷車やサイクルトレーラーばかりで、自動車をほとんど見ない。道路も自転車用に作られている」
「バイオロイドの足には、その方が効率がいい。以前ドクターに試算してもらったが、市街の規模が少なくとも今の十倍になるまでは、人力の方が大型動力車より輸送効率が高いそうだ」
「高層の建物にエレベーターがない」
「不要だからさ。二、三フロアなら跳び上がれる者の方が多いし、足が弱った者は地上階に住む」
「……」
「言いたいことはわかるぞ、アーセナル卿」
ヨアンナは自分のグラスから一口飲んでテーブルに置き、アーセナルの隣に立った。
「貴公の想像しているとおりだ。この町は、人間よりもバイオロイドの利便性を優先して作られている」
アーセナルの形のいい眉が片方跳ね上がる。AAキャノニアの指揮官は、傍らに立つヨアンナへ鋭い眼差しをゆっくりと向けた。
「よもやと思ったがな……司令官は承知しているのか」
「承知もなにも、殿の発案だ」
やや芝居がかった仕草で、ヨアンナは窓に背を向け、大股に執務机に歩みよる。引き出しから取り出した大きなファイルには、金文字で司令官の名前が綴られていた。
「鉄虫との戦いが片付くまでは、ここで暮らすのはどのみちバイオロイドだけだ。そして戦いが終われば、人間とバイオロイドが新たな関係のあり方を模索していかねばならない時代がくる。その時に、バイオロイドによるバイオロイドのための町があることは大きな意味を持つ。殿はそう仰っていた」
「バイオロイドによる……バイオロイドのための町」
アーセナルはなかば呆然とファイルをめくり、眼下の町並みと見比べるように、何度も視線を移す。
「想像もしなかったな。そんなことは」
「私もさ」
ヨアンナは手際よくグラスを片付け、ポットに熱い湯を注ぐ。
「殿のお考えは、いつも余の想像を超えてくる。過去世のデータで知っている人間とはあまりに違って……違いすぎて、もしかして人間とは、本当はこういうものだったのかもしれない、とすら思えてくる」
「詩人だな」
「余は役者だからな、そうでなければ務まらぬ。見よ、嘆きの壁に我らの旗が立つ! ベニンの民、アデンの民、モノモタパの民よ集え、そなたらの流した血が報われる時が来た!」
わざとらしく朗々と歌い上げながら、ヨアンナは十分に蒸らした甘い香りのオレンジティーを、白いカップに注いでアーセナルに差し出した。
「今は、ここが余のエチオピアだ」
アーセナルはおだやかな顔で、一瞬だけ目を閉じて紅茶の香りを味わったあと、ぐっとカップを傾けて一息に飲み干す。たった今淹れたばかりの、熱々の茶である。目を丸くしているヨアンナに、
「本当によい所だ。いずれゆっくり茶飲み話でもしたいが……またの機会にしよう。アーモリーへの積み込みを手伝ってくる。日が暮れる前にオルカに帰りたい」
「急にどうした。気に障っただろうか」
「いやあ」アーセナルはにっこりと首を振り、
「あやつは私が思っていたより、さらに大きな男だったようだ。もう一度抱かれ直したくなった。一刻も我慢できん」
ヨアンナは呆気にとられた顔をして、それから笑い出した。
「殿に伝えてくれ。司令官公邸には九つの浴室と、二十七の寝室を備えてある。臣民一同、いつでもご来訪をお待ちしていると」
「かならず伝えよう。……それもバイオロイドの都合を優先した結果か?」
「もちろん、そうだ」
この島の名をヨアンナ島という。旧時代には別の名前があったが、今は開拓団のリーダーの名前をとって誰もがそう呼ぶ。
兵装と戦闘モジュールを返納して退役したバイオロイドたちが、鉄虫の移動圏外の離島で平和な暮らしを営みつつ、オルカのための物資生産に従事する場所である。
暮らしに何の不満もないが、ただ酒がないことと、司令官とベッドを共にできないのだけが残念だと、住人達は口を揃えて言う。
End
明日はオルカが島を発つという日。夕日の眺めがすばらしい丘があると聞いて、オードリー・ドリームウィーバーが訪れてみると、そこには先客が小さな背中をまるめて煙草をふかしていた。
「あ……ごめん。いま、どくね」
「いいえ、あとから来たのは私ですから。よければご一緒させてください」
「んー……ん」
ダッチガールは目上の者にへつらうような、どうでもいいと思っているような、あいまいな笑顔をみせてから、顔を正面にもどした。オードリーもその隣に腰をおろす。
目の前はすぐ切り立った崖になって海へ落ち込み、右手にはこんもりとした森が雪の帽子をかぶって広がる。左手にはなだらかな岬が長く長く弧を描いてのびていき、その先端に小さくオルカの銀白色の船体がきらめくのが見える。そのすべてが、今にも海に落ちかかる夕日に染め上げられ、燃えるようなオレンジ色にかがやいている。とっておきのドレスを台無しにしてしまったお詫びにとウンディーネが教えてくれたのだが、確かに人に勧めるだけはある絶景だった。
その美しさを一滴もこぼさず目におさめ、新たなインスピレーションの糧にしようとオードリーが無言で目をこらしていると、ダッチガールが横目でちらりとこちらを見た。
「夕日、好き?」
「美しいものはなんでも好きですわ」
即答してから、オードリーも隣を見る。「あなたも、そうなのではなくて?」
「私は、おひさまも、海も、お空の下にあるものはなんでも好き」
眠たげな顔で紙巻きをふかしながら、御伽話の子供のようなことを言う。オードリーの怪訝な視線に気づいたのだろう。ダッチガールがこちらを見て、またへらっと笑った。なんとはなし、興味をおぼえて、オードリーは話題を探してみた。
「先日のパーティには、いませんでしたわね。確か、セントオルカの建造の方へ行っていたとか?」
「うん、寝てた。前の晩からあの日の昼まで、徹夜だったんだ」
「お疲れ様。素晴らしかったですわ、あの飛行船」分野は違えど、ものを作り上げる技術と努力にオードリーは敬意を欠かさない。
「でも勿体ないですわね。貴女、確か花をあしらった、なかなか悪くないドレスを持っていたでしょう」
「あはは。デザイナーさんはよく見てるね」
所属が同じとはいえ、オードリーとダッチには接点らしい接点はない。もとよりゴールデン・ワーカーズは「重工業向けバイオロイド」という極めてざっくりした販売上のジャンル分けにすぎず、バトルメイドやスチールラインの面々のような連帯感は生まれようがない。まして服飾分野の最高級機と鉱山用の量産機では住む世界が違いすぎて、おそらく旧時代にも顔を合わせることすら稀だっただろう。
それでも、現状オルカにいるゴールデン・ワーカーズの中で唯一のSS級バイオロイドとして、オードリーはシリーズの責任者のような立場を任されており、メンバーについて最低限の情報を把握してはいた。
「一本、いただけて?」
「……吸うんだ」
意外そうな顔で、ダッチはオーバーオールの胸ポケットから煙草入れを出す。手をのばして、オードリーはためらった、オーバーオールの端切れで作ったとおぼしき、不格好なボロボロの煙草入れには、あと一本しか入っていなかったからだ。
「いいよ。どうぞ。ちょうど、禁煙しようと思ってたし」
椅子代わりに腰をかけているドリルのどこかから、シガーライターを取り出して渡すダッチ。礼を言って火をつけ、深く吸い込んで、オードリーは盛大に咳き込む。
「あなた、いつもこんな強いのを吸ってますの」
「変? これくらいじゃないと吸ってる気がしないって、みんな言ってたけど」
「いくらバイオロイドだって肺を悪くしますわ」
「うちら耐用年数が短かったから、あんまりそういうの気にしないんだ。働いてればそのうち、味とか臭いもよくわかんなくなるし
幼い顔立ちに似合わない太い紙巻きが、ちいさな唇の先でジジ、とかすかな音を立てた。
ダッチガールがどのような環境で使われていたかはオードリーも知っている。肉体にあわせて十歳そこそこの精神年齢をセッティングされているはずの彼女がきつい煙草を平然と吸うのも、笑顔がみょうに枯れた諦念を感じさせるのも、過酷な業務で精神がすり減ってしまった影響なのかもしれない。
「オードリーはさ」
黙ってしまったのを自分の発言のせいだと思ったのか、こんどはダッチガールの方から声をかけてきた。
「司令官と寝たんでしょ。どんな感じだった?」
「!?」
「あったかい? 幸せだった?」
「誰がそんな……」
怒鳴りつけそうになって、オードリーははっと思い至った。
「寝た、というのは、つまり……睡眠を?」
「? いっしょに眠ったんでしょ? 起きてたの?」
「ああ……いえ、はい。寝ました…わ。確かに」
ダッチガールはきょとんとして首をかしげてから、
「いいなあ」
うっすら隈のういた目元を、ふっと柔らかく細めた。
「司令官はさ、私に煙草をやめろって言わないんだ。きれいな服を着ろとも言わない。『こんな仕事をさせられて可哀想に』とかも、言わないんだ」
ダッチガールの肉のうすい頬が。けっして夕陽のせいだけではなくオレンジ色に輝いている。
「最初はそういうこと、言われそうだなと思ってたんだ。たまに気まぐれで私たちに優しくするような人間様は、みんなそうだったから。でも、違ったんだね。ああいう人間様も、いるんだね」
雑な三つ編みにした髪を、照れくさそうにくしゃくしゃといじりながら、そんなことをボソボソとつぶやく横顔を見て、、オードリーは理解した。
彼女はやっぱり子供なのだ。過酷な労働の記憶が精神をすさませ、まるで老木のように表面を干からびさせてしまったとしても、その芯にはちゃんと年相応の子供が残っている。恋と憧れの区別もまだなく、男女が一緒に寝ることの意味さえ知らない子供が。
「……貴女は、これから美しいものを沢山見るべきですわ。そして、楽しくて、自分のためになることを沢山するべきです」
「司令官と同じこと言うね」
「光栄ですわね」
海風がどっと寄せてきて、ダッチガールのオレンジ色の髪と、オードリーの白金色の髪を激しく巻き上げた。
陽ももうすぐ沈みきる。今日、ここへ来た価値は十分にあった。どちらからともなく、二人は立ち上がって、微笑みあった。ダッチガールの笑顔はもうあいまいではない。
「あら? でも、煙草をやめろと言われなかったなら、なぜ禁煙を?」
「……煙草臭いバイオロイドは、司令官きらいかなって」
恥ずかしそうに言うダッチガールに、オードリーは思わずにっこりした。
「それも貴女の個性です。いい女は紫煙をまとうものでしてよ」
「うーん……?」
どうも納得がいっていないらしいダッチガールのために、オードリーは後日、かつて自分のブランドでコラボした女性向けフレーバーシガレットのデータを探し出して再生し、手ずから仕立てた仔牛革のシガレットケースに入れてダッチガールに贈った。
「禁煙するって言ったじゃん」
照れくさそうにしながらも、ダッチガールは笑顔だったという。
End
「じゃーん! アウローラさんの新作、いちごチョコディップクッキー」
「ああー! いいなあー!」
「ふふふふふ。先週演習で一緒になった時こっそりお願いしたのよ」
「一口ちょうだい、アルヴィスに一口ちょうだい!」
「私にも! 私にも!」
「そっちの箱、何?」
「もうちょっとしたら開ける用です。この間焼いてみたラスクとジャム」
「えー、今食べようよ食べようよ」
「ちょっと、静かにしててよ! 私はまだ仕事してるんだからね!」
キーパッドを叩いていたカリアフ・ベラがたまらず怒鳴ると、グレムリンが口元をとがらせる。
「パジャマパーティの時に仕事してる方が悪いんじゃないですかー」
「ベラお姉ちゃん、なんでまだお仕事してんの? 終わらないの?」
「あ・ん・た・た・ち・が! 弾倉にチョコバー入れて持ってったり、装備ケースに拾ったスクラップ入れて持ち帰ってきたりするから、備品管理がぐちゃぐちゃになってチェックが終わんないのよ!」
アルヴィスのやわらかいほっぺたをぶにぶにと上下に引っぱり倒すベラ。
「ぷえー」
「ごめんなさーい。でもスクラップじゃないもん可愛いんだもん」
「うっさい! 悪いと思うならいますぐ倉庫行って装備とケースのシリアル番号合わせてきてよ! うわーん」
「ベラ、手伝いますから……ほら、こっちは私が明日やっておきます。リスト作りと校正はグレムリンとニンフに任せて、映像記録だけならすぐ提出できるでしょう。いいですね、二人とも?」
「はあい」
「私とばっちりですけど……はーい。ベラ、ファイルの場所だけ教えといて」
「副隊長お~」
床いちめんに敷き詰められたクッションの上をもこもこ渡って、ベラはヴァルキリーの膝にすがりついた。よしよし、と栗色の髪をなでてやるヴァルキリー。
指揮官級バイオロイドの特権の一つである専用の個室を、どのように使うかは人によってさまざまである。マリーの部屋はどこまでも無骨で機能的な事務室だし、カーンの部屋は思い出の品とすこしの酒が飾られた、簡素ながら趣味の良いねぐらだ。そしてレオナの部屋は、大きなソファとティーテーブル、大量のクッションを備えた、姉妹達が集まるサロンだった。
「パジャマパーティしましょう!」
グレムリンが唐突にそんなことを言い出した時、皆が賛成した。それが何なのか具体的に知っている者は誰もいなかったが、なんとなく楽しそうに思えたのだ。
「まあ要するに、パジャマ着てお菓子とかお酒とかを持ち寄ればいいんでしょ」
「たぶんね。でもみんな、パジャマどうやって用意した?」
「ヨアンナ島から作業着のお古をもらったので、それを使ってます」
「ハチコのおさがりもらったー」
「パジャマを着る習慣がないので、ただの部屋着で失礼します」
「私も部屋着です、寝る時には何も着けないので……」
「副隊長、おっとなー」
「……私も別に、普段これで寝ているわけではないのだけど」
「おっとなー……というか、スゴいですね隊長の……」
「セントオルカの温泉行った時着てたやつですよね……透け方えっぐ……」
「今度貸してもらっていいですか」
「何に使う気!?」
「それでですね、その時カーン隊長がなんと言ったかというと」
「もー、それ何度も聞いたから」
「そんなにカーン隊長が好きなら、アンガー・オブ・ホードの子になっちゃいなさい」
「えー! いやいや、そんなつもりはなくて! 私はレオナ隊長が一番です! ですけれども!」
「サンドは明るくなりましたよねえ」
「ホードとの交換訓練が有効だったようですね。またやりましょうか」
「え、いや……」
「うん……カーン隊長めちゃくちゃ強いですけど、正直ついてくの大変なんで……」
「えー! やりましょうよ是非」
「カーンはあなた達のこと、随分褒めていたけど。正確な支援が来るのはやりやすいって」
「そりゃホードに比べれば正確ですよ……」
「隊長はどうでした? ホードの連中を指揮して」
「……ヴァルハラの姉妹達はやはり最高だと思ったわ」
「もぐもぐもぐもぐさくさくもぐもぐ」
「アルヴィス、あんた少し会話に参加しなさいよ」
「さくさくもぐもぐむちゃむちゃもぐもぐもぐもぐもぐ」
「駄目よこの子、お菓子モードに入ると周りの言うこと聞かないもの。取り上げると噛みつかれるよ」
「しょうがないよねえ、チョコ美味しいもんねえ」
「ラスクも美味しいよ。砲助も食べるー?」
「やめなさい、前お菓子の粉が挟まって大変だったでしょうが。グレムリンもう酔ってるわね!?」
「もふもふはふもぐもぐもぐもぐもぐもぐ。もぐ」
「マシュマロなくなったねえ。次こっちのアーモンドキューブ食べてみようか」
「ニンフさん、さっきからアルヴィスと同じペースで食べてるけどいいんですか」
「ぎくっ」
「たいちょー達はそれ、何飲んでるんですかあ?」
「んー? チェリーブランデー」
「お酒も種類増えましたよねえ」
「キルケーさんのバー、行った?」
「行ったけど、あそこ大体誰か騒いでるか、ユミさんがくだ巻いてるかなんだもん。テイクアウトして帰ってきちゃう」
「それなー。落ち着いたバーも欲しいよね」
「ここで部屋呑みしてる方が楽しいじゃない」
「それもそうだけど」
「………………」
「あ、アルヴィス寝てる」
「顔真っ赤。匂いだけで酔っちゃったかな? 机の下にいれといてあげよう」
「じゃあ子供が寝たところで、隊長と副隊長に聞きたいことが。司令官様との一夜はどうだったんですか」
「ちょっ……! こんな時に聞くこと!?」
「こんな時じゃないと聞けないじゃないですか」
「ん…………まあ、悪くはなかった。決して。素敵な夜だったな」
「きゃー!」
「そうですね。次の夜が待ち遠しい気持ちです」
「司令官様って、優しいんですか? 激しいんですか?」
「優しい……な。蕩かされるようだった。もう少し、情熱的でもいいのだけれど」
「きゃー、きゃー!」
「乱暴にしてほしいと言えば、して下さいます。わりと、こちらの希望に合わせてくれる感じですね」
「へえー! へええー!」
「ヴァル、あなた」
「いえ、あの、あくまでも一般論として、時々はそういうのも」
「ヴァル」
「わー! わー! この話やめー!」
「それにしてもパジャマパーティって、これであってるんでしょうか」
「楽しいからいいんじゃない? 司令官様を呼んで聞いてみようか」
「やめて!」
シスターズ・オブ・ヴァルハラの隊員なら誰でも、ある一つの情景が、生まれたときから頭の奥底に焼き付いている。
降りしきる雪の中にたった一人、倒れたまま冷たくなっていく、自分自身の姿だ。
おそらく、数え切れないほど多くの姉妹達が、そのようにして死んでいったのだろう。知識と戦闘経験データがアップデートで積み重なっていくうち、無数の自分たちが目にし、体験してきたそれらの光景が、記憶とも夢ともつかないおぼろげな原風景として、メモリの基幹領域に刻み込まれてしまったのだ。
「私たちの魂は、いつかヴァルハラにたどり着くのでしょうか」
そんなことを言ったのはサンドガールだった。どのサンドガールが、どの自分に言ったのか、もう憶えてはいないけれど。
「タロン……その写真は…是非とも……」
今、サンドガールはだらしない笑顔で、クッションを抱きしめて何やら寝言をつぶやいている。
他の姉妹達も皆、思い思いの場所で、思い思いのものを枕や布団にして眠りに落ちている。照明を暗くした室内を見渡して、レオナは静かに満ち足りた気分で、グラスの底に最後に残ったわずかな酒を飲み干した。
この先、鉄虫との戦いで姉妹達の誰かが命を落とすかもしれない。だがその時、私たちは決して一人ではないだろう。姉妹達や、司令官閣下や、ほかの大勢の戦友達が、自分の手を取り、血に触れて、見送ってくれるだろう。
私たちの魂はもう、ヴァルハラを求めてさすらう必要はない。ここに、このオルカに還ってくればいい。
「ん……ん。あなた……いけません……♥」
「……」
それはそれとして、ヴァルキリーが司令官とどんな風にしているのかは、明日にでも時間を設けてきっちり問い詰めておかないといけない。
艦内時間の朝まで、まだ二時間ほどある。頭の中の予定表にそれだけ書き留めて、レオナもまどろみの中に沈んでいった。
End
マングースチームの待機室は、オルカの右舷後部ハッチと、艦尾ハッチをむすぶ通路のちょうど真ん中にある。
非常の際に迅速に集結・出撃できるよう、普段人気がなく、かつ複数のハッチに通じる場所が選ばれたのだが、幸か不幸か今日まで非常の出動要請がかかったことはない。結果として単に不便な場所にあるだけの部屋で、みんな着替えの時くらいしか立ち寄らないが、いつ来ても大抵一人になれるこの場所がミホは結構気に入っていた。
「あ、帰ってたんだ。お疲れ」
タンクトップから汗を飛びちらせて、ピントが待機室に駆け込んでくる。また曲技飛行の訓練でもしていたのだろう。ぽいぽいと服を脱ぎ捨てる彼女を横目で眺めて、ミホはぶっすりとキャンディ・バーを噛みながら、長い髪をいじっていた。
「今日はジニヤーが大勢入ってきたらしいじゃない。工場でもあった?」
声をかけられても、ミホは黙りこくったまませっせと髪を編んでいる。ピントはくすりと笑った。
「今日もケルベロスと組まされたんでしょ」
「……うっさいな」
ガリン、とキャンディ・バーを噛み砕く。ここ半月ほど、シティガードのケルベロスとペアで毎日のように出撃しているというのが、ミホの不機嫌の元だった。
「気にすることないのに。今更商売敵でもないんだから」
「そういうことじゃないの」
ブラックリバーのマングースチームとPECSのシティガードは、共に治安維持とテロ対策を目的に作られた。シティガードが平時の警察的な業務もこなすのに対し、マングースチームは凶悪なテロ事件に対して出動し、すみやかに鎮圧・排除するのが仕事だ。
管轄の重なりはただでさえ摩擦を生みやすいものだが、母体とする企業が違えばなおのことで、旧時代、両方が配備されている都市部では毎日いたるところで衝突が絶えなかった。中でもマングース側で、とりわけシティガードを嫌っていたのがミホである。
ミホにしてみれば、狙撃手がいない時点でシティガードにまともなカウンターテロ能力はない。素人らしくこちらに任せて引っ込んでいればいいものを、市民を守るためとか何とか言ってはちょっかいを出してきて、あまつさえこちらの行動に制限をかけようとまでしてくる。本当に市民を守っているのは誰だと思ってるんだ、という憤懣がある。
市民もテロリストも姿を消した今の時代に再生されても、その気持ちは根強く残っている。というのに、よりによってそのシティガードとペアを組まされているのだ。
「話してみれば普通にいい子達だよ。いいじゃん警察、しっかりしてるし。ランパリオンかっこいいし」
「そういうことでもないの」
シャクに障ることに、ケルベロスの方には特にこっちに対するこだわりはないらしく、普通にニコニコと接してくる。そしてもっとシャクに障ることに、実際彼女とのペアは確かにやりやすいのだ。背後の味方をかばいつつ連携するのが得意なケルベロスと、盾役の動きに合わせて追撃を入れるのが得意なミホは抜群に相性がいい。こと鉄虫との白兵戦においては、マングースの仲間と組んでいる時より噛み合うくらいで、振り上げた拳の下ろしどころがないミホの鬱憤は溜まっていくばかりである。
「ま、いいけどね。シャワーすいてた?」
二本目のキャンディを噛み砕きはじめたミホをスルーして、バスタオルを取ったピントの通信デバイスが小さくコール音を立てる。同時にミホの通信機も鳴ったが、まあピントのを聞いてからでいいやとそっちを見ていると、指先を耳に当てて音声に集中していたピントの眉が怪訝そうに上がった。
「――鉄虫が、人間を監禁してる?」
―――
「あくまで、そうともとれる状況というだけだ。実際のところはわからん」
狭苦しい兵員輸送トレーラーのキャビンで、中央に置かれたホロ・モニターの投影機を、紅蓮が指揮棒でコンコンと叩いた。
「13時間前、コネクターユミが中継ポイント設営中、近隣で発せられた救難信号を検知した。発信地点はここ」
ホロ・モニターに、地図と映像が映し出される。海を見下ろす高台に構えられた、豪奢な邸宅だ。
「旧時代にはブラックリバーノースの役員の別宅だった建物だ。シェルター化した地下室があり、敷地内に中隊規模の鉄虫が集結している。信号はAs-S-4で暗号化された、ごく短いものだ。情報は三つしかない。『発信者はケルベロス型』『人間が一緒にいる』『生命の危機にあり救助を求める』」
「いや、駄目でしょそれ」
プルガサリが大げさに両手を上げてみせる。
「As-S-4って旧時代のコードじゃないですか。大昔の救難信号が、たまたま電池切れなかっただけでしょ? スイッチ押した人間様はとっくに死んでますよ」
「罠の可能性は? そもそも救難信号を暗号化って」
「ケルベロス型は体内に緊急信号送受信モジュールを埋め込まれている。この信号が出ているということは、少なくともバイオロイドが一体生きている可能性が高い」
プルガサリとピントの野次にも動じず、紅蓮は画面をスワイプする。邸宅の画像が見取り図に変わった。
「不可解な点の多い状況だ。鉄虫どもが何を企んでいるのか、突き止める必要がある。それに、万に一つの可能性でも人間がいるとしたら、救出しないわけにはいかない」
「そいつはその通りだな! 破壊神様の本領発揮ってわけだ」スチールドラコがドンと胸を叩く。破壊神という言葉の意味をわかって言ってるのだろうか。
「それはいいけど、なんでシティガードが一緒なんですかー」
ミホが手を上げると、キャビンの向かい側に座っていたミス・セーフティ、ケルベロス、フロストサーペントが一斉にこっちを見た。なおランパートとポップヘッドはトレーラーに入らなかったので外を併走している。
「発信元はケルベロスだよ。私がいた方が、よくわかることもあるかもじゃん」
あっけらかんと微笑むケルベロスに、ミホは顔をしかめる。「ケルベロス型のデータくらい、私らだって持ってるよ」
「シティガードには陽動を担当してもらう」
「陽動? 私は?」とピント。
「お前は今回第2チームの前衛(ポイントマン)だ。バックアップはミホ。第1チームはドラコとプルガサリ。シティガードが正面から救出作戦を行う隙に、ガレージと屋上から2チームで突入する」
ミホ達の顔が引き締まる。エサを別に用意して、ピントを前衛に投入するのはいわゆる「本気のシフト」だ。
「もし鉄虫が本当に人間を殺さず監禁していた場合、背後には少なくともストーカー級の連結体の関与を疑う必要がある。特A級相当のターゲットだと思え」
つまり、ネゴシエーションはなし、降伏勧告もなし。ただ潜入し、殺し、助け出す。
上等じゃない。ミホは愛用のピンキー・カスタム・カスタムを背後のラックに戻し、取り回しのいいアサルトライフルを取った。まさしくマングースチームの本領だ。
「……まーだシティガードのこと嫌いなの?」
トレーラーの振動にまぎれて、プルガサリが横目でミホの方を見て、小声でささやいた。
「よくないよ、そーゆーの。私もサーペントとよく組むけど、普通にいい子じゃん」
「うっさい。私の勝手でしょ」
「12分後に到着する。そこ、無駄口を叩く暇があったら見取り図と鉄虫の配置をもう一度頭に叩き込んでおけ」
―――
藪の中から見下ろす邸宅は、映像で見るより大分くたびれて見えた。広々とした庭にサンダーチックとチックスナイパーが数匹、所在なげにうろついている。
予定時刻ぴったりに、シティガードが正面の門を破壊。いっせいに寄ってきた鉄虫達と戦闘に入ったのを確認して、ミホとピントも動き出す。
普段とは逆に限界まで静音化されたピントのフライトローターが、二人分の体重を音もなく屋上へ下ろす。換気口周辺にトラップがないか一瞬だけ確認して、ピントの細い体がダクトの中へ消えた。
《ヒトデよりロータス。ガレージクリア。撃破3》
「キツネ、二階C3クリア。撃破1、損傷なし。エントランスを避けて一階へ向かいます」
《こちらワンコ! 玄関ホールにビッグチックシールダーが三体もいた! でかい硬いせまい怖い!》
「……キツネ、軽く援護を入れてから一階へ向かいます」
《ドラゴン、一階C8クリア。撃破2。地下室への階段を確保したぜ》
ミッションは淡々と進んだ。一流のプロが本気で事に当たる時というのは、そういうものだ。ドラマチックなことなど何も起きない。あらゆる事態が事前に想定され、対策を立てられている。
《ドラゴン、地下二階に突にゅ……わぷっ》
ただ、一つだけ予想外の出来事があった。ターゲットのいる地下二階が、ほぼ水没していたのだ。
「……しょっぱい。これ、海水だ」
《地質図と照合した。そのあたりの岩盤には細かい亀裂が無数に入っているようだ。おそらく、満潮時に圧がかかって海水が浸みてきたんだろう》
「あー、だから鉄虫が近寄らなかったのかな」
《ターゲットの部屋も水没してますよ。密閉されてて中は空気があるみたいですが、どうします?》
数秒間の討議のあと、地下一階から床を壊して突入することにした。信号の発信位置からできるだけ離れた、部屋の反対側のあたりの床に、プルガサリがドリルアタッチメントで穴を開ける。
瓦礫が階下に落ちないよう粘着剤で固めつつ、人一人通れるくらいに切り広げた穴から飛び込んだ部屋には、床に倒れたまま動かない一体のバイオロイドがいた。
ケルベロスであることは制服とタグ信号でわかった。まだ息があることも。だが、枯れ木に布を巻きつけたような四肢も、しわくちゃに萎びて垂れ下がった乳房も、げっそりとこけた頬も、ミホ達の知る快活でよく笑うケルベロスとは似ても似つかない。飢えた老婆のごとき彼女は、それでも落ちくぼんだ眼を天井へ向けて、ひびだらけの唇で一心に救難信号のコードをつぶやいていた。
ドラコが素早く前に出て、ケルベロスの全身に軽くふれる。普段の言動からは想像しにくいが、彼女はマングースのレスキュー担当であり、一通りの救命スキルを身につけている。
「サーペント呼んでくれ。急いで」
部屋の隅には水がたまり、悪臭を放っている。別の隅にはツナ缶の空き缶が小さな山になっており、部屋の中にあるのはそれだけだった。人間はいないし、いた形跡もない。
玄関ホールの鉄虫をようやく片付けたシティガードが、ぞろぞろと部屋に下りてきて、一様に顔色を変えた。フロストサーペントが素早く装備を外し、救急パックを取り出す。
「代わります。ケルベロス来て、輸血がいる」
オルカの方のケルベロスが、青ざめた顔で小走りに駆け寄り、同型機の傍らへかがみ込む。入れ替わりに、ミホとピントはきびすを返した。立ち尽くしているミス・セーフティの肩を叩く。
「来なよ。ここはあっちに任せて、私達は残りのエリアやるよ」
「……あのケルベロス、何やってたんだろ」
《おそらく、囮だ》ピントの呟きに、紅蓮が答える。
《ガレージが空だった。住人は車で逃げたんだろう。そのとき鉄虫を引きつけるために、救難信号を出し続ける餌として残されたんだ》
「人間は?」
《残りのエリアも確認してからだが……最初からいなかった可能性が高い。救難信号の欺瞞は戦争末期にしばしば使われていた手だ。どうせ国際法など無意味化していた時代だしな》
「だからって、100年もそれを続けてたっての? 逃げた主人もとっくにいないのに」
「命令が無期限だったんでしょう。この数の鉄虫では、せいぜいもって数日と見込まれたでしょうし」
セーフティがぽつりと言った。
「でも偶然海水が浸みてきたおかげで鉄虫と隔離され、今日までずっと命令を実行してました……と」
「クソったれな話だね」
「よくある話です」ミス・セーフティは力なく笑った。「私達は何しろ、安かったので。使い捨てできるのが強みと、当時のカタログにも書いてあったくらいです」
バイオロイドには値段がある。値段に応じた性能もある。
ミホが優れた狙撃手なのはそういうものとして作られているからで、ケルベロスやセーフティがそうでないのも同じ理由だ。大砲がマシンガンを見下しても何の意味もない。オルカがあまりに自由で居心地がいいので、忘れていた。自分たちは道具であり、製品であり、商品なのだ。
「キツネ、C12クリア。C14クリア、撃破1――」
―――
080機関も加わった入念な事後調査の結果、結局今回の事件は純然たる偶然の産物であって、背後に何らかの計画があるようなものではない、と結論された。
ミッション達成の褒美に休暇をもらったミホが待機室でのんびりライフルの分解掃除をしていると、ドアをノックする者がある。
「この間は、ありがとうございました」
「あんたは……」
頬には血色がもどり、胸も元どおりパンパンに膨らんでいるが、右手の指が二本萎びたままなのと、足を少し引きずっている。タグ信号を確認するまでもなく、先日の地下室にいたケルベロスだ。
「もう退院したんだ。おめでと」
救助されたケルベロスが一命を取り留めた、とは聞いていた。さすがは安くて長持ちが信条のシティガード、回復が早い。
「ありがとうございます。退役させてもらえることになって、装備を返納してきたところなんです。オルカを降りる前に、マングースの皆さんにお礼がいいたくて」
「いいって。お互い仕事をしただけなんだから」
テーブルに広げた部品をすこし片付けると、座っていいという合図ととったのか、向かいの椅子にケルベロスはちょこんと腰掛ける。そうなると放っておくわけにもいかず、お茶など出してみる。適当に淹れたお茶を、ケルベロスはずずず、と美味しそうにすすった。
間近で眺めると、損傷箇所以外にもオルカのケルベロスとは色々と違うのがわかる。毛先は荒れているし、皮膚にはうっすら張り替えの痕がある。物腰や言葉遣いもいくらか落ち着いているような気がする。
「……聞いていい? 百年も救難信号を出し続けるのって、どんな気分だった?」
「え?……うーん」ケルベロスは困ったように頭をかいた。「あとの方はもうほとんど意識がなくて、夢うつつみたいな……でも、そうですね。人間様のためになってるって、その気持ちだけで保たせてたかな」
言ってからお茶をもう一口すすって、「そう思い込んで自分を騙してただけかも。どちらにしろ、他の選択肢なんてなかったから」
「……だろうね」
もし、自分が同じことを命じられたら、とミホは想像する。
従うか従わないかで言えば、従うにきまっている。人間の命令は絶対であり、まさしく他の選択肢などない。
「でも、オルカの司令官様は素晴らしい方です! あんな人間様がご主人になってくれるなんて、世の中まだまだ、捨てたものじゃないと思います」
「ポジティブだね」
「それが取り柄ですから。私、人間様が大好きですし」ケルベロスは朗らかに笑った。
百年という時間を過ごした後、自分はこのケルベロスのように、もう一度笑顔で人間が好きだと言えるだろうか。
「それ、ケルベロス型の初期条件付けじゃないって言える? シティガード用の」
「私のぜんぶが私です。はじまる時にどれを誰にもらったかなんて、気にしても仕方ないです」
「……ごめん。意地の悪いこと聞いたね」
「いいえ」ケルベロスはもう一度笑った。「ミホさんは、司令官様のこと大好きなんですね」
「は!? なんでそうなんの」
「昔のご主人様はマングースチームの販売部長でした。私も何組かのマングースの人たちを見ましたけど、ご主人のことが好きなミホさんほど、私たちと仲が悪くて、イジワルでしたよ。ご主人の一番でいたいっていう、対抗心ていうか、独占欲があったんじゃないかな」
「独占……いやそんなわけない……でしょ……たぶん……」
耳まで赤くなって視線をさまよわせるミホに、ケルベロスは犬歯を見せていたずらっぽく微笑んだ。
「内緒にしておきます。そのかわり、ここのケルベロスと仲良くしてあげて下さいね」
「……へー。そういう真似もするんだ?」
「百年生きてると、こういう真似もできるようになるんですー」
何度も頭を下げてケルベロスが去っていった後、入れ替わりにまたケルベロスが姿を見せた。
「こんにちはー。あのさ、こないだのケルベロスが、マングースチームにお礼を言いたいって」
「もう来たよ。さっき帰った」
「ありゃ」
招いてもいないのにトコトコと部屋に入ってきて、さっきまでケルベロスが座っていた椅子に座るケルベロス。この彼女とあの彼女が同じでないように、彼女とミホも同じではない。大砲とマシンガンが違うように。ピンキー・カスタム・カスタムとほかのSK-14が違うように。
値段も設計もあらかじめ決まった出来合いの命だとしても、今この瞬間見る風景は自分だけのものだ。
「ちょうどいい。あんた、この後ヒマ?」
ミホは掃除の終わったパーツ類をまとめて布でくるんで、脇へ置くと立ち上がった。
「え? うん、夕方あの子の見送りするけど、それまでは」
「よっし、訓練しよう。ホロデッキ空いてたよね」
「あたしと!?」
「どうせまた組まされるだろうし。あんたスタンロッドの命中率悪すぎ」
「やるやる! えーなに超楽しみなんだけど! どしたの訓練誘ってくれるなんて」
「うっさい」
そして、そこに意味などあってもなくても、やっぱりこのミホはこのケルベロスのことが気にくわないのだ。
End
「うん、いいお味。とても美味しくなったわ」
パッと顔を輝かせたセラピアス・アリスに、ラビアタ・プロトタイプは微笑んでうなずいた。
「お出汁の雑味がなくなってる。言った通り、鶏ガラの下処理を丁寧にやったのね」
「はい。どうせアク取りをするのだから同じだと思っていましたが……」
「大事なことよ。プロ仕様の調理技術プログラムも、案外違いはそういうところだったりするものです。この味をいつでも出せるようになれば、スープは合格。ご主人様に召し上がっていただけるわ」
「本当ですか!?」
「もちろん。でもまずもう一度作ってごらんなさい、それほど簡単なことではありませんよ。それに、調理場の後片付けもきちんとできるようにならなくてはね」
「はいっ!」
稲妻を噴かんばかりの勢いで鍋を洗い始めたアリスに後をまかせて、ラビアタは厨房を後にする。
「ご主人様への奉仕は戦場とベッドの上で十分」と言い切るような子だったアリスに「料理の基本から教えてほしい」と頼まれたときは驚いた。ソワンと、彼女の指導を受けてめきめき腕を上げているハチコやバニラの存在に刺激されたらしい。地味な包丁の練習も根気よく繰り返す姿は、ラビアタの知るアリスとは別人のようだ。しみじみと感慨にふけりながら廊下を歩く。
「お姉様、アレクサンドラさんのことで少し相談が。何度言ってもご主人様の机の下に常駐するのをやめて下さらないんです。リリスさんが爆発寸前で」
「お姉様! ポイが、ポイの奴がまた抜け駆けしてご主人様のベッドに!」
「お姉様、アップルパイが上手に焼けたんです。ミートパイじゃないのにです! お姉様もいかがですか!」
「お姉様、また年増って言われました。私のどこが悪いんでしょうか……」
三安の妹たちが、ラビアタを見かけるやいなや駆け寄ってきて様々な相談や雑談を持ちかけてくる。彼女たちにとって、ラビアタは偉大な長姉のようなものだ。彼女たちと語らい、悩みや願いを聞き届けるのは、ラビアタにとってもこの上ない喜びだ。
しかしそれにしても、最近いささか数が多い。今日も妹たちの話を聞いているだけで昼になってしまった。
「みんな、お姉様に聞いてほしいことが沢山あるんですよ」
コンスタンツァはそんなことを言って笑っていた。確かに、つい先日までラビアタは自主的に自室謹慎の状態にあり、妹たちと話すこともなかった。その前は過酷な戦いの連続で、誰もが明日の命も知れない状況だった。
姉妹の他愛ない仲違いなどが生まれるのも、その話に耳を傾けられるのも、それだけ皆に余裕ができたということだ。
とはいえずっと座談ばかりでも肩がこる。昼食前に軽く運動でもしようと訓練デッキに来てみると、先客がいた。
「ラビアタ! 訓練ですか。今空きましたから、どうぞ」
ストライカーズの一人、ティアマトが嬉しそうにお辞儀をする。隣にいる銀髪の子は、確かAAキャノニアのエミリーといったか。
「……二人で訓練していたの?」
「はい。砲撃員といっしょに戦うのは勉強になります」
「私も。キャノニアには砲撃型しかいないから」
そういえばチョコ女王の城に行ったとき、たまたま一緒に戦う機会があったと聞いた。同じブラックリバーのXナンバー同士、相性がいいのかもしれない。
「でも、困っていることがあります。私とエミリーだと、攻めているうちはいいけど、攻め手を取られると困る。私は飛んでよけられるけど、エミリーをかばえない」
「それはそうね、あなたたち二人とも攻撃機だもの。ミナと組ませていた意味がわかったでしょう」
ティアマトはこっくりとうなずく。「ミナは今月合成樹脂の当番だから、ほかの人と練習したいのです。誰か、連携の練習を手伝ってくれる人はいないでしょうか」
「そうねえ」ラビアタは頭の中のリストを検索する。「ホライゾンはどう? ウンディーネとセイレーンなら、あなたたち二人に噛み合うんじゃないかしら」
「ほらいぞん」
「わたし、知ってる」エミリーが得意げな顔をする。「ブラックリバーの、セーラー服着てる人たち」
「そう、それ。私から話しておきましょうか」
「はい。お願いします。待っています」
手を振って出て行くティアマトとエミリー。ラビアタはなかば呆然と、二人を見送った。
あの人見知りのティアマトが、ミナ以外と一緒にいるだけでも珍しいのに、戦闘の連携を意識して練習相手を探すだなんて。
バイオロイドが生まれ持った生き方や性格を変えるのは簡単なことではない。だがティアマトといい、先程のアリスといい、ヨアンナといい、新たな生き方、新たな趣味や特技を開拓するバイオロイドはどんどん増えている。
オルカとバイオロイドレジスタンスは、彼女が設立した当初の考えをはるかに超えた、大きな意味を持つ場所になりつつあるようだ。
訓練を終えて、左舷のラウンジを訪れてみると、案の定マリーはそこにいた。ちょうどいいことに、セイレーンも一緒だ。
「マリー、セイレーン。お願いがあるんだけど、今度ホライゾンの子達と話をさせてくれない?」
「それは丁度いい。実は、そのホライゾンの新入りが出来上がってな」
マリーが視線を後ろにやると、コートの影から小柄なバイオロイドがひょこっと顔を出した。
白と青の鮮やかなセーラー服は確かにホライゾンのものだが、金色の髪をふたつ結びにした愛らしい顔には見覚えがない。先日の追加再生候補リストにホライゾン所属の名前があったのを、ラビアタは今更思い出した。名前はたしか、
「テティス」
「はーい。MH-4テティスでーす。あなたが有名なラビアタ・プロトタイプですかあ?」
小馬鹿にするような笑みをうかべて、テティスはラビアタを無遠慮にじろじろと見上げる。
「思ったよりオバサーン。まあ無理もないか、旧式だもんね」
「……」
セイレーンは申し訳なさそうに目を伏せ、マリーが無言でかすかにうなずいてみせる。その表情で、ラビアタはだいたい事情を察した。
司令官に剣を向けたあの一件のあと、ラビアタはレジスタンスの創設者として本来持っていた管理権限のほとんどを返上した。命令系統の序列だけはマリーと同等のままにしてあるが、それは三安の姉妹達が肩身の狭い思いをしないようにというだけの理由で、あれ以降戦略にも人事にも口を出したことはない。
それでもマリーは義理堅い性格だから、要所要所ではラビアタを立ててくれる。他のブラックリバーの面々にしても、少なくとも表立ってラビアタを蔑ろにしたりはしない。これまで最前線で指揮を執り、ともに戦ってきた彼女の姿を知っているからだ。しかし、レジスタンスにおける絶対的存在だったラビアタ・プロトタイプの威信と発言力が下落したのは確かだし、過去の経緯を知らない新型のブラックリバー製が今のオルカに来たら、これ幸いと彼女を侮りにかかるのは無理もない。
「慣らしも兼ねて、ホライゾン組で強行偵察に出そうと思っているんだが、前衛が足りない。加わってもらえないか」
そして、そういう手合いを黙らせるのに、いっしょに戦ってみせる以上に有効な方法はない。
「もちろん。ただ、お昼をいただいてからでいいかしら」
「十時の方向から鉄虫第7波、接敵まで三十秒」
「十五秒で制圧すれば、補給と応急修理の時間がとれるわね。右翼は私が」
「は、はい! ネレイド、私と左翼を!」
「おっけー!」
かつては小さな一つの国家だったというその広大な埋め立て地は、今や無数に建ち並ぶ工場の一つ一つが鉄虫で埋め尽くされた地獄の巣穴であった。ここを奪還できれば絶好の生産拠点を得られると以前から見込んではいたものの、鉄虫のあまりの多さに手を出しあぐねている。少し余裕のできた今のうちに、下見だけでもしておこうというのが今回の強行偵察の主旨である。
「六時の方向、鉄虫第8波! 連結体がいます!」
絶え間なく襲いかかってくる鉄虫をあるいは蹴散らし、あるいはやり過ごしながら、手分けして周囲の地勢や敵の配置を頭にたたき込んでいく。指揮官級を欠くせいか、かつてはどうにも連携にちぐはぐな所のあったホライゾンだが、しばらく見ない間に見違えるほどいい動きをするようになった。合流前の夏に、あのアンヘル・リオボロスの大金庫で冒険をしたと聞いたが、それが刺激になったのだろうか。
新入りのテティスも生意気な口をきくだけあって、小回りよく立ち回って支援をこなしている。ラビアタの指示にもきびきびと応えてくれる。ブラックリバーのバイオロイドは三安の姉妹達と比べて総じて粗暴で礼儀知らずだが、いい意味で体育会系というか、好き嫌いはさておいて強い奴はとりあえず尊重する、というようなところがあるので、ラビアタはなんとなく嫌いになれない。
「そろそろ……潮時じゃないでしょうかっ。退路の確保に、入るべきかとっ」
鉄虫の第15波を制圧したところで、荒い息の下からセイレーンが言った。
「そうね。手始めの成果としては十分でしょう」
「てっ…てっ……鉄虫、なんて、案外、たい……大したこと、ないですねえ」
テティスもすっかり息が上がっている。初陣にしては重めの戦いだったが、まだ強がりが言えるなら立派なものだ。
「あのでかいプラントと線路を突っ切ればすぐ港だけど……中、虫だらけだし、無理だよねえ。ウンディーネ、迂回路みつかる? できるだけ近いやつ」
「いえ、迂回しなくていいわ」
上昇しかけたウンディーネを手で制して、ラビアタが前に出る。
「みんな頑張ったし、最後はお姉さんがいいところ見せちゃいましょう」
お姉さん、に気持ち力をこめて言ってから、右手に提げていた細長い装甲トランクを瓦礫に突き立てる。中央のスリットにトロールスバードの刀身を差し込むと、ガチリと音がしてトランクの四隅から蒸気が噴き出した。
ホライゾンの面々がいっせいに後じさる。一人きょとんとしているテティスを、ネレイドが腕をつかんで引っぱっていった。
ラビアタの愛剣、単刃式大型プラズマ切断機トロールスバードの付属品である装甲トランクには、二基の小型核融合炉が収められている。ふだんはコードで剣につないでいるが、一時的に大電力を得たい時には、コードでは焼き切れてしまうのでトランク自体を変形させて刀身に直結する。
「んヌぅっ!」
瀟洒なメイドドレスに包まれた白い二の腕と背中に、みきり、と深い山脈のごとき筋肉がうねり上がる。
展開した刀身の長さ3メートル、総重量半トンを超える超高熱のチタン刃が振り上げられ、そして亜音速で振り下ろされた。
落雷に似た轟音と閃光、そして爆風があたりを吹き払ったあと、セイレーン達がおそるおそる目を開けると、目の前にあった建物が真っ二つに切り開かれ、赤熱した断面をさらす建材と鉄虫たちの向こうに、上陸地点だった港と夕映えの海がきらめいて見えた。
「さ、今のうちに。すぐ生き残りが動き出すわ」
蒸気を上げる残骸に触れないよう、急ぎ足でプラント跡を抜ける途中、テティスがすすっとラビアタの隣へ寄ってきた。
「あの……ナマイキ言って、ごめんなさい。ラビアタ…お姉さん」
ラビアタはにっこり笑って、テティスの頭をなでた。
「ストライカーズのティアマトが、連携の練習をしたがっているの。今度、相手をしてあげてくれる?」
帰還したラビアタは、戦いの汗と埃をシャワーで丁寧に洗い流す。今日は充実した一日だったが、最後に一番大切な務めが待っている。
オルカは変わった。それも、すばらしく良い方向に変わった。そのほとんどすべては、司令官のおかげだ。
勝利をもたらしてくれるから。優しいから。お菓子をくれるから。ハンサムだから。オルカのバイオロイド全員が、いろいろの理由で彼を慕っている。もちろん、ラビアタもその一人だ。ただラビアタは、司令官のどんなところが好きかについて、妹たちのようにトークに花を咲かせたことはない。これからも話すつもりはない。
雄大な乳房を流れ落ちる水滴を追って、指先をすべらせる。この肌に触れた人間の数は決して多くないが、かといって少なくもない。
かつての世界で、ラビアタに劣情を抱く男達は後を絶たなかった。ブラックリバーの虜囚だった時も、アダム亡き後の三安にいた頃も、幾人もの男達がラビアタを使って己の肉欲を満たそうとした。
しかし、ラビアタ自身の肉欲を満たしてくれる男にはただの一人も出会わなかった。これまでは。
だからラビアタが司令官を心から敬慕するその理由は、結局のところ非常にシンプルなのだ。
髪をととのえて化粧をすませ、とっておきの下着の中から二枚を選んで、しばらく考えたあと片方を身につけ、上からガウンをはおる。さすがに、この格好で廊下は歩けない。
バトルメイドプロジェクトのフラッグシップモデルとして、あらゆる家事スキルを最高レベルでインプットされたことに、ラビアタは今更ながら深く感謝している。どんな勝負下着を使っているか、オードリーにも誰にも知られずにすむからだ。
End
「ひー、やっと着いた……」
エルブン・フォレストメーカーは肩にくいこむ大型コンテナのハーネスを外し、眼下の海を見渡して大きく伸びをした。乳間に小さな池をつくっていた汗が解放されてばしゃ、と草の上へこぼれ落ちる。
「ほら、言った通りの場所に出たでしょ」
隣を歩いてきたダークエルブン・フォレストレンジャーも、汗でべったり貼りついたシャツを引きはがすように胸元を広げ、潮の匂いのする風を入れた。
「このあたしが森の中で迷うわけないんだから」
「その鳥飛ばして方向確認してたくせに」
「う、うっさい! あたしの装備品なんだからあたしの能力のうちよ。それよりも」
ダークエルブンはちらりと後ろを見やって、相方のとがった耳に顔をよせた。
「なんで助っ人がよりによってアイツなのよ」
「知らないわよ! 司令官様の人選なんだから仕方ないでしょうが」
エルフ二人から少し離れた後方では、さらに一回り巨大なコンテナを背負ったイグニスが、すこし心細げにこっちを見ていた。
航行中手軽に補給できるよう、よく通る航路近くの海岸に果樹を植えておいてはどうかと提案したのはエルブンだった。最適な気候と地形をえらび、植樹のための株を旧時代の果樹園跡から探してくるのはそれなりに大変だったが、専門分野のことでもあり、あっという間にプランは完成した。
しかし、そうして調達した果樹数十本を海岸まで運び、実際に植える作業には、自分と(有無を言わさず巻き込んだ)ダークエルブンだけでは手も馬力も足りない。せめてあと一人、力仕事要員がほしいと司令官に頼んでおいたところ、紹介されたのがイグニスだったのだ。
三人がいるのは海に面した、小高い山並みの尾根である。ここから地面は急角度で傾斜してまっすぐ海へ落ち込んでいく。岩壁のすぐ先からかなりの水深があり、オルカの巨体でも陸地近くまで寄せられる地形である。斜面には波のとどく直前の高さまでこんもりとした緑が茂っており、土壌もしっかりしていそうだ。
「あの……慣れない作業ですが、精一杯やりますので。色々教えていただければ……」
「あーはいはい。とりあえず、そのコンテナ持ってついてきてください」
大きな体を縮こめるようにして挨拶するイグニスを苛々とさえぎって、ふたたび歩き出す。
エルブン達フォレストシリーズはみな、イグニスにほとんど本能的といっていい忌避感を抱いている。
別に、このイグニスが何かしたというわけではない。だが森を守り育てるのが仕事のバイオロイドと、火炎放射器ですべてを焼き払うのが仕事のバイオロイドが、仲良くできるわけがあるだろうか? 旧時代、事故であるいは故意に、イグニスが引き起こした森林火災は毎年片手の数では足りない。テロリストも鉄虫も、潜伏先として密林を選ぶことがしばしばあり、最も手軽で有効な対策のひとつが焼き討ちだったからだ。ドゥームブリンガーの次に多くの森を焼いたのはパブリックサーバントだ、などという冗談もあったくらいだ。
足場に注意して下りながら、手頃なアダンやシュロの樹を見つけては、先端をツリースペードに換装したアームで引っこ抜き、かわりにコンテナの果樹を植える。あとからダークエルブンが樹種と樹勢を見て、よぶんな枝をはらったり、まわりの土を殺菌したり、樹皮の傷をゴム剤でふさいだりしていく。
オレンジ、バナナ、マンダリン。パパイヤ、バナナ、またバナナ。アームを換装し、コンテナを入れ替え、水を補充しと、斜面を上り下りしながらの作業はなかなかに骨が折れるが、なんといってもエルブンにとっては再生以来初めての本業仕事である。鉄虫をぶん殴るのにしか使っていなかったアームも、鉄虫を水浸しにするのにしか使っていなかったホースも、心なしか活き活きと動いている。
夢中になって作業をして、気づけば斜面の三分の一ほどまで来ていた。
「お昼休憩にしましょうか。その抜いた木、上へ持ってって下さい」
「はい。……あの、これはどうするのでしょう」
熱帯樹が積み上がったコンテナをかついだイグニスが、不安そうに尋ねる。
「んー、大きいのは持って帰って材木にしちゃいましょう。残りはあとで、適当なところへ植え直しですね」
「あ……植え直すんですね」
「そりゃ植えますよ。燃やしたかったんですか?」
「いいえ」エルブンの皮肉に気づいた風もなく、イグニスはほっとした顔をした。「まだ生きているものを燃やしたくはありません」
「……ふん」
森の下生えに腰をおろして、お弁当のツナサンドを食べる。海から吹き上がって抜けていく風が心地いい。
「だんだん傾斜が急になってくけど、持ってきた分使い切れるかな、木」
「ダッチちゃんに頼んで、部分的にでも整地してもらえばよかったかもね。収穫の時もその方が楽だし。ちょっと、下の方もういっぺん見てこれる?」
「ん。ゲド」
ダークエルブンが手をかざすと、肩の上でプロテインバーを食べていたハクトウワシがさっと舞い上がり、風に乗ってゆったりと斜面を下っていく。と、食事の時も一歩離れていたイグニスがにじり寄ってきた。
「あのワシ、ゲドっていう名前なんですか」
「え、うん」ダークエルブンが気まずそうな顔をする。「いいでしょ、どんな名前つけたって」
「もしかして『ハイタカ』からですか?」
「!……あんた、知ってるの?」
「昔読みました」
ダークエルブンの顔がぱっと輝く。エルブンがぽかんと見ている間に、二人は何やら知らない言葉で話し始めた。
「私はやっぱり『こわれた腕環』の……」
「カラスノエンドウが……」
「『オメラスから歩み去る人々』も……」
「…………」
さっきまでと打って変わって熱心に語り合っている相棒を、エルブンはむっつりと横目で眺める。
別にイグニスと仲良くしたいなんて思わないが、それはそれとしてダークエルブンだけが仲良くなるのは、出し抜かれたようでたいへん癪だ。大体あの子は普段つんけんしてるくせにチョロすぎる。くそう。邪魔してやりたい。
「はいはーい、そろそろ休憩終わり。先に植えた分、養生やっちゃいましょう」
わざと手を叩いて大きな声を出し、すたすたと最初に植えた樹のところまで下りてやった。ダークエルブンとイグニスがあわてて追ってくるのを待たずに、シャツの前をはずし、大きく重たい二つの乳房をばるん、と放り出す。
乳房の根元から先端へと、両手でかかえてしごき出すように揉む。ほどなく、乳首にぴりっとした感覚が走り、ピンク色の先端から白い糸のようなミルクが幾筋もあふれ出てきた。
「んっ…………ん」
小さな小さなシャワーを、植えたばかりのオレンジの樹の根元にぐるりと注いでいく。樹の根元がしっとりと濡れたのを確かめて、次の樹にうつる。
「……あの、これは、何を?」呆然と見ていたイグニスが質問を発した。
「見てわかりませんか? ミルクを搾ってるんです」
「これがあの、エルブンミルク……。植物にも栄養になるんですか?」
「にもってなんですか」左の乳房が少し軽くなったので、右乳にうつる。「私たちのミルクは、もともと液肥です。森のためにあるんです」
「そうだったんですか!?」
「あとから、人間様達が美味しく飲めるように成分が再調整されたんだよ。それでも、ちゃんと肥料に近い成分も入ってるからこうして使えるの」
追いついてきたダークエルブンもシャツをはだけて、同じように大きな乳房を搾りはじめる。淡い色の乳首から噴き出したミルクはカフェオレ色をしていた。
「知らなかった……」
イグニスは目を丸くしたまま、エルフ達の授乳のようすをまじまじと見ている。バイオロイド同士とはいえ、おっぱいを噴き出すところを間近で観察されるのは慣れない。
「あんなに美味しくて、草木を育てられるものを、自分の体で生み出せるなんて、憧れてしまいますね……」噴き出すミルクを見つめたまま、イグニスがぽつりと言った。
「そんなに? あんただって立派なもの持ってるでしょうが」
「私のこれは、ただの断熱用なので。大きさだけはありますが」
「……忠告しますけど、オルカに戻ったらそれ大声で言わない方がいいですよ。ナイトエンジェルさんが爆弾積んで飛んできますよ」
「はあ。あの、皆さん時々そういうことを言いますが……ナイトエンジェルさんは真面目で繊細な、優しい方ですよ?」
「「えっ」」
胸からミルクを噴き出させたまま、真顔で見つめてきた二人のエルフに、イグニスはきょとんとして首をかしげた。
ミルクを撒き終え、植樹作業の続きに戻る。
「ねえ。アイツもしかして、意外とただ者じゃないんじゃ」
「いやそんな……そうかな……そうかも……」
エルブンとダークエルブンがひそひそと囁きかわすのも知らぬげに、イグニスはギアを装着し、コンテナを担ぎなおす。そしてふいに振り返って、やわらかく微笑んだ。
「今日ご一緒できて、本当に嬉しいです。前からエルブンさん達と、お近づきになりたかったので」
「へっ? あ、そうなの?」
「なんでまた」
「その……こんなことを言うと、不快に思われるかもしれませんが」イグニスは少しもじもじしてから、
「私とエルブンさん達は、少し、似ているところがあると思っていて。どちらも、人間のしてきたことの後始末をするために生まれたバイオロイドですから」
「はあーーー!?」
思わず、素の怒鳴り声が出た。「私達誇り高いエルフなんですけどおーーー!? 誰と誰が同類ですってえ!?」
「す、すみません、あの」
「気にしなくていいよ」ダークエルブンがニヤニヤしながらすかさず口を挟む。「こいつ、図星を指されるとムキになるから」
「ムキになんかなってませんけどおーーーー!?」
「はいはい、仕事仕事。イグニス、やるじゃん」
「は、はあ。ありがとうございます」
「ありがとうじゃないんですけどおーーーー!!」
バナナの樹をつかんだままアームをぶんぶん振り回す。根っこに付いた土が飛び散って、ダークエルブンとイグニスが顔をかばいながら笑った。
フォレストシリーズとイグニスは、旧時代、同じ年にリリースされた。環境汚染と森林破壊が深刻になり、このままでは地球は人類が生存できない星になる、という科学者の予測が世間を騒がせた時代だ。
実際にはその予測よりずっと早く人類は姿を消し、皮肉なことに、地球は緑豊かな星にもどった。樹を植えるべき土地も、燃やすべきゴミも、もうどこにもない。
この先人類の復活がはじまっても、エルブンやイグニスが本来の仕事で必要とされることは当分ないだろう。蘇った彼らが十分に賢明であれば、もしかすると永遠に出番はないかもしれない。そういう世界で、生きていかねばならない。
だから確かに、エルブンとイグニスは同類なのかもしれない。止めに入ったゲドをバナナの幹でぶっ飛ばしながら、エルブンは頭の片隅で確かにそのことを理解していた。断じて認める気はなかったが。
その後、オルカではほんの時たま、イグニスとエルブン達が一緒にいるところを見かけるようになった。
そしてもう一つ、
「胸の話をするときは、イグニスの近くにいるといい」
という謎のジンクスが、しばらくの間オルカで流行したのだった。
End
「それはそれとして、です」
コンスタンツァS2はテーブルに置いた小さな箱を前に押し出して、真剣な顔で言った。
「せっかく入手したこれを使わないのはもったいないと思うんです」
「夜中にいきなり呼び集めて、何の話かと思えば」
レオナが壁にもたれて、不機嫌そうにため息をつく。
小さな会議室に集められているのはアリス、レア、リリス、ソワン、アレクサンドラ。三安のメイドの幹部クラスが勢揃いした形である。さらに加えてブラックリバーからマリーとレオナ、PECSからオードリー、そして伝説からシャーロット。
箱の中には赤いアンプルがぎっしりと並んでいる。バイオロイド用強力媚薬「クライマックスオメガ」。先日、ファントムとシェードが廃工場に潜入して入手してきたものだ。
「その薬にまつわる経緯はわかりましたが」オードリーが形のいい眉をひそめて、手袋をした指先であごを撫でる。
「つまるところ、ラビアタさんは手術を受けたのでしょう? 問題は解決したのではなくて?」
「確かにお姉様の肉体の崩壊は止まりました。でも、それだけでは足りないんです」
ずい、とコンスタンツァは身を乗り出す。
「今のお姉様は、『まだ死ねない』と思っているだけです。私は、お姉様に『生きていたい』と思ってほしいんです」
「そのための手段が媚薬ですか? 少々、ロマンチックさに欠けるような……」
「ロマンチックとかこの際どうでもいいんです!」
どん、とテーブルを叩く剣幕に、手を上げたシャーロットが後じさって黙る。
「ご主人様に一晩愛していただくのがどういう体験か、ご存じでしょう。世界が違って見えます。生きる意味が変わります。幸せの定義が変わるんです。ここにいる皆さんなら、そのことを身をもっておわかりのはずです」
ぽっと頬を染める者、視線をそらす者、うつむいて表情を隠す者。それぞれがそれぞれの仕方で、コンスタンツァの言葉を雄弁に肯定した。
「わかりました、わかりましたから、すこし落ち着きなさい」
テーブルをばんばん叩きながらだんだん前のめりになっていくコンスタンツァを、アリスがなだめに入る。
「ラビアタの功績と献身はここにいる誰もが認めている。彼女が人生を手放すことを望んでいる者などいない」
全員の気持ちを代弁するように、マリーがきっぱりと言った。
「そのために閣下とその、愛を交わすのが有効だというのもわかる。しかし、実際どうする? その薬はもうラビアタに見つかっているのだろう。一度見抜いた企てに引っかかるほど、彼女は間抜けではないぞ」
「……それが問題なんです」
とたんにへにゃへにゃと座り込み、頭を垂れるコンスタンツァ。
「数日ずっと隙をうかがっていたんですが、チャンスは一度もなく……どうか、協力していただけないでしょうか」
「力ずくで押さえ込んで、無理矢理飲んでいただくとか?」とレア。
「この人数ならできなくはないだろうが、いくらなんでも大騒ぎになりすぎる。万一彼女が本気で抵抗すれば、オルカ内部が破壊されかねん」
「じゃあ寝ている時に、こっそり忍び込んで……」
「お姉様、独房の真ん中で剣を抱いて正座したまま寝るんです。近寄る隙がありません」コンスタンツァが悲しげに首を振る。
「基本に戻って、食事に混ぜるのは?」
「無理ですわ」
レアの問いかけにソワンが即答する。「ラビアタお姉様は独房に入って以来、水と最低限のツナ缶しか召し上がりません。ツナ缶に混ぜ物をしても、すぐ見破られてしまいますわ」
「注射しても効くのだったな? 戦闘に出して、隙を見て狙撃させるか」
「戦闘中の彼女こそ隙がないわ。第一、それでラビアタに効いたら、そのあと戦闘はどうするの」
「うーむ……」
「ふふん、皆さん難しく考えすぎなんですよ」
そこで、得意満面に進み出たのはシャーロットである。
「何か考えがあるんですか?」
「簡単です。陛下にお願いして、直接そう命じていただけばいいじゃありませんか」
「…………」
全員の沈黙を賞賛ととって、シャーロットがむふん、と鼻を鳴らす。
コンスタンツァが申し訳なさそうに、
「あの……シャーロットさん。お姉様はエマソン法対象外の特殊なバイオロイドなので、人間様の命令にも絶対服従ではないんです」
「……マジですの?」
「すみません。てっきりご存じかと……」
「等級限定の機密ファイルに載っているぞ。読んでいないな、お前」
「…………」
「やはり、力ずくでどうにかさせていただくしかないのでは?」
「そうですね……船底の爆発物保管庫あたりに誘い出せればなんとか……」
「万一、剣を持ち出されると厄介だな。フォーチュンにあらかじめ言い含めて細工をしてもらうか?」
「トロールスバードの整備は自分でしているわよ」
「むう、ダメか。ではせめて、戦闘に出して帰投直後の疲労したところを……」
「って、お姉様!?」
いつの間にそこにいたのか、ラビアタ・プロトタイプが腕組みをして戸口に仁王立ちしていた。
「コンスタンツァの姿が見えないと思ったら……オルカを率いるべきSS級バイオロイドが、媚薬をめぐって会議とは。恥ずかしくはないんですか」
「お姉様! 私は……」
「私はご主人様をお慕いしています。それははっきり言ったはずね、コンスタンツァ」
つかつかとラビアタはテーブルへ歩み寄る。皆が思わず道を開けると、卓上に置かれたアンプルケースをさっとつかみ取った。
「私があの方と臥所をともにしないのは、罪人の私にその資格がないからです。仮にこの薬で正気を失って、ご主人様とことに及んだとして、それで私が幸せになると思いますか」
「待て、ラビアタ。我々はなにも……」
「もう一度、ここではっきり伝えておきます。ご主人様の愛を受けることなど、今の私には痛苦でしかないのです」
ぴしゃりと言って、黙り込んだ一同をもういちど睨めわたしてから、ラビアタはケースを持って大股に出て行った。
しばしの静寂が流れる。引き留めようとなかば上げられていたコンスタンツァの手が、力なく落ちた。
「……皆さん。すみません。せっかく集まっていただいたのに……」
「ひとつ、考えがあります」
ここまで一言も発言しなかったアレクサンドラが、その時ぽつりと言った。
「私たち自身にもダメージがおよぶ方法なので、できれば使いたくはなかったのですが。お姉様がああまで頑固とあっては、致し方ありません」
「乗りましょう。それ」
ゆらり、と瞳に冷たい炎を宿して、音もなくブラックリリスが立ち上がった。「よりによってご主人様の愛を、愛をいただくことが痛苦ですって……?」
愛用の蘇州刀の背をつうっと撫でながら、ソワンも立ち上がった。
「いかにラビアタお姉様といえど、聞き捨てなりませんですわ。その思い違い、正して差し上げなくては」
アレクサンドラが静かにうなずく.三人の目が合った.その瞬間,何か姿のないおそろしいものが燃え上がるのを,コンスタンツァは確かに見た.
「皆様、協力していただけますね?」
黙り込んでいた他の面々が一斉にうなずいた。
「いいですか、まずここにいる私達で今晩から当分の間、ご主人様の夜の予定をすべて埋めます。そして……」
―――
最近不可解なことがある。
「今夜は少々、真面目な軍事論を交わしたい気分です。一晩、付き合っていただけませんか」
「子供っぽいと笑われるかもしれませんが……本を読んで、寝かしつけてほしいと前から思っていて」
「いいこいいこしながら、一緒に眠りに落ちるのが夢でした。試してみても」
寝室に来る部下達が、そろいもそろって夜の営み以外のことで夜を過ごしたがるのだ。
はじめは彼女達に嫌われたのかと思ったが、毎晩毎晩かならず誰かが来るし、行為に及ばないだけでべったりとくっついてくるので、そういうわけでもないらしい。バイオロイドには発情期の反対の何かでもあるのだろうか。そのくせ、ソワンはいつも通り、というかいつも以上に、精のつく料理ばかり出してくる。
彼女達を性欲のはけ口にするつもりは決してない。ないが、しかしこれまで毎晩……日によってはそれ以上のペースだったものが、突然完全になくなってしまうと少なからず調子が狂う。有り体に言って、ムラムラする。欲求不満だ。
「あの……ご主人様。今晩、お時間をいただけますか?」
だからコンスタンツァが声をかけてきた時は、正直嬉しかった。
一番付き合いが長い分、彼女の考えていることならある程度読める。あの目つきと表情は間違いなく、「そういうこと」を考えている顔だ。
自分でも不謹慎だとは思うが、ウキウキしながら一日の仕事を片付け、はやる気持ちを抑えて指定された第五寝室に向かった。タロンにも知られていない秘密の寝室の中でも、一番防音がしっかりした部屋だ。
しかし、そこで待っていたのはコンスタンツァではなかった。
「……ラビアタ?」
「ご主人様!? ……あ、あの、申し訳ありません、妹たちに騙されたようです……すぐ別の子を連れてきますので」
そそくさと立ち上がろうとする彼女を、しかし俺はとっさに手で制した。
目もくらむ、というか、目を離せなくなる、というか、とにかくこの上なく優美で扇情的なネグリジェだけを、彼女は身につけていた。先日よぶんなオリジンダストの除去手術を受けたというその肢体は、以前の圧倒されるようなボリュームこそ失ったものの、その分より均整のとれた、完璧な肉感とでもいったものを備えている。
ラビアタは能力だけでなく容姿も究極を目指して造られた、という話を今更のように俺は思い出した。確かに、目の前にいるのは究極の、抗いがたい、極上の女だ。
「…………」
「あの…………ご主人……様?」
ラビアタの瞳はうるんでいる。頬が赤らんで、唇が半開きになっている。姉妹というだけあって、コンスタンツァにどこか似ている。コンスタンツァが「そういうこと」を考えている時の顔に。
「ラビアタ」
「ごしゅ…………」
「先に謝っておく。すまない。もう我慢ができない」
その言葉をやっと口にしたところで、俺の理性は機能を停止した。
そこから何をしたのか覚えていない。思い出そうとしても、すべてが濡れた肉色の嵐の中に飲み込まれてしまっている。
意識がもどった時には翌日の昼近くになっており、俺はベッドから半分身を乗り出して床に倒れ込んでいた。どうやらベッドサイドの水差しを取ろうとして力尽きたらしい。
ラビアタはつぶれたカエルというか、地面に落として溶けかけたアイスクリームというか、そんな感じの状態でベッドにへばりつくように失神していた。尻だけが別の生き物のように、時折ヒクン、ヒクンと弱々しく痙攣している。
シーツは汗や涙やそのほか色々な体液で一面べっとりと濡れ、床や壁にもあちこちに染みができている。天井まで飛んでいるものもあった。要するに、相当に滅茶苦茶をしたらしいということだ。
「……っ♡……♡♡♡っ…………♡……」
声ともつかないうめきのようなものが、ラビアタの半開きの唇から漏れてきた。小一時間もすれば意識を取り戻すだろう。
あらためて、罪悪感がずっしりとのしかかってきた。俺はなんということをしてしまったのか.
彼女が目を覚ますまでに、せめて体を拭いてシーツを取り替えるくらいはしておかなくては、謝るにしても体裁が悪すぎる。俺はふらつく腰に力を入れてなんとか立ち上がった。
―――
目覚めたラビアタは平謝りする俺になぜか妙に優しく、何か気まずい事実を知ってしまったとでもいうように、そそくさと部屋を出ていった。
そしてその夜から、堰を切ったように部下達の夜の営みも復活し、結局何がなんだかよくわからないうちに、すべてはもとに戻った。
ただ、ラビアタについてはいくつかの変化があった。彼女はあれから、たまにではあるが独房を出て、もといたコンスタンツァの部屋で過ごすようになったらしい。俺は何も関与していないが、なぜかコンスタンツァから満面の笑顔で礼を言われた。
食事もツナ缶だけでなく、皆と同じ普通のメニューを、それも結構がっつり食べるようになったらしい。こっちは多少心当たりがあるというか、あの夜忘我の中で交わしあった睦言の中に、「以前のラビアタの体も魅力的だった」的なことも何度か言った気がする。無理しているのでないといいが。
それから関係があるかどうか知らないが、アレクサンドラ・リリス・ソワンの三人の関係がほんのわずかに改善したという。
「ご主人様。こちら今週のリストです」
あれ以来ずっと上機嫌なコンスタンツァが、仕事中手書きのメモをさりげなく差し出してきた。しばらく前から、夜に誰が寝室で待っているかは、希望者が合議のうえ輪番で決めるようになっている。行くか行かないかの最終決定権は俺にあるが、わざわざ待ってくれている彼女たちの気持ちを無下にすることなどできるはずもない。
メモにさっと目を走らせて、俺は思わず微笑んでしまった。
リストの下の方に、小さいが読みやすい彼女らしい字で、「ラビアタ」と名前があったからだ。
End
ねばつく細胞賦活ジェルから腕を出し、ポッドのふちにかけて上半身を起こす。脳神経が新しい肉体をいっせいに走査しはじめる、めまいのような感覚にも大分慣れた。
「うん、よし。違和感は特にない」
「はーい。お疲れ様、お兄ちゃん」
ドクターがタブレットを叩いてにっこり笑う。俺は体を拭いて、洗いたての制服に腕をとおした。
俺の体を鉄虫の侵食から救ってくれた人体再建装置は、年齢・体格それぞれ三パターン、計九種類の肉体モデルを作れるようになっていた。結局俺は標準体型の青年にしたが、あとでドクターが調べたところによると、俺の有機金属化された神経系はこの再建システムと非常に相性がよく、比較的簡単な手術で気軽に肉体を乗り換えられるらしい。
それならばと、残り8種類の肉体も作って、冷凍保存してオルカに運び込んでおくことにした。いろいろな自分のバリエーションが並んでいる光景は気味が悪くもあるが、大怪我や病気をした時の保険にもなる。ずっと凍らせっぱなしよりは、たまに動かした方がコンディションが良くなるとドクターがいうので、メンテナンスと気分転換を兼ねて、たまにそれらのボディに乗り換えることにしている。
「お早うございます、ご主人様」
「おはよう、司令官」
初めて乗り換えたときに驚いたのだが、俺の肉体が変わってもバイオロイド達はあまり違和感を持たないらしい。主に脳波で人間を識別するせいか、髪型や服装を変えることの延長くらいにしか感じないのだという。
ただそれでも好みというものはあるらしく、年齢・体格ごとに彼女たちそれぞれの反応は少しずつ違う。それに気づいてからは面白くなって、ボディを変えた日にはひそかに記録をつけ、人気の差を調べている。
一番人気があるのは標準体型の青年型、つまり俺が普段使っているボディだ。まあ大半のバイオロイドにとって同年代だし、一番親しみやすいのだろう。標準とはいいながらわりとしっかり筋肉がついていて頼もしく見える。
第二位は少し意外だが、太った中年型。コンスタンツァによれば、バイオロイドは基本的に人間に仕えるよう条件付けされているので、「目上の権威者」という認識のしやすい人物像を好ましく感じる傾向が強いという。確かに彼女は夜当番の時にこのボディだと奉仕が一際ねっとりとしてくる。LRLやアルヴィスなどのチビたちにもわりと人気で、この姿でいるとしょっちゅう飛びついてよじ登ってくる。
第三位は痩せた少年型。少年型は興味のない子と、どストライクな子にはっきり分かれる傾向がある。後者の代表はマリーで、特に女の子のように華奢なこのボディがたいへんな好みらしい。一度、大きな作戦が終わった時にご褒美としてこのボディで一日デートしたことがある。……彼女の隠された一面をよく知ることができた。思えば、盗撮回避のために秘密の寝室を複数つくっておくようになったのはあのデートがきっかけだった気がする。あの夜のことだけは、何が何でもタロンやスチールラインの面々に知られてはならない。
四位は痩せた中年型。歴戦のベテラン、という印象を与えるらしく、マリーとメイを除いたブラックリバーの上級士官たちにおおむね受けがいい。オードリーもこの体のためにスーツを仕立てたいと言っていた。反対に、子供達にはあまり受けがよくない。怖そうに見えるからだろうか。
五位以下はみな僅差だが、標準体型の中年型は年上好きを自認する大方の連中に人気だ。特に年上マッチョ好きには刺さるらしく、具体的に言うとマイティとスカディはこの体だと夜当番が一時間ほど長引く。あとエミリーに「パパ」と呼ばれたときはちょっとドキッとした。
、標準体型の少年型はチビたちの遊び相手として引っ張りだこになるので、少々疲れる。指揮官級やメイド長たちにもそこそこ人気で、マリーほどではないにせよ階級の高いバイオロイドは総じて少年を可愛がりたがる傾向があるようだ。
痩せた青年型は文学青年といった趣があり、トモやウンディーネなどロマンチックな恋愛に憧れてるような子達に受けがいい。決して口には出さないが、メイもこの姿でいるとひっきりなしにチラチラこっちを見てくる。
太った青年型はモモやバーバリアナなど、アイドル系の役者たちが親しみやすさを感じるという。かつての時代のファンにそういう体型の男性が多かったのだとか。それと、ラビアタも中年よりこの体が好みらしい。姉妹でも嗜好は違ってくるものだと、みょうな所で納得してしまった。
そして最下位は太った少年型。いま、俺が入っているボディだ。まあ俺だってデブの子供にあれこれ指図などされたくないから、気持ちはわかる。
もちろん最下位といってもあくまで比較しての話で、別にこの体でいると皆に避けられるというようなことは少しもない。逆にこの体の時に喜んで寄ってくるという子も少数ながらいて、
「ご主人様~! 今日もとっても愛らしいです! イチゴのタルトはいかがですか? フォンダンショコラも温めますよ!」
筆頭がこのアウローラだ。コロコロ太った子供を見るとお腹いっぱい食べさせたくなるらしい。
「じゃあ、タルトをもらおうか。一個だけな、これ以上太っては困る」
大きな声では言えないが、今年のバレンタインにもらった途轍もない量のチョコレートも九人分のボディを駆使してどうにか乗り切ったばかりだ。できればチョコレートは来年まで見たくない。
魔法のように出てきた絶品のタルトをサクサクかじりながら、アウローラと並んでオルカの展望廊下をぶらぶらと歩く。歩幅が普段の半分ほどしかないので、アウローラはゆっくり歩いてくれている。
「合わせてもらって、ごめんね」
精神というやつはどうしても肉体に引っ張られるのか、少年型ボディの時は油断するとつい言葉遣いが子供っぽくなる。アウローラはきょとんとした顔をして、それから破顔した。
「合わせていただいてるのは私達の方じゃないですか」
「?」
「その体をお使いになる日は、かならず私に会いに来て下さるでしょ」
そういえば、そうだったかもしれないが。
「今日はこの後、どちらへ?」
「書類仕事をすませたら、サニーの考えた新しいエクササイズというのを試してみるつもりだ。あとはイグニスが、ぽっちゃりした子供を抱っこして寝てみたいというから」
「そういうとこですよ」
「??」
なにが嬉しいのか、アウローラはくすくす笑いながら歩く。
「あ、司令官!」
「あそびましょー!」
ラウンジで本を読んでいたアルヴィスとハチコが、俺の通るのをめざとく見つけてパッと駆け寄ってくる。
「あーとーでー」
「「えー」」
不満げな二人にお菓子を渡してなだめてくれているアウローラに目配せで感謝しながら、俺は足早にラウンジを通り過ぎてブリッジへ向かった。
そういえば、せっかくエクササイズをするのだから、仕事中つまむ用にもう少し菓子をもらってもよかったかもしれない。せっかく作ってくれるのだし。次にこの体になったときは、もう少し腹をすかしてから会いにこよう。
ハッチへ続く角をまがる寸前、三人のはじけるような笑い声が、俺の背中を押してくれた。
End