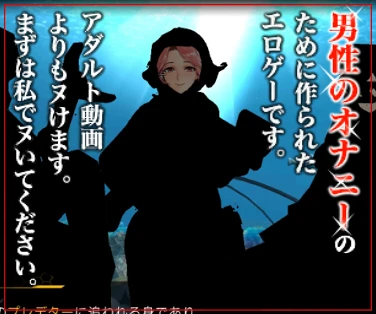撃ち出される銃弾を、空を舐める光の線が次々に灼き溶かす。光はそのまま、ジグザグに宙を駆ける白と黒のシルエットに襲いかかるが、青く輝く四枚の花弁が砕けちってそれを阻む。
不屈のマリーの思惟をうけて自在に飛ぶ四基の浮遊砲台「アイ・オブ・ビホルダー」は、先の先まで読み切った緻密なレーザー弾幕を展開し、ブラックリリスを完全に封じこめているかに見えた。
しかし一瞬、目の前に飛んできた瓦礫を蹴ってリリスは軌道を変える。針のようにまっすぐ向かってきた標的に対応できず、ビホルダーの一基が潰された。
一基分の隙ができた弾幕をかいくぐり、リリスはマリーに肉薄する。残った三基のレーザー砲がその姿を追うが、急所だけをロサ・アズールでかばったリリスに強行突破される。一呼吸の間に勝負はつき、黒光りする二挺の大型拳銃ブラックマンバが、銃身を交差させる形でマリーの喉元に突きつけられていた。
「……勝負ありだ」
マリーの苦々しげな声と同時に、周囲の建物、瓦礫、炎と土煙が一瞬で消え失せる。そこはオルカのトレーニングルームだった。
「これで……9勝13敗か。負けが込んできたな」
「鈍っているのではないですか?」
銃の撃鉄を互い違いに触れあわせる「残心」の構えをゆったりと解いて、リリスが言った。マリーは戦いの途中で吹き飛んだコートを拾って、肩に引っかける。
「鍛錬の時間は減らしていない。とはいえ、デスクワークが増えると、どうしてもな……お前の方は、動きが良くなっているようだが?」
「お姉様がようやく元に戻って下さいましたから」
リリスは機嫌よく微笑んでみせる。ラビアタが不在の間と独房に籠もっている間、三安のメイド全体の長姉役も兼任していたリリスだが、先日ラビアタがとうとう独房を出てくれたのだ。
「ようやく本来の仕事に専念できて肩が軽いのです。貴女も、そのはずでしょうに?」
「そうポジティブにばかり捉えられん、軍人はな」
対照的にむっつりと翳った顔で、マリーは首筋の汗をぬぐった。
かの無敵の龍が、封印艦隊を率いてオルカに加わった。これまで、最先任将校としてブラックリバー全軍を統括し、結果的にオルカ全体の戦力運用についても司令官の補佐を務めていたマリーは、その立場を否応なく彼女に明け渡すことになった。
彼女の階級、能力、実績を考えれば、当然のことではある。スチールラインの指揮に専念できて、肩の荷が下りた思いも確かにありはする。
しかし、軍隊的、組織的な価値観で生きてきたマリーにとって「降格」と感じる変化なのも確かであり、自分の裁量権が減ったこと以上に、司令官の傍らにいる時間が減った、ということがそう感じさせるのである。
「まあ、結構ですけど。そう何度も、貴女の憂さ晴らしに付き合う気はありませんよ?」
「ふん。……わかりやすいかな、私は」
「それを私に聞きます?」リリスもナースウェアの前を開けて手際よく体を拭きながら、失笑、という感じに笑った。
「私から見ればブラックリバーは皆さん、看板を下げているようなものですね。表情が読めないのはヴァルキリーさんくらい」
「ああ、まあ、あれはな……顔に出ないだけで、腹芸が得意なわけではないんだ」
「でしょうね」
第二次連合戦争当時、ブラックリリスは三安の切り札として、重要な任務にピンポイントで投入された。そして、最も多く与えられた任務の一つが、スチールラインの指揮官であるマリーの暗殺だった。
世界中の戦場で、マリーとリリスは何度となく命を奪い合った。勝敗はほぼ互角ではあったが、それはリリスがしばしばマリーと差し違えることを狙ったからで、指揮官と暗殺者が相討ちというのは、戦場においては敗北ということである。リリスはブラウニーや下級兵卒を捕らえ、目立つ場所でいたぶってみせることで、激高したマリーを誘い出す戦法を好んだという。
マリー4号自身も、戦争中は幾度もリリスと戦った。返り討ちにすることにこだわらず、退ければよし、としたのが、同型機との命運を分けたのかもしれない。
オルカが起動して訓練用ホロデッキを使えるようになってから、マリーは定期的にリリスをトレーニングに誘っている。お互い手の内を知り尽くした相手との試合はいい訓練になるし、かつてあれほど殺し殺され合った相手といま訓練で汗を流すというのは、なんだか奇妙な愉快さがある。
「指揮官同士、こうして折に触れ親睦を深めておけば、無駄な摩擦が生まれるのも避けられるだろう」
そう言うと、リリスはあきれ顔をする。
「戦ったら親睦が深まるとかいうその脳筋的発想、よしてもらえません? ブラックリバーだけですよ、そんなのは」
「ラビアタだってシャーロットと時々試合をしてるそうじゃないか」
「あれは純粋に訓練です。お姉様とあの破廉恥水着の親睦が深まるとか、おそろしいことを言わないで下さい」
人のことを言えた水着か、という言葉は飲み込んでおくマリーである。
「それより、グアムに着いたら妹たちに休暇を出しますが、よろしいですね」
「ああ。島の制圧と哨戒はスチールラインとヴァルハラで行う。ただ、フェアリーシリーズから何人か待機させておいてくれ。島中が密林みたいなものだからな」
「ダフネとレアに頼んでおきます」身づくろいを終えたリリスはため息をつく。「あの子達も森の多い島に着くたびに駆り出されて、可哀想なこと」
「エルフ達も行かせるが、あいつらは木の伐採を嫌うから開拓前提の探索には向かんのだ。仕方ないと思ってもらう」
「戦闘だけをしていればいい貴女たちと違って、私達の仕事は年中無休なのです。そのあたり、配慮してほしいものですが?」
「メイド達の精勤は認めるが、お前達の仕事はそもそも、皆がうらやむようなものであってだな……」
「こーんにちはー! トレーニングルーム使いたいでーす! なにコソコソ話してるんですか? 悪巧みですか? 痴話ゲンカですかー?」
ホロデッキ起動中のランプが消えたのに、いつまで待っても誰も出てこないので業を煮やし、ドアを強引に蹴りあけて飛び込んだネレイドは、冷えきった二組の視線に出迎えられた。
「あっ」
つかみを盛大に失敗したことにネレイドは気づいたが、もう遅かった。
「ネレイドさん」
ナースキャップを優雅に直しながら、リリスが優しく微笑んだ。「誰と誰が痴話喧嘩ですって?」
「いえあの」
ネレイドが慌てて振り向くと、一緒に来ていたはずのテティスはとっくに姿を消している。その肩に、革手袋をしたマリーの手がそっと置かれた。
「指揮官が着任して練度が上がったと思っていたが、その分規律が緩んだようだな」
「そうですね。マナーを教えて差し上げる必要もありそうですし」
反対側の肩にリリスの手が置かれる。ネレイドは死を予感した。
「トレーニングにいらしたのでしょう? 私達がお相手いたします」
「ひとつ、無敵の龍仕込みの腕前というやつを見せてもらおう」
「えっと今のは、軽いネリネリジョークというやつでですね」
「問答」
「無用です」
「あーーーーーーーーー」
数時間後、虚ろな目でホライゾン隊規をひたすら呟き続けるネレイドがカフェで目撃された。その傍らに、テティスがそっとお菓子を置いて去っていったのを見たという者もいる。
さすがにやりすぎたと思ったリリスとマリーが、賞品付きの水泳大会の開催を司令官に提案するのは一週間後、オルカがグアム島近海に到着してからのことである。
End
ノームです。
さっき、ひとつの命が奪われました。
数人のバイオロイドが、死体から皮を剥ぎ、はらわたを引きずりだし、骨から肉をそぎ、バラバラに切り刻んでいくのを、私は見ていました。
目の前では、大きな四角い鉢のなかに炎が燃えています。その上に油をぬった金網が掛けわたしてあって、じりじりと立ちのぼる熱気が、その向こうの海の風景をゆらめかせています。
きれいに洗って仕分けられた死体のひとかけらを、バニラさんが白いお皿に乗せて運んできました。お塩とごま油といっしょに。
「まずはレバ刺し、センマイ刺し、コブクロ刺しです」
「いただきまーす」
旧時代にグアムと呼ばれていた、新しい作戦区域に向かうあいだ、オルカは海上航行をすることになりました。
今いる区域からその島まではずっと海ばかりで近くに陸地がないため、鉄虫の危険がほぼないと判断されたからです。
長期間の海上航行ができるとなれば、換気も発電効率もまるで違ってくるので、潜行中はできなかったいろいろな活動ができるようになります。火や煙がたくさん出ることもその一つです。
「焼き肉がやりたい」
それを聞いた司令官様が、そんなことを仰ったのが発端でした。
かつての時代には、生の肉をテーブルに運んできて、お客が自分で焼いて食べる、という方式のレストランがあったのだそうです。野戦食みたいですね。
「ご自分でそんなことをなさらなくとも、私がいくらでも最高の焼き加減でお持ちします」
と、ソワンさんが反対したそうなのですが、結局は司令官様が押し切って。
折衷案として、
「生肉をそのまま食膳に上せるのはどうしても衛生面のリスクがある。試験的にまずバイオロイドが毒見をするべき」
ということになり、その役目に選ばれたのが私だったのです。
スチールラインのバイオロイドは胃腸が丈夫です。腐りかけのタマネギと水たまりがあれば一ヶ月戦えます。実際に私もやったことがあるので間違いありません。自慢ではありませんが、毒見役には最適といえるでしょう。
「んんっ……甘い…!」
生の牛レバーを食べるのは初めてです。レーションの中にレバーペーストが入っていたことはありますが、ぜんぜん味が違います。ぷるぷるした柔らかさの中に、噛むとぐっと固い歯ごたえがあって、それをザクッと噛みつぶすと、トロッと甘い濃厚な美味しさが口の中にあふれてきます。肝臓は栄養を貯めておくところで、滋養分が甘みになっているのだと、コンスタンツァさんが解説してくれました。
今日さばいた雌牛は、ずっと昔に野生化したのをヨアンナ島で試験的に捕まえて飼っているうちの一頭だそうです。こんな大きな動物を解体するところを見るのは初めてで、ついじっくり見入ってしまいました。本当は、肉というのはしばらく置いて熟成させると美味しくなるそうですが、私はただの毒見なのでもちろんそんなことはしません。切ったそばからいただいていきます。
センマイは黒っぽいひだひだが一杯重なっていてちょっと気味が悪いですが、食べるとクニクニと柔らかく、タレがよく絡んでお酒のつまみによさそうです。コブクロはコリコリと歯触りが面白くて、いくらでも食べたくなってしまいます。
「ミノ、ホルモン、ハツにタンです。付け合わせにサンチュもどうぞ」
いよいよ焼くやつが来ました。赤かったりクリーム色だったり、いろいろのお肉を熱くなった金網につぎつぎに乗せていくと、ジュウという音と香ばしい煙がもくもく立ちのぼって、海へたなびいていきます。ソワンさんが、わざわざ甲板にキッチン・ラウンジを設営した理由がよくわかりました。
「まずはタンを、ひっくり返さずに……と」
金蘭さんが食べ方のメモをくれたので、それにしたがって焼いていきます。牛の舌はさっき見た時あんまり大きいので驚きましたが、こうしてスライスするとソーセージか何かのようです。噛みしめるとよく締まった筋肉の中から美味しい肉汁が出てきます。ミノはさらに肉が締まっていて、目をとじて噛むと歯が筋肉を切り裂いていくザクザクという感触を味わえます。同じ締まった筋肉でもハツは柔らかくて、両面よく焼くとさっくりして、なんだかビスケットのよう。
ホルモンは脂をよく焼いて落としたものと、あまり焼かずに残したものと、二通り食べてみるといい、と教えてもらいました。まずは、あまり焼かない方を。
「脂がおいしい……!」
脂肪というのはこんなに甘いものなのでしょうか。フワフワと柔らかくてとろけるようです。
「じゃあじゃあ、よく焼くと……」
こんどはホルモン本体の薄くて軽い歯ごたえが前面に出て、しつこくなくていくらでも食べてしまいそう。脂肪がちょっと焦げてしまってカリカリしているのも、いいアクセントになります。
何度もひっくり返して、焦げ目が付くまでよーく焼いてみたり。次はあえて生焼けのままで食べてみたり。タレだったり、塩だったり、サンチュに巻いてみたり、いろいろな焼き方、食べ方を試していると、楽しくて美味しくて、お皿のお肉があっという間に消えていきます。時々、脂に火が移って燃え上がったり、失敗して焦がしてしまったりするのも、それはそれで楽しくて笑顔になってしまいます。
きっと「一番美味しい焼き加減」というものは確かにあって、私なんかが適当に焼いているだけではそこにはたどり着けないのでしょうけれど、焼き肉をしたくなる気持ちは、それとは別の所にある気がします。ソワンさんがいるのに、司令官様がわざわざ焼き肉をやりたがる気持ちが、なんだかすこしわかってきました。
「カルビ、ハラミ、ロースです。白いご飯も持ってきましょうか?」
「ください!」
内臓が終わって、本物のお肉が出てきました、もう止まりません。
ロースは一番いいお肉なので、満腹になる前に食べるようにと金蘭さんのメモにありました。塩と、タレと、レモンと、マスタードと、ネギ油と、順番に試します。美味しくてどれが一番とか決められません。
ハラミは横隔膜だそうです。膜なのに普通のお肉に見えるの不思議です。ロースより柔らかくてジューシーで、どれだけ噛んでも味が出てきます。私こっちの方が好きかもしれません。
カルビはタレに漬け込んだ肋の肉だそうです。味が濃いのと、タレがしみ通るまで時間がかかるので、一番最後に出すのだとか。
「むむ……!」
これはもう罪です。ご飯が止まりません。よく焼けた脂とタレが絡みあった、このしたたる汁だけでも一杯くらいいけます。
「ご飯おかわりください!」
サンチュと重ねると、爽やかさでまた味わいが変わります。二枚重ねて食べてみても面白いです。お肉。ご飯。お肉。ご飯。お肉。お肉。ご飯。
美味しくて、もっと食べたくて、お腹の中がぐつぐつ燃えるようで、手が止まらなくて、私は小さな火力発電所になったみたいです。
次のお肉の前に一度口の中をさっぱりさせようと、何もつけていない白いご飯をひとくち含んだら、なぜだか少し塩味がしました。それで初めて、私は泣いているのに気づきました。
「……あれっ」
ノーム型は、連合戦争末期に開発されました。
私たちの最初のモデルが目覚めた時にはもう、地球上に戦争と貧困のない地域はほとんど残っていませんでした。それからすぐに鉄虫が襲ってきて、そういう地域は一つもなくなりました。
私は平和な世界というものを知りません。飢餓と死体のない場所にいたことはありません。軍用糧食か残飯以外のものを食べたことはありません。私という一個体ではなく、ノーム型ぜんぶが、そうなのです。
だから、本当はわかっているのです。毒見というのは口実で、青空の下、おだやかな海の上で、おいしいものをお腹いっぱい食べる、そういう思い出をくれるために、司令官様は私を選んで下さったのだと。
「……デザートをどうぞ」
コンスタンツァさんが冷たいお茶と、アイスクリームをそっとテーブルに置いてくれました。
嬉しくて、幸せで、切なくて、お腹がぱんぱんで。うつむいてしゃくり上げながら、なかなか顔を上げられないでいる私の横で、アイスが海の日差しに照らされて、少しずつ溶けていきました。
後日。
焼き肉を食べた私はスチールラインでもうらやましがられました。次のベースデータ更新の時が楽しみです。これから先、オルカで生まれるノーム達はみんな、美味しい焼き肉の味を知っているのです。
ところで、レプリコンが気になることを言いました。
「旧時代の極東だと、焼き肉は精のつく食べ物で、そういうことの前や後に食べる文化があったんですって」
「……!?」
ソワンさんはこのことを知ってるんでしょうか。料理のことなら何でも知っているような人ですが、さすがに極東の大衆文化までは押さえていないかもしれません。知っていたらあんなに焼き肉に反対しなかったでしょうし。
「…………」
とりあえず、毒見でなにも異常がなかったので、司令官様は明日、焼き肉を召し上がるそうです。キッチン・ラウンジが同じ場所にあるなら、右舷中部ハッチを使われるはずです。ブリッジからあのハッチへ行く途中にはちょっと長い廊下があって、途中に仮眠室に使われる空き部屋があります。
明日はとっておきの下着をつけて、その仮眠室でこっそり待機しようと思っています。深い意味はありませんが。
もう一つ、幸せな思い出をいただいても、いいですよね?
End
「~Do you hear the people sing♪Singing a song of angry men♪~」
懐かしいメロディがふいに聞こえてきて、C-77レッドフードは顔を上げた。
ゆたかな金髪と、同じくらいゆたかなバストをリズミカルに揺らし、よく通る声で歌いながらカフェに入ってきた顔は知っている。伝説サイエンスの俳優バイオロイド、シャーロットだ。
「あら、お仕事中でした? ごめんあそばせ」
「いや、構わない。一段落したところだ」向かいに座っていたマリーが鷹揚に手を上げた。
伝説のバイオロイドは、レッドフードにとってはどうにも絡みづらい相手だ。劇にもショーにも興味はないし、ノリと情念で戦っているような連中ばかりで、レッドフードの軍人観からすれば失格というより問題外。そのくせ戦うとやたらに強いから、うっかり見下すわけにもいかない。積極的に話をしたい相手ではないが、たださっきのメロディはどうしても気になった。
「シャーロット殿、聞いていいだろうか。今の歌は何という名前なのか?」
「あら! 興味がおあり?」シャーロットは嬉しそうに笑った。「これはですね、『民衆の歌』といって、かのフランスの大文豪フーコーの『レ・ミゼラブル』に出てくる名曲ですわ」
「フーコーでなくて、ユーゴーです」
そのシャーロットの後ろから、アルマン枢機卿がひょいと顔を出した。髪のボリュームに隠れて見えなかったらしい。
「それに原典の小説ではなく、後年ミュージカルになった際のものですね。名曲なのはその通りですが」
「……細かいことを言わなくてもいいでしょ」
「フランスの歌だったのか。どうりでマリー隊長が歌っていたはずでありました」
口をとがらせるシャーロットを後目に、レッドフードはひとり納得していた。
ブラックリバーの初期の指揮官級バイオロイドは、歴史上の名将と言われた人物の思考パターンをもとに人格プログラムが組まれている。当時は、それが優れた指揮官を作る一番の方法だと考えられていたのだ。マリーは確か、フランスの著名な陸軍元帥がモデルになっていたはずで、ゆえに彼女はフランス人としての自己認識を持っており、フランスの物事には造詣が深い。
が、当のマリーは怪訝な顔をしている。
「私は知らないぞ?」
「ああ、いえ……そうか、隊長はご存じないかもしれません。昔の……マリー18号機という方がいらっしゃいまして」
「型番は聞いたことがある。確か、ユーコン川防衛戦を指揮した個体だったか」
「はい。私達の多くのモデルが、あの方の下で戦っていました。その方が、愛唱しておられた歌なのです」
何度となく聞いた勇ましい歌声は、レッドフード型の共通記憶としてメモリーに織り込まれている。思い返すと、自然と口をついて歌が出てきた。
――聞こえるか、闇の谷間にさまよう人々の歌が
――それは光へとよじ登る者達の歌
――おまえの胸の鼓動があの軍鼓の響きと重なる時
――明日新たに始まる命があるのだ
――すべてを差し出せ、それでこそ我らの旗は進む
――ある者は斃れ、ある者は生きるだろう
――おまえは立ち上がりチャンスを手にするか
――戦いに殉じた者達の血はフランスの野をうるおすだろう
「なるほど、勇壮な歌だな。私が気に入るわけだ」
マリーとシャーロットがぱちぱちと拍手をしてくれた。アルマンも拍手をしたが、すこし怪訝そうに首をかしげている。まあ本職の俳優であれば、素人の歌など聞くに堪えないものでもあろう。
「恐縮です。当時はただ丸覚えで歌っていましたが、まさか百年越しに曲名がわかるとは。再生はされてみるものでありますな」
「うむ。しかしな」マリーは首をひねった。
「私は自分の後期モデルとも何度か会ったが、そんな歌の話は聞いたことがない。聞かされたお前が覚えているほどなら、どこかで初期データに入りそうなものだが」
「それは……」レッドフードは言いよどんだ。「マリー18号隊長は、少し……何というか、変わったお方でありましたので。初期データには使われなかったのかと」
稼働中のバージョンの経験データを集めて、新しいバージョンの初期データセットの素材にする、というのは、バイオロイド生産においてしばしば使われる手法だ。一年前に再生されたばかりのレッドフードが、ユーコン川防衛戦を知っているのもそのおかげである。ただし、人格に問題があると判断された個体のデータは、当然ながらサンプルから除かれる。
「どんな奴だったんだ?」
「その……」
「失礼ですが、もしかして」アルマンがそっと手を上げた。「人間様への忠誠心がうすい、と見なされかねないような方だったのでは?」
「!……なぜ、それを?」
マリー18号機は防衛戦、それも極めて不利な状況下での防衛戦の達人として知られていた。そのため、数多くのレッドフード(ともちろん、その数十倍のブラウニー)が彼女の下へ送り込まれ、そして次々に死んだ。
かつてブラックリリス型との戦いで、頭に傷を負ったという。その傷のせいで脳に変調をきたしたのか、あるいは悲惨な戦いばかりで精神がすり減ったせいなのかは不明だが、彼女はマリー型にあるまじき厭世的な性格をしていた。
「この戦いは、はたしてバイオロイドを幸福にするのだろうか。このまま我々が人間に従うことは、よりよい未来へ繋がるのだろうか?」
そういったことを、少なくとも人間のいない場所では平気で口にした。督戦を任務とする立場から見れば、それははっきり敗北主義といってもよかったが、上層部に密告するようなことはレッドフードの主義に反した。何より、戦場ではどこまでも苛烈で献身的な、頼もしい指揮官であったから、彼女の下で戦い続けたかったのだ。
そんな彼女も、最後は鉄虫との戦いに身を投げ出すようにして死んでいった。あの歌を高らかに歌いながら、連結体の群れに突っ込んでいった背中を覚えている。それを目にした最後のレッドフードモデルも、それから数ヶ月とたたないうちに死んだ。
「……なるほど。それで理由がわかったかもしれません」
「理由とは?」
「先ほどの歌がおかしかった理由です」
アルマンは両手の指先を合わせ、そっと微笑んだ。
「レッドフードさんの歌った歌詞は、原曲の1番から3番までをまぜこぜに切り貼りしたものなのです。もとの1番はこう」
そして、鈴をふるような愛らしく凛とした声で歌い始めた。
――聞こえるか、民衆の歌が、怒れる人々の歌が
――それは二度と奴隷にはならぬ者たちの歌
――おまえの胸の鼓動があの軍鼓の響きと重なる時
――明日新たに始まる命があるのだ
――我らの軍に加わるか?
――力強く共に立ってくれる者は誰か?
――バリケードの向こうに、夢見た世界はあるのか?
――ならば戦いに加われ、自由になる権利を勝ち取るために!
「これは……」
「お聞きの通り、原曲は革命の……抵抗と解放の歌なのです」
スカートをつまんで優雅にお辞儀をしてから、アルマンは言った。
「おそらくマリー18号さんは、これをそのまま歌っては危険思想と見なされることがわかっていたのでしょう。だから歌詞を切り貼りして、ただの勇ましい戦いの歌に聞こえるようにして、みなさんに広めたのではないでしょうか。いつか、誰かが本当の歌詞に気づいてくれることを願って」
「…………」
彼女の、大きな傷跡のある横顔を思い出す。あの時、レッドフードはそんなことを想像もしなかった。同僚にも、部下達にも、気づいた者は誰もいなかっただろう。
「鈍い部下ばかりで、隊長はさぞかし落胆されたことでありましょうな……申し訳ありません」
「私に謝っても仕方なかろう」マリーが苦笑いする。それからおもむろに、革手袋の指で顎をなでた。
「なあ、レッドフードよ。この歌、むしろ今の私達に似つかわしいとは思わないか?」
「えっ?……ああ!」
二度と奴隷にはならぬ者達の歌。
闇の底から光へとよじ登る者達の歌。
自由を勝ち取るための戦いの歌。
これもまた想像もしなかったが、確かにこれは今のスチールラインの歌だ。司令官のもと、オルカに集って戦う兵士達の歌だ。
「ちょうど、教練の時に歌わせる歌が足りなくて探していたところだ。これも加えよう。人気があるようなら、正式にスチールラインの隊歌にしてもいい。どう思う、アルマン、シャーロット」
「素敵!」シャーロットがぱんと手を叩く。
「でしたら、音源を用意しないとなりませんね。楽譜があったかしら」
「私がデモテープを吹き込んで差し上げますわ!」
「異議なしであります。……ありがとうございます、隊長」
レッドフードは最敬礼をし、それからシャーロットとアルマンの方へ向き直ってもう一度ふかく頭を下げた。
「お二人も、ありがとうございました。お二人がいなければ、かつての隊長のお心をずっと誤解したままになるところでした。どうかこれからも、ご鞭撻をよろしくお願いいたします」
「あら、ご丁寧に。こちらこそ、よろしくお願いいたします」アルマンがにっこりと笑う。
「とりあえず、原典のミュージカル?でしたか、勉強しておきたいであります。オルカのライブラリにあるでしょうか」
「それはもちろん、古典ですもの。オリジナル版と、伝説アレンジ版と、どちらがいいですか?」
「……オリジナル版で」
その後、「民衆の歌」はスチールラインの教練歌に取り入れられ、ブラウニー達が歌いながら外縁デッキをランニングする姿がよく見られるようになった。
「歌詞がカッコいい」
「力づけられる」
「歌ってると頭がよくなったような気がする」
隊員達からの評判も上々であったが、残念ながら正式に隊歌に採用されるまでには至らなかった。
「そういえば18号には、ほかに変わったところはなかったのか?」
「そうですね……年上の男性が好みでありました」
「なにっ!? そんな奴の好みを取り入れて大丈夫かな……」
マリーとレッドフードがそんな会話を交わしているのを耳にしたレプリコンがいるが、そのこととの関連性は明らかでない。
End
あの人の腕の中で目覚めるのが好き。
私を抱きしめてくれる、あの人の腕が好き。
私の赤い髪を夢うつつに梳いてくれる、あの人の骨ばった指が好き。
「おはよう、メイ」
あの人の声で名前を呼ばれるのが好き。
頬にこすれる、あの人の胸のあたたかい肌触りと、体臭が好き。
目を開けるとやわらかい笑顔で見つめかえしてくれる、あの人の眼差しが好き。
朝のコーヒーはいつも、あの人が淹れてくれる。
メイはねぼすけになったな、なんて、あの人は笑うけれど、そんなことはない。ただ、あの人と寄り添ってまどろむ朝が幸せすぎて、いつまでもベッドから出たくないだけだ。だから先にベッドから起き出すのはいつもあの人の方。したがって、コーヒーを淹れるのもあの人の仕事、というわけだ。
コーヒーのあとはトーストを二枚と、ヨーグルトにフルーツを少し。二人とも、朝はあまり食べない方だ。
トーストをかじりながら朝のニュースに目を通すうち、だんだん引き締まって仕事の顔になってくるあの人の表情を見ているのが好きだ。
昨晩はあんなに激しく、しつこく、私をいじめて泣かせたくせに。今はもう、女にうつつを抜かしたりしませんよ、とでもいいたげな顔をしている。憎らしくて、ちょっとイタズラをしてやりたくなるが、前にいちどエスカレートして盛り上がってしまい、二人とも大遅刻して皆の笑いものになったことがあった。あんな恥ずかしい目は二度とごめんなので、我慢する。
ゆうべ作っておいたお弁当を渡す。家を出るのも毎日かならずあの人が先だ。私の方が身支度に時間がかかる、というのもあるけど、一番の理由は、
「いってくるよ、メイ」
「いってらっしゃい、あなた」
これが言いたいから。それと、いってらっしゃいのキスをしたいから。
私としては、結婚したときに退役して家庭に入ってもよかった(というか、いずれはそうしたい)のだけど、
「せっかく優秀なのだから、勿体ない」
とあの人が言ってくれるので、指揮官としての仕事は続けている。
もう鉄虫も散発的にしか出ないし、部下達もルーチンワークなら十分回せるようになったし、仕事といっても楽なものだ。今日もささっと業務を終えて、早めに帰宅する。掃除、洗濯、夕食の支度。家に帰ってからの方が忙しい。でも、あの人の帰ってくる場所をととのえているのだと思うと、それだけで幸せになる。
「ただいま、メイ」
「おかえりなさい、あなた」
おかえりのキスのあとは、すぐ夕食。私と違って、バイオロイド総司令官の仕事は激務だ。あの人はいつも腹ぺこで帰ってくる。
結婚するまで包丁なんて触ったこともなかったけど、SS級バイオロイドの演算能力をもってすれば料理を覚えるのなんて造作もない。今日のメニューは仔牛のシチューとかぼちゃのパイ。あの人は美味しい、美味しいと、ぺろりと食べてしまった。
夕食が済んだら、くつろぎの時間。あの人はソファに座って本を読む。私はその横に寝そべって、膝まくらをしてもらう。そこが定位置。
猫のように、ころころとひざの上を転がると、あの人がくすぐったそうに笑う。お腹に頬をすりつけると、あの人の匂いがして、細いけど力強い手がそっと髪と耳をなでてくれる。見上げると、微笑んでいるあの人と目が合う。
やがてあの人は本をわきに置いて、私を膝の上へやさしく抱き上げる。私は甘えて、されるがまま。昔から背が低いことは少しだけコンプレックスだったけれど。こうして膝の上にすっぽり収まって、顔の高さが同じになるのは、とてもいい。
背中に感じるあの人の息づかいと鼓動が好き。
耳元でやさしくささやく、あの人の声が好き。
あの人の手が、私のお腹の上にそっと組み合わせて置かれるのが好き。
手のひらの熱がじんわりと伝わって、お腹の下の方が温かくなってくると、女の一番大事な場所を預けているような気持ちになる。ふんわりと安心していくようで、ゾクゾクと高ぶっていくようで、相反する気持ちで私はいつも不安定になる。
でも、どれだけ不安定になっても、あの人の腕が包んでいてくれるから、私は大丈夫。
安らかで不安定な、その不思議な気分を十分に味わったあと、私からあの人の手にそっと手を重ねる。それが合図。
あの人の手が私の頬をなぜる。やさしくうながされるままに振り向くと、そこにあの人の唇がある。
熱くて甘くて優しい、世界一幸せなキス。
唇がふれあったまま、あの人の手がそっと私の肩に回されて、シャツを脱がしていく。私もあの人のたくましい背中に指をすべらせて……
「…………」
「……………………」
ナイトエンジェルは手を伸ばして、そっとディスプレイの電源を切った。
「……私達は呼ばれてオブザーバーになっただけです。何一つ罪はありません」
「そうですけどこれは……見てはいけないものを見てしまったのでは……」
ナイトエンジェルとダイカの見守るポッドの中には、安らかな寝息をたてる滅亡のメイの姿がある。その頭上のディスプレイに映し出されていたのが、二人がさっきまで見ていた光景であった。
封印艦隊と合流して以来、オルカの乗組員は大幅に増員し、カフェもホロデッキも混み合うようになってきた。そこで、より省スペースで効率的にストレス解消できる個人用娯楽設備をドクターが試作した。バイオロイドの脳波に同調し、潜在意識からのエコーを拾って結像したものを電子的に補強してシータ波として脳へ返す、要するに「願い通りの夢が見られる」というマシンである。
試験運転にはできるだけ高速の神経系を持つハイクラスのバイオロイドがいいというのでメイが選ばれ、装置や被験者に問題が起きないか監視するためにナイトエンジェルとダイカが呼ばれた。
「何かあったら呼んでね、何もないと思うけど」と、気軽にドクターが出て行ってしまった後、一応心拍数や脳波の表示に目を通していたら、モニタの一つに突然メイの夢の光景が流れ始めたのである。
「隊長がクソ恋愛弱者なのは知っていましたが、ここまで濃厚なお花畑だったとは」
「ま、まあ、夢があるのはいいことじゃないですか」
カプセルの中のメイはとろけそうに幸せな顔をして、だらしなく口元を緩ませている。時々ピクン、ピクンと体を震わせているのは、何を感じているのだろうか。
「でもこれ隊長、起きたらどうなってしまうのでしょう……」
「さっきまでの幸せな世界が全部夢だった上に、それを私達に見られていたとわかったら、という意味ですか? まあ、全力で私達に当たり散らしたあと、わんわん泣いて、それからなんとかしてすべてを無かったことにしようとするでしょうね。順序は違うかもしれませんが」
唯一救いと呼べるものがあるとすれば、仮想環境に登場する司令官(もちろん、ほとんどのバイオロイドの夢には司令官が登場するとあらかじめ想定されていた)は実際の司令官の思考・行動モデルを元に作られたという点だろう。すなわち、メイが勇気さえ出せば、この夢に近い一日を過ごすことも不可能ではない、とは言えるのだ。
「まあそんな勇気がこの人にあれば、最初からこんな機械に頼っていないでしょうけど」
へっ、とナイトエンジェルが冷笑したのと同時に、軽やかな電子音が鳴った。仮想環境を修了し、覚醒プロセスに入ったらしい。ドクターの説明通りなら、あと三十分ほどでメイが目を覚ます。
「あの私達、そろそろおいとました方がいいのでは……」
「そうですね。身の安全を考えるなら」
そそくさと席を立つダイカ。が、ナイトエンジェルは動かない。ドアに手をかけたダイカが振り向く。
「私は残ります、隊長の泣きっ面を拝みたいので」
「ですが、あの」
「それに目を覚ました時に、八つ当たりをする相手の一人もいないようでは、あまりに惨めですからね」
ダイカは微笑んで、ため息とともに何かを言いかけた。
「大佐は本当に……」
だがナイトエンジェルの切れ長の目がぎろりと光ったので、口を閉じて急いで出て行った。
ドクターの開発した催眠仮想環境誘導装置、通称「インキュバスD1」は、最初の被験者であるメイがなぜか激怒して泣きながら装置をめちゃめちゃに破壊した、という理由でお蔵入りとなった。
「よかれと思ってメイお姉ちゃんを呼んだのになー」
ドクターは不満げであったが、
「有機生命体の価値判断は不合理なものです。客観的に最善の結論が主観的にそうでないことは頻繁にあり、私は理解を放棄することがしばしばあります」
という通りすがりのスパルタンキャプテンのコメントで奇妙に納得し、以後開発を断念したという。
End
「勇気ある決意と共に、ゆけ!」
拳を突き上げ、両脚をふんばった力強い決めポーズに、わっと歓声が上がる。勇壮なファンファーレと共に幕が下りていき、俺は主演俳優をねぎらうために舞台袖へ移動した。
「お疲れ様、ランパート。かっこよかったぞ」
シャーロットの思いつきから始まったオルカ演劇会もすっかり定着した。今は「鋼の守護者ランパリオン」シリーズが大人気だ。かつての時代に、一般市民にも認知度の高かったランパートのプロモーションのために生まれた企画だという。
「ありがとうございます。しかし可能ならば、鉄虫の殲滅任務に専念できる環境を与えていただけることを希望します」
胸にライオンの顔がついた、いかつい姿のロボットが、階段をきしませながら下りてくる。どちらかといえばずんぐりした体形のランパートに、外装を取り付けるだけでここまでスタイルが変わるのは驚きだ。
「昇級してから初めての公演だったろう。何か変わったところはあったか?」
「はい。演算能力が増したため、舞台上で演技をしている間も並行して索敵情報にアクセスし、今後の戦闘計画をシミュレートできるようになりました」
ライオンの口の中にあるスマイルマーク(ここが彼の本来の顔だ)がチカチカと点滅して答える。
「演技中に他のことを考えてちゃ駄目だろ。アルマンが怒るぞ」
「何故でしょうか? セリフと動作の出力は台本で指定された通りに行っていました。ミスはありません」
「いや、そういうことじゃなくてな……」
先日のオーバーホールの際、フォーチュンがランパートの装甲材やアクチュエーター、一部の交換可能な回路などをより高品質・高精度のものに置き換える処置をほどこした。今のランパートはスペック上、シェードやギガンテスなどのS級AGSに近い性能を持っている。
性能が上がり、戦闘能力が増したのはいいことだ。ただ、俺はどうしても、以前彼にほどこした感情モジュール抑制措置のことが気になっていた。
ランパートは……正確には、旧時代に存在していたランパートの一体は、かつて痛ましい事件に遭遇した。死に瀕した人間の子供か、鉄虫に襲われている仲間か、どちらを助けるかの選択を迫られ、前者を選んで両方とも失うという結果に終わったのだ。その戦闘記憶をインプットされ、システムに無用の負荷がかかっていると判断したこのランパートは、スカディーに頼んで感情・共感モジュールの機能を抑制してもらった。平たく言えば、感情を捨てたのである。
それ以来、確かにランパートの戦闘スキルは向上した。警察署の廃墟を見て、わけもなく立ち止まるようなこともなくなった。しかし、それが彼にとって本当にいいことだったかどうか、俺は信じきれずにいる。
ランパートは戦闘以外のことに関心を示さなくなった。バイオロイドとすれ違うたび「おはよう、市民」と朗らかに声をかけることもしなくなった。この舞台だって以前は「市民との交流の一環」とかいって二つ返事で引き受けていたのが、今回はひどく難色を示し、結局俺が直接命令して参加させるしかなかった。昇級の際にも、もっぱら戦闘能力にかかわる動力系や装甲だけを強化してほしいと、ランパート自身から希望が出たという。
「……次の昇級はどうする? 戦闘系の回路はあらかた更新したが、それ以外のモジュールにまだ拡張の余地があると聞いてる。SS級になれるかもしれないぞ」
「不要です。戦闘に関わらない情報系統が増えることはかえってパフォーマンスを低下させます。現状がベストであると判断します」
「そうか……」
性能が向上して、本人も満足しているのだから、何も悪いことはない、とも言える。あんなにAGSを愛しているフォーチュンだって別に気にしていないのだから、俺の考えの方がおかしいのかもしれない。AGSはAGSであり、人間ではない。人間の考える幸せや不幸せが、彼らにとっても同じだとは限らないのだ。
それでも俺は心のどこかで思っていた。ランパートが捨て去ったものは、本当はとても大事な、捨ててはいけないものだったのではないかと。
そう思いながらも特に何もできずにいるうちに、オルカはグアムに到着し、そしてそこで俺はちょっとした事件に巻き込まれることになった。
同時にオルカも大変な事態に陥っていたのだが、俺がそれを知ったのはすべてが片付いてからで、だからランパートに起きたことも、すべてが終わるまで知らなかったのだ。
―――
ランパートは破損した脚部をのろのろと動かして、森の中を少しでも速く逃げようとしていた。
「頑張って、ランパート! もう少しだからね!」
「強き市民の盾よ! このサイクロプス・プリンセスがいるかぎり恐れることはないぞ!」
左膝のストリングプラーが損傷して、出力が30%ほどしか出ない。右脚は足首に銃弾を受けてセンサーが機能停止している。歩行も難しい状態だが、LRLとダッチガールが左右から支え、アルヴィスが後ろから押してくれるおかげで、なんとかヨタヨタと走ることができている。
しかし、当然ながら、追いかけてくるAGSの方がずっと足が速い。
「皆にないしょで島を探検に行きたい」
LRL達からそう言われたとき、ランパートは司令官に報告するか迷った末、結局自分がついていくことにした。戦闘以外の雑事に時間を割きたくはなかったが、司令官の時間を雑事に使わせる方が、より損失が大きいと判断したのだ。
三人はランパートが一緒に来ると知って大喜びしていた。理由は不明だが「鋼の守護者ランパリオン」の舞台公演がはじまって以来、年少のバイオロイドはランパートにひどく好感を持っている。
山あいの森に分け入って珍しい木の実を集めていた時、突然、一切の通信がつながらなくなった。すぐにオルカに帰還すべきと判断し、移動をはじめた時にはもう、周辺に所属不明のAGSが展開していた。
AGS群はこちらを遠巻きにして、散発的に攻撃をかけてくるだけで、積極的に攻めてはこない。しかしじわじわと包囲を狭め、特定の方向へ移動しようとすると執拗に阻止してくる。こちらを追い立て、孤立させようとしているのは明らかだ。
《……聞こ…………が……姉妹……》
通信機から時折、切れ切れの音声が聞こえるたび、アルヴィスが泣きそうな顔をする。今いる位置から一番近い味方はシスターズ・オブ・ヴァルハラのレオナ隊長が率いる部隊だ。わずかな通信内容から推測すると、彼女達も同様に攻撃を受けているらしい。だがAGSの巧妙な布陣によりそちらへ向かうことができず、逆にどんどん離れる方向へ追い立てられてしまっている。
「もう少しだ、もう少しだぞ、市民の盾よ! 尾根に出れば、きっとオルカと通信できて、たぶん……」
必死に励まそうとするLRLの声にも疲労が検知できる。
消耗はしているが、三人はまだどこも損傷していない。おそらくこの子達だけなら、このAGS群の包囲網をくぐり抜けてヴァルハラへ合流することも可能だろう。それをしないのは、ランパートがいるからだ。ランパートが重荷となって、三人は無為に敵から逃げ回る羽目に陥っているのだ。
そのように状況分析を終えたランパートは、すみやかに自爆すべきであると判断した。
「皆さん、離れて下さい」
ランパートは支えてくれている三人を振り払おうと腕を動かした。非常用に備えられた自爆プログラムのロックを外す。この子達に、あの時の自分のような思いをさせてはいけない。
「ランパート? どうしたの?」
「私は今から速やかに…………?」
今、なんと考えた?
あの時の、自分のような、思い?
ランパートの頭脳回路の中のどこかに火花が走った。二度、三度と走った。
そして、唐突にランパートは理解した。
ランパートは怖かったのだ。人間の命と仲間の危機の板挟みになり、どちらを選ぶべきか苦しんだことが。苦しみの果ての選択のせいで、どちらも失ってしまったことが。そして何より、いつかまた同じような苦しみに直面するかもしれないことが怖くて、それから逃げるために感情モジュールを捨てたのだ。
「ランパート? 大丈夫? どこか痛い?」
「……学習しました。これが『恐怖』」
もう長いこと使っていなかった回路を、次々と電子が走り抜けていく。固まった筋肉を伸ばすような、心地よい痛みに似た感覚とともに、認識が覚醒する。そして、ランパートはもう一つ理解した。
それから逃げてはいけない。立ち向かわなくてはいけない。たとえ、どれだけ怖くとも、それはランパート自身が。
私自身が向き合い、乗り越えなくてはいけないものだ。
「私が食い止めます……いえ」
私は脚を動かすのを止め、立ち止まった。肩を支えてくれていたLRLとダッチガールが心配そうな顔をする。この子達にこれ以上、悲しい顔をさせてはいけない。いや、させない。
「私と共に戦って下さい。ヴァルハラの皆さん達は、敵AGS群の向こう側にいます。突破して、合流しましょう。私達ならできます」
子供達の顔が、ぱあっと輝いた。私のメモリーの最深部に、その笑顔が自動的に記録された。
「………うん!」
センサーが敵の接近を知らせている。フォールンとポップヘッド、ドローンの混成部隊が、あと数秒で視認できるだろう。
武器はない。右手は下腕がまるごと焼失しているし、両脚にも損傷がある。かろうじて無事なのは左手のシールドだけだ。
だが負ける気はない。死ぬ気もない。ただ、決意だけがある。
今のような笑顔を守るためなら、私はどこまででも強くなれる。だって私は市民の盾、ランパートなのだから。
「学習しました。……これが『勇気』なのですね」
最初のフォールンが、木立の向こうから姿を現した。私とアルヴィスが盾を構える。その後ろでダッチガールがドリルの出力を上げ、LRLが左目の眼帯をはずす。
その時、ずっと試みていたオルカとの通信が一瞬だけ復旧した。
《……聞こえる!? 増援は…いけど、……を射出したから! それで、何とか……》
ノイズだらけのフォーチュンの声が聞こえて、また途切れる。同時に、私のセンサーが敵AGS群とは別の、高速で接近する物体をとらえた。
それは背後の、オルカのあるはずの方角から、マッハを超える速度で飛行してくる。補助カメラで上空をサーチするより早く、背後にいたLRLが空を指さした。青空をまっすぐに切り裂いて、ずんぐりした戦闘機のような形状のものが見える。先端についているライオンの顔が見える。私はあの姿を知っている。よく知っている。
「あれ、ハイパーライオンだ! ランパート、ハイパーライオンだよ!」
ダッチガールが叫んだ。私にも歓声を上げる機能があったなら、そうしていただろう。
「はい。アルヴィス。十秒だけ、ここを支えてもらえますか」
私は左手の盾のジョイントを外し、迫り来るAGS群へフリスビーのように投げつけた。先頭のフォールンに命中し、群れの前進が一瞬だけ止まる。その隙を突いて、腰のアクチュエーターをフル稼働させ、全力で空へ跳び上がる。
「ガードアップ! コード・ハイペリオン!」
私の声に応えて、ハイパーライオンが急角度で私の方へ向きを変える。その胴体がバラリとほどけるように展開して、全身に装着するためのアーマーに変形していく。
敵AGSの対空機銃が私を追い、何発かがボディをかすめるが、構ってはいられない。私とハイパーライオンの軌道が交差した瞬間、ライオンの両目がまばゆい閃光を放った。単なる演出効果だが、今の場合目くらましの役には立つ。
光の中で、ボロボロになった四肢をエクステンド・アーマーが覆う。
「ラン!」
対人コミュニケーターヘッドがライオンの口から現れ、インジケーターが青い燐光をはなつ。
「パリ!」
予備センサーを収めたサブヘッドが起動し、アイカメラが起動する。
「オォーーーーーン!!」
「「「鋼の守護者だあああああああ!!!!」」」
地上で見上げる子供達が、目を輝かせて叫んだ。
ポップヘッドの一体を踏み砕きながら、地響きと土煙を上げて私は着地した。
フォーチュンとドクターの謎のこだわりにより、このアーマーはギガンテスの外装の予備パーツを使って作られており、間に合わせの戦闘用外骨格としては十分な強度がある。さらに舞台上での動きをサポートするために、関節各部に補助モーターが備えられており、損傷した手足もある程度動かせる。
現状の戦闘能力は、平常時にくらべおよそ80%。だが、それで十分だ。
「残り20%は、勇気で埋める!」
台本のセリフがメモリーから勝手に出てくる。無意味な創作上の言葉だと思っていたが、今ならわかる。これはシグナルだ。弱き者を守るために力をふるう、どこまでもそうする決意を固めた己であるという表明なのだ。
身体が熱い。駆け巡る電流で回路が火花を散らしている。胸のオイルが沸騰しそうだ。
「ランパリオン! くるよ!」
「よっしゃああああああ!」
機銃を片手で防ぎつつ、踏み込んで回し蹴りで一体。肘打ちで一体。膝蹴りで一体、計三体のフォールンを立て続けに仕留める。
両膝と背部バインダーに装着されたタングステンブレードが分離し、右腕に放射状に装着される。同時に、右腕が高速で回転を始める。
関節部がひどく摩耗するので、舞台でもあまり使わなかったのだが、肘から先が完全に損壊してアーマーだけになっている現状なら何の問題もない。そう、たしかスクリュー・マグナム・パンチとかいう大仰な名前がついていた。ならば今はさしずめ、
「ブロウクン(壊れた)・マグナム・パンチ!!」
回転しながら発射された右下腕部がランパート型二体を貫通し、さらに中央のギガンテスに突き刺さって、すぐさま逆噴射して戻ってくる。後方のセルジュークからの砲撃は、
「なんのっ!」
ライオンヘッドが電磁反射粉末を放出し、ダメージを最小限に抑えた。アルヴィスとダッチガールがすかさず左右のフォローに入ってくれて、背中に飛びついたLRLをぶら下げ、熱帯の背の高い木々のあいだを駆け抜ける。
上空から視認したかぎり、交戦範囲内の敵AGSは十四体。うち六体はすでに叩いた。残りは後衛のドローンとセルジュークのみ。
右前方から砲撃が飛んできた。セルジューク型だ。大丈夫、この程度の火力なら想定の範囲内だ。切り抜けられる――
二体のセルジュークが、まとめて踏み潰された。
「!?」
大地が揺れ、木々が砕け散る。頭上に重い影がかかる。
セルジュークを踏み潰した巨大な脚の上には、それ以上に途方もなく巨大な鋼鉄の顎と、赤く凶暴な光をたたえた眼があった。
「タっ……タっ……」
LRLがひきつった声を上げる。激しい熱風が吹きつけて、私の身体がよろめく。それすらも、奴の鼻息にすぎない。
「タイラント!」
T-αタイラント。連合戦争の悪夢。全高十メートルにおよぶ鋼の巨竜が、私達の前にそびえ立っていた。
こんなものがいたのか、この島には。さすがにこれは、勇気でどうにかなる相手ではなさそうだ。
だが諦めたりはしない。どんな状況でも、光に向かって手を伸ばすことを諦めない。知恵と勇気の限りを尽くして、希望をつかみ取る者、
「それが、勇者だ!」
子供達を両手に抱え、身をひねって、巨大な顎の初撃をなんとかかわす。
「ぴぃっ!」
という悲鳴は、背中にぶら下がったLRLのものだ。奴の牙一本が、私の体の半分ほどもある。あの顎に捕らえられたら、私達など小骨のように噛みちぎられてしまう。
まともにぶつかってはいられない。大きなガジュマルの木の背後に入った隙に、私は抱えた子供達を降ろした。
「ここからできるだけ奴の気を散らせてくれ。それから、全力で逃げる準備を」
「ランパリオンはどうするの?」
「一か八かの賭けをするのさ。頼んだぞ、みんな!」
木の陰から飛び出す。タイラントがこちらへ向き直った。巨大な顎を一度、二度とかわす。一度でも避けそこねたら終わりだが、アルヴィス達がうまく牽制してくれている。
苛立ったタイラントが尻尾で何度も地面を打ち、動きを止めた。上体を高く上げたと思うと、尾から喉元へ、赤い光が何度も駆けのぼる。
「今だあああああっ!」
両手を組み合わせて前へ突き出す。マグナム・パンチ用のロケットブースターの出力を臨界まで上げる。
巨大な顎が振り下ろされ、喉の奥に赤い輝きが見えたその一瞬を狙って、私は両腕のブースターを最大噴射し、同時にアーマーをボルトアウトした。ランパリオンの外装が、まるごとタイラントの口の中へ突っ込み、プライマルファイアの砲口を塞ぐ。
ゴアッ……!!
爆炎があたりを焼き払う中、苦痛とも怒りともつかない咆吼が空気をビリビリと震わせる。私は脚のスラスターを全開にして後退し、脱出するLRL達に追いついた。
「さらば、ハイパーライオン!」
「やっつけたの?」
「まさか! さあ、全力で逃げますよ!」
ズシン、ズシンと、のたうち回るタイラントの地響きが伝わってくる。0.3トン分の超カーボネートチタンの塊が、六枚のタングステンブレード付きで口の奥に飛び込んだのだ。いかに暴君といえども、小骨が喉に刺さった程度には効いただろう。
異物を噛み砕き、吐き出したタイラントが、怒りのプライマルファイアであたりを焼き払ったのは、それでも私の試算より二秒ほど早かった。だがその頃にはもう私達は十分な距離を稼いでおり、やがて木立の向こうにシスターズ・オブ・ヴァルハラの白いコートが見えて、アルヴィスが喜びの声を上げた。
―――
一連の事件のあと、事態の全貌を把握し、皆をねぎらって回るのは大仕事だった。何しろどの部隊もまわりと連絡が取れず、個々の判断でてんでに動いていたから、あらゆる部隊の報告を順番に全部聞くしかなかったのだ。
しかしその中でも、ランパートの報告以上に驚かされたものはなかった。
「共感モジュールが復活しているだと?」
「はい。もともと削除したわけではなく、機能を抑制していただけでしたが……その抑制が勝手に外れています。こんなことが起きるはずはないんですが」
レポートを持ってきたスカディーも戸惑っている。
「自分でも理由は説明できません。ただ、そうしなくてはならないと強く考えた途端、それまで封鎖されていた経路が復旧したのです」
ランパート自身にも、よくわかっていないらしい。ただ、修理とともに軍用迷彩から元の白と青のカラーリングに戻したランパートは、以前よりも何というか、生き生きしているように見えた。ロボットに向けるのも妙な言葉だが。
「何にせよ、ちび達を守ってくれてありがとう。しかもタイラントと戦って無事だったなんて、大金星だ。望みがあったら何でも言ってくれ」
「ありがとうございます。ではお言葉に甘えて、二つ、よろしいでしょうか。一つは、以前にお話をいただいた、SS級への昇級処置をお願いしたいのです」
「おっ、その気になってくれたか! わかった、フォーチュンに頼んでおこう。もう一つは?」
ランパートは返事をせず、右手のマニピュレーターを意味もなくクルクルと回転させた。それがどういう意味を持つのかわからないが、俺の目にはなんとなく、彼が決まり悪がっているように見えた。俺はニコニコしながら待つ。彼が何を言うつもりなのか、なんとなくわかった気がしたからだ。
やがて、ランパートはそれまでより少し音量を下げた声で言った。
「……ハイパーライオンをもう一度作っていただけないでしょうか。可能ならば次回公演に間に合うよう、大至急で。次の公演では、ずっとよい演技ができると思うのです」
End
「あ、そうだった」
俺はふと思い出して、ベッドサイドに手を伸ばした。
「どうか……なさいましたか……?」
汗で額に貼りついた髪をぬぐって、ヴァルキリーがのろのろと顔を上げる。
「いや、ドクターがこの部屋に、新しい装置をつけてみたとかでな」
ナイトテーブルに置かれたよくわからない機械のスイッチを入れてみると、突然部屋が消えて、俺たちのベッドは夜の海へ放り出された。
「きゃっ!?」
ヴァルキリーがびっくりしてこちらへ身を寄せる。俺も思わず体を固くしたが、よく見ればもちろん部屋はある。壁と床と天井、いちめんに立体映像が投影されているのだ。
「へえ……」
合成映像なのだろうが、おそろしく良くできている。まるで部屋をガラス張りにして、本物の海の上に置いたようだ。月が雲間から照らし、遠く近く揺れる波をちらちらと輝かせる。通り過ぎていく波の音、時折遠くで魚が跳ねる音が聞こえる。真下に目をこらすと海面近くに何かがゆらめくのが見えて、ちょっと怖い。
スイッチの横についているダイヤルを回すと海が消えて、こんどは見渡す限りの草原が現れた。サアッという音と共に、夜風が草原の上を、月光を跳ねかえす銀色の波になって渡ってくる。
もう一度回すと、森の中になった。熱帯雨林だろうか。うっそうと茂る木々の葉の向こうをうろつく動物の、ざわざわという気配と息づかいが聞こえる。
「こりゃすごい。ヴァルキリーもやってみないか」
「いいのですか? では、失礼して……」
俺の体ごしにダイヤルへ手を伸ばすヴァルキリーの、白い脇腹と汗のういた背中を眺める。
「あ……本当。楽しいですね、これ」
ほどなく、俺ごしに腕を伸ばした不自然な体勢から、もそもそもそ、と移動して座り直すヴァルキリー。どうやら気に入ったらしい。このタイミングで思い出せて良かった。もう一ラウンド終えていたら、彼女に余計なことをする体力は残っていなかっただろう。
雪原、湖畔、山の上、洞窟の中。一体何パターンあるのか、回すたびに違う風景が出てくる。どれも夜なのは、艦内時間に合わせてあるのだろう。しばらく二人で次々に風景を切り替えて遊んでいたが、途中で気がついた。
「ヴァルキリー、広いところ嫌いなのか?」
高原だの砂漠だの、広々とした風景が出てくると、明らかに切り替えるのが早い。ヴァルキリーは俺の方を見てちょっと赤面した。
「嫌いというほどではないのですが。見晴らしのよすぎる地形は、すこし苦手で……不安になるんです。習性かもしれません」
「習性……ああ、スナイパーの」
「はい」
確かに、スナイパーが周囲から丸見えの場所にいたくはないだろう。しかしそれでは、好きな地形もあるのだろうか。聞いてみると、
「身を隠していられるけれど、まわりはよく見える地形……でしょうか。山頂の岩陰ですとか。そういうところは、安心できます」
「なるほど。狙撃手というのは大変なんだな」
漫然と装置をいじっていると、ヴァルキリーが俺を見上げて、肩に手を置き、少しだけ爪を立てた。
「ミホさんも同じか訊いてみよう、とかお考えになっているでしょう?」
「えっ、いや、その」
「……別に、構いませんけれど」
図星を突かれて、俺は苦笑いしながらダイヤルから手を離した。
マングースチームの狙撃手、マイペースで勝ち気なミホは一見ヴァルキリーと正反対の性格に見えるが、深く知ってみるといろいろとよく似たところが多い。同じ狙撃手同士、ということなのだろうか、戦いの後などにふと見せる表情など、姉妹かと思うほどそっくりなことがある。じゃあ二人が親しいかというと、別にそうでもないようなのが面白いところだ。
それと彼女達にはもう一つ共通点があって、どうもふしぎに気が置けないというのか、俺は自然体でその、お近づきになってしまうことが多い。二人とも、こういう関係になるのはオルカの中でもかなり早い方だった。それも他の子達のように満を持して、という感じでなく、気がついたらなんとなくそうなっていた気がする。レオナが最近までそれを知らなかったせいで、ヴァルキリーは先日彼女にしこたま怒られたと聞いた。
狙撃手というのは隊を離れて単独行動することが多いので、規律や上下関係よりも自身の判断を重視する性格にプログラムされると聞いた。そのあたりがバイオロイドの一般的な気質と少し違う、まるで人間と付き合っているような印象を与えるのかもしれない。
もちろん、二人が忠誠心や奉仕の心を欠くなんてことはないし、他のバイオロイドが人間らしくないなどということも断じてない。だいたい、俺には人間の恋人も友達もいたことはないのだから、この印象が本当に正しいのかわかりはしないのだが。
「……お疲れになりましたか?」
いつの間にか、ぼんやりと物思いにふけっていたらしい。ヴァルキリーが心配そうに声をかけてきた。
「ああ、いや、すまん。そんなことはないよ」
笑ってみせて、彼女の腰を抱き寄せる。が、ヴァルキリーはそっと俺の胸に手を添えてそれを制した。
「ご無理をなさらないで下さい。ここのところ、長い作戦が続きましたから。今夜はもう休みましょう」
「ン……いいのか? でも……」
「たまには、私も意識のはっきりした状態で添い寝をしてみたいです」
起き上がりかけた俺を寝かしつけるように、ヴァルキリーがくすくす笑いながら体重をかけてくる。俺はされるがままに、枕へ頭を沈めた。ころんと頭を回すと、壁の向こうでは雲が音もなく渦を巻いて流れ続けている。
「じゃあせっかくだから、寝付きのよさそうな風景を探してみるか。選んでくれるか」
これはこれで見応えはあるが、落ち着いて眠れる風景とはいえない。ヴァルキリーがダイヤルに手を伸ばし、風景がまた何度か切り替わって、止まった。
満点の星空。
銀色の月光に照らされて、青白くほのかに輝くような雪原が、どこまでも広がっている。音もなく、動くものもない。
「……やっぱり、雪景色が一番落ち着きます」
「ずいぶん見晴らしがいいようだけど、いいのか?」
「ここに身を隠していれば、安心ですから」
そう言うと、ヴァルキリーは俺の腕の間にもぐり込んできた。背中をぴったりと俺の胸に押しつけ、枕にした腕を抱え込んで顔を隠すようにすると、振り返っていたずらっぽく微笑む。
俺は空いている方の手で毛布を胸まで引き上げて、自分とヴァルキリーの体をすっぽり包み込む。満足げなため息が聞こえた。
「おやすみ、ヴァルキリー」
「おやすみなさい……」
ひんやりしたヴァルキリーの肌が、毛布の中で温まっていく。呼吸がだんだんゆっくりになる。腕にかすかに吹きかけられる彼女の寝息を感じながら、俺もとろとろと目を閉じていった。
眠りに落ちる寸前、そういえばなぜドクターが特にこの部屋を選んで装置を据えつけたのか、ヴァルキリーに説明しなかったのを思い出した。
まあいいだろう。俺はそのまま、安らかに意識を手放した。
ヴァルキリーとよく使うこの部屋はとびきり壁が分厚いが、それでも声が漏れるというので対策として環境音を流すことになった。そのついでに、壁の中にいろいろと音響以外の機器も仕込んだのだなどと、彼女は聞いたら傷ついてしまうだろうから。
End
「北岸の情報、どうなっているか!」
《伝令がもうそろそろ帰ってくるかと……あ、あれです、走ってきます!》
「急がせろ! 二十分前の情報が最新では、何をどこへ出すかも決められんぞ!」
マイクへ怒鳴りつけ、無敵の龍は苛立たしげに髪をかき上げた。「中世の戦争だな、これでは!」
グアム島最大の港。旧時代の名をアプラ港という。
軍港地区の乾ドックが生きていたのをさいわい、ここで出航以来初めての大型オーバーホールに取りかかっていたオルカは、上陸部隊との突然の通信途絶から数分後、正体不明のAGS群の攻撃を受けた。
元々オルカ自体に戦闘能力はほとんどない上、今は乗員の三分の一近くを欠き、何よりも司令官が不在にしている。文字通り、陸に上がった魚も同然である。敵の射程圏内に入ってしまったら最後なので、湾全体に広く遠く防衛線を敷くしかない。近距離無線すら使えない状況下で指揮権を預かる龍は、ひっきりなしに伝令を走らせ続け、人力で戦術情報を集めるという方法をとった。
「AGSをもっと水門に展開させろ! 鉄虫ではないのだから、海からも来るぞ!」
オルカ内部の通信環境は生きているので、こうしてブリッジで指揮を執ることはできる。だが本来ならほぼリアルタイムの戦場マップが描かれるはずのメインスクリーンに表示されているのは、伝令の報告をいちいち口頭で聞いて手で入力した、十数分も過去の情報だ。戦線までの距離によって遅延の度合いは異なるし、こちらの命令が向こうに届くまでにも同じだけの時間がかかる。それらすべてを計算に入れて的確な指示を出すのは、指揮官級バイオロイドの頭脳をもってしても簡単なことではない。
「桟橋のマングースはそろそろ限界だろうな。交替要員の用意は……ゴールデン・ワーカーズとウォッチャー・オブ・ネイチャーか。ラビアタ、誰を何名送れば同等戦力になる?」
「オードリーは何でもできるけれど、防衛戦の指揮にはあまり向かないわ。トリアイナを隊長にして、ウォッチャーの二人に、ドローンを多めに付けて行ってもらうのは? ああ見えて責任感の強い子だから、任せれば大丈夫」
「よし。聞こえたな、コンスタンツァ」
「はい、もうハッチに向かってもらっています!」
龍はこの艦に着任してまだ日が浅く、部隊の癖も飲み込んでいない。それ以前に、三安やPECSの家庭用バイオロイドまで含んだ混成部隊などという出鱈目なものを指揮した経験はないのだ。独房から引っぱり出してきたラビアタを補佐に、なんとか回している有様である。
「アーセナルさんから第4次伝令です。南東のプラント跡と、そこまでの道を制圧。増援はこのルートで送ってほしいと」
「よし、流石だな。待機させていたキャノニアの第三、第四分隊を向かわせろ。着いてからは向こうの指示に従うように」
「バミューダチームからの救援要請はどうする? 持久力はない子達よ、休ませないと」
「シティガードがまだいる。二手に分けて、片方をバミューダ分隊の援護に向かわせろ。そうだ、西側の住宅地跡のだ。ランパートがいない? フォールンでも何でも足しておけ!」
怒鳴り終えて、龍は傍らの椅子に身を投げ出す。今ある情報で出せる指示はすべて出した。次の伝令が来るまで、ほんの数分だが息がつける。
「どう思う」
「遊ばれているわね」
傍らのラビアタに視線をやると、彼女は即答した。
群盲象を撫でるがごとき戦況把握しかできなくても、わかることはある。どうやら敵は、本気でこちらとやり合うつもりはない。引けば押し、押せば引いて、決して全容を掴ませないようにしながら、翻弄されるこちらの隙をついて少しずつにじり寄ってきている。
よりによって歩兵部隊の中核であるスチールラインとヴァルハラ、双方の大半が島内に出払っているのが痛恨だった。彼らならば、この程度の戦術に踊らされはしないだろう。ブラックリバー以外の隊員達は、個々の戦闘能力こそ優れていても、戦いの中で相手の戦術や意図を感じ取り、戦線としてそれに即応するということにかけてはどうしてもワンテンポ遅れる。能力の高低ではなく、軍隊としてのマインド・セットが身についているか、という問題だからだ。
「時間稼ぎか? それとも単に、余裕があるから無理せず進めているだけなのか?」
「両方かもしれないわ、少なくとも、私達には焦る理由があるのだから」
《〈無敵の龍〉、アルバトロスだ。北東の山腹で爆発を確認。熱源パターンに特徴がある。97%の確率で、タイラント型が活動している》
「!」
龍は椅子から跳ね起きてメインスクリーンを見た。
防御力と飛行性能、そして情報処理能力が卓越しているアルバトロスには、限界まで延長した通信ケーブルを引きずってオルカ上空に滞空してもらい、観測と索敵を任せている。普段は司令官以外の命令を決して聞こうとしないアルバトロスだが、こんな見張り気球のような役目を文句も言わず引き受けてくれたのは、さすが最高位AGSともなると状況を読んで融通を利かせるくらいのことはできるらしい。龍が恥ずかしがっている肩書きをわざとつけて「無敵の龍」といちいちコールしてくるのは、彼なりの意趣返しなのかもしれないが。
アルバトロスからの、こちらは正真正銘のリアルタイム情報が反映されたスクリーンには、大きな赤い光点が一つ。そして、色も大きさも同じだが、やや輝度のうすい光点がもう一つある。
「アルバトロス、二つ目の光点は何だ?」
《タイラント型が存在する前提で、一時間前までの熱源観測データを再分析した。パターンが62%一致する熱源反応がもう一つある。確実に報告できる段階ではないが、推測を述べよう。おそらく、タイラント型は二体いる》
「タイラントが二体……!」
ラビアタの顔が青ざめる。その手が傍らに置いた大剣の柄をぎゅっと握った。
「抑えろよ、ラビアタ。お前は切り札だ。ここにいてもらわねば困る。艦隊とリンクできない今の私では、オルカに何かあっても守りきれんのだからな」
「わかっているわ」
彼女が何を心配しているのかはよくわかる。最大の問題はオルカへの攻撃などではないのだ。
上陸した司令官の行方が、いまだにわからない。その一事だけで、オルカの戦闘能力は半減していると言ってもいい。
彼は現存するただ一人の人間であるという以上に、オルカの精神的中心だ。オルカのバイオロイド全員が、程度の差はあれ司令官に好意を寄せていることは龍にもすぐに見てとれた。龍自身はまだ日が浅いゆえにそこまでの気持ちはないが、これまで出会った人間達の中で、最も心地よく従える相手なのは確かだ。
「少なくともSS級が一人、A級が二人随行していたのだろう? 上陸した連中だって、全員司令官の安全を最優先に動いているはずだ。そう心配することもない」
「わかっています……わかっているのよ」
気休めだとしても、そう言うしかない。お互い、それもわかっている。
「西岸部隊からの伝令、来ました。データ入力……え、これ?」
オペレーターを務めるコンスタンツァが驚きの声を上げると同時に、戦いが始まってからずっと沈黙していた通信ユニットが激しい雑音を流しはじめた。耳をつんざく音にまじって、かすかにバイオロイドの声らしきものが聞き取れる。
「通信が復旧したのか?」
「いえ、これは……」
《〈無敵の龍〉、アルバトロスだ。タイラント型がまたプライマル・ファイアを使った。おそらく、それにより発生した電磁パルスが、妨害電波網を一時的に乱している》
「何が幸いするかわからんな。友軍の信号を拾え! 断片でも何でもいいから、拾えるだけ拾うんだ!」
「ほとんど音声は……あ、でも位置情報だけなら」
コンスタンツァがコンソールに指を走らせると、あっという間にスクリーンが光点で埋め尽くされた。よく見ると光点のそれぞれには、オルカ隊員の認識IDがついている。
「上出来だ。ラビアタよ、お前の部下はよく鍛え込まれているな」
「自慢の妹達ですもの」
自分のIDに位置と時刻情報を乗せただけの数十バイトの情報なら、ナノ秒あれば送ることができる。通信が一瞬でも復活する可能性にかけて、絶えず送信を続けていた隊員がこれだけいたということだ。
「だが。細切れにされすぎている……」
スクリーンを睨んだ龍の眉がくもる。出発時に把握していたよりも、味方がひどく分散している。敵の分断戦術の結果だろう。そして、司令官に同行しているはずのエルブン達の信号もない。
「……もしご主人様の身に万一のことがあったなら、あの子達はそれこそ死んでも私達にそれを伝えようとするはず。信号がないだけなら、状況は良くないけど最悪ではないわ」
龍の思考を読んだかのように、ラビアタが青ざめた顔で、それでも決然と言った。
「戦術情報、艦内各部署に共有します。……救援に向かいたいという要請が、複数来ましたが」
「向かえるものなら向かっている。それより次の伝令はまだか」
「あと数分で、北岸の……あ、もう一件フォーチュンさんより、カタパルトの使用要請です」
「何だ、こんな時に!」
「さっきの信号で、ランパートが子供達と一緒に上陸していたのがわかって、オプションパーツを送りたいとか」
「オプションパーツ?……まあいい、カタパルトくらい好きに使わせろ。ここのAGSはどうなってるんだ」
「たぶん、LRL達の保護者としてついていったんでしょう。あの子達ったら」
「来た時から思っていたが、オルカは自由すぎる……いや待て、カタパルト? カタパルトがあるんだな?」
「ちょっと、何を考えているの」ラビアタが眉をひそめる。「スカイナイツでもないのに……あ、でもSS級なら、射出までは平気かも……」
「コンスタンツァ、救援に出たいと言ってるのは誰と誰だ? SS級だけを発艦デッキに向かわせろ。フォーチュン! カタパルト、他のも全基開けろ。緊急発進用の反磁シェルを人数分用意できるか」
《聞いてたわ! 無茶苦茶だけど、やってみせましょう》
「弾丸ども! いいか、お前達の仕事はバラバラにされた味方をつなげることだ。敵の攻撃が厚い方へ行けば味方がいる。走り続け、叩き続けろ!」
《了解!》
《ですわ!》
《えっ、あの、弾丸? すみません、これどういう》
反磁シェルに包まれた銀色の輝きとなってカタパルトから射出されるハイパーライオンとポックル大魔王、ほか数名のバイオロイド達を見送り、龍達は戦線の指揮にもどる。絶え間なく駆け込んでは駆け戻る伝令が、さらに二往復した頃、今度はグレムリンがブリッジに飛び込んできた。
「スチールラインオンラインです!」
「はあ?」
「SLOのチャットが使えるんです! なぜかというと!」
「ちょっとグレムリン、落ち着いて。SLOってあなた達が遊んでるゲームよね? それがどうしたの?」
グレムリンの(興奮したギーク特有の、情報量が多いわりに要領を得ない)説明を聞くうちに、龍とラビアタの顔色がみるみる変わる。話が終わる前に、龍はマイクをつかんで怒鳴っていた。
「全軍に通達! 今すぐスチールラインオンラインにログインしろ! やってない者はアカウントを作れ!」
数分後、戦線全域で連携が復活し、オルカは包囲網を押し返すことに成功する。
さらにそこから数十分後、司令官とフェザーがロバートを破壊したことにより島内全域で敵性AGSは活動を停止。通信妨害も止まり、戦闘は終結した。
「お前が味方でよかったと、つくづく感じたよ」
沸き返る歓声がひっきりなしに響き続けるブリッジで、龍は深々とシートに沈み込んだ。顔にかかってぼさぼさになっていた前髪を、今更のように手でなでつけながら、傍らのラビアタを見上げる。
「お互い様ね」
ラビアタも微笑んで、隣の空いていたオペレーター席に座る。汗でぴったりと腕に貼りついてしまった長手袋を引きはがすように脱いで、ぱたぱたと手を振って熱を逃がした。
「あれだけ性格も能力もバラバラなバイオロイドの個性を逐一把握して戦力化するなど、私にはできん芸当だ。私のように指揮モジュールを詰め込んでいるわけでもないのに、どうやっているんだ? 人間のいう、地頭がいい、というやつなのか」
「いやだ、あまり持ち上げないで。あなたの指揮あってこそじゃないの」
疲労困憊した二人のバイオロイドは、しばらく座り込んだままクスクス笑っていた。
「……なあ、考えたことはないか? もし、かつての世界で、我々が今のように……」
「詮無いことよ」
龍のつぶやいた言葉を、ラビアタは静かに遮った。
「そうだな……」
ばたばたと、ブリッジの外の廊下を走る足音が聞こえる。防衛線の部隊が帰還しはじめたらしい。間もなく、ここもまた騒がしくなるだろう。龍は立ち上がってうんと伸びをした。
「さて、閣下が戻られるまでにもう一仕事だ。まったく、統帥権を返還するのがこんなに待ち遠しかったことはないな」
「大活躍だったもの、きっと労っていただけるわよ。素敵なご褒美だっていただけるわ」
「褒美? 馬鹿な」続々と到着する戦闘報告の長いリストから目も動かさず、龍はフッと鼻で笑った。
「バイオロイドが主人のために働いて、なんで褒美をほしがるものかよ。一晩ぐっすり眠らせてもらえたら十分だと、閣下にはそうお伝えしてくれ」
「あら、そう?」
ラビアタはそれ以上何も言わず、だまってリストの整理を手伝い始めた。
のちにマリーから「司令官のご褒美」の意味を聞いた龍は、このときの返答を死ぬほど後悔することになるのだが、それはもう少し後の話である。
End
2101ねん3がつ18にち あめ
きょう、あたらしいけいさつのバイオロイドがきました。アニーというバイオロイドです。ふくとあたまがあかいです。
わたしは、ミスセーフティがよかったとおもいます。
パパは「アニーはセーフティよりずっとせいのうがいいんだ」といいます。なんでセーフティじゃないのかきいたら、そんなことをいうんじゃないとしかられました。
2102年5月1日 はれ
アニーが果じゅ園のどろぼうをつかまえました。トラックでにげるどろぼうを、大きなバイクで追いかけてつかまえました。どろぼうはずっとマンゴーをぬすんでいたので、みんな大よろこびしました。どろぼうは大人のひとたちが知らないところへつれていきました。
パパが、アニーがきてから村があんぜんになったといいました。わたしはアニーがこわかったです。てっぽうでうたれて血がでているのに、ニコニコわらっていたからです。
2103年1月13日 雨
またどろぼうがトラックでやってきました。アニーがじゅうでやっつけました。せんそうがはじまったので、どろぼうはどんどんふえるだろうけど、アニーがいるからだいじょうぶだと、パパとママが言いました。どろぼうなんかいなくなればいいのにと思いました。
2106年8月13日 はれ
アニーが毎日、子供をのせてパトロールしている。小さい子だけでなく、同い年の男子にも乗りたがる子がいる。ガザリもムハマドもバカみたい。アニーなんかにデレデレしちゃって、あんな大きいだけのみっともないバイクに夢中になって。バイオロイドなんかに夢中になって先が心配だと、町のおばさんも言っていた。
2108年7月21日 はれ
小さいころ、町へ行くと、大きなビルや役所の前にはみんなミス・セーフティが立っていて、私は彼女の浅黒い肌と、キリッとした物腰が好きだった。
いまの州知事は三安産業とべったり癒着している。学校では教えないけど、みんな知っていることだ。だから三年前から、どこの村でも町でもPECSのバイオロイドを見かけなくなった。私の好きだったセーフティも、どんどんいなくなってしまった。
年中お金がない、お金がないとしか言わない村の大人たちが、高価な三安のアイアンアニーなんか買ったのも同じ理由だ。
アニーはセーフティと正反対だ。小柄で子供っぽい顔だし、髪も肌も白人のようだ。控えめできちっとしたセーフティと違って、明るくてうるさくて、いつでも笑っている。そういう風に作られている、というだけの意味しかないのだけど。
私は三安なんか大きらいだ。アニーもきらいだ。
2109年3月18日 曇り
アニーが乗り回しているバイクに、馬鹿みたいに大きなマフラーがついた。反重力バイクは排気ガスなんか出さないから、ただの飾りだ。アニーが村に来て八年目の記念日だというので、ガザリがわざわざ自分の鋳物屋で、古いガソリン式オートバイのパーツを仕入れて加工したそうだ。前から自分のバイクをデコりたがっていたアニーは大喜びで、記念にバイクに「プレスリー」と名前をつけた。ガザリがプレスリーのファンだから、ということらしい。くだらない。
2111年5月29日 晴れ
村議会にアニーを加えようという話が出ているらしい。長年村の治安を守ってくれたアニーはもう村の一員だ、とかなんとか、年寄りたちが言っている。馬鹿馬鹿しい。そりゃあ十年もいれば村にも慣れるし、村中の誰とだって顔馴染みにはなる。だからって、バイオロイドを村会議員に? 国じゅうの笑いものになるだろう。
2111年5月30日 晴れ
鉄虫とかいう怪物が、世界中の都市を襲っているというニュースを見た。人間を狙って殺すので注意しろ、だって。アニーの銃と、お爺さん達の猟銃くらいしか武器のないこの村で、何をどう気をつけろと言うんだか。
2111年6月7日
私の名前はアイーシャ・ビンティ・アブダラーです。サラワク州のベマンという小さな小さな村に住んでいる学生です。
今日、私たちの村に鉄虫が襲ってきました。突然のことで、誰も対処できませんでした。村で戦えるのは警官バイオロイドのアイアンアニーだけで、彼女は勇敢に戦いましたが、鉄虫はどれだけいるのかわからないくらい沢山いて、アニー一人ではとても敵いませんでした。
アニーはできるかぎりのことをしました。村の皆を集会所に集めて、少しでも時間を稼いで川沿いに逃がそうとしていました。でも川の反対側からも鉄虫がやってきて、集会所の人たちは皆死んでしまいました。私はたまたま避難が遅れたせいで助かって、アニーは私をバイクに乗せて逃がしてくれました。
私はバイオロイドのセーフティに憧れていて、セーフティでないというそれだけの理由でアニーが嫌いでした。アニーも私に嫌われているのを知っていたはずなのに、他の人たちと何も変わらず、笑顔で話しかけてくれました。
バイクはアニーの宝物です。アニーが村に来てちょうど八年目に、私の幼馴染みで鋳物屋のガザリが、大きなマフラーを付けてあげました。アニーは喜びのあまり泣いてしまって、それ以来バイクにプレスリーと名前を付けて、すごく大事にしていました。
それほど大事なバイクに、アニーは迷わず私を乗せました。オートパイロットで、自動でミリ市に向かってくれると言っていました。
「きっと大丈夫だからね」
と笑ったアニーはその時もう血だらけで、でも怯えきっていた私は彼女を気遣う言葉ひとつかけず、バイクにしがみついていました。
村の方角に火が見えます。ラマとスリダンの方角にも。きっと鉄虫にやられてしまったのでしょう。アニーはまだ生きているでしょうか。
アニーは十年間、ひとりで、ベマンの村を守り続けてくれました。つらいことや嫌なことも沢山あったはずなのに、毎日笑顔を絶やさず、村中をパトロールする彼女のことを、私以外、村の人たちはみんな大好きになりました。みんな彼女を家族のように思っていました。村会議員として村の運営に加わってもらおうという話もありました。アニーが聞いたらきっと喜んだでしょうけれど、もう聞かせることはできなくなってしまいました。
ごめんなさい、アニー。つまらないことでずっと貴女を嫌っていて。
アニー、ごめんなさい。貴女が最後に助けたのが、私なんかで。
もしももう一度会えたら、貴女に会って、謝りたいと思います。
ミリ市の明かりが見えてきました。でも、火の手が上がっているように見えます。畑の向こうに赤い光が動いています。だんだん近づいている気がします。ここにもいるのかもしれません。
てっ
ページのほとんどが抜け落ちた、茶色く朽ちてボロボロの日記帳を、アイアンアニーは壊れないよう注意深く、そっと閉じた。
「あなたの遺伝子の種を回収した際、近郊で反重力バイクの残骸が見つかりました。その隙間に挟まっていたものです」
「この日記を書いた人は……?」
「人骨の痕跡らしきものがバイクの側に確認されましたが、それ以上のことは何も」
「……」
うつむいたまま動かないアニーを、共振のアレクサンドラは静かに見つめた。
エニウェアシリーズは三安の中でも例外的に多様な分野のバイオロイドが集まったブランドだが、アニーはその中でも例外中の例外だ。彼女はシティガードのシェアを奪うため……より正確に言えば、PECSと対立したことで生じた、治安維持業務というシェアの空白を埋めるために作られた。エニウェアから発売されたのは、三安にほかに適当なブランドがなかったからにすぎない。
アレクサンドラモデルは他のどのエニウェアシリーズとも同僚として同じ家に仕えたことがあるが、唯一アイアンアニーとだけはその記憶がない。他のメンバーに至っては、一面識もない者がほとんどだろう。これから共に鉄虫と戦っていくにあたり、彼女が本当にエニウェアに馴染めるか、どのようなポジションを任せればいいのか、見定めるのは彼女の義務である。
長いこと黙っていたアニーがようやく、目元をぬぐって顔を上げた。
「私は、幸せ者だったんですね」
「……そうですね」
アイアンアニーは人口の少ない田舎に配備されることが多かった。バイオロイド慣れしていない住民が多かったせいか、同朋のように扱ってもらえることも少なくなかったという。もっともそうした田舎にはたいてい、治安維持を担うバイオロイドはアニー一体しかいなかったため、鉄虫が勢力を拡大しはじめると瞬く間に全滅してしまったそうだが。
再生されたばかりのアニーにこの日記を見せることが、はたして良い影響を与えるかどうか、アレクサンドラは測りかねていた。しかし、
「彼女には見る権利がある」
という司令官の言葉があれば、逆らう理由はない。そして、今の言葉と彼女の表情を見る限り、それで正解だったようだ。
「……さきほど、残骸と言いましたが」
アニーから日記帳を受け取り、保護ケースにしまいながらアレクサンドラは言った。「マフラーなど外装の一部は、比較的良い状態で残っています。もし希望するなら、新造したあなた用のバイクに移植することもできるそうですが、どうしますか?」
「お願いします!」アニーは即座に答えて立ち上がる。
「よろしい。では各部署への挨拶回りを終えてから、工房へ行って現物を見るといいでしょう。艦内規則は頭に叩き込みましたね?」
アレクサンドラは満足げにうなずき、滅多に見せない、柔らかい笑顔を浮かべた。
「ようこそ、オルカへ。エニウェア・チームは、あなたを歓迎します」
End
日課のジョギングを終えてブリッジに戻る途中、コンスタンツァを見かけた俺は思わず声をかけた。
「お早うございます、ご主人様。ご用は何でしょうか?」
「いや、ご用というほどのものじゃないんだが」
用はない。声をかけてしまったのは、何とも言えぬ違和感を感じたからだ。
どことはっきり言えないが、いつものコンスタンツァと何かが違う。髪型ではない。香水でもない……。
じろじろ見つめられて、コンスタンツァは恥ずかしそうにうなじの後れ毛をととのえた。その手首のカフスを見て、俺はようやく気がついた。
「君は、いつもブリッジにいるコンスタンツァじゃないな?」
目の前のコンスタンツァはぱっと顔を赤らめ、それから嬉しそうに両手を顔の前で合わせた。
「おわかりになるのですか? はい、私はコンスタンツァS2・290です」
気づいてみれば簡単なことだ。オルカに所属しているコンスタンツァは一人だけではない。俺が来る前からレジスタンスには百人近いコンスタンツァ型がいたらしいし、俺が来てからも何十人か再生されたり、新たに合流したりしている。
「もしかして、『俺』を探してくれた探索隊の一人?」
俺は彼女のカフスを見ながら言った。勘違いでなければ、それはグリフォンのゴーグルの部品だ。
「はい」コンスタンツァ290はほんの少し寂しげに微笑んで、カフスに指をそえた。「私達の分隊は、残念ながら成果がないまま鉄虫に遭遇してしまいました。私は逃げ延びたのですが、グリフォン達は……」
「……すまなかったな」
以前マリーに聞いたところでは、俺を探すために98個の分隊が派遣され、そしてそのほとんどが帰ってこなかったという。謝ってどうなることでもないが、俺はそう言わずにいられなかった。
「とんでもないことです。ご主人様の探索に加わったことは、コンスタンツァ型全員の誇りです」
コンスタンツァがまた、ほんの少し微笑んだ。
嘘をつかぬよう、しかし自分の感情が決して相手の重荷になることのないよう、完璧に調整された、ほんの少しの笑顔。なるほど、彼女は間違いなくコンスタンツァだ。「俺の」コンスタンツァは、最近あまりそういう顔をしなくなったけれども。
「君は、ヨアンナ島から来たのか? オルカにいるコンスタンツァは一人のはずだよな」俺は話題を変えようと、強いて朗らかな声を出した。
「あ、はい。常勤しているコンスタンツァは416だけです」
彼女も少しほっとした顔で、胸元へ手を当てる。
「私は物資搬入の付き添いで参りました。原則として、各モデル一人ずつだけがオルカに勤務することになっていますので」
それは知っている。というか、俺がそう決めたのだ。日々どんどん増えていくバイオロイドの誰をオルカに残し、誰を後方支援に回すかは、俺がオルカに来てそう経たないうちに問題になった。議論は紛糾したが、最終的には全隊員が「自分たちのモデルのうち誰か一人はオルカに置いてほしい」という意見にまとまったので、それに従うことにした。操艦・雑務スタッフや、特殊な役割を持った一部の戦闘員を除いて、オルカにはレジスタンスにいる全機種から一人ずつが集まっている。
「そういえば、その一人はどうやって決めてるんだ」
「基本的には先任優先ですが……持ち回りのこともあります。半月か一月くらいで、定期的に交代している子達が結構いるそうですよ」
「そうだったの!?」
全然気がつかなかった。みんないつも同じ個体だと思っていたのに。
「オルカ勤務は皆の憧れなんです」コンスタンツァがあわてた様子で付け加える。
「誰もがご主人様のお側に仕えたいと思っています。指揮に支障が出ないよう、戦闘データなどは入念に引き継ぎを行っています。どうか、お目こぼしいただければ……」
「ああいや、責めてるわけじゃないが……うん? じゃあもしかして、コンスタンツァも?」
「いえ、21分隊の隊員は特別です。ご主人様を発見した功績がありますので、交代したりはしません」
よかった。俺の目もそこまで節穴ではなかったようだ。
しかし、俺は自分で思っているよりもはるかに、バイオロイド達の献身と気遣いに支えられて暮らしているのだ。あらためて思い知る。
「じゃあ、他のコンスタンツァやグリフォンはオルカに来る機会がないんだな」
「はい。その分、こうして仕事がある時には優先的に……あら、いけない!」
コンスタンツァは眼鏡のつるに手を当てた。「申し訳ありません、もう行かなくては」
「仕事の邪魔をしてしまったな。ありがとう、ためになる話が聞けた」
「いいえ、ご主人様とお話できて、嬉しかったです」
深々と頭を下げて、優雅にスカートのすそをひるがえしたコンスタンツァが、ふと足を止めて振り返った。
「私達を見分けて下さったこと、416にも話して差し上げて下さい。きっと飛び上がって喜びます」
290の言う通りで、ブリッジに戻った俺が、コンスタンツァ416(当然、彼女は最初からそこで俺を待っていたのだ)にその話をすると、彼女は飛び上がって喜んだ。比喩でなく、本当に飛び上がった。
「嬉しいものなのか?」
「これが嬉しくないバイオロイドなんていません!」コンスタンツァは勢いよくうなずいた。
「個体としての私達には、本当にわずかな違いしかありません。それを見分けるほど私達をよく見て下さる人間様は、かつての時代にもほとんどいませんでした。それは、私達一人一人を一個の人格として見て下さるということですから」
「そんな大層なものじゃないが」俺はなんだか照れくさくなってしまった。「ただなんとなく、違和感があったというだけだ。それと、カフスが違ったし」
「なおさらです。小さな装いの違いに気づいてもらえるのって、とても嬉しいんですよ」
コンスタンツァはますますニコニコと幸せそうに笑う。その笑顔があまりに眩しくて、俺はずっと以前から心の隅に引っかかっていたことを、つい口に出していた。
「……なあ。聞いてもいいだろうか。俺を探し出すために、何人くらいのバイオロイドが犠牲になったんだ?」
「……」
コンスタンツァの笑顔がふっと消える。彼女を傷つけてしまっただろうか。
しばらく目を伏せてから、コンスタンツァは顔を上げた。
「私達の戦いは、はじめからずっと不確かなものでした。あるかどうかもわからないものに手を伸ばして、多くの犠牲を払うのは、私達はずっとずっとしてきたことです。そして、私達が初めて手にした本当の勝利が、ご主人様を見つけたことです」
いつもかけている眼鏡を外し、コンスタンツァは俺の目をまっすぐのぞき込んできた。
「ご主人様を見つけるために命を落としたことを、後悔しているコンスタンツァ型は一人もいません。同型機として、これだけは自信を持って言えます。グリフォンも、他のスチールラインの皆さんだって、きっと同じだと思います。どうか、お気に病んだりなさいませんよう」
主人に嘘はつかず誠実に、しかし感情が主人の重荷になることはないように。久々に見るコンスタンツァのその笑顔は、けれど完璧ではなくて、あふれて伝わってくるその感情に、俺はただ黙ってうなずくことしかできなかった。
と、それで終わっていればよかったのだが。
翌日、訓練で見かけたレプリコンが珍しく大きな花のブローチをつけていた。
そのまた翌日、ニンフがスカーフを巻いていた。
次の週にはダークエルブンが三つ編みに、ダフネがサイドテールに髪型を変えていて、さらにレプリコンのブローチは星形になっていた。
「はい、レプリコン10889です!」
「私、ダークエルブン966だけど」
「ダフネ3301でございます」
どこから話が広がったものか。声をかけるとみな嬉々として自分のIDを名乗るので、きっと俺に見分けてほしいのだろう。せっかくの努力なのだからと、ひそかにメモをとったりしてできるだけ覚えるように努めたが、延べ300人を超えたあたりで頭がパンクした。退役組も含めるとすでに数万人のバイオロイドがいるのだから、どだい無理ではあったのだ。
見かねたコンスタンツァとマリーが自粛令を出してくれて、髪型やアクセサリの違いに毎夜うなされる日々はどうにか終わったのだった。
バイオロイド達は皆、ひたすらに献身的だ。それが単に、そのように造られているからに過ぎないとして、それに俺が引け目を感じても、何にもならない。俺が彼女達の上に立つのは彼女達自身の望みであり、人類としての義務でもある。これからの日々の中で、人類が彼女達に作った途方もない負債の、その億分の一でも、少しずつ返そうと努めていくこと。俺にできるのはそのくらいだ。
「グリフォン、ブーツ替えたのか?」
「な、なによ! こないだの戦闘で壊れちゃったから、新しいのができるまで儀礼服のをはいてるだけよ! 悪い?」
バイオロイド達のファッションの細部に目をとめる癖だけは残った。たまに気づいた時には、できるだけ口に出すようにしている。
コンスタンツァの言った通り、彼女達は本当に嬉しそうな顔をするのだ。
End
「んぎぎぎぎ……んににににに……」
変な顔をして首をねじ曲げながら粘っていたブラウニーの手の甲が、とうとうテーブルについた。
「負けたあーっ!」
「ふう……でも強くなってますよ、ブラウニー。こういう基本的なところに効いてくるんですね、オリジンダスト」
手首をくいくい曲げ伸ばししながら、ノームが言う。
「いやー、A級ッスからね、A級。分隊長抜いちゃったッスねー」
ブラウニーの得意げな顔がむかついたので、レプリコン1058はテーブルの下で向こうずねを強めに蹴っておいた。
オルカの艦底に近い倉庫の一角、入り組んだコンテナの影に比較的広いスペースがある。もとはイフリートが開拓したサボりスポットだったが、ブラウニーに発見されて以降、すっかりスチールラインの溜まり場になっている。
「ヴァルハラみたいにパジャマパーティとは言わないけど、もうちょっとちゃんとしたくつろぎスペース欲しいッスねえ」
床をごろんごろん子供のように転がりながら、ブラウニーが言った。
「それ以上どうくつろぐ気?」
「グレムリンがことあるごとに自慢してくるんスよおー! 今日は何のお菓子を食べただの、ふわっふわのクッションに埋もれて寝ただの!」
ブラウニー2056はつい先日、ドクターの研究所でA級バイオロイドへの昇格処理を受けた。等級が上がっても部隊内での階級には関係ないが、若干態度が大きくなった気がする。
「隊長のあの総ジュラルミン製みたいな部屋でパジャマパーティなんてできるわけないじゃない。全員でレーションかじって、アルミブランケットにくるまって寝るのが関の山よ」
「お菓子だけでもー! ここ水と乾パンしかないじゃないスか!」
「美味しいですよ、乾パン」
ぽりぽりと缶入りの乾パンをつまみ続けているのはノーム569。スチールラインの下級兵卒トリオである。
「そういうことじゃなーくーてー」
「シルキー伍長に頼んでおけば? まあ、あのアンドバリとかいう小さいのが来てから管理厳しくなったらしいけど」
「そう! そこなんスよ!」
がば、とブラウニーが起き上がり、レプリコンに指を突きつける。
「なーんで我らがシルキー伍長を差し置いて、オルカ全体の物資を仕切ってるのがあのヴァルハラのちびっ子なんスか!」
「それが本職だからでしょ。伍長もやっと楽になるって喜んでたわよ、仕方なくやってただけなんだから。あと上官を指さすんじゃない」
「釈然としないッスー!」
「別にここになくたって、カフェに行けば食べられるでしょうが」
「いやお菓子もッスけど、それだけじゃなくて」
ブラウニーはしばしもどかしげに両手を振った後、椅子に座り込んで真顔になった。
「最近……うちらの存在感軽くないッスか?」
「あー……」
それなら、わからなくはない。無敵の龍の合流により、それまでオルカ全軍の参謀役を務めていたマリー隊長はその座を下りて、スチールラインの指揮官という本来の立場に戻った。それ以来、レプリコン達の出撃機会は確かに減った気がする。特に、司令官が直接指揮を執る中核部隊として出撃する機会はめっきり少なくなった。
「まあ、仕方ないんじゃない。私達の戦法って、どうしたってねえ」
スチールラインの本領は死を恐れない物量戦にある。100人で吶喊し、99人死んでも最後の一人が走り抜いて勝つ、というのがスチールライン流だ。
だがオルカの戦いは、バイオロイドの生命を徹底して重視する。重傷を負った隊員は即座に離脱させられるし、それで戦線維持が難しくなればためらわず撤退する。おまけに、指揮通信システムの技術的な問題らしいのだが、司令官の直轄部隊は五人まで、しかもそれぞれ別機種でなければならないというルールがある。理念的にもシステム的にも、司令官の指揮下でスチールライン流の戦いはまったくできない。必然、直轄部隊は別のメンバーに任せ、支援や残敵掃討を担当するということになりがちだ。
「このままだと司令官様に忘れられてしまうッス……こうどかーんと、派手な戦果を一発挙げないといかんッス」
「私達の戦い方は、ある意味でもう時代遅れなのかもしれませんね」
「勝ててる上に死ななくて済むんだから、いいじゃない。明日ブラウニーが何人死ぬかで賭けができるような戦争に戻りたい?」
「それは嫌ッスけど……でもたまには司令官様の号令で、みんなで吶喊したいッス」
「吶喊すればいいというものではないですよ」ノームがたしなめる。「とはいえ私も時々は、命を捧げるような戦いをしてみたいとは思いますが」
「兵長までそういうことを……」
「こう、命を的にしている状況でこその張り詰めた充実感というものが」
「そッスそッス」
おとなしやかな物腰に反して、ノーム兵長も実は相当の脳筋というか、武闘派である。兵卒でまともなのは自分だけかと、レプリコンは何度目かのひそかなため息をついた。
レプリコン自身は、現状にさほど不満はない。もともと、死にすぎるブラウニーの手綱を引くために慎重で狡猾な性格に作られたのが自分たちだ。玉砕上等の戦術論には昔から賛成できなかったし、総指揮官が体育会系のマリーから冷徹な龍に変わったのも歓迎している。
「バイオロイドなんて昔から使い捨てだったんだから、慣れてないのはみんな一緒ですよ。私達の順応が遅れてるだけです。ホードなんか、今でもよくお呼びがかかってるじゃないですか」
「ホードは連携が優秀ですからね。やっぱり、私達もそのあたりを鍛えるべきなのでしょうね。新しい動きはちゃんと覚えましたか?」
「い、いま特訓中ッス」
「私ももうじき昇級しますし。そしたらもう少し、やれることも増えるでしょ」
「スチールラインフォーメーション、早く完成させたいッスねえ」
「まだまだ、実戦で使うには練度が足りません。他の部隊に負けない、きちんとしたものに仕上げなければ」
ぐっ、と握りこぶしをかためるノーム。
「あとどうにかしてお菓子の充実も」
「お菓子がどうしたって?」
つかつかと足音も高く入ってきたのはレッドフードである。
「げえっ、連隊長!」
「イフリートを見なかったか」
「いえ、見かけていません。イフリート兵長は静かな所が好きですから、私達がいる時にはあまり……」
「そうか。ところで休憩食に注文をつけるとは、偉くなったものだな上等兵」レッドフードは乾パンの缶を取り上げると、残っていた中身をざらざらと口に流し込んだ。
「ふぉふ……特訓がどうとか言ってたようだが、丁度いい、私が相手を務めてやろう」
「えっ」
「えっ」
「えっ」
「何か?」
「いえ、その、連隊長にお相手いただくなんてもったいないといいますか」
「私も、今は自分のペースでじっくり鍛えるべきかなーって」
「敵がこちらのペースに合わせてくれるものか。さあ行くぞ起立! 駆け足はじめ!」
「ひー!」
そこは下級兵卒の悲しさ、三人とも反射的に立ち上がって走り出してしまう。
「あっそうだ、スチールラインフォーメーションのポーズ!とか作らないッスか」
「作るわけないでしょう、バカなの?」
「こんな感じですか?」
「兵長!?」
四人の足音が倉庫の向こうに消えてから、数分後。
「やっと行った……あーうるさかった」
蓋のずれたコンテナの中から、もぞもぞとイフリートが這い出してきた。
「裏をかくのも楽じゃないよね。これでゆっくり寝れる」
テーブルの下にもぐり込んで安らかな眠りについたイフリートが、見回りに来たフェニックスとインペットに発見されるのは、ここからさらに数分後のことである。
End
「さて、酒はみな注いだな。乾杯の音頭はせっかくだから、新入りに頼もうか。アーセナル?」
「では僭越ながら。今宵はお招きいただきありがたく思う。乾杯!」
ロイヤル・アーセナルの、彼女らしい簡潔なかけ声とともに、五つのグラスがチン、と鳴った。
迅速のカーンの個室には物が少ない。
かといって殺風景というわけでもない。わずかな生活用品と、長い戦歴をしのばせるいくつかの記念品、そして上等の酒のボトルが少し。それらの品々が無造作に、しかしセンス良く並べられた、大人の隠れ家、とでも言いたくなるような居心地のいい部屋だ。
そしてその部屋はまさに今、大人達の隠れ家として利用されていた。
「噂に聞くブラックリバー将校会に、ようやく参加できて光栄だ」
「そんな大げさなものじゃない。ただの飲み会さ」
バーボンのグラスをあっという間に空にして二杯目を注ぐカーン。
「たまにこうして親睦を深めておけば、いざという時役に立つものだ。下の者相手では言えないこともあるしな」
ワイングラスを呷り、満足そうに息をつくマリー。
「いつから始まったんだったかしらね、これ」
ウォッカのソーダ割りを優雅に傾けるレオナ。
「後輩ができて嬉しいです。階級は私の方が下ですが……」
ビールを小さいコップできゅーっと空け、口元の泡をぬぐうブラッディパンサー。
「ははは! よろしくご鞭撻を頼む、先輩」
今日が初参加のロイヤル・アーセナルは、生のブランデーがなみなみ注がれたグラスをこともなげに飲み干し、カラカラと笑った。
「いい飲みっぷりだ。酒は強いのか?」
「さあ、わからん。心ゆくまで呑んだという経験はあまりないのでな」
二杯目のブランデーを、今度はチェイサーのビールと共に品良く傾けながらアーセナルは上機嫌に答える。「部下どもが止めるんだ。エミリーの教育に悪いと言って」
「ライバル登場ですね、カーン隊長」
「できた部下で羨ましいことだ。うちは人が呑んでいたら自分も呑み出す連中しかいない」
「最近、サンドガールが貴女をまねてバーボンを飲み始めたのよ。それこそ教育に悪いから、大酒は控えてほしいわね」
「そこまで面倒をみきれるか」
「レオナの部屋では、定期的にパジャマパーティとやらを開いているそうだな? 最近、うちの兵卒どもがヴァルハラがいい、ヴァルハラがいいと騒いでかなわない」
「私達は姉妹の絆が強いの。羨ましかったら貴女も部下達と仲良くなさい」
「こいつは部下に怖がられる一方なのさ」カーンがニヤニヤ笑いながら、マリーの肩に手を置いた。「だから飲み友達がほしくて、こんな会を始めたんだ」
「人聞きの悪いことを言うな。お前、もう酔っているな?」
「さっきレオナ殿も言っていたが、いつから始まったのだ、この会は?」
「……」
「夏だな。去年の夏だ」ふいに黙ったブラッディパンサーに気づかず、マリーが眉間に手を当てて記憶をたどった。「アンヘル・リオボロスの墓というか、金庫というか、そういうものを見つけたんだ。保存状態のいい酒が大量にあってな。それでほら、そうだ、あの時パンサーがひどい目にあって、慰めようとみんなで」
「思い出させないで下さい。泣きますよ」
「ほう、何が」
「やめて下さいってば」
ブラッディパンサーが立ち上がりかけたので、身を乗り出したアーセナルも笑って引っ込んだ。
「失敬、失敬。詫びにこいつをどうぞ」
笑いながら、アーセナルは長い包みを取り出す。ずっしりと重いそれを開くと、きつね色に焼き上がったスパイスフルーツケーキが現れた。
「ソワンに酒に合う菓子を頼んだら焼いてくれた。手土産だ」
「ナイフありますか?」パンサーがまだ眉根を寄せながら、それでも嬉しそうに言った。
「甘いケーキなのにどの酒にも合うのは、流石ソワンだな。しかし、彼女も随分丸くなってくれて助かる」
「丸くなった? 厨房では寄らば斬るという風情に見えるが」
「あんなものじゃない。あいつ、オルカに来るなり司令官に一服盛ったんだ」
「叛逆じゃないか!」
「そうよ。当時は戦いもまだまだ厳しくてね。私達は外征で留守がちだったから、詳しくは知らないのだけれど。コンスタンツァやペロは今でも彼女を警戒していると聞くわ」
「よく解体処分されなかったな」
「……まあ公平に言って、当時は司令官も今より未熟だった。突然『ブラウニーが可哀想だから食堂を拡充する』なんて言い出したのもあの頃だったろう」
「あったな、そんなことが」
「それで思い出したけれど」レオナが、カーンとマリーの二人へ向けてグラスを突き出した。「昔の貴女達二人は、司令官にずいぶん冷淡だったわね?」
「ん、そうかな」
「そうよ。食堂の話、貴女達は頭から馬鹿にして取り合わなかったでしょうが。何か理由があったの?」
「ああ、うん、そういう話か。理由というか……」
マリーとカーンは目を見交わした。何かあると察したパンサーが、ビールを半分ほどグラスに注いで差し出したのを、カーンが礼を言って受け取り、ぐっと一口で空にする。
「……昔の時代にな、結構いたんだ。一時の感傷や気まぐれで、我々にむやみに優しくしてくれる人間様というのがな。正直、あの頃は司令官も、その手合いだと思っていた」
「長生きすると、そういうことに意固地になってしまっていかんな」
マリーもワインから切り替えたウイスキーを飲み干して、フーッと長い息を吐く。
「……今は二人とも司令官に首ったけなのにね」
レオナがわざと茶化すように言うと、マリーは眉を跳ね上げる。
「よりによってお前にそんなことを言われる筋合いはないぞ」
「封印施設の護衛部隊の件、私はまだ忘れていないわよ」
「あのあとディナーを二回譲ったろうが!」
「理念の話をしているのよ!」
「まあまあ、お二人とも」
パンサーが慌てて止めに入る。「今日はアーセナルさんの歓迎会なんですから、それくらいに」
「痴話喧嘩なぞできるのは風通しがいい証拠だ。もっとやれ、もっとやれ」
「煽らないで!」
「この会のことだが」
マリーとレオナを止めるのに力を使い果たしたブラッディパンサーがぐったりと寝入ってしまった頃、アーセナルがふと言った。
「陸軍だけを集めているのか?」
「いや、たまたまだ。龍にはいつか声をかけたが、遠慮された」
「彼女は私達全員の上官のようなものだから、気兼ねもするんでしょう。スレイプニルも一度招いたのだけど、あの子はもう……」
「あっという間に潰れて、あっという間に復活して、真っ先に飽きて出ていったな」
「棚をいくつか壊された……もう呼ばん」珍しくむっつりとした顔になってカーンが言う。
「あとはドゥームブリンガーだが、あそこは……」
「そういえば、滅亡のメイはいまだに司令官に抱かれていないというのは本当なのか?」
アーセナルの言葉に、全員がぴたりと黙り込んだ。
「メイはなー……あいつはなあ……」
「あの人はねえ……」
「決して悪い奴ではないんだがな……」
マリー、レオナ、カーンがそろって額に手を当ててため息をつく。眠りかけていたパンサーまでが、むっくり起き出して頭をかかえた。
「信じられんな。どう見てもベタ惚れじゃないか」
「そうなんですが、あの人はなんというか、極端に恥ずかしがりで」
「ムキになる質だから、爆発すると何をするかわからない。ここへ呼ばないのも、それが理由だ」
「惚れた男の子種をもらうのに、恥ずかしいも何もなかろう。一晩食べてくれとひとこと言えば済む話じゃないか」
「貴女みたいに考えられたら話が早いのだけどね……」
「この前フェニックスにも相談されたよ。本人もだが、律儀に順番待ちをしている部下達が気の毒でな」
「出し抜いたりしないだけ、いい部下を持ったわね」
「お前、部下の仕込みで寝室に放り込まれたことがあるそうじゃないか。同じようにやったらどうだ?」
「もう言った。ナイトエンジェルが言うには、そんなことをしたら逆上して司令官をぶん殴って逃げ出しかねないと」
「核の鍵を預かる者が、そんな厄介な性格では困るだろうが」
「一言もない」
「まあ、すぐに答えが出る問題でもない。メイのことは次回の課題にしておこう」
マリーがグラスに残った氷を噛み砕いて、大きく伸びをした。
「明日はうちの小隊が探索担当だ。そろそろ休むよ」
「メイだけど、一度思い切ってここに呼ぶ? このメンバーなら、暴れて逃げ出しもしないでしょう」
「やってみるか……」
「六人だと、さすがにちょっと手狭になりますね。別の部屋を取りますか?」
言いながら、皆てんでにグラスと酒瓶を片付け、帰り支度を始める。ケーキを包んでいたクロスをたたんで懐にしまったアーセナルが、ふと笑みをこぼした。
「一人の男の寵を巡って争うというのは、厳しくも愉快なものだな」
「なんだ、唐突に」
「少なくとも私の同型機は、かつて抱かれたくてたまらない主人などというものを持った記憶はない。そういうたった一人の男のもとに、我々全軍がつどって戦うというのは、考えただけで心が奮い立つと思わないか」
「まあ、同意しないでもないけど」
「三安のメイド達はよくそういう争いをしたというが、こんな気分だったのかな。礼を言うついでに、ソワンに聞いてみるか」
「いや、あの人たちはまた、ものが違うのでは……」
四人が口々におやすみを言って出て行き、誰もいなくなった室内を、カーンは見回す。
酒臭さと、人いきれのなごり。潜水艦の悲しさで、換気はどうしても悪い。においがすっかり抜けきるには丸一日かかるだろう。
だが、カーンはこのにおいが嫌いではない。砂漠をひとり駆けている時には決して嗅ぐことのない、人と宴のにおいが。
髪留めを外し、さっきまでアーセナルとマリーが座っていたベッドにごろんと横になって、部屋の明かりを消す。
静かな寝息が聞こえ始めたころ、ドアの外の廊下を、夜直のブラウニーの足音がコツコツと通り過ぎていった。
End
「鉄虫を退治して下さり、ありがとうございます。でも私たちは、ご主人様の遺されたこの庭園を離れる気はありません」
着古されてボロボロのエプロンドレスを身につけたそのシザーズリーゼ型は、深々と礼をして言った。
「そうですか……近くの島に、私たちの補給基地を置かせてもらうのは構いませんか?」
「もちろん、どうぞ。ご主人様の所有地はこの環礁だけです。隣人が増えるのは大歓迎ですよ」
「ありがとう。では、のちほど……」
オベロニア・レアは一礼してふわりと舞い上がる。
リーゼと、その後ろに居並ぶ十数人の姉妹達の姿が小さくなっていく。高度を上げ、低く垂れ込める雲を抜けると、宙に浮かぶ機械の玉座が彼女を待っていた。赤毛の小柄なバイオロイドが、尊大に片肘をついて座っている。
「どうだったの?」
「駐屯は問題ないそうです。合流は……断られました」レアは悲しげに首を振ってみせる。
「ふん。厄介ね、あんた達は」
太平洋の真ん中に点々とつらなるこの小さな島々は、かつての時代には「真珠の首飾り」と呼ばれていたらしい。
星の落とし子を避けて航路を大きく制限された今のオルカにとって、この群島はアラスカに向かうための必須の足がかりとなる。何としても制圧し、補給拠点とする必要があった。海に囲まれた群島で、地上の敵を掃討するとなれば、ドゥームブリンガー以上の適任はない。
同時に、亡き主人の地所を守りラビアタの呼びかけにも応じなかったフェアリーシリーズの一団が、一部の島に細々と暮らしていることも以前からわかっていた。そこでオベロニア・レアのたっての頼みで、彼女も同行させることになったのだ。
《東側の島二つ、制圧終わりました。今からそちらに合流します》
ナイトエンジェルからの通信が入ってきた。待つまでもなく、空を切り裂くエンジン音とともに、ドゥームブリンガーの編隊が雲の下から現れる。ナイトエンジェルを先頭にきれいな楔形を描いた六体のバイオロイドは、メイとレアの眼下でふわりと散開して減速し、二人を囲む位置まで上昇して静止した。
「ジニヤーが軽傷を負いましたが、ほかに損害はなし。真水が出るのは大きい方の島だけですね。基地にするならあそこか、その隣の環礁でしょう」
進み出たダイカが、データバッドを叩きながら報告する。
「まだ生きてる農園があるとかいう話はどうなったんです?」
「いたわ。オルカに誘ってみたけど、フラれたところよ」
メイがくい、と親指でレアを示すと、レアは申し訳なさそうに頭を下げた。
「長姉が言っても駄目ですか。フェアリーシリーズは土地に根を下ろすと聞いてましたが、本当なんですね」
ナイトエンジェルが呆れたように言う。
「司令官に命令してもらえば一発じゃないんですかあ?」シルフィードがしきりに前髪を気にしながら言った。
「無理強いはしたくないというのが、ご主人様のご意志ですので……作物は分けてもらえるそうです。今年はカボチャが豊作みたいですよ」
「カボチャかあ……」
「どうでもいいわよ、島一つくらい」メイが手を叩いて会話を終わらせた。
「シルフィードとバンシーは見張りに残りなさい。あとは帰投。明日からしばらく島巡りよ」
翌日からはじまった群島の制圧作戦は、思いのほか難航した。
一つ一つの島は小さいが、起伏や原生林が多く、鉄虫が隠れる場所が無数にある。補給拠点にしたいオルカからすれば、森ごと焼き払ってしまうわけにもいかない。おまけに、かつてここを所有していたどこかの金持ちが、いくつかの島と島を海底トンネルでつなげており、片付けたはずの島にいつのまにかまた鉄虫が湧いたりする。
「もうやですー。帰ってソワンさんのとうもろこしご飯食べたいなあ……」
「文句を言うものではないですよ。私達は幸運なのです」
フラフラ飛ぶジニヤーを、レイスがたしなめる。
「何がですかあ」
「この地域は今雨期のはずですが、毎日晴れ続きでしょう。この好天が続いているうちに作戦を進めなくては」
「レイス、あなたそれ本気で言ってるの」
人手不足でスチールラインから駆り出され、久々に古巣の編隊長を務めていたフェニックスが眉を上げる。
「何か変でしょうか」
フェニックスが無言で指さした先へ、レイスが高高度爆撃用の強化された視覚をこらしてみると、数キロ彼方にオベロニア・レアがぽつりと、両手を広げた姿勢で静止したまま浮いていた。
「彼女が雲を散らしてんのよ」
「そんなことが!?」レイスが目を丸くして、あたりを見回す。「フェアリーシリーズのトップは天候を操作できると聞いてはいましたが、こんな広範囲に……」
「伊達にメイ隊長とタメを張ってたんじゃないってこと。因縁のある相手くらい、ちゃんと頭に入れておきなさい。私がいなくなってから、規律が緩んだんじゃないの?」
長い説教が始まろうとした瞬間、通信機からするどい警報が鳴り響いた。
「……私の不覚です。申し訳ありません」
再生ベッドに固定されたナイトエンジェルは、口惜しそうに顔を背けた。
「いえ、私が」片目を損傷したダイカがいそいで言い、痛みに眉をしかめる。「島をつなぐ海底トンネルを一つ、見落としました」
そのために、予期していなかった背後から奇襲を受けた。なお悪いことに、鉄虫側は切り札としてレーダー型を隠し持っていた。ナイトエンジェルの率いていた編隊は重傷を負わされ、レーダーはそのまま、あの農園がある方角へ飛び去っていったという。
報告を聞いたメイは無言できびすを返し、修復室から出て行こうとした。
「隊長! 待って下さい」
「ドゥームブリンガーの不始末は隊長の責任よ。私が片を付ける」
「フェニックス隊が追っています。作戦計画も見直しが必要です」
「レーダーの居場所だけ教えなさい。そこが拠点よ。根こそぎスラグに変えてやるわ」
「直掩が足りません。せめて私とダイカの予備機が来るまで」
「直掩には私がつきます」
ナイトエンジェルの言葉をさえぎって、修復室に入ってきたのはレアだった。
「先程、レイスさんから連絡がありました。農園が襲撃を受け……全滅したと」
普段穏やかな彼女の眼差しが怒りに引き絞られ、瞳が白い雷光をはなっている。豊かな黒髪までが、青白く光る細かな稲妻を無数にはらんで大きく膨らんでいた。
「私のエスコートでは不足ですか」
「いえ……それは……」ナイトエンジェルが絶句する。
「いいわ。ついてきて、レア」
「ええ」
怒りをみなぎらせた二人のSS級バイオロイドを止める言葉はなく、ナイトエンジェルとダイカはただ黙って背中を見送った。
「大丈夫ですよ。ああなったお姉様はすごいんです」
医療班のダフネがやってきて、二人の患者の頭を枕へ押しもどす。「メイさんは、私達の姉妹の仇を討って下さるのですから。お姉様はきっとそれを支えます」
「……別に、実力に不安があるわけではないです」
おとなしく点滴をつながれながら、ナイトエンジェルはため息をもらす。それから隣のダイカと目を見交わして、自嘲めいた笑みを浮かべた。
「ただ、できればついていって、この目で見たかったですね。あの二人のタッグなんて」
雨期だというのに連日晴天が続いていたのを、一気に取り戻すかのような豪雨だった。
すべてが灰色に荒れ狂い、伸ばした手の先も見えない。すさまじい雨と風と雷の中を、電磁フィールドに守られた二人のバイオロイドが悠然と飛ぶ。
「レーダーはこの先の島で休息しています」
ダイカから借りてきたデータパッドの表示と、自身の電磁波センシングの結果を交互に確かめてレアが言う。メイが玉座から首をのばして、画面をのぞき込んだ。
「よりによって、その島ね。……あんた、覚えてる?」
「忘れるわけがありません」レアが冷たく微笑んだ。
かつて、この島は三安の幹部の私有地だった。そして数百キロ離れた別の島に、ブラックリバーが保有する私設基地があった。
第二次連合戦争のさなか、その基地にいたドゥームブリンガーの隊員が先走って、この島を制圧しようとしたことがあった。姉妹を蹂躙されたオベロニア・レアは激怒し、みずからこの島に乗り込んでドゥームブリンガーを駆逐しようとした。そうなれば当然、メイも黙ってはいない。
戦争中、二つの企業国家間の相互確証破壊を保証する破滅的な切り札として温存され続けた二人が、もっとも直接対決に近づいたのがこの島だったのだ。
「こんな形で再訪するとは思わなかったわ」
「同感です。……ターゲットはこの岬、それと海底のここ。照準は問題ないですか。少し雨風を弱めましょうか?」
「私を誰だと思ってるの? それより、原子雲は成層圏に届くわよ。あんたの嵐で抑えきれるのかしら」
「私を誰だと思っているんですか」
二人は同時にクスリと笑って、そしてその後はもう笑わなかった。
やがて、嵐を貫いてオレンジ色の炎の柱が一本、二本と立ちのぼるのが、遠く離れたオルカからも見えた。
続いて、柱を包むように嵐が収束し、巨大な竜巻となって、膨大な粉塵と熱、そして放射性物質を上空へ吸い上げていく。
夜が明ける頃、すべては平穏に戻り、ただかつてビキニと呼ばれたこの環礁から、一つの島が消えていた。
***
本日、海域調査が完了。懸念されていた放射性物質の拡散はなし。オベロニア・レアの天候操作能力の精度は恐るべきものだ。
レイス少尉の報告に誤りがあり、農園のバイオロイドはダフネ型、ドリアード型各一名が生存。救助後、オルカに加わることを受け入れたものの、農園への執着は依然強く、治療ののち島へ戻り、今回造営した拠点の運営を担当してもらうことになった。
追記1。レイスの注意力について訓練の機会を設けること。
追記2。オルカを去る前日、フェアリー二人は司令官とベッドを共にしたらしい。それを聞いたメイ隊長が、二人を見送る時ものすごい顔をしていた。まあ、あの人の新参先越され連敗記録が今さら一つや二つ伸びたところで、大したニュースでもないが。
戦闘日誌 ナイトエンジェル記す
End
《司令官、貨物ハッチまでお越しいただけるでしょうか》
バンシーからの通信に、俺は読みかけの書類を放り出して立ち上がった。「コンスタンツァ、悪いけどあと頼む」
事情を知っているコンスタンツァはただ頷き、目配せをして送り出してくれた。
ハッチには大きな木箱が二十あまりも積み上げられ、広くはないデッキを占領している。そのてっぺんで、エクスプレスが汗を拭って水を飲んでいた。
「あっ、司令官! 見て見て、これ」
木箱の一つを開けると、むせるほどの濃い香りが鼻をうつ。箱の中には深い真紅色の、ビロードのような花弁を何重にもかさねた大輪の薔薇が、一本一本ていねいに茎の根元を濡らした綿で包まれて、ぎっしりと詰め込まれていた。バンシーと手分けしてすべての木箱を開き、数と品質を確かめる。
「朝からフェアリーシリーズの人たちが大回転してたんだけど、足りる?」
「十分だ。予定外の運送なのに、ありがとうな」
「どういたしまして!」エクスプレスはにっこり笑う。「司令官、またボディ変えたんだね? ほっそりしてるのもハンサムだよ」
「はは、ありがとう」俺は目元にかかる長い前髪を払って笑顔を返した。
《ダイカよりオルカ。偵察隊は予定ルートの半分を消化。会敵、損傷なし。引き続き警戒しつつ、帰艦コースに入ります》
ダイカからの通信が指揮官用のチャンネルに響く。作戦開始の合図だ。
「司令官、早く運び込んでしまいましょう」
「おう、急ごう」
バンシーと二人で箱を担いでオルカの廊下をバタバタと往復する。オルカにいくつかある俺専用の寝室のうちでも、二番目に大きい部屋が右舷第2フロアにある。待機していたシルフィードが、届く端から木箱を開けて大量の薔薇を大量の花瓶に挿していく。
部屋の中が半分ほども薔薇の花で埋め尽くされたあたりで、偵察隊帰投のアナウンスが入った。
「あとは私達でやっとくから、司令官は迎えに出てあげて」
「頼む」
慌ただしく部屋を出て、最上階の廊下へ向かう。哨戒任務から帰ってきた航空バイオロイドは、メンテナンスを受けるために必ずここを通る。エレベーターを降りるとちょうどタイミングよく、偵察隊の三人が廊下の向こうからこちらへ歩いてくるところだった。小柄な赤毛のバイオロイドが先頭を歩き、長身の二人があとに続いている。ドゥームブリンガーの指揮官・滅亡のメイと、その副官、ナイトエンジェルにダイカだ。
「お疲れ様」
俺はさも偶然通りかかったような顔で、何気なく声をかけた。
滅亡のメイはツンデレである。
いや、その言葉を知ったのはだいぶ後になってからだったが、とにかく好意を素直に表せない意地っぱりで、それでいて気持ちを隠すのが下手なため、態度と裏腹の本心がまるわかり、という不器用な性格である。
人の感情の機微にあまり聡いほうではない(ドクターに言わせると、これはだいぶ控えめな表現だそうだが)俺でも、彼女が俺を好いてくれていて、わざと裏腹にツンケンした態度をとっているのだと理解するには、それほどの時間を要さなかった。
そして理解してから、俺は彼女をからかうようになった。彼女の気持ちにわざと気づいていないふりをして、冷たい言葉を額面通りに受け取ってみせたり、精一杯のアプローチを綺麗にスルーしたりした。自分のことも、世界のことも、何もかもわからないことだらけの状況で、こんなに簡単に真意が透けて見えるのは彼女だけで、それがひどく愉快に思えたのだ。
他のバイオロイドにも似た傾向の子はいるが、メイほど極端なのはいなかった。だいたい皆、俺への好意を隠さず迫ってくるし、ある程度距離が縮まれば、一線を越えることになる。そうしてどんどん部下達との関係が増えていく中、メイだけが変わらず虚勢を張り続け、俺はその虚勢を放置し続けた。
そして気がつけばオルカに勤務するバイオロイドの中で、俺がベッドを共にしていないのは(もちろん子供組を除いて)メイと、彼女が本懐を遂げるまで遠慮しているドゥームブリンガーの面々だけになっていた。
ここに至って、ようやくメイも、自分だけが周囲から取り残されている、ということに気づいたらしい。
「……私、司令官に嫌われていると思う…?」
ある日の夕食時、消え入るように弱々しく、そうつぶやいたという。
「いいかげん、あのボケ隊長を何とかしてやって下さい。それが無理なら、せめて引導を渡して下さい」
そう報告しに来たナイトエンジェルの表情は鬼気迫るもので、俺はその時初めて、自分がどれだけ残酷なことをしてきたか理解したのだった。
「あら、司令官。暇そうで何よりね。私達はたった今哨戒から帰ってきたっていうのに」
俺を見た途端ぱっと表情が明るくなるメイ。そこから流れるように棘のある言葉が出てくるまでがいつも通りだ。今日の俺は彼女の一番好みの、痩せ型の青年ボディに乗り換えているから、笑顔がひときわ明るい。
ナイトエンジェルとダイカがそっとサインを送ってくる。俺が視線だけで頷いてみせると、二人は前を歩くメイに気づかれないよう、静かに脇の通路へ姿を消した。
「まあな。あ、そうだ」
すれ違う寸前、彼女を呼び止める。向き直った彼女の肩に手を置いて、
「夕食後、俺の寝室に来てくれ」
「ぴぅ」
変な声を上げてから一瞬の間をおいて、熱湯に突っ込んだようにメイの顔が真っ赤になった。
後ろを振り返るが、そこにいるはずの副官はいない。
「右舷の第2フロアだ。場所はわかるな?」
「なっ……えっ……あっ……」
ほそい肩を、やわらかく押す。小柄なメイの身体はほとんど抵抗なく、壁に押しつけられた。
「返事は」
夕暮れを思わせる薄紫色のきれいな瞳をまっすぐにのぞき込む。うっすら涙がにじんでいる。
たっぷり一呼吸の間があってから、
「…ひゃい……」
消え入るような声でメイは返事をした。
「よし」
俺は微笑んでみせて、身体を離す。立ち尽くしたまま、メイがいつまでも俺を見送っている視線を背中に感じた。
バイオロイドは誰もが、ある程度類型的な性格をしている。そのように作られている。だが彼女達は決して、書き割りの登場人物ではない。みずから考え、感じ、自分の人生を生きる一つの人格だ。
それを忘れ、今の関係も、相手の気持ちも、何をしようがずっと変わることがないかのように思っていたのは、俺の慢心と甘え以外の何物でもなかった。
彼女を抱かねばならない。
それも、待たせすぎてしまった分、できるかぎり彼女の望むシチュエーションを整えてそうせねばならない。
「どうしようかと悩んでいたところです。閣下から手を出して下さるのでしたら、協力は惜しみません」
「このままではメイさんのためにもなりません。是非やりましょう」
「正直、哀れで見ていられませんでしたわ。やっとその気になって下さって嬉しいですわ」
思い切って相談してみると、みんな驚くほど協力的だった。マリーとコンスタンツァはまだしも、ソワンまでがそんなことを言うとは、彼女の状態はよほど目に余るものだったのだろう。自分の罪深さをあらためて思い知る。
夕食時。ソワン手製のスタミナ丼を頬張りながら、俺は小さなモニタで食堂の様子をチェックしていた。壁際の一隅にメイトダイカ、ナイトエンジェルが座っている。任務明けのせいか、テーブルの上には少し豪勢なメニューが並んでいるが、メイはぼーっと皿を見つめたまま動かない。
「よかったじゃないですか隊長。ようやくその無駄な脂肪の塊に使い道ができて」
「……」
「本当によかったですね隊長。ねっ?」
「あ……えと……」
「でもまあ、どうせ土壇場になったら例によって、怖じ気づいて逃げ出すんでしょう? まだ早いとか何とか言って」
「なっ……そんな、ことは……」
「そうでなければ、『あなたのことなんか好きでも何でもない』とか心にもないことを口走りますか。それで後から私達をヤケ酒に付き合わせるのも、もう何度目になりますかね」
「うう…………」
「大佐、そんな言い方は……大丈夫ですよ、隊長。今度は司令官自らご指名で呼ばれたのでしょう? 誤解の余地もないですし、自然体で身を任せていればきっとうまくいきます」
「身を……任せ……」
両サイドからメッタ打ちにされて、メイはフラフラしながら機械的にサラダを口に運びはじめた。
これも作戦のうちである。メイは臆病で強情だ。誰にも言わずにいれば、一人で悶々とするうち考えがあらぬ方向へ暴走しかねない。一方、下手に人から何か言われれば、逆に彼女の意地っぱりな面を刺激して過剰反応を引き起こしてしまう。
逃げる隙を与えてはいけないし、自棄になるほど追い詰めてもいけない。適度に煽りつつ、同時になだめて落ち着かせ、ちょうどいい緊張状態を保ったままにする。微妙な火加減でソースを煮詰めるような繊細な仕込みは、やはりこの二人に任せるのが一番だ。
食事を終えたら、軽いエクササイズで腹ごなし。最後に強めのトレーニングを少しだけやって、肉体のギアが上がったところで切り上げる。今夜は長丁場になる。いや、する予定だ。
シャワーを浴び、身支度をととのえる。白いタキシードにエナメルの靴、ドレスシャツの胸をやや開けて、遊び慣れのした貴公子、といった感じの出で立ちだ。中身がそれに伴っているかどうか自信はないが、
「絶対に隊長の好みです。むしろ理想です」
とナイトエンジェルとダイカがそろって太鼓判を押してくれた。
第2フロアの寝室に行くと、部屋中にあふれるほどの薔薇が、壁のなかばまでを埋め尽くしていた。濃厚な香りに目眩がしそうだ。
絨毯も、壁も、ベッドも、一面深紅に染め上げられた中に、たった一つ置かれた、一抱えもある白バラの花束。
「どう? どう? 私とバンシーで飾り付けたのよ。超ロマンチックでしょ」
「こういったことは初めてで、上手くできたかどうか……」
ドヤ顔で鼻を鳴らすシルフィードと、自信なげに方をすぼめるバンシーの頭を撫でてやる。
「完璧だ。ありがとう、二人とも」
「じゃ、頑張ってね、司令官」
床に散らばる花びらを踏まないよう、つま先立ちで出て行く途中、バンシーがふと振り返った。
「あの……メイ隊長が、思いを遂げられた後は、もしかして、私達にも……」
「希望者にはな。だが後だ。今日はメイのことだけを考える」
シルフィードとバンシーは嬉しそうに頷いて、さっと部屋を出ていった。
三十分ほど待っていると、遠慮がちなノックの音がした。俺は花束を取り上げてから答える。
「どうぞ」
シュッと軽い音と共にドアが開く。入ってきたメイが、室内を一目見て硬直した。
視線が部屋の中をさまよって、最後に俺に釘付けになる。後ろでドアが閉まった。
大股にメイに近づく。赤い髪からはいい匂いがした。軍服もよく見るとピシッと糊が利いている。夕食後の僅かな時間でシャワーを浴び、新しい服をおろしてきたのだろう。その懸命さに、あらためて頬がゆるむ。
「しっ、司令官……私……」
「メイ、今までありがとう。そして、これからもよろしく」
大きな胸に、花束を押しつける。そのまま腰に手を回し、小さな身体をふわりと抱き上げた。
「あ……」
メイの瞳はうるみ、ほとんど泣きそうだ。ウルトラキングサイズのベッドに彼女を横たえてから、俺はタキシードの上を脱ぎ捨てて、彼女に覆い被さった。
「わたっ……わたし……」
花束ごしに身体を押しつけ、彼女の唇をふさぐ。
精一杯それっぽく振る舞っているつもりだが、これで本当に合っているのだろうか。と不安になってきた矢先、メイがぽろぽろと大粒の涙をこぼし始めた。
唇を合わせたまま、弱々しく俺に抱きついてくる。二人の胸の間で花束がつぶれ、ひときわ濃厚な匂いが立った。よかった、どうやら正しかったようだ。俺は彼女のコートを脱がし、ビスチェにそっと手をかけた。
その後のことは、栄光あるドゥームブリンガーにおける彼女の名誉と威厳を保つために、誰にも言わずにおこうと思う。
ただその日以降、俺の夜当番リストの名前は一人増えたし、その数日後にはもう六人増えた。
「隊長の脱処女マウントがうざすぎるので、まとめてお相手をお願いします」
という但し書きに署名はなかったが、誰が書いたかは、まあ、わかる。
End
真っ赤に錆びた刃は、ほとんどボロボロに崩れていたが、研ぎ直せばまだ使えそうなものもいくつかはある。
プラスチック製のラックに、大きいものから順に、きれいに掛けられているのは十数本のナタだった。
大きい方は大人が両手で振るうほどのサイズ。一番小さいものは子供でも持てそうだ。いくつか抜けがあるのは、誰かが持ち出したままになっているのだろう。
隣のラックにはノコギリ。その隣のラックにはアイスピックが、同じように整然と並べられている。そして最後の棚には、手元や顔を守るための防具、転倒を防ぐための長靴が、やはりサイズ別にきれいに揃えて収められていた。
キルケーは唇の端が皮肉につり上がるのを抑えられなかった。もちろん、安全には十分に配慮されている。他の人間に怪我をさせたい者など、ここには一人もいない。いや、いなかったのだ。
薄暗いコンクリートの歩廊を抜けると、そこがスタジアムだ。ワイキキ・ビーチのぎらつく陽光の下、小学校の校庭ほどの、広くもなければ狭くもない空間。その周囲に、一段高くなった客席が設けられている。中央の円形の床には、数十年の時を経てもなお消えない、バイオロイドの血の臭いが染みついていた。
その臭いのただ中に、微動だにせず立ち尽くしている小柄な人影に、キルケーはゆっくりと近づいて声をかけた。
「ここがC地区です。ドラキュリナさん」
***
「テーマパークのことをですね……」
組んだ長い指の上に額を伏せ、深い深いため息と共にキルケーは言った。
「話すんですよ……あの人。楽しそうに。いつか、引退したら行くはずだったそうで……」
「…………」
バーに集められた一同は苦い顔で、目の前のグラスを睨んだ。
先日オルカに加わったばかりの、ビスマルクコーポレーションのバイオロイド・ドラキュリナ。再生が保留されていたバイオロイドの一人であり、どこかしらに問題があるのだろうということは皆が察してはいた。しかし実際に再生されてみると、その問題の所在は誰の予想をも越えていた。
「この間、子供達に自慢話をしていました」
小さなビールグラスを両手で品良く持ったアルマン枢機卿がぼそりと呟く。
「まさか、ダッチちゃんにあの話を!?」シャーロットが気色ばんで立ち上がった。
「される前に、私が混ざって話をそらしておきました」
「よかった……」
大きな胸をなで下ろして、シャーロットはぐーっとジョッキを空ける。
「あー……なんか、ゴメン。同僚として」
ハイボールのグラスを片手に、ぺこりと頭を下げたバーバリアナを、セラピアス・アリスが咎めるような横目で睨んだ。手にはウイスキーのショットグラスをつまんでいる。
「ビスマルクの方って、皆パークのことをあんな風に教わるのですか?」
「んなワケないっしょ! アイツだけよ……まあ、アタシの知ってる限りでは」
「ともかく、何とかしませんと」ばん、とキルケーがカウンターを叩いた。
「あんな爆弾を放置しておくワケにはいきません。周囲のためにも、本人のためにも」
***
「……冗談でしょ?」
ドラキュリナはやっとのことで、それだけの声をしぼり出した。
「ホントよ」
客席の向こうから姿を現したバーバリアナが、吐き捨てるように言った。
「少なくとも、アタシが聞いてた噂どおりの場所ね。アタシも何十人もここへ送られたって聞くわ。他のいろんなバイオロイドも」
よく見ればスタジアムのそこかしこには、風化した人骨の残骸らしいものが吹き溜まっている。その中に混じって、バイオロイドの金属骨格もいくつか見えた。
もう秋とはいえ、熱帯の島である。寒いはずもないのに、ドラキュリナは黒いマントの端をつかみ、ぴったり体にまきつけて周囲を見回す。
「こ……ここだけよね? このパークだけ、こんなワケのわからないエリアがあるんでしょ?」
「世界中、ほとんどのテーマパークに、B地区とC地区はありました。私の知っている限り、観覧車と同じくらいには必需品でしたね」
キルケーが無情に答えた。
「だって……そんなこと、誰も言って……」
「アンタはね、騙されてたの」バーバリアナが、カツカツとピンヒールで瓦礫を踏んで下りてくる。「というか、ずっと誤解してたのよ。アンタのせいじゃないけどね」
***
「そもそも、彼女はどうしてあんな誤解を?」
「…………」バーバリアナの表情が沈んだ。
「はじめはね、ただの勘違いだったらしいんよ。アイツの最初期のモデルが引退することになってさ。知らない? 顔に硫酸をぶっかけられた事件。当時ちょっと話題だったけど」
ポカンとしているシャーロットとアリスの横で、アルマンが小首をかしげて記憶を検索する。
「ああ……ニュースになりましたね。確か、伝説の熱狂的なファンが暴走してやったとか」
「そう、それ。それがアイツの引退第一号。アタシらの会社じゃ、ファンじゃなくて伝説の仕込みだったってみんな言ってたけど」バーバリアナはほんの一瞬だけ細めた目でアルマンとシャーロットを見やって、
「ま、そこは今更どうでもよくて。普通さ、パークがどんな所かって、誰も言わないけど、みんな何となく察するじゃない? 噂とかで。でもアイツ、そういうの無かったのね、バカだから。人間様の言ったことを、そのまんま信じちゃったの」
キルケーが、濃いめに作ったハイボールのおかわりを差し出す。それを一口あおって、バーバリアナは酒臭い息を吐いた。
「それがウケたわけ。つまり、あー、勘違いしたまま、実際にパークへ送られた時の反応がね。なんか……性格とか、ピッタリだったんじゃないの? それで、アレよ。最初からそういう風に刷り込まれた、パーク送り込みで完成する商品として、モデルチェンジしたわけよ」
最後の言葉を吐き出すと同時に、苦いものを飲み下すように、バーバリアナはハイボールの残りを一気に干した。
「……」
「…………」
「………………」
「まあ、かつての人間様たちの行状や趣味を、ここでどうこう言っても始まりません」重たい空気を払うように、アルマンが言う。
「問題は、今ここにいるドラキュリナさんの誤解をどうやって解くかです」
「どうもこうも、普通に教えてあげればいいだけでは?」
何杯目かのウイスキーを舐め舐め、だんだん据わってきた目でアリスが言う。
「私の予測演算だと、普通に言っただけではあの方たぶん信じません」
「アイツ、変なとこ自信家だかんねえ」
「信じさせるなら、現地に連れて行くとか、記録映像を見せるとか、何かしらショック療法的な強引さが必要です。ただ、加減を間違えると……」
「立ち直れなくなるかもしれませんわね」シャーロットが深刻な顔をする。
「ご主人様からお話ししていただくのは? ご主人様のお言葉なら、信じないということはないでしょう」とアリス。
「有望な方法ではありますが……」
「お客様にそんな仕事を押しつけるのは、ちょっと申し訳ないですねえ」
「ただでさえ、隊員のケアについては陛下に……陛下のお体にご負担をおかけしています。このうえ、お心にまで負担をかけたくはありません」
「私は陛下にも十分気持ちよくなっていただくよう、毎回努力していますわ」
「そういうことではなく」
***
「ウソよ。信じないわ」
ドラキュリナは震える声で、バーバリアナをにらみ返した。
「こ、こんなの、ただ人間と、バイオロイドの死体があるだけじゃない……鉄虫に襲われたら、どこだってこうなるわよ」
「じゃあ、あそこ見てくる?」
バーバリアナは自分が先ほど出てきた、スタジアムの向こうにある瀟洒な屋敷を指さす。それが何のための建物か、キルケーには一目でわかった。
「個人用の『レジデンス』ですね。あれ」
広場での狂乱に参加するのではなく、一人で落ち着いてじっくり楽しみたいという客のための個室だ。そういう物好きに金持ちが多かったからか、中で行われることのおぞましさを少しでも和らげるためか、どこのパークでも決まって品のいい、金のかかった建物にする習わしだった。ハロウィンパークのレジデンスもそうだった。アリスとシャーロットが瓦礫の山に変えてくれた時には、言い知れぬほど胸が空いたものだ。
「そういう名前なんだ? 部屋ン中は、すごいよ。ベッドと、風呂と、いろんな道具」
それもよく知っている。部屋と道具類のメンテナンスも、キルケーの仕事だったから。
「ここは、人間様がご自分で直接おやりになるスタイルが主流だったようですね。私のいたパークではもっと、爆薬とか、機械とか……そんなものが多かったです。地域によって、文化の違いって出るものですね」
「だって……私……いつか、ここで、一番……ずっと、ずうっと、暮らすんだって………」
ドラキュリナの、愛らしい薄桃色の肌が真っ白になっている。目尻のつり上がった、気の強そうな大きな瞳はゆがみ、涙をいっぱいに溜めている。なるほど、と、キルケーは皮肉に納得した。確かに、彼女の容姿と性格は嗜虐心をそそる。ビスマルクコーポレーションの開発陣は、人の心の動かし方というものをよくわかっていたようだ。
バイオロイドの心も同じように動くのだとは、ついぞ考えなかったくせに。
***
「あら、オアフ島ですって」
特にいい考えも浮かばないまま深夜になり、バーの空気もよどんできた頃、アリスとアルマンの携帯端末が小さく鳴った。SS級バイオロイド用の公共情報ボードが更新されたのだ。
「オアフ島?」
「次の寄港地です。明後日には着くそうよ」
首をかしげたバーバリアナにアリスが答える。
「旧時代はリゾート地として有名だった島なのね。また水着が着られそう」
「貴女達は、またあの……」眉をひそめたアルマンが、ふと何かに気づいて身を起こした。
「リゾート地なら、テーマパークがありますね?」
キルケーが大型スクリーンを出して、衛星写真をもとにした地図を映す。
「本当だ、ここ。ワイキキ・ポリネシアンパークだって」
「写真で見える限り、建物もそこそこ残ってますね……」
「いい機会と考えましょう」アルマンが立ち上がって一同を見回した。「先行偵察隊が派遣されるはずです。それに参加して、ドラキュリナさんをここへ連れていきます。そのつもりで準備を進めましょう」
「準備って?」
「まず、あの方を夜当番に組み入れます」
「結局それかよ」
「さっき、ご主人様のお体に負担をかけたくないと言っていたのでは?」
「それはそれ、これはこれ。陛下の愛をいただくのは、事前のケアとして必須です。自己肯定感とレジリエンスに大きく関わります」アルマンは断言した。
「「「れじりえんす?」」」
「……心が強くなって、辛いことがあってもくじけなくなるという意味です」
「ああ、わかります」キルケーがぱん、と手を叩く。「昔はシラフじゃC地区のことなんて話せませんでした。こんな話できるようになったのは、お客様に何度も可愛がっていただいたからですし」
「どんな風にしてもらってるの?」
「私の場合はですね~」
「脱線しない!」カンカンカン、とアルマンがスプーンの柄で教卓のようにカウンターを叩く。
「それだけでは足りません。何かもう一手加えないと」
「あっ、閃きました!」
半分寝落ちしていたシャーロットが、いきなり跳ね起きて声を上げた。
「こういうのはいかが?……」
シャーロットのアイデアをひととおり聞いたアルマンは眉をひそめる。「それだと、結局陛下のお手を煩わせることに……」
「丸投げするよりは全然マシじゃない? アタシはいいと思うな」
「でも、ご主人様は明日お忙しかったはずですよ。上陸の準備もありますし、夜はドラキュリナさんのお相手をお願いするわけですし」
「……紙一枚のことですから、なんとかしましょう。最悪、私が署名をいただいてあとから追いかけます」
「じゃあ、先発隊は私とバーバリアナさんで……」
***
「……うわあああああん。わああああああああああ」
しゃがみ込んで大きな声で泣き出したドラキュリナを慰める言葉を、キルケーもバーバリアナも持っていなかった。
黒いマントに包まれた小さなその背中に、キルケーは何度か手を置こうとして引っ込める。
真っ青な空に吸い込まれていく泣き声が、やがて小さくなり、弱々しい嗚咽に変わった頃。
「キルケーさーん。バーバリアナさーん」
東の空を、ピンク色と金色のもつれ合った塊のようなものが、フラフラと飛んできた。近づくにつれ、それがアルマンとシャーロットを両肩にしがみつかせたアリスだとわかる。
「……ふう。ありがとうございました、アリスさん」
「さすがに、二人かついでオルカと往復は疲れますね……」
「空を飛べるの貴女だけなんですもの、仕方ないじゃないですか」
肩で息をしているアリスとけろりとしているシャーロットを置いて、筒のようなものを大事にかかえたアルマンがとことこと駆け寄ってくる。
「間に合ったんですか? お客様、書いて下さいました?」
「ええ、これ。お二人から渡してあげてください」
キルケーとバーバリアナは筒の蓋を外し、中に入っている紙を確認する。それから、もう嗚咽の声すらあげず、小さくしゃくり上げるだけになったドラキュリナのもとへ行って、二人して身をかがめた。
「ドラキュリナ。ほら、ちょっとこれ見てみな」
「…………」
「ドラキュリナさん」
「……」
何度も声をかけられてやっと、ドラキュリナは涙と鼻水でぐしゃぐしゃになった顔を上げた。キルケーが顔の前に広げた紙に、ぼんやりと焦点の合わない目を向ける。
「……指……令……書? 建………」
「建設指令書。いつか、鉄虫が片付いたら、ここにテーマパークを作れってさ。もちろん、こんなのじゃない、ちゃんとした本物のやつを」
「司令官直筆の、電子じゃない本物の紙に書いた公式文書ですよ。こんなの、オルカでも何人も持ってる人はいませんよ」
「…………」
ドラキュリナは虚ろな顔のまま、何も答えようとしなかったが、キルケーが指令書を筒にもどして手渡すと、それを胸の間に抱きしめて、またうずくまった。
キルケーもバーバリアナも、それ以上声をかけようとはせず、そっと音を立てないようにその場を離れる。一度だけ頷きあうと、二人は本来の任務である先行偵察と鉄虫の駆逐にもどるべく、小走りにアルマン達の後を追っていった。
***
「……いい? ここに砂利が20トン。こっちはざっくり45トン。1階と3階だと層剪断力の逃がし方が違うから、斜面をつかって基礎杭はこう……」
図書室の前を通りかかると、何やら蕩々と喋っている声が聞こえて、何気なくのぞいてみたキルケーは目を丸くした。
床に大きな模造紙を広げて、アルヴィスやダッチガール達を前にドラキュリナが得意顔で描いているのは、どう見てもテーマパークの城だったからだ。
「ドラキュリナさん!? 一体何を……」
「あらキルケー。決まってるじゃない、図面を引いてるのよ。この私の、ドラキュリナ・パークの象徴となる偉大なドラキュリナ城のね!」
「は……」
よく見ると線こそ粗雑だが、ちゃんと寸法が書き込まれている。ただの絵ではなく、設計用のスケッチだ。それも、基礎工事や配管まで考えられた本格的なものだと、キルケーには見てとれた。
「司令官がこのひとに、遊園地を建てるように命令したんだって」と、興味深そうにスケッチに見入りながらダッチガールが言う。
「その通りよ!」
ドラキュリナは大きな胸の間から、先日の筒を抜き出して、誇らしげに振り回した。
「直筆の指令書があるんだから。私の理想にかなう遊園地がないなら、自分で作ればいいのよ!」
そういえば、彼女の製造元であるビスマルクはもともと建築会社であり、彼女も土木工事の知識を備えているのだった。今更のように、キルケーは思い至った。あの時、シャーロットはもしかしてそこまで考えていたのだろうか。いやいや、そんなまさか。
「あなたもこの私を手伝うなら、城に一部屋くらいあげてもいいわよ。確かあなたも昔は……」
そこまで言いさして、ドラキュリナははっと口をつぐむ。得意満面だった顔が、罪悪感と怯えに一瞬翳る。
「あ、その……ごめん……なさ……」
「……いえいえ~」
キルケーは安心させるように、やさしく微笑んでから図面をのぞき込んだ。
「そうですね~、私はやっぱり、バーが欲しいですね。それとワインセラーと、できたら醸造所も~」
「……! なによ、贅沢ね!」
ドラキュリナの顔がぱあっと明るくなる。
「いいわ、やってあげようじゃない。このあたりが日陰だから、こっちから掘って……」
「プール! アルヴィスは滝のあるプールが欲しいです!」
「暗黒の書を集めた図書室も必須だぞ!」
「滝は難しいわね……城の壁を上手く使えばいけるのかしら……」
「おっ何々、工事の話? 解体いる?」
「いらないわよ!」
バーバリアナまで入ってきて賑やかになった図書室。満面の笑顔で図面を描き足しはじめたドラキュリナと、フンフンと頷きつつ見入っているダッチガール。よくわからないなりにはしゃいでいる子供達。
言いようのない幸せで暖かな気分が、口元から笑みになってあふれるのを、どうしても抑えられない。キルケーはもう一度だけ皆の顔を見回してから、一歩引いて俯瞰するのをやめ、楽しい夢の遊園地の設計に自分ものめり込むことにした。
「醸造所って、どれくらいの広さいるの?」
「広さより、高さと換気が大事でして~……」
End