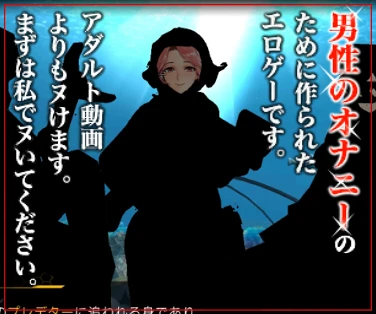黒のエナメルのバニースーツは切り裂かれるとほとんど同時に粉々にちぎれ、大量の血しぶきとともに風に飛んだ。
「ンニャーッ!」
猫めいた断末魔の悲鳴。アウローラは自分が目にしている光景が信じられなかった。
ペロがやられた? 変幻自在のネコバニー=ドーの使い手、次期四天王入りは確実と目されていたあのペロ=サンが?
呆然としている間にも、バニースーツの破片はアウローラと裸身のペロ、そしてペロをはさんで反対側に立つもう一人の人物に黒い雪めいて降りかかる。
自分のバニー強度では、この相手に一対一では勝てない。バニー・シニフリジュツでやりすごすか? いや、見破られたらその時こそ終わりだ。いったん離脱して態勢を整えるべき。そう計算結果をはじき出すまでにコンマ2秒。アウローラは三連続バック転を繰り出して距離をとると、即座に背を向けてダット・ダッシュを決めた。
ネオハコブネ・シティの高層ビル群が、高速で後方へ流れ過ぎていく。バニーガールであるアウローラの脚力は常人をはるかに超越している。強化ハイヒールで壁を蹴り、ビルからビルへ空中を駆けることなど造作もない。上空には華美なコマーシャル映像を車体側面に映し出す飛行アドトラックが何台も遊弋しているが、地上のサラリマン達はみな地面か手元のスマホに目を落としたまませかせかと歩き、頭上を見上げる者はない。
ビルからビルへ華麗に跳びうつりながら、アウローラの頭には混乱と後悔が渦巻いていた。ビフォア・アサメシ・ミッションと聞いていた。最近噂になっている謎の暗殺者バニースレイヤー、奴をペロ=サンと二人がかりでおびき出して仕留める。奴の実力を見誤っていたのは決して自分ではない、ミッションを課した上司の方だ。
「くそ、報酬の増額を要求しないと! 二倍でも足りない!」
眼下の通りが、灰色のビジネス街から猥雑な歓楽街へと変わった。「ミズミズしく安全」「上下運動」「肌色面積」などといった扇情的な謳い文句のエレクトリック立て看板が並び、オイラン、ボディコン、アメスク、さまざまに派手な恰好をしたポンビキ・・ガール達が、通りをゆくサラリマンに甘えた声をかけ、自分達の店へ招き入れようと袖を引く。
その中に一人、風船の束を持ったバニースーツ姿の女をみとめたアウローラは即座に壁を蹴って急降下し、彼女のすぐ隣に降り立った。
「ドーモ」
「えっ」
女が振り返るより速く、首筋にアテミ・チョップを一撃。意識を失ってくずれ落ちる体を抱きとめ、風船だけ奪って背後の路地へ放り込む。通行人の誰ひとり、当の女自身ですら、何が起こったのか気づかなかっただろう。
アウローラはそのまま何事もなかったように、笑顔で道行くサラリマン達に風船を配りはじめる。この国の大半の人間にとって、バニーガールとは架空の、おとぎ話の中の存在にすぎない。恰好だけバニースーツを着た常人の女たちが、歓楽街の性的な店にはいくらでもいる。木を隠すなら森の中。バニーガールを隠すなら、偽物のバニーガールの中だ。
もちろん、真のバニーガールであるアウローラの美貌とスタイルは、ただの恰好だけのコスプレとは次元が違う。先程まで見向きもしなかった仕事帰りのサラリマンたちが次から次へとフラフラ吸い寄せられてきては風船を受け取っていく。風船には「新装開店」「血が出る」と蛍光ピンクで大きくミンチョされており、どこかの店の宣伝なのだろうが、アウローラにとってはどうでもいいことだ。
作り笑顔を振りまく合間に、アウローラは胸の谷間からバイオニンジン・タブレットのケースを取り出し、三粒振り出して口にほうり込んだ。バイオニンジンの栄養分が身体に染みとおり、疲労した神経が冴えわたっていく。あと小一時間、明るくなるまで時間を稼げば、安全に支部へ帰れる。奴は闇に乗じる暗殺者。朝の光の下では襲ってくるまい。
「風船をひとつ」
「はあい! オコシヤスエー」
差し出された手に、残り少なくなった風船を渡そうとしてアウローラは手を止めた。薄汚れたピンク色の、ミトン型の手袋。点々とついている赤黒い染みは、血だ。
アウローラの前に立っているのはキグルミであった。モコモコした下ぶくれのスタイルは滑稽で愛らしくさえ見える。頭には二本の長い耳。背中に背負った、人の背丈ほどもある巨大なニンジン。そして、闇の中でなお暗く輝くアメジスト色の瞳。
それはつい先ほどペロを殺した、あの女であった。
「ドーモ、アウローラ=サン。バニースレイヤーです」
「ア、ア、あいえええええええ!?」パニックに陥ったアウローラは風船を投げ捨て、即座に十フィートほど跳びすさってから、両手を腰の前でそろえて丁寧にオジギした。
「ドーモ、バニースレイヤー=サン。アウローラです」
本質的に接待業であるバニーガールにとって、礼儀と挨拶は何よりも大切なマナーなのだ。
「イヤーッ!」そしてオジギから頭を上げた直後、アウローラはバニースーツの胸の谷間から抜き出したスクレイパーを投擲した。その間、わずかコンマ3秒!
しかし、バニースレイヤーは背中に背負った巨大なニンジンをそれ以上の速度で抜き放った。「イヤーッ!」半月型のスクレイパーが真っ二つに切り払われ、正確な二つの四分円となって地面に落ちる。
読者もご存じの通り、ニンジンというものは丸みのある円錐形をしており、物を切るのに使えるような形状ではない。しかしバニーガールは己のバニースピリットをニンジンに流し込み、鋼をも両断する刃に変えることができる。これは古事記にも書かれている厳然たる科学的現象であり、ゆえにバニーの振るうニンジンはニンジンキャリバーと呼ばれるのだ。
そして、これほど大きなニンジンをキャリバー化できるのは、バニースレイヤーのバニースピリットがそれだけ強大であることを示している。アウローラは背筋にふたたび戦慄が走るのを覚えつつ、即座に次の武器を準備する!
「イヤーッ!」アウローラは胸の谷間から取り出した泡立て器を投擲!「イヤーッ!」ニンジンキャリバーが泡立て器を真っ二つに切って落とす!「イヤーッ!」アウローラは胸の谷間から取り出したピーラーを投擲!「イヤーッ!」ニンジンキャリバーがピーラーを真っ二つに切って落とす!
「イヤーッ!」アウローラは胸の谷間から取り出したゴムベラを投擲!「イヤーッ!」ニンジンキャリバーがゴムベラを真っ二つに切って落とす!「イヤーッ!」アウローラは胸の谷間から取り出したクッキー型を投擲!「イヤーッ!」ニンジンキャリバーがクッキー型を真っ二つに切って落とす!
「イ、イヤーッ!」アウローラは胸の谷間から取り出したペティナイフを投擲!「イヤーッ!」ニンジンキャリバーにまっすぐ弾き返されたペティナイフが、アウローラの右肩を切り裂く!
「ンアーッ!」アウローラが右肩を押さえて膝をつく。白い二の腕を真っ赤な血の筋がつたい落ちる。
「大道芸は終わりか」バニースレイヤーがゆっくりとニンジンキャリバーを背中に構える。必殺の構えだ。「では、大人しくパイになるがいい。バニー殺すべし」
(訳注:パイになるとは、バニーガールの使う隠語で死ぬことを意味する。古事記の時代、畑に忍び込んだバニーが領主に捕らえられ、ミートパイにされたという凄惨な故事に由来する)
「なんだ、なんだ」「ダイドー・バスカーか?」
いつのまにか両者のまわりには、大勢のサラリマンやポンビキ・ガール達の人垣ができていた。一般人である彼らは、バニーガールが実在するなどとは思ってもいない。たった今繰り広げられた激しい攻防も、ただのストリート・パフォーマンスか、映画の撮影くらいにしか思っていないのだ。バニースレイヤーが小さく舌打ちをする。
酔っ払っているのか、サラリマンの一人がふらふらと寄ってきてバニースレイヤーの肩に手をかけようとした。即座に振り払うバニースレイヤー。すると、反対側からボディコン・ポンビキ・ガールが着ぐるみの腕を取る。背後から別のサラリマンが、ニンジンキャリバーの柄をつかむ。さらに別のもう一人が、バニースレイヤーの耳を握ろうとする。
「ヌウッ!?」バニースレイヤーが異変に気づいたときは遅かった。
空気の中に、ひどく甘い香りが混じっている。そして群がるサラリマンやポンビキ・ガール達の目は一様にどろんと濁り、うつろな笑いを浮かべている!
「かかった!」アウローラは会心の笑みを浮かべた。見よ、アウローラの右肩の傷から流れ出ていた血が、跡形もなく消えている。いや、赤く開いたままの傷口から、血は霧状になって空気の中へ散っていくではないか!
エル・アライラー! これがアウローラのヒサツ・ワザ、その名もパティシエ・フェロモンジュツである! アウローラの血は、空気に触れると甘い香りと洗脳効果を持つ媚薬と化すのだ!
すでに二十人以上の男や女がバニースレイヤーを取り囲み、その手や足を押さえつけていた。振り払おうにも、これだけの人数がいては、いかにバニー筋力といえども思うにまかせない。下手に全力を出せば殺してしまう。
「そのままもがいているがいい!」アウローラは胸の谷間からバイオニンジン・タブレットのケースを出すと、中身を残らず口の中へあけてから投げ捨てた。大量のタブレットを噛みくだきつつ、再度胸の谷間へ手を入れ、小ぶりのニンジンを抜き出して構える。丸みのある先端にバニースピリットが流れこみ、硬質の輝きをはなつ。
「死ね、バニースレイヤー! イヤーッ!」ハイヒールがアスファルトをえぐり、バイオニンジン栄養分で強化された渾身のツヨイ・バニー脚力でアウローラが一直線に迫る! バニースレイヤーは回避しようとするが、両脚にしがみついた虚ろな顔のサラリマンに阻まれて動けない!
「グワーッ!」ニンジンキャリバー・ダガーが一閃! 着ぐるみの布と綿を切り裂き、肉をえぐった手応えがあった。
(獲った!)あのペロ=サンを倒した相手を、この自分が! これは間違いなくキンボシ・オオキイだ! 昇進! ボーナス! 休暇! アウローラの心が湧き立つ。
しかし次の瞬間、アウローラの全身の毛が逆立った。
バニースレイヤーを取り囲んだサラリマンやポンビキ・ガール達が一斉に失禁し、地面に倒れる。強すぎるバニースピリットを浴びせられると常人はこうなるのだ。アウローラのバニー感知能力はそれほど優れているわけではないが、それでもこれほど間近にいればわかる。深手を負ったはずのバニースレイヤーのスピリットが、少しも衰えない。それどころか、不安定に揺らぎながらみるみる増大していく。
布の裂ける音がする。アウローラがたった今切り裂いたキグルミの裂け目が、ひとりでにみるみる広がって、キグルミ全体を覆い尽くしていく。バラバラにちぎれた布と綿がネオハコブネ・シティのよどんだ風に吹かれて飛んでいき、その下から現れたものを見てアウローラは息を呑んだ。
手首から鎖骨までを覆う変形燕尾コート。爪先から太ももの付け根までを覆う炎の色のタイツ。コートとタイツの間にはむき出しの胴体、そこへ局部だけを覆う、二枚のハート型ニプレスと一枚のバンソーコー!
エル・アライラー! それはおよそいかなる文献で見たことも聞いたこともない、異様なバニーの姿であった。いや、これは本当にバニーなのか? これはバニーを冒涜するもの、バニーに叛逆する姿なのでは?
「バニー……スレイヤー(バニーを殺す者)……」
アウローラが思わず呟いた言葉に、その新たな姿はうすく笑ったように見えた。ハウンスカル・メンポめいた額当てが、薄桃色の月明かりを受けて妖しくきらめく。
「そうとも、それが私の名だ。貴様たちバニーを残らず殺す者だ」
ニンジンキャリバーの切っ先がゆっくり持ち上がる。キャリバーまでもがまがまがしく姿を変え、その先端には金属の長いスパイクが装着されていた。
アウローラはようやく我に返り、パティシエ・フェロモンジュツを再度発動しようとする。しかし、あたりのサラリマンもポンビキ・ガールも、すでにみな失神してしまっている!
「イヤーッ!」バニースレイヤーは踏み込むと同時に、ニンジンキャリバーを下から上へ振り抜いた。その踏み込みの速度も、剣速も、先程までとは比べものにならない!
「ンアーッ!?」辛うじて両手首のカフスで受け、両断だけはまぬがれたものの、アウローラの体はなすすべなく上空へ吹き飛ばされる。
「イヤーッ!」その隙を逃さずバニースレイヤーは跳躍! 上昇するアウローラに追いつき、その体をさらに上へ蹴り上げる!「ンアーッ!」
「イヤーッ!」バニースレイヤーはビルの壁を蹴ってさらに跳躍! 上昇するアウローラに追いつき、その体をさらに上へ蹴り上げる!「ンアーッ!」
「イヤーッ!」「ンアーッ!」「イヤーッ!」「ンアーッ!」「イヤーッ!」「ンアーッ!」「イヤーッ!」「ンアーッ!」「イヤーッ!」「ンアーッ!」「イヤーッ!」「ンアーッ!」「イヤーッ!」「ンアーッ!」「イヤーッ!」「ンアーッ!」
とうとう二人のバニーの体は、高層ビルの屋上を越える高度まで舞い上がった。はるか下方に、ネオンに照らされた歓楽街がミニチュアのように見える。バニースレイヤーはビルの屋上を蹴り、すでにダメージで身動きのとれないアウローラの上に乗ると、片手でその両足首を、もう一方の手で両耳をつかんだ。そして背中に両膝をあてがい、その体勢のままキリモミ回転、垂直落下!
「イィィィヤアァーーーッ!」
エル・アライラー! これぞ古事記に記されたバニーガールの奥義の一つ、「ウォーターシップ・ダウン」である! 数十メートルの高さからうなりを上げてキリモミ落下したアウローラは、耳と足首を極められウケミ・ディフェンスもできぬまま顔面からアスファルトに激突!
衝撃波と砂埃が、ネオンに照らされたせまい通りをなぎ払う。軽やかに四連続バック転してバニースレイヤーが着地したあと、そこには肩までアスファルトにめり込んだアウローラの無残な姿があった。
「サ……サヨナラ!」
アスファルトの奥からくぐもった声を漏らしたのを最後に、アウローラの体はしめやかに爆発四散! バニースーツは粉々にちぎれて風に飛ぶ。そして爆風がおさまった後、しずかに赤い雪めいてアスファルトへ降り注いだ。
夜明け前の空がもっとも暗い。通りには、失神したサラリマンとポンビキ・ガール達がマグロめいて転がっている。遠くからマッポ・ビークルのサイレンが近づいてくる。まだ煙を上げる路面に落ち、風に吹かれてどこへともなく散っていく赤い破片を見送るバニースレイヤーの目に、ほんの一瞬、言い知れぬ哀しみの影がさした。
「ははははは! 小物とはいえグレーターバニー二人を相手どって勝つとは、どうやら貴様を見くびっていたようだ」
その笑い声は、突如上から降ってきた。
瞬時に戦闘態勢に戻り、ニンジンキャリバーを抜くバニースレイヤー。見上げた先、「ウサギは寂しいと実際死ぬ」と大きくミンチョされたネオン看板の上には、真紅に輝くバニースーツに、腰まである長い栗色の髪をなびかせたバニーガールが一人、堂々と腕を組んでいた。
バニースレイヤーの射貫くような視線を正面から受け止めたそのバニーは、ゆっくりと腕をほどき、腰の前で合わせて頭を下げる。
「ドーモ、バニースレイヤー=サン。ロイヤル・アーセナルです」
「……ドーモ、ロイヤル・アーセナル=サン。バニースレイヤーです」バニースレイヤーも一度ニンジンキャリバーを背中に収めて一礼する。「そのスーツ。四天王か」
「その姿、古事記に記された『逆バニー』か? 実在していたとはな」バニースレイヤーの言葉を悠然と無視し、ロイヤル・アーセナルは笑みを浮かべたまま言葉を続ける。
「バニーダイオウ=サンが貴様に興味をお持ちだ。我々の元へ来れば、バーを一つ任せてやる。貴様の腕なら、ゆくゆくは四天王の座も夢ではなかろう」
「愚問だ。貴様も逆バニーになるがいい」
バニースレイヤーが腰を沈め、斬撃の構えをとる。ロイヤル・アーセナルは笑みをおさめ、胸の谷間に手を差し込むと、細長く先端の尖った二本のニンジンを抜き出した。それを一本ずつ、左右の手にゆるやかに構える。
「我がキャリバーの名は『モンティ』と『パイソン』。貴様もバニーなら知っていよう」
バニースレイヤーの目が一瞬細まる。古事記の時代、アーサー王とナイツ・オブ・エンタクの首を次々に刎ねて全滅させた伝説のバニー。モンティとパイソンとは、彼女が携えていた二振りの魔剣の名前ではないか!
「勝てると思っているのか?」
「思うも、思わないもない。バニー殺すべし。それだけだ」
マッポ・ビークルのサイレンの音が徐々に高まる。空を裂くその唸りはそのまま、両者のあいだの殺気の高まりを象徴しているかのようであった。
今まさに凄惨な殺し合いが始まらんとするその光景を、大画面スクリーンごしに悠然と眺める一人の男がいた。
オルカ・スゴイヒロイ・ビルの最上階。フロア丸ごとが一続きの広大な広間になった、その中央にライオンの毛皮が何重にも敷き詰められ、どっしりとしたソファが据えられている。
ソファに腰を下ろし、左右に二人のバニーをはべらせたその男は、天井から吊り下げられたスクリーンに映る映像を満足げに眺めながら、傍らのワイングラスに盛られたバイオ・キスチョコをつまむ。
「ムハハハハ、アーセナルめ。遊びおるわ」
「よろしいのですか? バニーダイオウ=サン。あのような勝手を許して」左側にはべる黒髪のバニーガールがたくましい胸にしなだれかかる。彼女のバストは豊満であった。そう、この男こそがバニー達の王にして、このネオハコブネ・シティの真の支配者、バニーダイオウその人である。
「構わぬ。あいつは好きにさせた方が良い結果を出す」
「もし敗れたら?」右側にはべる氷の色の髪をしたバニーが、冷ややかにスクリーンを見やりつつ、バニーダイオウの二の腕に指を這わせる。彼女のバストもまた豊満であった。
「それならそれで、あのアーセナルを超えるバニーが一人いるということだ。この俺が直々にネンゴロして手駒に加えてやるわ」
バニーダイオウは両手を伸ばし、脇の下から抱きかかえるようにして左右のバニーの乳房を揉みしだいた。二人のバニーが切なげな声を上げる。
「昔から言うではないか、『二人のバニーを追って、二人とも手に入ったら実際良い』とな。ムハハハハハ!」
平安時代の伝説的バニーガールにして作家、モラサキ・シキブの言葉だ。このような古代のコトワザが何気なく出てくるところに、バニーダイオウの高い教養がうかがえた。
スクリーンの中で、二人のバニーのニンジンキャリバーが最初の激突をする。激しく散った火花を眺めるバニーダイオウの顔はあくまで落ち着き、帝王の余裕に満ちている。
「ムハハハハハ、ムハハハハハハハハハ!」
広間をかこむ防弾ガラス製の展望窓の向こうで雷鳴がひらめいた。広大な広間が一瞬、白と黒の閃光で染め上げられる。
嵐が来る。この頽廃の都市に迫る運命を象徴するかのような、激しく荒れ狂う嵐が近づいていた。
* * *
「……ていうのやりたい!」
満面の笑顔でニバが差し出してきた台本を、俺はどうにか読み終えた。
「これ、自分で書いたのか」
「そうだよ!」ニバは着ぐるみの胸を張る。逆バニースタイルになるのは真の力を発揮する時か、暑い時だけらしい。
「マジカルモモみたいな人気番組と違って、私たちみたいなのには予算もスタッフもなかなかつかないからね。自分で企画を立てて売り込むのは普通だよ」
「そうなんだ……」
「私、めちゃくちゃせこい悪役みたいになってるんですけど」
「私なんか最初に殺されるだけじゃないですか! 冗談じゃありません!」
「もしかして、このバニーダイオウの左右にはべってるのが私とティタニア?」
一緒に台本を読んでいたカフェ・アモールのバニー達が口々に文句を言うが、ニバは鷹揚に手を振る。「まあまあ。偉大な作品には犠牲がつきものなんだよ」
「勝手に犠牲にしないで!」
「私は戦い始めたところで終わってしまったんだが」
「あ、それは続編へのフックね」
無職期間中に方舟のライブラリで映画やら小説やら漫画やらをずいぶん鑑賞したおかげで、旧時代の文化についての俺の理解はだいぶ進んだ。だからわかるのだが、かつてニバの主演した一連の映画……『バニースレイヤー』シリーズは、一言でいって「色物」だ。突飛な世界観、突飛なキャラクターでシリアスな物語を演じ、そのシリアスさ自体がおかしみを生むという、屈折したユーモアを内包した作品である。
シリーズ自体は数作で終わったものの、コミカルでバイオレントなニバのキャラクターは人気を博し、他のさまざまな作品にゲスト出演するようになった。フレースヴェルグに聞いたところでは、ニバは「マニアの間でカルト的な人気を誇った、ヴィランとダークヒーローの中間的存在」だったそうだ。出てくると問答無用で女性キャラをバニーや逆バニー姿にできるのが、セクシー要員として使いやすいという理由もあったとか。
れっきとした主人公であるにもかかわらずエンターヴィランズ所属なのは、そうしたゲスト出演でイメージが変わって移籍させられたのかもしれない。他のエンターヴィランズの子と違って、役柄と素の自分があまりはっきり分かれていない感じなのも、そのせいだと考えれば納得できる。
「ここ、ビスマルクのマキナとメリーもいるんでしょ? セットとか作り放題じゃーん!」
「いくらマキナさんでも、町まるごと一つ作るのは……あーいや、前にやってたか」
「廃墟になった市街地などそこら中にある。適当に手直しして使えばよかろう」
「オルカから離れたところでないと駄目ですよ。最後には嵐を起こすんでしょう?」
「私はやるって言ってませんけど!?」
言い争いはいつの間にか、本当に映画を撮る方向へ進みつつあるようだ。新しいこと、面白そうなことに、皆がどんどん積極的になっていくのは俺としても大変嬉しい。問題なのはこのままいくと間違いなく俺がバニーダイオウ=サンをやらされることだが……。
「ニヒヒッ! バニーダイオウ=サンももちろん出てくれるよね?」
ニバと目が合うと、彼女は屈託ない笑顔で手を振った。
ペレグリヌスやサイクロプスプリンセスと話してあらためて感じたことだが、伝説やビスマルクの俳優たちにとって、「与えられた役柄」は決してただの虚構ではない。それは自分の中にあるもう一つの生き様、もう一つの人生観だ。舞台も観客も消えたこの世界で、彼らは自分自身だけでなく「役柄の自分」としても現実と向き合い、生き方を見いださなくてはならない。
マイナー色物映画の主人公として生まれ、流転のうちにヴィランになったニバも、彼女だけにしかわからない何かを抱えているのだろう。それらを飲み込んだ上でのこの笑顔なのだとすれば、付き合ってやらないわけにいかない。俺はニバに向かって、力強くうなずいてみせた。
「ヤッター! 私とバニーダイオウ=サンとの決着はPart9『ネオハコブネ炎上編』でつける予定だから、それまで頑張ってね!」
……やっぱり程度というものがある。
俺はまるめた台本を握りしめ、すでにシリーズ構成の議論に入りつつあるバニー達の間に割り込むことにした。
生態保存区域のはずれにある木立の中から、野兎が一匹、きょとんとした顔で俺たちを見ていた。
End
「お姉ちゃん……あいつ……デルタってひとと…同じこと……」
「大丈夫よ、シア」
細くふるえる妹の声にかぶせるように、私はわざと強い声を出しました。
生あたたかい風が頬をなぶります。まだ三海里も離れているのに、熱がここまで届いているのです。自分たちの指揮官であるレモネードガンマに砲撃され、炎を上げて沈みゆく何十隻もの敵艦の起こす熱波が。
「自分の……仲間なのに……」
「あれはデルタじゃなくてガンマ。それに私たちは無敵の龍隊長と一緒なのよ。心配ない、大丈夫だから」
艤装から身を乗り出して、妹の手をとりました。冷えきった指先を両手で包み、力づけるように何度も握ります。
「…うん。シア、怖くないよ。大丈夫だもん」
シアの指に温かみと力がもどってくると、私は妹の二の腕をかるく叩いて、微笑んでみせました。本当は肩を抱いてあげたいところですが、艤装を装備した状態では手が届きません。
「それでこそ誇り高きマーメイデンよ。戦団長様に、恰好いいところをお見せするんでしょう?」
「うん!」
ぶん、と頭を振って大きくうなずいたシアにもう一度微笑んでから、私は喉元の通信機に手を触れました。
「アンフィトリテより本隊へ。敵艦隊は残骸を越えて、さらに進出してくると見られます。予定通り出撃します」
《……了解です。こちらも作戦に変更はありません》
セイレーンさんのやや緊張した声が、通信機から返ってきました。
《敵は異常です。何をしてくるかわかりません。くれぐれも気を付けて下さい。どうかご無事で》
「ありがとうございます」私は通信を切り、水平線上に広がる炎の海と、その向こうから陽炎のように現れつつある敵艦隊を見据えました。
「行くわよシア。主機接続、抜錨!」
「よーそろー!」
地中海からはるばる地球を四分の三周して、私たち姉妹が無敵の龍隊長率いる連合艦隊に合流したのは、艦隊が北米大陸バンクーバーに集結して大規模作戦を決行する、わずか一日前のことでした。
慣熟訓練も十分に行う時間がありませんでしたが、私たちは志願して作戦に加えていただくことにしました。私とシアを受け入れて下さった龍隊長の恩義に報いなければなりませんし、バンクーバー島と大陸本土を隔てるセイリッシュ海は小さな島が無数にひしめく狭い海で、マーメイデンにとってはうってつけの戦場です。唯一の懸念は物々交換に使えるような手持ちの資材が何もなく、補給を受ける当てがないことでしたが……なんとレジスタンスを率いる人間の戦団長様は、補給も、整備も、それどころかご飯とシャワーとベッドまで、すべて無償でいいと仰いました。
目を閉じれば今も、オルカの食堂でいただいたご馳走が脳裏に蘇ってきます。ぴかぴかの白いご飯に、スープに、味のついたおかずが三種類も! どれもほっぺたが落ちるほど美味しく、しかもおかわり自由なのです。きっとこの作戦は決死行で、隊員の多くにとってこれが最後の晩餐になるのでしょう。それで大盤振る舞いをしたのに違いありません。
お腹いっぱいご飯をいただき、熱いシャワーを浴び、ふかふかのベッドでぐっすり眠って体調は万全。弾倉もバッテリーも満タン。艤装も十分に整備していただき、どこを動かしても止めても、少しの軋りもガタつきもありません。舳先が波を切る音まで軽やかに聞こえます。これほど完璧なコンディションで出撃するのは何十年ぶり、いえロールアウトして以来初めてかもしれません。どう考えてもこれがタダのはずがないので、たぶん私が何か聞き違えたのじゃないかと思いますが、その確認をする時間もないまま作戦が始まってしまいました。
聞けばこちらの海上戦力は、これまでほぼホライゾンだけで構成されていたとか。いつか同胞たちを迎える時のためにも、ぜひともここで働きをみせ、海にマーメイデンありという存在感をアピールおきたいところです。いいえ、そんな功名心は抜きにしても、こんなに良くしていただいて、戦果でお返ししなくては罰が当たるというものでしょう。
熱がちりちりと睫毛をあぶり、目が乾いてきました。破壊された敵艦群はもうほとんど沈んでいますが、漏れ出た重油が燃えながら海面に広がっているので炎の範囲はむしろ拡大しています。その炎を押し割るようにして前に出てくる敵艦隊を、私たちは大きく迂回して、側面に回り込みました。
艦載兵器の延長として発展してきたホライゾンやポセイドンと違い、私たちマーメイデンは一人一人が「艦そのもの」を代替するコンセプトで作られており、戦いのスタイルが根本から違います。もちろんサイズ差がありますから、大型艦艇とまったく同じことはできませんが、逆に私たちだけの武器も色々とあるのです。
「艦影解析、照合……旧独系ハイドリヒ級、旧北米系ジョン・ウォーカー級ならびにセンピル級」
敵艦隊のうち、前に出てきたのは高速艇と哨戒艇ばかり。大型艦も多数いたはずですが、どうやらレモネード・ガンマは小型艦だけを出してきたようです。私たちにウェイトを合わせたつもりでしょうか。
「舐めてくれたものね……シア、主砲装填、19・1・7。先頭の艦に一斉射」
「しゅわしゅわ弾E、どっかん弾、めらめら弾だね。てー!」
かけ声と同時に、シアの艤装に搭載された四門の砲塔が轟きを上げます。三筋ずつまとまった十二本の砲炎が空に弧を描き、敵艦の横腹に吸い込まれていくのを私は目で追いました。
三連装砲を構成する三本の砲にはそれぞれ違う弾頭が込められており、わずかにタイミングをずらして着弾するようになっています。まず最初に化学侵食弾が敵艦の塗装を溶かし、装甲材を劣化させたところへ徹甲榴弾が着弾して装甲を貫通。内部構造に予備ダメージを与えた後、浸透焼夷弾が内部を高熱で焼き崩します。広い船腹にきれいに四つの燃える穴を開け、敵ハイドリヒ級はゆっくりと傾いて沈み始めました。
私たちマーメイデンの第一の武器が、このモデル9・三連装高速多用途砲です。本物の艦載砲に比べればおもちゃのようなサイズに見えるでしょうが、相手の装甲や構造材に合わせた28種類の特殊砲弾と、それを瞬時に選択・装填できる高速装填装置、そして十センチ単位の精密砲撃が可能な照準システムの力で、五倍の口径の砲にも匹敵する実効破壊力を発揮するのです。
「続いて十一時方向、16・1・4二門、甲板に向けて2・2・2二門!」
「よーそろー! てー!」
調合の異なる化学侵食弾と指向性炸裂榴弾が堅牢なジョン・ウォーカー級の装甲を破壊し、さらに榴散弾が甲板上の対空装備を無力化します。私自身も電子妨害弾を上空へ撃ち、後続艦から発射されたミサイル群に妨害をかけつつ回避行動に入ります。機銃の弾幕が海面に無数の小さな水柱を立てますが、私たちはもうそこにいません。
「敵センピル級大破、続いてハイドリヒ級、マングシェフ級多数! シア、斬り込むわよ!」
「おっけー!」
私たちの第二の武器は、この小ささです。このサイズ、この速度で海上を動き回る敵を追尾できる武装は多くありません。隠れ場所が山ほどあるこの狭い内海で、密集した艦隊の間にもぐり込んでしまえば、もう私たちはほとんど一方的に攻撃を加えることができます。
「右舷を任せるわ、片っ端から沈めてしまいなさい! 左舷は私が!」
「よーそろーっ!」
シアの三連装砲が立て続けに火を噴き、右舷の敵艦の横腹に次々と穴が開いていきます。幼いところもある妹ですが、一度没入したときの集中力、攻撃精度は私などよりはるかに上なのです。私は左側の敵艦だけに集中し、船尾の舵に狙いをつけます。
「アンフィトリテより本隊、私からみて八時方向の哨戒艇三隻、足だけ潰しました。とどめお願いいたします」
《テティス了解でーす。いただいちゃいますねー!》
テティスさんの明るい声が返ってきてからほどなくミサイルの雨が降り注ぎ、航行不能になった敵哨戒艇の艦橋と砲塔を溶鉄に変えていきました。仲間のスコアにも気を配ってこそ、デキる海の乙女というものです。
今の私たちは組織上、龍隊長の直属部隊でホライゾン攻撃部隊と同格、という形になっています。合流したばかりの新参者がそんな高い地位をいただいて反感を買わないかと思ったのですが、
「恥ずかしながら、私はマーメイデンの方と連携して戦った経験がないので……動きの合わせ方は、たぶんお二人の方がよくわかっていると思います。基本的には独自の判断で動いてくださって構いません」
セイレーン副艦長はあっさりとそう言いました。ずっと昔、人類統合艦隊でご一緒したセイレーン大佐はもっと張り詰めていて、人に主導権を渡したりはしない方に見えましたが、あんなに柔らかい笑顔もなさるのですね。
「お姉ちゃん! 向こうのおっきい船も動き出したよ!」
先行艦隊はもう半壊しています。レモネードガンマもようやく、小粒の船では相手にならないとわかったようです。
「では、私たちも大物狩りを……」
砲撃の轟きが天地をひっくり返し、空と海のあいだを炎で埋め尽くしました。
――――
人差し指の長さほどしかない、小さな小さな魚。焚き火であぶって少し焦げてしまったそれを、シアが指先で慎重につまんで二つに裂いた。
「あ……」
二つを見比べた妹が小さく声をもらす。片方にだけ頭がついていて大きい。シアのお腹がぐう、と鳴った。つられて自分のお腹が鳴る前に私は手を伸ばし、頭のついていない方をとった。
「お姉ちゃんは、こっちが欲しいかな」
ほんの一瞬、シアは喉のつまったような、なんとも言えない顔をして、それから笑顔でうなずいた。
「「いただきます」」
一口分にも足りない、ちっぽけな魚の切れ端。それでも一週間ぶりの固形物、三ヶ月ぶりの動物性タンパク質だ。一片残らず味わい尽くそうと、口の中に全神経を集中させて何度も何度も噛む。肉も骨も皮も鰭もぜんぶ細かく噛み潰されて、唾液と混ざり合ってもうなんだかよくわからない液体になってしまってから、私たちはしぶしぶ口の中のものを飲みくだした。二人のお腹が、今度は同時にぐう、と鳴る。次にものを食べられるのはいつのことだろう。涙が出てきたが、何が理由なのかはわからなかった。
――――
「……お姉ちゃん! お姉ちゃん!」
うっすらを目を開けると、顔をクシャクシャにしてのぞき込んできたシアと目が合いました。この子は本当に泣き虫なんだから……。
「……!?」
左半身から燃えるような痛みが襲ってきて、急速に意識が覚醒しました。
ガンマ艦隊の、またしても味方を巻き込んだ一斉砲撃で形勢は一気にひっくり返されてしまいました。敵艦隊を足止めするために龍隊長が単身で決闘を挑み、それでも動き出した旗艦アナイアレイターを止めるため砲塔を直接狙撃したものの、潰せたのは第三砲塔のみ。私は盲撃ちを続けるアナイアレイターの主砲を至近で受けてしまい……失神していたようです。
自分の身体を見回して状態を確かめます。左舷砲塔は爆風で変形して使い物になりません。私自身も左腕と左脚にひどい火傷を負っていますが、骨は折れていないようです。
「シア、私が気絶してから、どれくらいたった?」
「んーと、んーと、十五分くらい……」
私は切り立ったせまい入江の奥の、磯になった部分に寝かされていました。位置情報を見ると、戦闘中の臨時補給地に定めていた小島のひとつです。すぐそばに、布と木の枝で簡単にカモフラージュした補給コンテナが据えてありました。私は急いでコンテナを開け、鎮痛剤と弾薬を取り出しました。
「戦況は? アナイアレイターはどこ?」
「ここを通り過ぎて、先行っちゃった……おっかけようとしたけど、お姉ちゃんを助けるほうが大事って、思って……」
大きな目に涙をいっぱい溜めて、しゃくりあげるのをこらえながらシアが答えました。シアの身体にも艤装にも、さいわい大きな損傷はないようです。
「ありがとう、助かったわ。……アンフィトリテより本隊、意識を失って脱落していました。申し訳ありません。戦闘続行可能です、指示をお願いします」
通信機のスイッチを入れると、ひどいノイズが耳を刺しました。アナイアレイターの主砲の電磁パルスで、通信が乱れているのでしょう。砂嵐の中から時折顔を出すように、切れ切れにテティスさんの声が聞こえます。
《……後の難民を乗せた便がいま離陸しました! 作戦は成功しつつあります! あとは何とかあのバカでかい艦を食い止めて、離脱するだけです! 生きて帰りましょうね!》
「え……」
「作戦成功だって! よかったねえ!」
黙ってしまった私に気づかず、シアはにこにこしながら艤装の弾倉にぽいぽい弾を詰め込んでいます。私も無事な右舷のハッチを開けて、アナイアレイターの装甲に合わせた弾頭を選びました。
「……龍隊長の仰ったとおり、司令官様は本当に素晴らしい方なのね」
「うん! シア、最初に会ったとき大好きになったよ」
「そう。シアはかしこいものね」
「えへへ」
嬉しそうに笑う妹を見て、私は一つの考えをかためました。艤装のうしろから非常用バッグを取り出し、いくつかの弾頭をそちらへ入れて肩にかけます。
「急ぎましょう。アナイアレイターを追いかけるわよ」
アナイアレイターの巨大な姿は、まだ水平線の手前に見えていました。おそらく向こうもダメージで最大速度は出せないのでしょう。船体のあちこちから黒煙を噴き上げ、僚艦の残骸で燃え上がる海をすすむ姿はさながら地獄の宮殿といったところです。
速力を上げて追いかける間にも数分おきに、雷鳴のような轟きと肌を叩きつけるような衝撃波がここまで伝わってきます。まがまがしい光の弧が三筋、ならんで雲を引き裂いてゆくのはアナイアレイターの主砲です。
「アンフィトリテより本隊、あの主砲はマーメイデンが何としても止めてみせます! 砲塔無力化後、残存艦を制圧する部隊をご用意下さい!」
通信機に向かって怒鳴り、速度を一杯まで上げました。見上げるような巨体がぐんぐん迫ってきます。
「シア、私の艤装をお願い。それと援護射撃とね」
「え? わかった」
私は艤装を切り離すとコントロールを妹に渡し、無事な右舷側の甲板に上がりました。敵艦の巨体が起こす波が、こちらをぐっと押し上げるタイミングに合わせて力一杯跳び上がると、船腹に引き上げられた昇降用タラップの一番下の段にかろうじて手がかかり、私は身体を揺すって回転しタラップへ飛び乗りました。
私たちの第三の、そして最後の武器、それは私たち自身です。マーメイデンは全員が、必要とあらば海兵として直接敵艦に殴り込むことができるのです。
自動化と無人化の進んだポセイドンの艦は、甲板上での白兵戦など想定していないことがほとんどです。思った通りアナイアレイターも同様で、散発的な機銃とドローンの迎撃をかいくぐり、私はあっという間に二番砲塔までたどり着きました。
アナイアレイターの主砲、22インチ三連装レールキャノン回転砲塔は間近で見ると途方もない大きさで、それだけでちょっとした要塞のようです。威圧的に空を睨む広い砲口は、私なら全身すっぽり入ってしまえそう。シアだと胸がつかえて無理かもしれませんが。他愛もないことを考えながらバッグからケミカルアンカー弾頭と、信管起爆ユニットを取り出して接続します。これで私たちの特殊弾頭は簡易的な手投げ弾に早変わりします。
起爆を三秒後にセット。頭上にならぶ砲口をねらって三つ投げ入れるとコンコン、と分厚い砲身の内部を弾頭が転がっていく音がして、正確に三秒後、ズンと小さな振動が砲塔を震わせました。爆発自体には砲塔を破壊するほどの威力はありませんが、大型AGSの動きさえ止める特殊粘着硬化剤がガッチリとこびりついた砲身内部は当分使い物にならないでしょう。
「あと一つ……!」
追撃してくるフォールン型を振り切って、私は艦首方向にある一番砲塔、まだ動いている最後の砲塔へ走ります。駆け寄る私の目の前で、長大な砲身がググッとわずかに動きました。
次の瞬間、巨大な壁に殴り倒されたように私は甲板に転がりました。
目がチカチカして、キーンという音とも言えない音だけが聞こえます。火薬式ほどでないとはいえ、これだけ大口径のレールキャノンとなると発射時の衝撃波も相当なものです。至近距離で電磁パルスを浴びたせいで、通信機が完全に死んでしまいました。ですが、リチャージに入った今がチャンス。ノイズすら流さなくなったインカムをむしりとって捨て、ふらつく足で砲口を目指します。
バッグから弾頭を取り出し、砲口へ投げ込みます。一つ、二つ……三つめの弾頭に起爆ユニットを取り付けようとして手が震え、ユニットが甲板に転がりました。最悪のタイミングで波が船体をわずかに傾け、小さな円筒形の起爆ユニットはそのまま砲塔の反対側へ転がっていきます。
ユニットの予備はありません。私は一瞬だけ躊躇しましたが、答えは最初から決まっていました。
「本作戦の主目的は北米の難民を救出することである」――ブリーフィングで龍隊長がそう仰った時、私は言葉通りには受け取りませんでした。新参者の私たちに知らされないだけで、本当の目的が他にあるか、あるいは北米の難民という言葉自体が何かの暗号なのだろうと思ったのです。だって、バイオロイドを救うために艦隊を動かす人間様なんているわけがないのですから。
ですが、それは私の早合点でした。司令官様は本当に……本当に、レモネードの支配からバイオロイドを救うためにこの作戦を始められたのでした。オルカは私などが思っていたより何倍も、何百倍も素晴らしい場所でした。
たとえ私がいなくなっても、司令官様ならシアのことをちゃんと守り、導いて下さるでしょう。マルタにいる仲間たちのことも、救って下さるでしょう。思い残すことは何もありません。
私は片手にケミカルアンカー弾頭を握ると、砲口のふちへ手をかけ、そのまま頭から中へ飛び込みました。
「シア、元気でね」
最後にそれだけ呟いて、私はかたく目をつぶりました。
「いやはや、驚いたでござる。殿のご下命にて駆けつけてみれば、大砲からアンフィトリテ殿の脚が生えてござった」
「申し訳ありませんでした……」
その十数分後、私はオルカ突入部隊の皆さんに囲まれて小さくなっていました。
少し考えればわかることでしたが、戦団長様の方でもアナイアレイターの状況は把握していて、緊急突入部隊を編成してくださっていました。しかも砲塔を潰してもガンマは諦めず、核融合炉を暴走させて艦を自爆させようとしたため、部隊の皆さんは融合炉の番人であるトリトン型とも戦わなくてはならなかったのです。その間、私は何も知らず砲塔に頭から詰まっていただけでした。
「二番砲塔を潰してくれていただけでも、だいぶ助かりましたよ」
「万一のことがなくてよかったですよ」
オベロニア・レア様とエラさんが、とりなすように言って下さいました。三安のレア様にPECSのエラさん、同じくPECSのキルケーさんに伝説サイエンスのゼロさんとコウヘイ教団のサラカエルさん。所属がバラバラなのが、本当に急ごしらえで集められたチームなのだとわかります。それほどまでに重要な緊急作戦のさなかに、私ときたら。
「肝心なところでお役に立てませず、お手数ばかりおかけして……」
「私たちのお手数なんてどうだっていいですけど、無敵の龍さんとお客様にはたっぷり叱られると思います~。覚悟しといた方がいいですよ~」
「まあその前に、身内に叱られるがよかろう」
キルケーさんとサラカエルさんがすっと脇へのくと、
「お゙姉ぢゃあ゙あ゙あ゙あ゙あ゙ん゙!!」
サラシアが飛び込んできました。
「シア頑張ったよ! 頑張ったよう! おねっ、お姉ちゃんがいなくなっちゃうんじゃないかって……! 怖がっだああああ!」
「そうね、偉かったねシア。ごめん、ごめんなさいね……」
結局私は、何もわかってはいなかったのです。すべてを一人で飲み込んだつもりになって、空回りして、シアをこんなに悲しませて……。
「聞けばお二人は、つい昨日こちらに来られたばかりとか。お館様は世にも稀なる名君でござる。ゆるりと時をかけて、そのお心を学んでゆかれるがよいでござるよ」
「はい……」
砲音が聞こえます。海上では残存艦艇の掃討が始まっているようです。私たちも参加しなくてはなりません。でももう少し、ほんの少しだけ。私はシアの肩を抱きしめて、そのぬくもりを感じていました。まわりを囲む皆さんの眼差しも、それを許して下さるようでした。
あとから思えば、この時になっても私はまだまだ、司令官様のお心をちゃんとわかってはいませんでした。オルカがどんなところで、私たちがここでどんな風に生きられるのか、それを本当にわかってきたのはもっとあとのことで、その間にはいくつも驚くような、時には信じられないような出来事がはさまっていたのです。
だから……ね? ガラテア。その、下着は……そういう信じられないような出来事の一つというか。決してやましいものではないのよ。だから、お願いだから……そんなに見ないで、返してもらえる?
End
「ビッグハンド・マンジューといって、旧時代にこのあたりの名物だった菓子だそうだ。一昨日の遠征隊がレシピを入手してきたので、アウローラに作ってもらった」
「美味しい! 私あんこ好きです。こんなに小さくて可愛いのに、おかしな名前ですね」
小さな和菓子を頬張り、お茶をすすって嬉しそうに息をつくアンドバリの頭を撫でてやろうとしかけて、鉄血のレオナは手を引っ込めた。勤務中は子供あつかいはやめてほしいと、この間釘を刺されたばかりだった。
オルカ艦底倉庫の片隅にパーティションを張って作られた管理ブースは、だいぶ前からアンドバリの第二の居室といってもいい状態になっている。訓練や出撃の合間に暇な時間ができると、ここで茶飲み話をするのが最近のレオナの習慣だった。はじめは、仕事柄倉庫に詰めっぱなしでヴァルハラの待機室にもあまり顔を出せずにいるアンドバリが寂しいだろうと案じてのことだったが、
「倉庫にはしょっちゅう誰か来るので、あまり寂しくはないんですよ」
と彼女は言うのだ。その言葉通り、倉庫には実に様々な顔ぶれが、引きも切らず訪れる。
「お疲れ様です! 明日の上陸隊用の資材、こちらですか?」
「はい、そのパレットにまとめてあるやつです。伝票も済んでますから、持っていってください」
「ありがとうございまーす! よいしょっと」
「すみません、小麦粉を追加で5袋いただいていっていいでしょうか。伝票はさきほど……」
「はい、受理してます。でも今月ちょっと消費が多いです、気を付けてくださいね」
「はいぃ……」
「.875インチのアンギュラ玉軸受あるかしら? お姉さん大急ぎで2ダース必要なんだけど!」
「インチ規格の部品はあんまり……奥の区画にまとめてますから、一緒に探しに行きましょう」
「補給物資番号Dav-730806が17分前に、Krc-730802が9分前にデッキに届いています。搬入を開始してよろしいですか」
「お願いします、いまAGS用ゲートを開けます。作業はトミーさんとスパルタンさんですか?」
「今回は重量コンテナが多いため、待機中だったアラクネーが加わります」
「じゃあ大型ゲートの方開けます! すこし待って下さい」
「来月少々特殊な食材を仕入れたいので、搬入の打合せをしたいのですが。それから倉庫のスペースを少し貸して下さいまし」
「いいですけど、この前の生きたサメ丸ごとみたいなのはもうイヤですよ……」
「カップトッポギの余ってるのないっすか?」
「ないです」
「みんな勝手なことばっかり言うんですから」
ぷりぷりしながら、それでも隠せない充実感のうかがえる顔で、アンドバリはペコペコとキーボードを叩く。
「それは何を?」
「書式が合ってない伝票がたくさんあって、リネームしてるんです。こういうのをほっとくと、わけがわからなくなっちゃうので」
C-33アンドバリは根っから几帳面で、物事をきっちりと整えるのが大好きだ。たまに娯楽室で見かけたと思えば、本棚の雑誌を巻号順に並べ直していたりする。局地での作戦が多く、備品管理が複雑になりがちなシスターズ・オブ・ヴァルハラだが、こういう性格の隊員はいないので、彼女が開発された理由もわかる。当たり前のようにオルカ全体の物資管理を任されているのも頷けるというものだ。
「アンドバリは本当に優秀だな」
「これくらい当然です。えへへ」
嬉しそうに笑ったアンドバリが、ふいにするどい顔になって廊下の向こうを睨みつけた。
「そこです!」
「ぎゃー!」
ボールペンが矢のように飛び、突き刺さった先は棚のかげを這いすすんでいたアルヴィスのお尻だった。
「くっそー! 今度こそ完璧な潜入だと思ったのにー!」
「逃げるぞ、隠密の白き野獣よ!」
「あなた達は毎回毎回本当にもー!」
「アルヴィス、お前このあいだみんなに怒られてまだ懲りないの」
「ふぎゃっ、隊長!? なんでここに!?」
「なんでじゃない。そんなに元気が余っているなら訓練を追加するから、自室で待機しているように」
「あーん!」
「LRLも、このことはエイミーに報告しておく」
「えーん!」
小さな泥棒二人がしおしおと帰っていくのを見送って、アンドバリがふんすと鼻から息を吐く。
「隊長がいてくださってよかったです。これでしばらく怖がって来ないでしょう」
「私からよく叱っておくから、アンドバリはあまり厳しくしないことだ。一緒に遊んだりもするのだろう?」
「それはそれ、これはこれです。仲がいいからって仕事に手を抜いたりしません」
仲はいいんだな、とレオナは少し安心したが、それは言わずにおくことにした。
「ごめんくださーい」
手土産のお菓子も食べてしまい、そろそろ帰ろうかと腰を上げたところへ、パーティションの戸口をノックする者があった。
「あ、お客様でしたか、すみません」
「構わない、雑談していただけだ。もう帰る」
レオナが立ち上がって手招きすると、新たな客は遠慮がちに入ってきて頭を下げた。アンガー・オブ・ホードの兵站管理担当、T-4ケシクだ。
「H7型の信管を1ケースいただきたいんですけど……」
「ありますけど、またですか? ついこの間補充しましたよね」
「はい。ハイエナさんのハンドグレネード用だったんですが……」いぶかしげな視線を受けて、ケシクの顔がみるみる暗くなる。
「スカラビアさんが……全部私の来る前の危ない仕様のやつに改造しちゃって……!」
「信管を改造? 危険なものなんですか?」
アンドバリがいそいそとお茶を出した。ブラックリバーのどの部隊でも兵站担当者はおおむね真面目できちんとしているが、中でもケシクは几帳面で細かいところに気がつく性格で、アンドバリと気が合う。正直、この性格でよくホードでやっていけると思っていたが、やっぱりそれなりに軋轢はあったようだ。
「床に落としただけでも爆発するような感度なんです。あんなの艦内で持ち歩けませんよ。万が一のことがあったらどうするんだっていうか、聞いたら最初にあの仕様にしたのもスカラビアさんらしいし、朝は起きないし掃除はしないしタバコは吸いすぎだし、何考えてるんですかあの人!」
煎茶をすすりながら、ケシクの声はだんだん高くなっていく。かと思うと、また急にすとんと沈んで、
「実は私、スカラビアさんのこと知らなかったんですよ」
「知らなかった?」
「初期記憶になかったんです」
そういえば、彼女はかなり古い共有記憶しか持たない個体だと、以前復元した時の報告書にあった。カーンのことさえ知らなかったというから、第二次連合戦争期に開発されたスカラビア型のことは当然知らないだろう。
「だから舐められてるっていうか、壁を作られてるのかなって……」
「そんなことないと思いますよ。ケシクさんは仕事すごくちゃんとやってますし、戦闘に出たって活躍してるじゃないですか。きっとみんなケシクさんのこと尊敬してます! ねっ、隊長!」
熱弁をふるうアンドバリにつられて、レオナも頷いた。「第一、オルカの中ではお前の方が先任だろう」
「そうですけどお……」なおも煮え切らない顔のケシクに、レオナは肩をすくめて付け加えた。
「初期記憶にないくらい大したことじゃない。私もアンドバリの記憶はなかった」
「えっ、本当ですか?」
アンドバリがこっくりと頷く。今のレオナは人類滅亡後、北欧の小さな研究所に保管されていた遺伝子の種から復元された個体だ。彼女の知るシスターズ・オブ・ヴァルハラ……つまり復元時に付与された初期記憶の中のヴァルハラに、アンドバリはいなかった。アンドバリ型はスカラビア型同様、連合戦争末期に開発されて部隊編成に組み込まれたモデルである。おそらくあの研究所近辺のヴァルハラ部隊は、かなり早い時期に全滅したのだろう。
「全然そんな風に見えません……」
「だから、大したことではないと言った。同じ部隊の仲間なのだから、真剣に仕事をしていれば自然とお互いのこともわかってくる」
「そういうものですか……」
感じ入ったようにつぶやいたケシクの背後、戸口の向こうでその時、何かが動いた。
「なんだ、あれは?」
「?」
ケシクも振り返って目をこらす。通路のすみの暗がりを、小さめの番重に足が生えたような物体がカチャカチャ歩いている。見ているとそれはある棚の前で停止し、六本ある足の二つを上に伸ばして、棚にある部品や資材をひょいひょいと取って自分のボディに収めはじめた。
「…………」
番重を半分ほど一杯にして、カチャカチャ引き返そうとするところを、席を立ったケシクが踏んづけて止めた。
「これスカラビアさんのです……作りに見覚えがあります」
「あの人は……!」
アンドバリがこめかみに手を当てる。レオナも呆れて首を振った。
「ものぐさな性格とは聞いていたが、銀蝿するのまで機械任せか」
《ちょっとー、誰ー? あーしの宅配3号くん捕まえてるやつ》番重の前端についている複合カメラから、スカラビアの声がする。
「私です!」
《げっ》
「私もいます。この目で見ましたからね」とアンドバリ。
「私もだ」行きがかり上レオナも言い添える。
《げげげ》
「これは没収します。帰ったら話がありますよ!」
暴れる「宅配3号くん」をぐるぐるに縛り上げ、盗品を全部ていねいに元の棚へ戻してから、ケシクは二人の方へぺこりと頭を下げた。
「お二人とも、ありがとうございました。いい機会と思って、じっくり話をしてみます」
「がんばってくださいね」
「ケシクさん、大変ですね」
テーブルの上を片付けながら、アンドバリがしみじみとつぶやいた。
「だが、ホードの戦績は上がっている。スカラビアが来てから、特に砲撃のスコアがな」レオナもそれを手伝いながら、愉快そうに含み笑いをする。「あの二人が一緒にやっているおかげだろう」
アンドバリが目を丸くした。「意外です。ケンカして能率が下がりそうなのに」
「ちゃんと仕事をするって、そういうものなのさ」
アンドバリの、つやつやとした藍色の髪に手を置いて、レオナは軽く撫でた。アンドバリは一瞬だけ何か言いたげな顔をしたが、だまってその手に頭をゆだねてくれた。
実のところ、自分の知識にない新しい隊員(しかも当人は最初から隊にいたつもりの)を迎えるというのは、レオナにとってもそれほど簡単だったわけではない。時には可愛くて仕方なかったり、時には声のかけ方もわからなかったり、戸惑いもあれば失敗もあった。だが今のところ、それなりに上手くやれているようだ。
「グレムリンが、またパジャマパーティをやろうと言ってる。ここで開いてみるのもいいかもしれないな」
「ダメですよ、酔っ払いを倉庫に泊めるわけにいきません。お菓子とジュースはまた融通しますので」
アンドバリがくすりと笑って答えた。これくらいは罪のない役得というものだ。
* * *
「実は、私もあいつのことは知らないんだ」
後日、指揮官級だけで集まって飲んでいる時、スカラビアのことを思い出したレオナが尋ねてみると、カーンは何でもないようにそう言った。
「あら、そうなの」
「旧時代には、うちの隊には来ないままだった。あの頃は早々に本部との連絡が途絶えて、勝手にやっていたからな。先日復元されたのが初対面だ」
「やりづらくはないのか?」マリーがワインを傾けながら聞いてきた。
「今更だ。……まあ、私だけちょっと馴染めていない、という気はするかな。部下どもはみんな知り合いのようだから」
「そういう時はだな、一度ゆっくり差し向かいで酒でも」
「お前はいつもそれだ」うんざりした顔で手を振るカーンに、レオナはふと思い立ってブランデーグラスを向けた。
「もっといい方法があるわよ。ケシクに相談してごらんなさい」
「ケシク?」カーンは豆鉄砲を食ったような顔をした。「ああ、あいつもスカラビアの記憶はないんだったか。しかし……」
「私の見たところ、結構うまくやっているようよ。たまには昔の自分に教わるのもいいでしょう」
「……」
何とも言えず苦々しげなカーンの顔がおかしくて、レオナは笑った。
End
薄闇の中をほそい鋼の線がまっすぐに伸び、銀色の輝きをにぶく放っている。
一方の端はドアノブに結びつけられている。もう一方の端は部屋を横切って椅子の脚をまわりこみ、そこから枝分かれしてテーブルの下と、屋外に通じる換気口の中へ入り込んで、C-4爆薬に埋め込まれた信管につながっている。誰かが不用意にドアを開ければ、開けた本人と、その後ろに控えている仲間の両方を、無数のベアリング弾が穴だらけにしてくれる。
ドアを細めに開けて中をのぞいた程度では駄目だ。身体が入るくらい開けてはじめて起爆スイッチが作動する。ショットガンでドアを破壊しようとしても無駄だ。換気口に仕掛けた爆薬は、ドアに対して銃を構えた人間の頭の位置へ直撃するように向けてある。
芸術的な技巧で張り巡らされたワイヤーと爆薬はしかし、
「オラァァァ! ぷっちょへーん・ざぁーーー!!」
パイルバンカーと体当たりでドアのある壁面を全部崩すという、あまりにも乱暴なブリーチングによって無駄になった。
「バカか、こいつら!?」
薔花は舌打ちをして、次の部屋へ後退しつつ腕のリールを起動する。風に乗って繰り出され、ブルガサリの全身にまとわりついて切り裂くはずだったワイヤーは、しかし割って入ったドラコがぐるぐる振り回す巨大なシールドにすべて巻き取られてしまった。
ワイヤーの特性が分析され、対策を立てられている。薔花はもう一度舌打ちをした。
「チョナ、何やってんだ! 援護よこせ!」天井に設置しておいた爆薬を手動で起爆して時間を稼ぎ、喉元の通信機へ怒鳴る。
《ごめ~ん、私いま捕まった~》
「はあ!?」
二階にいたチョナが捕まったのなら、階段へは逃げられない。瞬間的に判断した薔花は廊下の突き当たりの小さなガラス窓に狙いをつけ、肩から体当たりして突き破った。
冷たい外気が身をつつむ。コートの裾をひるがえして着地すると、そこはゴミ箱が乱雑に並ぶ狭い裏路地で、そして目の前には銃口を突きつけるピントがいた。
「はーい、チェックメイトね」
《セッション終了。攻撃組の勝利》
どこからともなく紅蓮の声が響いてくる。それと同時に、ビルも路地裏も、すべてが光のブロックと化して消えていき、だだっ広く無機質なパネル張りのVR訓練ルームが戻ってきた。
《10分休憩後、攻撃組・防衛組を入れ替えて再スタート》
「ちょっと待てよ! いい加減に……」
《フィールドはアンダーウォーター。必要な装備を用意しておくように》
「おい!」
「クソ、クソ、クソがっ!」
大ぶりのポークソテーに何度も何度もフォークを突き立てながら、薔花はひたすら毒づいていた。
「よしなって、もったいない」
向かいに座るチョナは疲れた顔でうどんをすすっている。
スヴァールバル諸島到着後、正式にオルカに所属する隊員となってから一週間。エンプレシスハウンドの二人に最初に与えられたミッションは、
「マングースチームと、徹底した連携訓練を行うこと」
であった。一昨日から二人はほとんど休みなくホロデッキで模擬戦闘をやらされている。
はじめのうちこそ一方的に翻弄できていたが、マングースのメンバーが二人の戦術を飲み込んでくるにつれ、じょじょに勝率が落ちてきた。今日の午前中などは五セット戦って一回勝てたきりだ。もともとエンプレシスハウンドは奇襲、暗殺、一対多のゲリラ戦を得意とする。集団戦も、同じ相手と何度も戦うことも、本来の運用方針にはないのだ。
「次は絶対ぶっ殺してやる……火薬量をもっと増やして、ワイヤーも……」
「そういうさあ、火力とかスキルとかで何とかするの、もう限界じゃない?」
「……」
言わんとすることはわかる。必ずしも個人のスキルで後れを取っているわけではない。勝てなくなった大きな理由は、マングースチームの連携が上達してきたからだ。ブルガサリを狙えばドラコがかばう。ピントを狙えばミホの弾が飛んでくる。
「私らもなんか練習してみる~? ハウンドコンビネーション!とかいって」
「絶対するもんか」
ズタズタになったポークソテーの一切れをフォークで突き刺し、口へ放り込む。
この流れで今更練習などはじめるのは、いかにも「チームワークを学びなさい」という思惑に乗せられているようで気にくわない。マングースの奴ら真似をするような形になるのも嫌だ。何より薔花もチョナも、生まれてこの方チームワークなどというものとは一切無縁に生きてきた。練習といっても、何をどうやればいいのか見当もつかない。
「あのババア、今更仕返してるつもりなんだ」ポークをもう一切れ、紅蓮の顔に見立てて突き刺す。「私が昔マングースを狩ってたのを根に持って、こんな形でいびりやがって」
「えー。そんな感じでもないけどなあ」チョナはずずず、と丼をかたむけてうどんの汁を飲む。「カイロちゃんの命令なんでしょー?」
「……」
「薔花?」
紅蓮の顔が一瞬司令官の顔に変わって、フォークが止まった。そうだ、訓練の内容はともかく、マングースとの訓練を命じたのは彼だ。監督を紅蓮に一任したのも。
「アイツも、本当は私たちが邪魔なのかな……だからこんな風に……」
「うわ、めんどくさ」チョナは顔をしかめると、丼に最後に残った卵の黄身をつるんと飲み込んで席を立った。
「どこ行くんだよ」
「カイロちゃんとこ~。話しててもらちがあかないから、直接聞いてくるね」
「ちょっと待てよ、おい!」薔花は細切れのポークソテーを慌てて口に詰め込んで、後を追った。
結局その日、司令官には会えなかった。別の子達に一日付き合っていたのだ。ただ、薔花の考えが杞憂だったことだけはすぐにわかった。
《次は攻撃組にピント・ブルガサリ・薔花。防衛組はドラコ・ミホ・チョナ。フィールドは市街地C》
翌日から今度は、双方のメンバーをシャッフルしての戦闘訓練が始まったからだ。
「勝手に動くなって言ってるでしょ!」
「知るか! お前等が足手まといなんだよ!」
《攻撃組にチョナ・ピント・ドラコ・ミホ。防衛組は薔花とブルガサリ。フィールドは旅客機》
「いいかげんにしなさいよ、あんた! ワイヤーの使い方考えろっつってんでしょ!」
「うるっさいんだよ! 見てわかれよ、そんくらい!」
《攻撃組にドラコとブルガサリ。防衛組にミホ・ピント・薔花・チョナ。フィールドは工場》
「今度こそ余計な真似するなよ」
「どっちが!」
《攻撃組にミホ。防衛組にそれ以外の全員》
「おい! いくらなんでも……」
《攻撃組に薔花、防衛組にピント。一騎打ち》
「コラァ!」
「クッソがぁ………」
ベッドに身を投げ出して、薔花は低くうめいた。
朝から晩まで、敵味方を入れ替え組み換え、三十以上ものパターンを試された。勝率をうんぬん言われなくなったのはいいが、一セットごとの心身の疲労がこれまでの比ではない。
何しろスキルも性格もよく知らない連中なので、動きの予測がつかない。来ると思ったところへ来ないし、来ないと思ったところへ来る。ちっとも思い通りに動かないくせに、向こうからはああしろこうしろと偉そうに指示を出してくる。チョナはなんだかんだ言って気心の知れた組みやすい相手だったのだと、不本意ながら気づかされた。
「…………」
そのチョナは悪態をつく力すらなく、枕に顔を埋めたままぐったりと動かない。
正直起き上がるのも億劫だが、何か食べておかないと明日に差し支える。戸棚の奥にカロリーバーか何か残っていないかとかき回していると、無遠慮なノックとともにドアが開いた。
「いるー?」
「おー、へばってるへばってる」
どやどやと入ってきたのはマングースチームの隊員四人だ。
「なんか用かよ」
警戒する口ぶりで薔花は身構え、ワイヤーを仕込んだ腕輪を無言で起動する。その目の前に、ブルガサリが手にした紙袋を突き出した。
「これ貼っときな。ドクターちゃん特製バイオロイド用湿布」
「?」
「メシ食う気力もねーだろ。今日はキツかったかんな」ドラコが持参したシールドの収納部からお菓子や飲み物を次々にベッドの上へ取り出す。
「おい、何を勝手に……」
止める間もなく、コップを床に並べるブルガサリ。ミホは鼻歌を歌いながら、寝たままのチョナの太ももに湿布をぺたぺた貼りはじめている。
「お゛~~~……」チョナが地鳴りのようなうめき声を上げた。
「あんた、ヘビの遺伝子が入ってるんだっけ。何食べるの? チキンスープとか持ってきたけど」
「飲む~……」
「ちょっと、お前ら」
「ジュースあるぜ!」
満面の笑顔でドラコがインスタントスープと缶ジュースを差し出す、チョナがのろのろと身を起こしてカップを取ったので、薔花もしぶしぶ缶を受け取った。ジュースはキンキンに冷えていた。
「だーから何度も言ってるだろ、ワイヤーと爆弾はどの辺に仕掛けるかだけでも最初に共有しとけよ! わかってれば私らだって使いようがあるんだからさあ!」
「お前らに使ってほしくて仕掛けてんじゃねえよ! だいたいどの辺に張るかなんて見たらわかんだろ!」
「わかんねーよボケ! お前はあれか、ミッパンチャンか!」
「ああ!?」
「ドラコ、もしかして察してちゃんって言いたい?」
「かまってちゃんじゃなかったっけ」
「まあ薔花はどっちもだよね~」
「うるっさい!!」
三十分後、室内には怒声が飛び交っていた。主に怒鳴っているのはドラコと薔花で、ミホとブルガサリがたまに口を挟み、チョナはケラケラ笑っている。
「おもしろ~い。薔花がキレてるのはいつもだけど、薔花にキレてる人がこんなに集まったの初めてかも」
「好きでキレてるんじゃねえよ!」怒鳴り返してから、薔花はほんのり赤くなった目元で一同を見渡す。別にアルコールが入っているわけではないのだが、すっかり場酔いしてしまっている。
「大体、お前らみたいな仲良しごっこなんてどうせ」
「うわ、仲良しごっこってリアルで言う奴初めて見た」
「ねえねえ、仲良しごっこと本当の仲良しってどうやって見分けるの?」
「馬鹿にしてんのか!!」
「私は見てるからね」その時、言葉少なにピーチソーダばかりぐいぐい飲んでいたピントがすっくと立ち上がって薔花を指さした。
「記録映像。あんたが昔どんなことをしたか、私は知ってる。でも、もうそんなこと言う時代じゃないのもわかってる。おかーさんと司令官が信じてるなら、私もあんたのことを信じようと思うわ。だからあんたが信じるに値するかどうか、私はずっと見てるから」
こちらも場酔いしたのか据わった目つきでピントは一息に言い切ると、
「おわり」ぺたんと据わって新しいソーダの缶を開けた。
「勝手に見てろ」薔花は低くつぶやいた。
さらに小一時間ほど騒いでから、マングースチームは引き上げていった。
「これ以上うるさくするとシティガードが来るし」
「明日もあるし」
「おやすみー」
空き缶やゴミはさすがに持ち帰っていったものの、お菓子の食べかすやジュースをこぼしたシミが部屋中に散らばっている。薔花は額の青筋を押さえて、深く深く息を吐いた。
「アイツら……」
「あ゛~……たまんないわ、これ。ジンジンくる…………」
ふともも一面に貼られた湿布をさすりさすり、チョナがのろのろとベッドから身を起こす。
「お前も手伝え」
「は~い」
手分けして床を拭き、食べかすを払う。ベッドにハンディクリーナーをかけていたチョナがふと笑った。
「こういうの、ちょっと悪くないね」
「何がだよ。最悪だよ」シーツの染みをチェックしながら薔花が毒づく。
「え~?」チョナはさらに笑った。「一日頑張ってクタクタになってさ、ご飯たべて部屋に帰ってきてさ。自分のベッドがあって、遊びに来る友達なんかいたりしてさ。こういうのじゃん?」
「だから何がだよ! 大体あんな連中友達でもなんでもない」
なおもニヤニヤ笑いをやめないチョナの背中に、薔花は携帯ほうきを投げつけた。
* * *
さらに数日が過ぎた。訓練は相変わらず苛酷だったが、少しずつお互いの動きのタイミングが読め、息が合うようになってきた。薔花にとってそれは嬉しいというよりは、むしろ新たな苛立ちの種でもあったのだが。
「皆さん、今日まで厳しい訓練お疲れ様でした。今日は今回の特別プログラムの総仕上げを行います」
その朝、フロアに下りてきた紅蓮は言った。
「総仕上げ? ってことは、今日でこの訓練終わり?」
紅蓮がうなずき、全員が一様に安堵の表情を浮かべた。薔花もやれやれと肩をすくめたが、
「最後のセッション、攻撃組は薔花、ピント、ブルガサリ、ドラコ、ミホ。指揮は薔花が執りなさい」
「は!?」紅蓮の言葉に目を剥いた。
「防衛組は私とチョナ。指揮は私が執ります」
「はいはい。よろしく~」
あんぐりと口を開けたままの薔花を後目に、二人はさっさとデッキへ行ってしまう。
「いや、ちょっ……」怒鳴るタイミングさえ逃して、薔花の手が空を泳ぐ。自分がマングースチームの指揮をとるだって?
できる、できない以前に、マングースの連中が従うはずがない。自分が逆の立場だったら絶対に従わない。同じ遺伝子から生まれたからって、才能まで同じだとでも思っているのか。
「そんじゃ行くぜ、リーダー」
「しっかりやってよね」
と、ドラコとブルガサリが薔花の背中をポンと叩いて先へ行く。ピントも黙ってその後に続いた。
「おい待てよ、納得すんのかよ」
「何に?」最後に薔花を追い越したミホが振り向く。
「このチーム分けだよ!」
ミホはうすく笑って、後ろ向きのまま二、三歩進んだ。「おかーさんはあんたならできるって思ったんでしょ」
「……」
「それとも、自信ない?」
「舐めてんのか!」
自棄になった気分で、薔花はずかずかと大股にホログラムの指揮所へ入った。すでに四人がテーブルを囲んで、薔花を待っている。
テーブルに投影されたマップを睨む。防衛組はすでに配置を完了していた。立てこもっているのは小国の大使館。大使を含むVIP(役のNPC)五名が人質になっている。建物は南向きの二階建て。集音装置で建物内の音を拾ったところ、防衛組と人質は全員二階正面の大部屋にいる。大使館はオフィス街にあり、薔花達は隣のビルの一室を指揮所にして、敷地を見下ろしている形だ。
二名では多くのことはできない。人質を監視しつつ窓を警戒しているのが一名、階下とそれ以外の方向を見張っているのが一名といったところだろう。薔花の視線がマップの隅々を素早く走る。監視の死角はどこか。侵入しやすい場所、迎撃しやすい場所はどこか。逃走ルートになりうる場所はどこか……テロを仕掛ける側も防ぐ側も、目を付ける場所はさして変わらない。薔花自身も昔はよくこういう所を襲ったものだ。鎮圧にやってくるマングースチームをおびき寄せるために。
「……西側から屋根に下りて、ラペリングで突入する。ピントがスチールドラコとブルガサリを運ぶ。アタシとミホはここで援護」
「屋根にトラップは?」
「アタシなら仕掛けるけど、チョナの奴はそういうの下手だから、この短時間じゃ無理」
何か口答えされるかと思ったが、三人とも頷いて素早く部屋を出ていった。ほどなく、ドラコを抱きかかえたピントが、指示通り建物西側から大使館の屋根に着地する。
その途端、爆発が起こった。
「!? ポニー、状況知らせろ!」
《ポニーよりローズ、ワイヤートラップに引っかかってドラゴンが負傷、私は無事! トラップないんじゃなかったの!?》
《迎撃チームより通告です。「見せしめに人質を一名殺した」》
ピントの怒声にかぶさるように機械音声が告げる。それで薔花は悟った。
チョナではない、紅蓮だ。紅蓮が薔花の手口を真似てワイヤートラップをしかけたのだ。紅蓮にできることが薔花にもできるならば、その逆も然りということか。
「上ッ等だよ、ババア……!!」薔花はヘッドセットのフレームが歪むほど力一杯握りしめて、獰猛な笑みを浮かべた。
「ポニー、すぐ戻ってスターを連れてもう一度屋上。トラップはアタシが何とかする。チョコはここで待機、催涙ガス弾の準備。あと玄関から出てくる奴は全員撃て」
それだけ言うと返事を待たず、ふわりと窓から宙に踏み出す。ビルの壁にひっかけたワイヤーで落下速度を和らげ、木の葉のように緩やかに舞い降りながら、薔花は大使館の屋上に目をこらした。
思った通り、コンクリート張りの無骨な屋上の要所要所に、薔花がやるのとよく似たワイヤートラップが仕掛けてある。見よう見まねにしてはそれなりのものだが、本人の目から見れば子供だましも同然だ。トラップの死角をすぐに見定めて、薔花は音もなく着地した。
ドラコは屋上のすみに座り込んで顔をしかめている。左脚が膝のあたりまで、べっとり赤黒い血に濡れていた。むろんただの映像処理で本当に負傷しているわけではないが、訓練用スーツの作用で左脚は動かせないし、痛みも感じているはずだ。そこから動くな、と薔花は手振りで合図して、袖口に仕込んだワイヤーカッターを取り出した。
「ねえ、さっきの記録ってのですけど」
「黙って。そろそろ動きがある頃です」
紅蓮はチョナの言葉を手で遮って、周囲の音に神経を集中した。
トラップが発動してから五分。いきり立って強引に突入してこなかったところは、まずは合格といえよう。だがそろそろ次の手を打ってこないと、こちらに時間を与えすぎることになる。作戦を変えて階下から来るか、あるいは……。
ズン、と天井が揺れた。よく知っている震動だ。
「まさか、天井を!?」
ぶち抜こうというのか。確かにブルガサリのパイルバンカーなら屋上から貫通することも可能だろうが、力業すぎる。
二人の意識が天井へ向いたその一瞬、窓から何かが撃ち込まれた。黄色いガスが噴き出す。催涙弾だ。
そしてその直後、別の窓を突き破って三人の人影が突入してきた。驚きつつも警戒を忘れなかった紅蓮の氷結ボルトで一人を射止めたが、二人目に肩を撃たれてボウガンを取り落とす。即予備の拳銃を取り出しつつ、それがブルガサリだったのに紅蓮は目を見張った。
ブルガサリはアサルトライフルを構えている。制圧火力は圧倒的に向こうが上だが、こちらには人質というアドバンテージがある。あえて足だけ自由にした人質二人が逃げまどうのを盾にして銃撃戦に持ち込む。
チョナは涙と鼻水を垂れ流しつつ廊下へ逃げ出そうとしたが、突入班の三人目である薔花につかまった。向こうには人質がいないが、ワイヤーも使えない至近距離の格闘戦ならチョナに分がある。ブルガサリを牽制しながら視界の隅で注意を向けると、ちょうどチョナのしなやかな回し蹴りが薔花の側頭部にヒットしたところだった。小柄な薔花の身体が真横に吹っ飛ぶ。
その袖口から、きらりと光を跳ね返す何かが伸びている。
「チョナ!」
注意して、と続けるより前に、倒れた薔花が腕をぐいと引いた。極細のワイヤーが、窓枠をこえて屋根の上へ伸びている。それが今たぐり寄せられて、先端にくくりつけられていたものが室内にころがり落ちてくる。チョナの目の前に落ちてくる、その小さな箱を紅蓮は知っている。
「それを撃てぇ!!」
薔花が叫んだ。最初に仕留めた一人……ピントが、肩から首にかけてを真っ白に凍りつかせたまま強引に起き上がり、返事もせず引き金を引いた。
閃光と爆音。紅蓮が屋上のトラップに使っていた対人小型地雷が爆発し、血だるまになったチョナが床に倒れる。
こうなってしまっては脱出するしかない。人質を使ってなんとか、ブルガサリを一瞬でもひるませて……伸ばした手に冷たいワイヤーの感触が巻き付いて、紅蓮は観念し、動きを止めた。
「隊員二名重傷、人質一名死亡、一名重傷。特に、自分たちの攻撃で人質を傷つけてしまったのは大きな減点ですね」
スコアを読み上げる紅蓮の冷たい声に、薔花は舌打ちをした。「仕方ないだろ。あんなとこにいる奴が悪いんだよ」
対人地雷を撃って爆発させた時、たまたま近くにいた人質の一人を巻き込んでしまったのだ。だがあのタイミングでなければチョナを仕留めることはできなかった。最善の選択だったはずだ。
「私たちの仕事に『仕方ない』はありません。犠牲が出たか、出ないか、結果がすべてです。常にベストの結果を目指して、最大限の努力をゆるめてはいけません」
そう言い切ってから、紅蓮の声はふと柔らかくなった。
「ですが制圧は成功、最重要VIPである大使自身は無事、敵リーダーも生かしたまま確保。初めての指揮にしては上出来といえるでしょう」
薔花は目を上げた。紅蓮は穏やかに、嬉しそうに笑っていた。
「屋上でパイルバンカーを使ったのは、ドラコ?」
「……そうだよ。ちょっとでも意表を突いてやろうと思って」
「いい判断でした。実際あれで、ブルガサリは屋上で陽動役かと油断しましたからね。彼女は一番優秀なアサルトマンですから、突入班から外さなかったのも正解です」
「そうそう、あんた意外と私たちのスキルちゃんと把握してんだね」ブルガサリが、思わず咳き込むほど強く薔花の背中を叩いた。
「動きもちゃんと見てるしね。えらいえらい」
「あと、自分が援護してもらえるかめっちゃ気にしてるよな!」
「ま、おかーさんに比べたらまだまだだけどね」
他のマングースのメンバーも次々に寄ってきて、肩を叩いたり、頭をわしゃわしゃ撫でたりする。鬱陶しくなって振り払っても、まだ皆薔花を取り囲んで笑っていた。チョナもニヤニヤしながら寄ってきて、
「立派にやれたじゃ~ん。血は争えないって奴なんですかねえ、お姉さん?」
「はあ!? 何を」
「そうですね」紅蓮はちょっと照れくさそうに何度か咳払いをしてから、
「さすが私の妹、と言うべきかもしれません」
「ざっけんなああああ!!」
薔花は全身をふるわせて力いっぱい怒鳴ると、きびすを返して早足で歩き出した。
「どこへ行くんですか。これから全体反省会ですよ」
「知るか!! 勝手にやっとけ!!」
「そんな薔花ちゃんにマル秘情報~。カイロちゃん今日の午後はホライゾンカフェに行くって言ってたよ」
「うっさいうっさい!!」
もう沢山だ。金輪際こんなアホくさい訓練に付き合ってやるものか。アイツに会って山ほど文句をぶちまけてやる。かっかと火照る頬を何度もぬぐいながら、薔花は足早にカフェへ向かうのだった。
* * *
――――
「……トラップが作動しましたね。おそらく、ピントとドラコでしょう」
ぱらぱらと埃の落ちてきた天井を見上げて、紅蓮はしずかに呟いた。二人とも無力化できていれば理想的だが、付け焼き刃のワイヤートラップでそこまでは望めない。おそらく、引っかかったのは注意力の足りないドラコだけだろう。
「さっすがあ~。なんでもできるんですね、隊長さん」
廊下から戻ってきていたチョナが、ナイフをくるくると手の中で弄びながら、からかうように言う。無造作にぶらぶら歩いているように見えて、窓から狙撃されるエリアを慎重に避けているのはさすがというべきか。
「紅蓮で結構です。作戦中は私語を慎むように」人質へ定期的にボウガンを向けて牽制しつつ、紅蓮は答える。
「んじゃ、紅蓮さん」
チョナは気にした風もなく側に寄ってくると、声をひそめた。「紅蓮さんって、カイロちゃ……司令官とエッチしたこと、あります?」
「!?……作戦中ですよ」
「いいじゃないですかあ。教えて下さいよ~」
「……」
一見冗談めかしたその口調の裏に、みょうに真剣なものを感じて、任務中にもかかわらず紅蓮は答えてやる気になった。「……あります。何度も愛していただきました。あなたは?」
「何度もか~。いいな~」チョナはいたずらっぽく笑った。「私はまだ一回だけ。まあ一回っても夕方から六時間くらい、ずーっと独り占めしてましたけどね~」
六時間!?と内心息を呑みつつも、紅蓮は先を促す。
「ご飯食べたあとずーっと繋がったまま、ゆっくりゆっくりお互い気持ちよくし合って、トロトロになってえ。そのまま眠っちゃって、朝になっても司令官がまだ私を抱きしめてくれてるの」
二つに割れた舌先をチロチロと出し入れしてチョナはもう一度いたずらっぽく笑い、そしてふいに笑みを消した。
「……誰かの体温に包まれて、あったかいまま目を覚ましたなんて生まれて初めてで。その時私……泣いちゃったんですよね」
紅蓮は首を回して、チョナをまっすぐ見た。
夢見るようなその眼差しを見れば、チョナがどんな気持ちでいるかは手に取るようにわかる。紅蓮も、他の多くの隊員たちも、彼のことを考える時、同じ気持ちになるのだ。視線に気づいて、チョナは慌てたように長い銀髪を何度も手ですいた。
「あーだから、何が言いたいかっていうと……オルカにいるのはいいなって、私思ってるんで。結構、本気で。たぶん薔花のやつも同じだと思います。私らなんてーか、アレだから、信用したくないかもですけど。そこだけはマジなので、当てにしてもらって大丈夫というか」
「ええ。頼りにさせてもらいます」心から、紅蓮は言った。
「あなたのような人が、薔花の仲間でいてくれてよかった。これからも、どうか彼女を支えてあげて下さい。私たち皆が、あなたたち二人を支えます」
ほっとしたように、チョナは柔らかな笑顔になった。
紅蓮はボウガンを持ち上げて、こちらを見ている人質を追い払う。最低限の行動プログラムしか入っていないNPCに盗み聞きをするような知性はないが、こういう話をしている時に見られるのは気分が悪い。
「それと、一つ教えておきます。訓練中の会話はすべて録音されて、反省会の資料として共有されますので」
「え゛」チョナの笑顔が固まった。
「ちょっ……あの、ここだけオフレコってことになりません?」
「なりません。さ、廊下側の警戒に戻って下さい」
「あの、ちょっと」
――――
足早に去っていく薔花と、薔花を追い払って明らかに胸をなで下ろしているチョナを、紅蓮は交互に見比べながら微笑んでいた。
たとえ薔花が反省会に出なくても、他の子たちが知れば面白がって教える可能性が高いわけだが、まあそのあたりは彼女の努力を汲んで手心を加えてあげてもいいだろう。
こういう他愛のない小さな秘密をいくつも、いくつも共有して、家族は本当の家族になっていくのだ。
End
「おそらくそれは、シュールストレミングというものではないでしょうか。ニシンを塩漬けにして発酵させたスウェーデンの伝統食品で、画像がこちらに」
「ほらー! ほらあー!! やっぱり失敗してなかったじゃない! お姉さんのツナ缶製造機ちゃんと動いたじゃないーーー!!」
何やら一人で憤慨して、鼻息も荒く去っていくフォーチュンの背中に向かって、ムネモシュネは静かに頭を下げた。ツナ缶製造機でシュールストレミングができたのなら、それは失敗なのではないだろうかと思いながら。
記憶の箱舟には「人類が残したすべての記録」が保管されている。具体的にはそれは、旧時代に公共または商業電子ネットワーク上に存在していたありとあらゆるデータを収録した超巨大なメインアーカイブと、電子化されていない紙の文書記録や書籍、絵画、音楽、映像作品などを可能な限り収集・データ化したこれも巨大なサブアーカイブからなる。レモネードデルタの侵攻により深刻な被害を受けはしたが、無事に残った部分だけでも世界最大規模のデータベースであり、レジスタンスの今後の作戦計画においても、もっと身近な日々の生活のためにも、情報源としての価値は計り知れない。
しかし一方、その情報量はあまりに膨大すぎて、扱い方をよく知らない者がアクセスしても簡単には求める情報にたどり着けない。それにまた、箱舟は人類共通の遺産でもある。オメガの暴虐は論外としても、不用意なアクセスによりデータを損なうことは厳に避けねばならない。
そんなわけで、知りたいことや調べたいことのある者に代わって適切にデータベース内を探し、しかるべき情報を速やかに引き出す、いわば「司書」の役割が必要ではないか?という議論がオルカで起こったらしい。そしてその任には、これまで箱舟の管理者だったムネモシュネがあたることになった。
ムネモシュネにとっては、長年慣れ親しんだ業務の一環である。むろん人間から直々の任命であれば断ることなどありえないが、不満も不安も少しもない。ただ想定外だったのは、閲覧窓口が開設初日から大盛況だったことだ。
「質のいい読み物が欲しいの。そうね、ピュリッツァー賞とゴンクール賞の歴代受賞作を、新しい方から10年分くらいお願いできる?」
「『陳氏菜経』の李卓吾本はありますか? 隆慶以降の校閲版では削除されたレシピが載っていると聞いたことがあるもので」
「ダイエット法を調べてください。できるだけ簡単でよく効くもの……」
「火星の開発状況の情報って見られますか」
「昔サンディエゴの空軍基地で最初のグリフォンモデルに飛び方を教えたっていう伝説のテストパイロットのこと、何かわかる?」
「マジカルモモ! マジカルモモの資料をあるだけお願いします! 設定資料と台本と絵コンテと、あと製作スタッフの個人SNSで公開されたラフデザインとか、そういう非公式なやつは特に重点的に!」
一般来館者用の第二閲覧室に設けられたカウンターには朝から晩まで行列が絶えることがなく、受付時間を一時間以上延長して、それでも足りずに翌日用の整理券を急遽配布することになった。
「……ふう」
初日だから皆、物珍しさで来ているのだろう。慌ただしかった一日の最後に、ムネモシュネはそう結論づけた。
しかし、翌日も、その翌日も、窓口はやはり大盛況だった。
「ご希望の15坪前後のカフェの設計図ですが、近代欧米のものを中心に32件見つかりました。それとノルウェーの建築法規集がこちらです」
「ありがと。ホライゾンの連中ってば、意外と注文が細かいのよ。ちょっと勉強し直さないと」
「こちらが当時の業界紙、こちらは芸能関連のエッセイ類です。これらを見る限り芸能プロデューサーというのは商業面の責任者のことであって、アイドル個々人の身の回りの世話や精神面のケアといったことは業務に入っていなかったようです」
「ほら、だから言ったじゃない!」
「ええー! だって聞いたもん! プロデューサーはアイドルの一番のファンでパートナーだって! だから私達も司令官に」
「それゲームの話じゃないの?」
「旧時代の主要な大型船舶輸送航路と、主な海難事故のニュース記事です。両者のデータを重ね合わせれば、大型船舶が沈んでいる座標が調べられるかと」
「うーん、そういうのもいいけどさ、もっとこう、謎を秘めた海賊の財宝の地図とかないの?」
「フィクションの資料でよろしければありますが……」
「ふう…………」
一日の終わりに消耗を感じるなど久しぶりだ。デルタの襲撃からオルカがやってくるまでの二ヶ月間、ムネモシュネはほぼ不眠不休で施設の修復と警戒にあたっていた。その頃と比べれば、問題にならないほど楽なはずなのに。
オルカの幹部クラスや技術・情報系の上位スタッフなど、業務上データベースを使う者には個別のアクセス権が与えられている。だから閲覧カウンターを訪れるのは、プライベートで知りたいことや読みたいものがある者だけだ。それがこんなに大勢いるということが、ムネモシュネにはひどく意外だった。
ムネモシュネ自身も、業務外でデータベースを閲覧したことはある。吹雪の夜など、たまに植物図鑑や花畑の写真を眺めたりしたものだ。しかしそれには、「命令されていないことを勝手にやっている」という罪悪感が常に伴った。オルカのバイオロイド達に、そんな様子は少しも見られない。彼女たちが特別なのだろうか。それとも、自分のように感情モジュールを抑制していないバイオロイドにとっては、それが当たり前なのだろうか。
その日、最初に訪れたのは一体のAGSだった。
「ここは、AGSの申し込みも受け付けているのかな」
人間とほぼ変わらないサイズのボディ。丸みのある女性型のシルエットに、白と水色を基調にした涼しげなカラーリング。箱舟のデータにあるどのAGSとも違うが、この外見については通達を受けている。ムネモシュネは丁寧に頭を下げた。
「いらっしゃいませ、グラシアス様。その節はお世話になりました」
彼女……ビスマルクコーポレーションのグラシアスはオルカとは別にこの島に駆けつけ、デルタ勢力の駆逐に協力してくれていたという。本来の姿は巨大なドラゴンだが、オルカの技術陣が新しいボディを作ったのだそうだ。
「礼を言われるようなことはできていない。襲撃自体を止められなかったのだから、むしろこちらが詫びなければならぬ」
氷の花弁のような装飾の付いた頭を振って、わずかに視線を落とすグラシアス。その優美な仕草に、ムネモシュネはしばし見入った。
「……それで、本日はどのようなご用でしょう」
「うむ、捜し物をしている。ここは、コンピュータゲームのデータなどは置いているだろうか?」
「もちろんです。題名をどうぞ」コンピュータゲームを欲しがる隊員は実際多い。ムネモシュネは手慣れた指さばきで該当ジャンルの検索窓を呼び出した。
「助かる。『サイクロプスプリンセス 強襲!スクランブル大魔境のマッスルウェディングベル』というのだ」
ずいぶんと長い名前だ。ニュースやレビュー記事らしきものがいくつもヒットしたが、プログラムファイルのカテゴリからは部分一致のデータばかり出てくる。サイクロプスプリンセスの名を冠したゲームは、どうやらずいぶん沢山あるようだ。
「メーカー名や対応プラットフォームなどはおわかりでしょうか」
「すまぬ、名前以外は詳しくないのだ」
ムネモシュネはレビュー記事を一件開いて内容を読んでみた。「あ……これは、『アーケードゲーム』と呼ばれる種類のものですね」
「そうだったかな。その、アーケードゲームというのだとデータがないのか?」
「残念ながら……」
配信されたゲームであれば一般市場にデータが流通しており、それらは残らず保存されている。しかし専用店舗に筐体で置かれるアーケードゲームは、基本的に個々のハードウェアの中にしかデータがない。メーカーや工場の内部サーバにはあっただろうが、そこまで踏み込んで保存できたケースは稀だ。「人類が残したすべての記録」と謳ってはいてもそれは理念であって、限界はあるのだ。
「そうか……いや実は、小さい方の姫君が、そのゲームを知っているらしくてな。この間、姫と楽しそうに話していたので、遊ばせてやれたら喜ぶかと思ったのだ」
検索結果の表示されたホロディスプレイに指をふれて、グラシアスは残念そうに言った。発光機能を備えた光学センサーに過ぎないはずのその両眼が、ムネモシュネにもはっきりと寂しげな眼差しに見えた。
AGSの情報処理系には感情モジュールが標準搭載されており、最高級モデルともなればほぼ人間と同等の感情表現も可能になる。知識として知ってはいたが、実際にその最高級モデルを目にしたのは初めてだ。機械でありながらこれほど情緒豊かにふるまえるAGSがいるなら、それは自分のような……生物でありながら機械に近づくことを求められたバイオロイドの、ほとんど上位互換といえる存在なのではないか。ムネモシュネはふとそのように考え、そんな羨望めいた気持ちが自分にあったことに驚いた。
「つまらぬことで煩わせたな。姫への贈りものは、また別に探すとしよう」
「お待ち下さい」きびすを返したグラシアスを、ムネモシュネは呼び止めた。「力不足で申し訳ありません。もう少し調べておきますので、明日またお越しいただけませんでしょうか」
その日一日、ムネモシュネはわずかな暇を見つけては改めて検索をかけてみたが、結果は同じだった。
より深く潜ってデータベースの中を直接探す方法もあるが、ムネモシュネ自身そういうジャンルに詳しいわけではない。そもそも「記憶の箱舟」計画の重点は自然誌や学術論文・公文書など公共性の高い記録にあり、文化・芸術、それもサブカルチャーには相対的に関心の薄い方だったはずだ(もちろん、それでも膨大な量のデータがあるのだが)。検索で見つからないものが、他の方法で出てくる可能性は低い。受付時間が終わり、夜間の淡い照明に切り替わった閲覧室で、それでもムネモシュネはホロディスプレイに向き合ったまま動かなかった。
脳裏から、グラシアスの寂しげな眼差しが離れない。自分でもよくわからない理由によって、あの眼差しをそのままにしておいてはならないと、ムネモシュネは強く思った。
自分の能力が及ばないならば、他者の手を借りるしかない。さいわい昔と違って、今の箱舟には大勢の他者がいる。
「ふむ。それでその、サイプリさんのゲームを探すのを手伝ってほしいと」
「はい。勤務時間外にご負担をおかけするのはたいへん恐縮ですが……」
すでに部屋着に着替えナイトキャップまでかぶっているT-9グレムリン1933、オルカのグレムリンに向かってムネモシュネは深々と頭を下げた。
オルカが箱舟に来て間もない頃、このグレムリンは真っ先にムネモシュネの所へやってきて、数テラバイトにおよぶ何かのゲームのデータをダウンロードしていった。実際の所、データベースへの無制限のアクセスが差し止められたのは、彼女をはじめとする数名の隊員があまりに頻繁にダウンロードを重ねたのがきっかけともいえる。
グレムリンは難しい顔をして腕を組んでいる。夜間に突然部屋に押しかけられて、迷惑に思っているのだろう。それも当然だ。だが彼女にはおそらくダウンロードしたいデータがまだまだあるはずで、自分の立場であればそれを見返りとして提示できる。ムネモシュネなりの精一杯の打算であったが、
「是非やらせて下さい!」
案に相違してグレムリンは、にんまりと実に嬉しそうな笑顔でナイトキャップを脱ぎ捨てた。
「ご協力いただけるのでしょうか」
「あったり前じゃないですかオタクはそういうの大好きなんですよ! さあ行きましょうすぐ行きましょう」
逆に手を引っ張られるようにして戻ってきた閲覧室で、ムネモシュネは改めてここまでの経緯と、検索結果を説明した。
「『スクランブル大魔境のマッスルウェディングベル』名前は聞いたことがあります。2090年代あたりのタイトルだったかな」
言いながら、グレムリンはキーを叩いて検索をかけている。当然ながら、ムネモシュネと同じ結果が出た。つまり何もない。
「なるほど、こうなるわけね。古いゲームだし、生きた筐体が残ってるってことはないよねえ……アケゲー……アケゲーのデータかあ……」
ブツブツ呟きながらさらにしばらくいくつかのキーワードを試したり、ファイルリストを眺めたりしていたグレムリンがふと目を上げた。
「旧時代のインターネット上にあったデータは、全部ここにあると思っていいんですよね」
ムネモシュネは頷いた。「『記憶の箱舟』計画の開始から人類滅亡までの30年あまりの期間に存在したあらゆるウェブページ・コンテンツについて一日単位のスナップショットが保管されています。先日レモネードデルタに破壊された分を除いてですが」
「それは、非合法な内容のサイトでも?」
「はい。コンテンツの内容による例外はありません」
「うーん」グレムリンは眼鏡をクイッと直し、顔をしかめてキーを叩いた。いくつかの検索ワードが流れては消え、やがて一つのウェブサイトのスナップショットが現れる。黒い背景に灰色のおどろおどろしい書体で「HAVEN」とだけ書かれている。
「これは?」
「違法ROMデータが置いてあるサイトです。ほんとはゲーマーの道義としてこういう所に頼りたくないんですけどね、まあ今の時代ならセーフで、す、よ、ね……っと」
グレムリンはサイトの内部をあちこち巡回したのち、トップページにある検索窓に、
「SE_KI_GA_N_NO_HI_ME」
と入力した。
隻眼の姫。サイクロプスプリンセスのことだろうか。英語のサイトなのに、なぜ日本語のローマ字などで検索を? ムネモシュネがその疑問を口にするよりも早く、
「ビンゴぅ!」
グレムリンが明るい声を上げた。「多分これです。えーダウンロード、一応ウイルスチェック……」
画面内では数十ギガバイトほどのデータが、ローカルストレージに引き出されている。解凍されたファイル名には確かに「cyclops_princess_romwbish」とあった。
「エミュレータは……同じサイトにあった、よしよし。でもいっぺん走らせてみないとね。すいません、これ一旦私の方で預かっていいですか? 明日の朝にはちゃんとしたのをお渡ししますんで」
「ありがとうございます……」ムネモシュネはほとんど呆然と呟いた。「あの、今のキーワードはどのような?」
「ああ、こういうアングラなデータって検索よけにわざと名前を変えてあることが多いんですよ。英語のサイトならファイル名だけ日本語にするとか、一音ずつ区切るとか」
「検索よけ……ですか」
「検索で見つけやすいってことは、警察とかに見つかりやすいってことでもありますからね」
そんなテクニックがあること自体、ムネモシュネには想像の外であった。「感服いたしました。ありがとうございます」
「いえいえ」朗らかに笑うグレムリンに、ムネモシュネはもう一度、深く頭を下げた。
「あ、ところでこのサイトもうちょっと見てっていいですか? 意外と貴重なROMがちらほら……」
瞳と眼鏡のレンズを輝かせて画面に見入り始めるグレムリン。先ほどゲーマーの道義がどうとか言っていた気がしたが、ムネモシュネは触れないことにした。
翌朝、約束通り窓口を訪れたグラシアスは、二人分のコントロールパネルとホロディスプレイ投影装置を備えた立派なポータブル筐体を見て飛び上がらんばかりに喜んだ。
「こんなものまで保存されているのか、ここは。すごいものだな」
「いえ、箱舟にあったのはデータだけです。そのほかはグレムリン1933様が、すべてあつらえて下さいました」
「おお、その者にも礼を言っておかねばなるまい。姫君たちが大喜びすることだろうな」
一抱えもある筐体を大事そうに撫で回すグラシアスを見ているうち、
「人間様は、なぜ、箱舟の管理者として本モデルを作ったのでしょうか」ふと、そんな言葉が口をついて出た。
「何と?」
表情のないフェイスパネルが、きょとんとしているのがわかる。ムネモシュネは急いで言葉を継いだ。
「本モデルはバイオロイドでありながら、機械のような精密さと堅牢さを求めて開発されました。この業務にはそうした性質が必要だったからです。ですが、グラシアス様のような……」
「まるで人間のような感情表現をする機械がいれば、それで間に合うのではないか、と?」グラシアスはおかしそうに、その先を引きとった。
「それは感情モジュールを買いかぶりすぎだな。私たちの感じているこれが人間の感情と本当に同じものかどうか、確かめる方法はないのだ。それから、これは想像になるが……」
グラシアスは口元にあたる部分に細い指をそえて、周囲を見回した。
「この箱舟は、地球に生きた生命の記憶を保存する施設だ。ならば、それを管理し、守る者は同じ『生命』であってほしいと、人間たちは思ったのだろう。私のような機械ではなく。……つまるところは、思い入れの問題だ」
「思い入れ……」
「人間というのは勝手な思い入れを、勝手な相手に託すものだ。私はそれをよく知っている」グラシアスは肩をすくめて、苦笑するようにクックッと小さな音を発した。「相手にもよるが、私は誰かの思い入れを背負うのは嫌いではない。そなたはどうだ?」
ムネモシュネは遠い、遠い昔の人間たちを思い返した。もう顔も覚えていない、ウォッチャー・オブ・ネイチャーの研究者たちを。
そうか。自分は、彼らに託されたこの仕事が好きだったのだ。ムネモシュネは理解した。だから探し物を見つけられないままグラシアスを帰したくなかった。だから、自分がこの仕事にとって意味のある存在だと思いたかったのだ。
「はい。本モデルも……同じように感じます」
ムネモシュネはもう一度、グラシアスに深く頭を下げた。
* * *
「ご要望の動画リストです。2100年代前半の動画配信サイトから、できるだけチャンネル登録者数の少ない零細配信者の、政治・社説系の談話を選び出しました」
「ありがとー! そうそう、こういうのが欲しかったんだ。動画は文書より改竄しにくいし、知名度が低いほどオメガの手が届いてないやつも多いでしょ? こういう所から昔のことを復元してみたいんだ」
「それであれば、欧米の新聞で一般的だった風刺的な一コマ漫画なども役に立つかもしれません。後日リスト化しておきます」
「それいいね! お願い!」
ムネモシュネは今日もカウンターに立つ。
あれからグラシアスは訪れていない。次に来たら紹介しようと、他にもサイクロプスプリンセスに関連したゲームをいくつかダウンロードしてあるのだが。
あの日の朝、筐体を届けてくれたグレムリンが、
(思い出しました。これクソ……ああいえその、個性的なゲームとして有名だったやつです)
そんなことを言って苦笑いしていたのと関係があるかもしれないと思うが、ムネモシュネにはよくわからない。いずれにせよ閲覧窓口は今日も盛況で、お客も仕事もひっきりなしだ。
「しばらく腰を落ち着けることになりそうなので、野外に菜園を拓きたいと思うのです。ここのような寒い土地でも作れる野菜や果樹について、調べたいのですが」
「それでしたら……」
指先がキーの上をすべって、止まる。
ほんの一瞬、ためらうように震えてから、ムネモシュネはきゅっと唇をむすんで検索窓を閉じ、カウンターの向こうの二人……オベロニア・レアとティタニア・フロストの方へ向き直った。
「……その分野でしたら、本モデルがいくらか知っております。検索なさるより早いかと存じます。よろしければ午後にでも、種子保管庫をご案内させていただけませんか」
笑顔でムネモシュネはそう言った。小さくほのかで、だが確かに暖かい、冬の花のような笑顔だった。
End
「この一月で、うちの連中がすっかりあんたに懐いてしまった。あんたの作る飯が美味すぎるせいだ」
窓際の椅子の埃をはらって、迅速のカーンは腰をかけ、湯気の立つ大きなスペアリブへおもむろにかぶりついた。
「心をつかむには、まず胃袋をつかむこと。基本よ」
少し離れた椅子にラビアタ・プロトタイプも座り、こちらは上品にナイフで肉を小さく裂いてから口へ運ぶ。二人の視線の先、部屋の中央に組まれた大きな暖炉にはホードとストライカーズの隊員が群がり、大鍋にぐつぐつ煮えているシチューをてんでにすくっていた。
「うまっ、アチチっ、うまっ」
「副司令! このソースみんな使っちゃっていいの?」
「アンカレッジに着けばまた何か手に入るでしょうから、いいわよ」
「やったー!」
「ちょっと、それまだ食べてないやつ!」
「そういえば、ヘラジカのもも肉は首に巻くとノドの痛みに効くそうですわ」
「んな勿体ないことしないわよ」
「うぎゃー!!」
「ウル! 裸眼では無理でしょう、こんな近くに鍋があるのに」
「だって眼鏡くもって何も見えない……」
ウルが昨日仕留めた、スパルタンほどもある巨大なヘラジカがもう跡形も残っていない。子供のように口いっぱいに肉を頬張ってはしゃぐ隊員たちを、二人の隊長は満足げに眺める。
「よかったらお料理、教えましょうか?」
「遠慮しておく。私は食うだけでいい」脂身のついた大きな肉片を歯で裂きとって、カーンは肩をすくめた。
「暇があったら、ケシクにでも仕込んでやってくれ」
「ケシクにできるなら、貴女にもできるでしょうに」
カーンはそれには答えず、口をもぐもぐ動かしながら窓の外へ視線を投げる。割れた窓ガラスの向こうには凍てついた木々と砂と岩、そして硬く青白い雪におおわれた原野がどこまでも広がり、はや夕闇に沈みはじめていた。
北米作戦後、アラスカにある鉄の王子の遺跡を再訪するためオルカと別行動をとったアンガー・オブ・ホードとストライカーズは、鉄虫とレモネード軍双方の目を避けるため海岸沿いの山地を縫うように進み、ようやくアラスカ州の半ばまでたどりついていた。遺跡のあるアンカレッジまで残りおよそ100キロ。バイオロイドの行軍速度なら一日の距離である。ハイウェイ沿いに、かつてはレストランかホテルだったとおぼしき広いロッジを見つけた彼らは、ここで休んで明日残りの行程を一気に進むことにした。
「このあたり、グレイシャー・ビューっていうそうですよ」
大きなマグカップに汲んだシチューをふうふう吹きながら、タロンフェザーがタブレットの表示を横目で見た。
「マジ? じゃあ氷河見られる?」
「上空からは見えました。少し海側へ行けば、すぐ見えると思います」ずずー、と両手でかかえたお椀を傾けてティアマト。
「私、氷河見たことないです。明日の朝、ちょっと行ってみませんか」
「氷河は何色? グレイじゃー」
「ぎゃははははは! ……ところでさあ。気づいてる?」
骨に残ったわずかな肉を、鋭い前歯でガリガリとかじりながら、ハイエナが急に声をひそめた。
「あったり前でしょ」
「誰か入口の外に来てますね」
全員がラビアタとカーンの方を見る。二人の隊長は手だけでサインを送り、ミナが全員をかばえる位置に、ティアマトとウェアウルフ、タロンフェザーがエントランスからの死角に、音もなく移動した。
その一呼吸後、エントランスのドアが押し開けられ、
「ちょっとあんた達……え?」
向けられた七つの銃口と一本の刃に、目を丸くしたのは一人のウェアウルフだった。
「そっか、あんたたちがあのオルカね」
全身に赤黒い傷跡の走るそのウェアウルフ……ウェアウルフC5F3m6は、差し出された熱いシチューを一口すすって、長い息をついた。
「ええ。悪いけど、今は隠密任務中なの。あなたの所属によっては、しばらく拘束させてもらうことになります」
「所属? 所属なんかないわよ」C5F3m6は自嘲的につぶやいた。「拘束したけりゃご自由に。でもそんな暇があるなら、さっさと逃げた方がいいわ」
「逃げる? 何から?」油断なく彼女の全身に目を走らせながらクイックキャメルが訊ねた。
「もちろん、鉄虫よ。このへん一帯奴らの縄張り。暗くなるとやってくるの」
「鉄虫? ここへ来るまでぜんぜん見なかったけど?」
「あんたたち、東から来たでしょ?」C5F3m6は逆に問い返した。「奴らはここから西の一帯と、北の山側にいる。どういうわけか知らないけど、ちょっと前から二手に分かれて敵対してるみたいなのよね」
ラビアタとカーンはすばやく視線を交わした。北米作戦の最後に鉄虫たちが見せたあの狂乱状態は、鉄虫の中に新たな敵対的派閥が発生したことによるらしい、という分析をオルカからも受け取っている。
「詳しく話してほしいわね。そもそも、あなたはどうしてここに?」
「急げっつってんじゃないの……別に話すほどのこともないわ」
ぼやきつつウェアウルフC5F3m6が語ったところによれば、ここには元々ブラックリバーや三安など、PECS以外のメーカー製のバイオロイドからなる小さな集団が暮らしていた。レモネードの支配はPECSのバイオロイドにとっても地獄だが、それ以外の者にとってはよりいっそう苛酷であり、彼女たちはそれを逃れてこのアラスカの山中までやってきたのだ。
「楽じゃなかったけど、なんとかやれてたわ。ド田舎のせいか、鉄虫もそんなにいなかったし。でも先月、突然奴らがとんでもない数で押し寄せてきた。私たちも抗戦したけど……結局は、ほとんど死んじゃった」
C5F3m6は肩をすくめた。「それだけ」
「プロジェクトオルカの放送は見たのでしょ? オルカに来てみようとは思わなかったんですの?」マーキュリーの問いにもC5F3m6は答えず、ただ再度肩をすくめた。
「私たちが逃げるとしたら、一緒に来ますか?」
今度は、C5F3m6は目を上げ、怯えるように一瞬だけ外を見た。
「……そうね。連れてってもらおうかな……」
「あんた、なーんか暗いわねえ。ほんとにウェアウルフ? サンドガールなんじゃないの?」オルカのウェアウルフ、ウェアウルフ1640があきれ顔で大きな声を出す。
「言ってくれるじゃない。そういうアンタは、ずいぶん幸せそうね?」
「まあねン」皮肉な口調に気づいているのかいないのか、ウェアウルフ1640はジャケットの襟をひらひらと振って笑った。「美味いメシ、いいオトコ、血湧き肉躍る戦場。これで幸せじゃなかったらウソでしょ」
「…………」
「お、羨ましくなってきた? 今からでもオルカに……」
「そのくらいにしろ、ウェアウルフ1640。ちょっと来い」
カーンはウェアウルフを手招きして、ラビアタと共にフロアの反対側へ移動した。
「どう見る」
「嘘はついてないと思いますね」ウェアウルフは声を潜めて、二人の上司を交互に見る。「いろいろ抱え込んではいるみたいですが。まあ、自分で言ったとおりの経歴ならそうもなるかなって感じです。でも、同型機の勘ってだけですからね」
「よし。十分だ」カーンが言う。ラビアタも小さく頷いた。
「なら、確認することはあと一つだけね」
ラビアタの言った通り、この任務は隠密作戦である。オルカの部隊が、なかんずくラビアタ・プロトタイプがここにいることを、絶対にレモネードに知られてはならない。ゆえにレモネード配下であろうと、それ以外であろうと、他勢力との接触は極力避けるのが基本方針だ。
しかし一方、傷つき苦しむバイオロイドともしも出会ってしまったのなら、それを放置することを司令官が許すはずもない。ここにいる全員が、そのことをよく承知していた。
〈カーン隊長、ラビアタ副司令〉
屋根に上がって索敵をはじめていたタロンフェザーから通信が入った。〈鉄虫の反応です。北と西の二方面から……数、どちらも数百から数千。やばめです〉
「だから言ったじゃない」C5F3m6がじれったそうに言った。「早く逃げようってば」
「まだです」ラビアタが大股に歩み寄った。「『ほとんど死んじゃった』と言いましたね。つまり、まだ生きている仲間がいるのでしょう。その人達はどこに?」
「……そんなこと訊いてどうすんの」C5F3m6は警戒する顔つきに変わる。「こっちのことは関係ないでしょ」
「関係はあります。死にかけた仲間を捨てて自分だけ逃げ出すような人なら、同行させるわけにはいきません」
「ふざけんな!!」C5F3m6は血相を変え、椅子を跳ね飛ばした。「そんなことするわけないでしょ。あいつらは……あいつらが私を……」
「自分たちはどうせもう助からないからって、送り出してくれた?」
サラマンダーが横合いから挟んだ言葉に、C5F3m6は目を見開く。
「ま、そんな所だろうな」カーンが静かに後を引き取った。「お前たちは死んでも仲間を捨てたりしない。何百人ものウェアウルフを見てきたが、そんな奴は一人もいなかったよ」
「嫌なことを言ってごめんなさい。私たちには医療スタッフがいるし、薬もあります」ラビアタが言い添えた。突然話を振られたケシクがぴょこんと立って頭を下げる。
「助けられるかもしれないわ」
〈あと20分以内に会敵見込み〉
「……ここから南に下った、氷河沿いの崖の穴」C5F3m6はぽつりと言った。「そこに、みんな寝てる」
「人数は?」
「五人」
「自分で歩ける奴はいるか」
「いないわ……私だけ」
「よろしい。総員戦闘用意」ラビアタの言葉に、全員が素早く立ち上がった。
極地の夜は早い。まだ五時にもなっていないのに、すでにあたりはとっぷりと夜闇につつまれていた。幅広のハイウェイをはさんで広がる原野の向こう、急峻に立ち上がっていく山々のすそに、無数の赤黒い光点がひしめいているのが見える。凍てついた大気に耳をすませば、足音の轟きもかすかに聞き取ることができた。
「うひょー。すげえ数」ハイエナが呟いた。
「頑張らナイト、チック電もできないねえ」
「ぶはっ」
「そうね。私とカーンで遅滞戦闘を仕掛けます」ラビアタは無造作に言った。重い金属音とともにトロールスバードの刀身が展開し、彼女の身長の二倍近い長さになる。
「他のみんなはウェアウルフの案内で負傷者を回収後、氷河伝いにアンカレッジ方面へ抜けて下さい。夜明けまでには合流します。合流ポイントはBからF」
「了解」
「うーす」
口々にうなずく隊員達。C5F3m6は信じられない、というように大きく手を上げた。
「何言ってんの……? え、あんたとあんたが隊長なのよね? その二人が捨て石ってどういうこと?」
「捨て石?」ウェアウルフ1640が怪訝そうな顔をした。「あそっか、あんたこっちで復元された口だもんね。生カーン隊長を知らないんだ」
「生ラビアタ隊長もね」とミナ。
「まあ、ちょっと大変な仕事になるかもね」ラビアタも笑った。「でも百年も戦っていれば、この程度のピンチは何度もあったものよ。ねえ、カーン?」
「弾は十分、体力は万全。欠けた仲間もいない」カーンも、片手にリボルバーカノンを抱え上げて微笑んだ。「ピンチの内にも入らないな」
カーンがさっと手を振ると、アンガー・オブ・ホードの全隊員が踵のホイールを起動し、甲高い唸りが周囲の空気を震わせた。ティアマト、ミナ、マーキュリーの三人はふわりと浮き上がり、ウルはC5F3m6といっしょにバーニングウォーカーの荷台へもぐり込む。
「作戦開始!」
迅速のカーンは一度踵を打ち鳴らしてから身をかがめ、二方向から押し寄せる鉄虫の群れのちょうど真ん中へ、稲妻のように突っ込んでいった。一拍遅れて、路面をくだく砲弾のような踏み込みとともにラビアタが続いた。
同時に残りの隊員達も反対方向へ駆け出す。そして、鋼鉄の嵐が巻き起こった。
ホードの隊員たちが目にしたことのある「本気のカーン」は常に独りだった。彼女と同じレベルで戦える者などいるわけがないからだ。
ストライカーズの隊員たちにとってラビアタ・プロトタイプは常に、自分たちだけでなくレジスタンス全体の長だった。彼女はいつでも最初のバイオロイドとしての責任と使命を背負い、過去のこと、将来のこと、そして全隊員のことをを考えていた。
だからかれらは知らなかった。自分と同等の相手に背中を預けた時、カーンがどれほど迅く駆けるのか。
だからかれらは知らなかった。すべての重荷を解かれ、ただ目の前の戦いだけに集中したラビアタがどれほどの戦闘者であるのか。
「おおおおおおおおおう!!」
リボルバーカノンが赤く輝く鉄虫のコアを貫き、砕き、また貫く。
思考の半分だけで目の前の敵を処理し、残りの半分で休息する……などという、節約じみた戦い方はもはや必要ない。脳の100%を叩き起こし、一体でも多く、一秒でも早く、一歩でも深く、敵を殺し、平らげ、蹂躙し尽くすことに全身全霊をそそぎ込む。その結果の隙だとか、消耗だとか、そういう小難しいことも考えなくていい。誰よりも巨きく、力強く、頼もしい剣が、いま自分の後ろにはそびえ立っているのだから。
「ぬうああああああああ!!!」
トロールスバードが鉄虫をなぎ払い、叩き潰し、またなぎ払う。
ここに守らなくてはならない弱者はいない。慮らなくてはならない主もいない。ただ芸術的なまでに鍛え抜かれ、研ぎ抜かれた牙を持つ一頭の狼だけが隣にある。今はただ、その最強の狼とどんな風に踊り、どのように戦場を組み立てていくか、それだけを考えていればいい。ああ、なんと愉しい仕事、なんと心躍る戦いだろうか。
「あれ絶対遅滞戦闘じゃないよね」
「もうあの二人だけでいいんじゃねーかな」
「呑気なこと言ってる場合ですか! 今のうちに距離を稼がないとです!」
バーニングウォーカーを中心にして、急傾斜の氷河を滑り降りるホードとストライカーズ。誰かが後ろを振り返るたび、鉄虫が破壊される新たな火柱が上がる。
「よかったねミナ! 氷河見放題じゃん!」
「もうちょっと落ち着いて見たかったんだけどなー!」
「私は……私たちは」遠ざかる戦いの光景を呆然と見ていたウェアウルフC5F3m6が、ふいに絞り出すように言葉を発した。「オルカを信じなかった。あんたたちの放送が本当だと思わなかった。なのに一月前のあの日、バンクーバーから輸送機が何台も飛び立ったと聞いて……それ以来、ずっと私たちはバラバラ。行くべきだったとか、もう遅いとか。ずっと後悔しかなかった」
「ああ、なるほど。あんた、それで出てきたのね?」操縦席のサラマンダーが振り向いた。「もう後悔したくないって。いいじゃない、そういうの」
「一つだけ言っておくことがあります」荷台のすぐ横を低空飛行するティアマトがきっぱりと言った。「私たちの司令官様は、差し伸べた手をいちど振り払ったくらいで見捨てるような、そんないじわるな方ではありません」
C5F3m6はうつむいた。激しく揺れる荷台の振動で、月明かりにちらりと、水滴のようなものが舞った。
「……ありがとう。ごめんなさい。私たちを助けて。おねがい」
「任せなって!」バーニングウォーカーの足元から、ウェアウルフ1640が大声で怒鳴った。
* * *
冷たく輝く星空の下、穴やヒビが一面に開いた古いハイウェイを、二人のバイオロイドが歩いていた。
服はボロボロ、あちこちに擦り傷や火傷を負っているが、大きな怪我はなく足取りも確かだ。
「思えば、こんな風に二人で戦ったことなかったわね。けっこう長い付き合いなのに」
「ホードはあまり他と組まないしな。それに私が来た頃にはもう、あんたは全軍の指揮官だった」
「そうだったわね」ラビアタ・プロトタイプは焼け焦げのできた長手袋を脱ぐと、両手を組み合わせてぐっと上に伸ばした。
「ねえ、信じてもらえるかしら。私、この旅がけっこう楽しいのよ。もちろん、大事な任務だとわかってるけれど」
「そうだな」迅速のカーンは歪んでしまった左のレッグブレードを何度も引っ張って取り外す。「帰る場所……帰りたい場所があって遠くに行くのは、いいもんだ。根無し草の旅とは全然違うな」
「アンカレッジで一息つけたら、バーでも探してみない? こんどは戦術論なんか、ゆっくり話したいわ」
「構わないが、あんた意外と絡み酒だからな」
「え、嘘!?」
「自覚なかっただろ」
やがてハイウェイの彼方に、見慣れた矩形の明かりが小さく見えてきた。バーニングウォーカーの灯火だ。誰かが手を振っているのも見える。まだ顔まではわからない。
二人のバイオロイドは一度だけ、お互いの拳を小さく打ち合わせ、それから大きく手を振りかえして歩を早めた。
End
ティートカップをよく拭いて消毒槽に入れ、腰の高さまである大きなミルク缶を台車に載せる。台車に積んだ缶の数をもう一度数えて、エルブン・フォレストメーカーは深いため息をついた。
「ぐぬ~。今週も対先月比マイナスかあ……」
エルブン・フォレストメーカーをはじめとする一連の森林保護・育成用バイオロイド、いわゆるエルブンシリーズは、パブリックサーバントの中でも独自性の高い一種のサブブランドを形成しており、それを反映してオルカでもチームとしての共用部屋をひとつ与えられている。エルブンミルクの生産加工所も兼ねているためそこそこの広さがあるその部屋の内部は、セレスティアとセクメトの力で壁や床から木々が生い茂り、ふかふかの下草まで生えて、ちょっとした森の中の空き地といった風情にしつらえられている。はらり、と缶のフタに舞い落ちた一枚の木の葉を、エルブンは優しくつまんで捨てた。
「やっぱ箱舟に落ち着いちゃってからぱっとしないんだよなー。早くヨーロッパ本土に侵攻しないかなあ」
「物騒なこと言うんじゃないわよ」木の根に腰かけてネイルの手入れをしていたダークエルブン・フォレストレンジャーが眉をひそめた。
「だってこの島、どこ行っても氷ばっかりで木が一本もないじゃない。箱舟の中は中で私たちの仕事全然ないし。おかしくない!? 自然といったらエルフでしょうが!」
「あの中はだって、水も光も温度も全部管理されてるじゃん。私らの出る幕なんかないでしょ」
「箱舟とやらは、生態系全体を保存して未来へ残すのが目的と聞きました。植物だけが繁茂しても、それはそれでバランスを欠くということなのでしょう」
黙々と料理書を読み込んでいたセクメトも目を上げ、しずかに言い添える。
「芝生潰してカフェやらバーやら建ててるくせにー!」
「そのカフェのおかげでミルクの消費も増えたんだから文句言わない。先月は例の選挙もやったし、ずいぶん売り上げ伸びたでしょ。それが元に戻っただけじゃないの」
「元に戻っちゃダメでしょーが! そんな甘い考えじゃこの生き馬の目を抜くオルカで生き残れないよ!」
「オルカってそんな所だっけ?」
だんだん、とミルク缶のフタを叩いてエルブンは力説する。彼女たちエルブンシリーズに共通する特殊体質にして、余人に真似のできない独自商品であるところのエルブンミルク。日夜文字どおり身を削って生み出しているそのエルブンミルクの売り上げが、このところ芳しくないのだ。具体的には飲料用の売り上げがどうも落ち込んでいる。ダークエルブンの言うとおり、先月の「ミルク総選挙」イベントで健康飲料としての認知度が一気に上がったのはよかったが、ブームが去るとまた需要は落ち着いてしまった。
「なんか対策立てないと……だいたいあんたのせいでもあるんだからね。もっと新人どものおっぱいに危機感持ちなさいよ!」
「はあ!? 何それ!」
エルブンミルクのうたう効能の一つにバストアップ効果がある。それに説得力を与えているのが、そろって豊かなエルブン達のバストだ。とりわけダークエルブンの胸はオルカでもトップクラス、身長比の補正を入れれば単独首位であり、エルブンミルクの人気をおおいに高めていた。
しかし最近、それはもう野放図に巨大なバストを備えた新人が立て続けに現れており、ダークエルブンの存在感は相対的に薄れつつある。エルブンミルクの消費低迷にはそのあたりが関係していると、エルブンは睨んでいるのだ。
「ただでさえ巨乳が渋滞してるところへバイソン女だの熊女だの忍者ママだの……あんたももっとミルクがぶがぶ飲みなさい!」
「毎日飲んでるわよ! だいたいミルクだけで胸が大きくなったら世話ないわ!」
「商品価値を根本から否定するなあ!」
「あらあら、賑やかですね~」
部屋の奥の木陰から、ミルク缶をかかえたセレスティアが頬を火照らせながら出てきた。
「今日の分のバナナミルク、できました。納品をお願いしますね~」
「セレスティア様! 聞いて下さいよ~!」
泣きつきにいくエルブン。話を聞いたセレスティアはおだやかに小首をかしげ、
「人気が落ちているのは悲しいですね~。でも、私たちのミルクに頼らなくてもみんなが健康で元気にしていられるのなら、それが一番かもしれませんね」
「そういうことじゃなくてー! 私たちの存在が軽くなってるってことですよ! セレスティア様だって不満じゃないんですか!」
セレスティアは困ったように笑う。「むかしの時代や島にいた頃に比べれば、オルカは夢のように幸せですから、不満などはとても」
「う……」
旧時代から生き抜いてきた彼女にそういうことを言われると、復元組のエルブン達としては何も言えなくなってしまう。もちろんエルブン達とて苦労してこなかったわけではないし、今の環境に幸福を感じていないわけでもない。司令官が来るよりずっと前、戦いが一番厳しかった頃は、エルブンミルクは販売どころか軍需食糧として徴収されていたのだ。その頃に比べれば、確かに今のオルカは夢のようである。
「でもミルクの売り上げは、えーとほら、エルブンシリーズ全体の地位向上にもつながるんですよ! 向上心! そう向上心です! 不満でなく!」
「どんな命にも、それに似つかわしい地位と役割があるものですよ~」
「そうですよエルブン。高望みをするのは高貴ではありません。陛下のおそばに侍る者は、つねに謙虚でいなければ」セクメトまで本を置いてそういうことを言う。
「うぐぐぐぐ」
どうもエルブンシリーズの上位モデルはみんな浮世離れしたところがあって、こういうことにはまるで頼りにならない。いったん諦めて出荷作業を済ませようと、エルブンは台車を押して部屋の出口に向かった。飲料用以外にも加工用、調理用、製菓用など、エルブンミルクにはいろいろな需要があるのだ。
ドアを開けると、緑色の壁が行く手をふさいでいた。
「あっ、すみません。こちらは、エルブンシリーズの皆様のお部屋とうかがったのですが」
「うげげっ!」
思わず素の声が出た。入口に立ち塞がっていたのは壁ではなく、一人のバイオロイドだった。たった今やり玉に挙げていたエルブンミルク低迷の元凶の一人、ガーディアンシリーズのフリッガである。熊の遺伝子を導入されたというその体躯は2メートル近くあり、エルブンとは大人と子供ほども違う。エルブンは思わず身構え、
「なななんなんなんですか! やろうってんですか!」
「いえ、あの……ご迷惑でしたら出直してまいります」
「何やってんのよあんた」声を聞いたダークエルブンが出てきて、ひとまずミルクの台車を後ろに下げた。「お客さんじゃない。ごめんごめん、ちょっと驚いただけ。とりあえずどうぞ」
「お邪魔します……うわあ、素敵な部屋」
身をかがめておずおずと戸口をくぐってきたフリッガに、エルブンはあらためて息を呑んだ。
(でっっっか……)
背が高いだけでなく、左右にも前後にも大きい。骨格自体が大柄な上に、みっしりと筋肉がついているのだ。彼女がいるだけで部屋がちょっと狭くなったような気さえする。
(そりゃ胸もすごくなるわけだわ……)
「あら、珍しいお客様! ようこそいらっしゃいました」
セレスティアが立ち上がり、にこやかに両手を広げて歓迎の意を示した。「ミルクはいかがでしょう? 搾りたてがありますよ」
決して背の低い方ではないセレスティアだが、それでもフリッガの方が頭一つ以上大きい。気づけばダークエルブンも、まじまじとフリッガの胸を見つめていた。少しは危機感を抱け。
「これは……カシの木? 本物なんですか?」
「ナノマシンでできた疑似植物です。でも本物と同じように呼吸や光合成をするし、季節になれば花も咲くんですよ」
「へええ……では、この地面も?」
「そちらは私のナノマシンで構成した疑似土壌系です。制御にコツがいりますが、有機物や埃を分解してくれる、便利なものですよ」
ひとしきり感心したフリッガは大きなマグカップで出されたバナナミルクを美味そうに飲み干し、大きく息をついてから口を開いた。
「実は、今日はお願いがあってうかがいました。こちらには、母性をイメージした牛柄の衣装があると聞いたのですが」
「別に母性をイメージしてませんが、牛柄ビキニならありますよ」
エルブンが答えると、フリッガはずいと身を乗り出した。
「それを一着、貸していただけないでしょうか?」
「……ほほ~う?」
肉の質量にちょっと後ずさりつつ、エルブンはニヤリと笑った。「ご自分で着るんですか?」
頬をさっと赤らめてうなずくフリッガ。エルブンの笑みがさらに深まる。
オルカにおいて、ビキニを好んで着る隊員は非常に多い。中には単純に肌を出し、肉体美を誇示すること自体を楽しむ者もいるが、フリッガはどう見てもそういうタイプではない。にもかかわらず、あんな扇情的な衣装を着たがるとすれば、その理由は一つしかない。
「司令官様のためですね~?」
ニヤニヤしながらさらに斬り込んだエルブンは、しかしオヤ、と笑みを消した。反応が予想していたのと違う。
フリッガは頬を赤らめつつも唇をきゅっと引き結び、眉根を寄せていた。その表情からは欲望や期待というより、ある種の決意と悲壮さが感じられる。どうも、単に司令官を悩殺するために水着を欲しがっているわけではないようである。
「……まあいいですけど、あれって数があんまりないんですよね。背丈が違いすぎるから、貸したら伸びちゃうだろうし」
しかしいずれにせよ、理由はそれほど重要ではない。エルブンは思考を切り替えた。せっかく獲物が向こうから飛び込んできたのだ、遠慮なくたっぷり搾り取らせてもらおう。ミルクだけに。
「私にできるお礼でしたら、何でもいたします」
「えー、それじゃ~あ~」
「エルブン?」
わざとらしく顎をさすってみせるエルブンの頭上から、セレスティアのしずかな声が降ってきた。
「私たちはエルブンミルクの生産にかかわって、いくつもの特権を司令官様からいただいています。この上、べつの代価を求めるのはよくないことですよ」
「う……はい」
「フリッガさん、私のビキニをお貸しします。紐の長さを調整すれば着られるでしょう、手袋とソックスは……」
「私用の予備がありますから、お譲りしましょう」セクメトが言い添えた。「何かただならぬ事情があると見ました。私の方は当面着る予定がありませんから、伸びてしまっても構いません」
「ありがとうございます」フリッガは深々と頭を下げた。「何かお礼をさせて下さい。そうでないと私の気が済みません」
「そのようなことは~……」
「はいはい! お願いしたいことあります!」エルブンは慌てて手を上げた。こうなったら最初に思いついたアイデアだけでも実現させなくては。「フリッガさんもこう言ってるんだし、いいですよねセレスティア様!」
セレスティアが仕方ない、というようにうなずき、エルブンはガッツポーズをとった。
「じゃあですね、コトが済んだらでいいので……」
* * *
「エルブンミルク、体によくてとっても美味しいエルブンミルクはいかがですか? 皆さんもエルブンミルクを飲んで、私のような健康で丈夫な体になりましょう」
「コーヒーミルクのホット二つ」
「プレーンください」
「こっちバナナミルクをLで」
「はい、はい。少しお待ちくださいね。あっ、プレーンミルクは今ので品切れです。申し訳ありません」
生態保存区域の広場の一角、朝から行列の絶えないミルクスタンド。少し離れたところからそれを見守るエルブンは得意絶頂だった。
「へっへーん! どうよ私のこの商才、この企画力!」
「はいはい、大したもんよ」
ダークエルブンが肩をすくめて賛同する。エルブンが要求したお礼とは、牛柄ビキニを着たフリッガにそのままエルブンミルクの販売係をやってもらうことだった。
彼女が看板娘をつとめることで、バストアップ効果の説得力は前にも増して復権。そのうえ新たに、身長を伸ばしたい隊員達にも需要が広がり、売り上げはミルク選挙の時すら超える勢いだ。
「本日はご好評いただきまして完売です。ありがとうございました~、皆さん」
フリッガが一礼して、スタンドの後片付けを始めた。そこへやって来た子供組と何ごとか話していたと思うと、ピッチャーを手にこちらへそそくさと走ってくる。
「あのう、すみません。あの子たちのために一、二杯分だけ、どうにかならないでしょうか?」
「しょうがないな~。ここで出しちゃうから、貸してください」
今日も夕方前に完売してしまった。明日からは増産も考えるべきかもしれない。木立の影で胸をはだけながら、エルブンは鼻息も荒く考えをめぐらせる。
「アクアランドももうすぐできるし、あっち用の新商品もどんどん考えていかないとね。今晩も企画会議だからね、遅れずに来るのよ!」
「あんた本当にそういうの好きね……いいからはい、出して出して。フリッガさんもありがとうね」
「いえ、やってみるととても楽しいです。小さい子たちも大勢来てくれますし」
フリッガの満ち足りた笑顔からは、先日の悲壮さは少しも感じられない。彼女があの「デート抽選会」の幸運な当選者の一人だったことを、エルブンは後から知った。ビキニを使って司令官とどんなデートをしたのか、さすがのエルブンもそこに立ち入る気はなかった。
「今度あのアイアスさんって人も紹介してくださいね。ライバルはどんどん取り込んでいかないと」
「ライバル?」
「いえこっちの話です。このままエルブンシリーズの地位を爆上げして、ゆくゆくはアクアランドの隣にフォレストランドを建設するのよ!」
「あ、それちょっと面白そう」
陽射しの下、エルブンの明るい笑い声に合わせて、白とコーヒー色の二すじのミルクがキラキラと揺れながら、それぞれのピッチャーに降り注いでいった。
この数日後、生態保存区域は夏周期に入り、タイミングを合わせてオープンしたムネモシュネのかき氷屋にエルブンミルクは人気を根こそぎ持っていかれることになるのだが、それはエルブン・フォレストメーカーのいまだあずかり知らぬことである。
End