基本スペック
駆動方式[4WD]/ミッション[6速]
初期馬力[280ps]/カーナンバー:2568
マキシ2・3~車種称号【疾風】

全長:4,600mm
全幅:1,785mm
全高:1,360mm
最高速度:351km/h
| モード別カテゴリー | 称号 |
| ST無敗 | 【首都高無敗】 |
| 夏休み称号 | 【伝説のR使い】 |
| ワンメイクバトル | 【R34キング】 |
| エンジン形式バトル | 【直6選手権】 |
| 期間限定首都一TA・1 | 【伝説のGT-R】 |
| 期間限定首都一TA・2 | 【俺のR】 |
| 車種限定バトル | 【史上最強GT-R】 |
備考:第二世代GT-R、およびスカイラインGT-Rの最終型。
性能の高さ・扱いやすさ・知名度の高さからSKYLINE GT-R (BNR32)と並んで使用者が多い人気車。
加速力は良好かつ最高速もよく伸びる。
コーナリング性能も決して悪くはないものの、重量配分がフロントヘビーなせいかリアがやや滑り易い点や、R32と比べ重めな回頭性はコースによっては難を感じる場面もある。
RX-7 Type R (FD3S)等のコーナリングマシンを普段使っているプレイヤーからすれば少々扱いにくいかもしれない。
またボディサイズが多少大きい為、擦り抜けや回避行動にも注意が必要。
TAにおいても基本性能の高さからタイムは良好ではあるが、ボディの大きさから箱根や大観山のような道幅がタイトなテクニカルコースでは気を使う必要がある。
対戦においては、他の厨車同様素晴らしい活躍を見せることが多く、遭遇率も高め。
対接触性能やブーストも強力で、特に対接触性能についてはこの車を押し返すことが出来るか等、強い車の一つの指標として比較対象にもしばしば挙げられる。FDクラスの車であれば敵車が前にでていても1mくらいなら簡単に封じ込めることが出来る。
以上の点から、ボディの大きさとリアがやや滑り易い点にさえ気をつけることが出来れば、初心者から上級者までオススメ出来る車である。
この車を乗りこなすことが出来れば、殆どの6速車は乗りこなせると言ってもいいだろう。
6RR Rev3.05アプデ後に対接触性能がやや弱体化したものの、6RR+になり以前の強さに戻った様な印象を受ける。(要検証)
選択可能カラー
| カラー名 | マキシ2•3~色称号 |
|---|---|
| ベイサイド ブルー(M) | 【青い/蒼き】 |
| ミレニアム ジェイド(M) | 【鋼の/鋼鉄の】 |
| ホワイト | 【純白の/雪色の】 |
| スパークリング シルバー(M) | 【銀色の/白銀の】 |
| ブラックパール | 【黒い/漆黒の】 |
ミレニアムジェイドを選択するとV-specⅡ Nürとなり、通常仕様より5mm車高が下がる。但し性能に差はない。
出典:2009/06/24 3DX未来研通信第29回
更新回数及び追加カラー/(M)=メタリック
| 1 | ブルー | 21 | ブルー(M) |
|---|---|---|---|
| 2 | イエロー(M) | 22 | オリーブ(M) |
| 3 | ダークオレンジ | 23 | ホワイト2 |
| 4 | ペールブルー | 24 | シルバー |
| 5 | パープルシルバー(M) | 25 | ブラック(M) |
| 6 | ダークパープル | 26 | ピンク2 |
| 7 | ダークピンク(M) | 27 | ペールグリーン2(M) |
| 8 | ダークレッド | 28 | イエロー3 |
| 9 | ゴールド | 29 | グレー(M) |
| 10 | ミントグリーン | 30 | ダークオレンジ2(M) |
| 11 | ライトレッド(M) | 31 | ガンメタル |
| 12 | ダークグリーン(M) | 32 | ライトイエロー |
| 13 | ブルーグリーン(M) | 33 | ペールイエロー |
| 14 | ライトパープル | 34 | オレンジ |
| 15 | ピンク(M) | 35 | ペールブルー2(M) |
| 16 | グリーン3(M) | 36 | ダークブルー2 |
| 17 | ライトブラウン(M) | 37 | ライトイエロー2 |
| 18 | ブロンズ(M) | 38 | ライムグリーン |
| 19 | ベージュ(M) | 39 | ペールピンク |
| 20 | イエローグリーン(M) | 40 | レッド(M) |
カスタムカラー1つ目の「ブルー」は3DX+までは水色に近い色だったが、4からは純正色の「ベイサイドブルー」よりも濃い青色になった。
エアロパーツセット
A:GTカー風のエアロ。GTウィングをつけるとさらにそれらしくなる。
フロントバンパーは2001年GTマシンに似ている。しかしインパルGTバンパーにはあまり似ていない。
ヘッドライトにカーボン製のカバーが付き、デザインが大きく変わる。
B:GT-R (R35) NISMOをモチーフにしたエアロ。ボディ下部に赤いラインが付く。フロントグリルの形状はVeilside製STREET DRAG MODELに少しだけ似ている。
フロントナンバーがオフセットされ、リアのバックライトと赤いライトが外される。

6RRまで。フロントはトミーカイラ、リアとサイドはAbflugに少しだけ似ているエアロ。アイラインが付きウィングは純正にハイマウントステーを装着した仕様になる。
またこのエアロのみ、リアのバックライトと赤いライトが外される。
C:URASの2Door D1SPEC1っぽい。D1のER34に近い形状。このエアロを装着しているプレイヤーが多く見受けられる事から人気のあるエアロ。
ウィングはダックテールになり、フロントナンバーがオフセットされる。無駄に張り出したリアバンパーは好みが分かれるか。
ウィングレスにすると2004年に野村謙が使用していたD1マシンっぽくなる*1。
D:C-WEST製を意識したような形状。アンダーパネルがむき出しになる。
フロントもN1Ⅲに似ており、N1Ⅲバンパーの開口部を大きくしたような形にも見える。リアは純正バンパーに大型のディフューザーを組み合わせた感じに。
エアロC同様、フロントナンバーがオフセットされる。
E:URASのTYPE-GTに似たレーシーなエアロ。エアロC同様、フロントナンバーがオフセットされる。

F:ミッドナイトクラブ ロサンゼルス*2のオリジナルエアロに似ている。マフラーは2本出しになる。

G:スーパー耐久に出場していたファルケン☆GT-R レースカーに似ている。
大きめのフォグランプが付き、リア周りがスリムに仕立てられている。ウィングは小ぶりのものが付く。

H:nismo R-tune仕様。6Rから再収録。
4からフロントアンダーパネルは純正同様無塗装の黒になる。
全体的に纏まりがあり、エアロCと並び装着しているプレイヤーが多い人気のあるエアロ。
R32とR33のエアロH同様あっさり仕上げたい人にオススメ。

差分(3DX+まで)

I:Varisのスバル・WRX STI(VAB) ARISING Ⅱ ULTIMATEを移植したようなエアロ。リアはWRX STI(GVB) Ultimateに近い。
下部とウイングに赤いラインが付く最近のNISMOエアロ風。
またこのエアロ以降、フロントバンパーのウインカーが外される。

J:フロントはスバル・BRZ STI Concept風。マフラーはエアロFと同じく2本出しになる。

K:KRC風エアロ。フロントはスバル・BRZ STI Performance Conceptに近い。マフラーはセンター2本出し。

ダクト付きボンネット
A:トップシークレット製に近い形状。ボンネットピン付き。

カーボンボンネット(ダクト付き)1:

B:nismo製に近い形状。ボンネットピン付き。

C:レーシングサービスタカギのワンオフ品に似ている。

D:ファーストモールディングのエアロボンネットに近い。

余談だが、マキシ5の稼働開始時~2014/10/28までステッカー「ワンポイント1」を装着し数字01を選択すると端の部分がカーボン調に変化するバグがあった(00,02~09は変化せず)。
2014/10/29に行われた大型アップデートでこの現象は発生しないようになった。
カーボンボンネット(ダクト付き)2:

カーボンボンネット(ダクト付き)3:03年GTマシンのボンネットに少し似ている。

車種専用ウィング
A:ALTIAの大型リアスポイラー。
もともとはGT-R以外のR34系に装着されるものである。
B:R32やGC8の車種別Bとほぼ同じ形状。

C:R35風のカーボン製ウイング。

エアロミラー
ガナドール・スーパーミラー風のエアロミラー。

カーボントランク
トランクリッドがカーボン地になる。エンブレム類は外れない他、鍵穴も純正同様にある。

ワークスステッカー
nismo仕様。元のボディカラーはロールケージを除いて完全に隠れる。

ちなみにエアロHをFRPボンネットBと一緒に付けるとR-tune仕様になった*3。

サイドステッカー
ドアのブレスラインに沿って前方寄りの位置に貼られる。
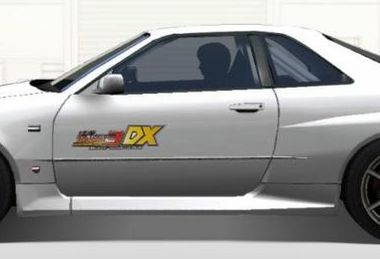
雑記
- キャッチコピーは『人に翼を』。
- 湾岸マキシに登場しているBNR34は、ウインカーがクリアレンズになっていることとボンネットにNACAダクトが開けられていることから、後期型のV-SpecⅡと判別できる。
- RB26DETTが登場して10年の節目に登場したBNR34は、先代であるBCNR33から大幅な進化を遂げた。大型ディフューザーを装備した量産車初のアドバンスドエアロシステム、マルチファンクションディスプレイ (MFD) 、ドイツ・ゲトラグ社製6MT等、第二世代スカイラインGT-Rの最後に相応しい進化を遂げている。
- V-SpecⅡはV-Specと比較するとリアのブレーキローターが大型化*4されたほか、各種フットペダルがRの文字が入った樹脂製からアルミ製のものに変更され、シフトノブもGT-Rロゴが入ったアルミ製のものに変更されている*5。また、量産車初となるカーボンボンネット*6を採用。NACAが開発したV字型エアダクト(通称:NACAダクト)が付き、軽量化を図ると共にタービン付近の温度を軽減させる効果が図られている。
- NACAダクトとは空気の取り入れのためにアメリカ航空諮問委員会(NACA)で開発されたエアインテークのことで、形状を細かく説明すると、上から見ると三角形で奧に行くにつれて横幅が増える形状で入口は長方形。NACAフラッシュインレット、NACAスクープなどとも呼ばれる。
NACAはアメリカ航空諮問委員会の略で翼型などについて多くの基礎的・網羅的研究を行った組織であり現在のNASAである。
- NACAダクトとは空気の取り入れのためにアメリカ航空諮問委員会(NACA)で開発されたエアインテークのことで、形状を細かく説明すると、上から見ると三角形で奧に行くにつれて横幅が増える形状で入口は長方形。NACAフラッシュインレット、NACAスクープなどとも呼ばれる。
- 外装は標準と比べて前方下部に樹脂製、後方下部に量産車初のオートクレーブを用いて焼成されたカーボンディフューザーや、可変2段リアウイングスポイラーのアドバンスドエアロシステムを採用。
このディフューザーは車体下部前後を覆っており、走行風を取り込んで圧縮・整流させボディ下面を通り、リヤで拡散させることでダウンフォースを発生させる仕組みとなっている(標準車と比べバンパー下部が大きい)。
さらにフロントバンパーの幅をタイヤハウジングより大きくしているが、これは空気をタイヤハウジングへ溜めさせ、負圧でブレーキを冷却させるためである。湾岸マキシではあまりに関係ないかもしれないが、純正エアロのまま愛用している人も多い。 - トランスミッションはドイツのゲトラグ社製でスカイライン初の6速MTが採用された*7。
高価ではあるが、6MT化によって日常で使いやすくなることもあり、NISMOから「ゲドラグコンバージョンキット」という形でR32・R33型へのスワッププログラムが提供されていた。- 通常の5MTの1~4速が6MTの1~5速で割り振られるため、RB26のトルクの薄さをカバーしつつオーバードライブとなる6速で高速巡航性能を確保という形となる。
裏ワザ的な発想だと、このコンバージョンキットに入っているファイナルギアを使わずあえて5MTのファイナルをそのまま使うことで、5MTの1~4速レンジを6MTの1~6速に相当させることも可能。
高速巡航を使わないと割り切るのなら更にクロスしたギアレシオで楽しく走れる。
- 通常の5MTの1~4速が6MTの1~5速で割り振られるため、RB26のトルクの薄さをカバーしつつオーバードライブとなる6速で高速巡航性能を確保という形となる。
- ボディカラー「ミレニアムジェイド」選択時に変化するグレード「V-specⅡ Nür」は2002年2月に500台限定で生産された特別仕様車である。
タービン、カムシャフト、ピストンなどを専用に強化したN1仕様のエンジン(ゴールドに塗装されたヘッドカバーを持つ)をはじめ、300km/hスケールのスピードメーターやグレードを表記したアルファベットが立体エンブレム(通常は平面ステッカー)になるなど、第二世代GT-Rのフィナーレを飾るにふさわしい豪華絢爛な装備類が奢られていた。
当初は300台限定での販売が予定されていたが、発表後に問い合わせが殺到。急遽プラス200台の増産が決定し、計500台での販売となった。それでも発表(2002年1月24日)と同時に予約が満杯となり、即日完売という大盛況ぶりであった。- 湾岸ミッドナイトRではボディカラーに「シリカブレス」を選択すると「M-spec」グレードに変化した。頭文字の「M」は「MAN(大人の感性)」「MAXIMUM(最高のドライビングプレジャー)」「MEISTER(職人の拘り)」など複数の意味が込められている。
M-specにも専用装備が用意され、熟練の職人が1脚ごとに仕立て上げる本革シートや1.5mm厚のクッション材を巻き込むことでソフトな握り心地とした本革ステアリング、M-spec専用「リップルコントロールショックアブソーバー」、リヤのスタビライザー径もV-specの24.2φから柔らかめの23.0φに変更されており、サーキット走行やより高い走行性能を求める層を意識したV-specII仕様に比べ乗り心地と上質感を重視した「大人のためのGT-R」をコンセプトとした仕様になっている。またM-specにもNur仕様が存在する。
- 湾岸ミッドナイトRではボディカラーに「シリカブレス」を選択すると「M-spec」グレードに変化した。頭文字の「M」は「MAN(大人の感性)」「MAXIMUM(最高のドライビングプレジャー)」「MEISTER(職人の拘り)」など複数の意味が込められている。
- R33では100台限定でイギリスへの正規輸出が行われたが、R34も100台限定でイギリスへ正規輸出された。国内仕様との違いは、ヘッドライトのハロゲンバルブ化*8、スピードリミッターの速度変更(180km/h→250km/h)、200マイル/hスケールのスピードメーターなど。
- 余談になるが、同車は標準車よりV-spec等の上級グレードや、特別仕様車の方が合計の製造台数が多くなっている。
- ミッドナイトパープルやミレニアムジェイド等の限定色を除く標準色で一番製造台数が少ないのは、前期型のみに設定されていた「ライトニングイエロー」。合計で68台しか製造されておらず、標準車に至っては19台しか製造されてない激レアカラーである。
- ミッドナイトパープルやミレニアムジェイド等の限定色を除く標準色で一番製造台数が少ないのは、前期型のみに設定されていた「ライトニングイエロー」。合計で68台しか製造されておらず、標準車に至っては19台しか製造されてない激レアカラーである。
- 3DX+までは標準のメーターをモデルにしていたが、4からは色や文字配置からMine'sのフルスケールメーターがモデルだと思われる。(Nürとは異なる)
- 原作では「R200CLUB編」にて、山本和彦率いる「YM・SPEED」のデモ車としてベイサイドブルーの個体が登場。その後、「ガレージACE編」にて後藤元が率いる「ガレージACE」のデモ車として登場しており、「阪神高速環状編」においても神谷兄弟と対立している「Kレーシング」のデモ車として、加えてアニメ版では元木康郎の経営する「CCRファクトリー」の新しいデモ車としても登場している*9。
- 特にガレージACEのデモ車は後藤のGT-Rチューンの集大成ともいえる入魂の一台であり、快適装備を残しながら筑波で59秒台という驚異的なタイムを記録する実力を持っていた。また「Rキラー」として鳴らしていた友也をC1外回りで撃墜し、彼が本格的な走り屋として目覚めていくきっかけを作った。
「走る宝石」とも言われる程の非常に高いレベルに仕上げられたACEの34GT-Rであったが、友也に託してから数日が経過したある日の夜、ブラックバードとのバトルにおいてC1外回りの汐留S字でクラッシュし、一瞬にして廃車になってしまう*10。 - 第二部「湾岸ミッドナイト C1ランナー」では、「有栖ガレージ」代表の有栖高彦の渾身の一作である“アライズGT-R 7号車”として、第三部「銀灰のスピードスター」では、元自動車評論家の輸入車ブローカー・石神滉一の愛車として、第四部「首都高SPL」では、主人公・工藤圭介率いるチューニングショップ「CRスペシャル(CRS)」が製作したコンプリートカー・Kシリーズとして登場するなど、主要登場人物の愛車に数多く抜擢されている。
- 2009年に上映された実写版『湾岸ミッドナイト THE MOVIE』では、松本莉緒氏演じる秋川レイナの愛車がクリスタルホワイトのBNR32ではなく、アクティブレッドのR34に変更されている*11。
こちらの仕様は赤色のボディカラーにエアロHとFRPボンネットA、エアロミラーでそれらしくなる。
- 特にガレージACEのデモ車は後藤のGT-Rチューンの集大成ともいえる入魂の一台であり、快適装備を残しながら筑波で59秒台という驚異的なタイムを記録する実力を持っていた。また「Rキラー」として鳴らしていた友也をC1外回りで撃墜し、彼が本格的な走り屋として目覚めていくきっかけを作った。
- 『頭文字D』では峠の神様“ゴッドフット”こと「星野好造」が搭乗。ベイサイドブルー(原作のカラーリング)かミレニアムジェイド(アニメ版のカラーリング)にエアロH、ホイールはヨコハマのSUPER ADVAN Racing version 2でそれらしくなる。
- 海外ではカーアクション映画「ワイルド・スピード」シリーズの2作目(X2)と4作目(MAX)と9作目(ジェットブレイク)に、主人公ブライアン・オコナーの愛車として本車が登場している*14。
- 初登場はX2の前日談にあたる『The Turbo Charged』で、警察から逃げる途中で乗り捨てた三菱・GTO(3000GT)に代わる車としてブライアンが中古車店で購入。登場時はミントグリーンの塗装で、砂埃を被っていた使用感のある状態だったが、ブライアン自身が整備工場の一角を借りて修理してシルバーに塗り直し、X2本編の舞台となるマイアミまでストリートレースで金を稼ぎながら旅をした。
- X2本編では、上記のシルバーボディにブルーのバイナルグラフィックスを施しており、同色のネオン管を装着。助手席を外しNX社製ナイトラス・オキサイド・システムを多連装で搭載。そしてC-WEST製エアロパーツ、A'PEXi製のEL式追加メーター、HKS製の排気システム、日立製の電気式4WDシステムを搭載した完全なストリート仕様となった。
- MAXでは麻薬組織による最後の運び屋を決めるストリート・レースに参加するため、FBIの押収品リストにあった車両をブライアンが自ら選別。それらから使えるパーツ(+発信器)をかき集めて造り上げた。ボディカラーは青。NISMO製エアロパーツ、イーストベアー製エアロボンネット、RAYS製VOLK RACING RE30、Turbonetics製インタークーラー、magdenパフォーマンスコンピュータ、OMP製バケットシート、OMP製4点式ハーネス、MOMO製ステアリング、MATTSWEENEY製ロールケージを装着している。
- 『ワイルドスピード・ジェットブレイク』ではラストシーンにて登場。ボディーカラーはブルーで、NISMOエアロ+Z-Tuneフェンダーに純正ハイマウントウイング、RAYS・ボルクレーシングTE37Vを装備している。ちなみに車両ナンバーは第7作目で登場したR35型GT-Rと同一である。
- 尚、X2とMAXでは両方とも途中でお役御免となり、別の車*15に乗り換えている*16。
- ちなみに、『ワイルドスピード・MAX』に登場する車両は本物のGT-Rではなく、SKYLINE・25GT TURBO(ER34)*17をBNR34風に改造した車両である*18。
その理由としては、4作目の撮影当時である2009年当時、本物のBNR34は1台8万ドル(760万)と非常に高価だったのに対し、ER34は1台約1万4000ドル(140万)と安かったのと、FR駆動のER34の方がドリフトしやすいという利点があった。その為、スタント用の車両にはER34にBNR34風の外装パーツを装着した車両を使用していた。*19。 - 湾岸マキシにおいてはどちらの仕様も完全再現は不可能である。
X2の仕様はシルバーのボディーカラーにエアロC(もしくはエアロD)を装着すれば若干似せられるがどちらのエアロもフロント、リアのデザインが若干異なる。
MAX仕様はブルーのボディカラーにエアロH+FRPボンネットA+RAYS VR30REでほぼ再現できた。*20しかしボンネットのダクトの有無(映画ではついていない)、リアの形状(前述のバックフォグランプなど)が異なる。
- 元気社の「首都高バトル」シリーズでは以下の代表的なライバルが使用している。
・迅帝(無双帝)/岩崎基矢*21
・鉄翁/黒崎雅和*22
・RECORD.0
・紅の悪魔/宮川雷斗*23
・蒼い彗星/小山晴彦*24
・天の永井/永井丈明
・ゴシック・ザ・マイロード/三沢喜一
・素敵に無敵/風間駿一
・リライアブルセンター/宇喜田政史
- スーパーGTの前身JGTCでは参戦初年度の1999年はチャンピオンを決めるものの、2002年の途中からエンジンをRB26DETTからVQ30DETTに変更したが1度も勝利する事なくシーズンを終えた。ラストイヤーの2003年には市販車のモノコックに前後パイプフレーム化と言う、さながら原作後期以降のブラックバードそのものといった構造になりボディラインも全体的に低く構えたシルエットフォーミュラのような外観になった*25。
このラストイヤーでザナヴィニスモGT-Rがチャンピオンを決め、翌年JGTC最後の年にZ33フェアレディZに変わってからもチャンピオンを決めると言う快挙を繋げた。
- BNR32による復活から13年愛されてきた第2世代GT-Rだったが、平成12年排ガス規制に適合できなかったため、2002年8月に生産終了、そのままモデル廃止となってしまった。
この排ガス規制によって国産車、特にスポーツカーが次々と生産終了・モデル廃止に追い込まれてしまった。S15シルビア、JZA80スープラ、FD3S RX-7なども同様の道を辿った。
それから5年後、GT-RはR35として復活したが、R35GT-Rはスカイラインとはまったく関係のない独立した車種であるため、”スカイラインとしての”GT-Rは2024年時点でBNR34が最後となっている。- 2014年に日産の高級車ブランド・インフィニティから、Q50(日本でV37型スカイラインとして販売されている車種)をベースにR35GT-Rに搭載されるVR38DETTエンジンを搭載、4WDを採用した「Q50 Eau Rouge Concept」が発表され、スカイラインGT-Rの復活と期待されたことがあったが、同年12月に開発中止となってしまった。
- 2001年にR34型の後継として登場したV35型は「新世代スカイライン」と銘打って発売され、海外版のインフィニティ・G35は世界各国で高い評価を得た。しかし日本国内では…
- …などの理由で、従来のスカイラインファンからは「これはスカイラインではない*26」「スカイラインの伝統が途絶えた」「失敗作」といった酷評を受け、セダンの需要低迷なども重なり販売は低迷してしまった。
もっとも、エンジンをフロントミッドシップに搭載する新型プラットフォーム採用による重量配分改善、デザインを曲線的にしたことによる空力性能の改善など、R34型から改良された箇所も少なくない。
初代スカイラインは旧プリンス自動車工業の高級車としてデビューしたため、「高級路線への回帰」という観点からすれば原点回帰とも言える。 - 元々V35型のコンセプトモデルである「XVL」はスカイラインとは別のモデルとして発表され、日産の新しいスポーツセダンとして開発が進められていた*27。しかし、XVLのコンセプトがスカイラインの根源的なそれと重複する部分も多かったために、ルノーの上層部の意見によりXVLを次期スカイラインとすることが決定され、V35型として発売することとなった。
- 上記の通りV35型で全モデルがV型6気筒エンジンに変更されたため、直列6気筒エンジンを搭載した最後のスカイラインでもある。現在でも直列6気筒と、完全な丸4灯テールランプ*28の復活を望む声は大きい。
- 中古車市場でも人気が高く、販売期間が歴代スカイラインに比べて短い事による生産台数の少なさから、現在では殆どの物件が1000万円以上という超高額で取引されている。
- 通常モデルが1998年-2001年、GT-Rは1999年-2002年の3年間で、歴代のスカイラインの中で最も短い。総生産台数は6万4,623台(その中でGT-Rは1万1,344台)。
ただしGT-Rのみに限るならば、4代目スカイラインをベースとした2代目スカイラインSKYLINE 2000GT-R(KPGC110)の3ヶ月が一番短い。ちなみに最も販売期間が長いモデルはV36型(セダンが2006年11月から2014年12月まで、クーペが2007年10月から2016年1月まで)の約8年間。
- 通常モデルが1998年-2001年、GT-Rは1999年-2002年の3年間で、歴代のスカイラインの中で最も短い。総生産台数は6万4,623台(その中でGT-Rは1万1,344台)。
- ミッション切り替え音:ブローオフ 例「シャーン」








