| No.025 | ||||
|---|---|---|---|---|
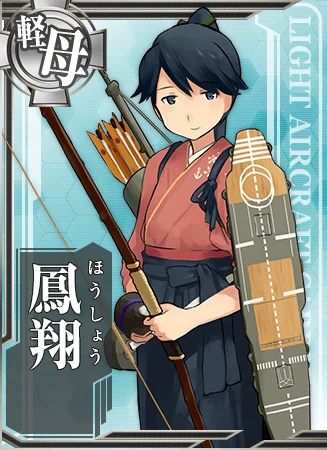 | 鳳翔(ほうしょう) | 鳳翔型 1番艦 軽空母 | ||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 30 | 火力 | 0 / 19 | |
| 装甲 | 15 / 39 | 雷装 | 0 | |
| 回避 | 24 / 39 | 対空 | 10 / 29 | |
| 搭載 | 19 | 対潜 | 0 | |
| 速力 | 低速 | 索敵 | 32 / 69 | |
| 射程 | 短 | 運 | 20 / 69 | |
| 最大消費量 | ||||
| 燃料 | 25 | 弾薬 | 25 | |
| 搭載 | 装備 | |||
| 8 | 九九式艦爆 | |||
| 11 | 未装備 | |||
| 装備不可 | ||||
| 装備不可 | ||||
| 改造チャート | ||||
| 鳳翔 → 鳳翔改(Lv25) → 鳳翔改二 (Lv91+改装設計図+試製甲板カタパルト+高速建造材x20) ⇔ 鳳翔改二戦(Lv92+開発資材x20+高速建造材x20) | ||||
| 図鑑説明 | ||||
| 航空母艦、鳳翔と申します。 最初から空母として建造された、世界で初めての航空母艦なんです。 小さな艦ですが、頑張りますね。 | ||||
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:洲崎綾、イラストレーター:しばふ
定型ボイス一覧
| イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳 翔 | 鳳 翔 改 | 鳳 翔 改 二 | 鳳 翔 改 二 戦 | 追加 | ||||
| 入手/ログイン | 航空母艦、鳳翔です。ふつつか者ですが、よろしくお願い致します。 | ◯ | ◯ | × | × | 編集 | ||
| 航空母艦、鳳翔です。改装して頂きました。微力ですが、力の限り努めさせていただきます。 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 母港*1 | 編集 | |||||||
| 母港1 | 詳細 | お茶にしましょうか。 | ◯ | ◯ | × | × | 編集 | |
| 提督、鳳翔も共に参ります。最後まで。 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 母港2 | よい風ですね。 | ◯ | × | × | × | 編集 | ||
| 私の夢ですか? そうですねぇ、いつか二人で小さなお店でも開きたいですね・・・って、あらやだ、ごめんなさい。忘れてください。 | × | ◯ | × | × | 編集 | |||
| お疲れ様です。お風呂にしますか?ご飯にしますか? それとも・・・ふふっ、冗談ですよ。 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 母港3 | お疲れ様です。お風呂にしますか?ご飯にしますか? それとも・・・ふふっ、冗談ですよ。 | ◯ | ◯ | × | × | 編集 | ||
| 私の夢ですか? ……そうですねぇ、いつか二人で、小さなお店でも開きたいですね。 ……て、あらやだ、大和!? 見てた? これは、これはね、ええと、あの……大和、さん? | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| ケッコンカッコカリ | いつか…いつかふたりで、のんびりと船旅を楽しみたいものですね。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| ケッコン後母港 | 提督、何時もお疲れ様です。時には、ゆっくりお休みになってください。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 放置時 | 提督、私ここに控えていますので、御用があればいつでもおっしゃってくださいね。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 編成出撃 | 編集 | |||||||
| 編成 | 実戦ですか・・・致し方ありませんね。 | ◯ | ◯ | × | × | 編集 | ||
| 実戦……ですね。この時の為、今、鳳翔はいます。貴方と共に! | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 出撃 | 鳳翔、出撃致します。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 開戦・攻撃*2 | 編集 | |||||||
| 戦闘1 | 昼戦開始 | 風向き、よし。航空部隊、発艦! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘2 | 昼戦攻撃 | これは、演習ではなくて実戦よっ! | ◯ | ◯ | × | × | 編集 | |
| 鳳翔航空隊、行きなさい! | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 戦闘3 | 夜戦開始 | やるときは、やるのです! | ◯ | ◯ | × | × | 編集 | |
| 貴方達を、逃しはしません! | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 戦闘4 | 夜戦攻撃 | いつまでも演習って訳にもいきませんっ! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘時ステータス*3 | 編集 | |||||||
| 小破 | ああっ! 飛行甲板が! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| あぁぁっ! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 中破/大破 | このまま沈む訳には参りませんっ! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 轟沈 | 私も…沈むのですね… | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 戦闘終了*4 | 編集 | |||||||
| 勝利MVP | そんな、本当ですか!?私もお役に立てたのなら、嬉しいです。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 旗艦大破 | あぁぁっ! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 装備・改修*5 | 編集 | |||||||
| 装備1 | 改修/改造 | すみません、私の武装を強化してくれるなんて。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 装備2 | 私には・・・少し大袈裟ではないでしょうか? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | 大丈夫ね。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| その他 | 編集 | |||||||
| 帰投 | お疲れ様でした、艦隊が帰ってきましたね。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 補給 | すみません、私の武装を強化してくれるなんて。 | ◯ | × | × | × | 編集 | ||
| 提督、ありがとうございます。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 入渠(小破以下) | そうですね、少しだけお休みします。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 入渠(中破以上) | 私が無茶しては、ダメですね。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 建造完了 | 新しい子たちが来るみたいね。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 戦績表示 | 提督にお知らせが届いていますね。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
時報ボイス一覧
| 時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳 翔 | 鳳 翔 改 | 鳳 翔 改 二 | 鳳 翔 改 二 戦 | 追加 | |||
| 00 | 編集 | ||||||
| 01 | 編集 | ||||||
| 02 | 編集 | ||||||
| 03 | 編集 | ||||||
| 04 | 編集 | ||||||
| 05 | 編集 | ||||||
| 06 | 編集 | ||||||
| 07 | 編集 | ||||||
| 08 | 編集 | ||||||
| 09 | 編集 | ||||||
| 10 | 編集 | ||||||
| 11 | 編集 | ||||||
| 12 | 編集 | ||||||
| 13 | 編集 | ||||||
| 14 | 編集 | ||||||
| 15 | 編集 | ||||||
| 16 | 編集 | ||||||
| 17 | 編集 | ||||||
| 18 | 編集 | ||||||
| 19 | 編集 | ||||||
| 20 | 編集 | ||||||
| 21 | 編集 | ||||||
| 22 | 編集 | ||||||
| 23 | 編集 | ||||||
季節ボイス一覧
| 季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳 翔 | 鳳 翔 改 | 鳳 翔 改 二 | 鳳 翔 改 二 戦 | 追加 | ||||
| 春 | 桃の節句 | 編集 | ||||||
| 春の訪れ | 編集 | |||||||
| ホワイトデー | 提督、これをチョコレートのお返しに? かえってお気を使わせてしまって、すみませんっ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
| 春 | 春、お花見の季節ですね。提督、空母の皆さんを連れて、お花見行かれます? お重をご準備しましょうか。ふふっ、腕によりをかけますね。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
| 春本番 | 編集 | |||||||
| 夏 | 梅雨 | また雨……こんな日は、食べ物が傷みやすくて困ります。洗濯物も……。どうしましょう? | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 初夏 | 編集 | |||||||
| 夏 | そうですねー、浜辺の艦娘と提督のために、浜茶屋を開きましょうか。間宮さん、伊良湖さん。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
| 盛夏 | 編集 | |||||||
| 夏祭り | 編集 | |||||||
| 秋 | 秋 | 少し涼しくなってきました。秋ですね。 | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 秋刀魚 | 確かに、旬の秋刀魚は大変美味しいものです。塩焼きも、お刺身もいいですね♪ 準備しますね? | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
| 晩秋 | 編集 | |||||||
| ハロウィン | 編集 | |||||||
| 秋のワイン | 編集 | |||||||
| 冬 | 冬 | 編集 | ||||||
| 師走 | さ、師走大掃除、頑張りましょ? 赤城さん、そちらを。加賀さんは、その窓をお願いします。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
| クリスマス | 提督。クリスマスの料理、和風アレンジで幾つか挑戦してみたんです。よかったら…どうですか? お口に合えばいいのですが…。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 年末 | 編集 | |||||||
| 新年 | 提督、新年明けましておめでとうございます。本年も、全航空母艦をどうぞよろしくお願いします。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
| 節分 | はい。節分用のお豆を、全て炒っておきました。足りないようでしたら、お知らせくださいね。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
| バレンタイン | 提督、あの……どうかと思ったのですが、私もチョコレートをお渡しできれば、と……あの…… | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
| チョコレート、いかがでしたか? きな粉と和三盆を使って和風に……そうですか、良かった。 | ◯ | ◯ | 編集 | |||||
| 周 年 | 二周年記念 | 編集 | ||||||
| 三周年記念 | 提督、艦隊は三周年を迎えました。本当にお疲れ様です。これからも、がんばりましょう。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
| 四周年記念 | 提督。艦隊は、四周年を迎えました。本当にお疲れ様です。これからも、頑張りましょう。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
| 五周年記念 | 編集 | |||||||
| 六周年記念 | 編集 | |||||||
| 七周年記念 | 編集 | |||||||
| 八周年記念 | 編集 | |||||||
ゲームにおいて
- 早ければ1-3からドロップする軽空母。建造でも出る。初空母が彼女という提督もそれなりにいるのではなかろうか。
- 駆逐艦の睦月型や、軽巡における天龍型、重巡における古鷹・青葉型など、いわゆる低燃費組(または旧型)の軽空母代表。
- このため、同カテゴリの他種と比べ能力値の限界は控えめとなっている。
- 無改造で空母として使える艦としては最も低レアリティ(低レアリティだから能力が低いとも言える)。
空母とか軽空母って?(クリックで展開)
- 航空母艦の略。艦これには、アイコンが【航】の正規空母と、【軽母】の軽空母、と大きく分けて2種類がある。
- これまでの駆逐艦や軽巡洋艦、あるいは戦艦とは異なり、その行動の大半を艦載機に依存する艦種。なので無装備状態では何もできない。
艦載機を装備することで、航空戦を行ったり、昼砲撃戦中にさらに艦載機攻撃を行うことができる。
- 軽空母は正規空母より若干ステータスが低い傾向があるが、燃費が軽めなのが序盤のうちはありがたい。
- 軽空母と正規空母はどちらも求められる場面があるので、単なる優劣にはなっていない。
- 歴史的には帝国海軍は軽空母という分類は設けていないので、この分類は艦これ独自のもの。
鳳翔独自の運用
- さすがに火力・防御力の絶対値で上位軽空母他に劣るので、高次海域の最前線を張るには提督のこだわりを要する。
改造して近代化改修をし、高位の航空機を準備しておきたい。
- 最大の強みにして、独自の特徴が低コスト。戦闘消費、修理資材ともに非常に軽い、空母カテゴリの特異的存在。
- 改造前は搭載機総数19機に過ぎないが、改造後は42機と倍増する。龍驤改の搭載総数43機より1機少なく、軽空母の搭載総数としては最下位である。
- しかし、この42機が3スロットの中にバランスよく配置されるため、存外に実戦でも通用する能力だったりするのだ。
- 平均的にまとまった艦載機の振り分けは、バランスよく色々載せてよし、一点特化させてよしと、器用な運用ができる。同じ軽空母でも龍驤とは取り回しがずいぶん違う。
- スロット構成が平均化されているという事は、1スロットに壊滅的被害を受ける事が少なく、比較的下位の艦載機でも戦力を構成し易いと云うメリットになる。
- 一方、副砲や電探、彩雲といった補助兵装を搭載すると一気に運用機数が減る。
また飛び抜けて大きいスロットが無いので、ホロ艦載機のパワーを爆発的に発揮させるという運用も苦手。
- 元祖一航戦の鳳翔だが、艦これ的な特性はむしろ飛鷹型や五航戦姉妹に近い。そちらを用いる際、鳳翔の運用経験をそのまま活かせるだろう。
- 練習空母の史実に相応しく、艦載機熟練度システムとの相性は抜群。
- 熟練度を上げるにはその艦載機で出撃を繰り返す必要があるが、燃費の安い鳳翔ならこの任務にうってつけ。
前線に送り出す予定の艦載機を積み込んで安全に空戦ができる1-1,1-2などに送り込めば、優れたコストパフォーマンスで実戦錬度に叩き上げてくれるだろう。
- 熟練度を上げるにはその艦載機で出撃を繰り返す必要があるが、燃費の安い鳳翔ならこの任務にうってつけ。
鳳翔に関連する任務
- 鳳翔が指名で必要となる任務がある。
- 精鋭「艦戦」隊の新編成 (2015年10月30日に追加)
- この任務はマンスリー任務で繰り返し実行が可能であるが、任務達成にアイテム「熟練搭乗員」が必要。
熟練搭乗員の入手は以下の任務で可能で、ほかにも獲得機会がある。 - この任務はさらに強力な艦上戦闘機隊を入手する任務の起点となっている。
- この任務はマンスリー任務で繰り返し実行が可能であるが、任務達成にアイテム「熟練搭乗員」が必要。
- 「熟練搭乗員」養成 (2016年7月15日に追加)
- 精鋭「艦戦」隊の新編成 (2015年10月30日に追加)
装備ボーナスについて
キャラクター設定について
- 秘書艦としては甲斐甲斐しく世話をしてくれる…というよりその雰囲気も合わせて新妻そのもの。そんなわけでついたもう一つのあだ名が、艦種に引っ掛けた「良妻軽母」。
- 2014年1月22日のアップデートで鳳翔改に追加ボイスが新たに実装され良妻軽母感が強まった。
- さらにお艦と呼ばれるようにもなり、千歳のボイスや鳳翔さんの夕食券で小料理屋を営んでいる設定が加えられた。
- 2014年1月22日のアップデートで鳳翔改に追加ボイスが新たに実装され良妻軽母感が強まった。
期間限定グラフィック
- 2017年1月1日のアップデートで新春modeの母港グラフィックが公開された。
- 割烹着に熱燗と、いかにも鳳翔さんらしい格好。中破するとほろ酔い姿を見せてくれる。
ちなみにこのイラストは、元は2016年末の大規模同人誌即売会の角川ブースで販売された艦これグッズの「二合徳利&お猪口2個セット」に添えられたもの。
また、このイラストの差分絵で徳利の代わりに神籤箱を持った巫女姿のものが、2017初頭の三越とのコラボグッズ絵として使用された。
限定イラスト:新春mode
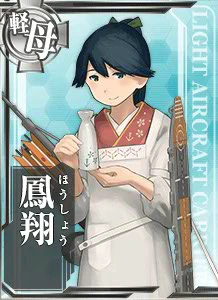
- 割烹着に熱燗と、いかにも鳳翔さんらしい格好。中破するとほろ酔い姿を見せてくれる。
- 2021年1月13日のアップデートで「節分mode」が追加された。
- 節分modeの多くが豆まき系の中、普段の恰好で箒片手に鬼除けの柊鰯を用意する辺りが鳳翔さんらしい。
- 中破しても襟の辺りが少し破れる程度で、殆ど露出が増えない。
限定イラスト:節分mode
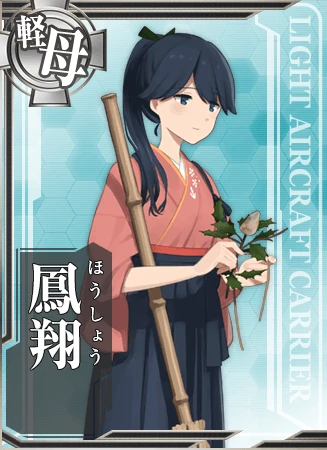
小ネタ
- 「最初から空母として設計・建造された艦」として日本で最初に起工・竣工し、かつ「最初から空母として設計・建造された艦」の中で世界で最初に竣工した艦である。
それゆえエピソードには「日本初」のものが多い。
大正11(1922)年に竣工した純粋な航空母艦であり、従って本来はこんなに小さくても正規空母であり、太平洋戦争を生き抜いた筋金入りの大ベテランである。詳細は上の来歴の項目を参照。
漂う年長の雰囲気はこれが元。
だが、彼女にBB(ryなどと言うと各方面に結構な数の敵を作ることになるので覚悟して発言すべし。
諸元
- 竣工時の諸元は以下の通り。
諸元
全長/全幅/喫水 168.2/18.9/6.2m 排水量(基準/常備) 7,470t/9,494t 機関出力 30,000馬力/2軸 速力 25.0kt 航続力 10,000海里/14kt 主兵装 14cm砲単装4基4門
8cm高角砲単装2基2門
7.7mm機銃単装2基2丁装甲 - 搭載機 常用15機+補用6機 乗員 548名
来歴
- 膨大なため、起工以降 - 開戦後 - 終戦後の期間に分けて記述する。
1919 12.16 特務艦として浅野造船所にて起工 1921 10.31 「鳳翔」と命名 11.13 進水、後横須賀工廠にて艤装 1922 12.27 竣工、横須賀鎮守府所属 1923 2.22 英国人パイロットのジョルダンが、一〇式艦上戦闘機にて着艦試験に成功 3.16 日本人パイロットの吉良俊一大尉が、一〇式艦上戦闘機にて着艦試験に成功 1924 ― 島型艦橋撤去等の改装実施 9.1 第1艦隊所属にて大演習参加 11.15 第1艦隊より除籍 1925 9.1 連合艦隊に編入 1926 3.30 中城湾発・厦門を経て4月5日馬公着 4.19 基隆発・舟山島を経て29日寺島水道着 12.1 連合艦隊より除籍 1927 3.25 連合艦隊に編入 3.27 横須賀発・青島を経て4月5日旅順着 1928 3.29 有明湾発・舟山島を経て4月2日基隆着 4.1 第1航空戦隊編入 4.14 馬公発・厦門を経て20日奄美大島着 12.10 第1航空戦隊より除籍 1929 4.1 第1航空戦隊編入 4.13 大連発・秦皇島を経て22日佐世保着 1930 5.17 奄美大島(古仁屋)発・南洋方面に向かう、6月19日横須賀着 1931 3.29 佐世保発・青島を経て4月5日裏長山列島着 1932 1.29 横須賀発・上海に向かう、2月12日上海沖に進出、敵軍・敵基地攻撃に当たる
三式艦戦(常用6+補用4)、一三式艦攻(常用6+補用3)2.2 第3艦隊・第1航空戦隊編入 2.19 杭州敵基地と交戦、3月2日佐世保着 1933 5.20 第1艦隊・第1航空戦隊編入 6.29 佐世保発・馬鞍群島を経て7月4日基隆着 7.13 馬公発・南洋方面に向かう、8月21日木更津着 10.1 20日まで連合艦隊演習に参加 10.20 第1航空戦隊より除籍 1934 11.15 第1艦隊・第1航空戦隊編入 1935 3.29 佐世保発・馬鞍群島を経て4月4日寺島水道着 10.26 北海道東方において、台風で甲板前端圧潰、入渠修理 1936 4.13 佐世保発・青島を経て22日寺島水道着 8.4 基隆発・厦門を経て7日馬公着 1937 3.27 寺島水道発・青島を経て4月6日有明湾着 8.6 第3艦隊指揮下 8.8 第3艦隊航空部隊・第1空襲部隊に部署 8.12 馬鞍群島方面進出を下令、22時00分佐世保発・中支方面に向かう 8.13 台風を避け北上、14日済州島付近より南下 8.16 馬鞍群島付近から敵基地攻撃開始、敵機2機撃墜10機撃破 8.17 上海付近の敵基地・陣地攻撃 8.18 敵陣地攻撃 8.22 偵察攻撃 8.23 第3師団上陸作戦に協力、敵部隊・陣地攻撃 8.24 第3梯団上陸作戦に協力、敵部隊・陣地攻撃 8.25 各地攻撃、延べ19機(1航戦全体) 8.26 各地攻撃、延べ16機(1航戦全体) 8.27 各地攻撃、延べ29機(1航戦全体) 8.28 各地攻撃、延べ24機(1航戦全体) 8.29 各地攻撃、延べ36機(1航戦全体) 8.30 各地攻撃、延べ23機(1航戦全体) 8.31 各地攻撃、延べ23機(1航戦全体) 9.1 各地攻撃、延べ18機(1航戦全体)、2日佐世保着 9.16 佐世保発・南支・広東方面に向かう 9.22 艦戦15・艦爆12・艦攻3にて飛行場攻撃
敵13機撃墜、艦戦5が帰途洋上不時着水(一航戦全体)9.23 艦戦10・艦爆艦攻18にて飛行場攻撃
戦爆24にて飛行場攻撃、1機未帰還
艦戦6にて陸攻隊護衛、24日馬公着9.26 馬公発・南支方面に向かう、29日馬公着 9.30 馬公発・中支方面に向かう、各地攻撃後10月19日佐世保着 12.1 第1航空戦隊より除籍 1940 11.15 第1艦隊・第3航空戦隊編入 1941 2.24 佐世保発・南支方面に向かう、3月3日馬公着 11.15 主力部隊に部署、内海西部に待機、機動部隊引き揚げ援護を下令 1941 12.8 太平洋戦争開戦。呉発・機動部隊の避退援護、13日呉着 1942 2.4 呉入港 2.8 警戒部隊に部署、米機動部隊の本土来襲警戒に従事 3.5 南鳥島に来襲した米機動部隊迎撃を下令、同日取り消し 3.12 警戒部隊第一航空部隊に部署、本土東方洋上に出撃下令
同日出撃、15日小笠原付近で反転、伊勢湾に入港3.20 伊勢湾発・同日呉着、同日呉発・内海西部にて待機 4.18 内海西部出撃・米機動部隊迎撃、20日反転帰投 5.5 主力部隊主隊に部署、MI作戦支援下令 5.8 呉入港 5.12 呉発・内海西部にて待機 5.29 内海西部発・ミッドウェー北西方に向かう 6.1 搭載機が主力部隊前方に油を発見、爆撃 6.4 主隊空母隊に部署、作戦支援に従事 6.5 ミッドウェー攻略作戦中止、艦攻1機が炎上中の飛龍に人影を報告 6.14 柱島泊地に帰投、15日呉入港 6.20 第1航空艦隊編入、機動部隊付属部隊に部署 6.29 呉発・内海西部にて待機 7.14 第一航空艦隊解隊、第三艦隊編入、機動部隊付属部隊に部署 7.19 呉入港、23日呉発・内海西部にて待機 8.6 呉入港、9日呉発・内海西部にて待機 8.14 機動部隊待機部隊に部署 8.18 呉入港整備 10.18 呉発・内海西部にて待機 11.24 呉入港 12.7 呉発・内海西部にて待機 1943 1.3 呉入港 1.8 呉発・内海西部にて訓練 1.15 第3艦隊・第50航空戦隊に編入、機動部隊・訓練部隊・第3部隊に部署 1.20 呉入港 1.26 呉発・内海西部にて訓練 2.14 呉入港 2.16 呉発・内海西部にて訓練 2.18 呉入港 3.1 呉発・内海西部にて訓練 3.19 徳山入港 3.21 徳山発・内海西部にて訓練 4.14 徳山入港 4.22 徳山発・内海西部にて訓練 6.1 徳山入港 6.9 徳山発・内海西部にて訓練 6.23 徳山入港 7.23 呉発・内海西部にて訓練 8.17 呉入港 8.22 呉発・内海西部にて訓練 9.14 呉入港 9.21 呉発・内海西部にて訓練 10.5 呉入港 10.23 呉発・内海西部にて訓練 10.27 徳山入港 10.29 徳山発・内海西部にて訓練 11.8 呉入港 11.25 呉発・内海西部にて訓練 12.4 呉入港 12.16 呉発・内海西部にて訓練 12.22 呉入港 12.24 呉発・内海西部にて訓練 12.29 呉入港 1944 1.1 第50航空戦隊解隊、北東方面艦隊・第12航空艦隊・第51航空戦隊に編入
北東方面部隊・第2基地航空部隊・第31空襲部隊に部署1.4 呉発・内海西部にて訓練 1.13 呉入港 2.20 第51航空戦隊より除籍、連合艦隊付属部隊に部署 2.27 呉から徳山に回航 3.3 徳山発・内海西部にて訓練 3.26 呉入港 4.30 呉発・内海西部にて訓練 5.11 呉入港 5.19 呉発・内海西部にて訓練 6.12 呉入港 6.15 呉発・内海西部にて訓練 6.17 呉入港 6.30 呉発・内海西部にて訓練 7.31 呉入港 8.7 呉発・内海西部にて訓練 9.1 呉入港 9.9 呉発・内海西部にて訓練 12.19 呉入港 12.27 呉発・内海西部にて訓練 1945 3.1 徳山入港、後呉回航 3.3 呉発・内海西部にて訓練 3.19 5時32分米機動部隊艦上機7機による空襲、小型爆弾3発命中、戦死6名 3.21 呉入港 3.27 呉発・内海西部にて訓練 4.10 呉入港、以後偽装係留 4.20 第3予備艦と定める 6.1 第4予備艦と定める 8.15 呉港務部にて終戦を迎える 10.5 除籍 1945 12.1 呉地方復員局所管の特別輸送艦に指定される 1946 8.31 特別輸送艦指定解除。日立造船株式会社築港工場にて解体開始 1947 5.1 解体完了 - 歴代艦長
1922 9.20~ 豊島二郎 大佐*6 1923 4.1~ 福与平三郎 大佐 12.1~ 海津良太郎 大佐 1925 4.15~ 小林省三郎 大佐 1926 11.1~ 河村儀一郎 大佐 1927 12.1~ 北川清 大佐 1928 12.10~ 原五郎 大佐 1929 11.30~ 和田秀穂 大佐 1930 12.1~ 近藤英次郎 大佐 1931 11.14~ 堀江六郎 大佐 1932 12.1~ 三竝貞三 大佐 1933 10.20~ 竹田六吉 大佐 1934 11.15~ 山縣正郷 大佐 1935 6.12~ 寺田幸吉 大佐 11.15~ 酒巻宗孝 大佐 1936 11.16~ 草鹿龍之介 大佐 1937 10.16~ 城島高次 大佐 1939 11.15~ 原田覚 大佐 1940 8.20~ 杉本丑衛 大佐*7 11.1~ 菊池朝三 大佐 1941 9.15~ 梅谷薫 大佐 1942 8.1~ 山口文次郎 大佐 11.25~ 服部勝二 大佐 1943 7.5~ 貝塚武男 大佐 12.18~ 松浦義 大佐 1944 3.1~ 国府田清 大佐 7.6~ 室田勇次郎 大佐 1945 3.5~ 大須賀秀一 大佐(~5.1) 5.5~ 大須賀秀一 大佐*8 5.18~ 古谷啓次 大佐*9 9.20~ 金岡国三 大佐/第二復員官 1946 3.8~ 吉田正義 第二復員官 6.4~ 作間英邇 第二復員事務官/復員事務官
「最初から空母として設計・建造され、世界で最初に竣工した」航空母艦
- 世界初の定義が妙に細かいのは「最初」とするカウントの仕方次第でどれが初かが変わるため。
- 鳳翔の起工は1920年12月16日、竣工したのは1922年12月27日である。
以下に挙げる艦が各種の「世界初」の記録を持つ空母たちである。- 「世界初の航空母艦」はイギリス海軍「フューリアス(1915起工、1917空母改装)」。
- 巨大軽巡から航空母艦へ改装された、いわゆる改造空母。
但し実験艦としての要素が強く、最初の飛行甲板は全通式ではなかった。
まず前部に発艦用、後に後部に着艦用と別々に設けられたが、最終的には全通式に改装されている。
単に「世界初の空母」と言った場合はこのフューリアスを指す。1918年には世界初の空母搭載機による攻撃も行っている。
- 巨大軽巡から航空母艦へ改装された、いわゆる改造空母。
- 「初めから全通飛行甲板を持った艦」はイギリス海軍「アーガス(1914起工、1918竣工)」。
- 「最初から空母として設計され、世界で最初に起工した艦」はイギリス海軍「ハーミーズ(1918起工、1924就役)」。
- 起工は鳳翔よりも2年程早いが、改装空母「イーグル」の実績を踏まえて慎重に時間をかけて建造されたため、鳳翔より約2年遅れての竣工となった。
- なお、鳳翔の建造にはこのハーミーズを始めとした各種イギリス空母の設計、運用データが参考にされている。
- 「日本初の【航空母艦】」は「若宮(1901起工、1914改装、1920空母登録)」
- 元英国製商船「若宮丸」、日本海軍において1920年(大正9年)に新設された「航空母艦」という新しい艦種に初めて在籍した艦である。
事実上は商船改装の水上機母艦だが、この当時は空母を発着する艦上機という機種がまだなかったために、水上機母艦と航空母艦の境界が存在しなかった。
若宮は実験的に仮設滑走台を設けて日本で初めて陸上機を発艦させている。
第一次世界大戦では青島攻略戦に参加し、日本海軍として初めて艦載機による航空戦を展開した。搭載機は水上機4機(常用2機・分解収容2機)であった。
- 元英国製商船「若宮丸」、日本海軍において1920年(大正9年)に新設された「航空母艦」という新しい艦種に初めて在籍した艦である。
- 「世界初の航空母艦」はイギリス海軍「フューリアス(1915起工、1917空母改装)」。
- 鳳翔の起工は1920年12月16日、竣工したのは1922年12月27日である。
- 鳳翔は大正七年度計画(八六艦隊案)の計画艦で、由良、鬼怒、阿武隈、神風と同じ出自。
当時「航空母艦」という艦種はなかったので、特務艦として予算計上されている。- 建造計画段階の仮称は「特務船第七号」。
- 大正8(1919)年、造船所に建造を内示した時の予定船名は「龍飛(たっぴ)」。
翌9年、建造計画表の変更時に「鳳翔」と正式決定された*10
仮名と実際の名は両方とも「龍飛鳳翔」という四字熟語から取られている。
この言葉は「天子・英雄(=龍鳳)」が「立ち上がる(飛翔)」様を比喩したものである。 - 建造を請け負った浅野造船所での通番は56。
浅野造船所は後に幾度かの合併や名称変更を経て、現在はジャパン マリンユナイテッド京浜事業所となっている。
そして、浅野造船所を受け継ぐ浅野ドックは1995年に閉鎖されている。
- 大正8(1919)年、造船所に建造を内示した時の予定船名は「龍飛(たっぴ)」。
- 空母「鳳翔」は、この名を持つ艦としては2代目となる。
先代は、明治2年(1869年)に長州藩がイギリスに発注し、政府に献上した砲艦「鳳翔」。- 空母「鳳翔」も、建造と運用にラトランド将校・センピル卿といったイギリス人技師の多大な協力があったとされており、2代続けてイギリス生まれの英国淑女と同様、なにかとイギリスに縁のある艦名である。
尚、空母「鳳翔」建造に『当時は同盟国として』協力したイギリスの両氏だったが、後の日英開戦により「日本への空母技術の輸出」が軍事機密漏洩と認定され、スパイ容疑で拘束されてしまう。
当然、遡及処罰も良い所だったので、最終的には不訴追となったものの……
戦争中は紳士淑女の国イギリスですらアレであった。 - なお、字は異なるが、幕末に江戸幕府がイギリス商船(帆船)を購入して「鵬翔丸(ほうしょうまる)」と命名した艦がある。
航海練習船として使用していたが1860年に台風で沈没しており、帝国海軍には引き継がれていない。 - 鳳翔型2番艦の名前は*11「翔鶴」(未成。幕府海軍から数えて二代目)。
経緯はともかく、赤城の姉「天城」と同様、ワシントン海軍軍縮条約により建造前に中止されている*12
船殻を製造した浅野造船所が鳳翔進水後の船台で引き続き担当する計画だったが、中止により大量解雇を招いたという。
そのため鳳翔と翔鶴(提督諸官隷下のほう。幕府海軍から数えて三代目)は叔母と姪の関係に当たる。
「翔鶴外一隻の航空母艦」つまり3番艦ないし後継空母の計画も内示されていたようだが、合わせて中止された。
最終的に、条約の空母枠1隻は「翔鶴」→「天城」→「加賀」と矢継ぎ早に受け渡されることになる。
- 空母「鳳翔」も、建造と運用にラトランド将校・センピル卿といったイギリス人技師の多大な協力があったとされており、2代続けてイギリス生まれの英国淑女と同様、なにかとイギリスに縁のある艦名である。
- 建造計画段階の仮称は「特務船第七号」。
- 空母として最年長なだけでなく、艦これに登場するどの重巡や駆逐艦よりも年上。
- 現在実装されている中で最も年上の駆逐艦神風と比べると、竣工日で言うと鳳翔のほうが1日だけ年長である。どちらも終戦まで生き残った。(神風側の戦歴は神風のページを参照)
- 実験艦として、また数多くのパイロットを育ててきた練習空母として、まさに空母たちの母親であり、史実的にもイラスト的にも艦隊のお艦と呼べる存在。
- 鳳翔艦長を拝命された方は30名。
艦長経験が鳳翔しか無い又は最後の艦長職が鳳翔であった方5名を除いた25名の中で、23名の方はその後も航空母艦の艦長を務められ、艦長育ての名人っぷりも発揮。- 有名どこでは、真珠湾攻撃時やミッドウェー海戦時の第一航空艦隊参謀長を務め、後に連合艦隊参謀長も務めた草鹿龍之介。
翔鶴の初代艦長、ミッドウェー海戦後の第二航空戦隊司令官などを務めた城島高次。
瑞鶴の三代目艦長や大鳳の初代艦長、第一航空艦隊参謀長や第二航空艦隊参謀長などを歴任した菊池朝三など。 - 戦死された方も少ないという、お艦は愛と共に艦長達に幸運も授けられたようです第四南遣艦隊司令長官「山縣正郷様」瑞鶴艦長「貝塚武男様」第26航空戦隊司令官「杉本丑衛様」御三方のご冥福をお祈りいたします
因みに空母艦長にならなかった2名の次職は戦艦伊勢と水上機母艦千代田の艦長という、何やら底知れぬお艦パワーが働いたのだろうか?。
次職内訳は赤城(9名)、加賀(3名)、瑞鶴・瑞鳳・海鷹(2名)、翔鶴・大鳳・龍驤・龍鳳(1名)、伊吹と笠置は艤装員長(就役していれば極マレなケースを除き艦長になります)
- 有名どこでは、真珠湾攻撃時やミッドウェー海戦時の第一航空艦隊参謀長を務め、後に連合艦隊参謀長も務めた草鹿龍之介。
- 史実では鳳翔ママより英国淑女と妹たちや天龍龍田、長良、球磨型五姉妹の方が年u(このコメントは何者かによって削除されたデース、あんまり詮索すると両舷四〇門ブチ込みますわよ)
- ちなみに
重巡一のBB(粛清「すべての重巡の姉」古鷹とは1つ違い。なのにこっちは母、向こうは姉……。
- ちなみに
設計 ― 先駆故の苦難
- 自身の言うように、飛行甲板、速度、搭載機数、対空砲等々、全てが小ぶり。
- しかし空母黎明期に起こった数々の大問題をその細腕で悉く潰してきた功績は極めて大きく、それらの成果は後に続く娘達に洋の東西無く受け継がれていった。
- 特に就役直後は、海軍先進国であったイギリスやアメリカ含めどこの国も艦載機運用に関する知識・技術が未熟で、各々が手探りで航空母艦という艦種の有り方を模索していた時期であったため、様々な問題に直面している。
第一の問題 : 小さく軽い船殻
- これは生涯最初にして最大の問題であった。
- 洋上の波の波長よりも艦の寸法が小さいと揺れる頻度が多くなり、船体が軽いと小さな波でも大きく揺すられるため艦載機の発着艦に支障をきたす。
- 鳳翔では揺動を軽減すべく、須式転輪安定儀と言うジャイロスタビライザーで動的に制動しており、同様の処置は龍驤でも行われた。
- このスタビライザーは全部で4基が用意されたが使われたのはこの2隻向けの2基だけ。
残り2基は瑞鳳と祥鳳に搭載予定のものと言われる。 - しかし洋上での実運用において、合成風速を稼ぐのに風に船を立てると主に前後にしか揺れないため、専ら巡航中や食事中の居住性向上に貢献したそうな。
- 波を踏み潰せるだけの重さがない小さな艦はいちいち波に乗り上げるので前後の揺れは抑えようがなかった。
しかし横揺れは前に進むことで側舷を均等な頻度で叩かれるので、艦の大きさに関わらず小さくすることが出来た。
そのため着艦時はともかく、発艦時にジャイロスタビライザーは意味が薄かった。
- このスタビライザーは全部で4基が用意されたが使われたのはこの2隻向けの2基だけ。
- 娘達は大きくなることでこれの問題を克服していった。
- 鳳翔では揺動を軽減すべく、須式転輪安定儀と言うジャイロスタビライザーで動的に制動しており、同様の処置は龍驤でも行われた。
第三の問題 : 着艦装置の未熟
- 鳳翔の就役した1920年代には着艦した艦載機を減速させる装置であるアレスティングワイヤー(着艦制動索)の方式が二種類あり、鳳翔で採用されたのは英国発の縦索式であった。
- 縦索式は艦載機の進入方向に対して平行、つまり艦の前後の向きにワイヤーを張り、艦載機に櫛のような装置を付けることで、摩擦によって徐々に減速させる方式。(鳳翔の場合は縦に108本のワイヤーを張っていた)
もう一方の横索式は艦載機の進入方向に対して直角、即ち艦の左右の向きにワイヤーを張り、艦載機の尾部に取り付けたフックで引っ掛けて減速させる方式だった。
現代の空母に採用されているのは横索式のアレスティングワイヤーである。 - アメリカで1911年に装甲巡洋艦「ペンシルバニア」*13を使って行われた史上初の着艦テストでは横索式だったが、連続して使用するには技術的な問題があり、「英国式」の縦索式が先行していた。
- 横索式のアレスティングワイヤーでは、高速で進入してくる機体を受け止められるだけの耐久性と、ワイヤーを張る装置に負荷をかけないだけの柔軟性を維持しながら、機体を減速・停止させなければならず、技術的難易度が縦索式に比べて高かった。
- 横索式が実用的になったのは1927年にフランスの空母「ベアルン」で採用されてからである。
- 縦索式は艦載機の進入方向に対して平行、つまり艦の前後の向きにワイヤーを張り、艦載機に櫛のような装置を付けることで、摩擦によって徐々に減速させる方式。(鳳翔の場合は縦に108本のワイヤーを張っていた)
- 縦索式では艦載機を減速・停止させるのを、ワイヤーと機体側の装置との間の摩擦抵抗に頼っているため制動性能(ブレーキ能力)が低く、横滑りしやすいという欠陥がある。
- さらにこの方式の場合、着陸の方法として前輪を先に着地させる「2点着陸」を要求され、これも不安定さの一因になっていた。
横索式の場合は「3点着陸」という前輪・尾輪が同時に着地する方法が一般的で、こちらは比較的安定性が高い。 - 鳳翔ではこの縦索式制動装置に加えて、ワイヤーを張る装置を兼ねた高さ40cm程の展開式の段差(当たると倒れる)が進入方向直角に複数設置されており、これにぶつかることでさらに減速させようと言う目論見だったが焼け石に水状態。
- 開発者である英国海軍でも止まれなかった場合の対策は考えていたが、その方法は「甲板に建てた柱に飛行機をぶつけて止める」というとんでもない代物だったためパイロット・飛行機の被害が多発。
結局1926年にこれらの制動装置をすべて撤去し、1931年にフランスから横索式を導入するまで、イギリスの空母ではなんと「着艦してきた飛行機に整備員がとびかかって押さえつける。」というやっぱりとんでもない方法で停止させていた。
流石英国。
- 開発者である英国海軍でも止まれなかった場合の対策は考えていたが、その方法は「甲板に建てた柱に飛行機をぶつけて止める」というとんでもない代物だったためパイロット・飛行機の被害が多発。
- さらにこの方式の場合、着陸の方法として前輪を先に着地させる「2点着陸」を要求され、これも不安定さの一因になっていた。
- この様に着艦制動装置が未熟であったにも拘らず、なんと飛行甲板前部が長い下り坂になっているという鬼畜仕様だった。当時は艦上機用のカタパルトが無かったため、初期の発艦は下り坂の滑走台を使っており、同じ発想であった。
- かなりの余裕をもって着艦しないと重力に従って海面へ、頭から滑落する羽目になる。
- 前述の大き過ぎる艦橋、未熟な着艦制動技術、飛行甲板前部の下り坂とが相まって、就役したての頃は発着艦(特に着艦)の難度が、非常に、極めて、現代では到底考えられない程に高かった。
なんと初めて着艦できた者に三菱が賞金を出したほど。これぞホントのほうしょう(褒賞)金。- 賞金は1万円(10万円との記述も)。当時一流大学卒の初任給が80円の時代にこれだけの賞金を出すあたり、いかに難度が高かったかが窺える。
獲得したのは三菱がテストパイロットとして雇っていた元英海軍大尉ウィリアム・ジョルダン氏。
初成功は大正12(1923)年2月22日*14であった。 - 帝国軍人初については、鳳翔航空長の吉良俊一海軍大尉が翌月3月16日*15に達成。
またこのときのテスト機は鳳翔建造に合わせて開発された国産戦闘機「一〇年式艦上戦闘機」。
機体設計は英国ソッピース社から技術者を招き、エンジンはスペインのイスパノ・スイザ社のものを三菱で国産化し搭載した。- この快挙の直後、2回目の着艦テストに失敗。
制動索が引っかかり艦橋のある右舷側から落っこちた吉良大尉、着艦事故一号の記録ホルダーでもある。
東郷大将ら高官の環視下であわや大惨事一歩手前の状況となった。
ちなみに吉良航空長は無傷、機体を乗り換え3回目の着艦を成功、沈着さを賞賛されたんだとか。
- この快挙の直後、2回目の着艦テストに失敗。
- 賞金は1万円(10万円との記述も)。当時一流大学卒の初任給が80円の時代にこれだけの賞金を出すあたり、いかに難度が高かったかが窺える。
- あまりの着艦難度の高さに流石に思う所があったのか、日本海軍は後にフランスから横索式を導入し加賀でテストの後、国産化に成功。
前述の艦橋移設と併せて着艦難度の緩和に努めた。- しかしながら発着艦時の事故が無くなることはなく、大正終期にはついに悟りを開いた4代目艦長の小林省三郎大佐より専属救難任務艦の常設、すなわち「トンボ釣り」が具申され、航空戦隊の定員として駆逐艦を以て充てられるに至る。
第四の問題 : 起倒式煙突
- 鳳翔建造時、艦載機が着艦する際に排煙の気流が影響を受けるという事態が予想されていたため、これを排除すべく起倒式の煙突が採用された。
しかしこれといった効果が無く無駄に重かっただけで、復元性向上のため第四艦隊事件以後固定式に改められ、多くの空母も固定式を採用していった。 - 別の煙突絡みの失敗といえば、後部排気式を採用した英国の改装空母アーガス。
- 同じ改装空母の加賀がアーガスを参考にしたばかりに同じ轍を踏み、着艦に支障を来す、焼き鳥を焼くなど失敗。
これに比べれば小さい問題であったが・・・。
- 同じ改装空母の加賀がアーガスを参考にしたばかりに同じ轍を踏み、着艦に支障を来す、焼き鳥を焼くなど失敗。
第五の問題 : 未設置だった航空機用燃料タンク
- 空母には自分用の燃料タンクと、搭載する艦載機用の燃料タンクの二つがあるのが常識。
- 通常は防御面への考慮から、艦船用の燃料タンクのすぐ隣に航空機用の燃料タンクが設置されるのだが、鳳翔は船体が小さくスペースが無かったため、航空機用燃料タンクを設置することができなかった。
- このため鳳翔では、航空機用燃料を石油缶に詰めて艦内に保管していたという。
- 鳳翔の第十六代艦長で後に連合艦隊参謀長を務めた草鹿龍之介氏によれば「鳳翔艦内へはライターすら持ち込み禁止だった」とのこと。
店内は禁煙ですよ
- 鳳翔の第十六代艦長で後に連合艦隊参謀長を務めた草鹿龍之介氏によれば「鳳翔艦内へはライターすら持ち込み禁止だった」とのこと。
- RJや瑞鳳と同じくらいある部分が足りないのはおそらくこのせいだろう……*17。
- あまりの足りなさからか、対空兵器を満載して局地用防空艦にする構想まで湧きあがったが没になった。
詳しくは天龍の項を参照して欲しい。
成功点 : 着艦指導灯
- ここまで数々の問題点を挙げてきたが、失敗ばかりしていた訳ではなく、「着艦指導灯」というパイロットの目視だけで最適な降下角度で降りているかどうかわかる、便利な装置が取り付けられていた。当時はフランスや日本が導入していた。
- 第二次世界大戦中、イギリスやアメリカでは降下の誘導を誘導員の判断で行っていたが、当然技量によって差ができてしまい、着艦事故の元となった。
- この装置は第二次世界大戦後各国が導入し、改良された「ミラー・ランディングシステム」は超音速ジェット艦載機が主流の現代でも艦載機の着艦に無くてはならない装置となっている。
武装 : 軽巡並みの砲火力
- 詳細は上記の諸元を参照してもらいたいが、特筆すべき点として竣工当時50口径三年式14cm単装砲を飛行甲板下に片舷2門ずつ、計4門を装備していた点が挙げられる。
- これは搭載数だけで言えば、当時の最新鋭軽巡であった天龍や龍田の主砲門数に並ぶ砲火力。
ただ、天龍型が片舷に4門とも指向可能なのに対し、鳳翔は片舷2門なので実際は天龍型の半分の火力となる。 - 「何故空母に軽巡並みの砲火力を?」と思うかもしれないが、これは設計当時、空母でも敵艦艇と直接交戦する可能性があると考えられていたため。
- 空母黎明期に空母の主任務として想定されていたのは、それまで主に軽巡が担っていた偵察・索敵任務。
当時まだカタパルトが開発されておらず、当然水上機運用も出来なかったため、偵察・索敵は軽巡が単艦で主力艦隊の前に進出し、目視で行うものとされていた。
そのため偵察任務中に、敵側の偵察艦とサシで直接砲火を交えるということも当たり前。 - 空母にもこれと同じ様なことをやらせようとしていたため、「最低でも自衛のための砲火力は必要だよね!」という事で、空母にも軽巡と同等の砲火力を持たせるのが当時の流れだった。
- 「商売道具の飛行機を持っているのになぜわざわざ艦砲を?」と思う事なかれ。当時の航空機は航続力も搭載量も貧弱な上に夜間や悪天候では危険すぎてそもそも飛べず、そう都合よく好転の日中でばかり敵艦と遭遇するはずもないので、自衛のためにも砲兵装は必要だったのだ。
- 上述のイギリス海軍空母「アーガス」や「ハーミーズ」も軽巡並みの砲火力を搭載しており、鳳翔や赤城、加賀では彼女らに習う形で当時の軽巡と同等、あるいはそれ以上の砲火力を搭載している。
- 空母黎明期に空母の主任務として想定されていたのは、それまで主に軽巡が担っていた偵察・索敵任務。
- この砲は1942年の10月に撤去され、代わりに25mm連装機銃が2基設置されている。
- ちなみに竣工直後の赤城と加賀は、船体が巨大で余裕があった事もあり50口径三年式20cm連装砲を三段甲板の中段に2基4門、同単装砲を舷側飛行甲板下に片側3門ずつ装備していた。
- これは搭載数だけで言えば、当時の最新鋭軽巡であった天龍や龍田の主砲門数に並ぶ砲火力。
戦歴 ― 鳳翔の戦前、戦中、戦後
- 昭和3年の仮編時と、昭和4年の正式発足時の第一航空戦隊の最初期メンバーを赤城とともに務める。
「航空戦隊?…航空部隊とは違うんですか?」- 昭和7(1932)年、加賀と連れ立って第一次上海事変に派遣、下駄履きでは無い艦載機を運用する艦として初陣を迎え、所属する第三艦隊の航空機隊は帝国海軍航空機初の撃墜スコアを挙げた。
「これは、演習ではなくて実戦よっ!」「…流石に、慎重に攻めたいところだわ」- 昭和7年2月5日の上海沖の花鳥山島北方で鳳翔航空隊が最初の撃墜戦果を挙げたとされるが、結果的に撃退、墜落したものの、公式には撃墜とされていない。
鳳翔戦闘機隊3機が敵戦闘機隊9機と交戦、うち1機に致命傷を与えるも逃げられ、初撃墜を逃した。
なおこの致命傷を受けた1機は辛くも帰投が叶ったが、修理せずに別のパイロットが乗り込んでしまい、離陸直後に墜落したという。
これは偵察爆撃機の護衛任務中の会敵として、爆撃任務の付随戦果として評価されるに留まっている。
「少し大袈裟ではないでしょうか?」 - 公式な初撃墜の確定戦果は2月22日の加賀航空隊の生田隊のもの。。*18
「みんな優秀な子たちですから」 - このあたりはアメリカにイチャモンつけるついで、一連の戦闘で戦死者を出した加賀に華を持たせたい軍令部の意図*19が透けて見えなくもない。
- この血生臭いドサクサの真っ只中、鳳翔新聞なる艦内新聞が創刊されている。しかも日刊。
??「…気になるんですかぁ?いい情報ありますよぉ?」 - 昭和7年のこのとき、13式艦攻が魚雷や爆弾、増槽の任務転換にあまりに時間がかかりすぎる、海戦になったらどうなるのかと鳳翔から航空本部にクレームがついた。だが航空本部はこれを黙殺、それから10年後にどうなるかの答えがでたのであった。
- 昭和7年2月5日の上海沖の花鳥山島北方で鳳翔航空隊が最初の撃墜戦果を挙げたとされるが、結果的に撃退、墜落したものの、公式には撃墜とされていない。
- 第一次上海事変後~日中戦争時の一航戦メンバーは赤城、加賀、龍驤、そして彼女であり、赤城、加賀、龍驤&お艦の3組で一航戦・二航戦・予備戦力のローテーションを回していた。
- 昭和7(1932)年、加賀と連れ立って第一次上海事変に派遣、下駄履きでは無い艦載機を運用する艦として初陣を迎え、所属する第三艦隊の航空機隊は帝国海軍航空機初の撃墜スコアを挙げた。
- 1941年9月12日に軍令部が内示した『昭和17年度海軍戦時編制』では「秋月」「照月」「初月」ら三隻からなる第二十五駆逐隊と鳳翔、それに特設航空母艦(商船改造空母)2隻で第七航空戦隊を編成予定だった。
が、編成前に太平洋戦争が勃発したため立ち消えとなってしまった。 - 太平洋戦争開戦時は第三航空戦隊に所属。瑞鳳・三日月と組ませることで、当時の三航戦を再現できる。
開戦後は長門ら主力戦艦と共に桂島に停泊していたが、最初の任務として真珠湾攻撃から帰投する南雲機動部隊を出迎えるべく主力戦艦らと共に出撃する。- 艦長の梅谷薫氏の証言では、この時の鳳翔の任務内容は対潜警戒。
- 日本近海までは佐伯を基地とする各航空隊が行い、それ以降は鳳翔の出番だった。
艦隊が反転し帰還コースに入った日の午後、小笠原群島の南西を航行中、鳳翔は艦隊右後方に位置し対潜哨戒を行っていた。
搭載機を全機出撃させていたがスコールが幾度となく襲い、それを避けているうちに艦隊からはぐれてしまう。
夕闇が近づき、スコールが激しくなる中艦載機の収容を進めるが、最後の1機が着艦する頃には機が中々着艦コースに入れいないほどの荒天になってしまう。何十回も進入を繰り返して漸く着艦した頃には艦隊から大きく外れてしまう。
迷子の子供を探しているうちに自分が迷子になるオカン、いるなあ…。
連合艦隊司令部も鳳翔の所在がつかめなくなり、連合艦隊参謀長の宇垣纏は「そんなばかげたことがあるか」とあきれている。 - 艦隊から500浬も離れてしまい、荒天で起倒式の通信アンテナをもぎ取られた鳳翔は、友軍に所在を教えられないまま、2昼夜も遅れて漸く豊後水道までたどり着く。
入泊の支援のため駆逐艦「早苗」(艦これ未実装)がやってくるが、何を勘違いしたか周辺に敵潜水艦を発見と通報。ダメだ!!
誤認だったのだが、周辺から掃海艇が何隻もやってきて爆雷攻撃するわ、飛行機まで飛んでくるわで大騒ぎとなる。 - この大騒ぎの中で行われた伝言ゲームの末に、呉では「鳳翔撃沈」の噂が流れたりしていて、艦長は連合艦隊参謀から冷やかされる羽目に。
煙草盆で喫煙していたら山本長官から「水戦司令官となった気分はどうだった」とからかわれるなど、太平洋戦争緒戦の鳳翔の出撃はピリッとしないものに終わった。
- 日本近海までは佐伯を基地とする各航空隊が行い、それ以降は鳳翔の出番だった。
- 艦長の梅谷薫氏の証言では、この時の鳳翔の任務内容は対潜警戒。
- 開戦後の初出撃での騒動後、三航戦は内地に居続けていたが、1942年2月上旬、米機動部隊はマーシャル諸島を襲撃すると、本土への奇襲を警戒した海軍は第一艦隊を中核とした警戒部隊*20を編成、3月中旬に警戒出動したりもしたが、航空機輸送任務に従事する瑞鳳をよそに、鳳翔は引き続き本土に居続ける事になる。
- 実戦空母としては1942年6月のミッドウェーへの出撃が最後。
- ミッドウェー海戦後、1943年1月15日附けで龍鳳の他、駆逐艦夕風、鹿屋海軍航空隊、築城海軍航空隊と共に第五十航空戦隊を編成する。
- これ以降鳳翔が前線に出ることは無く、内地に留まって練習空母としての運用がなされる。
- 背負っている矢を見ると、他の空母と違いオレンジ色に塗られているのはこのせい。通称「赤蜻蛉」と言われる練習機の色である。
- ミッドウェー海戦で壊滅した機動部隊を再建するべく、1942年7月14日に翔鶴瑞鶴を基幹とした第三艦隊(六代目)が編成され、この艦隊への搭乗員補充を鹿屋、築城の両航空隊が担当することになっていた。
- 第五航空戦隊から一気に数字が飛んだが、これは第五十航空戦隊が艦載機搭乗員を育成するための練成部隊であるため。
- 編成当時、龍鳳は横須賀で入渠中であったため、1943年3月20日に龍鳳が復帰するまでは一人で搭乗員の育成を行っていた。
また6月12日からは、被雷損傷して修理に回された飛鷹の代役で龍鳳が第二航空戦隊へ編入されたため、またしても一人で搭乗員育成をする事になった。
- 編成当時、龍鳳は横須賀で入渠中であったため、1943年3月20日に龍鳳が復帰するまでは一人で搭乗員の育成を行っていた。
- 編成時の司令官は、鳳翔の第十五代目艦長を務めた酒巻宗孝少将。
- 同年5月10日には酒巻少将に代わり、やっぱり鳳翔の第十七代目艦長を務めた城島高次少将が司令官に着任する。
- これ以降鳳翔が前線に出ることは無く、内地に留まって練習空母としての運用がなされる。
- しかし度重なる激戦と、1943年11月2日から11日にかけておこなわれたろ号作戦(ブーゲンビル島沖航空戦)で第三艦隊の艦載機隊が壊滅。
- 艦載機を失った所属空母達が内地へと戻って来たため第五十航空戦隊は1944年1月1日附けで解散。
鳳翔は夕風、築城海軍航空隊と共に第五十一航空戦隊へ編入され、基地航空隊を中心に搭乗員育成に務める事となる。
が、それからいくらもしない同年2月15日に夕風と共に第五十一航空戦隊から除籍。
連合艦隊附属として空母艦載機の搭乗員訓練任務に復帰する。
- 艦載機を失った所属空母達が内地へと戻って来たため第五十航空戦隊は1944年1月1日附けで解散。
- 1944年の春には、新型艦載機に対応するべく大改装が施される。
- 実は鳳翔さん、上述の通り小柄なため飛行甲板が短く、新型の艦載機を飛ばすのにとても苦労していた。
- 就役した頃の艦載機といえば発艦距離が10m程度と短い、軽量の木製複翼機。
重量があり、長い滑走距離が必要となる全金属単葉機なんて物は無かったから仕方ない事と言えるが・・・。 - 実戦では九六式シリーズまでしか運用しておらず、実は零戦を乗せたことが無かった。
- 就役した頃の艦載機といえば発艦距離が10m程度と短い、軽量の木製複翼機。
- 大改装第一弾は飛行甲板の延伸。
船体は延伸せず、飛行甲板のみを強引に延伸してギリギリ天山は飛ばせるようにした。 - 大改装第二弾は着艦制動装置の更新。
「三式一〇型着艦拘束装置」や「空廠式三型滑走制止装置」といった最新型の着艦装置で近代化改修を受け、開戦当初の翔鶴、瑞鶴に勝り*26新型正規空母達と同等以上の着艦能力を得た。
「私には・・・少し大袈裟ではないでしょうか?)」- このため、日本初の着艦を成し遂げた時の縦索式制動装置からフュー式制動装置、萱場式制動装置、呉式制動装置、三式制動装置と、日本で採用されたほぼ全ての着艦装置を装備した事になる。
特に最後の改修では後部の呉式制動装置を残したまま中央部を三式制動装置に改造したおかげで、九三式中間練習機から流星に到る当時運用されていた全ての艦上機を受け入れる事が可能な唯一の存在であり、彼女以外にお艦の名に相応しい艦娘は居ないであろう。 - また発艦に関しても、風が強く、かつ甲板後部より少数機での発艦という条件付きだが知らない子や軽装備の流星でも運用が可能。
特TL型の艦上機に用いる予定であった補助ロケットを使えば過荷重状態でも発艦可能と計画されていた。 - 特TL型と言うのはタンカーに飛行甲板を装備した、輸送任務もこなせる護衛空母。
と言うとあきつ丸を連想しがちだが、どちらかと言えば発想は速吸に近く、速吸に全通甲板を装備したような物と言えば理解し易いかもしれない。
一型から四型まであり搭載機数は10~15機、飛行甲板長は125~150m、速力13~18ノットと、その能力はタイプによって異なる。
しまね丸や山汐丸などが有名。
通常の使用機材は三式指揮連絡機(対潜)や九三式中間練習機で、着艦装置の充実した鳳翔とは違い、通常の艦上機は補助ロケットを使用すれば発艦だけは出来るという代物である。
- このため、日本初の着艦を成し遂げた時の縦索式制動装置からフュー式制動装置、萱場式制動装置、呉式制動装置、三式制動装置と、日本で採用されたほぼ全ての着艦装置を装備した事になる。
- これらの大改造でなんとか新型機に対処できるようにはなった。
- スペック上は、アメリカのカサブランカ級護衛空母やイギリスのコロッサス級護衛空母と同等になったが、米英では空母用の油圧カタパルトが実用化されていたため、無理なく大重量の新型機を発艦させることが出来、こちらは実戦空母として運用された。だがカタパルトは万能ではなく機体が発艦していく度にいちいち大重量の機体をカタパルトに設置するのは骨が折れる上時間が掛かりすぎるので、どちらかと言えば飛行甲板面積の都合上離艦に使える距離が短くなってしまう先頭の機体をカタパルトに設置して発艦させ、その後は普通にカタパルトを使わず発艦させていた。また、軽量な機体を好んで使う護衛空母も存在した。
- しかし、元々船体が小さく飛行甲板の延伸にも限度があり、また速力も低いため当時実戦配備されていた全ての艦載機を問題なく飛ばせたわけではなかった。
詳しくは飛鷹のページの小ネタ欄を参照して欲しい。 - 無理やり伸ばした飛行甲板のせいで外洋航行能力を失い、これ以降は前線に駆り出されることなく瀬戸内海に浮かび続けた。
- 実は鳳翔さん、上述の通り小柄なため飛行甲板が短く、新型の艦載機を飛ばすのにとても苦労していた。
- 1945年4月20日には長門らと共に第四予備艦(≒解体待ち)となり、他の艦と同じく迷彩柄で、島に見せかける偽装が施された。
- 偽装のハリボテで飛行甲板は使用不能となったため、練習空母としての運用も中止され、挙句には大事な艦長まで退艦。
書類上居るだけになってしまい、実質、艦としての運用が出来なくなってしまった。 - 実の所この時行った偽装はほとんど意味がなく、特に呉近辺にいた艦はすぐに米軍に捕捉され、その正体を暴かれてしまうことになる。
・・・のだが、鳳翔さんは比較的正体不明の期間が長かった。- 米軍資料によると、少なくとも1945年5月末までは正体不明艦だったようだ。
偵察の目を掻い潜り、ついに捕捉されたのは同僚達から遅れること、5/28。
「Ship believed to be unidentified CVL seen at Beppu Wan 27 April 1945.Heavily camouflaged.(1945/4/27に別府湾にて発見した正体不明の軽空母と思われる船。厳重にカモフラージュされている。)」
とのことで、情報分析に負荷を与えている。
このときの米軍の分析は600~620ft(約180m)級とのこと。
曰く、「RYUHO and possibly HOSHO.(龍鳳と多分鳳翔。)」
…昭和19年の改装時に延伸した甲板のせいか、自信無さ気な消去法的結論を導き出したのは約1ヶ月後の6/27のことであった。
まぁ普通の船は1割全長が伸びたりはしない訳で。 - 4/27に何をしていたのかは不明だが、退任予定の大須賀艦長が別府湾を拠点とする海鷹へ転任を控えており、申し送りなどで2隻で別府湾に居ても不思議は無い。
瀬戸内海で稼働中のフラッシュデッキの生き残りは海鷹・鳳翔のほかは何隻かの揚陸船で、米軍は海鷹を捕捉済なので、揚陸船と誤認された可能性もある。 - ちなみに当時の別府湾は連合国の機雷散布と機動部隊の攻撃機で制空権、制海権ともに喪失しており、前日に病院船の高砂丸が機雷を引っかけたりと危険極まりない状況であった。
- 余談だが、後日海鷹も触雷により被撃沈の危機に陥ることになるが、巻雲をして「ムリゲー」と言わしめた空母の曳航を見事成功させ、犠牲を最小限に留めたのが駆逐艦夕風(艦これ未実装)。
日米開戦から鳳翔の護衛・トンボ釣りを務め続けた峯風型駆逐艦10番艦。
鳳翔の予備役送りで呉から別府湾に担当替えになっていた。 - 海鷹の排水量は約16,000トン、ホーネットの排水量は約20,000トンで4,000トンほど差があるが、最新鋭の夕雲型と老朽艦の峯風型の機関出力は1万6,000馬力も違う。
とはいえ巻雲の場合は敵勢力権下のソロモン諸島だったことも考えなければいけない。
- 米軍資料によると、少なくとも1945年5月末までは正体不明艦だったようだ。
- 偽装のハリボテで飛行甲板は使用不能となったため、練習空母としての運用も中止され、挙句には大事な艦長まで退艦。
- 1945年3月と7月の呉軍港空襲の際は、ほぼ無傷で燃料さえあれば実戦投入も可能であった為にマークされていた大淀や、比較的大型の利根、龍鳳が近所にいたこともあってか、ほとんど被害を受けることはなかった。
- 終戦直前には特別警備艦(浮き対空砲台)への艦種変更を受け、大破着底した利根らご近所さんからかき集めた25mm機銃と機銃員を偽装の周囲に配置して、防空要塞と化していた。
- 戦後は改装で無理矢理延伸した分の飛行甲板を撤去して外洋航行能力を取り戻すと、1946年8月まで復員輸送艦として約四万人の将兵と民間人を南方から日本へと連れ帰った。
- 復員船として訪れた先の一つシンガポールでは、艦尾を失った高雄が係留されたまま浮き事務所兼宿舎として残務整理にあたっていた。
そんな高雄へ鳳翔は入港のたびに日本酒、スルメ、沢庵、素麺など懐かしい日本の味を差し入れし、大いに喜ばれたという。
遠い異国の地で最期の時を待つ高雄にとっての、ささやかな「酒保鳳翔」であった。
- 復員船として訪れた先の一つシンガポールでは、艦尾を失った高雄が係留されたまま浮き事務所兼宿舎として残務整理にあたっていた。
- 全ての役割を終えてから9ヵ月後の1947年5月1日、大阪(日立造船・築港工場)にて解体完了。
娘達の生と死を見届けた「全ての空母達の母」は、一人静かに娘達の元へ旅立った。
その他 ― あんなことやこんなこと
他の艦娘との関わり
- 有名な「1號艦」の昭和16(1941)年艤装作業時の写真で、右端に見えている飛行甲板は鳳翔。極秘の存在であった大和を国内のスパイの眼から隠すためのカバーとして横付けされていた。
二次界隈において「やまほう」と呼ばれる類の物ははこれによる。- もちろん全然隠せていない。が、これは目立った砲を持たないお艦を側に置くことでスケール感を見誤らせ、特に主砲の諸元を推定させないのが主な狙いだったと考えられている。
- 2015/01/01発売の副読本「艦これジャーナル」の表紙はこの写真が元になっている。裏表紙で飛行甲板だけが右端にちらり。実に忠実。
- 更に忠実に表現するなら両艦の間のスペース、遠くに間宮さんがいたらよかったのだが……。
- 2013年10月23日のアップデートで実装された千歳の時報で
「午後七時。そろそろ晩ご飯ですね。鳳翔さんのお店に行ってみます?」
……まさかの居酒屋/小料理屋鳳翔が公式化。
鳳翔さんの人気は留まる所を知らない。- なお史実上の料理エピソードはというと、連合艦隊に所属していた頃に士官烹炊室に腕利きの料理人を配し、艦隊随一の烹炊係を擁していたとのこと。
夜食に寿司が出てきたかと思えば、翌日絶品のフレンチトーストが出たりと、和洋を問わず抜群の腕前だったとか。
- なお史実上の料理エピソードはというと、連合艦隊に所属していた頃に士官烹炊室に腕利きの料理人を配し、艦隊随一の烹炊係を擁していたとのこと。
映画出演
- 1942年12月公開の東宝の国策戦争映画「ハワイ・マレー沖海戦」製作時に同作スタッフが実際の鳳翔を見学している。
ちなみに、当時は海軍の協力を得られず一線級の空母は見学の許可が下りなかったため、当時既に旧式艦だった鳳翔だけが許可が下りたというエピソードが残っている。 - また1944年9月には瑞鶴と共に東宝の戦争映画「雷撃隊出動」に出演したが、この際には海軍の全面協力のもと、空母上でのロケも行われている。
さらに同映画では攻撃を受ける敵空母役としても出演、炎上中の黒煙を表現するため煤煙幕を盛大に噴き上げながら走り回る鳳翔の姿を見ることができる。
ちなみに艦内の撮影には瑞鳳も使用された。 - スタジオジブリの映画作品「風立ちぬ」にも登場。
ジブリ作品に登場した実在艦は彼女以外に摩耶などがいる。
イラストについて
- イラストのワンポイント柄の和服にタスキ掛け・胸防具無しの装いは、弓道における女性の礼射(改まった場で行う射)のスタンダードスタイル。
- これが許されるのは高段位(おおむね五段以上)の射手さん。
最先任空母である彼女らしい差別化と見る事が出来る。 - 男性の礼射は「肌脱ぎ」という、左肩を肌蹴る作法。祥鳳さんのアレである。
- これが許されるのは高段位(おおむね五段以上)の射手さん。
- 手に持つ弓は「塗弓」という戦闘用の弓と思われる。
- 現在弓道で用いられるのは南雲機動部隊の持つ「竹弓」で、これは焦がした竹ひご*27を束ねた芯材の前後に竹板を貼り、側面をハゼ*28で塞いだものなのだが…いかんせん使っている接着剤が、ニベという魚から採る水溶性の糊なので、このまま戦場に持っていくと雨や湿気でバラバラになってしまう。
- そこで、いわゆる「白木」の竹弓に麻糸を隙間なく巻き付け、漆で塗り固めた塗弓が、主に戦場で使われた。
白木の竹弓ほどの冴えはなく、重量も重くなるなど性能的には劣るものだが、耐久性に優れるため、本来は長年使い込んで冴えの鈍った名弓を「塗る」ことで保存性を高め、逸品を末永く使うという意味合いもあった。
彼女の塗弓も、そうして長年射込んできた名手の証なのかもしれない。
ちなみにこの塗弓に、装飾と更なる補強*29を兼ねて籐を巻いた弓が、今日でも流鏑馬や時代劇に登場する、かの有名な「重籐弓」である。
公式四コマ
- ファミ通のサイトで公開されている公式四コマ漫画では「全ての空母の母」のイメージが取り入れられ、空母寮の寮母さん的立ち位置。
- 初登場の第14話では手製の慰問袋が駆逐艦の子達に大人気という癒し系キャラとして登場。まさにお艦。
- バレンタイン話である29話では次のハロウィンに備えて慰問袋をたくさん作りためていたことが発覚。
やはり夜なべして作っていたのだろうか。
公式四コマ二巻のキャラ紹介では「趣味は裁縫」となっている。
- バレンタイン話である29話では次のハロウィンに備えて慰問袋をたくさん作りためていたことが発覚。
- 第16話では終始ご飯の献立を考えてたり、コマと角度によっては他の軽空母より頭一つ身長が高いなど保護者のように描かれたりしている。
何これ超和む。- ちなみに、献立を考える際に加賀を見て焼き鳥を、飛鷹を見て巻き寿司を思いつくなど無意識とは言え
ちょっとあんまり天然な所も披露された。
- ちなみに、献立を考える際に加賀を見て焼き鳥を、飛鷹を見て巻き寿司を思いつくなど無意識とは言え
- 初登場の第14話では手製の慰問袋が駆逐艦の子達に大人気という癒し系キャラとして登場。まさにお艦。
雑誌デビュー
- KADOKAWAが出版するアニメ雑誌「娘TYPE」11月号(2016年9月30日発売)の表紙に、赤城と手を握り合った鳳翔さんの描き下ろしイラストが採用された。
8620形蒸気機関車58654号機
- “鳳翔さんの同期”とされる蒸気機関車。当時の鉄道院が日立製作所に発注したもので、現在は鉄道省・日本国有鉄道を経た後身のひとつであるJR九州が所有、「SL人吉」などで運転されている。
- 艦娘の元ネタになった軍艦・艦艇と同時期に製造され、現存する鉄道車両は他にもかなりの数存在する*30のだが、中でも彼女が特筆されるのはいくつか理由がある。
- 保存鉄道として鉄道施設そのものから保存されているものではもっと旧い物もあるのだが、名目上は保存ではあるものの、VVVFインバータ世代の電車・気動車がかっ飛ばすJRの本線上を営業運転する資格を持っている蒸気機関車としては世界的にも最古の部類に入る。
- 昭和50年に一旦廃車となり、その後は静態保存とされていたが、ほとんどの蒸気機関車がSL終焉期のブームに乗った静態保存とは名ばかりの野ざらしにされる中、彼女は屋内展示かつボランティアによって良好な状態に保たれていた。
その後、北九州市のSL復活運動の後押しを受け、昭和62年、発足したばかりのJR九州に国鉄の後身として“返還”され、動態復活することが決定される。
翌年、整備を終えて車籍復活となった。 - 長年JR九州の努力によって運行が続けられていたが、当時は肥薩線で「SLあそBOY」として勾配線で主に運用されていたこともあり、確実に劣化が進んでいた。
平成17年になると台枠の歪みが酷くなり、DE10形ディーゼル機関車の応援を仰ぐものの、車軸焼損などが頻発、一旦は動態運転継続断念の決断が下される。
同年8月をもって運用を離脱したものの、JR九州は九州新幹線開業を控えて観光資源が欲しいこともあり、正式な除籍は行わなかった。 - その後の調査の結果、再び彼女に幸運が訪れる。日立製作所内に製造時の図面が現存しているのが発見されたのだ。
日本車両とサッパボイラによる大修繕が行われ、平成21年、営業運転再開の運びとなった。 - 同じ国でその国のために生まれ、片方は敗戦によって姿を消す運命となり、もう一方は命を永らえてまだ現存する。
彼女に本当に魂があるとしたら、一体何を思うだろうか。
ただひとつ言えることは、大日本帝国海軍も、日本国有鉄道も、等しく滅びたという事実である。- ……令和4年、新製100周年を記念する特別列車の運行とともに、令和5年度限りで本機の営業運転を終了するプレスリリースが発表された。聖地?巡礼を行う際は、くれぐれも周囲の人やJR九州職員の迷惑にならないように心がけること。
- そもそも、艦これがサービスインした時点で、比較的近年の技術で作られている電車ですら、鉄道会社の保守的な体質の象徴とされた、戦前の技術である釣掛式*34の最終盤グループだった、東武5000系*35・名鉄6750系*36がすでに消え、あれだけ国鉄停滞と、「面白みのない今どきの電車」という悪い意味のシンボルだった103系も大量廃車が進行している最中だった。艦これ初期からのプレーヤーの世代にとってはまさに「『鉄腕アトム』*37の世界を先取りした電車」だった営団6000系すら廃車が始まっていたのである*38。地方私鉄でも保守部品の入手の困難を理由に旧型車の淘汰が進み、762mmの簡易線以外から、釣掛式電車が消え去った時代が、まさに2010年代だった。
- 電気動力車まで追い出すとキリがないのだが、蒸気機関車に限って言えば、現在本線運用がある最古参の機関車は、JRに限定すると高名なC57形1号機だが、私鉄所属も入れると、「走る博物館」大井川鐵道所属機のC10形 8号機がある。彼女は綾波の月遅れ同期(昭和5年。『綾波II』4月30日就役・佐世保、C10 8号7月24日新製配置・大宮機関庫*39)である。このC10 8号もまた、綾波(II)に負けず劣らず波乱含みな経歴の持ち主で、大量生産されたC11形と軸重が異なる少数形式であったために国鉄では早々に廃車されるも、そのままラサ工業の貨物専用線へ、運転終了後は観光運転用に宮古市に譲渡、その後大井川鐵道に譲渡され、1997年に車籍登録と、流転しながらも一度も正式に静態化に移行したことがない(他にはC57 1号だけ。コイツは鉄道省→日本国有鉄道→JR西日本と経営母体が連続しているバケモン)経歴の持ち主である*40。
- 蛇足だが、令和5年早春イベントで実装された第百一号輸送艦、彼女と番号繋がりの国鉄101系とは、秩父鉄道1000形として転じていったグループのうちの本当に最後の1編成だった第1010編成が平成25年度(2013)いっぱいで営業運転終了・除籍と、わずか半年だけだが『艦これ』と接触した。
なお、101系はクモハ101形902号が現在、大宮の鉄道博物館に保存されている。101系は海軍以上にビンボーな国鉄の方針変更に翻弄された形式のひとつだが、大宮の彼女は「国鉄新性能電車」のトップバッター、旧形式モハ90系 モハ90503号として世に生を受けた後、「小田急ロマンスカーと言えばここからが花道」と言われる小田急SE車に対し、国鉄のメンツを背負って高速度試験に臨み、135km/hのレコードを出しながらSE車に一歩及ばなかった*41編成の1員である。ちなみに小田急のレコーダーである第3011編成は、営業運転終了後、保存も考えられたが、当時の経堂検車区にスペースの空きがないということで、解体されてしまった。101系を元にした技術で作られた、151系、153系、新幹線0系、そしてライバルSE車までもが、速く走ったほうがそれだけ速く消えていき、「所詮下駄電」の101系だけが僅かに引っかかったのである……
- ……令和4年、新製100周年を記念する特別列車の運行とともに、令和5年度限りで本機の営業運転を終了するプレスリリースが発表された。聖地?巡礼を行う際は、くれぐれも周囲の人やJR九州職員の迷惑にならないように心がけること。
- その名を「直接」受け継いだ船はいない。だが、神原タグマリンサービス保有の曳船や深田サルベージの海難救助船、さらには令和3年3月30日にJMU磯子で
進水した水産庁の2000トン型漁業取締船が『鳳翔丸』を名乗ることで今も名跡は続いている。
君死にたまうことなかれ
- 「やは肌のあつき血汐にふれも見でさびしからずや道を説く君」や近年では某SNSでの無双ぶりでお馴染みの歌人 与謝野晶子(1887~1942)の本名は与謝野志やう(よさのしょう)、同じく歌人の与謝野鉄幹と結婚する前の旧姓は鳳(ほう)で、つまり出生名が「鳳志やう(ほうしょう)」、本艦どころか幕末生まれの先代が現役バリバリの頃から既に擬人化(?)されていた、というこじつけが出来なくもない。
なお、彼女の戒名は
白桜院鳳翔晶燿大姉
といい、命日は『白桜忌』と呼ばれている。
旧態に挑み続ける一方で奔放な逸話も多かった彼女はやはり現実での鳳翔の擬人化(?)と言えないこともないのかも知れない。
この艦娘についてのコメント
- 鳳翔ってアナログ仕事は得意そうで提督から渡された書類を卒なく処理しそうだが、一方でデジタル仕事になるとパソコンの前でわけわからんことになってそう -- 2025-02-01 (土) 17:57:07
- 鳳翔さん「提督、インターネット壊しちゃいました……」 -- 2025-02-01 (土) 19:16:36
- クラッカー・ホーショー -- 2025-03-01 (土) 15:59:20
- ある漫画で弥生のお兄ちゃんが「インターネットという会社はない」とAIに教えていたのを思い出した(実際はそういう名前の会社もあるみたいだが) -- 2025-03-01 (土) 21:45:50
- 艦爆や艦攻、偵察機とかを戦闘機とか言うとお冠になりそうだけど鳳翔もDSプレイしている提督に「ゲームウォッチばっかりやってるんじゃありません」とか言いそう。あと機械に疎いネタは神風のイメージが強い -- 2025-02-01 (土) 21:09:58
- 家電製品は壊れても何でも右斜め45度での打撃で直せそう。 -- 2025-02-01 (土) 21:24:54
- 鳳翔さん「提督、インターネット壊しちゃいました……」 -- 2025-02-01 (土) 19:16:36
- 二月一日、ホウショウサンカワイイ -- 2025-02-01 (土) 22:14:08
- 鰯の頭も信心から・・・即ち柊鰯弾頭、深海棲艦は死ぬ。 -- 2025-02-02 (日) 19:49:47
- 1番最初に手に入れた空母系で、空母の攻撃力すげえってなった艦なんだけど、ソートすると下から3番目なのが謎 -- 2025-02-17 (月) 10:15:11
- まだ1-1で出ました -- 2025-02-27 (木) 22:05:26
- 3月1日。ホウショウサンカワイイ -- 2025-03-01 (土) 15:30:47
- ふと考えたのが史実では日本軍は一度完全解体となったが、もし戦後再独立を見越して一部維持の方針となってたら海上自衛隊初の空母として「航空護衛艦ほうしょう」が誕生することになったりしたのかな? 葛城と龍鳳は空母として損傷が致命的だし、古さを考えると戦力面よりドクトリン維持の目的が強そうだが -- 2025-03-01 (土) 21:37:03
- 野暮な言い方だが、政治的に厳しい気がする。日本最初の空母というメモリアルな名前だからこそ逆に敬遠につながるかも。近年は「あきづき」「まや」が対空重視護衛艦で名前が復活してたりするし、空母「かが」もいるのだし、例えば今だったら試験艦「あすか」のような試験的な任務に就く小柄な空母として「ほうしょう」の名前が出てくる可能性も考えられなくもない…かな?個人的な意見だが。 -- 2025-03-01 (土) 23:05:05
- 四月二日 ホウショウサンカワイイ -- 2025-04-02 (水) 01:47:10
- 提督に向かってなんだその鎖骨はけしからん -- 2025-04-14 (月) 05:29:57
- 弊害が認知されてサウナブームが一段落したあたりで乗っかるあたりお母んらしいといえばらしい -- 2025-04-15 (火) 07:09:28
- セクシー殺人スライディング鳳翔さん「バーニャ♀」 -- 2025-04-15 (火) 09:45:14
- 大和撫子って感じでよき -- 2025-04-28 (月) 22:44:45
- 鳳翔さん(の中の人)が本当に母になったのう…… -- 2025-06-08 (日) 12:21:53
- 空母の母だけでなく、人間の母にもなった。 -- 2025-06-08 (日) 23:13:07
- 名実ともにお艦となったとか目出度いのぅ -- 2025-06-09 (月) 00:00:04
- 鳳翔さんが新しいアニメ化・・・(違う) -- 2025-10-05 (日) 19:45:17
- 鳳翔さんも怒ったら提督から貰った指輪捨ててるのかな -- 2025-10-06 (月) 13:42:20
- Xで話題になってたやつで草 -- 2025-10-06 (月) 14:03:26
- 今後声も聞き納めになるかもしれないな… -- 2025-10-09 (木) 07:33:30
- 羽根つきしている姿の新規絵スタンディがリアイベ(横浜)で確認された模様。 -- 2026-01-03 (土) 12:44:11
