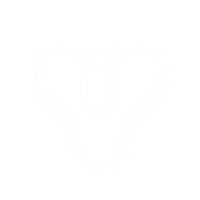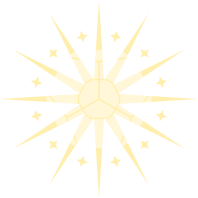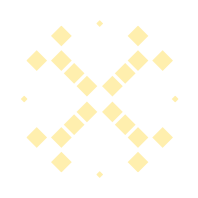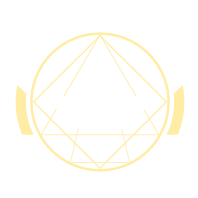▬
エヴァの旅
タワーの日常 
弓形に吊り上げられた眉は、多くを語っていた。
エヴァ・レバンテは無表情でいることに耐えらず、にやりと笑った。「要求は実にシンプルだったわ。ZIVA事件終結記念のシェーダーよ。でもザヴァラが提案した色は…」
彼女の付き添いが生地を持ち上げる。蛍光イエローと深紅という恐ろしい色の組み合わせで、ひときわ不愉快なその縞模様を見ずとも目が痛くなりそうだった。テスはため息をついた。「ハイヴを震え上がらせるほどの実力者だけど、デザイナーの作業場には近づけないほうがいい」
2人が笑っていると、振動がタワーを揺らし始めた。しばらくするとこれまでに聞いたことがないような音が遠方から鳴り響き、2人はそちらに向き直った。それは大きな音だった。
ラウンジとして使っている小さな部屋の中で放送が鳴り響いた。「避難命令77が発令されました。これは訓練ではありません。全住民は指定された避難エリアまで即座に移動してください」
テスがドアを開けようとした時、さらに近くで再び爆発が起こり、2人の足下を揺らした。廊下に煙と悲鳴が流れ込んできた。
これ以降のエヴァの記憶は途切れ途切れだ。彼女は空気を求めてテスと一緒に走った。シティに住んでいるいとこたちを心配し、彼らの名前を口にした記憶がある。その時すでにエヴァは人波に飲まれて前方に押し流され、テスは後方に取り残されていた。
再び爆発が起こり、防火扉が音を立てて閉じた。テスとはぐれたエヴァは、約30名の人々と一緒に、塔北部とガーディアンの間にある小さな貨物室の中にいた。1人の男が反対側にあるドアを開けようとして、封鎖されている、と大声で叫んだ。
すると、天井が崩落すると同時に、大きな球体がデッキに落下した。ポッドから這い出てきたカバルは、その分厚いアーマーのせいでぎこちなく、市民に向かって銃撃を始めた。
その時だった。彼らの背後で目も眩むようなエネルギーの爆発が起きた。その10人の男が叫んでいるかのような大きな叫び声が聞こえたが、エヴァがようやく見えるようになったときに目にしたのは、彼女の背丈ほどもある剣でカバルにとどめを刺そうとしている、1人の巨大なガーディアンだけだった。
ヘルメットをかぶったシャックス卿は部屋を見渡している。2歩ほど進んでエヴァの隣に立つと、驚くほどの優しさで、彼女を立たせた。
「マダム」と彼が話し始めると、エヴァはその低い声が胸に反響するのを感じた。「力を貸してほしい」
エヴァはその言葉に従い、市民たちの誘導を行い、先を行く彼に続いた。クルーシブル・マスターという強力な協力者を得た彼女は、すぐに皆を説得して集中させることができた。脱出地点に到着すると、3人のホークのパイロットが不安そうな面持ちで船と一緒に待機していた。
最後のグループが乗り込んでいる間、シャックスはその重たい手をエヴァの肩に乗せた。そして頭上から一言、「戦友よ」と言った。すると彼は巨大な剣を担ぎ、再び戦闘へと戻って行った。ホークがタワーから離れていく間、エヴァが見た最後のタワーの姿は、かつての面影を失い、炎に包まれていた。
光の喪失 
「ヴァレンティナと、息子のルイスよ! ペレグリン地区! 居住ブロック10の4階! そこに…」爆発により通信が途絶えそうになったが、彼女はできる限り大きな声で無線に向かって叫んだ。「そこにいるの、緑色の日よけが目印よ! お願い!」
通信相手である女性警備隊員の声からは動揺している様子が伝わってきた。「部隊を送ります! でも戦闘で辿り着けるかどうか――」
「私のタワー・アクセスコードを渡したでしょう」エヴァは自分の声に驚いた。まるで気の短い権力者のようだった。
通信相手は沈黙していた。「分かりました。私が行きます! オーバー」
エヴァは壁に再びもたれかかり、顔を上げて辺りを見回した。どうやら、ここはパン屋だったようだ。今では、小さなテーブルはドアの封鎖に使われていて、カウンターのガラスケースは反対側にある陳列台にぶつかって粉々になっている。
彼女に通信機を貸してくれた警備隊のエクソが、店の外の半壊した壁越しに再び何発か発砲した。エクソは彼女のほうを見て心配そうに訪ねた。「銃は使えるか?」
その困った表情を見て理解したらしいエクソは、通信機の方に手を伸ばした。彼女が床の上を滑らせて通信機を渡すと、エクソはすぐにコードを入力した。再び近くで爆発が起こり、他の部屋の住人たちが覚えて悲鳴やうめき声を上げた。
エクソは通信機に向かって叫んだ。「ガーディアンの支援を頼む、場所はアンカー地区1400ブロックの角だ! 多くの住人がいるが、身動きが取れない!」エクソは通信の終わりを合図するように、体を乗り出してさらに半ダースの銃弾を発砲した。カバルが獣のような咆哮でそれに応えた。
それから2分もしないうちに、エヴァの耳に音が届いた。全出力で移動しているスパローの音だ。彼女は勇気を振り絞って、半分身をかがめながら、建物の外を覗いた。ハンターとウォーロックの姿が目に飛び込んできた。2人の姿はまるで侵入者たちに降り立つ復讐の天使のようだった。彼らの身のこなしはプロフェッショナルそのもので、そこに慢心など見られなかった。2人の攻撃は効率的で強力だった。兵士たちは退却を始めた。
その時、何かが起こった。エヴァには何が起こったのか分からなかったが、ガーディアンたちがよろめいたのだ。まるで糸が切れたかのようにウォーロックは膝をついた。ハンターは頭を振り、片手を挙げた。光を呼ぶ合図だ… だが、何も起こらない。
カバルはこの時を待っていたかのように、いっせいに攻撃を始めた。ハンターは突進してきたセンチュリオンに吹き飛ばされ、踏みつけられた。ウォーロックは立ち上がることなく、大勢の兵士にハチの巣にされた。
あまりの出来事にエクソは呆然と立ち尽くしていた。エヴァがしゃがむように言うと同時に、エクソはスナイパーに撃たれ、倒れた。
恐怖のあまり、部屋の隅で吐きだした者もいた。エヴァに悩んでいる暇はなかった。彼女は地面に落ちた通信機を拾うと、住民たちを押しのけて反対側の窓に向かった。強化されたケースを使ってガラスを叩き割ると、大きな破片を窓枠から取り外し、子供たちをそこから避難させた。建物を最後に後にしたのは彼女だった。逃げる彼女を追うように、近くの壁を数発の流れ弾がえぐり取った。
彼らは振り返らずに走り続けた。彼女は自分たちが今どこの地区にいるか分からなかったし、辺りの建物にもかつての面影はなかった。いつもの通路や整備された大通りの大半が、瓦礫の迷路と化していたのだ。最後の希望であったシティは今や、崩壊した廃墟の迷路になっていた。
大人たちが静かに話し込んでいる間、子供たちは全員で肩を寄せ合っていた。常に誰かが泣いていたが、皆必死になって大きな音だけは立てないようにしていた。
突然、通信機から高音が鳴り響き、驚いたエヴァは思わず後ろの壁に頭を打ちつけてしまった。自分がまだ通信機を持っていると思っていなかったのだ。彼女は通信機を取り出すと、パッドに触れた。
押し殺した声が聞こえてきた。「もしもし?」
エヴァは低く落とした、驚くほど荒れた声で応えた。「こちらエヴァ・レバンテ。トッツィ?」
一瞬間が空く。「トッツィは死んだ。ただ、彼女からあなたに連絡するように言われた」また長い間が空く。エヴァは叫びたい衝動を抑えた。「申し訳ない。ミセス・レバンテ。ブロック10は消えていた。恐らく、戦闘が始まってすぐに自動防衛システムが起動し、司令船が墜落したんだろう…」
その後の言葉はエヴァの耳には入ってこなかった。
故郷に隠れる 
エヴァは胸元に抱え込んだ小さな通信機で時間を確認した。信じられないことだが、テスと談笑していた時からまだ2時間も経っていなかった。時間が、まるで暁旦の祭りで売られている伸びるキャンディーのように引き延ばされているようだった。彼女にとってテスと過ごしたのは数日前の出来事に思えた。そのさらに前、いとこの部屋でくつろぎ、ヴァレンティナにハグして、ルイスにお別れの挨拶をしたのは、いつだったろうか…
「エヴァ、彼らには何の借りもない」住民の1人がしわがれた声で言った。声の枯れていない者はいなかった。空気中に大量の灰が飛散し、誰もが喉を痛めていた。
エヴァは布きれを口に当て、咳き込みながら応えた。「冗談じゃないわ」その声には怒りが込められていた。「彼らのおかげで安全に暮らすことができたのに見捨てると言うの?」
論争の的は、倉庫の床に力なく横たわっていた。4人のガーディアンだ。全員が負傷し、派手なアーマーの隙間から血が流れていた。この小さな一団の未来を心配する一方で、彼らのファッションセンスには感心する他なかった。中でも洒落た格好をしていたのは、もちろんハンターだった。
彼女と言い争っている太鼓腹の男はファッションに興味がない様子で、質素で機能的な制服を着ていた。総意の同盟のものだ。彼はエヴァをにらみつけ言葉を絞り出した。「全員で移動するのがやっとなんだ、自分たちだけでも手一杯なのに、怪我をして力を失ったガーディアンを連れて行くなんて。なぜ危険を冒してまで――」
「彼らが何度、あなたのために命を危険に晒したと思ってるの?」エヴァは布きれを顔から外すと、灰まみれの痰を吐いた。彼女の母親が驚いて墓から蘇ってきそうな光景だ。「とにかく進むのよ、彼らと一緒に。耐えるしかない。この状況はあくまで一時的なものよ」
顔を歪める彼に構わずエヴァは続けた。「彼らが光を取り戻したら、きっと…」
エヴァの演説は通信機から聞こえてきたノイズによって中断された。それはエヴァが驚いて通信機を落としてしまうほど大きな音だった。強化ケースが通信機を守り、近くにいた人々にもザヴァラ司令官の低い声がはっきりと聞こえた。「シティの住民よ。心して聞いてくれ」
砂漠で水を求めるかのように、住人たちは通信機に近寄り、輪を作った。ザヴァラは生き残りたちにとって柱であり、希望の光だった。彼ならきっと…
「シティを放棄する。できる限り多くの人々を避難させているが、カバルが街のガーディアンを襲い始めた。移動できる者は、荒野に向かってくれ」エヴァはまるで殴られたかのような衝撃を受けた。
「カバルはトラベラーに細工をし、私たちと光を切り離した。シティを維持するのはできない。君たちを守ることもできない」長い間があった。言葉に悩んでいるようだった。ザヴァラが再び話し始めた時、その声にはかなりの疲労が感じられた。
「星系内に集合地点を設ける――放送を聞き逃さないでほしい。我々はいずれシティに戻ってくる、だが… それがいつかは分からない」また間が空いた。「無事を祈る。決して諦めないでくれ」彼の声はそこで途絶えた。
一団の中で叫んだりしたものは1人もいなかった。数時間とはいえ彼らがここまで生き抜くことができたのは、大きな音を立てなかったからだ。だが、彼らは涙を流した。灰に覆われた彼らの頬に、涙の跡ができていた。彼らは周りの人々と顔を見合わせ、誰もが今の状況を理解しようと努めていた。
エヴァは泣かなかった。彼女は通信機を見つめながら、ザヴァラの肩を思い出していた。彼女はよく、ザヴァラのアーマーの大きな肩当てのことを笑っていた。彼の左肩に取り付けられた保護プレートは実に巨大だった。そして今は… ようやく理解できたような気がした。彼が両肩で背負っているものの重さを…
エヴァが立ち上がると、皆が彼女に注目した。彼女は一瞬ためらった後、慎重に言葉を選んだ。「ほとんどのガーディアンが脱出する。彼らに協力しましょう」エヴァはガーディアンたちの方を示した。「彼らを生かせれば、きっと私たちを守ってくれる、そうすれば助かるわ」エヴァが皆を見渡すと、うなずいている人々の姿が見えた。
「どこに行くの?」1人の女性が訪ねた。
エヴァは再び通信機を見た。「カバルが今の通信を聞いていたかもしれない。私たちが逃げ出すと思って、壁を監視している可能性もあるわ」エヴァは部屋の外を見上げた。「だからここにとどまるのよ。シティの境界まで移動して、カバルに見つからないような場所を見つける」
彼女は通信機を拾い上げると、それを肩に掛けた。「皆、立つのよ。トワイライトギャップまでの道のりは長いわ」
新たな日常 
シティ郊外に向かうのは簡単なことではなかった。彼らは毎日、カバルの支配力が拡大していくのに直面した。住民の集団や少数のガーディアンたちが突破を試みては、血に飢えた船の大群に撃墜されていった。街はもう安全ではない。各地区の中心部では、隊列を組んだパトロール部隊と騒々しい戦車が行き交っていた。
長年ガーディアンのサポートを行ってきたエヴァは、彼らの雑談を耳にすることも多く、この恐ろしい侵入者たちについてよく知っていた。タワーで聞いた通り、彼らが単調かつ事務的に、ブロックを1つ1つ徹底的に調査していることがわかった。
エヴァたちは隠れながら観察し、カバルが調査を行っている時だけ移動した。そうやって慎重に動き続け、彼らはついにシティの奥地に辿り着いた。そこは大昔に放棄されていて、人類は壁に投射された影でしかなかった。
エヴァは毎日のように話し合いを行い、中心部に物資補給のためのパトロール部隊を派遣した。夕方は今後に備えた会議に時間を費やした。
幸い、夜は裁縫の時間をたっぷり取ることができたので、生存者たちが移動中に体を冷やさないようにいろいろと作ることができた。
回復した3名のガーディアン(ギャップに向かう途中でタイタンは死亡した)は、助言を与えてくれるようになった。生存者たちは彼らの提案に従い、2日以上同じ場所にとどまることはなかった。夜には必ず歩哨を立て、放送を聞くために1日置きに通信機の電源を入れた。彼らは連絡を待ち続けた。希望は捨てていなかった。
ガーディアンたちがザヴァラの声を聞いた時、エヴァは同じ部屋にいた。彼らはザヴァラの簡潔な声明を何度も繰り返し再生した。「この星系に残されている光よ… タイタンに集合せよ」
エヴァはドアを閉じ、他の住民が話し合いを耳にしないようにした。もう1人のウォーロック、タムは、トリンの姉妹であることを明かした。彼女たちは、この地を離れて、何らかの方法でタイタンに向かうべきだと考えた。たがハンターのラモスも頑として譲らず、ここに残るべきだと主張した。
話し合いが徐々に暗礁に乗り上げ、とうとう止まってしまった時、3名のガーディアンの視線の先にはエヴァがいた。彼女は両手を挙げると、「あなたたちが正しい選択をすると信じている」と言った。ガーディアンたちは残ることにした。そしてすぐに、彼らの「任務」に必要不可欠な存在となった。
それまでとにかく生き残るだけを考えてきたが、いつの頃からか皆で協力してシティから住民たちを避難させることが目的となっていた。物資回収部隊は、出発した時よりも人数が増えた状態で戻ってくるようになった。偵察部隊はシティの郊外を探索し、カバルの監視の緩い脱出経路をいくつも発見した。
エヴァは、タワーで休日を過ごすために活用していた能力が、この地下運動を動かすのに必要不可欠な能力であることに気付いていた。彼女は古い教室にあったボードを急いで集めてスケジュールを作成し、古い書類やチラシを活用して、住民たちや、時には光を失ったガーディアンのことを運び出した。
気づけばこれがエヴァの日課になっていた。彼女はアンダーグラウンドの裏方に徹した。計画を練り、行動し、裁縫を行い、それを繰り返した。ようやく奥地と連絡がつき、生存者たちをEDZに連れて行くことが最終目標になっても、エヴァは列車が計画どおりに運行できているかを確認していた。
彼女はいくらか思案した後、自分の役割を秘密にしておくように皆に頼んだ。テスのようなごくごく親しい相手に自分の無事が伝われば十分だった。エヴァがシティから出るチャンスは何度もあった。
だが、船団と一緒に行ける機会が訪れる度に、彼女は思いとどまった。エヴァは気を引き締め、自分の仕事を続けたのだ。
カバル大戦の数カ月間、エヴァ・レバンテはこのようにして過ごしていた。
大義のための戦い 
「…アブエラ? マダム?」
ほとんどささやきと言えるぐらい静かな声だが、エヴァを起こすには十分だった。ぼんやりした意識がはっきりするまでの束の間、彼女は自分がペレグリン地区にある自宅の居間に座っていると思った。大好きなアフガン犬がカウチの向こう端にいて、そばに立っているカルロスが彼女の顔をのぞき込んでいる… だが、のぞき込んでいる顔はカルロスではなかった。
ハンターのラモスが心配そうに彼女を見下ろしていた。アンダーグラウンドにやってくるガーディアンのほとんどが彼女を祖母のように扱う中、ラモスは何ヶ月も続いた戦争の間もずっとグループから離れずにいてくれていた。
彼の世話焼きぶりと来たら時には息が詰まるほどで、彼女は両目をこすりながらため息をついた。「起きてるわよ。今、何時?」彼女は寝ていた古いカウチの上で半身を起こし、横向きで寝たせいで絡まった髪を梳かしながら顔をしかめた。
「7時頃かと」彼の声は低く、ややおどおどしていた。
彼女は彼をにらみつけた。「1時間前に起こしてくれる約束でしょ」
彼は口をゆがめるようにして笑った。「睡眠が必要そうでしたので」
彼女は慎重に立ち上がり、おぼつかない足取りでよろよろと歩きながら、苛立った顔を見せないように顔を背けた。「みんな待ってるの?」
「先ほど着いたばかりです。それで起こさなかったんです。彼らはあなたがあと10分ほどは現れないものと思っているでしょう」彼は自分を正当化しているようだった。
エヴァは再びため息をついた。「ありがとう、ラモス。確かに私には睡眠が必要だった。昨夜はまた遅くまで起きていたから。すぐに行くと伝えてちょうだい」
「はい」彼は明るい声で返事をし、自信に満ちた軽やかな足取りで部屋から出て行った。
エヴァは建物の2階にある部屋の居住空間を出て、バスルームに足を踏み入れた。朝の日課は決まっていた。配給品の容器から栓をした流し台に水を注いで顔を洗い、できるだけ廃墟の中の半ば腐ったようなカウチで眠っていたように見えないように努めた。
彼女は鼻先から水が滴らせながら、目をつぶったまま顔を拭うタオル代わりの布きれへと手を伸ばした。目を開けた彼女は、自分が見知らぬ誰かを見つめていることに気がついた。
エヴァは子供の頃から痩せ気味だった。食事は全部きれいに食べなさいと、母親にたしなめられたことを今でも覚えている。今、自分を見つめ返す女性は明らかにやつれている。目の下はたるみ、髪の毛は乱暴に短く刈られ、着ている服ときたら! 襲撃の日に彼女が来ていた服は厳しい生活には全く不向きなもので、2週間も持たなかった。自分で縫って作った手製の服はタワーでは絶対にあり得ない代物だったが… ここではそれで間に合わせるしかなかった。トレードマークであるショールがまだ使えることだけが救いだ。それは良き時代を思い出させてくれる…
エヴァは居間に向かいながら、良き時代があったからこそ、グループが階下に集まっているのだと思いを巡らせた。アンダーグラウンドの全てのセル・リーダーが、重要な、しかも最後になるかもしれない会談のため、一堂に会したのだ。
アンダーグラウンドにとって、カバル大戦は見事な勝利だった。彼らは勝ったのだ。シティに残った民間人とガーディアンは、去りたがらないか、去れない者たちのみだった。エヴァは悲しみに眉をひそめた。
リージョンの襲撃によって、安全だと思われていたバンカーからガーディアンが追い出されたという話が、数週間に一度は入ってきていた。最初の襲撃、そしてその後数ヶ月に渡って大勢の民間人が犠牲になってしまった。
板で塞いだ窓の隙間から街を見下ろした彼女は、心に満足感が湧いてきたことを認めざるを得なかった。アンダーグラウンドがこれからすべきことは、撤退し、農場と人数が多いホーソーンのグループを目指すだけだった。エヴァは空っぽの街から視線を上げ、ゆがんで廃墟となったタワーの遠景を見た。
彼女はここに留まると決めていた。ラモスのようなガーディアンが時々様子を見に来てくれるし、誰かが後に残って明かりを灯しておく必要がある。街にはまだ生きている難民が残っていて、出ようとしているかもしれない。
彼女が窓に背を向けて階下に向かい始めると、アパートの前の通りで爆発が起き、エヴァの視界は真っ白になった。
最後の日 
エヴァは2分の間に2回頭を振り、自分がどこにいるのか理解しようとした。何の前触れも無かった。頭上にエンジンのうなる音が数秒間聞こえたかと思うと、大きな爆発が地下アパートの前の通りを切り裂いた。
爆風が彼女を人形のように地面に吹き飛ばした。全身が痛み、すぐ近くのどこかでカバルの兵士たちがしわがれ声で叫ぶのが聞こえた。ガーディアンの武器の射撃音が応えていた。誰かが悲鳴を上げた。
彼女は即座に、奥の隅のサイドテーブルに置いてあるショットガンのほうへよろめきながら向かった。3歩、4歩。武器を手に取り、構える。その時、アパートのドアが大きく開け放たれ、1組のサイオンが武器を構えて踏み込んで来た。
タワーの針子、エヴァ・レバンテなら驚いていただろう。さっき鏡の中で見たやせこけた女は、何ヶ月も武器の空撃ちをして過ごしていた。度重なる訓練によって行動できるよう鍛えられていたため、最初の1発で右側の1体の胸を捉え、部屋の外に吹き飛ばしたのだ。だが訓練では、銃の反動を体験できなかった。武器が跳ね上がった時、彼女は腕の中で何かが折れるのを感じた。
たじろいだおかげで彼女は助かった。意図せず横に回転し、もう1体のカバルの射撃を回避することができたのだ。彼女は大声で叫び、再び武器を構え、応戦の射撃で彼を反対側の壁に叩きつけた。
荒い息遣いの中、彼女は片手で武器を再装填し、耳を澄ませて待った。外からはもう何も聞こえなかった。下の階では激しい戦闘が行われていた。彼らを助けなければ。彼女はドアへ向かい、足を踏み出した。武器を持つ手を伸ばして…
ウォードッグがアパートの窓を突き破る音はまるで新たな爆発のようだった。エヴァが振り向くと恐ろしい野獣は横に避け、新たな1組がホバリングしている輸送機から小さな生活空間へと飛び込んできた。彼らは驚くべき優雅さで着地した。3組の飢えた目がエヴァを睨みつけた。3つの牙の生えた口が待ちかねたように唾液で床を汚した。
エヴァは撃った。
野獣は突進した。
世話人 
エヴァ・レバンテはツタに覆われた物置の外壁にもたれて立ち、奥地のサッカー場を見下ろしていた。古いネットがたるんでいる。張り直しが必要だ。付け替えるような訪問者は誰もいなかったし、今の奥地の住民はスポーツを好むようなタイプではない。
サッカー場の向こうはヨーロッパ・デッドゾーンのゆるやかな丘陵地帯で、地平線には、捻じれたトラベラーの破片が見える。アパートでの攻撃から持ち直しつつあった最初の数日、彼女はその光景を不思議な気持ちで見つめていた。
今、彼女は雲が所在無げに乱れて破片の周辺に集まるのに退屈していた。エヴァは微笑み、壁にもたれるのをやめて彫刻された杖に体重を預けた。考えてみれば、あれだけのことが起きた後なのに、退屈するだなんて。
奥地での最初の数日は、到着するなり外で迎えてくれた看護助手たちによる慌ただしい医療処置の繰り返しだった。それはシティを取り返すための大規模な作戦、カバル大戦の最後の日々だった。
地下から来た年配の女性の優先度は低く、混乱の中では彼女が会いたいと願っていた旧友でさえも彼女を見逃した。
今の彼女は1人だった。いや、ほぼ1人だった。彼女は振り向きクリプトアーキのタイラ・カーンが奥地の郵送フレームと雑談をしているのを見た。活動拠点がシティに戻ったことに伴い、ダルビーはタイラの研究助手のような存在になっていた。彼らは共にデッドゾーンのレンズを通して人類の歴史の詳細な調査を続けていた。タイラはタワーでの混乱から生まれたこの仕事ができることをこの上なく喜んでいるようだった。
折に触れて偵察のデヴリムも雑談しにやってきた。彼は時折この小さなグループのことを大胆にも「ベテランクラブ」と呼び、紅茶を飲みながらニヤリと笑うのだった。
当然、2人ともまだやるべき仕事があり、その役割を非常に真剣に受け止めていた。
エヴァは決して、公式に奥地に滞在しているわけではなかった。タワーにおける彼女の役割は本部にとって重要なものではなかったとはいえ… 彼女に急いでマーケットに戻るよう頼みにくる者がいなかったのだ。時々、テスとバンシーが訪れ、彼女は新たな拠点を立ち上げる方法についてアドバイスをした。
だが、エヴァは失われたものために奥地にいるのだ。
彼らは数人ずつ、トボトボとやってきた。彼らに共通する点は、破片とつながりを持っていないことだ。彼らは座って、遥か遠くのそれを見つめる。そして力を失ったガーディアンとしてカバル大戦がどれだけ過酷なものだったかを語った。何人かは文字どおり傍観者にならざるを得なかった。
光が戻った時、そのうちの何人かが違うように感じると言った。まるで、体に合わなくなったスーツのように皮膚の下に存在しているようだった。
小さなエクソの女性が、特にエヴァの印象に残った旅人だった。そんなに小さなエクソが作られているとも思わなかった。その女性は落ち着きがなく、話しながら動き回り、びくびくとしていた。
多くのガーディアンと同じように、光に違和感があると言うので、エヴァはいつもしていたように同じ質問を投げた。「つまり、光が変わったということ? それともあなたが?」
エクソは止まり、目を細めて考えた。彼女は奥地に到着してから初めてじっとしていた。
この繰り返しだった。質問を投げかけるだけで落ち着くこともあれば、中にはもっと時間がかかる者もいた。時にはエヴァと同じように破片を見上げながら数週間も奥地に留まることもあった。
何人か… 何人かは奥地へ来ても答えが見つからず、地平線上の巨大な目印に向かって歩いて行った。エヴァが知る限り、そのうちの誰1人として、奥地に戻ってくる者はいなかった。
奇妙な生活だった。決して彼女が願ったものではない、新たな奇妙な時間、新たな奇妙な役割。だが、彼女はそれが得意なことに気づいた。
そして、エヴァ・レバンテはシティへ戻る気がなかった。
目に見えない傷 
エヴァの小さな部屋にある通信ユニットが、彼女を安眠から目覚めさせるには十分な大きさで甲高い音をたてた。エヴァはこの小さな離れにデッドゾーンから拾って来た布と芸術品を飾りちょっとした生活空間にしていた。だが、この頃急に目覚めると、自分が一瞬どこにいるのか思い出せないことがあった。
彼女はうめきながらベッドから這い出し、近くの家具に掴まって身体を安定させた。ウォービーストによる傷は広範囲に及んでいて、彼女は今もブレイ・テクノロジーが骨と腱を接合しなおした脚にこわばりを感じていた。
彼女は通信ユニットの前にある小さなイスに腰をおろした。スクリーンが部屋を照らしていたが、それ以外はほぼ完全な暗闇だった。テス・エベリスのイメージが自動的に映し出されると、彼女はぼんやりとユニットを見つめた。シティの昼間の日差しの中で、テスは仕事のために完璧な服装をしていた。
「今何時だか分かっている?」エヴァは苛立ちをにじませながら尋ねた。
「分かってはいるけど」テスの声の何かがエヴァの気を引き、姿勢を正して観察させた。テスの顔はこわばっていた。彼女は… 怯えているようだった。
「テス、一体どうしたの? 大丈夫?」エヴァの意識はすっかり覚醒して、鴨の羽色のローブの端をぐっと引っ張り、自分の身に引き寄せた。突然、寒気を感じたのだ。
「ごめんなさい。ただ… すぐに知らせたかっただけなの。タイラは今頃ラフールから連絡を受けているはず」テスは視線を落とし、遠くを見てから再びカメラを見上げた。「ケイドが死んだの。昨日リーフで何かが起こった。詳しいことは全く分からないけど、みんなその話をしている」
エヴァは心配そうに口元をきつく結んだ。彼女は決してハンターバンガードを好いてはいなかったが、多くの人が彼を尊敬している。頼っている。そして、ケイド6を殺せるだけの力がある者がいるとすれば… 「リージョンの仕業?」
テスは首を振った。「まだそういう話は出てないわ」エヴァは通信を初めてから初めて彼女はかすかな笑顔を浮かべた。「でもあくまで噂だから、何だってあり得るわ」
エヴァは険しい表情で椅子に背を預けた。「お気の毒に。彼を気に入っていたものね」テスはごまかすように肩をすくめた。「そんな振りはやめて。ついこの間市場でそんな話をしたばかりよ」
テスはやめると、悲し気に頷いた。「追悼式があると思う。こっちに戻れる?」
今度はエヴァがスクリーンから視線を外す番だった。誰かが彼女に戻るよう頼むのはこれが初めてだった。それも、あろうことか葬儀のために。エヴァは何かを口実に断ろうとしたが、テスは続けた。彼女の煙ったような声にはユーモアの明るい響きを帯びていた。
「こっちにいる間、フレームたちの祭日プログラムを考えてあげられるわ」
エヴァは目を大きく見開いた。「フレームたちが私抜きで祭日をやるですって?」
テスの顔いっぱいに笑顔が広がった。「驚きよね! なぜか祭日用品が必需品と一緒に新しいタワーへ移送されたのよ。あなたのプログラムが始まったら、タグのついたクレートを見つけられたの」テスは通信ユニットを取り上げると、部屋の隅のマネキンの上に鎮座する暁旦の帽子が見えるようにレンズの角度を調整した。
エヴァは信じられないというように首を振った。「私抜きで暁旦をしたのね」
テスの顔が枠内に戻ってきた。「イコラが夏の間、誰かに頼んで戦争の終結を記念するイベントも開催したわ」
エヴァは顔に不快感を表さないよう務めた。「どうだったの?」
テスは評価として左右に大きく首を振った。「そうね… まあまあよ。ええ」エヴァの口元が固く締まるのを見ると、テスは笑った。「あなたが開催するのとはまた違ったわ」彼女は溜息をついた。「ああ、笑うって気分がいい。タワーに戻ってきて! 追悼式に顔を出すだけでもかまわないから。最後にハグしてから何年も経った気がする」
部屋の暗闇の中で、エヴァは振り返り、窓の外を見た。地平線の上にぼんやりと輝く破片はまるで過去を象徴する碇のようだった。
エヴァは友人に向って振り返り、笑顔を見せた。
もう故郷には戻れない 
貯蔵ユニットのドアを引いて開けたエヴァ・レバンテは、その臭いに吐き気を催した。彼女は随行する2体のフレームのほうを向き、中を指さした。
「全体の消毒から始めて。きれいになったら、箱を運び込むわ」フレームはどちらも頷き、肯定のビープ音を鳴らした。彼らは入り口をまたぐなり掃き掃除を始める。エヴァは服を汚さないよう、杖をつきながら何歩か後ろに下がった。
彼女の周囲には、活気に満ちた市場が広がっている。ランチカウンターで食事を取る休憩中の市民、露店を見る買い物客、清掃やパトロールや配達を行うフレームたち、そしてガーディアンたちで溢れていた。彼らが素早く動き回り、浮かび、飛び跳ねる様はまるで色とスタイルの暴動だった。
エヴァはテスと(ある程度は)アマンダに説得されて戻ってきた自分自身に苛ついて顔をしかめた。どこか違和感があるし、どこか… 心地が悪かった。しかも、彼女が商品を貯蔵するために与えられたのは、ファクション・ウォー以降掃除されていないようなスペースだった。
彼女は市場の歩道にベンチを見つけると感謝しながら腰をおろし、行き交う群衆を眺めた。シティのファッションは、リージョン襲撃の日以来、素早く変化していた。彼女はまだ追いついて、居場所を探している最中だった。特に実用性よりもスタイリッシュで装飾的な呼吸機器を被っている人が多く見られた。シティの再建と復旧のための作業をしている頃の名残だ。
それにガーディアンたちときたら! 戻ってから、彼らと多くの時間を過ごしているテスに光の戦士たちのファッショントレンドについて教わったエヴァは大いに感銘を受けた。テス、鋳造所、そしてバンガードは素晴らしい仕事をしていた。旧タワー時代からアーマーのデザインとシェーダーの図面が大幅に改善されていたのだ。
「私はここで一体何をすればいいの?」彼女は1人で不平をつぶやいた。「私に何ができ…」ヘルメットの上にトサカのようなものを乗せているガーディアンと、ローブを風にはためかせているウォーロックが通り過ぎるのを見て彼女の声は次第に小さくなっていった。
「そうよ」彼女は立ち上がり、フレームに掃除をやめるよう告げるためにドアへ向かった。その瞬間、何者かが行く手を遮った。レザーのトレンチコートと、輝く黒いヘルメットのガーディアンだった。
「エヴァ?」その声はひずんでいた。ヘルメットにエヴァの困惑した顔が反射している。
手袋をはめた手が上がり、ヘルメットが外されると、ラモスの笑顔が現れた。「アブエラ! 俺だよ!」彼女がほほ笑むと、彼は彼女を引き寄せ精一杯抱きしめた。
「悪い子ね。感謝するチャンスもくれないなんて」彼女は身を離すと、彼の肩を優しく叩いた。「人の命を救って、そのままシティを取り返しに去るなんて。感謝くらいしたっていいだろ?」
ラモスは笑った。今まで見た中で一番幸せそうだった。光は彼をたやすく照らしている。彼は近くに立って、様子を見ている2人のガーディアンのほうを向いた。「この人がエヴァ・レバンテだよ! 話したろ? この人はまるで伝説だ!」
彼は2人を身振りで示した。「エヴァ、この2人はグリマーのようにピカピカだよ。リージョンが攻撃してくる直前にガーディアンになったばかりなんだ」
エヴァは2人に深くうなずいた。「2人とも、お会いできて嬉しいわ」
1人は手を挙げぎこちなく挨拶し、もう1人は首を傾げた。「ここで… 何をしてるんです?」
彼女は溜息をついた。「まあ、特に… 特に何も」
ラモスは笑って言った。「彼女の裁縫の腕は一級なんだ! 戦争の英雄だよ! それにその前は、タワーを支える1人だったんだ。暁旦の祭日を気に入ってただろ? あれを始めたのは彼女なんだ!」
2人は感心して彼女を振り向いた。「どうやってザヴァラを説得したんです… あんな…」
彼女は微笑んだ。「楽しいことを?」彼女は3人のガーディアンの反応に笑い、杖で地面を2回突いた。「すごくいい話よ。少し時間はある?」
ラモスは笑った。「そりゃもう! 食事に行こう。新米ガーディアンたちにタワーで暮らすことが何を意味するかってことを教えてやらなきゃならない」
友人の助けを借りて、エヴァ・レバンテはタワーの市場を楽々と歩いた。ここは「最後の安全な都市」、故郷だ。

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ