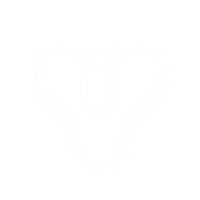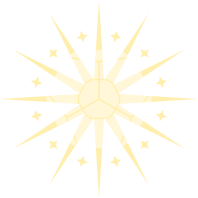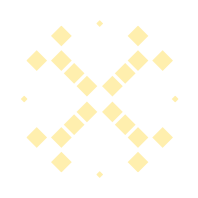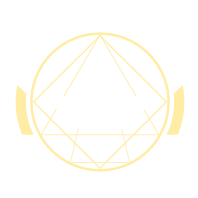エイラの恩寵 
「彼女曰く、この踊りはトラベラー以前から存在していたらしい。大切な人と、沈み行く太陽の下で踊ったのだとか。その話を信じたわけじゃないが、少なくとも信じたいとは思った」――ホーソーン

「パイクレースは危険なゲームだ。特に武器が使用される場合はな。大概はそのパターンだ。負傷者も多いし、動く金も大きい。だから好きなんだ」スパイダーは提案されたレースの詳細を記した綿密なデータ表示を眺めた。HUD上では凄まじい速さで複数の計算が行われていた。「それに賞品としてああいうスパローが用意されてると、やりたがる奴も多い。そもそも、どこであんな代物を手に入れたんだ?」
フォールンのギャングリーダーが肩をすくませる。「ガーディアンはギャンブルが好きなんだ。死ぬほどな」
「確かにそれは言えてるな」スパイダーはデータ表示を縮小し、訪問者の方へ目を向けた。「もちろん、それなりの出費はある。警備、清掃、買収。安上りとは言えない」
フォールンのごろつきはしびれを切らして歯をギリギリと鳴らす。「お前は喋りすぎだ。人間みたいに話しやがる。さっさと額を言え」
スパイダーは当惑しながらも、そのまま話を続けた。「まず、全ての掛け口から分け前をもらう。5%だ。次に、騒ぎで出たスクラップや死体はすべて俺のものだ。俺の縄張りだからな。最後に、レースが始まる前に誰が勝つのか教えてもらう必要がある」
フォールンがうなずく。「3%だ。スクラップはやる。勝つのは俺だ。いつだってな」側近が同意するように笑った。
スパイダーは同意を表すために、4つの手のひらを表に向けた。「取引成立だな。幸運を祈る」
トゥームライダー 
「包帯を巻いて… これでばっちりです」――ゴースト

オシリスはクモの巣の装飾を押しのけてハンガーに入った。セイント14がしゃがみこんで、年季の入ったスパローに長い包帯を巻きつけている。
「皆きっとこのスパローを見たら怖がるぞ」とセイント14は誇らしげに言ったが、オシリスの表情を見て話を切った。「悪い知らせか?」
オシリスは緊張した面持ちで作業台の端に腰を下ろした。「彼らは脅威に晒されている惑星からの撤退を計画している」と彼は言った。「つまり、ピラミッドが追ってこないという不確かな希望だけを頼りに逃げるということだ。もしピラミッドに追われたら、我々はこれまでとは比べ物にならない大きな痛手を負うことになるだろう」
無意識に、オシリスはグローブを外した。金属製のガントレットから解放された彼の手は老いて見える。彼は指の爪がボロボロになった両手をもみ合わせた。「もし火星が暗黒の手に落ちてしまったら… もし水星が――」
「それ以上言うな」セイント14が命じるように言い、オシリスは口を閉ざした。
セイント14は立ち上がると、大股2歩でオシリスの前に立った。ウォーロックの肩をつかみ、彼を立たせる。セイントはオシリスの手を取り、無言でオレンジ色をした三角形のキャンディーを握らせた。
オシリスは素直に数個を口に入れ、黙って味わった。
しばらくしてから、彼が口を開いた。
「不味い」その声からは感謝の念が伝わってくる。
「そうだろう」とセイント14が答えた。「もっと食べるといい」
番人の嘆き 
奴らはお前の接近音に恐怖するだろう。

スパイダーは20本すべての指を広げ、横柄に見下ろしている。彼の前には損傷したアーマーを身につけたウォーロックが立っている。武器は持っていない。
「お前たちガーディアンは入り組んだ岸辺で繰り広げられている暴力や嘘を見ては、自分たちが優位な立場にあると思い込んでいる。だが、大崩壊以前の人間が言っていたように、『獣と寝れば、自らも汚れる』ものだ」
スパイダーは前のめりになり、ボロボロになったガーディアンを観察する。「ウォーロックよ、酷い有様だな。自分の姿を見てみろ」ウォーロックは反抗的に腕を組んでいるが、金属のヘルメットの奥は恥辱で燃えているのをスパイダーは感じ取った。彼は深く笑った。
「幸いにも、まだお前の誇りを救済する時間は残されている。誰もお前の… 犯した罪を知る必要はない。ここではファイアチームが消息不明になるのは日常茶飯事だ。お前が犯人だということを知っている者はわずかだ。それに目撃者には忘れてもらうよう俺が説得してやってもいい。だがその代わり、俺のために働いてもらう」
スパイダーは前かがみになり、唸るように低い声を出した。「でなければお前は1人だ。今すぐお前から全て奪うことだってできる。その武器。スパロー。アーマー。お前自身を殺すことはできなくとも、使えるものをひとつ残らず剥ぐことはできる」
スパイダーは下の腕2本を大げさに広げた。「で、どうする?」
ウォーロックは聞こえるように嘲笑った。「お前につくくらいなら光を失ったほうがマシだ」
スパイダーは武器を構えた配下に目をやった。「お前らはいつだってそうだ、誇りがどうとか言ってな。その誇りとやらのせいで、バンガードは失敗を重ねてきた。仕方がないな。剥ぎ取れ」
復活の翼 
永遠への疾走。

若い母親が焦りを抑えようとしながら、シティの裏通りを走り抜けていく。ワイドパンツを履いた脚を懸命に動かし、カバルの榴散弾の跡が残っている石畳を裸足で踏む。
「ロリーン! ロリーン、どこにいるの?」不安げな声を出さないように必死だ。騒ぎは起こしたくないが、侵攻が始まってからは平静を保つことが難しかった。「ロリーン!」
彼女は裏道から、今は間に合わせの市場へと変わった広場に出た。日用品が積まれたテーブル、スクラップと化したカバルの機械類が詰め込まれたプラスチックの箱、そしてジュージューと音を立てるケバブのグリルを見渡した。いた! 彼女は広場の奥に、くるくるの黒髪が一瞬動くのを見逃さなかった。人混みを押しのけ、光るスパローの上に座っている少し大人びた8歳の息子を探した。
力強い機械の上に座るロリーンはとても小さく見え、その機体の仕上がりは上空のトラベラーの姿が反射して映り込むほど見事だった。近くの屋台には、ラーメンをすすっているガーディアンのファイアチームがたむろしている。他人事のように、死の機械の上で遊ぶその子を眺めていた。
駆けつけた母親が息子をスパローから下ろした。彼は文句を言いながら抵抗する。「でも乗っていいって言われたんだよ、ママ! 動いてないし!」
「ダメよ、ロリーン」彼女は落ち着いた声を出そうとする。「家から出る時は私に言わないとダメって言ったでしょ。心配したじゃない。帰るわよ」彼女は息子の細い腕を引っ張って市場を通り抜けた。
「もっと遊びたい!」子が反抗的に地団駄を踏んだ。「僕もガーディアンになる!」
「ダメ!」彼女はピシャリと答えた。しゃがみこみ、息子の目を真っ直ぐ見つめた。「ダメ。そんなのダメよ。絶対に」

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ