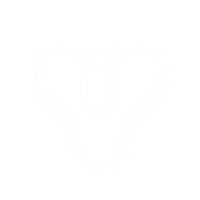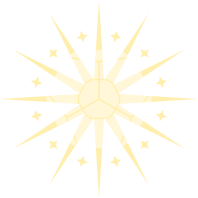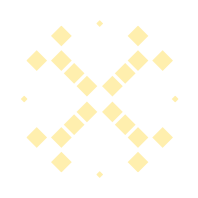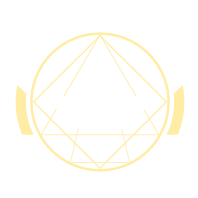記録1 - カロンの影 
このページは黴と記憶の刻印により損傷を受けている…
記された言葉により、自然と精神の中で経験が再現される…
カタバシスの目を通して見た景色…
私は名誉ある招待を受け、最奥の聖廟へとたどり着いた。そして誰から案内を受けるわけでもなく、リヴァイアサンの腹部へと足を踏み入れた。ほつれの目立つ、しわの寄ったカルスの旗が目にとまった。最奥の大広間は煌めくこともなく、黄金時代の物語を思い起こさせた。上っ面を磨きそれを皿の上に並べようとも、表層を剥ぎ取れば… 中身は古い。過去に取り残され、時代遅れと化している。
その先にいた、鮮やかな官軍の衣装を身に纏ったリージョナリーが私に向かってうなずき扉を開けた。向こう側に巨大なカルスの像が立っている。彼と話す媒体となっていた栄光の広間にある自動機械や彫像型のロボットと同様に、本人によく似ていた。
カルスの像が音を立てて動き出した。「随分と早いな。お前の部族は先頭を行くのが常のようだな、ハンターよ。どうせならこの部屋を移動させておくべきだったか? そうすればお前はリヴァイアサンの広間の数々をもっと長い時間をかけて歩き回り、ワシのもてなしを楽しめただろう」
彼はどんな答えを期待しているのだろうか。「この船は実に見事だ。私は仕事を引き受けるつもりでここへ来た」と私は話を切り替えた。
居心地の悪い静けさが支配する。
「直接会うとしよう、カタバシス。いいものを見せてやる」
カルスの像がドーム状の部屋を指した。渦状の壁に様々な種類の戦利品らしき物が飾られている。フックに掛かった骨。恐怖に怯える目をした、最後の瞬間を捉えた剥製。
カウンシラーの一団が私を見ながら、彼らを取り囲んでいる他の3つのカルス像から、機械のプレートを受け取った。彼らは、金線細工が施されている、電気回路の編み込まれた合金製の巨大な檻の周りに集まると、神聖な祈りを捧げながらそのプレートをそこに置いた。すると、1人の人物が座している真珠光沢の椅子を取り囲むように、その檻が墓へと姿を変えた。
「早い到着とは実に縁起が良い。今のワシの状況を見てみろ。なかなか見られるものではないぞ」檻の中から息を切らしたカルスの声が聞こえる。今にも窒息しそうな声だ。
しおれていたカルスの姿が膨張した。私は一瞬、嫌悪感を覚えた。そして彼は私の感情を感じ取った。「光に支配されているお前に比べれば、まだワシのほうが自由だ。お前はワシがこの肉体に満足していると思うか? 小さすぎる。ワシの自動機械はこの姿を模したものだ。ワシの大きさを反映している。奴らはワシと同じだ。無と同じように、ひとつの自我の集合体なのだ」
私は歯ぎしりをして目を見開くと、別の角度から彼の姿を見るために横へと移動した。彼の肌は所々、半透明になっており、それが私の胃をキリキリとさせた。
「お前の考えはお前の恐怖と同じくらい分かりやすい、カタバシス。来い、来るのだ… ワシを見ろ、そしてカウンシラーたちに解放してもらえ」
カウンシラーたちは、カルスの生ける不幸の象徴の上にさらに厚いプレートを置くと、私の存在を無視するかように横を通り過ぎて部屋の出口へと向かった。プレートの中の機構が動き出し、その隙間から眩い光が発せられた。そのフレームの周りを滑らかに走る真珠層が、穢れた威厳を湛える玉座のような器へと繋がっている。その玉座の下では、粘性の高い高貴なワインが泡状になって封印されたフレームの中へと注がれている。カルスは、最後のカウンシラーがフェイスプレートを固定するまで、その白亜質の塊のような目で私を見ていた。フェイスプレートの中にある深淵のオーブが、まるで開けた夜の大地で光る獣の目のように輝いている。今部屋にいるのは我々だけだった。
「カタバシス、嘘についてどう考えてる?」
私はその含意をくみ取った。「嘘には様々な種類がある」
「そしてどれもが弱さの象徴だ」カルスの声が拘束する器から漏れ出て部屋を満たした。「神々は嘘をつかない。ワシと同じように、神は嘘をつく能力も理由もない。本当の力が危機に晒されることはない。本当の力は嘘を強要しない。だが、ワシは最後の神だと信じていた存在に裏切られた」
「つまり騙されたと…?」私はその質問の切れ味を鈍くするために敬称を付けた。「…皇帝陛下」
「宇宙を彷徨っていたワシが暗黒に見つかった時、自分の生み出した者たちに拒否されたワシは、信頼できる存在を手に入れたと感じた。それはいわば崇拝の対象だ。それはいずれワシの元に戻り、より高みへと連れて行ってくれると約束してくれた。一緒に星々の中で踊り、その消えゆく狂気を一体となって最後まで飲み干すのだと。だが、恐怖の艦隊がそこに留まることはなかった。それは甘美で、実に味わい深かった。だがワシは空っぽだ。無だ。嘘が生み出した地獄に閉じ込められている」
「だが神々は嘘をつかない」と私は述べた。
「そのとおり。我々の本性…」カルスはそこで言葉を切ると感情を込めて言った。「…内に存在するその姿を見られることは、至福の喜びだ」4つの像がカルスの器を支えるために前に歩み出る。彼の声が全ての像から同時に鳴り響く。「来い。この広間に影を投げかけ、飲み干すのだ。我々はすぐにその嘘つきと話をし、そこから真実を引き剥がすだろう」
慌てた様子で余白に次のように殴り書きされている。「密輸者のスイッチはまだ機能している。メンテナンス用のサイドハッチだ。通気口を蹴破るしかなかった」
記録2 - 権力と奪還、パートI 
このページは黴と記憶の刻印により損傷を受けている…
記された言葉により、自然と精神の中で経験が再現される…
カタバシスの目を通して見た景色…
我々のボロボロのスレッシャーが、不毛なネッススの大気に音を響かせている。再突入の轟音越しに、カルスの言葉が耳に鳴り響く。「この船はお前のものだ」
船の椅子の大半は空っぽだ。クィンジクという名のサイオン・オフィサーが私の正面に座っている。彼女は船に乗ってからずっと私のほうを見ている。私の右側にいる、ごつごつとしたカバル・センチュリオンは、爆発物の入ったバッグと投射ライフルを装備しながら、圧力スーツについているコネクターを調整している。私が他のカバルに殺されないようにするのが彼の役目だ。私が指揮を執ると知って、船員の多くが不快感をあらわにしていた。
まず私が口を開いた。「ネッススでリージョンから船を隠すのは難しいと思っていた。正直に言うと、リヴァイアサンがいまだに襲撃を受けていないことに驚いている」
「そうすれば奴らは死ぬことになる」とセンチュリオンがぼやいた。「稚拙な戦術だ」
「それは重要ではありません。カルスはあなたが船を持つに相応しいと考えたのですから」私のゴーストのギルガメッシュが私をにらみつけた。
クィンジクは冷笑すると体を乗り出した。彼女の声がそのヘルメットからあふれ出してきた。「カイアトルの台頭でリージョンは混乱しているのだ、人間よ…」彼女の言葉にわずかな敵意のようなものを感じた。「…そして、トロバトルも滅びた。彼女は自らの艦隊の使者を送り込んでいる。多くの船は記録を残すことなく行き来している。しばらくの間、我々の存在が気付かれることはない」
荒くれ者がうなずいた。
「それは初耳だ。この船の離陸にも気付かれないと?」と私は聞いた。
「しばらくの間は」とギリーがサイオンの言葉を引用した。
「だが普通は気付かれる… なにしろリージョンの船だからな。お前は私を泥棒に仕立て上げるつもりなんだろう?」
「カバルの船は全てカルスのものだ」とセンチュリオンがぼやいた。「それにクィンジクはお前の質問には答えない」
「そうか」私が前屈みになり、両手の上に頭を乗せると、スレッシャーが着陸態勢に入った。私は湿気の多いチクチクとした土壌に足を降ろすと、赤く染まっていく深緑色の空の下、太陽に背を向けた。地平線上の黒い山頂を背景に、混雑したカバルの造船所が遠くから光を発している。
「お前がカタバシスか」とカバルが私に言った。彼は自分を指した。「バアルトランだ」
「お前が鉄球のごとき粉砕者か」と言って私は自分のゴーストを指した。「こいつはギルガメッシュだ。もしくはギリーと呼んでくれ」
バアルトランはしばらく考えてからうなずいた。「分かった。ただ戦いが起こった時のために、私の名前は覚えておけ」
「基地を相手に撃ち合いをするつもりはない。今回は物資をできるだけ穏便に取り戻すことが目的だ、バアト」
「その呼び名は気に食わん」
「ギリーも最初はそうだった。だがそのうち気に入るようになるさ」
ギリーがバアトに向かってうなずくと、バアトは不満そうにうなずき返し、歩き始めた。私たちは彼に続いて絶壁を横切って中庭へと向かい、不毛な大地と太陽のない薄闇へと足を踏み入れた。
造船所は岩から切り出した巨大な平地で、荒い滑走路と小屋の周りにはフェンスが張り巡らされている。あらゆるカバル帝国時代の船で溢れかえっていた。ギリーが反対側の端で輝いているアークの光を発見した。カバルの一団の中に特別目を引く存在がいる。空色のマントを着ており、まるで稲妻のように目立っている。彼の言うことなら、彼らは何でも信じるだろう。ギリーは少しだけ言葉を聞き取ることができた。それは誰もがどこかで聞いたことがあるような内容で、批判や相手の弱みの追求、煮え切らない周辺地域の対応策、そして過去に戻らないようにするための対処方法について話していた。
慌てた様子で余白に次のように殴り書きされている。「貨物ベイの扉の先のメンテナンスホール。フロア側の居心地の良い場所」
記録3 - 権力と奪還、パートII 
このページは黴と記憶の刻印により損傷を受けている…
記された言葉により、自然と精神の中で経験が再現される…
カタバシスの目を通して見た景色…
小型船が、旗艦の周りに寄生虫のように群がっている。クィンジクは、カバルの貨物船級の船艦を示した。「グリコン・ヴォラタスだ」彼女は中庭の周辺に張られたバリアに指を触れ、「これを越えろ」とまるで動物に指示するように言った。クィンジクは開いた手を地面に置くと、泡状のボイドエネルギーで飽和状態のレディオラリアを転移させた。それは爆発を起こすと、彼女とバアトをバリアの向こう側へと吹き飛ばした。私は紐にだらしなくぶら下がっているテックス・メカニカ・ライフルを踊らせながら、光の階段を使って後に続いた。
バアトがようやく不安定なジェット噴射を抑え込んだ。クィンジクがその前に歩み出て彼のチェストプレートの機器を調整すると、バアトがこちらを振り返った。「これはトランスマット関連のデバイスだ」と彼は不満げに言った。「私が奴らの信号受信機を止める。そうすればロケーションアンカーを外すまで船を隠すことができる」
私たちはバラバラになって静かな中庭へと入り、各々の仕事に取りかかった。クィンジクと私は停められているインターセプターの間を縫うように進み、バアトはできるだけ目立たないように、中庭の隣にある巨大な信号アンテナへと向かった。
威圧感漂うグリコン・ヴォラタスが姿を現し、我々を飲み込まんとする巨大な波のように空高く立ちはだかった。私が前輪の影に身を潜めている間に、クィンジクがコマンドデッキに繋がっているサービスシュートを開いた。
私は開いたハッチから中を覗き込んだ。廊下の先に見えるブリッジで、1人のサイオンが診断プログラムを走らせている。私は静かに這って中に入り込むと、担いでいたロングライフルを背から外した。
「撃ってください」
「ギル、銃はうるさすぎる」腕には自信があった。だがあのサイオンに警報を鳴らされる可能性を考慮したのだ。
<無知だな>煮え立つようなクィンジクの声が私の脳に波紋を起こした。<無用な心配だ>
勝手に頭の中に入ってくるな、と私は心の中で呟いた。
波紋が広がっていく。<お前の精神は乱れ、負荷が掛かっている。混乱した理屈は嘘を生み出す>
「私たちにはこの船が必要です」ギリーが囁いた。彼が私の視界の端に入り込む。「何もしなければ、あのサイオンに周辺の全カバルを呼ばれてしまいます!」
クィンジクがハッチから姿を現して隣で膝をついた。「こいつはイリクスだ、ゴースト。彼女は我々を裏切ったりはしない」
「彼女はレッドリージョンです。カルスは彼女の処刑を望んでいるはずです」
「サイオンは様々な派閥に属している。だがカバル内では、我々は議会に籍を置き、自らの未来に向かって進んでいる。私が彼女を理解しているように、彼女も私の忠誠心を理解している」とクィンジクは言うと前に進み出た。
ギリーはサイオンに近づくクィンジクを見守った。「上手く行かなかったら、ためらっている暇はありません」
彼の言葉が私の肺を押しつぶした。かすかな期待を込めた短い呼吸が肺から逃げ出す。私は銃を構えて待った。
イリクスはクィンジクに気付くと動きを止めた。彼女は振り返った。彼らはお互いに頭を下げた。彼らはお互いに共感し、沈黙の中でひとつの結論を導き出した。
彼らの野望が何であれ、それはこの船、この瞬間、そしてここにいるカバルよりも、さらに先に進んでいる。こんな考えに至ったのは、最後にガーディアンの安っぽい飾りを身につけた時以来だった。私は光に守られた不死のシティの夢を売り払った。それが永遠に続くと考えていたのだ。永遠とは、それが崩れ落ちる瞬間を見られるほど長くは生きられない者が見る夢でしかない。
イリクスはギリーと私を見てから、私のライフルに目を移した。恐怖を感じている様子はない。彼女は自制を求めながら、自分たちの目的を静かに再確認しているのだ。その瞬間、私は自分が未熟に感じた。私は立ち上がった。
私たちがエンジンを暖め始めると、イリクスは挨拶もせずに群衆に加わり、私たちに操作を任せた。
バアトがトランスマットから現れてブリッジの中で具現化した。彼は息を切らしながら、なんとか誇らしい言葉を絞り出した。「無事に爆弾を設置した。これで追跡されることはない」
グリコンが大気を切り裂くと同時に、巨大な爆発が造船所を揺らし、船体全体に振動が走った。下に見える中庭全体に向かって炎が吐き出され、過去の財産を業火へと変えていく。バアトは言った。「あの火種は過去を焼き払い未来への糧となる」
逆よりはましだ。
慌てた様子で余白に次のように殴り書きされている。「扉は故障中。我々が飛び込んだ時からずっとその状態だ。ここには近づかないことにしている」
記録4 - 無の泉 
このページは黴と記憶の刻印により損傷を受けている…
記された言葉により、自然と精神の中で経験が再現される…
カタバシスの目を通して見た景色…
血液が油を含む泥水やダークエーテルと混じり、キャビンの床に開いた排水口へと飲み込まれていく。私は座った。ハーベスター船全体に荒々しい騒音が響き渡っている。私の耳にはその音が、下のデッキにあるウォービーストの檻の中から聞こえてきていた。鎖を噛みちぎろうと狂ったように軋む歯。汗ばむ体で壁に体当たりする音。
バアトが小石の雨を浴びながらハーベスターに乗り込んだ。「貨物室は確保した。負傷者も回収した」と言うと、背後に迫るリーフの嵐を遮るように、彼はベイを閉じた。
「どれぐらいだ?」と私は聞いた。ここには我々の2人しかいない。
彼は懸念を弱さの現れだと勘違いしていた。「明日の収穫の準備をしよう」
私は質問の仕方を変えた。「クィンジクはこれをあとどれだけ必要としているんだ?」
「岸辺を離れるまでに2日分の収穫量が必要だ」
「彼女は目的を言っていたか?」
「私に聞くな」
「詳細も分からずに命令に従うことに不満はないのか?」
「クィンジクはお前の質問には答えない、光の戦士よ」
「またそれか」それも一度ではない。
「お前の話し方は私の父に似ている。質問ばかりだ」と言うとバアトは唸り、装備を置いた。「父はカルスを捨て、ガウルと一緒にクーデターを起こし、一族の顔に泥を塗った。私は父の枷を脱ぎ捨て、皇帝に忠誠を誓った。私は慈悲を与えられたのだ。私はすぐに一族の復興させ、その血を残す権利を取り戻すだろう。忠誠心は盲目ではない。忠誠心は褒美なのだ」
「つまり負け戦から逃げて、勝ち目のありそうなほうについたということか」
「父は勝機を見出す前に小さな可能性を捨てた」バアトはそこで間を取り、言葉を選んだ。「カルスは暗黒の謎を解き明かし、それを使ってトロバトルを取り戻すだろう。必ずな」
__________________________________________________________________________________________________
クィンジクが研究所の入り口に立ち塞がった。船を手に入れた後、研究所はすぐにリヴァイアサンからグリコンへと移設された。危険な雰囲気を醸し出すありとあらゆる機械が置かれている。彼女は指を私に向けた。彼女の言葉が私の精神の中で再構築された。「ここはお前が来るべき場所ではない」
「あれを何に使うのか教えてほしい」
「なぜだ? 奴らは動物だ。使命を持つ獣だ」
私はその意味を考えた。彼らは昔、今とは異なる存在だった。弱き存在は埋められ、無視され… しかし…
「ひとりのハンターに対してよほどの思い入れがあるようだな」
彼女は暗にケイドのことを示した。「死体への冒涜と同じだ。お前たちは死を崇高なことだと考えている、違うか?」
「お前の質問には答えない」クィンジクの怒りが私の精神に入り込んだ。彼女は私を追い払うと扉を締めようとした。
「バアトならそうする。彼の兵士もだ。お前は牢屋に入ってくれとスコーンに丁寧に頼むのか? それとも私と本音で話がしたいのか?」
彼女が私をにらみつけた。「お前のゴーストはどこだ?」
「ハンガーのメンテナンスだ…」
「来い」とクィンジクは言うと、私を研究所の中へと誘導した。そこには、種々雑多なポンプとワイヤーで彩られた巨大な容器がいくつも置かれていた。「これは…」彼女は目の前にある一番大きな容器の覗き窓を開いた。
覗き窓を通して狂犬のようなスコーンの目が私と視線を合わせた。黒い液体が揺れ動き、その生物はもがきながら液体の中でくぐもった叫び声を上げた。
「暗黒への結びつきが強化された。彼らの精神は我々の精神のようにリンクしている。だがバロンがいなければ、彼らの精神は空っぽのままだ」
それは容器の壁を狂ったようにひっかき、指先で金属を掘るような耳障りな音を響かせた。
「思考力を持たない割には随分と暴れている」と私は言った。
「彼らは最後に与えられた使命だけを頼りに生きている。彼らの標的はフィクルルだ。行方不明の王子の仇を取るためにな。ただ…」クィンジクはタンクに手を当てた。彼女が凝視すると、暴れていたスコーンの動きが止まった。「…ある意味では、彼らの精神は器となる。そこを介して多くの思想を… 通わせることができる」彼女はスコーンを解放した。そのスコーンは疲れ果て、再び溺れた。目が恐怖の悲鳴を上げている。「この個体には荷が重すぎる」
「それが我々の助けになるのか」
「カルスは暗黒を彼らの中に注ぎ込む。そして我々は彼らからあらゆる知識を絞り出す」
「どうやって?」と私は聞いた。
「アノマリーに到着すれば分かる」
慌てた様子で余白に次のように殴り書きされている。「タービンのメンテナンスデッキは菌類で塞がれている。侵入口を見つけたら、スイッチを切替えろ」
記録5 - 鑑賞 
このページは黴と記憶の刻印により損傷を受けている…
記された言葉により、自然と精神の中で経験が再現される…
カタバシスの目を通して見た景色…
リーフでの厳しい日々が6週間続いている。スコーンにハイヴ、嫌悪するようなことだらけだ。まだグリコンよりも開けた岸辺のほうがマシだ。だがなんとかやりくりできている。我々は小惑星帯を横切り、フォボスに船を止めた。古いカバルの基地はまだ稼働していた。私は率先して基地にいる宿られた兵の掃除に取りかかった。たまには外に出たほうがいい。この忌々しい存在はかなり御しやすく、ファイアチームを組む必要すらなかった。
アノマリーと比較すると、我々の小さなサーペントシップは虫や塵でしかない。遠くに見える星のように指だけで潰せてしまえそうだ。かつて火星が存在していた場所に開いた底なしの穴が、右舷の全ての窓を埋め尽くした。乗員は何時間も観覧室の中に立っている。中には引きずり出される者もいた。それはあまりにも巨大で、惑星大の穴から暗闇が囁きかけている… まさに無限だ。我々は理性の崖っぷちに佇んでいた… それはこちらを拒んでいる。
昨日、カルスが我々の前に現れた。その2歩後ろには彼の書記官がいた。彼はこちらの状況を確認した。そして彼らが親交と称するもののために、最初の1体を選択した。
彼らは船に何かを運び入れた。スコーンは暴れ続けていた。クィンジクはそのスコーンを観覧室へと入れた。
ギリーも丸窓越しにそれを観察していた。私は夜に、彼の囁き声を耳にした。
「同じです… 最初から最後まで。あなたの言うとおりです、カタバシス。これはただの檻であり、牢獄です。ただ私たちが想像していたよりも遙かに大きい」
我々はここで何をしているんだ?
慌てた様子で余白に次のように殴り書きされている。「タービングラインダーの真上付近で休むことができる。休んでいる間はタービンの騒音が守ってくれる」
記録6 - 過度な強欲 
このページは黴と記憶の刻印により損傷を受けている…
記された言葉により、自然と精神の中で経験が再現される…
飽くなき欲求、カルスの目を通して見た景色…
群衆は皇帝であるワシを支持している。だがこれはまだ始まりにすぎない。アムソットがこちらの到着を知らせると、観覧室に皆が押し寄せてきた。その中にはあのガーディアンと小さな光――非常に興味をそそられる存在だ――の姿もあった。そのゴーストが観察する一方で、ガーディアンは諦めてその後へと下がった。同情を禁じ得ない。
皆がワシの尽力の集大成を見るためにやって来た。ワシは同時にあらゆる場所に存在することができる。至る所にある像が、隅々まで目を光らせているのだ。装甲運搬車は、王冠に異常がないかを監視している。王冠は鑑賞されるため、要塞陣地由来の金で飾られている。それをハイヴの手から解放するために多くの命を犠牲にしたが、実に快く曲がるものだった… 意識に橋を架け、服従させる能力を持っている。捧げ物を横目に、無意味なことを一斉に喋るスコーンが鞭で打たれ、王冠に繋がれている――棘でできた、ワシの素晴らしい才能による道具だ。勇敢なカウンシラーたちが、彼らの魂を固定して交わりに備えている。偉大さが我々を待ち受けている。
傍観者たちよ。楽しませてやろうではないか。
ワシは4対の巨大な手を鳴らす。「さあ… 始めるのだ」
すべての視線を大きな観覧用の窓に向けると、シャッターが上がり火星の墓を露わにする。特異点の中心部から、蔓のような暗黒の帯が螺旋状に伸びている。それはワシのすべてを虜にし… 緊張した肉に食い込む鉤のような囁きで、その中心部へと手招きする。ワシはその刺激的な苦悶に恍惚とする。「いいぞ…」
カウンシラーたちが王冠に手を置き、それを通して認識を集中させる。彼らはスコーンのシナプス経路の集合体をこじ開け、特異点のミーム的球体の生地に縫い込む。引っ張られるような力にグリコンが抗う。
速度が周囲の現実を引き裂きながら、特異点へと突き進む。我々は苦悶を前にして宙吊りの状態になる。それはすべての視界を満たす。曲がり角のすぐ向こうにある無。時が止まり、宇宙がワシの意思に適応しようと弧を描く。今だ。
「ワシを喜べ。ワシはお前のイメージの中で、己のすべてを模倣した。多くのことを乗り越えるため、意識を拡張し… あらゆる器の喜びと体験を得た。だが様々な視点を持ちながら、まだ自分の目を通してしか見ることができない――それ以上のものが欲しいのだ」ワシは暗黒の無を覗き込む。「お前は… 忘却だ。破壊ではなく、すべての出来事が混じり合ったものだ。ワシはお前のようになることを願う。存在を貪ることを。ワシを高みに導くというお前の約束をまとめ上げることを」荒々しく笑った。ワシのすべての姿が渦巻く特異点に釘付けになっている。「ワシを見よ!」
宇宙は折れ曲がり、弱々しい現実へと戻される。またしても無視された。スコーンが一斉に上げる意味をなさない金切り声が、囁きをかき消す。どの耳からも、その金切り声しか聞こえない。
ワシは手を伸ばす。最後に会った時、お前に教えられたように。ワシは運搬車からスコーンの意識をひとつひとつ開いて、お前を探す。何もない。いつもそうだ。そこでワシは彼らの死体を引き裂いて開ける。断続的に手足を引き抜き、頭蓋骨から意識を引き抜き、お前のために磨く。金切り声が遠くの囲いの中からしか聞こえなくなるまで、ワシは探し続ける。
目をそらすことのない乗組員一人ひとりと視線を合わせる。彼らの中に、ワシはお前を見る。お前の存在を。緊張の背後から覗き返す… 観察者を。
慌てた様子で余白に次のように殴り書きされている。「ごみ捨て場の下を掘って場所を作った。まだ稼働中だから、急いでくれ」
記録7 - 憤怒 
このページは黴と記憶の刻印により損傷を受けている…
記された言葉により、自然と精神の中で経験が再現される…
カタバシスの目を通して見た景色…
悪夢に蝕まれた浅い眠り。
サイレンが鳴り出した時、私は通りにいた。
私は長い間トラベラーを眺めながら横たわっていた。信じられない気持ちで。半ば自動化された意識の思考の狭間で。
レッドリージョンがすべてを一掃する。彼らの一斉射撃でタワーが壊滅していくのが見える。
立っていないのは自分だけだ。
瓦礫が落ちる。私は隔離されている。ギルガメッシュに手を伸ばすが、そこに彼はいない。
檻が我々の光を窒息させる。
炎が通りから通りへと追いかけてくる。光もない。弾薬もない。シティが燃えている。
無慈悲な神の下で、顔を持たない風が私に叫んでいる。赤い装甲の死が、防壁を縁取り、
シティが燃えている。
私は逃げる。逃げる。逃げる。逃げる。逃げる… 罪の意識で重くなった足取りで。
シティが燃えているのに、何もしなかった。
.
.
.
ギルの壊れた星が私の恥辱を見つける。
そこにいるのは、生き延びようとしている我々だけだ。
我々は共に這いつくばって彷徨う。
慌てた様子で余白に次のように殴り書きされている。「悪夢が戻ってきた。何か月もかかったが、いつも必ず戻って来る――今回はより強烈だ。積み荷を引き受けてから毎晩、連中はうなり声を上げている。3つ離れたデッキにいるはずだが、それでも声が届いてくる。ギルが船の中をうろつく回数が増えた。
そろそろ非常用の荷作りを始めなければ。ハンガーの近くで場所を見つけられると思う… クィンジクの研究所の反対側で。ここはごった返してきた」
記録8 - アケロンの壁 
このページは黴と記憶の刻印により損傷を受けている…
記された言葉により、自然と精神の中で経験が再現される…
カタバシスの目を通して見た景色…
カルスの墓の運搬車が再び観覧室を見渡す。彼のすべての姿が、ぎらぎらとした金属と不安の塊の周りに立っている。彼の呼ぶところの王冠である。幾度にもわたる失敗を経て、この交わりの場に出席する乗組員は少なくなった。ギリーと私はぺちゃくちゃと喋る多数の死体の上方に立つ。それらから出ているプラグとケーブルが、醜い王冠の下のスコーンの肉の中へと繋がれている――エーテルがたっぷりと含まれたスコーンへと。要塞陣地の金は変色している。最後の交流が試みられて以来、何らかの地衣類がその貴重な金属の装身具を侵していったのだ。
「金は退色しないものだと思っていた」私はギリーに言う。「それが純粋さの表れなのだと」
「光のように?」
「うむ…」私は唸る。ギリーは王冠を凝視する。観覧用の窓とその向こうの深淵を。
バアトが私の隣に陣取り、手すりに寄りかかる。「ガーディアンは皆、疑念に支配されているのか?」
カウンシラーたちが王冠に近づく。
「バアト、経験から言わせてもらえば、己を過信する者は死にやすいぞ」カウンシラーたちが王冠に手をあてる。そして私は突然、この部屋が静止していることを強く意識する。我々の傾きを。
激しくなる喋りにかき消されまいと、バアトが大きな声で言う。「お前のゴーストがスコーンに語り掛けているぞ。力の限りにな」
「興味を引かれただけだ。何か利用できそうな切り口を探している。そうだろう、ギリー?」私は疑いを隠そうとしつつ尋ねる。
ギルガメッシュは何も言わない。観覧カーテンが格納されていく中、虹彩をじっと前方に向けている。
速度が周囲の現実を引き裂きながら、特異点へと突き進む。船体が慈悲を求めて呻き声を上げるが、カルスの興奮した笑い声が重なり合ってそれをかき消す。今回は違う、通路ではない。壁だ。我々は激しく衝突する――しかし、一気にではない。それは着実な転落の衝撃だ。方向は決まって下。宇宙の帯が我々の周りで折れ曲がり、消えゆく関連性という名の輝く細い針の群れへと吸い込まれ砕ける。周辺で起こる破壊は勢いを強め、燃え尽きる。ひとつひとつの光の針の間の空間が広がっていく。「それ」が存在を得るまで。
その変遷は消極的な膜組織に似ている。魂の深淵が氷で覆われ、嘆きの声を上げている。形態と表現の間の黄道障壁で、氷が擦れ合っている。
我々は横断する。太陽はない。空虚な流れの中を、方向も分からぬまま漂う。
.
.
.
「皇帝はどこだ?」
慌てた様子で余白に次のように殴り書きされている。「ハンガーの外れに鍵のかかった場所がある。もし誰も使っていないのなら…」
記録9 - 異端の血肉 
このページは黴と記憶の刻印により損傷を受けている…
記された言葉により、自然と精神の中で経験が再現される…
空虚な器の目を通して…
休止。拘束。
[ノック]
脅威。
外の嵐。
雨が渇きを和らげる。
閃光で輪郭が露わになる。
私の知る輪郭。
[ノックが強くなる]
静かな囁きが私から広がる。
すべての者へと。
父として、フィクルルとして。
バロン。ケル。
全て消え去った。
そして新たな声が…
[ノックが繰り返されている]
迫っている。
恐怖と混乱。
いや。
この意識の下にある意識が、表に出たがって叫んでいる。
無、スコーン、息子… フォールン… エリクスニー… 王…
アクリースは屈しない。
立て。囁きに埋もれた声がそう命じる。
アクリースは屈しないが、アクリースは死んだ。
引き剥がされたのだ。
__________________________________________________________________________________________________
グリコンの背骨が折れ、椎骨が入れ替わっている。
スコーンがその交わりを無の中へ迎えるように、遠吠えを上げる。
彼らは中枢のローカスを通して聞こえる囁きに従う。
「救済を迎えよ」
慌てた様子で余白に次のように殴り書きされている。「ハンガー付近の船体の外にスキャナーアレイがある。クィンジクのフィードを確認するため、そこに回線を繋いだ。聞くための場所が必要だった」
記録10 - 樽の中の血 
このページは黴と記憶の刻印により損傷を受けている…
記された言葉により、自然と精神の中で経験が再現される…
カタバシスの目を通して見た景色…
血が流れ出るように、何週間もの時が過ぎていく。
「お前のゴーストはどこだ?」バアトが、潰れたスコーンを腐敗した暗黒の蔓の中へと投げ込みながら唸る。落下以来の無限の拡張の中、グリコン一帯にそのような黴が生えており、広がり続ける一方だった。
「分からない」私は自分の内臓からギザギザの刃を引き抜きながら言った。「どこかで親交でも深めてるんだろう」
「ここにいます。何かお望みですか?」ギリーが姿を見せて言う。
「穴を塞いでくれ」私は呻く。
我々を奇襲し、今では墓へ戻っている3体のスコーンの方にバアトが目をやる。「残りの連中はこいつらの死を感じ取るだろう。距離はあとどのくらいだ?」
「船がまた方向を変えたのでなければ、この方が起き上がりさえすれば遠くはありません」ギリーが私の方を示す。「クィンジクは本当に確信しているのですか? 王冠を断ち切れば、私たちは戻れるのだと」
「うまくいくさ。せっかくこのコマンドキーを発掘したのに、無駄に終わっては困る」
私は帝国のセキュリティキーを掲げて言った。「スコーンを止めるためだと言っていたじゃないか!」バアトが怒鳴る。
「奴らを止めても、出られなかったら意味がない」
「私はカルス皇帝に命を捧げると誓った! 見捨てろと言うのか!」彼が私を見下ろす。
「見捨てられることに関しては、私も少しは知っている。彼は望む物を手に入れるためにお前を利用した。私を利用したのと同じように。彼は消えたんだ、バアト。そして我々も同じ道を辿ろうとしている。そうしたら、お前の血筋はどうなる?」
私が立ち上がるのと同時に、波がグリコンを襲う。それは目に見えるものというよりは、電球の破裂に近い。長い点滅の後、ぴりぴりとした痺れが訪れる。感覚の喪失。それが冷たく張り詰めた金属のように、船の中を移動しているのが聞こえる。
3体のスコーンの身が突然動き、歪みながらグロテスクに復活する。
「残りたければ好きにしろ、粉砕者よ」
__________________________________________________________________________________________________
我々は唸り声に追われながら通路を抜け、船のブリッジにたどり着く。私はコマンドキーでドアを封鎖した。そして観覧室の入り口にあるコマンドコンソールの下でクィンジクと会う。彼女は15人の体制支持派の兵士に囲まれて立っている。
「これで全員か?」私は尋ねる。
クィンジクが頷く。私がコマンドキーを観覧室のドアに差し込むと、しばらくしてピストンが離れ、ドアが開いた。クィンジクが一瞬意識を集中させる。「空っぽだ…」彼女の声が響く。
我々は観覧室に入る。兵士たちが部屋のあちこちで配置につく。バアトが暗黒に侵された王冠の横を通り過ぎ、観覧用の窓のところで崩れるようにひざまずいた。
彼は無限を見つめる。「忠誠を捧げるのに値する者を、どうやって選べばいい?」
私は彼に歩み寄る。「どんな者でも自分なりのやり方がある。正しい者などいない。お前は誰の負い目も感じなくていいんだ、バアト」
クィンジクから準備が完了したと合図があった。最後にここで交信したカウンシラー一人ひとりの焦げた手形を彼女の目が追う。その様子を見ながら、私は王冠に近づく。
ブリッジに続く階段に金切り声が響き渡る。擦れる金属が炎の訪れを告げる。
「私がこうするのは、他の者を生かすため」クィンジクの声が漂う。「苦痛は意図していなかったが、カルスが欺くことは予想しておくべきだった。彼の秘密を盗み去ろうという野心が、我々皆を失敗に導いた」
「ここから出してくれれば、貸し借りなしだ」
彼女の次の言葉は私の頭の中へと送られた。<そうしよう。ここはお前のいるべき場所ではないからな>彼女は掌を王冠の上に置く。
速度が周囲の現実を引き裂きながら、無限の中へと勢いよく後退していく。我々はクィンジクと王冠を取り囲む17人の防衛者として、無の中に立つ。金切り声は大きさを増し、折れ曲がる鋼の呻きを通して、スコーンの震える肉が我々のいる無へと注がれる。
複数のファランクスのシールドの後ろから、スラグライフルが四方を一斉射撃し、スコーンの列を次から次へと爆破していく。インセンディオが、残されたものを火葬しようと射撃の合間に進み出る。私は我々の輪が発砲を受ける前にレイダーを銃で倒し、浸水を食い止めるためにボイドウォールグレネードを投げる。グリコンが暗黒の波とぶつかり合う中、クィンジクが繋がりを断ち切ろうとしながら悲鳴を上げる。無が我々に巻き付き、逆火が彼女の手を焦がす。戦いが終わるころには、スコーンの死体と空のマガジンが床にずらりと並んでいた。
金切り声が弱まっていく。暗黒の波がグリコンを震撼させると同時に、金属の擦れる音が観覧室に響く。焼かれていないすべてのスコーンが痙攣し、再構成を始める。兵士たちは錯乱し、再構成が進むのを止めようと、身をよじる死体の山に向けて発砲する。
混沌の中で稲妻が空気を引き裂き、3人のリージョナリーを貫いて、インセンディオのタンクを破壊する。強風で7人が死に、輪が小さくなる。我々が稲妻の方向へ発砲し返すと、悪臭を放つ2体の変異体が現れる。彼らは部屋に突入し、拳を鳴らしながら後ろ足で立つ。私は片方に向かって突撃し、ボイドに滑り込んで鞘から刃を引き出す。バアトは足元にあったファランクスのシールドを掴み、もう片方に挑んだ。稲妻がシールドにぶつかる。我々は残っている銃で彼らに射撃を浴びせ、間合いを詰める。私が敵の両手と頭を断ち切って向き直ると、バアトがシールドをもう1体の顔にお見舞いするところだった。
クィンジクが叫び声を上げる。振り返ると、黒い炎が彼女を飲み込み、宇宙が我々の周りで渦巻いていた。彼女は踏みとどまろうと自らの痛みを我々へと拡散させるが、効果はない。
私は振り向いてバアトを見る。彼のずっと向こうの無の中に、燃え立つ香炉を引きずる巨大な影を見る。そして悟る。我々はここで死ぬのだと。
慌てた様子で余白に次のように殴り書きされている。「メスを使うスペースの下に隠れ家を作った。近くに研究技術をしまい込んだ」
記録11 - 不機嫌 
このページは黴と記憶の刻印により損傷を受けている…
記された言葉により、自然と精神の中で経験が再現される…
カタバシスの目を通して見た景色…
上手くいかなかった。実を言うと、クィンジクがちゃんと仕事を終わらせられたのかさえわからない。ギリーの話では、私を蘇生するための安全な場所を探すのに何日もかかったらしい。一味を従える大きな者が、彼を捕まえようとしていたのだ。
私はカバルの死体を埋葬することにした。犠牲者が多すぎて全員を回収することはできないが。
我々は密輸者の物置を使い、身を潜めた。私は船の中のそういった物置に、非常用の荷物をしまっておいたのだ。
彼らのうち一人にでも見られたら終わりだ。
経過を追い始めてから少なくとも1か月… いや、3か月近くは経つ。波には規則性がない。波にぶつかると船の配置が変わり、また道を探さなくてはならなくなる。
ギルガメッシュは以前よりよそよそしくなった。口数が減ったし、数日にわたって姿を消すことがある。今のところ、必ず戻っては来るが。
私は死ぬ時、シティが燃える夢を見る。最初に訪れるのは死の夢だ。目覚めた時、どのくらいの時が経ったのかわからない。ギリーは… 何も言おうとしない。
今回の人生と私が覚えている最後の人生の間には、無数の人生があった。
私は遺体安置所に暮らしている。
__________________________________________________________________________________________________
私は生きている。年老いている。
「起きてください」ギリーの声はか細い。
「なぜだ? 飢えることしかすることがないのに」
「また諦めるのですか? いっそのこと、あなたを置き去りにした方がいいですか?」
私はごろりと向きを変えて彼の方を向く。「諦めるわけじゃない。ただ… 私の光を取って、持っていてくれ… 出口が見つかるまで」
「私は、私たち自身が出口なのだと考えていました――私たち2人が。でも、また堂々巡りをしているようです」
「食べる物がないんだ、ギル。空虚さに苛まれる感覚は、お前には分からないだろう。約束してくれ。我々が外に出る時まで、私のことは放っておくと」
ギルガメッシュは何も言わず、長い間私をじっと見つめる。私は目を閉じる。
「約束します」
慌てた様子で余白に次のように殴り書きされている。「通気口の迷路。この中のどこかのはずだ。いまいましい黴が、常に行く手を阻んでくる」
記録12 - 債務者のナイフ 
このページは黴と記憶の刻印により損傷を受けている…
記された言葉により、自然と精神の中で経験が再現される…
ギルガメッシュの目を通して見た景色…
私は自分のガーディアンだった者の遺体の傍を漂う。私は彼の恥辱を長い間隠してきた。彼の炎が消えた時に暖めるのが自分の責任だと信じていた… しかし今では、その責任が私を命に繋ぎとめる手綱だったことがわかる。冷ややかに渦巻く、息の詰まるような現実だ。それに首を絞められて喘ぐことは、もうない。
真実を見よ、と囁きは告げた。私はこの船の上で苦しんだすべての瞬間の中にそれを見た。向こう側の世界へ外挿された暴力の小宇宙。逃れる方法はひとつしかない。カタバシスもじきにそれを知るだろう。
スコーンの傍観者が我々を取り囲む。
私はカタバシスを起こす。
「ギリー…」カタバシスがライフルを傍らに、私の前で膝をつく。「これはどういうことだ?」
「出口です。もうあなたを運ぶことはできません」
「私を… 見捨てるのか?」カタバシスの視線がスコーン、ライフル、彼のゴーストへと移る――いや、もう彼のゴーストではない。トラベラーのものでも、誰のものでもない。
「私はすべてを犠牲にして、あなたを前進させてきました。生き延びるのに必要なすべての力へと、あなたを導きました」私は彼が忘れたがっている真実を共有する。「一体何のために? そうしたところで、何も変わらない。すぐに次がやって来ます」
スコーンが接合部の外れた通路に侵入する。カタバシスが沈む。「お前は、しないと言ったはずだ…」
「トラベラー… あなたが私をこの弔いの鐘の中に閉じ込めていた。今こそ、私たちを解放する時です」
「どういう意味だ?」彼の言葉は重石のようだ。
「私たちの光を断ち切るのです。さもなければ、彼らが幾度となくあなたを八つ裂きにしますよ」私はスコーンの方を示す。
「お前はそんなことはしない」
「あなたの死は重いものです、カタバシス。ですが、私はあなたが学ぶまで、何度でもあなたを連れ戻すでしょう」彼は理解できていない。「私が痛みを感じないと思っているのですか? あなたが辺獄に隠れている間、私が苦しんでいないと?」
カタバシスが身を乗り出す。「私はお前に頼まれたことをすべてやってきた」
「置いて行ったじゃないですか!」私は叫ぶ。「あなたはここで私を置き去りにした。シティでもそうです。トラベラーに背を向けさせた。私たちはまるで、あのタンクの中のスコーンのようです。恐怖と混乱の中で… 永遠に溺れている。あなたが原因です」
「シティが燃えていた。私は生きたかった。すべては… 我々が生きるためだった」
彼はまだ分かっていない。この場所は太陽系と何も変わらない。血の樽だ。後戻りする理由はない。「今、光は燃えています」
「我々なら生き延びられる」カタバシスが掌を差し出す。「頼む」
「私は生き延びたいのではありません、カタバシス」私は彼から離れる。「私が求めているのは、救済です」
「…手遅れなのか」カタバシスがすべてを悟り、弱々しくすすり泣く。
「あなたなら終わりにできます。私たち両方のために。今度はあなたが犠牲を払う番です」私は言う。
「お前の言うことは全部嘘だ!」カタバシスがライフルを掴む。
レバーからアクションへ。
銃撃から無へ。
ゴーストから死んだ記憶へ。
慌てた様子で余白に次のように殴り書きされている。「ブリッジの下の水は、次の波で再び立とうと待ち構えている死体で溢れている。気をつけろ」

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ