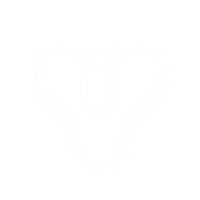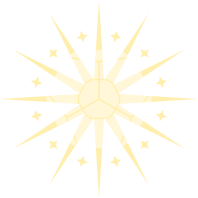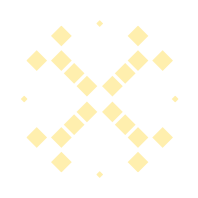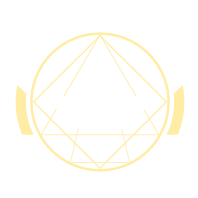「武器は何も隠さない。見たままが全てだ。その武器がそうありたいと願っているかは関係ない」――セイント14のシャックスへの言葉
大嵐以降に、トラベラーの光を浴びる最初のエリクスニーになることは、ハウス・オブ・ライトのケル、ミスラックスにとっては名誉なことであり、彼も自分がそうなるとは考えてもいなかった。彼はタワーの歩道に立つと、オールマイティが残した傷跡の下で、ここまで自分を導いてくれた人生の選択肢を振り返った。全ての出来事を一つにまとめる糸が存在しているのかもしれない。だが、彼にはそれを思案するような時間はないだろう。
ミスラックスに影が忍び寄っていた。広い肩幅、湾曲した1本の角。星々を圧倒するようなシャックス卿のゴツゴツとした輪郭が、数世紀も前から続く彼の本能を呼び起こした。ミスラックスが武器を構えずに済んだのは自制心のおかげだった。
「まさかこんなところにいるとはな」シャックスはそう言うと、コツコツと足音を立てながら、ゆっくりと階段を降りた。「あそこにいたのか?」
「何?」
シャックスは手すりの前にいたミスラックスの隣に立った。「あそこにいたのか?」彼は再び聞いた。そう言うと、目を合わせることなく、今度はトラベラーの先にある地平線を指した。
ミスラックスはシャックスの動きを目で追った。彼には理解できなかった。
「シックスフロントの戦いだ」とシャックスは、彼らしくない優しい声で言った。「私がそこでフォールンをどれだけ殺したか知っているか?」
ミスラックスはその質問に毛を逆立てた。そして自分が本能的に武器に手を伸ばそうとしていることに気づいた。だが、トラベラーの存在と彼の心を傷つけたその質問が彼の手を押さえつけた。「何人だ?」彼が聞いた。だが答えは知りたくなかった。
シャックスは息を吐き、手すりの上で手を組むと、そこにかなりの体重をあずけた。「数百はいってるな」と彼は静かに言った。「皆、恐怖の中で死んだ」
ミスラックスは喉の奥でエーテルと胆汁が混ざるのを感じた。彼の手足は震えていた。体の中で怒りが炎を上げ、表に出てこようとしている。だが、彼はその怒りを抑制すると大きな溜息をついた。彼の呼吸と一緒に吐き出されたエーテルが一瞬、虹色の雲となって姿を現した。
「お前は人間を何人殺した?」とシャックスが質問した。
「数え切れない」ミスラックスはそう答えたが、その表現でも足りない気がした。その考えが彼の心をかき乱した。彼は先ほどよりも深く溜息をついた。シャックスはおぼろげな光の中で輝く浄化されたエーテルを見つめた。
「お前がタワーにいると聞いた時――」とシャックスが言った。「壁から放り投げてやろうと思った。これまでお前たちに殺されてきた者たちのことが頭に浮かんだからだ。暗黒時代、光なき者たちは八つ裂きにされた」彼は悲しそうに鼻で笑った。「だが、私は奴らのことを思い出した」
しばらく静寂がその場を支配した。長い沈黙の後、ミスラックスが聞いた。「誰のことだ?」
「3人のスカベンジャーだ。崩壊した配水管の中で身を寄せ合っていた。奴らは食糧を盗んだ… 誰もが飢えていた。自分たちのために盗んだのかもしれないし、他の仲間や、家族のためだったのかもしれない…」シャックスが肩をすくめた。「私はそいつらを殺した。3人とも、素手で」
「私は人間も手にかけた」シャックスははっきりと言った。ケルは自分の中の怒りが混乱に変わっていくのを感じた。「暗黒時代、私はウォーロードだった。自らの暴力を高貴な色で塗りつぶし、必要性を理由にそれを正当化した。その血と腐敗は私に忠誠を誓う人々が作り上げた伝説によって覆い隠された。だが隠しただけで消えたわけでない。その事実はまだここに存在している」彼は自分の胸当てを指で叩いた。「この奥深くに」
いつのまにか影が伸び、星々が空に姿を現し、トラベラーは半分影に隠れていた。
「あるところに1隻の船があった」ミスラックスはようやく口を開いた。「兵士が乗っていたのかもしれない。民間人かもしれない。今となっては分からない」彼はトラベラーから視線を逸らすと話を続けた。「私は部隊を率いて船に乗り込んだ。抵抗する者を全て始末し、降伏した者たちを1か所に集めた」
シャックスはミスラックスのほうを見た。表情のない仮面が無言で疑問を投げかけている。
「我々は捕虜をどうすべきか話し合った。一部の者は警告のために手もとに置いておくべきだと主張した。中には交換の材料にすべきだと言う者もいた」ミスラックスは視線を逸らすと、肩を落とした。「だが、私は若かった。気が短かった」彼は目を閉じた。「私はエアロックを開けた。それが一番簡単な解決策だと思ったからだ」
2人の戦士は再び黙り込んだ。やがて最後の光が地平線の向こう側に姿を消した。シャックスが無愛想にその場を後にし、ミスラックスは怒りと混乱の残骸と一緒に取り残された。逆説的に言えば、それが答えだった。
彼はこの瞬間に至るまでの選択肢の糸を目にした。大いなる機械へと導き、エラミスが苦しんだような運命を遠ざけることになった選択肢の数々。彼とシャックスはどちらも、これまでの人生経験が導き出した異なる結論に反して、受け入れることを学んだ。
すなわち慈悲だ。
「敵は自らを神や王だと思い込んでいる。間違っていると教えてやるのだ」――カリスト・イン
1隻の輸送船が背の低い住宅ビルの外に止まっていた。トラベラーのオーラを反射した光が、いつもと違った影を道の上に作り出していたが、今日は誰もそれに注意を払っていなかった。褐色砂岩作りのその道沿いの住人たちは、運送屋がその建物から家具を運び出す様子を見ていた。
退役した第一世代レッドジャック2体が、通りに大きな音を響かせながらアンティークの寝椅子を運んでいた。その機械音に混じって、楽しそうに彼らを追いかける子供たちの笑い声が響く。レッドジャックたちは昔とは違ってバンガードの記章を身につけていなかった。その代わりに彼らの体には、シリアルナンバーと長期保管会社のロゴがついていた。
「ほら、彼らの邪魔をしちゃ駄目よ」と、作業着を着たがっちりとした背の高い女性が言った。彼女の服にはレッドジャックと同じロゴがついており、片方の袖にソニアという名前が縫い込まれていた。
「順調?」と彼女がロビーの中に向かって言った。
「あとは椅子が2つと、衣装ダンスだ。それと軍用品の件でシティ保安部隊に連絡する必要がある」と、建物の中にいる作業員が答えた。
ソニアは溜息をつくと、2人の子供に警告の視線を送りながら、階段を上って建物のロビーに入った。中に入ると、データパッドに荷物を登録している同僚のマロンと、その近くで手持ち無沙汰にしている2体の第一世代レッドジャックの姿が見えた。
マロンが言っていた軍用品はかなりの量だった。胸の高さぐらいまで積まれた弾薬箱、強弾性ケース、整理されていないボディーアーマーの山、そしてストラップ付きの頑丈な布で一部が覆われている1本の大きな剣。
「全て彼女の部屋にあったものなの?」信じられないといった様子でソニアが聞いた。
マロンは首を振ってそれに答えた。「驚いたろ? まるで兵器庫だ」
「近親者が取りに来るの?」とソニアが質問した。
「彼女に親戚はいなかった」とマロンが溜息交じりに答えた。彼からデータパッドを受け取ると、ソニアはチェックリストを確認した。
「つまり、これはどうなるの? なぜ運び出すの?」ソニアはリストを確認しながら言った。
マロンは肩をすくめて溜息をついた。「ビルのオーナーが部屋の片付けを望んでいるんだ。なんというか… その、エリクスニー居住区から離れたいっていう人が多い。だからオーナーは部屋を空けて売りに出したいんだろう。人ってのはそういう、歴史のあるものが好きなんだ」マロンは頭上のひさしに合図を送るかのように、片手で払うしぐさをした。「ここにはガーディアンが住んでたからな」
ソニアは眉をひそめながらデータパッドから顔を上げた。「私たちのために命を賭けて戦った真の英雄じゃない。それなのにどこかの家主が彼女の部屋を売って儲けようとしてるってこと?」
「俺に言われてもな」マロンは不満そうに言うと、レッドジャックのほうを振り返り、次に運び出すものを指示した。「彼女がタワーに住んでいたら、その部屋は多分、神殿になっていただろうな。だが、彼女が住んでいたのはタワーじゃなかった。だからそうはならない」
彼は返答を待たずに、衣装ダンスを外に運び出したレッドジャックについていった。
自分の考えと一緒にその場に取り残されたソニアは、再びデータパッドに目を落とした。彼女は親指で1つのアイテムをなぞり、左、そして下へと画面をスワイプした。
[削除しますか?]
ソニアは緑色のチェックマークをクリックした。彼女は少なくとも1つのアイテムがどこにあるべきかを知っていた。保管庫の中に置いておくべきではない。いずれ解雇されることになるかもしれない。あるいは、自分から辞めるか。
スロアンもきっとこうしてほしいと望むはずだ。
「汎用性が高い。それ自身のみでは、何の意味もない空の管にすぎない。だがそれこそが無駄を排除した美しさでもある。重要なのは、それに何を入れ、それをどう活用し、何に使うかだ」――バンシー44
金属の階段に分厚いブーツの音を響かせながら、サラディン卿は中央タワーの間にあるキャットウォークを下っていった。バザーは思いのほか静かで、間もなく始まる外交的会談の戦略を練る時間を彼に与えてくれた。
「今回の決定に当たり私の意見を…」サラディンは歩きながら考えをまとめていた。「議会に追加の要求を…」彼はうなると首を振った。「司令官、フューチャーウォー・カルトを頭数に入れるのはどうかと…」彼はうなった。どれも違うような気がする。
サラディンは足を止めてシティを見渡した。デジタル式の輝く霧によって街全体が覆い隠されている。彼は目を閉じ、首を振ると、少し時間を取って気持ちを落ち着かせた。ここには、戦いの音も、銃声も、悲鳴も存在しない。それが存在するのは彼の頭の中だけだった。
「ザヴァラ。友として言いたいことがある」とサラディンは再び話す練習をした。そして目を開けてトラベラーを見ると、納得したようにうなずいた。
「もっと大きな声で言わないと司令官には届かないぞ」
突然介入してきた自分以外の声に促されてサラディン卿が振り向くと、不快なほど近くにオシリスがいた。失望の仮面に隠されたサラディンの感情が驚きから困惑に変わった。「盗み聞きとはらしくないな、ウォーロック」
「馬鹿なことを言うな」とオシリスは言うと、ゆっくりとサラディンに近づいた。「お前の独り言は耳のついている者なら誰にでも聞こえる。私はたまたま近くにいただけだ」彼は手を広げて説明すると、背中で両手を組んだ。
「これから会談がある」サラディンはそう言うと、不意にその場を後にしようと振り返った。オシリスが横に移動し、サラディンと階段の間に入ると、鉄の豪傑が迷惑そうな表情をした。
オシリスは注意深く両手を挙げた。「頼む、サラディン卿。少し時間をくれ」
サラディンは胸の前で両手を組んだ。彼の眉間のシワが苛立ちを現していた。
「司令官に協力を申し出るつもりなら、今はやめておいたほうがいい」オシリスはそう説明すると、サラディンの肘に手を置き、彼を道の端に誘導した。
「ザヴァラ司令官は現在、多大なストレス下に置かれている」オシリスは続けた。「お前は自分なら力になれると思っているだろうが…」彼は眉を上げると、横目でサラディンを見た。「恐らくそれは間違いだ」
「遠回しな言い方はやめろ」サラディンが足に力を入れた。「何が言いたい?」
「最後にーーお前の言い方を借りれば――盗み聞きをしたのはいつだ?」
サラディンが苛つきながら言った。「盗み聞きなどしない」と彼はうなった。
「だとすれば、お前が他のガーディアンたちにどんな風に言われているのか知らないのも当然のことだな」オシリスが優しい声で申し訳なさそうに言った。その声色は明確に彼の気持ちを表していた。これは悪いニュースであり、彼は悪いニュースの伝達者になりたくなかったのだ。
サラディンは何も言わなかった。彼は文句を言うきっかけを失っているようだった。オシリスは話を続けた。
「我々のような信念を持たない多くの者は、最近の女帝カイアトルとの重大局面での、お前の決定に疑問を抱いている」オシリスはサラディンに顔を近づけると、秘密事を共有するかように静かに言った。「お前が司令官暗殺の首謀者だと考えている者もいる」
「鉄の豪傑はそんなことはしない」サラディンは声を震わせながら言った。「私は――」
「分かっている」オシリスは素早く冷静に言った。「ただ、お前のことをよく知らない者もいる。お前は声を大にしてカバルとの休戦に異議を唱えた。彼らはそれを考慮して実に説得力のある議論を行っている」
サラディンは目を閉じると、ゆっくりと息を吸った。銃声、叫び声、そして悲鳴が、これまでないほど大きくなっている。もしかしたらそれは彼の心臓の音なのかもしれない。「それならなおさら記録を修正する必要がある」
「そのためにシティに来たのか? 記録を修正するために?」オシリスが声を荒げた。「数分前まで私は、お前がここに来たのはザヴァラに協力するためだと思っていた。そうじゃなかったのか?」
サラディンはザヴァラのオフィスのほうを見ると、拳を握りしめた。「ラクシュミ IIは――」
「ラクシュミのことは任せろ」オシリスはそう言うと、再びサラディンの腕に手を伸ばした。今度は鉄の豪傑は動かなかった。「勝てる戦い以外は避けろ、サラディン卿。私は彼女の扱い方を心得ている。お前の力が再び必要になる時がいずれ来るだろう。だが今はその時ではない」
サラディンはオシリスを厳しい目つきで見た。今にも口から文句が出てきそうだったが、彼はその言葉を飲み込んだ。彼はうなだれた。
「ありがとう、オシリス」サラディンは信念を打ち砕かれたように弱々しく言った。「お前は真の友人だ」
「少量を施し、少量を取ればいい。ただし、取るほうは少し多めだ」――放浪者
放浪者はバーに入った瞬間、トラブルの匂いをかぎつけた。彼の直感はすぐにその場を離れるべきだと訴えたが、著しく地味な格好をしたフードの人物が、緊張した様子で自分の近くに立っていることに気が付いた。
顔はフード付きのクロークで隠されていたが、隅にいる人々から発せられる怒号を聞き漏らすまいと、体を横方向に傾けていた。
「誰かさんに落ち着くように言え」と放浪者は横を通り過ぎながらつぶやいた。「俺が何とかする」
「落ち着いてください」上品な声がその人物のクロークの下から響いた。
「分かった」その人物は溜息をついたが、その声はまだ緊張していた。
放浪者が群衆の中をかき分けて進む。武装した者、叫んでいる者、さらにはその両方が当てはまる者がいた。多くが最後のカテゴリーに属しているようだ。彼はニヤリと笑った。経験から、無口な者こそ誰よりも危険であることを知っていたからだ。
人だかりの中心に辿り着くと、3人のエリクスニーがテーブルを囲んで座っていた。彼らは自分たちを取り囲む群衆を意識的に無視していた。彼はためらうことなく群衆をかき分けると、一番大きなエリクスニーが座っている椅子の肘掛けに野良猫のように座った。エリクスニーが不満気に声を上げたが、放浪者はそれを無視してドサリとテーブルの中央にトラストを放り投げた。
放浪者は群衆のほうを振り返った。「一体何にそんなイラついてるんだ?」
「どうやら無線はあまり聞かないようだな」と誰かが言い、群衆が笑った。
「俺のお気に入りの場所はどこも電波が届きにくいんだ」と放浪者が言った。「何があったか教えてくれ」
群衆がいっせいに話し出し、非難の声が不協和音を作り出した。
「おいおい!」放浪者が叫んだ。「偽物の夜ばかりを眺めている連中がいるみたいだな」と言うと、彼はエリクスニーのほうを見た。
「今の騒がしい声で聞き取れたのは、どうやら誰かが道具をなくしたってことだ。だから質問させてくれ」と彼は言った。「自分の持ち物じゃないものを持っていったか?」
大きなエリクスニーが口を開いた。その声は低く落ち着いていた。「我々とお前たちの間で考え方の相違があった。どこまでが自給で、どこまでが共同物資なのか」彼は肩をすくめた。「我々は学んだ。だから埋め合わせをした」
放浪者はうなずいた。「新天地での生活にこういう問題はつきものだな。それにここにいる連中は、サブマシンガンのスペアパーツを探すために隣人の道具箱を漁るような奴らばかりだ」
声が聞こえてきた。「待て、私のサブマシンガンがないぞ――」放浪者が手を上げた。
「それと、この長い夜のことで奴らを批判するのは筋違いだ。どうやら、この暗闇のせいで脳みそが縮んじまった連中がいるようだ。俺が知ってる限り、ミスラックスはバンガードと協力してベックスの件を調べている」と彼は言った。
エリクスニーは少し緊張がほぐれたようだった、しかし放浪者が指を1本立てた。「個人的に1つだけ質問がある」と彼は言った。
「俺たちは長い間戦ってきた、お前たちと俺たちがな。そんなことは誰でも知ってる。どちら側も大量の血を流してきた。だがそれとは別に、昔のお前たちの仲間が飢えに飢えていたという話を聞いたことがある」
群衆が押し寄せ、体の大きなエリクスニーが緊張した様子で体をこわばらせた。
放浪者は身を乗り出した。その声は重々しかった。「お前たちが歩くこともままらない子供を食ったっていう不愉快な噂も流れてる」
エリクスニーが椅子を引いて立ち上がり、群衆が息をのんだ。放浪者はその場で立ち上がり、自身よりも1メートルは背の高いエリクスニーを見下ろした。
「幼い子供にそんなことはしない!」エリクスニーが叫んだ。「絶対に」
放浪者がうなずいた。「他はどうだ?」
エリクスニーは群衆を見ると、その大きな頭を放浪者に近づけた。彼の声は落ち着いていた。「我々のような年寄りは、つまり最初から戦い続けてきた者たちは… そのとおりだ。生きるためにお前たちの戦士の死体を利用したこともあった」
「戦争だった」と彼は言うと、放浪者の胸をかぎ爪で突いた。「しかもお前たちは肉でできている」
放浪者は笑った。「聞こえてるぞ、兄弟」と彼は言うと、エリクスニーのかぎ爪を見た。「そいつを向けられたせいで、そいつをガーリックバター風味にしたらどんな味がするかってことしか考えられなくなった。旨そうだ!」彼はその巨大な生物に向かって体を傾けると、自分のひび割れた唇を舌で舐めた。
エリクスニーはその小さな男を品定めしてから肩を落とした。「たがさっきも言ったように、大昔のことだ」と彼は言った。「我々は今ではハウス・オブ・ライトだ。これからもそれは変わらない。我々はお前たちと和平を結んだ」
放浪者が手を伸ばし、エリクスニーの胸元を叩いた。「そのとおりだ」と彼が言うと、エリクスニーが椅子に座った。「とは言え、悪しき過去を消せるわけじゃない」と彼は言うと、群衆のほうを見た。「だが今その話を持ち出すのも間違っている」
群衆から不満そうな声が上がった。彼らの戦いは既に終わっていた。
エリクスニーが肩をすくめた。「ミスラークスから、二度と人間を食べてはいけないと言われている」と彼は静かに言った。
放浪者がうなずいた。「ああ、俺もザヴァラから同じように言われてる」
エリクスニーが吹き出し、咳き込みながら笑った。放浪者もそれに釣られて笑った。彼はテーブルから銃を拾い上げると、群衆を追い払いながら空いていた椅子を引き寄せた。
「場所を空けてくれ」と彼は言った。「こいつらはちょうどトランプで負けそうなとこなんだ」
目の前の扉は全て開かれている。
ヘレナは怪訝な顔をしながら廃墟の割れた窓をのぞき込むと、もう一度データパッドの座標を確認した。彼女がシティのこの区画に来たのは初めてだった。
「ママ?」と彼女が不安げに呼ぶと、その声が空間にこだました。
「こっちよ」と母親が答え、ヘレナは驚いた。
彼女が錆びた扉を手前に引くと、一段下がった場所にあるコンクリートの部屋の中で、母親が長いテーブルの上に置かれている道具を一心不乱にダッフルバックに詰め込んでいた。部屋の向こう側の壁の近くでは、1人の女性がプラスチック製のシートを丸めていた。部屋の中は化学薬品のような匂いがする。
大きな黒いバッグを背負った男が、コロンと酒とすえた汗の臭いを漂わせながら彼女を押しのけるようにして横を通り過ぎた。
ヘレナは、テーブルの上にある小型のシグナルジャマーがオレンジ色に瞬いていることに気づいた。その後ろにいるエクソは、鉄骨の走る床の裂け目に腰まで沈み込んでいた。
「ピッタリだ」と彼は言いながら体をくねらせると、その裂け目にさらに深く沈み込んだ。「ただ、そんなに遠くには行ってないだろう。私が彼を見つける」と言うと、彼は穴の中に姿を消した。
「何があったの?」とヘレナが質問した。
「質問はなしよ」と母親は言うと、顔にかかっていたブロンドの髪をかき上げた。「早く移動しないと」彼女は部屋の向こう側に向かって頷いた。「その山を持っていってちょうだい」
ヘレナは警戒するように腕を組んだ。「ママ、ここで何をやってるの?」
「今は説明している時間がないのよ」と母親はぴしゃりと言った。「あなたは状況が分かってない。その窓から奴らがのぞき込んでいたのよ。ラーメン屋での会話もあなたは知らない」
ようやく母親が顔を上げた。瞳の中で危険な感情が渦巻いている。「奴らは闇を利用して私たちの視界を奪うつもりよ。そうなってからでは手遅れなの。だから手を貸してちょうだい」
ヘレナは隅に積まれているガラクタにゆっくりと近づいた。青い液体が染み込んだタオル。ゴムチューブ、奇妙な金属のスクラップ。「臨時作業員」と書かれたラミネート加工されたカード。
彼女は小さな声で言った。「ママ、何をやったの?」