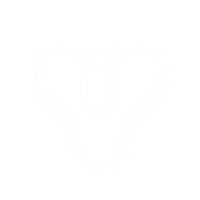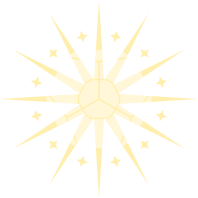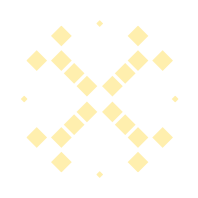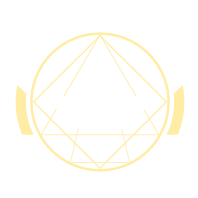- 「過去は過去でしかない。戻ることはできない。今できることは、皆にふさわしい未来のために、刃と血でもって戦うことだ」――バルス・カウトゥール
- 「船が欲しいのか? 艦隊の友人に頼めば、また失われたリージョナリーを回収してくれるだろう。もっとも、見つかりたくないというのなら話は別だが…」――スパイダー
- 「多くの勝利は無謀に思える。それでも前進するのだ。一歩ずつ前へ、一つずつ傷を負いながら。手に入れられるまで進み続けるのだ」――女帝カイアトル
- 「ガウルはその虚栄心のために死ねと命令した。私は帝国のために共に戦ってくれと懇願する。選ぶのはお前だ」――女帝カイアトル
- 「同志よ、思う存分食べよう。トロバトルは失われたかもしれないが、その精神は我らの伝統に生き続けるだろう」――女帝カイアトル
「過去は過去でしかない。戻ることはできない。今できることは、皆にふさわしい未来のために、刃と血でもって戦うことだ」――バルス・カウトゥール
カウトゥールは、ヴァラックの花の柔らかい繊維を手でなぞりながら歩く娘を見ながら笑みを浮かべた。彼女が通った後には、生物発光性の花粉が日没の光の中を舞う。カウトゥールは目を閉じると大きく息を吸い込み、雨期の始まりを告げるその強い香りを大いに楽しんだ。
「どうして私をここに?」彼の娘が聞いた。娘が話している間も、カウトゥールは記憶にある娘の姿を思い出していた。小さな子供が明るい色のローブを身に纏いながら飛び回っていた。彼が目を開けると、大きなバトルスーツを身に纏った成熟した戦士の姿がある。
彼は彼女の腰にぶら下がっているメッキ加工されたブロードソードを示した。「今朝、厳しい訓練を行なったと書記官から聞いている」
「私の剣は飽くことを知らない」と彼女は答えると、武器を抜き、ふざけてそれを父親に向けた。彼女が笑顔を若干曇らせた。「直接見ればよかったのに」
カウトゥールは努めて平静を装った。「すぐにその機会は訪れる、タナム」
タナムは剣を鞘にしまった。カウトゥールは甲冑で乾いた草と花弁を踏み潰しながら娘に近づくと、肩に手を置いた。
「それで結局何の用だ? 戦争前夜に故郷の思い出話か?」とタナムは聞いた。
彼女の父が笑った。「そんなに思い出が大切か?」
タナムがしかめ面をした。「毎日、懐かしく思ってる」
「誰でもそうだ」と深いため息をつきながら彼女の父は言った。「とにかく。お前にはそれを直接目にできる最後の機会を与えたかった」
タナムは振り返ると眉をしかめた。「最後の機会?」
「もう十分だ」とカウトゥールは言った。体中の骨に低い音が反響し、景色が変わった。遠くの山が波打ちながら空まで伸びていき、花々が突然、浮遊して泡の雲へと姿を変えた。世界が不明瞭になり、光と物質が粘度の高い液体のように、大きくなる空の裂け目へと吸い込まれていき、それを完全に飲み込むまで影が大きく広がっていった。
彼らはバルバトス・レックスの中で目を覚ました。船はまだ星々の中を進んでいた。彼らの手は錆びた剣の持ち手を握りしめていた。1人のサイオンが近くに立っており、3人を繋げていたサイオニックエネルギーのおぼろげなツタが姿を消した。
カウトゥールはサイオンに向かってうなずいた。「2人にしてくれ」
「理解できない」と2人きりになるとタナムはすぐに言った。
カウトゥールは剣を高く構えた。「4世代前、この武器は我々の一族に帝国内での居場所をもたらした。その歴史は、精神の旅の中で、強固な中核的役割を果たしている」彼はそう言うと、刃を慎重に眺め、その重さの配分を確かめた。「だが歴史とは勝者の贅沢品に過ぎない」
カウトゥールはその武器を両手で持つと、それを半分に折り、ガントレットでその破片をすり潰した。
タナムは少し後ずさりした。「父さん…」
「これが生まれた世界は今や姿を消した」とカウトゥールは続けた。「もはや後ろを振り返っても故郷はない。それは今、そびえ立つ山を越え、大いなる海原の向こう側の、遙か遠く前方に存在している」
タナムはうなずいた。「我々はカバルだ。山を喰らい、海を飲み干す」
カウトゥールは体を乗り出した。「だが、都合の良い空想をして飢えを癒やしているようでは、この未来は実現できない。だから我々がこの手の思考に興じることは二度とない」
タナムは体をこわばらせた。「なるほど」
「太陽系には我々の仲間が眠っている。だが、彼らは我々の街が魂の炎で焼かれる姿を見ずに済んだ。故郷の思い出を慰めとせず、その傷の記憶を怒りの糧とするのだ」
タナムはうなずいた、ただ感情のしこりが彼女の口を開かせた。「奴らを恐れているのか? 太陽系の戦士たちを」
カウトゥールは誇らしげに笑うと、娘の手を取った。「そんなことはない。なぜなら、タナムが一緒に戦ってくれるからだ。タナムの剣は飽くことを知らない」
「船が欲しいのか? 艦隊の友人に頼めば、また失われたリージョナリーを回収してくれるだろう。もっとも、見つかりたくないというのなら話は別だが…」――スパイダー
帝国の戦士たちよ。帝王はお前たちの力を必要としている。
ガウルは我々を失望させ、レッドリージョンは血でその代償を払うことになった。お前たちは散り散りになり、見捨てられ、敵に追い詰められた。お前たちは帰郷を望んでいる… だがトロバトルは今や我々のものではない。
帝国の連合艦隊が太陽系に侵入した。我々のもとに戻って来い、同士たちよ。我が軍に再び加わり、崩れた帝国の再建に力を貸してくれ。名誉と力をもって、我々は帝国の歴史に新たな章を書き記すことになるだろう。そして――
センチュリオンは通信機器のスイッチを切った。洞窟内に作られた間に合わせの鉄屑の扉から外を覗き込むと、岸辺の上空に浮かぶ複数の惑星が目にとまった。まるでラベンダーの海の中で眠るゴリアテのようだ。
スクリーブのさえずりがこだまし、センチュリオンの注意を引きつけた。彼女は扉を閉じると、スラグライフルに弾を込め、大きくなるその音に耳を澄ます。ようやく静寂が戻ってくると、彼女は壁に寄りかかり、力なく武器を落とした。その銃は彼女の家名のもとに支給され、兄弟の血を浴びた。それが今では、寝ずの番をしている空のヘルメットの横で、色あせた記念品として埃をかぶっていた。
メッセージが彼女の頭の中でもう一度再生され、彼女はうなり声を上げた。王冠。ガントレット。杯。金属を熱で拷問し他の物に作り替えたにすぎない。そこには誰かの意志が存在している。帝国は彼女をどんな形に作り替えたのだろうか? 圧力スーツを通して古いケーブルが低い音を立てながら共鳴している。そのスーツは筋肉の萎縮した彼女の体には、見事なほど合っていなかった。
彼女はガントレットを叩きつけて通信機を粉々に破壊した。スレッシャーのエンジンが遠くでうなり声を上げ、無数のリージョナリーたちがそれに答えるように歓声を上げた。彼女はしゃがみ込むと、深い眠りへと落ちた。
「多くの勝利は無謀に思える。それでも前進するのだ。一歩ずつ前へ、一つずつ傷を負いながら。手に入れられるまで進み続けるのだ」――女帝カイアトル
「汝に幸あれ、帝国の戦士よ」と女帝カイアトルは、負傷したレッドリージョン・センチュリオンに近づきながら言った。静かに丸窓から外を凝視していた兵士は、彼女の声を聞いて飛び上がった。彼は反射的に振り返ると、痛みに顔をしかめた。カイアトルは、彼の右腕全体と胸部を包み込んでいる黒ずんだ合成繊維に目を落とした。その腕は傷つき、ボロボロだった。彼女はこのカバルが再び戦場に赴くことはないということをすぐに理解した。
「陛下!」と戦士は言うと、怪我をしていないほうの拳を自分の胸に当てた。カイアトルは敬礼を返した。
女帝は患者のデータを表示するモニターを一瞥した。「ヴァルツイの子、ヴァラスト」と言うと、彼女は丸窓から外を見た。太陽の輝きがその目に映る。「帝国はお前たちレッドリージョンのために戻ってきた。だがお前の心は重いようだ。何を悩んでいる?」
ヴァラストが視線を逸らした。「申し訳ない」
「謝る必要はない、我が兄弟よ」とカイアトルは言った。
ヴァラストはため息をついた。「何年もの間、その日を生き抜くことだけを考えてきた。常に戦いの中に身を置き続けて。だが今は…」彼はそこで言葉を詰まらせると、ベッドのシーツを掴んだ。生地は安っぽかったが、彼がこの数年間で触れてきた何よりも柔らかかった。
「長い間、戦いの中に身を置き続けると、平和を苦痛に感じることがある」とカイアトルは言った。
ヴァラストはシーツを離した。「私は自らがアクリウスの生まれ変わりだと信じ、一族のために新たな太陽を手に入れようとしてきた」彼は丸窓の外に視線を移す。「だが失敗した」
カイアトルが笑みを浮かべた。「その物語は昔から私のお気に入りだった」彼女は椅子を引き寄せて座った。「その物語は昔と今では少し伝えられ方が違う。知っているか?」
ヴァラストは首を振った。
「昔のものは、今のものほど有名ではない。だが幸運にも子供の頃に私はそれに触れることができた」と言うと女帝は続けた。「アクリウス以前に、3人の戦士たちが大いなる山を登り太陽を手に入れようとした。だが恐ろしい怪物が彼らの前に立ちはだかった」
「最初の戦士は、その怪物を出し抜こうと影の中に潜り込んだ。だがそれでも怪物は彼の匂いに気づき、戦士をひと噛みで食い殺した」
「二番目の戦士は怪物から逃げるために、風を操る機械を作って空高く飛んだ。だが、気まぐれな風は考えを変え、怪物の胃袋へと彼女を放り込んだ」
「三番目の戦士は真正面からその怪物に立ち向かった。その手にはセベルスが握られていた。結局は彼女もその鋭い牙の餌食になった。だがその刃は血の味を知ることができた」
ヴァラストが顔をしかめた。「全員失敗したのか?」
カイアトルはその質問の意味を考えた。「最初の2人に関しては、そのとおりだ。彼らは戦いを避けることを考えた。だが3人目の戦士は名誉ある死を遂げた」
ヴァラストはしばらく考え込んだ。「負けても、彼女は敵に爪痕を残した」
カイアトルはうなずいた。「そして再び彼女のような者が立ち上がり、怪物はさらに死に一歩近づいた」
「他にも立ち向かった者がいるのか?」とヴァラストは質問した。
「当然だ!」とカイアトルは叫んだ。「彼らはカバルだ、そして太陽は彼らにとって手に入れるべきものだった。何度も繰り返し、カバルの強大な戦士たちは敗北し続けた。だがそのたびに新たな傷を負わせ、ついにある戦士がトドメを刺した。その戦士こそがアクリウスだ」
ヴァラストが顔をしかめた。「子供の頃から、アクリウスが私の英雄だった…」
「彼が英雄であることに変わりはない」とカイアトルは言うと、ヴァラストの手を握りしめた。「だが、最初に傷を負わせた戦士も立派な英雄だ」
ヴァラストは目を輝かせながら彼女の手をきつく握りしめた。「陛下、感謝する」
カイアトルは首を振った。「我が兄弟よ、礼を言うのは帝国のほうだ」
「ガウルはその虚栄心のために死ねと命令した。私は帝国のために共に戦ってくれと懇願する。選ぶのはお前だ」――女帝カイアトル
(強力な電撃が木を砕き、ネッススの戦場にいる朱色に染まった生物たちに降り注ぐ。)
サイオンのヴァトクはかつて臆病者だった。それも一度きりの話ではない。彼はベックスタワーの影の中で体をこわばらせながら弾のないライフルを握りしめ、これまでの自分の軽率な撤退の数々を思い出していた。
彼はリーフの砕岩群で、ワイヤーライフルの縦射と魂の炎の集中砲火から逃げ出した。
彼は容赦なく前進し続けるクロノマトンたちから逃げ出した。水銀の砂漠のど真ん中で彼の体液は今にも沸騰しそうだった。
中でも特に、光の力が封じ込められた外殻を持つ、太陽系の不死のガーディアンたちには近づかなかった。彼が何度も命拾いをしているうちに、やがてリージョンが新たな目標を見つけ、彼を戦場へと連れ戻した。リージョンは彼が弱いことを知っていた。だが数多くのリージョナリーを失った彼らには他に選択肢がなかった。
(渓谷に雄叫びが響き渡り、煙を上げるスレッシャーが回転しながら虚無へと飲み込まれる。)
自分が生き残ったことに対してヴァトクに罪の意識はなかった。サイオンにとって、生存こそが自らに許されている唯一の権利だった。手に入る名誉など存在せず、昇進することもなく、富を築くこともできない。リージョンが与えてくれたのはその命だけであり、ヴァトクはそれをできる限り長続きさせたいと考えていた。
ただその状況は、ガウルが原子レベルまで融解し、宇宙の彼方へと霧散したことで一変した。ウォーロックの時間デバイスを用いた計画も失敗し、リージョンの勝利を約束するオールマイティは、冷淡な神によって小石のように投げ捨てられてしまった。
そして今、女帝カイアトルが、ヴァトクが想像もしていなかった「自由」という約束を手にその姿を現したのだ。強大な帝国はフリゲートと輸送船で構成された艦隊を率い、世界と世界の間に存在する隙間を破壊的な力で埋め尽くした。ヴァトクに人生で初めて、ただ生き残るためだけでなく、生きるための目的を選ぶ権利が与えられたのだ。
(コロッサスが喊声をあげ、それに応じるようにスラグライフルの不協和音がこだまする。)
戦いは彼を飲み込み、彼の同胞たちは命を落とした。彼には自分が助かる方法が分かっていた。光の当たらない大地の裂け目に逃げ込めば身を隠すことができる。彼はそこなら自分が生き残れることを知っていた。
(ヴァトクはライフルをリロードすると、女帝への忠誠の誓いを口ずさんだ。)
彼はかつて臆病者だった。だが今は違う。
「同志よ、思う存分食べよう。トロバトルは失われたかもしれないが、その精神は我らの伝統に生き続けるだろう」――女帝カイアトル
要約
以下に、カバルのデータファイルを翻訳したものを記録する。このデータはザヴァラ司令官の指示のもと行なわれた、ヘイストック作戦で入手したものだ。このログでは、解読に成功したファイルの一つを取り上げる。データコンテンツの抽出とさらなる解読の試みに関する詳細報告は、ログR11312を参照。
どうやらこのファイルには、カイアトルに敬意を表することを目的とした公的な集まりで振る舞われる食事のレシピが書かれているようだ。ここで示されている食材は、様々な種類の古代のカバル書にも記述があった。帝国の経済史を解読したところ、対象の素材は安くて避けられがちなものであることが示唆されている。このレシピは古く、かつ階級の低い者が書いたものであり、売れ残りの商品を利用して腹の足しになる美味しい料理を作ろうとした、貧しい労働者たちの独創的(かつ挑戦的)なアイデアの一つだと思われる。
カイアトルが公的な集まりのメインディッシュにこれを選択したところに、彼女の意図が感じられる。帝国の一般民との繋がりを示すことで、絢爛豪華なカルス時代や功利主義のガウル政権とは違うことを証明しようとしているのだろう。
ここで留意すべきなのは、解読の大部分は成功したが、一部のデータに損傷が見られたということだ。クリプトアーキのコメントは理解するための補助的な役割に過ぎない。翻訳にはまだ曖昧な部分があるが、可能な範囲で推測して訳出ししている。
— [CBXパーサーエラー]
— 溶剤の混合物が混ざるまで[CBXパーサーエラー]する。
— 表面が裂け始めるまでアトロトルの腱を叩いて柔らかくし、溶剤の混合物の中に浸して寝かせる[36–84時間置く。ここで言及されている単位は未知のもので、控えめに見積もっている]。
— [黒い四角形]にするため、柑橘類を潰して、ふるいにかける。果汁を捨て、果肉と苦みのある皮を取っておく。塊が[CBXパーサーエラー]状になって焦げるまで、最高温度で固形物を[キッチンバイス? 翻訳に自信なし]で圧縮する。それを天日干しにする。
— 腱が伸びて柔らかくなったら、溶剤から取り出して海水で洗う。リボン状に薄切りにして置いておく。
— アトロトルの腰肉を[回転装置]に引っかけて、香りが出るまで石に叩きつける。
— 繊維を切るように腰肉を四角状にスライスして置いておく。
— 大きな鍋に、水、シャウラック油、(季節に応じた)根茎の混合物を入れる。沸騰させ、腰肉と腱を加える。[CBXパーサーエラー]が沈み、液体の表面全体が光沢のある黄土色になるまで煮詰める。
— それから数時間[CBXパーサーエラー]し、お玉の背に[CBXパーサーエラー]までスープにとろみを出す。
— 厚く切った[黒い四角形]と一緒に盛り付ける。