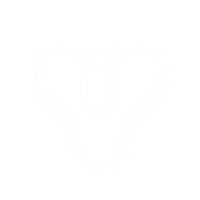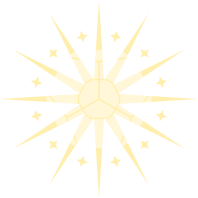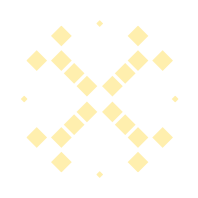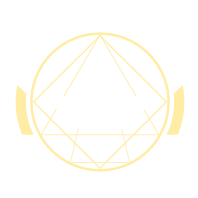▬
レネゲードからの手紙
I: 結果への結論 
我々はそれぞれ自分の道を歩いて独自の進路を見つけなければならず、その一歩一歩が、己の送ってきた人生と自らの決断に特有のものである。それでも皆つながっている。全員。自らの選択によって。結果によって。運と、自らの歩みと決断によって。個々の人生は、過去の自分、今の自分、こうであるはずだと主張する自分、こうなりたいと望む自分、つまり我々個人の存在の各段階によって形成される。あるいは自分にそう言い聞かせながら、自分自身の物語の中で道に迷っている。実際には「私」というものはなく、個の存在もない。過去にもなかったし、未来にもない。お前。俺。お前のファイアチームと友人。お前の敵と味方。すべての生命が他の生命とともに動き、衝突し合い、良くも悪くも、一つの生涯(複数の生涯?)を形成する。
俺は、このことを理解するには長い時間が必要だった: 俺たちは誰も孤独ではない。俺はそれを「最初の理解」と呼ぶ… 少しばかり内輪のネタだ。だがお前には分かるかもしれない。いや、分かってくれると確信している。だからこうしてお前に手紙を書いているのだ。だからこそ、大局から隔離された状態で人生を過ごしてきた俺が、単純な賭けに自分のすべてを託すリスクを冒すんだ。お前は他の人とは違う。つまり、優れているということだ。俺よりも。彼ら… 闇を引きつける者たちよりも。
どうしても、これをお前に理解してもらいたい。お前の道はお前自身のものではない。共有されているんだ。それには影響力がある。それは目に見える形と見えない形の両方で結果を生み出す。そして今お前が歩いている道は… 危うい。お前自身にとって。お前にそれが見えていようといまいと。他の者たちにも影響を及ぼす。お前が影響を与えるかもしれない、というより、与えるであろう人たちにとって危険だ。これから起きる衝突。想像もされていない新たな道。お前自身の人生の狭い視野を超える、周囲への影響。これについて考えてみたことはあるか? 俺がこう聞くのは、お前を動揺させるためではない。お前は道を見つけるだろうし、俺は判断が必要になる時まで判断を差し控える。俺がこう聞くのは、善悪や大小を問わず、我々の意図の副次的な影響について考えている時こそ、俺たちは最良の状態にあるからだ。それこそが、今ここで俺が求めていることのすべてだ…
お前にはしっかり考えてほしい。
これまでの行いについて。そしてまた、これからの行いについて。
お前は、自分が誰だと主張している? 誰になりたい? そしてその答えの波紋はどのように広がって、周囲の人々の人生に触れるのか?
お前の人生と行動について考えてみろ。この先もずっと考え続けるんだ。
お前が引き寄せる危険を俺は追いかけてきた。そこから得た知識を活かして、手を貸せる場面では手を貸そう。俺たちが出会うことは決してないが——お互いに自分たちを追い詰めるすべてに立ち向かおうとする以上、少し離れたところで道が交差するだろう——が、今この瞬間から、我々の人生はがらりと変わる。
我が名はシン・マルファー。ガーディアンであるお前こそが、希望だと信じている。人からはそれが嘘だと聞かされていたが。
——S。
II: 偉大な征服者、英雄への恐れ 
かつて、ある男を知っていた。彼は怪物だと言われていて、俺も長い間その意見に同意していた。しかしもう、「怪物」、「野獣」、「他の者」といった呼び名がほのめかす力を彼に与えることはしない。恐怖は人を怯えさせ、弱らせ、支配する。怪物なんてものはいない。何らかのショックを受け、誤解している者がいるだけだ。それでも恐ろしいことには違いない。だが、彼のことは知り得る。征服し得る。力を持つには値しない者だ。黒い服を身にまとい、罪の重さによって歪められたその男は、希望を武器として用い、杖として人に差し出すと公言した。希望の光は彼にとって偽りの約束だった。「希望ほどはかないものはない」と彼は言った。そしてそれはそのとおりだ。希望の喪失ほど身にこたえるものはない。しかし彼は他のことも知っていた。それは彼が決して誰かと共有しようとせず、彼の言葉や行い、そして存在そのものの不気味な脅威によって曇らされた真実だ。いかなる真実か?
希望は不滅だということだ。
薄れることはあるかもしれない。存在の痛みと苦しみの中で失われることもあるかもしれない。しかし希望は常に存在する。どこかに。丸見えの状態、あるいは視界から遠く離れたところに隠されているかもしれない。
恐怖を強く求め、出会ったすべての者に呪いを与えたその男は、今お前の訓練の場となっている生死を賭けたゲームを極めた。お前を始めとするガーディアンが他の光の覇者に対して力を行使するのを見ると、彼がライバルを気楽に始末していたという話を思い出す。お前が彼と同じだと言いたいわけではない。誰も彼と同じにはなれない。シャックス卿も違う。ザヴァラ司令官も違う。彼の「影」や、彼の称号を名誉の印のように身につける者たちも、すべて違う。「ドレドゲン」は「奈落の底」という意味の古語だ。人間ではない。ハイヴでもない。ただの忘れ去られた深遠な領域であり、彼の罪に対して安らぎを与えるべく、ろくでなしの周りに巻き付けられた不確実性と恐怖の層にすぎない。それは「無」を意味する。虚ろだ。彼の道もそうだ。お前が勝利を味わい、クルーシブルの恐怖心の炎を受け入れているとき、自分自身と向き合ってみろ…
その挑戦、あるいは「敵」に与える苦しみに、お前は喜びを覚えるのか? 戦闘において自分に匹敵する者に立ち向かい、自分の力の限界を試す興奮に、お前は大きな喜びを感じるのか? 相手の威勢をくじくことに快感を覚えるのか?
その答えをじっくり考えてみろ。自分の行いの中で真の自分を模索してみたまえ。お前は英雄なのか、征服者なのか? 片方はもう片方を抑えつけられるが、その逆はありえない。
私見だが、お前にはその両方の素質が見て取れる。
——S。
III: 内なる炎 
どんな感じだった? クロウを追って、入り組んだ荒れ地のリーフを進むのは? バロンを一人ずつ追いかけ、お前の友人を殺した殺人鬼を追跡するのは? 高潔な行為か? あるいは純粋に、「正義」への熱意に突き動かされた、怒りの復讐か?
俺はその感情を知っている。その感覚を知っている。喪失感に続いて、報復によってしか埋められない大きな穴が現れるんだ。俺はその穴を二度感じたことがある。一度目は、俺の知っていたすべてが灰になった時だ。俺はほんの子供だった。あの苦しみに終わりはあるのか、あるとすればいつなのか、知る術はなかった。ジャレンという3番目の父が、苦しみの向きを変える手助けをしてくれた。目的を与えてくれたんだ。狩りの仕方を教えてくれた。生き延びる術を教えてくれた。報復の仕方を教えてくれた。
気分が良かった。内なる炎が灯るみたいで。少なくとも俺はそう思った。実際には、「良かった」のは苦しみが曇ったからにすぎず、自分が集中する方向が変わったことによって、喪失の重荷が覆い隠されただけだったのだ。なぜ悲しむんだ? なぜ打ちひしがれているんだ? 怒ればいいじゃないか。だから俺はそうした。長い間。
ジャレンが死んだ——後に怪物となる悲しみの武器に殺されたのだ——後、かなり長い間、俺は彼を憎んだ。俺は再び一人になった。途方に暮れた。何の道しるべもなくて。捨てられた気がした。自分以外には、すべてを失ったことで残された穴しかなかった。
俺の人生を二度に渡って壊した男。最初は故郷パラモンを焼き払い、続いて、我が師であり、まだ荒野を歩いていた父を殺害することによって。しかし俺はただの若者で、怒りと恐れを感じているだけだった。報復——内なる炎——は慰めではなく、重荷だった。その本質を見抜くのに必要な自信がなかったからだ。
影で行動を起こした殺害者、俺を置き去りにしたジャレン、この世界、途方に暮れている自分自身、俺を信じてくれないジャレンのゴーストに対して、俺はずっと怒り続けた。怒りがすなわち俺だった。短い間、お前がそうであったように。俺が知りたいのは、果たしてお前は考えたことがあるのかということだ…
お前の最近の攻撃性はケイドの死が原因ではなく、発散するためのきっかけにすぎなかった。お前の第二の人生全体が、ガーディアンとして戻ってくる前にお前が失った人生と、大崩壊によって失われた世界のための報復によって突き動かされている可能性もあるのだ。お前は本当に保護と改善を求めて戦っているのか、それとも復讐のために戦い続けているのか?
今、何のために戦っているんだ? お前の存在は怒りによって定義づけられるのか?
イエス、あるいはノーという答えによって導き出される結論は? 正直に。誠実に。自問してみたまえ…
何のために戦っているんだ? 自分の中に湧き上がる炎、あるいはその火花でさえ、感じているのか?
—S。
IV: 何か新しいこと 
知ってのとおり、俺はガーディアンを追ってきた。今お前が歩んでいる道で、俺はガーディアンを追ってきた。彼ら自身の道だから、全く同じ道ではない。しかしある意味似た道だ。誤りに早く気づく者も中にはいる。俺は殺人鬼ではないが、必要に迫られて武器を抜いたこともあった。とはいえ、俺は他のやり方を好む。殺すほど決定的でない方法がいい。しかしこういう生き方、すなわち影にはまり込んだ答えを探し続ける人生を選ぶ者の大半は、自分の行動のもたらす影響を把握していないことに俺は気づいた。熟考する者はほとんどいない。理解している者もほとんどいない。制御不能なものを制御しようとする者たちによって為された被害を見てきた。それが繰り返されてはいけないことだ。全力を尽くして、俺は腐敗に立ち向かい、囁きを受け入れてしまったすべての者に挑む。
とはいえ、俺たちはここにいる。お前は伝説のガーディアンで、まるで踊っているかのように奈落の底の縁に近づいてきている。そして俺は、そういう運命を引きつける者に立ち向かう。だが、俺は食い止めようとはしていない。こんなことは初めてだ。
これは何か新しいものだ。
お前と俺が言葉を交わせること自体が、新しい。お前には何かがある。特別な何かだ。
単なる勇敢さではない。勇敢さなんてものが現れては消えるのを俺は何度も見てきた。単なる力でもない。俺が出会った中でも一番の愚か者たちは、一番優れた戦士でもあった。お前は好奇心旺盛だが、好奇心は武器ではない。道具だ。そして、勇気と力と好奇心が混じり合うどこかの地点に、リスクに値する何かが見える。
だから進め。光のために戦い、闇に立ち向かうのだ。俺は希望に満ちた心を持って見守ろう。
だが覚えておいてくれ。もしもお前が行き過ぎてしまったら、もしもお前の歩みによって罪のない者が犠牲になったら、もしもお前の道が邪悪な意志へと逸れて、囁きがお前の真実となったなら、俺がその場に行って終わらせ、お前を始末するだろうということを。だがお前は俺がそう言うということを既に知っていた。
これは脅しではなく、ただそうあるべき形だということを理解してくれ。
——S。
V: 木霊の後の静寂 
俺はお前の旅路の中で理性の声となるべく、最善を尽くしてきた。お前に提供できる事実は少ないが、経験と、俺の存在という真実はある。だがここにはもう一つの真実がある…
俺は目新しいことはほとんど何もお前に話さなかった。どの言葉も。どの質問も。熟考するようにお前に求めた時も。俺はお前が既に選んでいた道を進むように促しただけだ。自分の行動についてよく考えてみる気持ちが、お前という人間の核心にはある。俺はそれを見てきた。それを耳にしてきた。お前の仲間のガーディアンが、お前の功績と勇気と無私の心について語るその言葉の中に。お前は破滅の危機と背中合わせで歩くかもしれないが、核心の部分において、気高く正しい戦士だ。
もしも俺が、周りの人々と世界への思いやりを広げられるように、お前に手を貸せていたとしたら。もしも俺が、自分自身をよく吟味し、自分の可能性について考えられるようにお前を手伝っていたなら。それならそれでいい。だがそういったことは、元々にお前の中にあった要素だ。
これは叱咤激励ではない。これは英雄としてのお前のエゴを後押しする言葉でもない。俺はお前が知らない事を経験しているから言っているだけだ。
今お前は、自分の本質について自問していることだろう。「自分の考えや行動にあれこれ口を出すこの『裏切り者』は誰なのか?」と。お前は俺について警告を受けたこともあるかもしれない。もしかしたら、お前は少し怖がっているかもしれない。「ゴールデンガンを持つ男は他人との折り合いが良くない」と聞いているだろう。その手の戯言の判断はすべてお前に任せよう。しかし自分を擁護するために手短に言うなら…
もしこれらの言葉がお前にとって最善のものでなければ、この会話自体が言葉ではなく鉛によって交わされていただろう。そして、お前にとっては最後の会話になっていただろう。
お前にも邪悪な考えがあるし、聖人ではない。俺たちは純粋さからほど遠い。俺たちを最善の存在にするのは罪の欠如ではなく、自分の行為の重みを感じ、その重みや誘惑に屈しないようにすることだ。
お前の知らない秘密を俺は知っている。なぜ、どうやって、ということは重要ではない。そんなのは後回しでいい。だがこれは知っておいてもらいたい…
お前が最悪の状態にある時。望みが消え失せて、頭の中では世界で一人きりになってしまった時。不利な状況になって、絶望に包まれた時。お前の炎を思い出せ。それは常にそこにある。一度火がつき、怒りによって、恐怖によって、導火線が燃え出せば、炎は留まる。それはお前がここにいて、いかなる障害であろうと立ち向かうことを永遠に示す合図の光だ。そして最終的には、お前がそう決めさえすれば、お前を守るのは囁きと影ではなくなる。そういった腐敗がもたらすのは苦しみだけだ。いや…
それがお前にとっては初めて大声で口にする言葉になり、お前の敵にとっては最後の言葉になるだろう。
その瞬間を疑うな。これが俺からの唯一にして最善の忠告だ。どっしりと構えて。明瞭に話せ。木霊の後の静寂が物語を語り、ラスト・ワードは永遠にお前のものとなるだろう。
——S。
VI: 贈り物と灰色の手 
銃は届いたか? 手に馴染んだだろうか? それを使える者は多くない、だが光から甦った者なら扱える。これは俺だけが知っている秘密だ。お前はあれを持つに相応しい、それだけは間違いない。お前が持っているキャノンはお前のものだ、だがレプリカではない——友人からの贈り物だ。
俺は数え切れないほどの暗黒の使者たちを始末してきた。子供のころからずっとだ——ひっきりなしというわけではないが、もはやそれが俺の存在意義になっている。俺の考えは昔から明確だ——影を探せばお前の未来は奪われる、暗闇を探せば俺がお前を始末する。個人的な恨みがあるわけではない——今はな。確かに最初はそうだったし、あるひっそりとした尾根に辿り着くまで、その考えは変わらなかった。お前もこの話——ジャレン・ウォードと彼のラスト・ワードのバラッド、そしてドレドゲン・ヨルとパラモンの話を聞いたことがあるはずだ。ドゥルガ、ベロール、北海峡、サロー、パハニン、狩りとジャレンの死、ドウィンドラーズ・リッジ、そして怪物のようなある男と俺の最後の戦い。話せば長くなるし、思い出すつもりもない。もうたくさんだ。どの話も過去のことだ。我々は——お前と俺で——新しい物語を書いている。これは俺にとって最終章であり、お前にとっては予期せぬ序章だ。
俺は常に極端な人生を歩み続けてきた。光と暗闇が存在している。俺は自ら目標を立て、影が呼び出すとされている腐敗に抗うことにした。妥協はしない、だが中立が常に存在していたことには気付いていたような気がする。さらに俺は多くの「英雄」たちが、無知とプライド、そして利己心から、非業な死と悲惨な結末を迎えるさまを目にしてきた。俺は多くの者を退けてきた。その数は誰にも想像できないだろう。告白してもしきれないほどだ。俺はお前を見ている。常に監視している。俺には自分の行動が間違っていたという感覚はない。だが俺が今、自分が間違っていたのではないかと心の中で考えているということは自覚している——それは確かだ。
俺にとって、世の中は白と黒だけ、つまり善と悪だけだ。お前の中には目が眩むほどの光がある。英雄の中の英雄だ。俺にはお前に光をもたらしている希望が見える。
だが見えるのはそれだけではない、これは——まあ、恐らくだが——今までなかったことだ、ややくすんだ色が見える。
以上、これをもって最後の秘跡および最後の言葉とする。
——S。

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ