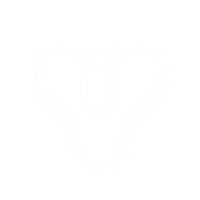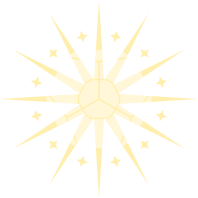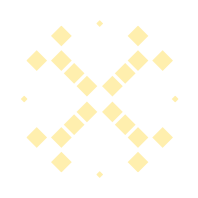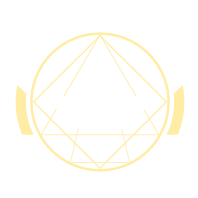- 「人生はタイミングがすべてだ。いつ引き金を引いて、いつキスを求め、そして何よりも、いつ逃げるべきかを知る必要がある」――ケイド6
- 「これは私の道だ。今も、そしてこれからも」――シロウ4
- 「求められるものが正しいものとは限らない。重要なのは、どちらが自分のためになるかだ」――リスボン13
- 「私は長い間旅をし、多くのことを乗り越えてきた。その距離と回数は私にも分からない。分かっているのは、私の人生はまだこれからだということだ」――ミカ10
- 「私は自分が何者かを知っている。私はタイタンだ。可能な限り、シティとその破壊を企てる者たちの間に立ち続ける」――セイント14
- 「何をできるかは問題ではない。違いを生み出すためにそれをどう活用するかが重要だ」――エイダ1
- 「確信は私たちの最も偉大な財産。それがなければ、私たちは闇夜の銃弾でしかない」――ラクシュミ II
- 「責任を感じない日などない」――エルシー・ブレイ
- 「これから自分がどこに向かうのか、楽しみだな」――バンシー44
- 「既に人間でない私が人為的ミスなどできると思うか?」――ハリ5
- 「シルヴィーは一族の汚点だ。ことあるごとに息子を私にけしかけてくる。彼が命を落としたとしたら彼女の責任だ」――クロビス・ブレイ1世
- 「ウィルヘルミーナは自分が思っている以上に私に似ている。どんな犠牲を払ってでも不死を求める。家族も例外ではない」――クロビス・ブレイ1世
- 「あの子は無能だ。アルトンの遺伝子を操作したが意味がなかった。なるほど。だから私には他に孫が3人もいるのか」――クロビス・ブレイ1世
- 「愛しいルシアよ。この人生、そして次の人生でも、お前は私の隣にいるべき者だ。今からでもそれを実現することはできる」――クロビス・ブレイ1世
- 「アナスタシアがラスプーチンに執着しているせいで仕事が滞っている。エクソは我々の未来だ。もう少し研究が進めば、彼女にも理解できるだろう」――クロビス・ブレイ1世
「人生はタイミングがすべてだ。いつ引き金を引いて、いつキスを求め、そして何よりも、いつ逃げるべきかを知る必要がある」――ケイド6 
シティの遥か上空、タワーに数多くある小部屋のひとつの中で、ケイド6は古い本に目を通していた。預言者の図書館から引き出した書物は経年劣化により破れやすくなっているだろうと彼は思い、1枚1枚丁寧にページをめくっている。触覚は問題なかった。金属の指には非常に精密な射撃を繰り出せるほど十分な回路が張り巡らされている。それでも、微かに触れただけで脆い紙を破いてしまいそうだった…
ケイドはあるページで手を止めた。「船乗りが語り奏でれば、嵐と冒険が、暑さと寒さが――」
突然、驚くほど冷たい風がケイドの手から本を吹き飛ばしかけた。「こんな呪われた氷は崩れてしまえ!」と彼は叫び、腰かけから転げ落ちそうになった。
彼は姿勢を正して深呼吸をする。気を確かにしろ、ケイド。呪われていようがなかろうが、お前は氷の上にいるわけではない。お前は地球に、シティにいるのだ。
だが、まるでカメラのフラッシュの後に数秒見える光線のように、記憶が残存する。春か遠くの月の雪のような平原、氷と鉄の棺。
—閃光—
エクソサイエンスの工場の外にある浜沿いに貨物を次から次へと積むケイド1にとって、エウロパとはそういうものだった。空でさえも平坦な灰色に変わり、下に広がるもの全てに影を落とし、光を殺してしまう。警告の空だ、と彼は思った。船乗りたちの歌でそういうものがあった気がする。
いずれにせよ、働く気を削いでしまうような環境だった。ケイドは貨物のひとつに腰掛けた。「休み時間だ」と彼は声をかけた。「必要かどうかにかかわらず、昔はこの時間に昼食を食べた。昼休みの間は働きたくはない」
隣でノックス4が安堵と渇望のため息をつく。「昼食がなつかしい。腹が減る感覚もな」
ケイドは機械の顔面が許す限りの笑顔を浮かべた。「ふむ…」とアブラム博士の真似をしながら喋りだし、「つまり… 飢えることに飢えているということか?」
ノックスは堪えきれずに爆笑した。ケイドは弱々しく鼻で笑った。そんなに面白くはない。だが友の笑い声が大きくなるとともに、ケイドもつられた。やがて、2人は互いを掴んで大笑いした。
そして徐々に2人の喜びが弱まった。「ところで、あの『精神科医』のことをどう思う?」とノックスが尋ねた。「ささやき声については話したのか?」
ケイドは頭を横に振った。精神科医の意味の無さについて皮肉を言う前に、彼の金属の頭に囁きが響き始めた。赤い空模様の朝、船乗りの警告だ。だが自分は船乗りではない。
荷積み場からすすり泣く声が聞こえてきた。そして、スノースーツを着た背の低い何者かが飛び出し、工場の反対側へと逃げて行った。ケイドとノックスが叫び、盗み聞きの犯人を追い始めた。まだ狙撃を会得していないケイドはブレイ・テクに至急された拳銃を探り、震えながら照準を合わせ…
—バンッ—
ケイド6は隠れ家に戻るとやっと我に返った。戦利品の山を探っていると… 「あった!」彼はペンを見つけた。これで終わりではない。彼は本を開き、今度はページを無遠慮にめくり、殴り書きし始めた。
「我々と同じような体験をしてきたエクソと一緒に過ごせば、聞いてきたことが見えてくる…」
「これは私の道だ。今も、そしてこれからも」――シロウ4 
「スズメ?」シロウが尋ねた。
彼のゴーストがコックピット内の彼の隣に姿を現した。「何ですか?」
「なぜシロウ4なんだ?」
スズメは時計回りに45度回転してエクソを間近で見つめた。彼女流の眉を上げる表現だ。「もう少し詳しく説明してください」
「はいはい」彼はゴーストの明らかな懸念を軽くあしらった。「つまり、何でその名前なんだ?」
「あなたの名前だからです」
「だが私を起こした時に別の名前を言っていたとしても、お前を信じていただろう」
スズメはゆっくりとした反時計回りの回転をした。自分たちで言うところの口をつぐむようなものだとシロウは解釈した。
「ええ、まあ、そうでしょうね。でもあなたの名前はあなた自身に刻み込まれているんです――人の目の色が遺伝子に書き込まれているように。あなたはシロウ4なんです」
「ふん。じゃあ、何で『シロウ』なんだろうな」
「わかりません。『シロ』というのは昔の日本の言葉だと、文脈によって意味が異なりました。ほとんどの場合は白色という意味ですが、城という意味もあります」
「城って感じでもないな。白色だとしっくりこない」
「他にも…」スズメの光が点滅した。「純粋や純潔という意味もあります」
「ハハ!」
「笑うと思いましたよ。なぜ急に自分の名前に興味を持ったのですか?」
「エウロパで学んだ全てのことについて色々考えてたんだ。今までは自らの選択によって自分というものを定義していたと思っていた――選択によって善悪が決まると。だが、私たちは他人が選択したものによって左右されることもある。自分でガーディアンになることを選んだわけではない。名前だって自分で選んだわけじゃない。エクソとして生まれるのだって、そうだろう?」
「つまり…」スズメは急な自己分析に戸惑い、空中で不安定に揺れた。「新しい名前が欲しいということですか?」
「うーん。いや。そういうわけじゃない…」
スズメは時計回りに45度回転し、また彼をまじまじと見つめた。
「…シロウ4が自分にとって何を意味するか、もう決めたからな」
「求められるものが正しいものとは限らない。重要なのは、どちらが自分のためになるかだ」――リスボン13 
リスボン13のゴースト、ピリが声を震わせた。「私たちはなんてことを…」
「必要なことをしたまでだ」
リスボン13は銃を彼女に向けた。
「本当にそうでしょうか? 私たちは本当に――うわ!」悲鳴を上げて彼女はエネルギーレーザーを避けた。
リスボンは神性では遅すぎることに気づいた。彼は手持ちのハンドキャノンに持ち替えた。
近くの爆破から発生した石片が突然ピリのシェルを激しく打ち付けた。話し合いで解決することを彼女は願った。だが、考える猶予がなかった――逃げるので精一杯だ。
「聞いてください、リスボン! お願いです!」ピリは懇願した。銃撃音が、彼女が発する言葉を一字ずつ途切れさせる。次々と発生する爆破を彼女は避けた。「私を撃ちたいなら撃って構いません! ですがその前に理由を教えてください!」
問いに答える形でグレネードが宙に舞った。ピリは今までに何度もこの戦術を見てきたから今更騙されることはなかった。彼女は落下する爆発物の方へ向かい、岩棚の下に身を隠した。爆発は彼女の感覚を乱したが、正気に戻る時間さえも与えられなかった。リスボンなら漂う煙の周囲を飛ぶ彼女の姿を探すだろうと考え、もくもくと土埃が上がる地面のわずか数センチ上を高速で進んだ。
そして次の瞬間、リスボン13の足元が彼女の目の前に出現した。すんでのところで激突するところだった。一体どうやって相手の予測を見越して先回りしたのだろう? すぐに話をしなければと彼女は思った。今すぐに!
「分かりました。まず初めに、あなたは私を壊そうとしている。それは分かりました。ですが、なぜですか? その後は?」彼女は尋ねた。
リスボン13は沈黙を貫く。
ハッと理解した。ピリは空中で揺れ、自分が出した結論に驚愕した。「…秘密を墓場まで持って行くつもりなのですね。ダメです… それはいけません。自分を殺すなんてダメです。やめてください! リスボン、他に方法があるはずです」
リスボン13が自分のゴーストから漂う煙のほうへ顔を上げた。「彼女の言う通りだ。こんなのは間違っている」
「何ですって?」
リスボン13が見ているのは自分のゴーストではない。「使うのに恐ろしすぎる力というわけではない。ただ、耐えきれないほどの重荷を背負うことになる」
「重荷?」ピリは尋ねた。リスボン13が前に進み、ゴーストは横に避けた。
そして、そこにはまた彼が立っていた。
もう一人のリスボン13――彼のドッペルゲンガーは、ピリの数歩後ろに立っているリスボン13に腕を伸ばして肩に手を置いた。
「お前は自分を疑ったことがない。一瞬たりともな。他の者たちは自らの弱点をさらした。プライドと自己陶酔だ。だが、お前はレッカナが言ったことを覚えている」
リスボン13が頷いた。「この力を持つ責任を負うことができる者がいるとすれば――」
「お前しかいない」とドッペルゲンガーが言った。「今お前が恐れているのは、お前が予想していた責任とは異なる。むしろ…」ドッペルゲンガーがゴーストの方を見返しながら話を続けた。「…これだけの力を持っているのに、欲しい物が手に入らないという重荷だ」
リスボン13は自分のファイアチームとゴーストに対して距離を置いて冷たい態度を取っているかのようだった。ブラックガーデン以降続く論争――ああ、戦いを止めるように彼女が何度嘆願したことか! リスボン13の中で死んだもの――ガーデンの洞穴でこのドッペルゲンガーに殺された何か――その棺に打たれた無数の釘。だが今、彼の生き写しの手を振り払うその身からは昔のリスボンの温もりが白く輝くほど発していた。「お前のせいだ! お前が全て滅茶苦茶にした」と彼は言った。
「俺たちは自分の選択に対して責任を持たなければならない。お前がこの道を選んだ。彼らは彼らの道を選んだ。今度は新しい道を選択する番だ。共にな。お前が欲しがっていたものからお前を解放することができる。お前の重荷を取り除くことができる」
ピリは次に何が起きるか分かっていた。彼女は爆発が来るのに備え、リスボンに手を貸す態勢に入れるよう心の準備をした。
しかし何も起きなかった。
「…彼女を忘れさせてくれるか?」
リスボン13の影が彼を抱擁した。「ああ」
「私は長い間旅をし、多くのことを乗り越えてきた。その距離と回数は私にも分からない。分かっているのは、私の人生はまだこれからだということだ」――ミカ10 
ミカ10はここ何年もやってきたように、旧ロシアの緩やかな丘をさまよっていた。この先も何年も同じことを繰り返すだろう。
小さな青い目の点滅が景色に映えるゴーストの群れが彼女の後ろをついてくる。ミカは多くのゴーストの捜索を手伝ってきた――誰かがフォールンのスカベンジャーに警戒している間にガーディアンを探す方が楽だった――だが、彼女は自分にも手を貸してくれたらいいのにと密かに願っていた。正常に機能する船を探すのはそんなに難しいことじゃないはずだ!
とはいえ、探しているのが大気圏の遥か先、木星までたどり着けるような船なら滅多に見つからないだろう。彼女の小さなお供たちは自分たちの未来を見据えているなか、ミカの輝く目はしっかりと過去を見つめていた――ディープストーン・クリプトだ。
昔は地球に隠され、シベリアの雪原の下に埋もれているものだと彼女は思っていたが、今はもっと遠方にあるのではないかと疑っている。もっと暗く、孤独な場所に。かなり肌寒い場所にあるという確信はあった。
彼女は黒い塔の下に広がる黄金の平原で何千回も戦う夢を、これまでに何千回も見てきた。そして50回ごとに、混沌の最中で、年上の男性が父親らしい手を彼女の肩に置き、「環境に慣れればいいだけだ。ここは火星よりも寒い」と声をかける。100回ごとに、彼女は塔の中に入り、また違う男性が肘掛け椅子に座ってノートに書きこんでいる姿を見る。「夢は心の奥底からのメッセージだ」と彼は教える。「メッセージの意味を理解するまで、夢は繰り返される」
毎度毎度、彼女が誰に会おうが何を聞こうが、ミカ10は目を覚ましては宇宙に引き付けられるような感覚を味わった。きっと内蔵されている磁石が緩くなったのだと彼女は思い、彼女の身体を作った者を呪った。人間の場合、身体の間隔とはコミュニケーションの一種で精神と肉体を繋ぎとめるものだ。だがエクソの場合、それは全て偽りである。寒い、暑い、空腹、疲労、痛み――そういった信号は実際の欠如や破損とは繋がっていない。彼女の身体は感覚がほとんどない。稀に傷つく時は、誰かに指摘されるまで彼女は気づかないでいる。
だから、そういった意味では、ゴーストは彼女の助けとなっている。
「私は自分が何者かを知っている。私はタイタンだ。可能な限り、シティとその破壊を企てる者たちの間に立ち続ける」――セイント14 
多くのエクソと同じように、セイント14は度々ディープストーン・クリプトの夢を見ていた。黄金の平野。迫るような黒い塔。不気味なほど見覚えのある顔が押し寄せる、下で繰り広げられる戦い。機械でできた同胞らの多くと一緒で、こういった夢には慣れっこで、深い意味には全く関心がなかった。知ってもろくなことはないだろうと、自分の中で既に結論を出していた。それに、目覚めている間の生活で一杯一杯だった。
しかし、無限の森の万華鏡のような深みから帰還して以来、夢の頻度も奇妙さも増した。
最初の数週間は戦いの代わりに、決闘で誰かしらと向き合っていた。オシリス、マリン、ザヴァラ、アナ――彼をベックスから助けたガーディアンまで。誰が相手だろうと、彼はありったけのエネルギーと光を戦いにつぎ込んでは毎回敗北していた。地面に仰向けに倒れ、塔を見上げては誰かが中から一部始終を見ているのだと思っていた。
ピラミッド艦の群れが太陽系に侵入してくるとラスプーチンが皆に警告する日の前の晩、彼の夢の迷宮に冬が訪れ、見たこともないような巨大な有翼のベックスと柔らかな雪の吹き溜まりに向かって突進する夢を見た。多くの晩と同じように彼はその晩も敗北し、ベックスの体液と似ているがそれよりも穢れている虹色の液体が、体の節々から吹き出し雪を溶かすのを見た。
起きている間、彼はいつもの活力を維持し、オシリスの試練でガーディアンが腕を磨く手伝いをするのに充実感を覚えた。結局のところ、現実で起きている戦いに集中すべきだった。自分の頭の中で起きている制御できないものの心配をしても意味がない。
だが、太陽系に新たな嘆きの空白が開かれる前の晩、ある女性が塔の入り口に現れた。彼女の衣服は黒く、髪の毛は若白髪だった。セイントがベックスに対して何の効果も発揮しないグレネードを次から次へと投げるのを、彼女は腕を組んで見ていた。
「そんなに眩しい光を出し続けたら自分の目が眩んでしまう」と彼女は舌打ちした。「ただ見るだけじゃなく、観察することを覚えたらどうかしら」
強烈な一振りでベックスがエクソを切り捨てた。セイントが地面に崩れ落ちると女性がため息をついた。
静けさが漂い、雪を踏む足音が響いた。「あなたの父親とそっくり」頭の横で跪く彼女が言った。「何もかも」
彼女は熱を測るように彼のヘルメットの額に手を当てた。「次の人生では、もっと私に似るといいわね」
そう言うと彼女は手を彼の目元まで下ろし、彼が目覚めるまでのわずかな時間、全てが暗闇に包まれた。
「何をできるかは問題ではない。違いを生み出すためにそれをどう活用するかが重要だ」――エイダ1 
何らかの力で嫌な状況に置かれてしまうことは誰だってある。真の試練は、そういう状況に置かれた時にどう行動するかだ。私たちは大崩壊が繰り返される場面に直面している。その兆しは自らの周辺でたくさん見られる。もう目を逸らすことはできない。暗黒が来たのだ。そして、私は再び試されている。
私は大きなポテンシャルを秘めている。作ること。構築することができる。他の者にはできないことが私にはできる… そして、心のどこかでそのままでいいと思っている。この才能を他人に分けたくない気がする。この力にはとてつもない責任が付いてくる。自分はどういう風に使いこなせばいいのか分かっている。同じように使いこなせるだろうと他の者を信頼することはできるだろうか? 他の者が使えるようになった場合、この能力は邪悪に、無駄に使われることはないだろうか? 暗黒が都合の良いようにその能力を操るのが目に見えてしまう。
その一方で、多方面にいるエクソの技術を促進させることに繋がり、私たちの立ち位置が向上して優位な種族であることを確立できる。シティはバンガードが与える以上の保護が必要だと昔から思っていた。自分ならそれを広範囲に提供できるし、全員がその恩恵を受けることができる。ディープストーン・クリプトへこの身を突き進め、ブレイ・エクソサイエンス施設の本領を最大限発揮できる。この暗い夜を食い止められる。アーマリーの名は既に知られている。必要な者たちに助けを与えられていないなら、無意味な機関だ。
だが、そうなったら私の存在意義は? ブラックアーマリーとその伝統を、忘れられた怪しげな工場という存在に衰退させてしまう、ただのエクソの1人となってしまうだろう。そんな歴史は残したくない。アーマリーも… 私も… 私たちが作る武器以上の存在だ。自分たちが象徴するもの――その真義は――監視の目がなければ堕落してしまう。でも、今行動を起こさなければ、残せるものもなくなってしまう。暗黒は何も産まない。ガーディアンたちはさらに多く求めるようになる。アーマリーは進化しなければならない。
「確信は私たちの最も偉大な財産。それがなければ、私たちは闇夜の銃弾でしかない」――ラクシュミ II 
ラクシュミ IIは何を聞いているのか明確に分かっていた。クエリこそが質問だった。正確さと柔軟なアプローチが必要だ。
リモートアーカイブデータベース、テキスト検索開始
ようこそ、ユーザー「ラクシュミ II」
検索クエリを入力してください
エクソ 身分 変更 大崩壊後
結果
光る文字列がホログラフィックディスプレイを満たした。何十万もの電子的な藁山の中に求めている針はなさそうだ。
検索クエリを入力してください
エクソ身分/OR/名前変更――"ブレイ・エクソサイエンス"
結果
藁山は少し減ったが、全てを調べるには数年かかるだろう。
ラクシュミ IIは藁の中で静かにしばし考えてみた。
検索クエリを入力してください
エクソの名前を検索および特定; クエリサブコマンド: 検索結果を"エクソ名前検索"とフラグする
結果
これだ! これでひとつの巨大な藁の山に絞り込むことができた。何らかの針がこの中から見つかるはずだ。
検索クエリを入力してください
エクソ名前検索とフラグされたクエリエントリ; エクソの名前を特定 -#; クエリサブコマンド: 検索結果を"エクソ名前検索-#"とフラグする
結果
何百万もの検索結果のうち、何かひとつ内容が変わったとしてもラクシュミ IIには見分けがつかないだろう。
検索クエリを入力してください
エクソ名前検索-#とフラグされたクエリエントリ; "-#"を特定; 結果を"エクソナンバー"とフラグする; エクソ名前検索-#+エクソナンバー+1 = の結果からエクソ名前検索-#とエクソナンバーとフラグされたエントリを相互参照; 結果"藁山"をフラグする; 藁山とフラグされたクエリエントリ; 大崩壊後のデータを抽出
算出には他の検索と同じくらいの時間がかかったが、入力したコマンドが正しく解釈されるかラクシュミ IIは自信がなかった。何かを待っている時ほど時間が長く感じるものだ。
結果
藁山が消えて両手で数え切れるほどの光るデータポイントだけが残されたのを見て、ラクシュミ IIの目が大きく開いた。この中に針は何本あるだろうか?
数分読んだだけで彼女は分かった。以前にも同じことが起きていたのだ。数時間後、彼女はアーカイブから得られるものは全て手に入れたと判断し、さらに調査をするためにいくつかメモをとった。
自発性リセット症候群の歴史的基礎
—ヘイカ3/4: 悪名高い暗黒時代のウォーロード。リセット後は孤独なレイダーと化した。
—ヴァンダー2/3: リセットにより無能となったため、大惨事から救出された。リセット後はシティの警備員として従事。ゴーストは月で破壊された。(リセット前と後のどちらか? ゴーストは自発的なリセットからエクソのガーディアンを守るのだろうか?)
—リラキー5/6/7: 奇妙なケース。重度のエクソ精神解離拒否反応関連の悪夢や発作に苦しんだことが知られている。ジャンプシップを乗っ取った後、消息不明となった。
—セラス7/8: タイタンの居住地をデータマインするために送られた技術者。帰還時にリセットが発生。リセット後、クリプトアーキを援助する研究技術者として従事。
以上が自らを再起動させたと思われるエクソたちだ。自らの身分情報を消去し、新しい数字を引き継いだ。それとも、誰かが彼らの代わりに実行したのだろうか? アーカイブに残されていない者たちの記録がどこかにあるのだろうか? 1人か2人くらい、現在も生きている者はいるだろうか?
ラクシュミ IIは目を閉じ、呼吸を落ち着かせ、相反する感情に集中した。重大なものを発見したように感じたが、彼女の同僚はただの好奇心と見なすだろう。人々は多くの場合、エクソを軽視する。器と血肉の間に線が引かれているかのようだった。その考えはラクシュミ IIの気に障ったが、それと同時に彼女自身もエクソは普通の人間とは違うと知っていた。己の存在をリセットするエクソは――それがどんな理由であれ――それを証明していた。
だが果たしてそうだろうか?
医療記録をざっと調べてみると、黄金時代にはインチキ療法と見なされていた病気や病因などが検索結果に表示された。心因性記憶喪失、解離性遁走、逆行性健忘症、自己抹殺、裏切り理論…
一体どういう意味なのだろう?
ラクシュミ IIは確信が持てず、それは決まって悪いことの前兆だった。
「責任を感じない日などない」――エルシー・ブレイ 
心底憤りを覚えるし、イライラする。家族と友達を失ってしまった。世界は引き裂かれ、私はその中心に残された空虚の中に立たされている。なぜ私なの? なぜ私はここに1人ぼっちなの? この痛みは生存者の罪悪感などという言葉では説明できない。家族が恋しい。私たちを繋げる血を持っていない今、もはや家族とは何なのかもわからない。たまに、私はブレイ・テクの歩く広告塔として作られたのではないかと思ってしまう。商品のように。「エクソ・プロジェクトが大成功した証を見ろ」私は記憶と衝動の集合体――忌まわしい何かでしかない。
そんなことは真実じゃないと知っている。ただ… どうすればいいかわからない。私の存在意義はそれだけじゃないはず。私は「普通の生活」は送れない。あの家庭で生まれた以上は無理だった。私は怒りで満ちている。先人たちの過ちを正したい。祖父が解き放った人類の疫病… それを意図して彼は私を作ったのだろうか? 認識されなかった罪悪感と報いを受ける恐怖の産物なのか? 彼はそんな感情を抱くようには見えなかったが、彼も結局はただの人間だった。
彼がこれを計画していたかどうかは知らないが、いずれにしても私はあのクリプトを破壊して、クロビス・ブレイと彼の悪魔じみた産物により生まれた影を、この世から取り除いてみせる。
それは私にとってどういう結末になるのかも分かっている。いずれは私の目的も果たされ、自分自身をどうすればいいか迷うこともなくなる。私で最後にする。
「これから自分がどこに向かうのか、楽しみだな」――バンシー44 
ふう。自分がどこにいたのか、何をやってきたのかなんて常に分かっているわけではない。時たま、ある武器が作業台に転がり落ちてきて、自分が手を加えたような… 痕跡が… 見える。記憶を刺激する一瞬の何かのようなものが。確たるものではない。ハッキリとした証拠ではない。
身体の傷跡を見る限り、色々なことを経験してきたようだ。必要ならもっと身体を張る。タワーは俺の家だ。肌に合うし、何を犠牲にしようと守り抜いてみせる。ここでは機械ではなく、人間のように扱ってくれる。人々に受け入れられて仕事も楽しめるなんていう状況は滅多に巡り合わないし、それに… これまでの人生でやってきたことの中でも最も大事な仕事をしている気がする。人類を守る、ガーディアンを武装する、自分にとって大切なものを守る準備をする。これ以上自分にとって意味がある仕事はないと思う。
エクソとして生きることは呪いではない。エクソにしかない可能性を得られた。俺は… なんていうか、運が良い。過去の重荷を負わずに済んでいる。殆どの人は1回しかチャンスが与えられない。正しい道に進めるようになるまでに44回もやり直してきた。今度こそ上手く行く気がする。43回も過ちを犯してしまったみたいだが… 45回目の人生はやりたくないということだけはハッキリしてる。自分が大切に思う人たちや故郷を守るために全てを犠牲にしなければならないなら、それでいい。新しい世代が誕生すべき頃合いかもしれないし。
自分がなりたかったのはこれだ。俺が選択したことだ。良き人でありたい。違いをもたらしたい。多くの人は私利私欲に突き動かされている。貪欲だ。自分の思い通りに行かないものに執着する。俺はそういったものに左右されないように気を付けている。自分の道しるべは自分自身であることを目標にしていて、今のところ結構上手く行っている気がする。皆も同じくらい恵まれるべき――正しいことをするために最初からやり直すことができるべきだ。俺は自分ができることをやり続けるだけ。人生には善や悪の問題が溢れかえっている。手を貸す価値があるのはひとつだけだ。
「既に人間でない私が人為的ミスなどできると思うか?」――ハリ5 
「なぜここにいるのか分かる?」
「もちろん。この面接に招待したのはそっちだ… あ、お茶は結構、ありがとう。飲み物は飲まない」
「どうして私が――」
「興味を持ってるかって? もちろん。目覚めてから色々調べた。そっちはフューチャーウォー・カルトと呼ばれるものの一員だ。賢明な予防策とは合わない不思議な名前だが」
「そうね…」
「だから私に対する興味は、カルトの“賢明な予防策”と何か関係があると推測する。私たちの種族はその昔、誰もよく分かっていない戦争のための超兵士として作られたということは分かった。そして現在、戦争を繰り返すこの宇宙に住んでいる他の人たちと同じような暮らしをしている。だが私たちエクソは不死身でもある気がする。変じゃないか?」
「この会話そのものが変ね」
「自分たちのことを言ってるわけじゃない。つまり宇宙全体が色んな侵略を試みる異種族がいるせいで戦争をしている中、超兵士になるためだけに設計された人たちがいる。なのに、我々エクソは自由に生きていていいのか?」
「続けて」
「例えば私。私は研究者――科学者だ。それに、読んだ限りだと相当頭が切れる科学者みたいだ。そして私が目覚めた時も、以前と同じように科学者としての生活を送ることが自然のように思えた。超兵士? 超科学者という方がしっくりくる。銃のどちら側から弾を撃てばいいのかさえも分からない。だが、私の研究所にいたら話は違う。機械に触れたりちょっと見るだけで、使い方がわかる。なんと言うか… まるで…」
「自転車に乗るみたいに」
「何に?」
「何でもない。目が覚めた時のことを詳しく教えて」
「そうだな。私は突然この研究所にいた。あそこの床で寝ていた。周りを見て、後はさっき言ったとおり。何がどう動くか全て知ってた。でも、何も思い出せない。」
「何も? 自分の名前でさえも?」
「そう。何も思い出せない。いや、言語や運動能力は当然覚えてる。でも本当に異様な感覚だった。それがどういう状態なのかずっと調べたが、デジャヴという言葉以外にしっくり来るものがない。何もかも懐かしいのに知らないもののように感じた。自分の身体でさえも。かなり… 不安になる。でも、自分の研究に関するファイルをいくつか見つけた。自分が書いたものだって分かった。まるで自分が書いたことを忘れたものを読み返しているみたいに。どこで、いつ、なぜそれを書いたのかは覚えてないが、確実に私の思考だった。私が書いたものだと確信が持てた。その結果、自分の昔の名前を見つけた」
「その昔の名前について話そう。なぜ数字を変えたの?」
「いや… あれは… 違って… 新しい身分が必要だった」
「大丈夫?」
「大丈夫だが、なぜそんなことを聞く?」
「今何かおかしかった。目が一切動かなかった」
「悪いが、言ってることの意味が分からない。それで… 仮説は思いついたか?」
「いくつか。名前を変える前は、何を研究していた?」
「ああ、同僚のゴンザレスとムワンギと進めていたプロジェクトか。良い人たちだ。2人に会ったことは?」
「少しだけ。研究の内容は?」
「まあ小難しい話はしないが、ダークマターと暗黒エネルギーに関する研究を進めていた。私が一番関心がある分野だったみたいだ。あることを調べている途中で目覚めたみたいだが…」
「あること?」
「その… エラーだ」
「エラー?」
「そう。我々が収集したデータには、奇妙な… 異常が見られた。ここだけの話だが、ヒューマンエラーが原因みたいだ。過去の資料を見直して何か抜けてないか調べている」
「それで? 何かおかしいところは?」
「いや。むしろ結構癒された。やっぱり私は素晴らしい科学者だったのだと証明された」
「…」
「その… 妙だな。喉が結構渇いたみたいだ。やっぱりお茶をいただいても?」
「シルヴィーは一族の汚点だ。ことあるごとに息子を私にけしかけてくる。彼が命を落としたとしたら彼女の責任だ」――クロビス・ブレイ1世 
シルヴィー
母親が恐怖の叫び声を上げた。「そんな! 奴は私の娘にも拷問を与えるの? エルシー、あなたじゃないと言って。お願い! あいつに例の歩く隔離病院に死ぬまで閉じ込められたなんて言わないで!」
「お母さん。お母さん、聞いて。私は大丈夫。私はお父さんとは違うから、神に感謝するわ!」と答えるが、母親は信じてくれない。彼女の存在を温かい気持ちとしてしか覚えていないため、何を言っていいのかわからなかった。母親は泣き始め、彼女の涙に含まれるアミノケトンと香しい酸の匂いを感じた。塩分を含んだオピオイドが彼女の皮膚に光っている。顔を隠して自分の存在を消したかった。彼女は自分の顔を見るたびに叫び、さらに激しく泣いた。
とうとう諦めて、小さなゲスト用のベッドに座ることにした。家の中は、自分と同じような身体の中で死んでしまった父親の思い出がたくさん詰まっている。シルヴィーは心底彼を愛していたと姉たちから聞いた。クロビス2世も彼女を愛していた。彼が不貞を働いた後もだ。
やっと眠りに落ちることができたが、不安はまだ残っていた。殺人と、熱い血と、ナイフで作られたマネキンの身体の夢を見た。牢獄が並んだ塔をがむしゃらに走り、屋上にたどり着くまでに囚人を何人も何人も惨殺したのを覚えている。
ベッドから転げ落ちる勢いで叫びながら目覚めたが、母親が側にいて身体を支えてくれた。「よしよし、大丈夫よ。ただの夢だから」
彼女に抱きついた。今度は自分が泣く番だ。だが夢を説明してる間も、目からは何も零れ落ちない。「私が知ってる人が皆その独房の中にいたの」と叫んだ。「お母さんも、お父さんも、ウィラも、アナも、アルトンも…」
「ああ、愛しい我が娘よ」と母親が囁く。「私たちを殺す夢を見るのは当然よ。あなたのお祖父さんがあなたをそういう風にしたのよ。彼は触れるもの全てを殺してしまうから」
「ウィルヘルミーナは自分が思っている以上に私に似ている。どんな犠牲を払ってでも不死を求める。家族も例外ではない」――クロビス・ブレイ1世 
ウィラ
「悪くない」ウィラは認めた。「悪くないわね」
お辞儀をした。「あなたの知り合いを再現することができて光栄です、ブレイ博士」
「こちらこそ。記憶喪失のことは申し訳ないけど、祖父の作品はいつも悪夢のような欠点がつきものなの。唸ったり自分の四肢を引きちぎったりしてないだけまだマシね」
理解できなかった。「本来そういう反応をするものなの?」
「私たちの父さんがそうだったの」
目の前にいる小さい、褐色の肌の女性を見ていると、愛おしい気持ちとイライラする気持ちが交差し、その感情は自分の心に「お姉ちゃん」と語りかけている。
「ねえ」彼女に提案を持ちかけた。「もしおじいちゃんが記憶を失えば、もっと…」
彼女は微笑んだ。「おじいちゃんらしくなくなるかもって?」
「そう」笑いを返した。「今となっては私よりもおじいちゃんのことを良く知ってるでしょう。いや、昔からかもしれないけど」
「祖父の記憶を消したとしても彼は変わらない。変わるなら彼はやろうと思わないもの」ウィラは彼女の研究所のベンチに近づくように促した。投影にはレンガが組み合わされているような小さな機械が表示されている。「これはZIVA。私の最新プロジェクトよ。過去のナノマシンを丸ごと時代遅れにしてしまうようなウイルス性のナノロボットよ」
たじろいでしまった。この小さなものを見ているとベックスを思い出す。
「大丈夫よ。」ウィラはぎこちなく自分の腕を触ってきた。彼女は自分を恐れているのだと気づいた。「あと数年あれば、ZIVAを使ってあなたの脳を修復することができたのに。身体全体を変えることだってできた。私は自分にそうしようと思う。自分なりの不死身になる方法。私は何にでもなれる」
「気味悪い」と答えた。「ちっちゃい虫から身体ができてるみたい」
彼女は渋い顔をした。「祖父が死ななかったら、私たちがブレイ・テクを経営する日は一生来ないのよ? 私たちには計画があったの、エルシー。私たちの計画。彼のじゃない」
「あの子は無能だ。アルトンの遺伝子を操作したが意味がなかった。なるほど。だから私には他に孫が3人もいるのか」――クロビス・ブレイ1世 
アルトン
「俺たちの父親はこのために死んだのか…」
アルトンが引き付けられるように手を伸ばした。彼に手を差し出すと、つねられた。「痛い!」と怒りをあらわにした。
「どうしてこの程度で痛みを感じるようにしんだ? ちょっと待て」彼は机の後ろを漁り始め、伸縮式の突っ張り棒を引っ張り出してバットのように握った。「避けるなよ」
彼は力いっぱい、こちらの頭めがけてその棒を振った。反射的に避けてしまった。「ちょっと!」
「当たったとしても――」彼は主張し続ける。「何で痛みを感じるんだ? この程度で傷を負うわけないじゃないか! 痛みは傷つくという信号を送るためにあるんだろう?」
なぜ彼は自分を試しているのだろう? 痛みへの耐性で家族関係が分かるとでも思っているのだろうか?
覚えていられればよかったのにと思った。
「アルトン」さっきつねられたことに対する反撃だと思いながら彼に言った。「おじいちゃんの仕事を手伝うように、おじいちゃんが私をエウロパに招待したの。ウィラとアナも招待された。でも、あなたは呼ばれてない。何で?」
しかめっ面をするとともに彼の額に細かい皺が現れた。「俺はどちらかというと研究よりも修理に向いているんだ。K1での惨事の後はその始末を任された。だが俺の技術はエウロパでは必要ないと判断したんだろう」
「なるほどね」疑るように返事をした。
彼はペンを指の間でクルクルと回している。「奴からもそう聞いているだろ」
「アルトン、おじいちゃんは… あなたのことは一言も言ってなかった。お姉ちゃんたちのことはたくさん喋ったけど、あなたのことは一切話してない。少し変だなと思って」
彼がペンを落とした。瞳が怒りで燃えている。
「祖父は女性を恐れていると母さんが言っていた。自分には女性を制御できないと思っているからだって。俺のことは何でもお見通しだとあいつは思ってるんだろうな。きっと自分が既に所有しているものには何にも興味がないんだ」
「愛しいルシアよ。この人生、そして次の人生でも、お前は私の隣にいるべき者だ。今からでもそれを実現することはできる」――クロビス・ブレイ1世 
ルシア
ルシアおばあちゃんが自分の眉から汗を拭いている。「網を引っ張るのを手伝ってちょうだい」
一緒に引っ張ろうとするが、水の中で何かに引っかかっているようだ。自分の服を脱いで穏やかな川の中へ飛び込み、長いこと放棄された船外機のプロペラ翼に引っかかっている漁網のところまで泳いだ。網はズタズタになってしまっている。せっかく飛び込んだのだからと、素手でオオカミウオを捕まえることにした。水の上まで上がると、周囲の人たちが自分をじっと見ている視線を感じた。子供が何人か指を指し、男の集団は口笛を吹いて何か叫んでいる。ルシアは彼らに対してスラナン語か、もしかしたらジュカ語で叫び返した。どちらか分からないと認めるのが恥ずかしかった。
「変態ども!」彼女は文句を言った。「恥ずかしいと思わないのかしら?」
「私がロボットだからよ、おばあちゃん」と答えた。それか、普通ならオオカミウオは人間を襲うのに、そのオオカミウオを手でしっかり握って窒息させているからかもしれない。
「あなたはロボットじゃない。完全に置換された人工物ですらないわ。あなたは身体を持っていて、その身体は人間と同じで、人間とは尊重されるべきものよ。基本的人権がある」驚きを隠せなかったこちらにウィンクを返してきた。「私は馬鹿だってクロビスに言われたの?」
自分の父方の祖母は古い家族写真の中では目まいがするほどの美貌の持ち主だったが、それは今も変わらない。だが、彼女の力は間違いなくその卓越した頭の回転の速さにあった。彼女は旧名のルシア・リンを名乗っており、簡単には見つからなかった。社会保障も受けていない。彼女を改めて尊敬する気持ちになった。
「何でここで生活しようと思ったの?」と、オオカミウオを処理する彼女の隣でタオルに身を包みながら聞いた。白身がパサパサしていて、天にも昇る匂いがした。お腹が鳴った。完璧な幻想だ。
「大した理由じゃないわ。スリナムは素晴らしい環境保護区よ。私も保護されたかったの。それに――」彼女が肩をすくめた。「故郷だから」
「何から保護されたいの?」
「あなたのお祖父さんからよ」
彼女は魚の歯を見せてきた。「彼はあなたに嘘をついていたということを忘れないで。あなたの父親は、あなたを作るためのクロビスの試作品だった。でもエルシー、あなたは何のための試作品なの? クロビスの死を治療するため? 目的が何であろうと、彼はそれを自分自身に適用することを恐れているわ。つまり、あなたもそれを恐れるべきということよ」
「アナスタシアがラスプーチンに執着しているせいで仕事が滞っている。エクソは我々の未来だ。もう少し研究が進めば、彼女にも理解できるだろう」――クロビス・ブレイ1世 
アナ
「わあ、エルシー! すごく綺麗よ!」
アナは勢いよく抱きついてきて、シャンプーに含まれるラウリン酸ナトリウムと、彼女の恋人のキスの名残りと思われるローズヒップオイルの長鎖脂肪酸の味を感じて安心した。可能な限り彼女を強く抱きしめ返した。前に彼女に触れたことがあるのか、思い出せない。
アナは耳が元々あった場所に向けて囁いてきた。「私が怒ってるか聞く前に言わせて。怒ってるわけないでしょ。秘密にしておくかどうかはあなた次第だもの」
「ありがとう」と息をもらした(息はしない。息はできない)。「おじいちゃんは私が――病気にかかってるか分からなかったみたい。最近まで、ね」
「本当に病気だったの?」アナはからかうように言ったが、彼女の声には恐れが見え隠れしている。「もしかしたら嘘の診断だったのかも。あなたをこの身体に入れるために。自分で検査したの?」
「覚えてない」と白状した。
「そうね、そりゃそうよ。手紙を読んだわ」アナは身体を離し、肩に手を当ててきた。「エルシー、一番大事なのはあなたがずっと側にいてくれるということ。一緒にやりたいことがたくさんあるの! これでやっとオリュンポス山を登れるわ。山頂まで登ったら、あなたを崖から突き飛ばして無事に着地するのを見届けるの」
彼女の笑顔は伝染する。自分の口内の光が、彼女の瞳に反射した。

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ