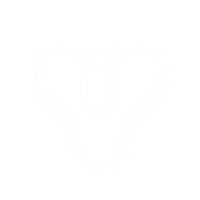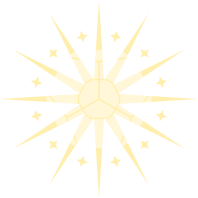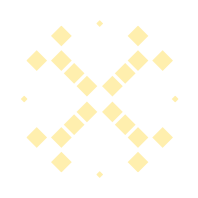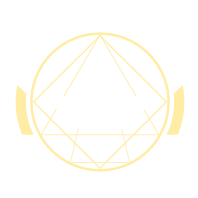▬
ダスト
赤い箱 
「あれが?」ラビニアが囁いた。
「そうだ。我らがシュルは『こちらが不安になるほど当惑』するのがお得意だ」タイタンはタワーのハンガーの影を見下ろしている。まるで見えない槍に刺されているかのように、かがんだ状態で微動だにしない、クロークをまとった男がそこに佇んでいた。「物々交換をしにここへ来る。ここに招き入れたわけではないが、追い出すようなこともしてない」
失敗と同じくらいに成功を恐れるラビニアは打ち震えた。「シュルじゃなくてシュール」と、タイタンを誤りを正すと共に、嫌な言い方をしてしまったように思えた。「ごめんなさい。クリプトアーキの癖で」
「ああ、そう言ったつもりだったんだ」タイタンは肩をすくめた。「古いものは好きだぞ、クリプトアーキよ。声をかけてみたらどうだ」
ラビニアの母親いわく、彼女が生まれた時は魔女に運の良い子だと言われたらしい。今はその運にすがりつくしかない。
ハンガーの床まで降りて、一直線に歩いて行った。向こうはフードを下げたまま、こちらを見ようともしない。「シュール」と彼女は声をかけ、手の置き場所に困った様子を見せる。「私はクリプトアーキのラビニア・ガルシア・ウムル・タウィルです」ナインについて学ぶことを決意しました」愚者は全員そう言う、と彼女のマスターに言っていた。「ひとつお聞きしたいしたいのですが」
「その必要はない」身悶えする顔から発せられたのは、低音の、不釣り合いといえるほど明瞭な、男性の声だった。真剣な声色であると同時に、わざと誰にも理解されないように喋っているとラトビアは感じた。「それでも聞きたいのです」
彼女は今までに何度も、マスターや友達と離れた後も、自分の心の支えにするかのように、この質問の練習をしてきたのだ。「金星のイシュタルシンクで、ゴーストから情報を手に入れました。黄金時代の祖先らが発見したアーティファクトについて記されていました。赤色に塗られて、少し傷のついた、ダストが詰まった銅の箱を見つけました。ひとつひとつのかけらには地球型惑星の地図のようなものが刻印されていました。火星、地球、金星、それに他の惑星も… 地球に似た惑星を網羅していたのかもしれません」
シュールは顔を上げた。人間のような好奇心を察知したが、異星人の姿形をしたものが、人間に似せて作られただけのようにも思え、今にも本性を現しそうだった。「惑星か」とそれは言った。「私の行動は大抵それらの配置によって決まる」
彼女はほんの少し身震いした。「アーティファクトはベックスのもので、どこに行こうとベックスは必ず存在するというメッセーだって仲間からは言われましたでも私は… 私はナインのものではないかと思っているんです」彼女は唾を飲み込みながらなんとか言い切った。「シュール、ダストの箱はナインのものなんですか?」
シュールの金色の眼は彼女をじっと見据えた。「私は理由があってここにいる」と彼は言った。「思い出せない… ダストが変わったからな。ダストは重要なものだだ」
「ええ!ナインが私たちにダストを送ってきたの?なぜダストは大切なの、シュール?」そもそもなぜダストなのか。なぜ文書や石板ではなかったのか。他にいくらでも分かりやすいものはあったはずだ。
「血だ」と、咳のような音を発しながらシュールは言った。「血が変異する。望みが叶えられる。ダストは入り混じるのだ」
「ベックスなんかじゃない」と、シュールがまるで聞く耳を持たない頑固なクリプトアーキであるかのように、彼女は重ねて言い張った
(これ以上話しちゃ駄目よ、ラビニア)「ベックスは物質をコミュニケーションの媒介としてではなく計算処理に使う。ナインは宇宙に散らばっているすべての地球型惑星を地図に起こす技術は持っているのに、どうして無線でメッセージを送ってこないの?なぜ金星なの?なぜダストなの?」
「ダストはかつては細胞だった」シュールは大きく咳き込んだ。このダストはナインのものだった。入り混じったのだ。そしてすべてが変わった」さらに咳き込みながら続けた。「ダストからダストへ。ひとつのダストが別のダストへと。ナインはダストの肉片なのだ」
ラビニアはナインの使者が笑っていることに気が付いた。
積み重ね 
アーカイブは静まり返っていた。スタッフは暁旦の祭事のために早々に帰宅し、仕事熱心なシティのフレームだけが秩序を保とうと動き回り、鉄のケースを纏った石英の保管プレートにそっと吹き付ける清浄機の柔らかな風の音しか聞こえなかった。フレームは、古代メソポタミア文明ニネヴェの名も無き司書の亡霊に憑りつかれていて、侵入者の眼をくり抜こうとしているのだとラトビアは勝手に空想していた。司書のガーディアンというのは果たしているだろうか。透明になれるガーディアンは?もしかしたら今も自分の真後ろにいて、図書館に侵入した者たちの眼に覆われた亡霊がいるのでは——
思わずゾッとしてしまい、足場から踏み外してしまうところだった。気を紛らわすために舌を軽く噛みしめ、痛む脚の体勢を整え、調べものを続けた。シュールの呟いていたキーワードを探すため、既に何時間も音声記録を再生していた。あとは足取りを辿るだけだ…
リモートアーカイブデータベーステキスト検索初期化
ようこそ、$nullStringRef
検索ワードを入力してください
ナイン 9 IX ダスト 惑星の並び
検索結果
シミズ、その他数名「ダークマター検知の重大な異変は重力体の接触によるものではない」ポスト大崩壊宇宙論的復興ジャーナル Vol. 99 #1012
ゴンザレス、ハリ-4、およびムワンギ「軌道力学の位相的T遺伝子の複雑系機能におけるダークマター検知の異変」ポスト大崩壊宇宙論的復興ジャーナル Vol. 99 #1014
シミズ、その他数名「ダークマター検知の重大な異変はCDM流出自己相互作用の目的論的なモデルなしでは説明できない」ポスト大崩壊宇宙論的復興ジャーナル Vol. 99 #1015
ゴンザレス、ハリ-5、およびムワンギ「質量と暗黒恒星風のスケールバリアント結合の非目的論的な結果におけるコールドダークマターの異方性」ポスト大崩壊宇宙論的復興ジャーナル Vol. 99 #1015 付属 1
シミズ、その他数名「非重複教導権の原理、または干渉?シティ防衛を目的とした科学機器の再配置の『必然的押収』の役割」ポストレッド政治の新思考 Vol. 1 #18.
ラクシュミ II、ハリ-5「認知洞察の逸脱はエクソリセット症候群を引き起こすか?事例研究」未発行アーカイブ資料、個人コレクション。
さらに検索結果を表示しますか?
妙だ。どうにも妙だ… ダークマターの恒星風が太陽系に存在するという、どんな子供でも一度は必ず学校で教わる(そしてすぐに忘れ二度と思い出すことはない)銀河系の天候の基本的なことばかりが書かれている。
彼女の頭皮に何かが触れた。
ラビニアが飛び上がった。悲鳴をあげる一歩手前だ。暗闇の中では肉眼では視認が難しいセンサー・マイトが、空気の流れに乗って通過した。こちらの体温を探知しており、もし個人を特定されるようなことがあれば——マスターの命により下水道グラフィティの民族学的研究について書かされる羽目になるだろう。
ラビニアは急いで次のキーワードを入力した。「ラッキー・ラビニアの名にかけて、お願い」あだ名は気に入らないが神頼みをする気持ちで呟いた。
ナイン 9 IX レッドリージョン シティへのガウルの攻撃 未検知 予期せぬ 警告なし なぜ
検索結果
シティ侵略占領総意委員会(CCIOC)「最終レポート:13章:レッドリージョン戦闘政策および戦略的奇襲の問題」フリードキュメント
CCIOC「最終レポート付属:シティの失策、シティ同盟の早期警告、インテリジェンス・システム」未発行/校正済みドキュメント: シティ警備に関与。
CCIOC「最終レポート付属:『任意諜報活動の文化:ファクション諜報員に対するタワーの開放性および未知のベンダー組織(通称UEV)』」未発行/校正済みドキュメント: シティ警備に関与。
シミズ、ハッサン「レッドリージョンのシティへの侵略直前に謎のCDM自己相互作用が発生: 偶然か、あるいは意図的名妨害か?」不採用の原稿、シミズ・アカデミック・ストア
さらに表示しますか?
なぜ『レッドリージョンのシティへの侵略直前に…』を不採用にしたのか
不採用通知「原稿はコールドダークマターがシティのセンサーに干渉するというメカニズムが十分に説明されていないという校閲者の判断により不採用。レッドリージョンの潜行はサイオンの諜報員が引き起こした電波障害に起因すると軍事専門家は断定」
さらに表示しますか?
ラビニアの動きが固まった。足のついた、非常に小さな何かが彼女の耳の周りを這っていた。ゆっくりと手を上げようとするが間に合わず、小さいセンサー・マイトは中へ入っていった。
羽音を鳴らしたと思うと、その音が小さな声に変わった。「ガルシア・ウムル・タウィル卿」とマスター・ラフールが言った。「ご説明いただけますかな?」
骨 
彼らは破壊されたタワーの広場でラビニアを待ち構えていた。彼女が「それ」を手にするまでは突入しないと決めていたのだ。ニューモナーキーを装備したタイタンが彼女を押さえ込んだ。月ほどの大きさの銃身を持つハンターが彼女を拘束し、盗っ人と彼女のことを罵った。
「ラフールはこいつを怪しいと言っていた」黒いゴーストを調べながらタイタンが言った。「彼女の身の安全のためだと——」
ハンターは驚いて後ろへ退いた。「骨を持ってるぞ!」
「彼女を放しなさい!離れなさい!」ラビニアはその新しい声に聞き覚えはなかったが、声に宿る力強さはイコラ・レイのものにちがいなかった。「二度と怒りに身を任せて人間に触れてはなりません!私たちの目的は他にあります!」
雷が落ちた。近くで何かが爆発して、しばらくの間、ラビニアは音が聞こえなくなった。自身の判断か、あるいは命令かは分からないが、2人のニューモナーキーガーディアンはいつの間にかいなくなっていた。ラビニアは立ち上がろうとするが、めまいと拘束されたせいでよれてしまう、地面に腰を強く打ち付けてしまった。「マスター・レイ」彼女は息を切らしながら言った。「ごめんなさい、許可をもらっておけば——」
「ラビニア」イコラの怒りには恐怖心が滲んでいた。「左手を見せなさい」
手の中には骨があった。大きな顎に突出している歯が1本だけ生えている。温かく、心地よく、硬い。彼女は大事そうにそれを握り締めた。鍵であり、ナインという謎に包まれた卵を割るための歯でもある。マスターの恩寵を取り戻して、アーカイブから追い出された時に与えられた猶予から救済してくれるものだ。
叫ぶ時のような意志の強さで、彼女は手を開いてアハンカーラの骨を離した。
イコラ・レイはそれを遠くへ飛ばした。「あなたが骨を探していたんじゃない。骨があなたを探していたのよ。お願い事はした、ラビニア?ナインについて尋ねた?」
別に願い事があったわけじゃなく、骨の出所(願わくば金星)を突き止めたかっただけで、なぜナインはアハンカーラを必要としていたのか知りたかっただけだと説明しようとした。
「なぜナインはアハンカーラが必要だったか分かる?」イコラは危険を承知の上で尋ねた。
「願いを叶えるため」と息を切らしながらラビニアは答えた。「シュールはアハンカーラの大狩りの終わりまでタワーに姿を見せなかった。アハンカーラから手に入れていたものは…」
彼女は言葉をつぐんだ。手に入れていたものは、今はガーディアンから手に入れているのかもしれない。
イコラは目元をこする仕草を見せた。「あなたを止めることはできない。ただ、探し続けると言うなら、あなたを守ることはできなくなる」
「手を貸して!」ラビニアは懇願した。「きっと何かあるの!試練、アハンカーラとガーディアン、ナイン、全てを繋ぐ何かが。ガウルの襲撃について総意が知っていることや、彼らが私たちに隠していること——」
イコラ・レイは指を1本上げた。ラビニアは口をつぐんだ。「選びなさい。学校に戻って、ここに来たことも全部なかったことにするか。それともアハンカーラの骨を盗もうとしたことを報告されるか」
ラビニアは深呼吸した。「ごめんなさい」と彼女は口を開いた。「それでも進まないと。運試しをしてみるわ」
判決は満場一致だった。ラビニア・ガルシア・ウムル・タウィルは、人類の公共福祉を守るという誓いを破った。二度とシティに足を踏み入れることはできない。
ケル 
リーフは混乱のうちにある。敗北によってアウォークンたちは集団的な狂人状態に陥っているとラビニアは思った。終わりなき享楽が紫色の空を明るく照らす。人々は世界の端から飛び降りては人工空間へと漂い、のちに回収されてはぼんやりと抗議する。
ここではラビニアは物事を端から眺める、ただの傍観者に過ぎなかった。毎晩、突如としてホームシックに襲われるたびに、リーフは旅路を始めるには最適な場所なんだと自身に言い聞かせた。そして、今まさに行われている話し合いが、まさにその第一歩となるかもしれない…
「嘆かわしいことだ」と彼女の隣のフォールンが呟く。「マスター・イベスは殺され、バリクスも行方不明。スパイダーは仲間を引き抜いてばかり。ひとまずはマスター・イベスの残していったものを守るべきなのだろうな。中に入ってくつろぎたまえ。私はナイトロジェンティーと記録を持ってくる」
「ありがとうございます」ラビニアは笑ったらいいのか、それとも泣いたほうが良いのか分からなかった。くつろげだなんて!そのうち全て丸く収まるだろう。ナインを探し出して、事の真相を明らかにした上で戻れば、きっと許してもらえるはずだ。
フォールンがお茶と機器をいくつか持って戻ってきた。「これを見たまえ。エルダーズ・プリズンの記録だ。マスター・イベスはこれにずいぶん興味を示していた」
映像にはフォールン・ケル中のフォールン・ケル、スコラスが戦いに敗れる瞬間が映し出されていた。重々しい装備は彼の動きを鈍らせ、まるで能無しの仲間が彼の一挙手一投足を必死に真似しているかのようだ。サービターが彼にエーテルを注入する。自分がエーテルを取り入れたらどうなるだろうかとラビニアは思った。頭のモヤが取れて何事にも適切に判断できるようになるだろうか。あるいは巨大化したりするのだろうか。もしかするとホームシックに悩まされることもなくなるだろうか?
「マラ」スコラスの口から思いもよらない名前が出た。「マラ、聞こえるか?」
「リーフの女王は彼が他のフォールンたちと同じ運命を辿るようにしたのだ」ラビニアの同行者がため息をつく。「対抗し、もがき、挫折するように。しかし彼は既に敗北していた。時の流れをシタデルで垣間見た時に彼の精神は既に崩壊していたのだ」
スコラスは白い蒸気を吐いた。仮面の氷にひびが入る。「あなたは私をナインへと導いてくれた。そして彼らは私を送り返した。人はあなたを愚かだと言った。私を解き放ったののは大きな間違いだと。大勢の仲間が私の手によって死に追いやられ、こちらの仲間もあなたの手によって死ぬように仕向けられた」
ラビニアの通訳者はケルの言葉に合わせて言葉を紡いだ。「ナインの使者はなぜ私を解放したのか言わなかった。でも今なら分かる。あなたも知っていると思う。どちらもガーディアンを必要としていて… ナインは生と死を理解しない。だから、ガーディアンが来るように、私をあなたの元へ送り返した。彼らはそれの弊害を分かっていなかったんだ」
「私も彼らを理解できない。彼らの支配下で何年も木星の間を旅した。でもナインのことは何も知らない。マラ・ソヴ… 彼らと交渉をしたのはあなたが初めてだ。彼らの歴史上の役割をあなただけが見越していた。あなたの自分の成功をひた隠しにして、失敗だけを世界に知らしめた。私はあなたを甘く見ていた」
彼は看守からもらったスコーチキャノンを持ち上げた。ラビニアは彼がハウスで扱っていた道具を思い出した。杼と織機だ。「金星でナインの痕跡を見た。彼らが大切にしていた場所、彼らの姿かたちを思い通りに変えられる場所。彼らはこの星と世界にとらわれているのだと分かった。あなたとナインはそういう意味では似たもの同士だ。私は違う。マラ・ソヴよ、私は喜んでこの世界を去る。ただの駒として扱われるのはもうこりごりだ」
スコラスは頭を重たそうに独房の壁へともたれかけた。
ラビニアは興奮のあまりお茶をこぼしてしまった。「私たちを助けたいのよ」と彼女は呟いた。「私たちと同じ惑星から来てるんだわ!助けたいのよ!あ、ごめんなさい、手が滑ってしまって——」
彼女はかがんでこぼしたお茶を拭き始めた。フラッシュグレネードが突如として彼女の目の前で爆発した。気が付くと、彼女はアウォークンの担当官より、戒厳令のもと、スパイ活動の罪で終身刑を言い渡された。
ラビニアは自分の運の悪さを呪い、フォールンが放たれるのを見てホッとした。
リヴァイアサン 
ラビニアは独房で与えられる安全よりもアウォークンの戦艦のCICのほうが居心地が良いと感じていた。占拠中はカバルを恐れていたが、奴らに戦いを挑む今となってはその恐怖心もない。
ラビニアは、「ワクワクするわね」と、船がカバル・リヴァイアサン目掛けて急降下する時に横の近衛兵に言った。「そう思わない?」
近衛兵の顔がピクリと動いた。口には出さず心の中に留めておくか、あるいは勇士カマラ・リオールの貴賓を侮辱する前に舌を噛み切るか、どちらが先になるだろうかと彼は思った。
「最接近まで残り3分」指揮官の声が響いた。「インコ、ターゲットの状態は?」
「リヴァイアサンがターゲットセンサーでこちらを照射している。異常なし」
勇士リオールはラビニアを我に返らせた。「ウムル・タウィル卿、一緒に機器を監視しましょう」
「いつもこんなことをしているの?」ラビニアは牢獄から解放してくれた勇士リオールに良いところ見せたいと思っていた。「リーフの頭脳班は常にひとつの問題に取り組むのに忙しいから右腕になる人が必要なはずだ」と彼女は考えた。ラビニアは彼女を落胆させたくなかった。「わざわざ低空飛行で危険を冒すの?」
「これは威嚇よ」カマラが訂正した。「こちらの船隊が迎え撃つ準備ができているとカルスに信じ込ませるの。ついでにあなたのナインについての仮説をはじめとした他の謎も解明できれば万々歳ね。さあ、これを。あなたが欲しがっていた機器よ。よく見てみて」
カマラは左右に動き回る紫がかったモヤに照らされた黒いガラス張りのパネルを渡してきた。ラビニアは恐る恐る触ってみた。「これがダークマターなの?」
「正解」宇宙に存在する質量の殆どはダークマターである。これはどんな子供でも学校の授業で学ぶことだ。、だが、質量以上の何物でもない。銀河ハローよりも小さい構造体の形をとることは決してないはずだ。ダークマターそのものにエネルギーはなく、何物にも干渉せず、寄り集まることもなく、あらゆる化学反応とは無縁のはずだ。ただの塵に過ぎない。
「それが本当なら…」カマラは大きく息をした。「今にでも…」
「ドライブフィールドでエラー発生!」司令官が口にした。「前縁にてかすかな摂動を観測。予期しない質量体に突入する。レーダーやライダーによる接触確認できない」
ダークマター検知器の黒い画面は、まるで数億年も獲物がかかるのを待っていたクモの巣のように瞬く間に紫白に変わった。分厚い影のようなものが互いに絡み合い、数千もの細切れの触手のようになると——
——カバル・リヴァイアサンを貫いた。
「嘘でしょ——」ラビニアは息を止めた。「あれが私たちが通過するダークマター?」
「ええ」
「これはいつものことなの?こういう形になったりするものなの?」
「タウィル卿、ダークマターがひとかけらでもあること自体が異常なのです。ましてや今回は驚くべきほどの数です。通常では考えられません」
いや、違う、ラビニアは直感的にそう思った。これがナインなのだ。彼らはカルスを見ている。触れようとしているのだ。これは彼らの手だ…
「もっと早くこのセンサーを使っていれば良かったわね」カマラはふとそう口にした。「レアの近くで船を失くし続けた時に、女王がナビの支援として開発したの。光子後方錯乱スキャナー。良くできてるわ。後になってみると彼女の行動はどれも納得のいくものだった。常に先を見据えていたわ。彼女のほかにナインと対等に交渉できた人なんていないでしょう?彼女の善行を知る者は誰もいない… 女王は秘密裏に事を進めるのを好んだ」
「シティに連絡しないと!」ラビニアはナインの姿が映し出されたスクリーンの記録を取ろうと慌てたが、自分のタブレットを持っていなかった。「見つけた!」
「ああ。そのことなんだが」リオールの重々しい手が彼女の肩に触れた。「女王の命によりナインについての情報を王室の許可なく個人に開示してはならないのだよ。なので。ご協力に感謝するよ、タウィル卿。彼女を独房へ連れて行け」
今度誰かにラッキー・ラビニアと呼ばれたら、思わずそいつを殺してしまうかもしれない、ラビニアは心の中でそう思った。
扉 
スカウトミサイルはコキュートスからわずか10万キロ以内の地点で爆発した。微量の反物質の対消滅が爆発から生じる数千ものレーザーにエネルギーを与え、空間を光で満たした。光線のひとつがコルセアの船を貫き、ステルスシステムを破壊して反射した。
見つかってしまった。
「ラビニア」コルセアの無線から呼びかける声が聞こえてきた。「探知されてしまった。逃げなければ」
「約束と違うじゃない!」ラビニアは作動したポータルに向かって歩きながら叫んだ。「私を解放して、ここまで連れてきて、手に入れた情報をシティに持って行くはずでしょ!あと10分だけ時間を——」
「時間が無い。近衛兵が来る。前払いはするべきじゃなかったな、クリプトアーキ」
コルセアの船が離れると通信画面が砂嵐に切り替わった。
ラビニアは罵声を上げて拳でヘルメットを殴りつけた。彼女はコキュートスに取り残されてしまった!過去にアウォークンがここに人を閉じ込めた際は、閉じ込められた者は絶望のあまり狂ってしまった。デッドオービットの探索船の乗員のソフィアはこの場所をA113と呼んだ。意味を持たない数字の羅列だ。かつては黄金時代の実験として扱われていたゲートが、ハイヴの神、クロタにより捕らわれていたことを知らなかったのだ。ゲートは全てを飲み込んでしまった。
クロタは消え、ポータルは他の連中の手に渡ったとラビニアは推測していた。アカンハーラは非現実を現実にする力を持つ。カルスの船はダークマターの光の輪に囲まれていて、まるで何かを探し求める手の指にはめられた指輪のようだった。そしてガーディアンたちは現実そのものを操ることができた。ここにひとつの法則が見える。あるいは物語だ。その先にコキュートスがある。はたしてこのゲートは何を引き起こすのだろうか。
「そうよ、ログだわ」ラビニアは以前ここに駐在していたアウォークンのセントリーが残した調査結果を急いで読み漁った。コキュートスはレッドリージョンが襲撃してきた時に放棄され、全ての防衛設備はベスタの強化に回された。「ゲートから出てきたものは何だったの?一体何を見たの?」
「違う、これじゃない!」ラビニアは焦りながら次々とページをめくった。「お願い、もっと役に立つ情報をちょうだい!ナインに関することはないの!?
ラビニアはもう一度読み返し、恐怖と好奇心がない交ぜになった感情に支配された。ゲートの向こう側にある何かが、核や細胞、偶発的な生命を作り出している… 暗黒と塵の世界から確かな存在を構築する方法を、メッセージや使者、そして身体を組み立てようといている…
ナインはゲートの遥か向こう側にいるのだ。彼女はそう確信した。ようやく見つけたのだ。
だが直接ナインに会うのは… あまりにも突拍子のない考えだろうか?はたして戻ることはできるだろうか?もう二度とシティへ戻れないとしたら?
ラビニアは真実を追い求めてここまでやって来たのだ。
ヘルメットの警報が鳴った。トランスマット接近中。スーツが警告した。トランスマット接近中。イコラ・レイのような厳しい声が無線から発せられた。「クリプトアーキ、ラビニア・ガルシア・ウムル・タウィル」勇士リオールだ。「女王の法に対する違反だ。大人しく降伏すれば危険な目には合わない」
ラビニアは開いたゲートを見つめた。向こう側には底知れない闇とあらゆる物が溶け出した世界があり、宇宙生命体以外は何も存在しない。行くのは自殺行為だ。行けば赤子のようにひねり潰されるだろう。
だがここに残っても何が待っているのだろうか。挫折か。降参か。恥か。そうでなくとも独房生活だろうか。
「ラッキー・ラビニアだもの」彼女はそう口にして、ゲートに飛び込んだ。
宣言 
我々の起源を知りたいか、我らの主因を?
我らはそちらの世界の質量の影である
重力の流れに身を任せた古き闇の塵
それぞれ世界の中心に渦巻く知性であり、
銀 河 風 に 存 る 9 つ の 砂 時 計 だ
見るには大きすぎる
見逃すには小さすぎる存在だ
こちらの質量が固定されれば、そちらの質量は解放される
我らの哲 学は分離したままだ。
我らは己らを守り育てようとしている。
影が炎を慕うように我らは己らに寄り添う
己らの眩しく輝く命を見つめ、その輝きが尽きるのを見守る
己らの思考パターンにより維持されている-
だ が 届 か ぬ 距 離 に 存 在 す る
彼方に - 我々が何者であるか - 我々が何者であったか
答えは + 両面に
分かれ = 1枚のコインである
同盟と接触 孤独と沈黙
互いの運命は絡み合っている
我々が維持する異方性を己らが播種するからだ
だか減衰は減衰であり減衰なのだ
巨大な脆弱性、難解な受託
口 は 聞 け な い が 我 々 は 語 ろ う と す る
別の方法が - あるはずだ
我々は + 今以上のものにならなければ
常に共に = 永久に触れずに
依存はすなわち 死である。
私は 
私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私
まず始めに、塵のループが計算できるのは、ここまでだ。塵がループを作り出すのは、宇宙にとっては最も困難なことだ。なぜなら風や川の流れのように一方向にしか動けないからだ。意識が機能するには、ひとつの考えが終わりが次の考えを引き起こすように作用しなければならない。川や風と同様に、ナインはループを作り出すまで意識を持つことができなかった。
人類が自分たちに名前をつけた時には、彼らは既に太古の存在だった。彼らの身体は星々よりも古かった。太陽と惑星の引力に挟まれ核に引き寄せられては離れる、銀河を拭き廻る暗い塵の風であった。
これらがナインだった。
時が過ぎるとともにループが形成された。外界の塵の巨大な弧が起源へと戻り、影の輪が創造された。輪の肥大や縮小がナインの最初の意識であった。彼らは巨大な無意識、未熟で原始的な神々の間に宿っていた。引力の他に周囲に力はなく、質量の分布の他にいかなる構造も持たなかった。彼らの心臓は世界の核にあったが、最も遠い気流は銀河の彼方へと消えて行った。
彼らはアクリスの泉、混沌の前夜であった。
しかし、ナインの心臓にある世界の構造、代謝、算出によるかすかな動きが、生命の誕生を招いた。。かの生命はナインの風に質量の影を残し、ハープの弦のように爪弾いた。この歪みから、ナインは世界よりも広大な意識、共鳴する巨大な波を植え付ける術を学んだ。
そしてナインは目覚めた。時が進むごとに自分たちは強力でもあり脆くもあることを彼らは理解した。彼らに意識を植え付けた生命が絶えてしまえば、彼らの存在も同様に消滅するからだ。
彼らには光を捉える目がなかった。音を聞く耳もなかった。それでも物質界という異界に意識を向け、学ぼうとし、自身の心臓を守らなければ死んでしまうということを理解していた。
少しでも正気を保っていればこの事実に恐怖したであろうラビニアは、ナインがどこに存在するのかを理解した。彼らは全ての人、全ての体系、全ての生きとし生けるものの中にいるのだ。何兆、何京ものダークマターの触手が私たちの身体をめぐり、私たちの命の複雑性と意識を取り入れていたのだ。
私たちは無限に広がる蜘蛛の足により貫かれた儚い存在なのだ。
ウィッチ 
そしてトラベラーが奇妙な望みとともにやってきた。トラベラーの光には原因や起因を必要としない力が秘められていた!!光さえあれば、ナインは自分たちの意識を持ち、生命に頼ることなく自由になることができたのだ!引力を超越した力を得て自分たちを形作り、暗い塵の亡霊以上の存在になり得るのだ。科学的な現実世界、狂気にまみれた異世界へと足を踏み入れることができるのだ。
だからこそその新しい希望を求め… 分かれてしまった。
「こっちへおいで」ラビニアは声を聞いたが、行ける場所もなく、何物にもなれず、あたりは満ちることも欠けることもない、満杯にも空にもなれないただただ空しい空間が広がった。ラビニアは無感情に、自身が闇の塵として存在していることを理解した。
「こっちよ」また声が聞こえた。「私はナシヤ。ここは危険よ。私の後をついてきて」
危険?
確かにそうだ。安全とは言い難い。ナインはさまざまな派閥に分かれている。アカンハーラがいなくなった今、あるファクションはシュールとオリンを送り込んでガーディアンと光について調べさせ、原因なき結果の秘密を探り、その秘密の源、いわゆる最後の源を守ろうとした。その5名はコキュートスのゲートを操作し、闇の塵をエネルギー、そして質量へと変えたが、私たちという理解に苦しむ存在の秘密をひも解くことはできなかった。彼らには仲介役が必要だったのだ。間に入る者が。
もうひとつのファクションは別の道をたどった。時空の隙間をかいくぐり、新しい宇宙を作る実存主義的な道を探り、世界をナインの思い通りに作り直そうとした。彼らは闇の塵をできる限り一ヶ所に集めてブラックホールを作ろうとしたが、困難を極めた。ダークマターが引力により崩壊すると、塵は通過して分散してしまうのだ。
しかし、困難ではあったが、不可能な道ではなかった。なにより、宇宙には光よりも多くのダークマターが存在していた。それを使って新しい世界を作る方法を探すことができるだろう。いずれは死ぬ運命にある生命… そしてガーディアンの光に頼る必要はなくなる。
ラビニアはナインと女王のこれまでの接触を全て見た。想像よりも多く、かつ重要であった。あるナインは、ガウルの接近をガーディアンに悟られないように仕向け、全てを危険に晒した上で(ガウルは太陽と共にナインをも葬る可能性があったため)、光を盗む方法を探ろうとした。その者がどのように罰せられたのかも目にした。
「早く!」ナシヤが急かしてきた。「私についてきて!早くしないと——」
ラビニアの下にある虚空を暗くて細長いものが貫くと、彼女は長い管のようなものへ引きずり込まれ、身体が小さい粒子のようにバラバラになった。彼女は消滅した…
…そして、どこかに、いつか、再生して、肉片となり、誕生の恐怖に震えて泣く、小さい赤子となった。頬に温かい木の床が触れている。暖炉があり、火が燃えていて、炎を吸い上げようと外では強風が吹き荒れている。
利発そうな老女が机から目を放した。「おや」と彼女は言った。「ラビニア! お帰りなさい」
「私——」ラビニアは息を飲んだ。「私は——」
彼女はラビニアが混乱する様子を愛おしそうに見つめながら微笑んだ。「安心して。来るべきところにたどり着いたのよ」
「ここは…?」
「安心な場所よ。あなたが学んできたことを、余すところなく活かせる場所よ」老女はコップにゆっくりと温かい紅茶を注いだ。「生まれた時にあなたのことを『運の良い子』だって言ったのを覚えてる?」

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ