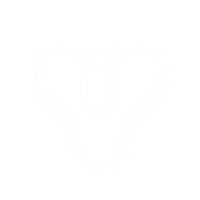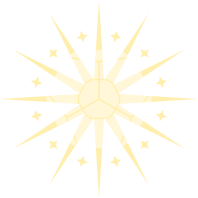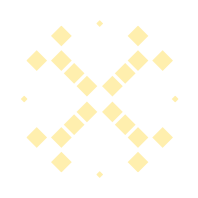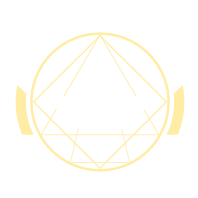▬
監禁と脱出
アシェル: 観察 
科学者であったに関わらず、アシェル・ミルが最初にしたことは、標的を撃つことだった。
ピラミッドがイオの大気中に浮きながら、十分な速度を持つ投射物であれば命中しそうなほど接近していた。アシェルは二度瞬きをする間に、攻撃の角度とその投射物の質量を把握していた。
アシェルは煎れたコーヒーが冷える前に固定レールガンを完成させた。
アシェルは磁気コイルをチャージすると、風がやむまで待ち、一斉射撃を行なった。投射物がキネティックバリアに命中するか、上手くいけばピラミッド本体に当たり、多少はダメージを与えられると考えていた。
だが予想に反し、命中の瞬間、投射物が消えた。
眉間にしわを寄せる一方で、アシェルの顔には隠しきれない喜びが徐々に広がった。彼の金属腕が自発的に静かな音を立てた。彼の研究所の目の前に停泊して、このような小細工を披露するだけの図太さをピラミッドが持ち合わせていたということだろうか?
あちらとしても間違いなくアシェル・ミルのことは想定していなかったはずだ。
彼は新たに、検知可能な放射エネルギーと無線信号を搭載したミサイルを作成し、それをピラミッドに向かって発射した。それも同じように命中と同時に消失し、信号は途絶え、イオの地表から検知できなくなった。
続けて別の弾頭も飛ばした。こちらは中継基地を小型化したものだった。彼はそれを自分の端末にリンクさせたうえで発射した。ピラミッドに触れた瞬間、ミサイルは膨大な放射エネルギーと無線信号を発した。
アシェルは笑った。それはまだそこに存在していた。ピラミッドの領域内にとどまっていたのだ。視覚的には検知できず、信号も途絶えているが、物理的にはまだそこに存在していた。
ピラミッドがどうやってこの事象を引き起こしたのかは今は重要ではない。だが彼の頭には零点エネルギーにまつわる様々な幻想が渦巻いていた。そしてある疑問が彼の思考を停止させた。あの忌まわしい形体の周囲で仮死状態になっているミサイルに、あの船は一体何をしたのだろうか?
そしてその目的は?
スロアン: 監督者 
スロアン副司令官の目に、波に飲み込まれそうになっている過積載のバンガードの小型船が映った。「危ない!」と彼女が通信装置に向かって叫ぶと、船が体勢を建て直した。「液体メタンに飲まれれば、直接死ぬことはないにしても、リヴァイアサンに殺される」
「おいおい、リヴァイアサンなんているはずがない」とパイロットが意気揚々と言った。17歳にも満たないシティから来た少年だ。「それにあれがメタンだって言うなら、あんたはなんでヘルメットをかぶってないんだ?」
スロアンが決まり悪そうに笑った。彼女は口答えされることに慣れていなかった。「肌に潤いを与えようと思ってな、新入り」とスロアンは言うと、通信機を叩いた。
フォールン・ケッチの叫び声が聞こえ、スロアンはすぐに船外の通路に飛び出した。デッキで作業をしていた船員に向かって叫び、射線の通らない場所に隠れるように言うと、膝をついてスカウトライフルを構えた。
最初の数体のドレッグは地面に触れる前に死んだ。しかし海から吹きあがる風のせいで次の攻撃は大きく目標を外れた。地上部隊がこちらの船員よりも輸送シャトルを狙うと考え、体を反転させて船に照準を合わせた。だが相手は予想に反して物資のほうに向かっていた。
悪態をついて手すりを飛び越えると、彼女は落雷のごとく地面へと降りた。イヤホンが突然活気づく。「セイレーンの監視、こちら物資船ウィーン・スティンガー、着陸できる場所を探している」
「5番発着所、南側だ!」と彼女はライフルの射撃音越しに叫んだ。「運んできたものを降ろしてくれ。すぐに物資班を向かわせる」
さらに2体のドレッグを倒すと、ケッチのエンジンが叫び声から鳴き声に変わる。ケッチは射撃を続けながら、発着場に向かって複数のワイヤーライフルを容赦なく発射した。
スロアンは大声で仲間に呼びかけた。死者はおらず、新しい物資のクレートが2つ奪われただけだ。隣の発着場を見てくるようにチームに伝えると、いつもの場所に戻るために長い階段を昇り始めた。
シティに運ぶ黄金時代の機械の積み込み作業中は妨害を受けなかった。奴らの目的はあの物資だった。相手は既に退却を開始しているのだ。
彼女は空のピラミッドを見上げ、顔をしかめた。
オフィスの扉が閉まり、シューっと音をたて密閉された。パネル上の柔らかな青い光が密閉状態であることを示していた。スロアンは部屋を横切ると、船体の横に空いた穴から海を眺めた。
アナ: 摩耗 
彼女はあらゆることを試してきた。偉大なるブレイ。皆を守ると約束した一族。その才能と勇気をもってしても、これは彼女の限界を越えていた。
ラスプーチンは死にかけており、十数のスクリーンは光を失ってアナの司令ステーション中に散らばっていた。血まみれのコードが自分の指を通り抜ける光景が彼女には想像できた。ザヴァラの声が環境音のように彼女の耳に響いている――遠くの戦闘音のように彼女の精神に溶け込んでいた。ピラミッドの歪んだ波のイメージが今も生々しく残っている。これは攻撃ではない。これまで練ってきた最善の策を全て打ち切るようにという命令だ。
爆発は起きていない。サイレンも鳴っていないし、激しい電気の火花も散っていない。戦う相手や直すものもない。ひとりのガーディアンが呆然とした様子で、静かな黒いガラスの中に閉じ込められているだけだ。
彼女には確信があった。
アナの目は、光を照射しながら複数の端末の間を飛び回っているチンジュの姿を追っていた。作業を続けるうちに、負荷が掛かり、徐々にその速度が遅くなっていく。
「アナ」とチンジュが歪んだ声でぎこちなく言った。「彼を見つけました。大部分は、と言うべきですが。でも時間がありません」
その言葉が遠くの銃撃音を切り裂いた。「えっ?」アナが聞き返した。最初、彼女の声は落ち着いていたが、その情報を整理するうちにどう表現すべきか分からなくなっていた。「何ですって!?」
チンジュはうめくと、静かに怒りを吐き出した。「ピロリー… エングラム…」
「まだ準備できてない」
「アナ、今しかありません!」
「彼が正気を失っちゃう! 私には… できない」
チンジュに繋がっている光の鎖がひとつずつ弾け始めた。「一か八か、やるしかありません!」
その可能性が部屋の反対側へとアナを突き動かした。彼女が空中に向かって命じると、それに反応して金庫が開いた。アナはそこから十二面体の箱を取り出すと、チンジュの目の前に固定した。
「チンジュ、やって!」
ゴーストのシェルが求められた形に変形すると、コアが光とデータを吐き出した。そのエングラムに純粋な情報が流れ込み、渦巻く光の束で満たされる。
「終わった…?」
「できる限りのことはしました」
窓の外では、空気の摩擦によって生じた炎が空から降り注ぎ、防衛体制を取っている軍事衛星が低軌道上に浮かんでいた。その衝撃が遠くから伝わってきた。
バンス: カナリア 
タイタンが聖域に入ってきたことで、修道士バンスの顔から笑顔が消えた。この臭いには覚えがあった。古い火薬、燃えた油、焼けたベックスの液体、そして幾たびの人生を通して酷使されてきた鋼鉄の独特の香り。
「パーフェクト・パラドックスを手に入れたのか」とバンスは言った。その声は自分が思っていたよりも落ち着いていた。彼は手を伸ばした。「見せてもらえないか?」
タイタンは肩をすくめると、自分の荷物からショットガンを取り出した。そして待っていたバンスの手にそれを渡した。
バレルを指でなぞると、ストックの重さを計った。「なるほど」と彼は言った。「オリジナルのパーフェクト・パラドックスではないな?」
タイタンは狼狽した様子で立ち尽くしていた。バンスは頭を傾けた状態で少し間を空け、そして再び話し始めた。
「これはセイント14の墓からではなく、フラクタリンを動力源とした4次元立方体から手に入れた、そうだな?」
タイタンはうなずいた、そして黙ったまましばらく盲目の男を見つめた。「サンダイアルが作ったものだ」と彼はようやく言った。
バンスが銃を握りしめた。かなりの重量がある、7発――いや、8発入っている。タクティカルマガジンだ。これを手に入れるのは容易じゃない。
「それで、この武器を手に入れるためにどれだけの時間軸をこの時間に繋いだ? この無意味で醜い物のために、我々の世界は今、どれだけの現実の重圧に耐えているんだ?」
バンスの頭の中には、ショットガンに絡まる無数のクモの巣のイメージが浮かんでいた。「これのためにどれだけのフラクタリンを犠牲にした? 400か?」彼はそこで言葉を切り、愕然とした。「もっとか?」
「トレンチバレル付きだ」とタイタンは付け加えるように言った。
「この聖域から出て行け」とバンスは言うと、死んだ動物の死体のようにショットガンを置いた。「お前はあらゆる存在の終末の訪れを加速させた。おかげで予言のアップデートが必要になった」
アシェル: 予知 
アシェル・ミルはイオを横断しながら文句を言った。
山岳地帯を横断する道を選択すると、足元の緩い土壌に悪態をつき、大きすぎる荷物に文句を言い、移動中の宿られた兵を罵り、肩を叩くシリコン・ニュロマライフルを呪った。
揺り篭に邪悪なエネルギーを注いでいるピラミッドを見上げ、あざ笑った。彼は言葉選びに定評があったが、今求められている言葉を紡ぐだけのエネルギーは残っていなかった。
そうこうしているうちにイオの夜は深まり、アシェルも疲労を感じていたが、コツコツと前に進んだ。彼が足を止めたのは、殻に水晶のような黒いオベリスクをいくつもつけたカタツムリを調べた時だけで、それも短時間だった。
揺り篭の地下に眠る洞窟の中を静かに進んだ。土の壁から見たこともないような根が突き出していた。シュリーカーの声のパターンを慎重に観察すると、音を計算に従って反響させ、宿られた兵の一団を自分とは異なる方向に誘導した。彼は邪魔されることなくその洞窟を通過した。
エリスは巨大な木の根の近くで小さな野営地を設けていた。彼女は遙か頭上から降り注ぐ光の近くに膝をついていた。光は木の組織を通過し、神秘的な形成層の花弁を照らしていた。アシェルのもとに樹液と焦げた植物油の匂いが漂ってきた。
エリスは会えたことを喜んでいたが、彼女が彼がどれくらいの頻度で物資を届けるのか聞いてきた時、アシェルは彼女から、思わぬ訪問客に当惑しているような気配を感じ取った。
持ってきた物資をアシェルが開封する間、彼女は木について話し、メッセージとその囁き声について説明した。さらに、例え自分の命が危険に晒されるようなことになっても、未知の存在の本性を垣間見たいという危険な好奇心を語った。彼女は楽しそうに話を続けた。アシェルには彼女の言っていることが完全に理解できた。
彼はたき火の近くで暖を取った。近くには小さなテーブルがあり、その上にはハイヴのキチン、木の枝、灰だらけの土、そして開かれたノートが置かれていた。個人の日誌だと気づき、すぐに乱暴に閉じた。
彼は再び荷物の中に手を伸ばした。上質な黄金の酒(とんだ間抜けがイソプロピルアルコールと間違って彼に持たせたもの)が入ったボトルを取り出すと、それをテーブルの上に置いた。彼は2つのきれいなグラスを持ってきていた。グラスはメモリの付いた大きなシリンダーの輸送ケースに驚くほどピッタリと収まっていた。そのうちの1つを取り出すと、ボトルの隣に静かに置いた。
アシェルは咳払いをすると、ブーツの紐を結び直し、立ち上がって荷物を背負った。
「全て上手くいっているんだな?」と彼はエリスに聞いた。
「ああ」と彼女は渦巻く光線に没頭しながら言った。
彼は体の向きを変え、軽く咳払いをする。「お前に任せておけば大丈夫なのかを知りたいんだ」彼ははっきりと言った。
エリスは彼に向き直り、目の前に立っている男に視線を合わせた。「できる限りのことをする」と彼女はようやく言った。
アシェルはうなずくと、長い帰路についた。
スロアン: 防波堤 
スロアン副司令官は機嫌が悪かった。自分の心に問いかけてみたが、アマンダ・ホリデイに心当たりはなかった。
タイタンの波がセイレーンの監視の巨大な支柱に繰り返し打ち付けている。こんな状況でなければ、今もそこに船員がいて、その巨大なマンモスの足の間を行き来しながら、修理や補強作業を行なっていただろう。
だが、今はそんな状況ではなかった。
「箱桁を作って補強することも可能よ」とアマンダは言った。
「お前ならな。だが私には無理だ」とスロアンが言った。防壁の建造に携わったことで、アマンダは技術者としての確かな経験を積んでいたが、教えるのは幾分苦手なようだった。
アマンダのホログラムがラーメンをすすった。「どれぐらい持たせる必要があるの?」
「心配する必要がなくなればそれでいい」とスロアンが言った。「あれがぐらつき初めてから、ピラミッドのことを心配する暇もなくなってしまった」
「欲がないわね!」とアマンダは楽しそうに言った。スロアンがそのゴワゴワとした髪を掻き上げる。
「いい?」とアマンダがうめくように言った。「足下には黄金時代のタイタンの技術が山のようにある。橋の入ったエングラムだってあるはずよ」
スロアンは力なく一点を見つめた。確かにそのとおりかもしれない。ただスロアンには失われた技術を探している時間はない。
「それなら防波堤を作ろう! テトラポッドを柱に固定するか、海上に何か設置して打ち付ける前に波を砕けばいい」
「波にやられたくないなら、こっちから出向いて迎撃する。こんな風にね!」と言うと、アマンダは前屈みになり、ラーメンの器の中で何かをしたが、スロアンの位置からは何も見えなかった。
「見てないじゃない」とアマンダは言うと、器を前方に傾け、スープを机にこぼしてしまう。彼女は大声で笑った。
「そろそろ時間だ」とスロアンは言うと、アマンダの芝居がかったふくれっ面に向かって嬉しそうに手を振ってから通信を切った。
ホログラムが消え、スロアンは暗闇の中に取り残された。彼女はしばらくそこから動かなかった。
アナ: 物理学 
ザヴァラはグラスを2つ置いた。ベルベットのような酒を注ぎながらアナの顔を見た。彼女の視線は机の上の粒子に注がれていた。目をそらしてしまえば、大きな木製のキャンバスの中に消えて、今にも見分けがつかなりそうだった。
トラベラーは彼の背後にぶら下がり、周囲は黒い雲に覆われ、空から切り離されているようだった。
彼女が口を開いた。「負けるとは思ってなかった」
「負けてはいない」
ザヴァラはアナのほうにグラスを押した。
「動くことができなかった。まだ何も分かってない――何一つ救えなかったのかもしれない」彼女が言った。
「敗北に直面した時に行動を起こすのは簡単ではない。我々は予想される未来の姿を常に心にとめておかなければならない」
アナはザヴァラを見た。「何もやらないのは簡単。問題はそこじゃない。これはストレステストであって、私はそれに屈した」
「信じるんだ、アナ。我々にも過去の失敗を受け入れられない時期があった。お前がいなければシティは灰と塵になっていただろう、しかも一度や二度ではない」
アナはグラスを手に取った。彼女は酒の匂いをかぎ、顔をしかめ、テーブルに戻した。「あなたは私を信頼してくれた。ラスプーチンは私の仕事だった」
「そうだな、今もそれは変わらない。今後の課題だ」とザヴァラは言うと、酒を飲んだ。「今は新しい仕事がある。エリスが助けを必要としている」
「まだ間に合うなら何でも言って」
「私はケイドが死んだ時、バンガード内の動揺が、いずれ避けられない悲運に繋がると考えた。それはつまり、彼が替えがきかない人物であることの証明でもあった。彼のような… 独特な客観性がもたらすバランス感覚がなければ、私には人々を導くことはできないと思っていた。結局のところ、彼の命も無限の選択肢の中のひとつでしかなかったということだ」
「ザヴァラ、私は――」
「落ち着け、その役目を任せるつもりはない。お前がケイドを殺し、我々がずっと間違った相手を追っていたというなら話は別だが」
「もし仮にそうだとしたら、私を許してくれた?」
「理解はしていただろう」と言って彼は笑った。「あの時イコラから言われた。物体には慣性というものがあり、動き出したものは止まらないと。あの言葉は今でも心に残っている。だがそれを受け入れるのが難しいこともある」
アナは首を振った。「それはただの物理学よ」
「人生の原則のひとつだ」と言うと彼はアナを見た。その言葉の意味を考えているアナの表情から少し険しさが消えた。「なんとかして足がかりを見つけ、目の前にある大地をしっかりと踏みしめよう」
アナがうなずいた。「ケイドのニワトリはどうなった?」
ザヴァラが溜息をついた。「セイントからピジョン卿とかいう地位を与えられたようだ」
こわばっていたアナの顔が笑顔に変わった。
「人生は我々を待たない。どれだけそれに専念したとしてもだ。だから目の前にある酒を飲め」そう言うとザヴァラは笑い、グラスを持ち上げた。「ピラミッドとの戦いでピジョン卿から召集命令が出る前にな」
バンス: 予言者 
音楽が美しく鳴り響いた。修道士バンスがそれに耳を傾ける。その顔が不意に喜びに満ち溢れる。
「繰り返し聞こえてくる」と彼は、自分と若いウォーロックに小さな声で言った。ウォーロックは無限の炉を覗き込むようにして、熱心に別の時代の武器を作成していた。
彼女は静かに耳を傾けた。だが何も聞こえなかった。彼女は自分の仕事に戻った。
「なぜ誰も不死鳥に同情しないんだ?」
ウォーロックが顔を上げ、固まった。バンスは彼女の向かい側にいたが、彼女は彼が近づいてきたことに気付かなかった。まるで会話の最中かのように、彼の質問には前置きがなかった。
「えっ?」とウォーロックが聞き返した。
「確かにいくらでも復活できる。だがそのたびに炎に包まれた死を経験することになる」とバンスは言った。「その羽から灰を落した途端に、再び死が訪れ、炎に包まれる」
盲目の男は振り返ると、聖域の中を照らす日光を顔に浴びた。
「そして誰もその歌声の話をしない」
ウォーロックは炉を貸してもらったことに礼を言うと、立ち上がってその場から去ろうとした。
「礼には及ばない」と彼は振り返らずに言った、だが彼の虚ろな微笑みは優しそうな笑顔に変わっていた。彼は机の上にある書物と巻物を示した。
「予言を自由に見てくれてかまわない」と彼は言った。「ようやく私の研究も終わったようだ」
アシェル: 結論 
アシェル・ミルは、オービットに向かって飛び立つ助手の船を見送った後、その仕事ぶりに対して感謝の気持ちを十分に伝えていなかったことに気付いた。
一瞬、手紙を残すのも悪くないと思ったが、それだったら他のことに時間を費やすべきだし、優先事項を順番に片づけていたら、助手のために時間を作り出すことは不可能に近い。そんなことをしていたら目的が完全に変わってしまう。だから彼はその代わりに、ピラミディオンに向かうことにした。
ベックスは生まれない、作られるものでもない。この難問を解き明かしたいがために、アシェルはイオを訪れた。その異質な資源と未知の力を手掛かりに、彼はピラミッドも同じ目的のためにここに現れたのではないかと考えた。暗黒の船はそのベックスの謎を手中に収めようとしている。
しかし、その権利を先に主張したのはアシェル・ミルだった。そして彼にはそれを守る準備ができていた。
彼は間もなくピラミディオンの門の前に立った。思っていたとおり、ベックスのセキュリティが起動する。しかし彼にとっては想定内だった。プレートに壊れた死体を積み重ね、中へと入っていった。
彼は最初に現れた数百体のベックスを倒し、次に現れた一団も始末した。ミノタウロスがうなり声を上げながら目の前に現れると、レディオラリアのコアを鉄の拳で砕いた。彼はそのかぎ爪のような四肢を乗り越えて前に進んだ。そして死体から静かに流れ出る冷たい液体の中に足を踏み入れた。
アシェルは口いっぱいに血を飲み込むと、そのまま前進を続ける。
回転ゲートの前で止まると、その不規則な波を観察し、一瞬の隙を突いてそこをすり抜けた。そして体にまとわりついてこようとするレーザー網を慎重に通り抜けた。足下の地面がちらつき、狂ったように形を変え続ける間も、重力の歪んだ空間の中で落ち着いて姿勢を維持した。
そしてベックスの監視が始まった。
ピラミディオンの通路には無数の赤い瞳が並んでいた。アシェルが近くを通ると、金属のマネキンが無言で立ち上がり、さえずり、震えた。
目の前に見覚えのある空間が現れる。スレートと漂白剤の臭いを生々しく漂わせる幾何学的な排水口だ。
見上げると、あり得ない形をしたフラクタル構造が存在していた。遙か頭上には、ペンローズの渦の中に巨大なレディオラリアの湖があり、金属の浜辺に静かに波を打ち寄せていた。
彼は金属の腕を伸ばしてその湖に触れた。そして肉体の残っている腕でそれに触れた。
彼は両手でそれに触れ、そしてその湖を引きずり下ろした。
スロアン: 狂化 
轟音を鳴り響かせてタイタンから出発したガーディアンの船を見送った後、スロアン副司令官はオフィスに戻り、ハイヴから手に入れた黄金時代のテクノロジーを身に着けた。
彼女の肩から重たい動力源が弾薬帯のようにぶら下がっている。彼女はそれを首にかけると、巨大で不格好なスーツを着る作業に取りかかった。頭を下げて灰色のフードをかぶると、目の前にモニター画面が現れた。その言語は、まだこの段階では理解できなかったが、彼女は緑色のオプションを選択した。
シューという音と共に、スーツが彼女の体型に合うように形を変えた。重量はあったが、動きの邪魔にはならない。彼女は自分の腕に焦点を合わせ、そのままじっと見つめた。するとその物質が分厚い装甲に穴を空けた。素晴らしい機能だ。
彼女はアークエネルギーを作り出そうとしたが、スーツがその光を遮断した。光を透過する方法を学ぶ必要がありそうだ。
彼女は目で他のオプションを選び、再び実行を選択した。痛みは一切なかったが、冷たいチューブが体の側面を通って、腹の辺りでとぐろをまいたのを感じた。これにより彼女の疑問がいくつか解決した。
スロアンは外に出た。外では嵐が起こっていた。まるでタイタンが、空に居座っている侵入者を追い出そうとしているかのようだった。彼女がその強風の中に足を踏み出すと、雨が彼女の第二の皮膚の上で玉を作った。一歩進むごとにスーツがその歩行に合うように調整され、前の一歩よりも楽に足を踏み出すことができる。
アイコンが点滅し、ハイヴ・スロールが彼女に向かって突進してきた。彼女はスロールの首と腕を掴み、そのまま引き裂いた。実に簡単だった。
彼女は笑った。するとスーツがその声を喊声として認識し、増幅し、大々的に流した。その声は、雨ざらしの発着場にある廃棄された貨物コンテナにこだまし、セイレーンの監視を通り抜け、上空のピラミッドに向かって響いた。
空で稲光が走り、嵐が一層激しさを増した。
アナ: ブラックボックス 
ヘラス盆地を横切るガーディアンのスパローを見送った後、アナ・ブレイは最後まで自分を信じてくれる親友を見た。ザヴァラが思い出させてくれたその信頼は、太陽系内のウォーマインドの全ての武器を合わせたよりも強力な絆だった。それは現在進行形の約束であり、まだ希望は残されているという意見の一致でもあった。チンジュはそれを「リバース・サルベージ」と呼んだ。彼女は過去の残骸から何かを作り出すことを得意としていた。
建造物はもぬけの殻だった。彼女はできるだけ多くの機械をタワーに送っていた。今にもあふれ出しそうなほど貨物船いっぱいに物を詰め込んで輸送した。
彼女は大きな窓ガラスの方を向いた。軍事衛星のキャノンが静かに並んでいる。カバルの姿はない。火星の地下に埋められたあの死神は完全に活動を停止した。もしもの場合に備えて、遠隔操作が可能なバルキリーのサブルーチンは今も稼働している。
チンジュがジャンプシップの最終確認を開始した。暗黒のピラミッドが上空から迫っている。船の貨物倉にはエクソの試作型シャーシが固定されていた。作業は慎重に進められた。
バンス: スズメ 
ガーディアンが聖所を離れた後、修道士バンスは持ち物をまとめ、焼け付くような水星の地表に向かって足を踏み出した。この行程を何度も繰り返していたかのように、無限の森への入り口は簡単に見つかった。彼は頭の中でこの場面を描き続けていたのだ。
今回は実際に足を踏み入れた。
無限の森がうなり声を上げ、バンスは目まいがするような虚無に襲われた。その反響は何の形も成していない。聖なる場に足を踏み入れた途端に、膝をついて嘔吐した。
嵐に鼓膜を叩かれながら、彼は自分の荷物を漁り、無限の肖像を取り出した。それはこの巨大な空間の中では途方もなく小さく見えた。そして震える指でそれを無限の森の音の波長に合わせた。メトロノームのように時が刻まれ、そして…
静寂があたりを包んだ。無限の森は封印された。
バンスは突然、自分が巨大な岩の上を歩いているような感覚に襲われた。これまでに何度もそうしてきたように、軽々とその石からジャンプした。それと同時に、彼は高く舞い上がっていた。彼はあらゆる方向に向かって、落下し、笑って、歌いながら、全ての道を通り、全ての現実に足を踏み入れ、希望のメッセージを拡散した。
オリジナルである本物のバンスは、その並行存在が際限なく発生しているのを感じていた。そのエコーが姿を消すごとに、まるで勇気づけられているかのようだった。嬉しさのあまり、呼吸をすることさえも忘れ、彼は声に出さずに何度も感謝した。すると安堵させるように無数の手が彼に触れた。彼はいつの間にか涙を流していた。
その黄金のエコーの渦の中で、修道士バンスは大きな声で歌い始めた。
「これは――」
背後から彼自身の声がそれに答えた。「未来に向けた希望だ」
バンスはその声に向かって飛んだ。自分のクロークを感じ、手は喉を掴んでいた。その形が歪み、彼の手の中で冷たさと鋭さを増した。
バンスは思わずのけぞったが、なんとか手は離さずにいた。彼はその手を目隠しをした相手の顔に押しつけると、目に指を食い込ませた。
相手は叫び声を上げた。残念だったな、とバンスは大笑いしながら心の中で呟いた。まだ目を残していたのがお前の運の尽きだ。

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ