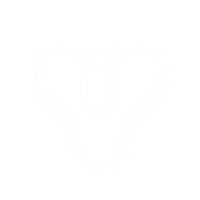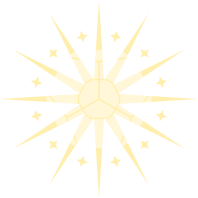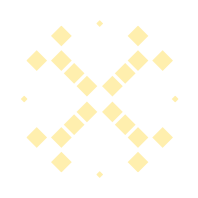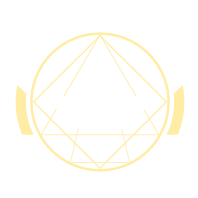終戦後に日の出を見られなかった者たちを偲んで。 
ジョルヨン・ティルは玉座の前に跪き、その目は床を見ている。「彼がブラックガーデンには入ったのは反抗のためではない。あなたを喜ばせるためだ。でなければ彼があれほどのリスクを犯すはずがない。彼にあそこまでさせることができるのは、この宇宙であなただけだ」彼は頭の頂点を穿つような女王の冷たい視線を感じていた。
「ジョルヨン、それは言い訳のつもりですか?」女王が不満そうに言った。「下らない。しかも子供じみている。暗黒は軽々しく扱うべきものではありません。お前のせいで何かを目覚めさせてしまったかもしれない。私は我らを守るために命令を下したのです。最も信頼の置けるクロウであるお前なら、そのことを理解していると思っていました」
「無論です、我が女王よ。理解はしています」
マラ・ソヴはゆっくりと高座から降りてくると幼なじみを見下ろした。彼は彼女の家臣でもあった。「理解していると言うが、お前は私の命令に背いてあの場所へ向かいました」
彼女は腰を支点にして前屈みになると、彼の耳元に触れそうなほど唇を近づけ、囁くように言った。「これは反逆か?」その言葉が虚ろな謁見の間に静かに響き渡った。ジョルヨンの血が凍り付いた。
「我が女王よ、どうか理解してほしい。ユルドレンは生まれながらにしてあなたの血族だ。あなたも互いのためになるのであれば何でもするはずだ」彼はそこで区切ると、次の言葉を慎重に選んだ。「彼はあなたの兄弟だ。ただ、私の兄弟でもある。彼には数え切れないほど助けられた。戦いだけじゃない。絶望していた私を救ってくれた。自信を持たせてくれた。ラヴィスカが死んだ時、私の世界が崩れ落ちた時、彼は私を私自身から救ってくれた」
体の中で感情がわき上がってきたジョルヨンは、いつのまにか顔を上げ、上から見下ろしていた女王の視線と目を合わせていた。「ユルドレンは私の兄弟でもある。私は彼を愛しているし、彼がどこに行ってもついていくつもりだ。彼が望むのであれば、それが例え死であったとしてもだ。彼はあなたにも同じことをするだろう。それを反逆と言うのであれば、好きにすればいい」

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ