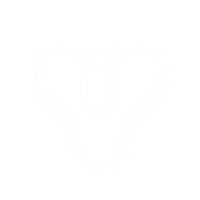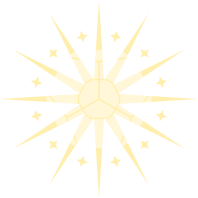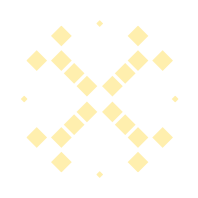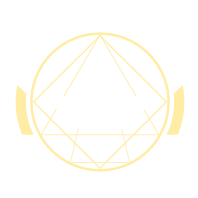「こういったものがどれだけあるんだ?」――アーサー・ヴォロニン中尉 
第1章: 配達中
ヴォロニンは運んでいた弾薬箱を落としかけた。落とせば、近隣の人々も大きな被害を受けることになる。彼らが想像しているような災害に比べればまだましだろうが、自分の身体を酷使するような混乱を来すには十分な規模だ。彼はこの手の仕事が嫌いだった。
「おい、モロゾバ!」とヴォロニンは息を切らしながら自分の上官に言った。「これがどこ宛てなのか知ってるか?」
モロゾバは子供をベッドに寝かしつけるように、ゆっくりと荷物を降ろした。「分からない。ただ上層部から急ぎだと言われている。タイタンで何か恐ろしいことが起きているんだろう」
ヴォロニンはヘルメットを脱ぐと額の汗を拭った。タイタン? 一体何が起こってるんだ? 連絡も飛び飛びだし、指示もおおざっぱなものだ。弾薬を調達しろ。弾薬を指定する座標に届けろ。弾薬を備蓄しろ。それを繰り返せ。ハンヴィーはなし。つまり道を使わず、目立たないように行動しろということだ。
これだけの弾薬が一体どこに運ばれ、何に使われるのだろうか? ヴォロニンは荷物を持ち上げるとペースを上げた。
何時間にも感じられる間、彼はモロゾバの後ろを重い足取りで歩き続けた。荷物は非常にかさばり、天気は夏真っ盛りで、これまでに経験したことがないほど乾燥していた。
目的地に到着すると、配達物のリストを忙しそうにまとめているバイコフから、おざなりな歓迎を受けた。見知らぬ2名の兵士が大地から突き出ているシャフトに荷物を移動させている。1人がコマンドを入力をすると、「ドスン」という音を空洞に響かせながら荷物は地下へと消えた。
「あれはどこに行くんだ?」とヴォロニンは質問した。バイコフは眉をひそめて険しい顔をした。彼はリストへと目を戻した。
「さて次にいこうか?」と、ヴォロニンが1年間かけても蓄えられないほどの元気を込めてモロゾバが言った。
「そうするしかないなら」
空は灰色になり、そこから立ち去る頃には雲が頭上を覆っていた。調達する、そしてそれの繰り返しだ。
ガイダンスとサンクチュアリの喪失。 
第2章: 衝突
最初の稲妻はヴォロニンの腕に静電気を走らせ、周りの空気を塩素のような刺激臭で満たした。気がつくと彼は、自分が無傷であることを確かめるかのように、自分の胸に手を当てていた。2つ目の稲妻が近くの大地に落ちるのを目にした。そしてまた雷が落ちる。これほど近くで稲妻を見たのは初めてだった。彼は唖然としながら大地に立ち尽くしていた。自分の命を案じるべきだと思う一方で、彼の心は恐怖というよりかは混乱によって支配されていた。
雨は降っていなかった。彼は地平線の方を見た。雲が、何かしらが見えるはずだった。だがそこにあるのはキラキラと光る青い稲妻のカーテンだけで、それはこちらに向かってきていた。
彼は大股で塵を蹴り上げながら、その場に弾薬箱を置き去りにし、急いで近くにある避難場所を探した。稲妻が激しく大地を打ち、火を放ち、岩を焦した。生じるタイミングにもなんら論理性はなく、あまりにも頻繁に稲妻が落ちるので、雷の音すらそれに追いつくことはなかった。
この混乱の中、モロゾバの姿は見失ってしまった。荷物の運搬で既に消耗していた彼の精神に残されていたのは、ごくごく単純な本能だけだった。走れ。
本能に従い、彼は走った。その身を取り囲みつつある終末を避けるために。足下の大地が揺れた時、彼の耳に声が聞こえてきた。「…予備避難ステーション…」それが唯一聞き取れた言葉だった。そしてその直後、雷のけたたましい音がその通信を飲み込んだ。
そのステーションにたどり着くには西に向かわなければならないことは理解していた。風は立っていられないほど強まり、彼は突然激しさを増した嵐により再び混乱状態に陥った。地面に激しく叩きつけられた彼は、自分の感覚中枢を確認した。空気の中を波打つ電気によってスクランブル状態になっていたが、なんとかコンパスを読み取ることはできた。西へ。彼は走った。
そう遠くない。 
第3章: 友のために
ヴォロニンは根こそぎにされた木々とビークルの残骸に身を隠しながら、破壊的な嵐の中を進んだ。彼は全ての終わりを目にしながら、自分がまだ生きていることが信じられないでいた。
ステーションは嵐に飲み込まれ、四方を包囲されていた。住民たちがひとまとまりになってSMILEポッドへと向かっている時、稲妻がその存在感を誇示し、近くにある燃料供給装置に火を付けた。そこから生じた爆発は住民一行を引き裂いた。そしてヴォロニンがその恐怖と熱から顔を背けようとした時、彼女を見つけた。ステーションからはおよそ250メートル、モロゾバは焼け焦げて煙を上げながら、瓦礫と灰の中に横たわっていた。
ヴォロニンは自分の感覚中枢を研ぎ澄ませた。だが空中の電磁フィールドが邪魔をする。彼女がまだ生きているのか、そして救い出せるのかさえ、全く分からなかった。彼女はヴォロニンよりも地位は上だったが、それでもなお敬意を持って彼に接してくれた。ヴォロニンの結婚生活が地獄と化した時もずっとそばにいてくれた。
「どうせ誰も助かりはしない」そう思った彼は、稲妻と暴風の嵐の中、彼女のもとに走って向かった。
たどり着き、グローブを外して彼女の顔から灰と血を拭っていると、嵐が頭上から襲いかかってきた。
間もなく82歳を迎える彼が自分の死を受け入れた時、彼らを取り囲んでいた嵐がやんだ。稲妻もおさまっていた。風も止まった。ステーションでは、住民たちの目が空に釘付けになっていた。だがヴォロニンはモロゾバだけを見ていた。まだ息はある。彼女は目を開くと、彼と目を合わせた。唇に微かに笑みをたたえた後、彼の背後に視線を移動させた彼女は恐怖に目を見開き、表情をこわばらせた。
ヴォロニンが振り返ると、そこには神の顔があった。
ようやく訪れた救済。 
第4章: 対面
ヴォロニンは口を大きく開いたまま固まっていた。肺は息をすることを忘れている。心臓の鼓動は早まり、胃はムカムカとし、これが人生の最後の瞬間なのだろうかと弱々しく考えた。彼はようやく立っているような状態だった。
トラベラー、人々はそう呼んでいた。彼は太陽系を旅する中でその話を聞いてきた。だがそれを生きている内にその目で見ることになるとは思っていなかった。今はむしろ、まるでトラベラーに見られているかのように感じる。
頭上の球体に引き寄せられるかのように、一歩前へと進んだ。彼はつまずいた。足下の地面はかなりの熱を帯びており、ブーツのゴムが溶けていた。畏怖と共に陳腐な考えが頭をよぎった――「トラベラーの目に自分は今とんだ間抜けに映っていることだろう」――そうして彼は自分を恥ずかしく思った。
遠くではまだ雷が鳴り響いている。その時、彼は自分が嵐の目の中にいることに気づいた。すさまじい轟音が周囲を取り巻いていたが、自らの周りは穏やかだった。間違いなくこれはトラベラーの仕業だ。偉大なる救世主。この状態がいつまで続くか分からないまま、彼はモロゾバを掴み立ち上がらせた。彼女は重傷を負っており、足の傷からは血が流れていた。
「離れるな」と彼はモロゾバとトラベラーに対して言った。それに従ったのは1人だけだった。トラベラーはその場を離れ、やがて嵐は戻ってきた。
「私から離れるな。こんな状況でそれは許されない」――アーサー・ヴォロニン中尉 
第5章: 忌まわしき命令
ヴォロニンはモロゾバの傷から流れる血を止めるために、ふくらはぎにアームバンドをきつく巻き付けた。風によって泥と瓦礫が舞う中、彼はモロゾバの足をできる限り清潔に保とうとした。稲妻がさらに近づいてきている。オゾンの不毛な臭いが再び漂い始めており、彼は時間があまり残されていないことに気づいていた。「戻ってこい!」と彼は絶望を感じながら神に向かって叫んだ。彼はモロゾバを立たせると、彼女を肩で支えながら、歩みを阻まんとするあらゆるものを払いのけながら進んだ。
避難ステーションまで250メートル。一歩一歩が消耗との戦いだった。この時、コールドスリープという考えが彼の励みになっていた。そのためには何としてもSMILEポッドまでたどり着かなければならない。だが嵐もまた、それを黙って見過ごすつもりはなかった。近くのハンヴィーに強烈な雷が落ち、その爆発によって彼らは遠くへと放り出された。地面に落ちた時、彼はモロゾバが自分の手から離れたのを感じ、同時に彼の頭が石に打ち付けられて雷よりも大きな音を立てた。視界が暗くなっていく中、彼は空のトラベラーを目にした。それは遠ざかり、彼から離れていこうとしていた。
…そして彼は残骸と暴力から引きずり出され、担架へと乗せられた。「…モロゾバ?」彼は力を振り絞り起き上がった。顔に酸素マスクが付けられた。目だけでも動かし、モロゾバが生きていることを示す痕跡を探そうとした。ヴォロニンは周囲の地獄から何も読み取ることができなかった。「すまない」彼はそう思いつつ、空の球体が自身を見捨てたことに憎しみを覚えた。
コールドスリープさせられる前の最後の記憶は、空に生じたすさまじい爆発と猛烈な光によって、その視界の全てが奪われた光景だった。

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ