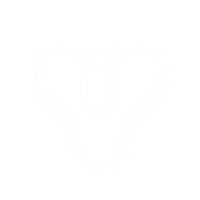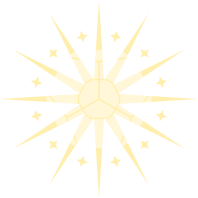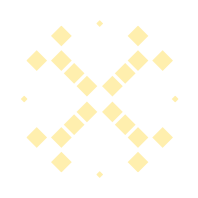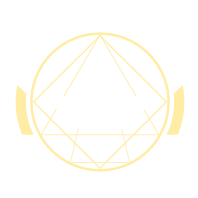凶報の使者。 
イコラの図書館にトランスマットした時、オノールは不機嫌だった。タワーに行くのは大嫌いだった。扉のない部屋で、別館の湿っぽい地下から遠く離れたところにいても、放浪者の硫黄の臭いを嗅ぐことができた。他の者たちはよく我慢できているなと彼女は不思議に思っていた。
イコラが書き物から顔を上げて笑顔を浮かべた時、彼女の苛立ちは少し収まった。「会えて嬉しいわ」と彼女は言った。
「嬉しいのか? 何か重大な用事のために呼び出されたものだと思ってたんだが」
「『安心した』のほうが正しいかもしれない。こういう任務を任せられる人は他にいない」イコラは席につくように合図した。オノールは首を横に振った。
「ほう?」
「あなたを褒めるつもりで言った。他の人がダメという意味じゃない」
「嫌な仕事を任せるからってお世辞はいらない」
イコラはため息をつき、データパッドをタップした。「我々の組織の中で、また汚染されたガーディアンが出たと報告があった」
クロークの内側でオノールのデータパッドが音を鳴らした。彼女は機械を取り出し、スクロールして内容を読んだ。「命令違反、バンガードの機密漏洩… 日常茶飯事だな。長期的および故意の拷問?」彼女は不思議そうに顔を上げた。
「フォールンの一般市民がハウス・オブ・サルベーションから逃げ出している」イコラは重い口ぶりで補足した。「彼女のファイアチームによると、彼女はエラミスがどういう風に暗黒を手に入れたのか知りたかったらしい。彼らが間に入ろうとしたら…」彼女の声が段々小さくなった。
オノールが鋭い視線を向けた。「自分の仲間も拷問したのか?」
イコラが頷いた。オノールはデータパッドをクロークの中にしまった。「今、彼女はどこに?」
「自分で暗黒に触れようと、まだエウロパにいると私たちは読んでいる」
「なるほど。バンガードの制限が解除されたことで、彼女はもっともらしい否認を主張できるわけか。その力に魅せられた者であれば誰でもそうする」と彼女は辛辣に指摘した。
「何度も同じことを言わせないで。バンガードは――」
「バンガードはタワーに暗黒が入るのを容認した。放浪者の移り気な監視下で行われている限り、ガーディアンたちに触れさせるのを許可している。さもなければ、罰として私を派遣するということだろう」
「罰ではない」イコラは冷静に訂正した。「償いだ。あなたにはまず彼らに協力するチャンスを与える。自己中心的な行動を反省し、人類が歩むべき道へ戻るように」
「そして今のところ、そういう奴は一人も出てきていない」
「だからといって、全員がそうだとは言い切れない」
「このトレスティンという奴はどうなんだ? 彼女ならって思ってるのかもしれないが… これで何人目だ? 私が彼らに猶予を与えることはない、彼らが私を先に殺さない限りはな」
「もういい」イコラの目が光った。「今回の件の結果について、楽観的なふりをするつもりはない。でも、暗黒に触れた者は永遠に汚染されたままという確証もない。その証明ができない限り、あなたへの指示は変わらない。分かった?」
オノールは歯を食いしばり、彼女をじっと見つめた。「今後は?」と言ったあとに首を横に振った。「いいさ。また奴らがどこかで大騒ぎした時に聞けるだろうからな」
「やりたくないならしなくてもいい。気持ちは分かる」
オノールは不安を抑え込んだ。「私は約束を守る」と彼女が言った。そして、一瞬にして彼女の姿が消えた。
炎と力によって鍛えられた。 
「やりたくないならしなくてもいい」イコラが言った。「気持ちは分かる」
図書館の反対側でオノールが睨む。穢れたガーディアンを追跡するという不快な任務に身を捧げており、彼女は潜みし者の中でも最も献身的な人物の一人であるといえる。しかし、だからこそイコラは心配だった。会うごとに彼女はどんどんやつれていっている気がする。ちょっとしたことで怒る。この聖戦のせいで疲弊してきているのだろうか? 彼女に休息ではなく新たな任務を与えることは間違いだったのだろうか?
「私は約束を守る」オノールはトランスマットする前にぴしゃりと答えた。
そう言われたところでイコラの不安は一向に改善されなかった。彼女はため息をつき、こめかみを撫でた。
だが、彼女にはあまり考えている余裕がなかった。また空気が割れるような音をたてた。イコラが目を開けると、先ほどまでオノールがいた場所にセイントが立っている。「イコラ・レイ、突然来てしまって申し訳――」
「どうやってここに?」彼女は思わず言った。潜みし者以外、彼女個人の図書館の場所は知らないはずだ。彼女はそう思っていた。
エクソは困惑した様子で彼女を見つめた。「ト――トランスマットで来たんだが」とあっさり答えた。もう一度話しかけようとした。「申し訳ないが、話したいことがある」
「いいえ、誤るのは私のほう。座って」彼女は肘掛け椅子の周りに積みあがっていた本を急いで片付けた。「あなたからのメッセージは受け取った。2回も同じことが起きたのは残念ね」
セイントが座ると、彼の巨大な体躯に比例して椅子が小さく見える。「確かに残念だ。不気味でもある。私は恐れている…」彼は言葉に詰まり、目を逸らす。窓の外を見ると、午後の光が黄金色に変わり、空に沈みはじめていた。「戦場では何をすればいいのか確信が持てる。迷いはない。試練もそうだった。だが、今はどうすればいいか分からない」
「よく分かる。私も、こういう事は私たちの能力を含めてあらゆるものを疑うために起きるんじゃないかとたまに思うことがある」イコラが彼の隣に座った。「だけど、こういう時に試練を任せられる人はあなたしかいない」
「試練にその名が与えられた者でも駄目なのか?」セイントは悲しそうな笑いを漏らす。「いずれにしても、あいつはやりたがらないが。尋ねても、忙しすぎるからとすぐに拒否される。手に負えないなら打ち切れと言われた」
「確かに彼は忙しい。カバルのゴタゴタで、3人目のバンガードのように動き回っている。だがカイアトルとの件が落ち着けば、もしかしたら…」
「そうじゃない。私は彼が忙しくてホッとしているんだ。忙しいのは良いことだ。失ったもののことを考えずに済む。だが、それでも彼は…」
「前とは違う?」
「いや。そうなんだが、それだけじゃない」彼は苛立ちで首を横に振った。「例の件について報告した時に、私と同じように心配するかと思った。だがその代わりに、次は詳細を書き留めてておいてくれと言われた。使えるデータが集まるだろうって」と、嫌悪に満ちた言い方で答えた。
イコラは話の続きを期待するようにセイントを見た。何も言わないと分かると、彼女は自分の席にまた深く座り、考えた。さして驚くことではなかった。オシリスは実験主義的であったし、気を遣うようなタイプでもない。いつもよりトゲトゲしい発言ではあるものの、セイントがなぜそんなに気にしているのか分からなかった。まるでオシリスに怒っているかのように気が立っている…
「あれだけ色々あった後なら、そんな風に言われて腹が立ったでしょう」彼女はゆっくりと話した。彼女の考えを肯定するかのように、セイントは目を逸らした。「でも彼が言うことも一理ある。私たちは暗黒についてあまりに無知すぎる。データは多ければ多いほど有利になる」
セイントは何も言わなかった。窓から入ってくる光が彼のヘルメットをオレンジ色に染める。
「だけど」彼女は続けた。「そのためにガーディアンを危険な目に遭わせるべきではない。今オシリスがどう考えていようと、試練はファイアチームを鍛えるために始まったもので、その目的は今後も変わらない」彼女は立ち上がり、片手をエクソの肩に置いた。「絶対ね」
彼は地平線を見つめたままうなずいた。「そうか」
掘れば跡が残る。 
もうすぐ終わる――カドマス・リッジを登るにつれ、トレスティンはそう感じた。
雪で増幅した日光が彼女の目を突き刺す。雲の上まで到達したのだ。彼女は視線を下にやり、眼前の岩山を見つめた。次の岩棚へ手を伸ばすと、筋肉が硬直した。
今更後戻りはできない。
無線から聞こえるサラディン卿の声が雑音混じりになった。「カバルの侵入… ベックス… 前方」トレスティンのゴーストが無言で電源を落とした。鉄の豪傑の命令を実行する者は他にも近くにいる。彼が見逃すことはないだろう。
従わない者はいないだろう――特に、彼女の元チームメイトなら。サッジが「私たちは暗黒の手前にいる境界線の役割を果たすべきだ、この裏切り者!」と言ったとおり、彼女は仲間を裏切った。
| 実に細い線だ。なら、なぜそれを飛びこさない? |
彼らがその素質を持っていなかったからだ。彼女自身の手でそれは確認した。確証を得るためにどちらもかち割り深く探った。だが、なかった。エウロパの氷の殻の下に潜む海のような、埋もれた巨大な飢え。表面からは検知できないが容赦なく引き寄せてくる激流。彼女は誰も裏切るつもりはなかった。ただ解放したいだけだった。
| もうすぐ、お前も手に入れられる。もうすぐ、お前は解放される。 |
疲労で震える筋肉に堪え、手を押し上げて、やっとのことで雪を掴んだ。彼女は頂上にたどり着いたのだ。
少しの間、彼女は荒くなった呼吸を落ち着かせるように堤防で寝そべった。視覚が明確になると彼女は息を呑んだ。輝くばかりの白に浮かび上がる黒い石。彼女の心臓の動きに合わせるように鼓動しているようだった。奥底に潜む欲望に同調するように。
心の奥から温かい、聞き覚えのある声が聞こえてきた。「バカだな」ヤラだ。突如、彼女の中で小さくも顕著な飢えが芽生えた。これは… 寂しさだろうか?
| 弱さだ。お前の眼前にあるのは力だ。 |
鼓動がさらに大きくなった。全身の血管に血が流れているのを感じながら、オベリスクへ近づいて手を伸ばした。こんなに近づいたのは初めてだ――
「それ以上はダメだ」新たな声がトレスティンに呼びかけた。ただし、今回は頭の中からではなかった。振り返ると、数メートル先に剣を抜いたウォーロックが立っていた。「トレスティンだな。私はオノール。こちらに付いてこい。大人しく」
トレスティンは彼女を見て、オベリスクの方へ飛んだ。
最後に彼女が感じたのは鋼だった。純粋な、冷たい鋼が、彼女の心臓を貫いた。
「だがお前はここにいる。これが本当の始まりだ…」――シン・マルファー 
エネルギーを失った軍事衛星が宇宙の虚空を力なく漂い、黄緑色に輝く金星のシルエットを横切っていく。
静止軌道にいるジャンプシップ「NS66クラウドエラント」の薄暗いコックピットの中から見ると、金星はまるで宇宙の暗闇から見上げる瞬きをしない目のようで、軍事衛星はその中に誤って入ってしまった砂粒のように見えた。シェルを奪われ、ただの金属の球体のような姿になったゴーストが、コックピットの端で浮かびながら、孤独な金星を横切る軍事衛星の姿を見つめていた。
「現在、金星には認可済みのバンガードの任務は存在しません」とゴーストが言うと、その冷たい青い瞳を回してガーディアンを見上げた。「なぜ彼がそこにいると?」
ウォーロックのシャユラが椅子にもたれかかると、古いレザーが軋んだ。彼女はゴーストではなく、コマンドコンソールの中央に置かれている人間の頭蓋骨を見ていた。その空洞の目が彼女をにらみ返す。
「彼がそこにいる理由は重要ではない」彼女は頭蓋骨の頬骨を調べながら力なく言った。彼女の指が小さな穴に触れた――ショットガンの弾が命中した痕跡だ。「重要なのは彼を見つけることだ」
シャユラのゴーストは彼女から視線を外すと、暗闇の中で優しく光る金星を見た。
「いつ地球に戻るのですか?」と彼が聞いた。
シャユラは言葉では答えず、その代わりに瞬きをすると、その輝く目をゴーストに向けた。ゴーストは静かにビープ音を鳴らすと、先ほどの質問を再考した。
「戻るんですよね?」ゴーストがまた質問した。
「いや」とシャユラがきっぱりと答えた。「戻る意味がない。あそこには私を見捨てた者か裏切った者しかいない。あそこに残されているのはトラベラーだけだ。それに、シティにいなくても光を感じることはできる」と言うと、シャユラは手を上げてその手のひらから、燃えさかる炎のカーテンを呼び出した。
「プラクシックファイアが私を導いてくれる」とシャユラは言った。彼女の瞳に炎が反射していた。
「見てみろ。まだ保護されている。使える」
ハウス・オブ・ライトの記章を身につけた小さなエリクスニーが、瓦礫の散乱する浅い階段を駆け上がった。そして足を止めると、後ろからついてきていたクロムアーマーのガーディアンのほうを振り返った。エリクスニーはそのガーディアンの様子を確認してから、金星の険しい風景の中に建っているコンクリートブロック製の巨大な灰色の建造物のほうを示した。
「学びの場には相応しくないな」とガーディアンは階段を登りながら言った。その目は警戒するように、かすんだ空に向けられていた。彼の磨かれたマスクの上で湿気が輝く玉を作り出していた。彼の黒いフードがその他の要素から彼を保護していた。「ここはどういう場所だ?」
エリクスニーが首をかしげ、4つの目を順番に瞬かせた。「人間ではない。分からない。ただ機械が中にある」
「なぜお前たちはそれを持ち帰らない? 高品質な物資を回収することで昇進できると聞いたぞ」ガーディアンは質問すると、倒壊したその建造物を示した。
エリクスニーは再び首をかしげると不明瞭な声で言った。「お前はスパイダーの秘密の言葉を聞くことに熱心になりすぎている。来い、まだ道のりは――」そこでエリクスニーの言葉が途切れると、サブマシンガンの銃撃を受けたことで、その声が湿気のこもった悲鳴へと変わった。
ガーディアンが振り返った。クロークがその背中で渦を巻き、彼の手にはハンドキャノンが握られていた。ところが、崖の上から降りてきたのはベックスでもフォールでもなかった――黒と金で彩られたアーマーを身につけたガーディアンが、サブマシンガンの銃口から煙を上げながら、地上へと滑空してきた。シャユラのブーツが枯れ葉の散ったプラザに優しく触れた。目のない彼女のマスクの視線は、クロムで覆われたハンターに固定されていた。
「彼は戦闘員じゃない!」とハンターが叫んだ。
シャユラはそのガーディアンにゆっくりと近づいた。「エラミスの裾の中で彼を見つけたのか? それとも彼女がいなくなった後、お前自ら暗黒に忠誠を誓ったのか?」
ハンターは階段まで後ずさると、ハンドキャノンの照準をシャユラに合わせた。彼はそのアーマーを知っていた――試練の報酬だ。「お前を知っているぞ…」彼の声は震えていた。「ここにいるはずがない。バンガードはいつお前を解放した?」
「解放されたわけではない。自分の意思で出てきた。奴らは敵のためにゲートを開くのに大忙しだったからな」シャユラはそう言うと、エリクスニーの死体にサブマシンガンのバレルを向けた。「だが、私がここにいる理由は知っているはずだ」
「お前は既に弾を数発消費している」とガーディアンは言うと、ハンドキャノンを使って挑発した。意識が逸れたその瞬間、シャユラは2度のバースト射撃で6発の弾丸を彼に撃ち込んだ。
ガーディアンが崩れ落ち、銃が音を立てながら階段を落ちていった。その直後、彼のゴーストが物質化した。そのシェルは怒りに燃えていた。「何をしているんですか!? 私たちは――」
シャユラは稲妻のように素早く動くと、プラクシックファイアの剣から炎を上げながらゴーストの隣に突然姿を現した。恐怖に悲鳴を上げたゴーストは、一瞬でバラバラになり、輝くパーツの山になった。
ハンターは階段の上に崩れ落ち、咳き込んでいた。その口は血で染まっていた。シャユラは砕けちったゴーストから視線を逸らすと、サブマシンガンの照準を獲物に合わせた。「裏切り者め」彼女はアドレナリンの効果によって呼吸を荒げながら、震えた声で言った。
ハンターは笑うと、自分の血で喉を詰まらせながら言った。「お前はドレドゲンと同じだ」と彼は苦しみながら言った。そして、さらに小さな声で続けた「…あるいはマルファーと変わらない」
「私が始末したのは暗黒のエージェントだ」とシャユラが言った。今度はハンターは言い返さなかった。彼はそのまま動かなかった。
胆汁がシャユラの喉の奥まで昇ってきた。
「奴らは様々な姿で現れる」

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ