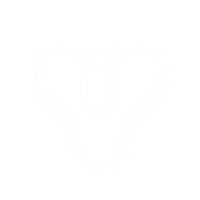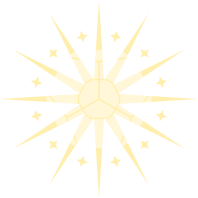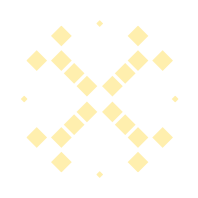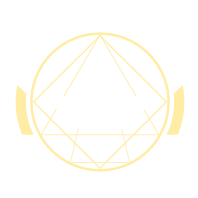フォアランナー
古の伝説の新たな幕開け。
バンシー44は、作業台の上に置かれたレリックを注意深く観察しながら己の心の中に浮かび上がる疑問について考えていた。中でも特に気になることがあった。一体誰のためのものなのか?
その形状から、何らかのピストルであると推測できた。だが、そのサイズはまるで巨人用かと思えるほど大きかった。機能は、対物ライフルとしての性格が強い。「12.7mmか… まるでハンドキャノンを作っていると知らずに組み立てたような代物だ」
バンシーはこんなものを操れる戦士などいるのかと考えていた。すると近くでシャックスの声が聞こえ、一瞬気を取られた。「ああ、そうか。もしかするとタイタンなら… それも特に大きな奴なら」
その武器には、火のごとき命と氷のごとき眠り、そしておそらく他のもっと異質な外的要因による傷跡が刻まれていた。バンシーはそのレリックの声を聞いてみたかったが、事前の調査で最後の一発が既に使われた後であることを知っていた。一体どんな一発だったのだろうか。
これを持ってきたガーディアンなら、突然分解してしまう予想外のリスクも気にせず試し撃ちしてくれるかもしれない。だが、バンシーはこの武器がもはやマガジン1つ分ですら持たないことに気づいていた。
レリックの横には取り外されたブリーチライトが置かれていた。これを大型化して、ケーシングとハンドガードをカスタムし、感覚中枢リンクスコープを装着… 他にもいろいろなアイデアを考えていた。
これは、レリックを作った者たちへ捧げるオマージュであり、供物であり、レガシーである。
その思いを胸にしながら、銃器技師は仕事を始めた。
アガーの杖
「愛する兄よ。私がしてきたように、あなたもいつの日か世界を自分の好みどおりに形作ることになるでしょう」――マラ・ソヴ女王
マラ・ソヴは半円なって囲む子供たちを楽しませるために飛んでいる鳥の真似をする兄を眺めた。まるで駄菓子を配りでもしたかのように、皆が彼の話に夢中になって集まっていた。
ユルドレンは足を踏み出し、細い剣を空中へとかざした。生い茂るバリオンの巨木に英雄のポーズをした彼の影が落ちる。
「嵐を切り裂け!」彼が叫ぶと、アウォークンの子供たちは笑いと拍手で大騒ぎした。「そう。二羽のハヤブサは、まるで風を切る刃のようだった」そう言うと彼は見事な剣を鞘におさめた。「一緒にいれば、誰にも止められなかった」
マラは振り返り、境界内の奥深く、空に浮かぶ宇宙港に停泊するアウォークンの艦隊を見渡した。まもなく彼らは下船する。今夜は喜びの宴だ。愛する者が戻って来ないかもしれない未来に備えて、家族は思い出を心に刻む。朝には土星に旅立つことになる。
遠方の小惑星が雷鳴のようにとどろき、子供たちを驚かせて騒がせた。
「アガーはまた戦っているようだな」ユルドレンはそう言って、景色が見えるようにベンチの上に立った。差し迫る嵐を見るかのように、彼は手を眉の上にやった。
やっと6歳になるかというような幼いアウォークンの子供が立った。少女の目に心配の陰りが宿っているのをユルドレンは見た。
「アガーは大丈夫? 戦ってるのが見えるの?」
「ああ」とユルドレンが答えた。「こっちにおいで」
少女が一歩近づいた。
「君の名前は、確かイーリスだったか?」とユルドレンは尋ねた。少女は畏敬の念を抱きながら頷いた。ユルドレンはベルトから望遠鏡を取り出し、彼女に渡した。「私が指すところを見てごらん」
イーリスは王子が指差す、空が光っている方向を見た。
「アガーが見える!」と少女は大声で言った。「レガも見えるよ!」
ユルドレンは少女の肩を優しく叩いて微笑んだ。「アガーとレガが一緒にいるなら絶対に負けない。私たちみたいに。君も仲間と一緒なら、きっと大丈夫だ」
マラがユルドレンの目を見て、前に出た。「お話は終わりです。王子は朝に長旅へと出発しなければならないので、休む必要があります。お家に帰りなさい」
子供の姿が見えなくなった瞬間、マラが睨むような表情を見せた。「くだらない話ばかり…」彼女はユルドレンの方へ身をかがめた。「子供たちにバカなことを教えるのはやめてください」
ローレンツドライバー
「トリガーを引いても、もう武器システムが爆発することはない」――プロトタイプ7.2.1修正メモ
「このライフルは?」2機のブリッグが貨物を運搬する音より大きな声でスコルソが尋ねる。彼女の監督者、ピークシという名の三つ腕のバンダルが武器を覆う布を剥ぐ。武器用ではない素材を組み合わせて作られたライフルをしばし分析し、ブリッグが進む方向を示した。
「良い料理だって腐る」ピークシが言う。「運べ。だが、スペアパーツは全部置いていけ」
スコルソは頷いて了承の意を示したが、すぐに作業に戻らずにピークシの近くに寄り、倉庫を見渡す。「本当にやるのか?」と、ささやくように聞く。
スコルソがライフルを近くのクレートに置いたところで、ピークシは彼女から離れた。「恐らくな。2本の手で挨拶を交わす一方で、もう2本の手は隠されている。生き残るための手段だ」
スコルソは避けるピークシを追い詰めるようにクレートを回り込み、4つの目を細めた。「スパイダーは怖がっている」と再びささやいた。「そうだろう?」
ピークシはすぐに身を寄せた。「それ以上口を開いたら、もうどうなっても知らないぞ」と、鋭いささやきを発し、背後に目くばせする。
「そもそも、私たちはどこに行くというんだ?」スコルソはピークシの数多い目を追いながら尋ねる。監督者は素知らぬ感じで肩をすくめる。
「さあな」ピークシは嘘をつき、彼女ににんまりと笑顔を向ける。「だが、一部のエリクスニーが言うように『全ては光の意思』なのかもしれないな」
ギャラルホルン
「破壊に美しさがあるなら、そこに至る過程も同様のはずだ」――フェイゼル・クラックス
ランディはついにタワーにたどり着いた。コスモドロームからの道のりは長かったが、ショー・ハンの的確な指示のおかげでなんとかなった。旧ロシアからの旅で船が爆発したのは2回だけだったし、2回目の修理(前よりはるかに良くなった)をしているゴーストを守っている間に、戦利品まで見つけた!
ランディがタワーの着陸パッドに姿を現すと、様々な年代の人間やガーディアンが集まってきていた。その中にある人物がいた。ランディはその人物から、エキゾチックで神秘的なオーラが放たれているのを感じた。擦り切れた肘で人混みをかき分け、やっとのことで突破すると、その人物がガーディアンであることに気づいた。彼はタワーの手すりに片足を乗せて立っている。ランディのゴーストは、この人物について何度か話したことがあった。確か何かの英雄だと言っていた。
だが、それがどうした。ランディだって英雄なのだ。
そのガーディアンが手にしている武器を見て「すごいな」と口にするタイタンがいた。ランディはその奇妙なチェインメイルのバイザーを被ったタイタンを見た。
「ただのロケットランチャーだ。こっちにだって旧ロシアで手に入れたランチャーがある」そう言ってランディは自慢げにランチャーを取り出した。
すると、ランディのゴーストであるダンディが彼をつついた。「よく聞いてください、ベリーブルー」ダンディが続ける。「あのガーディアンが手にしているのは、最強の狼の群れを放つ装置です。つまり発射するたびに、追尾式マイクロロケットの群れが襲い掛かってくるという地獄が繰り広げられるわけです。カラスの群れを指して人殺しと呼ぶ話をしたと思いますが、それはこっちの群れにこそ相応しい呼び名でしょうね」
ランディは自分のランチャー「悪い予感」を掲げながら、「これにも追跡モジュールを付けられる」と言うと、ダンディは笑いながら「かもしれません」と言った。
ランディは「悪い予感」に視線を落とし、自分の装備の凡庸さに誇りが悔しさに変わるのを感じた。そして怒りのままにランチャーをガーディアンの頭上、タワーの手すりの上に投げつけた。
ガーディアンはくるりと向きを変え、姿勢を崩さず肩に担いだ「ギャラルホルン」を発射し、「悪い予感」を吹き飛ばした。そしてさらに小型の追尾式ロケットが落下する「悪い予感」のかけらを追跡し、地面に落ちる前に花火のように木っ端みじんにした。あとには燃料の燃える甘い香りが空中に漂うばかりだった。
思わずランディの口が開いた。
ガーディアンは一歩前に出て、笑顔でランディの手にギャラルホルンを渡してきた。
「これを使って伝説の一歩を踏み出せ」
代替案なし
弾薬がない? 問題ない。
オースティンはレイラインの外の、バンケットテーブルほどの大きさの平らな石の上へ投げ出された。高い壁が全面を包囲している。アセンダントエネルギーの異常で発生した、存在しないはずの空間だ。
これなら十分だろう。
石牢の隅から彼女を投げ飛ばした波打つエネルギーの壁まで、この空間の大きさを測る。手を魔術の波の中へ放り出し、ウェイファインダーの技を使いラインの境界線を掻きまわす。発生させた逆流はやがて勢いを増し、暗黒の中をうごめくものの注意を引いた。
彼女はしばし休み、そして再び渦巻く魔術の中へ手を伸ばし、あるはずのないものに触れようとする。濁ったエネルギーの中で、ハイヴ・スロールが伸ばした腕を掴んだ。
焦りながら探り、やがて細くて脆いものを引き当てた。一部は未知の次元に転移の途中で取り残されている。彼女は手をすぐさま閉じて捻り、拳の中で腕が砕けるのを感じた。腕の主が悲鳴をあげる。
彼女は一歩下がって最後の魔力を振り絞り、苦悶の音に引き付けられラインに侵入しようとするシヴ・アラスの貪欲なハイヴの群れの前に、薄いクリスタルの壁を生成した。
ハイヴたちは彼女の罠に流れ込んで大きな一塊となり、互いに押し潰し合うような状態になっていた。貪欲なハイヴの塊はどんどん膨れ上がり、クリスタルの壁に爪を突き立てる。
オースティンはバリアに背を向け、女王が来るのを待った。
ラディエント・ダンスマシン
素早く動けるように作られている。予想外かつ決定的な社会的利益をもたらす。
機転が利くイライアは、次元の波打つエネルギーに身を任せていた。
彼女の周囲の空間で、シヴ・アラスのハイヴたちが唸りながら口を鳴らし、層をなした魔術を歯で食いちぎる。彼女が近くにいることを感じ取っているのだ。
彼女はエネルギーの中を指でなぞった。故郷への道をあてもなく必死に掴もうとしていた際に見つけた場所へ近づくと、大きなさざ波が生じる。
見つけた。
流れの中で身体をひねり、自身の存在を示す。夢見る都市を思い、彼女の周囲に安堵の空気が流れる。サバスンが捕らえられている姿を思い描いた。長くに渡る歴史の中で、彼女がここまで弱体化するのは初めてのことだった。
ハイヴは勝利の雄叫びをあげ、揺らめきながら彼女がいる空間に現れる。
イライアはかすかな魔術を身にまとい、レイラインから身を投げだす。唸るハイヴの群れが彼女を追って裂け目から飛び出し… 虚無へと転がり落ちてゆく。
ルーンのリボンからぶら下がるイライアは、遠く忘れ去られた地の黒き石へ落ちていく彼らを眺める。流れに身を戻す際に、魔術が彼女の手を切り裂く。
彼女は再び次元を閉ざし、思考をクリアにし、待ち構えた。
無の籠手
これはいわば方程式だ。お前が消えれば私が称えられる。お前が倒れれば私が強くなる。
スジャリはアメジスト色の乱気流の中を仰向けで流れていた。
意識を集中させて冷静さを保つことで、次元の狭間の魔術の流れに身をとどめようとした。姿を見せないように。ハイヴに気づかれないように。
周囲にハイヴを感じる。その禍々しい存在がレイラインに負荷をかけ、潜在空間の入り口が実体化するのを待っている。
エネルギーの爆発でラインから投げ出された後にたどり着いたのここがどこなのか分からないが、彼らをこの場所に留め、夢見る都市から… マラから遠く引き離しておかなくてはならない。
マラの帰還を思うと希望がわいてくる。薄紫の霧の中にマラの顔が見える気がする。
影響はかすかだがすぐに見られた。レイラインの流れが穏やかに変わり、スジャリは女王の元へと引き戻される。
彼女は一生懸命マラのことを考えないようにした。その代わりに、暗黒の次元の世界の狭間に捕らわれた、恐ろしいほどに曖昧な状態の静けさと垣間見える漆黒について思いを巡らせた。
彼女は欲し、乞う。流れが彼女を聞き入れる。流れが穏やかになり、スジャリは再びあてもなく漂う。
ハイヴを故郷へ案内するくらいなら、この不毛な領域で死んだほうがマシだ。