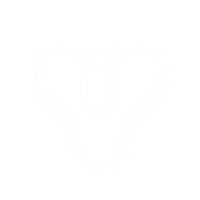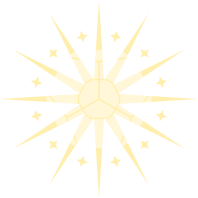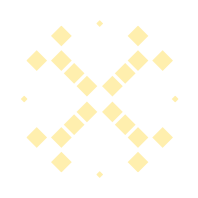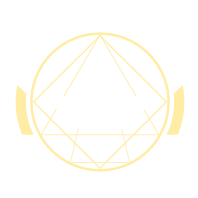「最初の大災害は過去のことになったかもしれないが、2番目はどこまでもついて回るぞ」——放浪者 
放浪者は座席を後ろに倒し、頭の後ろで手を組んだ。アルカディア級ジャンプシップがシティへ向かう物資を運ぶ列車の上空を轟音を立てて飛んでいる時、彼はその中に座っていた。彼の隣にいる船の持ち主のタイタンは、下にいてスピードを上げている列車と並行に並ぼうとして悪態をついていた。
「苦労に見合った報酬がないと困る」と彼女はうめいた。
「次のギャンビットでは2倍のかけらが手に入ると言っただろう。期待していい。信じてくれ」放浪者は背筋を伸ばして座りなおした。「近くに寄せろ。後は俺がやる。ただ、ちゃんと戻れるようにしてくれよ」
船のサイドハッチを開けると、空気がうなりを上げてキャビンに飛び込んで来た。彼は騒音に負けないように叫んだ。「あんたらが軍にいなくてよかったよ。こんなふうに買収するのが簡単だからな」
「亜空間に消えな」タイタンが怒鳴り返した。
放浪者は船から飛び出し、下の列車に上手く着地した。彼は巨大なハンドキャノンを取り出し、這い進んだ。風が彼の上着を切り裂いた。
「純粋にどれだけ頑固かってだけで、生存と全滅の命運が分かれることがある」——放浪者 
放浪者は困っていた。
彼はこの列車がレッドジャックに護衛されているものだと思っていたのだ。この車両の後ろで2人を殺してきた。
2人の巨大なタイタンの肩越しに、探していた箱を見ることができた。彼らのアーマーには、クルーシブルの印がついている。これは交渉にあたって、細心の注意が必要だ。彼らは放浪者にライフルを向けた。キョンシー AR4。いい品だ。
「まあまあ」と放浪者は声を出しながら、手を挙げた。「騒ぎを起こしたいわけじゃない」
彼らは顔を見合わせた。その後、一瞬彼を見た。
「ここで何をしてやがる、放浪者」左に立っている方が言った。
放浪者は笑った。「ジョクサー。元気か?」
「乗せられるな」右側のタイタンが言った。「レドリックス?」放浪者は、ギャンビットの常連を見つけたのだ。「聞いてくれ、兄弟。後ろにあるその箱が必要なんだ。探しものを見つけるのが大変なのは分かるだろ。俺はあさり屋だ。きつい暮らしだよ。見逃してくれ」
「ザヴァラは気に入らないぞ、放浪者」とジョクサーは言った。
放浪者は片方の眉を上げた。「つまり、あんたらはバンガードの言いなりだってことか?」
彼らは答えなかった。
放浪者は2人に近づいた。「なあ。頼むよ。やってくれたら必ずあんたらに礼をする。来週のギャンビットに顔を出してくれればいい。かけらのレートを2倍にしてやる」
タイタンたちは再び顔を見合わせた。
「宇宙事象の時もあるし、地獄から来た獣の時もあるし、たった1人の人間の時もある」——放浪者 
放浪者は、見晴らしのいい列車の屋根の上からレッドジャックを見た。シャックス卿の馬鹿なフレーム2体が車両のドアをガードしていた。放浪者はハンドキャノンをホルスターに入れ、かわりに長い剣を抜いた。彼は下のデッキに飛び降り、弧を描く一振りでフレームの頭を落とす。剣を鞘に納め、それが倒れる前に身体を受け止めた。静寂だ。
レッドジャックが2人いるということは、どこかにもっといる。銃撃戦は始めたくはなかった。車両に入り、身を低くかがめる。彼は笑いを抑えることができなかった。レッドジャックは確かに頑張ってはいる。だが平均的なジャックは、3つ以上の任務を耐えぬくことはなかった。
ギャンビットはクルーシブルのガーディアンに人気だった。彼らはよく、アーサイトとダリアの伝説について語る。シティの早期の頃からいる、戦闘経験豊富なレッドジャックだ。放浪者は実物を見なければ信じないと思った。彼は動き続けた。
「アルマゲドンが発生した回数を数えるのはもうやめた」——放浪者 
放浪者は探しているものを見つけた。3つの長いコンテナには「テックス・メカニカ」のマークがついていた。
彼はそれぞれの蓋の下に長い剣を差し込んでこじ開けた。ライフル、ピストル、それに… ハンドキャノン。放浪者はハンドキャノンを長い箱から取り出し、ぼんやりした明かりの中にそれを掲げた。放浪者は広い世界を見て来た。この銀河における暗黒時代の兵器の情報源の1つは彼だ。ギャンビット。
暗黒時代の武器は光と光が戦っている時代に作られた。その当時は全てがもう少しだけ効率的だったし、破壊的だった。もちろん、放浪者の見解では、だ。
だが、テックス・メカニカ? 彼らは集まって、そして非常にいいキャノンを作った。放浪者は手にしたそれをまじまじと見つめた。伝説の品だ。
列車が揺れる衝撃で彼は白昼夢から目を覚ました。
彼は運べる限りのものを手に取った。
「終末みたいな顔と砂漠のマナみたいな目をしてた。一目見て、俺はもう終わったって分かった」——放浪者 
放浪者はたどり着いた場所から列車の後部へと折り返した。彼はジョクサーとレドリックスを通り過ぎた。どうやら彼らは放浪者が首を落としたレッドジャックを発見したようだった。2人は慌てて列車がシティに到着する前にフレームを元通りにしようとしていた。
「少しは落ち着いたらどうだ」と放浪者は言った。
「地獄へ落ちろ、放浪者」とレドリックスは明らかに不愉快そうに言った。
彼とジョクサーは放浪者が身に付けているテックス・メカニカの装備をじっと見つめた。彼らは考え直しているようだった。放浪者は座れるように、ロケットランチャーを外した。
「なあ兄弟。これは全部ワケあってやってる。ギャンビットもだ。俺が好きで毎日お前らとあそこへ行ってると思うか? お前らはまともじゃない。好きでやってるわけがないだろ。ワケありなんだ」
彼はポケットから闇のかけらを取り出した。それは冷たく光っていた。「今までどれだけの光のかけらを集めたか考えてみろ。沢山だ、そうだろ?」
「ミソクラストが恋しい」とジョクサーは言った。放浪者は彼の声に不快感を聞き取った。
「ああ、ミソクラスト、持ってたよな! それでもカバルはタワーを占拠した。光はあんたを裏切った。俺のこともな」
放浪者は彼らに闇のかけらを掲げて見せた。「だが、これは特別なものだ。俺が作った。ほんの一握りでも見つければ何ができるかを見たな。よく考えてみてくれ」放浪者はランチャーを肩に掛けなおし、後ろを見ずに立ち去ろうと向きを変えた。
「俺につけば、闇の真の力を見せてやる」
その時が来たら… タイタンよ、彼のために道を切り拓くか? 
「彼女は蛇だった」——暗黒時代の放浪者
✱✱
初めて彼女に会った時、何よりも目についたのはその入れ墨だった。彼女の腕に絡みつく、1匹の蛇。後に、大衆を奮起させるには象徴的なものが必要だと悟った時、彼はその蛇のことを思い出した。「ギャンビット」という戯れの象徴として。
それは、後にシティと呼ばれる最後の安全な都市が台頭するよりも前のことだ。彼は煙のように各地を渡り歩く、真の放浪者だった。彼を単に「放浪者」と呼ぶ者たちもいた。彼には他にもいくつも呼び名があり、決まった名前はなかった。
当時の彼女にとって、彼は「エリ」だった。彼らが2度目に会った時、彼はこう言った。「出発する前に、少し踊らないか?」
「今はダメ」と彼女は言った。
すると彼が尋ねる。「あれ、いま俺はなんて言った?」
「少し踊らないか?」彼女は繰り返した。
「喜んで」そう言って彼は腕を上げ、一歩踏み出した。
それを見て彼女が笑う。
そして彼は動きを止めた。
「この手が通じたのは初めてだ」
彼は遠征隊に加わり、彼女と共に戦った。 互いの命を救い合いながら。
やがて彼は、彼女のことを親友と思うようになる。
だがそれは間違いだった。彼女は彼の前から姿を消すことになる。
少なくとも、彼の知る彼女とは。
「最初の大災害は過去のことになったかもしれないが、2番目はどこまでもついて回るぞ」——放浪者 
エメラルド・コースト。ヨーロッパ・デッドゾーン。
はるか上空でガーディアンのジャンプシップが轟音を立てた。放浪者はカバルのシールドとアーマーを通り過ぎながら海岸線に沿って歩いた。タワーの光が、彼のささやかなゲームの役に立っている。
彼は巨大なハンドキャノンを握りしめ、ゴーストがその頭の周りを死肉にたかるハエのようにブンブンと飛び回っている。その光はまるでベックスの目のように赤かった。放浪者は歩きながら戦場を見渡し、デレリクトのAIにハンガーまでトランスマットさせる武器やスクラップを頭に入れていた。浜辺にはカバルの器材が散乱し燃えていた。放浪者はその全てに使い道を見出すつもりだ。デレリクトの日々のメンテナンス。追加の貯蔵器。
放浪者は、カバルのシールドを2つ組み合わせれば、日差しを避けて昼寝ができる気の利いた小屋が作れるだろうと考えた。
彼は打ち捨てられたスラグライフルに向かって這っているリージョナリーの横をのんびり通り、その頭を撃った。キャノンの轟音が浜辺に響き渡った。
ギャンビットの稼ぎは順調で、他の戦場を手に入れるための資金も貯まりそうだった。
かがんで倒れたコロッサスのアーマーの通信機を弄っているサイオンの横を通った。
放浪者のキャノンが火を噴き、小型の変形したカバルを後ろに弾き飛ばす。その頭はすみれ色の蒸気となって消えた。
放浪者はそのままブラブラと歩き続け、デレリクトが戦場へ到着する準備を進めた。周囲は静かで、時折キャノンの轟音だけが響き渡った。

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ