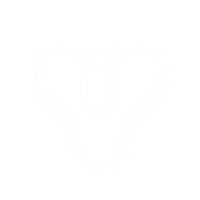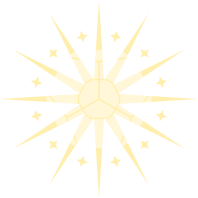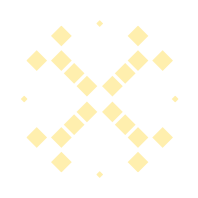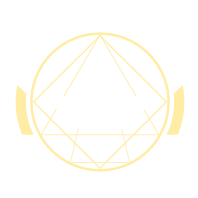ウィータブレウィス 
人生に無駄にできる時間はない。

「罠だったらどうします?」クロウを中心に歪んだ円を描きながらグリントが言った。クロウは錆びた2つの倉庫の間を走っている雑草だらけの通路に勢いよく入っていった。「ここはデビルズの古い縄張りです。確かに友人は私たちを逃がしてくれたのかもしれません。ですがスパイダーがあなたを捕まようとしていたら…」
「もしそうならとっくの昔にそうしている」クロウは影から影へと視線を移しながら落ち着いた声で言った。「そもそも、私が来ることを知らなければ罠を仕掛ける暇など――」
レーザーがクロウの鼻をかすめた。倉庫の屋根の上から、しゃがれ声のエリクスニー語が響く。クロウがその声に従って両手を挙げると同時に、グリントは姿を消した。
「よく熟れた極上のいちじくを探している」クロウは自分に向けられている複数のスナイパーライフルに取り付けられた照準器の電子音越しに叫んだ。彼らの耳に届いただろうか?「いちじくだ!」と彼はさらに大きな声で叫んだ。
ひとつ、またひとつと照準器が視界から消えていった。すると彼の右側でキーッという金属音が鳴り響き、間に合わせの扉が横へと引っ張られると、見覚えのある昆虫のような顔が姿を現した。
「アヴロック」クロウは言いながら両手を下げた。「昇進したようだな」
冗談を言う気分ではないようで、エリクスニーは溜息をつきながら後ろに下がって倉庫の中へと入った。クロウも彼に続いて中に入り、扉を閉めた。
「新任の女帝のオッズはどうなっている?」彼はそう言うと、素早く瞬きを繰り返した。そこは暗く、クロウに見えるのは動きのない複数の巨大な物体に取り囲まれながらクレートの上に座っているアヴロックの輪郭だけだった。「女帝がザヴァラ司令官を跪かせるかどうか賭けをしているんだろう」
「耳の早い奴だ」とアヴロックが唸った。「情報はタダじゃない」
「心配するな、隠れ家から良い物を持ってきた」クロウがグリマーの塊を持ち上げると、その青い光が壁沿いに積み重なっている担保品の数々を照らした。「持つべきものは元レッドリージョンの友というわけか、なるほどな」
アヴロックはニヤリと笑うと、わざとらしい所作で長い腕を広げた。エネルギーシールド、開封済みのプラネットクラッカーの箱、マグマランチャー… カバルのありとあらゆる装備品が部屋を埋め尽くしている。
部屋の隅でひときわ目を引く物体が光を放っていた。スパローだ。洗練されていて、ブロンズ色に磨き上げられている。クロウはそれを近くで見るためにゆっくりと歩み寄った。
「美しい機械だ」彼の仲間が声に出して同意した。「ヴァル・マラグは、自分が最初に女帝の軍事会議に加わると豪語している」
小さな光が一瞬またたき、グリントが近くで見ようと再び姿を現した。「自分に賭けるとは」グリントが言った。「まさにあなた向けのカバルです」
クロウはしゃがみ込んで、スパローの鼻先に取り付けられた飾りを観察した。「動機は多いに越したことはない」と彼は呟いた。
彼は立ち上がるとアヴロックのほうを向いた。「彼の賭けに乗ろう。ヴァル・マラグが議席を手に入れたら、年季の入った私のスパローは彼のものだ。ただ、我々が彼の証明の儀式を妨害したら、その時は、当然…」
フォールンが吹き出した。「大きく出たな! スパイダーはお前を手放すべきじゃなかった。手数料は7%だ」
「7%!」グリントが憤然とまたたいた。「スパイダーの手数料は高すぎです。そう思いませんか?」
アヴロックは彼を無視して、何もない空間を示した。「そこにお前のスパローを置いておけ。さて、賭けの詳細な取り決めをしよう」
「自分のスパローを賭けるなんて信じられません」アヴロックの耳に届かない場所まで移動してからグリントが呟いた。「あなたは長い距離を歩くのが嫌いなはずです」
クロウが肩をすくめた。「それよりも勝つことのほうが好きなんだ」
スピード・カラー 
「ある程度のレベルに達すると、決断力がスピードのカギを握ります」――ペトラ・ベンジ

エヴァ・レバンテが上質な白いシルクの糸を針に通している。ランプが、テーブルの木目と彼女の目の前にある美しい黒い布地全体を照らしていた。彼女がこの衣服に触れるのは、シティにある自分の小さな家が静けさに包まれる夜だけだった。
彼女はひと縫いするごとに、この秘密の仕事のきっかけとなった、数か月前の奇妙な出会いを思い出していた。
それは深夜の出来事だった。タワーから徒歩で帰り、自分の家の前まで来た時、彼女の耳に柔らかくて静かな聞き覚えのある声が聞こえてきた。「エヴァ。本当に久しぶりだ。相変わらず元気そうだな」と言うと、オシリスが出入り口の近くの影から姿を現した。
元装飾技師は鼻を鳴らした。「数世紀の間、50歳のままでいる人から言われてもあまり嬉しくないわね」
「私も他の部分では年齢を感じている。入ってもいいか?」
「もちろんよ」と言って彼女は扉を開けると、玄関に入る前に彼が両肩越しに後ろを確かめていたことに気付いた。
「またタワーで会えて嬉しいわ、オシリス」と言うと、エヴァは目の端で彼を見ながらやかんを火にかけた。「バンガードの公務で来たわけではないようね」
「ああ、そうだ。頼みがあっててここに来た、もしくは契約を結びたい。どうするかはそっちに任せる」そう言うと、オシリスはカウチの端に居心地悪そうに腰を下ろした。エヴァが笑った。狭いアパートのありふれた内装に対して、彼の式服はかなり不釣り合いに見えた。
「旧友の役に立てるならいつだって歓迎よ。例え私が歳を取ったとしてもね」と言うと、厳しい表情をした訪問客を優しい目で観察した。「何が必要なの?」
「特注品のハンタークローク。カラスの羽をイメージしたものだ」
「タワーにはその要求を満たしてくれるような装飾技師がたくさんいるわ。数年前に衣服の受注生産はやめたのよ。指が動かなくなってきたから」と言うと、彼女は反射的に拳をマッサージした。
「信用できる者に頼みたいんだ。秘密を守れなければ話にならない」と、感情の読めない視線を向けながらオシリスは言った。「やってくれるなら、生地選びのために、後でグリントというゴーストをこちらに送る」
「秘密のクローク? まるで昔のケイドみたいね。そういえば、最後に縫ったハンタークロークも彼に頼まれたものだったわ…」彼女は声を悲しそうに震わせたながら、お茶を入れた。
それから数か月後、彼女は頼まれたクロークの仕上げに入っていた。微かな光に照らされた黒い生地が、繊細な白いシルクを際立たせている。彼女の作品の中でも傑作の部類に入る。
エヴァはこの新たなクロークの持ち主のことを考えずにはいられなかった。ここまで秘密主義を貫く人物とは誰なのだろう? エヴァはとにかくこれが、ケイドのような素晴らしいハンターの手に渡ることを願った。
パラダイムシフト 
あまりの速さに新たなバリアを開発する必要がある。

「彼女のことは二度と口にするな」オシリスは怒りながらエクソのタイタンに言った。彼の声が騒々しいハンガーに響き渡った。
数十メートル先のジャンプシップの影の中で、クロウとホリデイが同時に顔をしかめた。彼らは船から下りたばかりだったが、もしクロウの反応が遅れていたら、この口論のまっただ中に足を踏み入れることになっていただろう。諜報活動をしていたおかげで、私的な会話に対する彼の第六感は誰よりも発達していた。現場だけでなく拠点でもこの能力の有効性が証明されたのはありがたいことだった。
「ああもう」怒って出て行くオシリスを見ながらホリデイが呟いた。クロウは説明を求めて彼女を見た。このエクソの正体は? 初めて聞いたその「彼女」とは誰のことだ?「後で説明してあげるよ」と彼女は囁くと、遮蔽物の後ろから出た。
「ホリデイ!」クロウが慌てて言った。だが遅かった。彼女は既にエクソの横に並び、同情を示すように彼の肩に手を置いていた。
彼は足の前後を入替えながら、自分に与えられた選択肢の重さを量った。物事がいたって順調に進んでいたとしても、新たな状況が訪れる度に彼は不安を感じていた。タワーではほとんどのガーディアンがマスクをつけておらず、会話に加わりたいという気持ちもあったが、自分の顔を見せたらどうなるかはしっかりと理解していた。それでも、マスクをつけている時間が長くなればなるほど、自分が余計に注目を集めているような気がしてならなかった。いずれは疑念を呼び起こすだろう。
だがそうとも言い切れない。エクソはヘルメットをかぶっていたが、ホリデイは最近クロウと出会ったときと同じように、特にそれを気にしていないようだった。
そもそも、永遠にマスクをかぶり続けるのと影の中でコソコソし続けるのは、どちらのほうがより怪しまれるだろうか? クロウは階段の下から出ると平静を装った。彼が近づくとホリデイの声が聞こえてきた。「私に何かできることがあれば言ってね?」
彼らが何を話しているのかを考え始めた瞬間、エクソが彼のほうを向き、雷鳴のように言った。「で、彼は? 体は細いが動きが力強い。恐らくハンターだな」
用意していた当たり障りのない挨拶の言葉がクロウの頭の中から消失してしまった。喉をつまらせ、彼が無言のままうなずくと、ホリデイが笑いながら彼の背中を叩いた。
「彼はクロウ。カバル関連の全ての情報の提供者だ」と彼女が言った。「。クロウ、彼はセイント14。彼は… その、色々な仕事をしてるけど、主にオシリスの試練の管理をしている」
今回に限っては、彼はマスクに感謝した。マスクがなければ、その名前に驚いたことに気付かれていただろう。彼はその名前を知っていた、当然だ――ここでは称賛と共にその名が語られ、入り組んだ岸辺ではその名は嫌悪の対象となっていた。彼の腕を掴んでいるこの陽気なタイタンには、そのどちらも当てはまりそうにない。
彼のスパイの本能が再び彼を救った。「そうなのか? それは興味深い」クロウはそう言うと、少し力を込めて同じように彼の手を掴んだ。「試練という名前でしか聞いたことがなかった。オシリスが関係しているとは知らなかった」
セイントは残念そうに笑いながら手を離した。「彼は数多くの重要な任務に関わっている。私は自分のできる範囲で協力している」
「あなたの協力があってこそよ」とホリデイが正した。「彼はあなたに感謝すべきよ」
クロウはセイントを見た。オシリスが他人に感謝する姿は想像したこともなかった。
「協力に感謝は必要ない。我々は見返りを期待せずに、互いを高め合うべきだ。バンシーは例外だがな」と彼は、こちらにウィンクするかのように付け加えた。「彼にはグリマーの貸しがある」
クロウは笑った。もはや警戒心など失われていた。彼はここまでセイントに気を許している自分に驚いた。そして同じように彼に好かれたいと感じていた。ここまで親しみやすい人物とオシリスのような威圧的な人物にどのような共通点があるのだろうか?
彼の思考の外で、ホリデイの話し声が聞こえる。彼は彼女の話に意識を戻した。「…お互い様だってことよ。そう思わない?」
突然、セイントの態度が変わった。「私はそうは思わない。戦場では、戦友がつまづいたら、彼らが立ち直るまで彼らを背負わなければならない。自分が怪我を負ったとしてもだ。そうしなければ前に進むことはできない…」
彼の言葉がクロウの琴線に触れた。セイントとオシリスはかなり古い付き合いなのだろう。こんな風に安心して誰かに自分の背中を任せられるのはどんな気分なのだろうか? 同じ大義のために一緒に戦うのはどんな感覚なのだろうか? 彼はそれを知りたくてしかたなかった。
「話せてよかった、ミス・ホリデイ。お前もな、線が細いクロウ」とセイントは皮肉を言うと、その場を後にした。
クロウは、群衆を軽々とかき分けていく大きな背中のタイタンを見つめた。「お会いできて光栄だ」と彼は弱々しく言ったが、既に声の届かない距離にいた。
ホリデイが笑った。クロウは彼女に視線を向けた。今なら何が起こっているのか説明してくれるだろうか?
彼女は首を振った。「長い話になる」と彼女は言うと、彼の肩に腕を回した。「酒を飲みながらじゃないと話せない。今回はそっちの奢りでいいね?」

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ