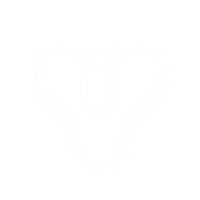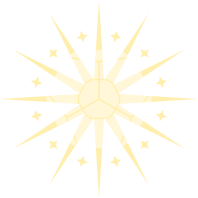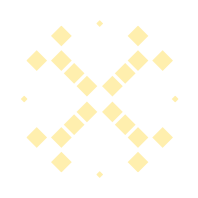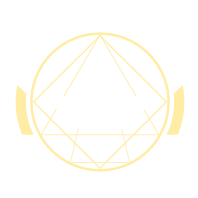鎖の長さ|第1部 
「ジョルヨン、我が友よ」ユルドレン・ソヴが囁く。「お前と私でブラックガーデンを手に入れるぞ」
「うん?」ジョルヨン・ティル、ラキス、クロウの中でも有名なスナイパーであり斥候、そして伝承の語り手である彼は、ユルドレンの傍らにうつぶせの状態で四肢を伸ばしている。年季の入ったスプリマシーライフルを、肩でぐっと固定する。その銃身は彼の背丈の2倍ほどあった。「何、お前と俺でバスタブに土星を浮かべるって?」
「私は本気だ、ジョル」
「口は何でも本気で言えるさ。火星に行くぞ、とかな。へっ...目標まで2,900m。風と角度は?」
「3時の方向から21km/h。南にあと2°だ。何と言われても私は行くぞ。本気だ。お前も来い!この機会を逃せば、一生後悔することになる」
「死んじまったら、何も後悔できないさ!発射準備完了」
「撃て」——スプリマシーの重低音。反動が激しく肩を打つ。命中したかどうか確認するまでもない。「肝心なときにはいつもお前がいてくれた。お前なしで成功はありえない。おまけに...」そう言いながらユルドレンは拳を開いて見せた。電光石火のごとく空中で掴んだ空の薬莢だ。「我々がやらなければ、ガーディアンの誰かがやるまでだ。気づいたときには、マラがそのガーディアンたちをクロウとして雇っているだろうよ」
ジョルはごろんと右を向き、ユルドレンを見つめた。クロウ達の主は勝ち誇った笑みを浮かべる。ジョルヨン・ティル、ラキスは目を細め、片手で弾倉を取り出し無造作に放り投げた。ユルドレンがそれを受け取る。「お前はきょうだいにそっくりだな」ジョルヨンはため息をつく。「だが彼女は汚れ仕事をするときに、満面の笑みを浮かべたりはしない」
「私は一族の美点をみんな受け継いでいるんだよ」ユルドレンはそう言って、ジョルがボルトを空にし、薬室を空にするのをじっと待っている。「今までガーデンに入った者はいない。想像してみろ、いったい何が見つかるか」こうした会話、あるいは口論に勝つのは、普段であればユルドレンだ。けれど時に、ジョルは思いがけない粘りを見せる。
「言葉にできないほど恐ろしいもんだろ」
「誰も名前をつけていなければ、何だって言葉にできないに決まっている。ジョル!前人未踏の地だぞ!心惹かれないのか?」
「惹かれないね。きょうだいはそれを禁じているだろう、ユルドレン」
ユルドレンは明るい口調で答える。「だからこそ、やってみる価値があるのだ」それに、アウォークンの民は、彼の間一髪の新たな生存劇に心躍らせてくれるだろう。英雄の存在が人々にどれだけの影響を与えるのか、マラは本当の意味では理解できていない。女王の座に空白は許されない。けれど英雄は違う。彼自身もう分かっている、何が自分の望みなのか。それは決して、武功などではなかった。
鎖の長さ|第2部 
彼らは秘密裏に出発するつもりだった。「誰も気づかないさ」ユルドレンはジョルに請け合う。「盛り上がりが最高潮の時を見計らって、抜け出す。誰かが嗅ぎ付けたときにはもう、我々はメリディアン・ベイに向かって飛行中だ!」
「自信過剰も大概にしろよ。出発する頃には、お前が何やら企んでるってことはシティ中に知れ渡るだろう」
「心配無用だ」
船に向かう途中、遊歩道やバルコニーからユルドレンのファンや信奉者が群れを成して歓声を送ってくる。彼は手を振り続け、あちこちに顔を向け、笑みを浮かべてみせる。こんなに良い気分を味わう機会は、二度とないかもしれないと思いながら。ひとつだけ心で燻っている黒い感情を挙げるなら、ある事実に対する恐れと確信だ。民衆が自分を愛するのは、ただ女王に最も近い存在であるから。それだけなのだ。民衆は疑問に思わないのか?彼がなぜ女王のに反し続けるのか。なぜいつも、冒険のためにきょうだいのそばを離れるのか。
ユルドレンは、きょうだいに認められたいのだ。彼自身、その気持ちを自覚しているし、受け入れてもいる。しかし彼は、女王の予想を超えた、計画も予見も掌握もできないようなことを成し遂げたうえで認められたいと願っている。つまり、驚嘆の念を交えた感謝が欲しいのだ。
己の鎖の長さを確かめるために、誰かから目一杯離れるなら、その鎖がぴんと張るまで遠ざからなければ意味がない。理に適っているだろうか?きっと適っているだろう...残念ながら。今のところ可能性は2つある。実は彼は自由の身であって、きょうだいの側につくことも、自分なりの選択をすることもできる——もしくは鎖が長すぎて、未だにそれを測れていない。
ゲートにて|第1部 
ユルドレン・ソヴにガーディアンを痛めつける機会を与えたら、「ラスプーチンがトラベラーを撃ったぞ」と叫ぶよりも早く、彼は行動に移すだろう。そのような評価がガーディアンたちに浸透するよう、彼は常に努めてきた。ユルドレンはトラベラーにたかる蠅どもを嫌悪している。奴らは塗絵のような薄っぺらい道徳規範を教わった、幼い下級神。何も知らないただの文鎮。ひとりよがりで、自分の存在を当然とし、分不相応な領域に居座る無神経なものたち。しかも自らの居る体系を理解する必要がない。仕組みを気にせず世界を移動できてしまう能力こそ、彼の最も嫌うところだった。
だから彼はガーディアンに対し、考え付く限りの仕打ちを行ってきた。狙い撃ち、撃墜し、破滅が明らかなクエストへ派遣し、およそ耐えられない悪臭を放つセレノフェノールの中へ奴らのゴーストを浸漬し、固い岩にドリルで穴を開けたちの悪いパトロール・ビーコンを埋め、彼らの強力な武器に細工して、分解してしまうように仕向けた。
しかし銃撃戦になるといつも思うのだ。純粋で狂おしい恐怖を持たずに戦うというのは、どのような感じなのだろうか。
「ジョルヨン!」と彼は鋭く囁いた。坂の下にいるゴブリンが、こちらにもう1発スラップグレネードを放り投げてくる。「ジョルヨン、どこだ?」
返事がない。
グレネードの爆音がユルドレンの耳を突き抜け、オゾンが鼻腔を激しく押し上げる。彼がくしゃみをすると、ゴブリンがくしゃみの方に発砲する。溶けた砂の中のガラス片が遮蔽物に跳ね返り、砕け散ってパリパリと鳴る爆風へ変わる。ユルドレンは上り坂の300m地点にいる。ガーディアン、武装したカバル、恐れ知らずのベックスが、至近距離でかかってくるかもしれない。悲しいかな、人類はまだ遠くでぐずぐずしている。標的をほとんど目視できていない。ベックスのいまいましい点は、奴らのテレポート能力だ。ゴブリン10体に追い詰められているのか、それとも1体しかいないのか、ユルドレンには分からない。
弾丸が傍らを掠めていった。
ゲートにて|第2部 
レディオラリア液が砂に飛び散る。「やっと追いついた」ジョルヨンが息を切らしながら無線で話しかけてくる。「だがこちらも追いつかれたみたいだ」
その発言を立証するように、カバルの迫撃砲が一斉射撃を行った。ライフルの発砲音を手がかりに、賢く弾薬をさばいている。ベックスを相手にするとき、カバルは通常、弾薬を無駄に使わない。相手がテレポートしない種族と知り、玩具を使いたくて仕方ないセンチュリオンがいるようだ。ジョルヨンが通信スイッチを押して無事を知らせる。ユルドレンは安堵し、呼吸を整えた。
息を荒く立ち上がると、ガーデンのゲートがやっと見える。もちろんゲートの位置くらい、誰もが知っている。大変なのは中に入ることだ。
大気がぼやける。真空中の磁束に沿って雲が発生し、視界を遮る。突然の放電が起こると、ベックス・ミノタウロスが立ちはだかっていた。悪態をつくユルドレン。攪乱用のグレネードを投げて走る。
「もっといい方法があるはずなんだ」喘ぎながら言う。「何かないか?」
「お前の嫌がる方法しかない。マッハ20の船でゲートを突破する」
「ゲートは今ロック状態だ!カバルの銃撃をすり抜けられたとしても、ベックスを騙してゲートを開けさせなきゃならん!」
「つまり、ゲートロードを手元の武器だけで殺るしかない...」
「...いや」ユルドレンが息を吐いた。「その必要はない。名案を思い付いた」これがユルドレンの生きがいだ。死の傍らぎりぎりを、その髭を掠めて走り、歯牙鋭い口から飛び退く。「通信を切れ。ステルス状態になるんだ。それから不幸なターゲットを2、3体見繕うぞ...」
ゲート通過 
2人は腹這いになって、芋虫のように火星の砂漠をほふく前進した。光学迷彩のポンチョが、彼らの輪郭を曖昧にしている。徘徊中のカバル・ハーベスターが、地平線の彼方で唸り声をあげた。8時間前からジョルヨンは、カバルの歩兵をライフルで狙撃しては、対射撃の自動作動から逃げ続けている。ユルドレンは、音割れするバトルネットで、さらに強力な武器が起動され集中砲火を浴びせる音を聞いていた。戦闘兵器は今やメラメラと燃え上がり、激しい怒りで膨張している。
ジョルヨンがユルドレンの足首に触れた。指先でコードを叩く——距離は?——
「50m」ユルドレンが囁く。「ベックスにこの場所がバレたとしても、まだ余裕はある」
突如、空気にチクチクしたものが混ざり始める。怪力を込めた亜音速の唸り声が、辺りの砂を巻き上げているのだ。見るからに力自慢の化け物が、彼らの真上で目覚めていた。「前言撤回」呟くユルドレンに、今度はベックスが反応する。
彼はポンチョを脱ぎ捨て、リボルバーとデフレクション・グレネードを握りしめ、鬨の声を上げた。2人の目の前で、縁取りのある傾いた輪が火星の砂漠から突き出している。ブラックガーデンのゲートだ。フォールン・スキフが通れる大きさは十分にあり、溢れるエネルギーによって振動し続けている。
その開口部から、ベックスのゲートロードの影が伸びてきた。金属と精神が衝突融合した自己集合体である巨体。聖地守護のために存在する、ある意味ここで生まれたベックスだ。機械自身が見出した、途方もない目的に殉じるように、身も心も作りかえられたのだから。
「おい、でかいの!」ユルドレンが叫ぶ。「こっちだ!」
ジョルヨン・ティル、ラキスは——落ち着いて——慎重に——空へ向けライフルを発射する。スプリマシーの巨大な弾薬筒による発砲音が、砂丘の向こうまで響き渡る。
ゲートロードが2人をはるか高みから見下ろす。ユルドレンは大声で喚きつつ、その足元に向かって何発かでたらめに撃ち、がなった。「ダンスは好きか?ステップはしっているのか?」
ベックスの実体内部には、ある強力なアルゴリズムが実装されていた。一時的に存在しているに過ぎない場所をモデル化し、潜在的脅威を予測演算し、その場で武器エネルギーを放出するメリットと、後々のために力を温存する有益性とを比較検討するのだ。この時点でユルドレンがまだ生きているのは、ひとえにその演算の結果である。
カバルの戦場周波数に合わせていた骨伝導マイクが、ユルドレンの喉元で起動する。ジョルヨンのライフル音の位置を特定し反応したのだ。ベックスの巨体に向かって声を張り上げ、ジグを踊ってみる。「火星は今から雨ですよ!メリディアンベイは偏西風の季節だ!天気予報、ご覧になっていませんか?」
彼はジョルの手をつかんで引っ張り、共に全力疾走を開始した。ゲートロード、そしてそれが放つかもしれない攻撃に向かって。何がやって来たのか、ベックスの機械には分かるはずだ。しかし——演算。あれは確実にカバルなのか?それとも取るに足らない塵が、ゲートに滑り込んだだけなのか?後者の確率がいくら低くとも、アルゴリズムは比較検討せざるをえない。
ゲートロードが2人を抹消すべく武器を構えたとき...
彼らはゲートの入り口に滑り込んでいた。ユルドレンが親指を折らんばかりの勢いで、デフレクション・グレネードを起動する。時空に位相的な歪みを発生させる眩い球体がユルドレンの周りを包む。彼はジョルヨンをきつく抱き寄せた。2人とも息を落ち着かせる。貫通できないバリアだが、あまり長くはもたない。そして消滅までは、この中の限られた量の空気で呼吸しなければならない。
外では怒り狂ったカバルの艦隊輸送船が、ゲートロードの上に着陸していた。
バリアが解けた時、ゲートロードは死亡しており、ユルドレンとジョルヨンが居たのはもはや火星ではなかった。
ガーデン内部 
ユルドレンとジョルヨンは身を寄せ合い、白いでっぱりの天蓋の下で震えていた。雨が降っている。その雨がどこから来ているのか、ユルドレンにはよく分からない。緑の霧の上の方か?それにしても一向に止まない。彼とジョルヨンは上を向き、雨水を飲んだ。ここは2つの花畑の間にある裂け目の底だ。汚れひとつないガーデンの外観と、熱帯のむっとする悪臭を隔てる場所である。
「ここではあらゆるものが成長するんだな」ジョルヨンがつぶやく。「自分の爪を見てみろよ」
ユルドレンは手を観察する。爪が下向きにぐるりと曲がり、指の後ろに回り込んで根元に醜く巻きついていた——あるいは、そのように不快な幻覚が見えた。ひどい幻想だったが、常軌を逸しているという意味で、つまり赤ん坊が産声をあげるような意味で、すばらしいと思った。ここで起きている新しい秘密が、彼に語りかける。ユルドレンは言う。「汚いところだが、そう評されるのも致し方あるまい。雨は止みそうにない。そろそろ行こうか?」
「おうよ」ジョルヨンはうねる蔦をぐっと握りしめ、身体を持ち上げる。蔦は彼の手首に巻きつこうとしている。文字のような形をした小さな歯が、彼の肌に食い込んだ。それを見つめていたジョルヨンは口を開きかけ、ひとまず腕を引いた。
「大丈夫か?」
「今のところは」ジョルヨンが呟く。「今のところは、な」
彼らは裂け目の道を進んでゆく。緑の霧が頭上に渦巻き、湿った花弁と肥沃な黒い土壌が足首の高さまで堆積している。湾曲した角を持つ、幅広で平べったい昆虫たちが、地面で取っ組み合いをしている。ユルドレンは1匹ひっくり返してみた。昆虫には内臓がなく、下から見るとただの空っぽの甲羅だった。ジョルヨンがシダを引っ張ってみると、その根は金属製の糸と回路基板につながっていた。くねくねと蠢く、濡れたマイクロチップ状のものが、むきだしの大地を徘徊している。
「気に入らない場所だ」ジョルヨンの声が空気を震わせる。「地上に戻ったほうがいい...」
彼の言う地上とは、裂け目を登ったところにある、ガーデン内の地上だ。はるか彼方の丘まで赤い花が広がる、手入れの行き届いた区域。けれどユルドレンが思うに、そこはベックスが多すぎる。ベックスたちはずっとここで、花を育て、土を運び、壁を作り、石と光を利用して太古の建造物を築いていた。この地を管理しようとしていたのだ。
彼は息を吸い込む。「お前の言う通りだよ、ジョル。これは生命だ。ここではあらゆるものが成長する」
この地を滅ぼしてはならない。略奪や破壊を許してはならない。トラベラーの不死の戦士たちは、視野の狭い二者択一を教義としている。そこに適合しない物々は、すべてそのように侮られてきたのだ。どうしようもなく気分が高揚し、彼は泥を撥ね上げた。大笑いしながら走り出す。
背後からジョルヨンの叫び声。「ユルドレン、何を探してるんだ!」
叫び返す。「分からない!だから素晴らしいのだ!わかり得ないということが!」
狩猟中 
1体のカバル兵を追い、前方の花畑を通り抜ける。大量殺戮の現場からまろび出た、最後のリージョナリーだった。負傷し、止血帯から黒い油が滴っている。その跡をたどりながら、ユルドレンは冷たい悪意に満ちた怒りに駆られていた。このガーデンで戦だと?間抜けなカバルの探検なんぞで勃発した争い。下らない、実に忌まわしい...報いを受けて当然だ。ガーデンはありのまま存在させるべきだろう?秘密の果実が自生するように...
地面は傾斜に差し掛かった。赤い花々が、背の低い絡まった草むらへ紛れてゆく。風が囁く...柔らかな語彙、原初の文法だけで構成されたようなセンテンス、音楽的なこの律動。ジョルヨンが小さく呟いた。「脳が侵される...」頭を支配するような声におののく姿は、何かの感染症を恐れているようにも見えた。「もうそろそろ...」と言いかけた彼の声は、ユルドレンがどんどん前進することで掻き消える。ユルドレンは絡み合った下生えを事も無く通り抜け、低い谷を下りてゆき、ベックスを見つけた。ベックスだけではない、何十体ものゴブリン、ミノタウロスがいる。石像のように動かず、苔に覆われ、輪になって並んでいる。ストーンヘンジならぬロボットヘンジか。それらは歌っていた。旋律は儚く、生気に欠け、しかし人間にはない清澄さがこもっていた。この場所がいったい何なのか、ユルドレンは知っている。
カバルのリージョナリーは、石の後ろにしゃがみ込んでいた。ユルドレンがそっと忍び寄る。傷つき、呻くカバルが気づいた時にはもう、彼はナイフをその頭部に当てていた。唇の割れ目、およびその下の柔らかい組織の真上に押し付ける。「動くな」ウルラント語で話しかける。「声も上げるな。最高に研ぎ抜かれた一本だ」
「言われんでも分かる」リージョナリーは現地語で唸った。「おらの目の前にあんだから。ほんとに毛を剃られるかと思ったべ」
「ここがどこか分かるか?」
「おらが行ったことのある中で、1、2を争う最悪な場所...」
「空気の素晴らしさが分からないのか?」ユルドレンは言う。「実に甘美だ。花粉の香り。雷鳴の余韻。お前はなぜここに来た?」
「来たくて来たわけじゃねぇことは確かだ、旦那。おらたちミルクロボットに誘拐されてきたんだ」
低く抑えた発話には、若干ウルラント語の文法が混ざっている。ユルドレンの疑念は確信に変わった。ここは、生存と繁殖をかけて互いに捕食し合う、概念上の戦場なのだ。ベックスが歌い、ガーデンはそれを何かに変換する。この会話さえも大気中に濃い影響を与えているようだ。「あいつらはなぜここにいる?何をしたいんだ?」
「あいつらはここで祈っているんだよ、旦那。自分たちを材料にしてデカい船を造ってる。最低なやつらだよ。生き物を憎んでる」
「どうしてそれが分かる?」
「ああ、種が教えてくれるんだ、旦那」リージョナリーが言う。「見えるかい?」躊躇なくヘルメットを殴りつけ、緊急医療装置を作動させる。密閉シールが破れ、黒いジェルの輪がシューシューと音を立てながら噴き出す。リージョナリーは崩れ落ちた。ヘルメットが彼の幅広な膝の上に転がる。
ジェル層の下で、彼の頭蓋骨全面が、ボコボコとした苺状のテクスチャに変わる。何千もの小さな種が、カバルの肉にうずもれて輝いている。ユルドレンはうっとりと、その皮膚に触れた。
「ユルドレン」ジョルヨンが無線を寄越した。「今お前、最大級にゲスい顔してるぞ」
「この地には秘密があるんだ」王子はつぶやきを返す。骨伝導マイクは冷たく無機質で、どうにも体にしっくりこない。それに比べて密集した「あばた」でぽこぽことした質感を得た、リージョナリーの温かな奇形頭蓋骨...「たくさんの秘密が、彼の中で育ってる。ジョルヨン。ガーデンは彼の中で秘密を育てていたんだ」
「だから何なんだよ?」ジョルヨンはぴしゃりとはねつける。「脱出しようや、王子様。ここの連中に何が起きたか知らないが、同じ目に遭わないうちに!」
ユルドレンは察した。ジョルヨンは神秘を恐れている。未知が彼を怯えさせている。実に賢明。実に合理的。有能な斥候、有能な兵士、そして生存者として正しい反応だ。
しかしユルドレンはどうしても想像してしまう。マラはこの場所を見て、どんなに驚嘆するだろう。もし、ここに連れて来られたら。この地をいっしょに探索できたら。
中枢の後|第1部 
「マラ、君のために花を摘んできた」
女王の従者らが、ユルドレンのために道を空ける。いくつもの驚愕の瞳が、彼の顔と傷、そして手中に収まった鉢植えの花の間を行き来した。何人かの従者は、何やつ、と咄嗟に訝って武器へ手を伸ばし、やっとその人物がユルドレン・ソヴ——女王の限りない寛大さの恩恵を一心に受けるアウォークンの王子であることを思い出すほどだった。
「アスフォデリアという名の花だ」彼はひざまずき、きょうだいに花を差し出した。「ブラックガーデンでしか育たないと言われていたが...それも今日までの話。ここに、我々の領土に植えよう。根を張って繁殖していくはずだ。この花を見れば、誰もが我々の片割れの遺産について思い出せる」
マラの表情が消え、ぞっとするような一瞬が流れた。つと彼女は微笑み、手招きをした。「ああ、おユルドレン。ブラックガーデンに赴かれ、よくぞお帰りくださいました。どうぞ、こちらへ」マラは花弁を1ひら摘み、指先に乗せた。持ち上げて光にかざす。「見事ね。イリン、世話をしてあげて」
それだけ言って花を手渡してしまう。ユルドレンは抗議の言葉を飲み込んだ。マラが自分で植えてくれるのではと期待していたのだ。
その後、2人は水入らずの時を過ごした。彼女は静かで穏やかだった。ユルドレンは覚えている事をすべて話した。「中枢は見た?」マラが優しく尋ねる。
中枢の後|第2部 
「中枢...」ユルドレンはきょうだいの問いを反芻する。ほどなく記憶が混乱してきた。イバラの木立を走り抜けたとき、枝や棘で頬に切り傷ができた。はち切れんばかりの巨大な果実が肩にぶつかり、熟れすぎた果肉をまき散らした。果実は、重く膨張したゴーストのような形をしていた。すぐ外で争う声が聞こえたときは、分厚い蜘蛛の巣の下でジョルヨンと身を寄せ合い、息を潜めていた。それでも心臓の鼓動は...あれは私の心臓だったか?それとも...誰だ、誰の心臓だった?
気がつくとアパートの一室に座り込んでいた。見覚えのある洗濯室だ。白黒のタイルできた床。乾燥機の中でもモノトーンの衣類が踊っている...違う!あれはクロウだ。黒い羽毛が舞っている。嘴がガタガタ鳴っている。大柄なカバルの老婆が、彼の左側にあるたらいの中に腰を下ろした。針金のブラシで背中をこすり始める。腹からアリス・リーの顔が浮き出たベックスゴブリンが、カウンターの後ろで洗剤を売っている。「ユルドレン」声をかけられた。「あんた、穴が空いてるよ」カバルの老婆が、うん、うんと唸った。自分の体を見下ろす。手に黒い真円の穴が空いていた。乾燥機は時間切れとなったが、出てきた「それら」はまだ濡れていた。
「ユルドレン」マラが彼を揺さぶる。彼女は普段誰にも触れないのに。「あなたは中枢を見たの?」
確かに、ガーデンに中枢があるのは極めて自然な摂理のようだ。彼は口を動かした。「ベックスの群れがいた...自分たちの願う物を手に入れようとして。彼らは...そこで、望む姿に成長できるんだ」
「質問に答えていないわ」冷たい口調でマラが言う。全くもって正論だ。そして、ユルドレンが今までに聞いた彼女の発言の中で、最も奇妙だ。
「その場所の中枢が何であれ....」ゆっくりと答える。「種、だと思う。種が残って、そこで成長する。たとえば...グリマーのノードのような。あるいは...」稲妻のごとく考えが閃く。「あるいは、仕掛け。一種の罠だ。探索者を引き寄せ、その者らに理解できないものがあれば、それを滅茶苦茶にする」
ガーディアンをおびき寄せる餌だ。トラベラーを復活させるための、画期的な一歩になりうる。
「行ってはいけないと言ったのに」燃える瞳でマラが言う。彼女は外套をぎゅっと引いた。「あなたは私に身を捧げているのでしょう?」
「きょうだいよ、それはもちろんだ」
「そう言いながら、逆らうじゃない」
ああ、その通りだ。なぜならその2つは同じことだから。君の予想を裏切らない限り、この献身は顧みられない。
突然、底知れぬ孤独感が彼を打った。
ジョルヨン 
武器庫でジョルヨンに会ったとき、ユルドレンはぎくっとして息を呑んだ。自分が彼に対して、まったく信じられないほど配慮に欠けており、恥ずかしくなるほど不作法だったという事実に気づいたのだ。「やあ」と畏まらず呼びかけてみたものの、どう謝罪すればよいのか分からない。ガーデンから帰還して以来、ジョルヨンと話していない。女王にジョルヨンの働きを進言することもなく、彼の勇敢さを称える祝賀会も開いていない。あんなことがあって...その後よく眠れているかと尋ねることすらしていない。彼のことを忘れていたのだ。
「よう」ジョルヨンが、顔を上げずに言う。「昨日は練習場に来てなかったな」
「いやあ、お前に監視役は必要ないだろう」からかうつもりで言ってみるが、白々しく素っ気ない口調に聞こえてしまう。「最近どうだ?私は...」私は...夢を見ている。夢を記録している。起源書庫で血眼になって、裏付けを探している。真実であってほしいと熱望する事柄の裏付けを。アウォークンの未来は、ガーデンの中にある。それを信じさせてくれる事実を探している。地球には光の源がある。どんどん明るくなってゆく、目もくらむようなかがり火が。アウォークンが今のままの姿で生き残ることはないだろう。マラの展望とアウォークンの起源は失われ、シティ生まれの理想主義者たちが主張する、退屈な思想に出し抜かれてしまうだろう。ガーディアンどもは我々が見つけたものを、皆殺してしまうだろう。
もしもガーデンが、トラベラーのアンチテーゼだとしたら?もしもアウォークンがガーデンに、新たな均衡の地、闇と光の中間点を見つけられるとしたら?光が強くなるにつれ、闇は深くなる。
ジョルヨンが何か言っている。「あ...すまない」ユルドレンは、リボルバーをいじりながら低く返した。「何と言ったんだ?」
「あそこで起きた事について、話し合うべきだと言ったんだ」
「...そうだとも!」ユルドレンは漸く気づいた。ジョルヨンがあの場所の重要性を分かってくれないのではと、ずっと恐れを抱いていたのだ。嫌悪と恐怖は自然な反応だろう。しかし、その先の未来を見なければ。「全くその通りだ。記憶が薄れる前に、私たちの見たものをすべて記録しよう。もっと早くこの話をすればよかった——」
「ユルドレン、俺は見たことを誰にも教える気はない」
「そりゃあ...」ジョルヨンの言葉で、彼の心に温かく小さな火が灯った。「もちろんだ。誰にも教えない。私たちだけの秘密ってことだろう?」
「いや、全部忘れたいと思ってる」ジョルヨンは答えた。その手が撃針を取り落とす。床で鈍い鐘のような音が鳴り、それはベンチの下へ転がっていった。彼は拾おうともしない。「秘密を持たない主義でね」
その発言について、ユルドレンはしばらく考えた。根底の本音が吹きつけて、彼の心を凍えさせていく。「そうか...」ジョルヨンは自身の出自や血統をよく理解している。射手としての実力は公的に記録されている。ユルドレンのクロウの一員として、危険な偵察任務に就いてはいたが、諜報員ではない。ユルドレンは...ジョルヨンのことなら何でも知っている。
今度はジョルヨンが、大げさなくらい気楽な口調で聞いた。「明日は練習場に来るか?ひとしきり、一緒に撃とうかと思ったんだが」
「明日はだめだ」ユルドレンは答えた。「やることがある」頭の中では既に想像が始まっている。ガーデンで託宣エンジンを稼働させたら、マラはどう反応するだろうか。他には何があるだろう。彼がおそらく理解でき、彼女がきっと知りたがるようなことは...
崩壊の後 
彼女が消えた。彼は今や終わりのない不安にさいなまれ、未来を憎んでいる。なぜなら未来が怖いから——その空虚さが恐ろしく、彼女のいない孤独な永遠を想像できないからだ。火星の裂け目の端でつまづいた時、このまま落ちて彼女に会いに行こうかと...すべて終わらせてしまおうかと...ごく自然に思った。気温は高く、全身汗だくだ。背中に吊り下げている、古く壊れたクロウ・ドローンの胴体が、肋骨を圧迫し肺を胸骨に押し付ける。息をうまく吸い込めない。
ドローンに船を修理させなければ。もう一度。火星を脱出して、彼女を捜し出さなければ。
クロウ・ドローンの重さが、手と膝にずっしりのしかかる。視線が空を泳ぐ。星々と、輝くヘラルドが、環状平面と嫌な光の壁を通過していく。ドレッドノートにすべてを奪われた瞬間が蘇った。ついに、疑問の余地なく完全に、きょうだいの計画が潰えた瞬間が。すべての音が止まった瞬間、彼は拒絶の叫び声を上げた。それでも——彼の魂が彼女と共に死ぬことを懇願しているにもかかわらず——彼はデフレクション・シールドに手を伸ばし、生き延びた。
ベックスの死体がブロック塀のように積み重なり、陰を落としている。休息を求めて彼は這っていった。
生を選択した彼は、ガーデンのゲートからそう遠くないカンドル島に墜落した。ガーデン。アウォークンが進むもう1つの未来を示した場所。どうしてマラは、決して誘いに乗ろうとしなかったのか。
彼女の声がずっと聞こえている。渇望による幻聴に違いない。しかし彼の脳内に響くあのハミング、あの囁き声、あの星の光の興奮...
クロウのドローンの群れが墜落現場を発見し、戦闘機を修理した。あのとき軌道速度の半分に到達したところで、カバルの銃の的となり、ヘラス盆地に落とされたのだ。修理を繰り返すうちクロウたちは死に、おそらく戦闘機もこれ以上の復旧は望めない。そしてきょうだいは消えた——消えた!彼は彼女に従い、彼の民も彼女に従っていた。彼も民も、女王の意向を信じていたから。彼女にはいつでも計画があった。間違っても、どうでもいいシティのために何千人も死ぬような計画ではない。
帰らなければ。帰らなければ。帰り道を見つけなければ。だが力は残っているのか?人々が愛した英傑にはなれない。アウォークンの目標や、きょうだいの未来計画に対する信頼を回復することはできない。彼はもう信じられないから。
世界はすでに骸と化した。我が物顔で道を行くガーディアンに傷つけられ、カバルの要塞には腐臭が満ち、肉と骨と砕けた装甲が散らばっている。ベックスの胴体が脆くも崩れ、砂塵を巻き上げ散らかした。死の場所。死と戦争の場所。トラベラーという支柱に寄りかかりながら、その支柱たるトラベラーの傀儡によって引き起こされた戦争の場所。
目に何か入っている。まばたきを繰り返し取り除こうとする。その間も必死に彼女の声を聞き、皮膚の下に星の光の棘を感じようともがく。彼女は言ってくれるだろう、彼は正しい道を歩んでいると。自分はまだ生きていると。
けれど何も感じなかった。
キングス 
ようやくケルの前に引きずり出されたとき、すでに彼は何週間も虐げられ、殴打され、強制的に走らされ、畜舎のような環境で、いっそ笑みすら浮かべていた。
ハウス・オブ・キングスの偉大なケルは、明快かつ簡潔に彼を表現した。没落したハウスのユルドレン王子、2人きゅうだいの劣った方、スコラスに敗れた者、ドレッグ以下のバリクスにそそのかされた者、艦隊の無駄遣い、アウォークン貴族最後の生き残り、種族最後の生き残り。
ケルを見上げる。ユルドレンは真相を述べることすら求められなかった。ハウス・オブ・キングスのケルは、彼に名を与えた。そしてケル自身の名もおのずと決まった。没落したハウスの傷ついた支配者、最後のケル。
「お前は私にできないことができる」ケルがユルドレンに告げた。「折れて打ちひしがれた者よ。意地を持たぬお前は、苦渋の命を下すときにも、何も失うことはないだろう。今はフォールンの黄昏の時代——御旗を犠牲にせねばなるまい」
謁見の場で反論のうめき声を上げるユルドレンの前に、彼は膝をついた。「我は汝に投降しよう。なぜなら汝は失脚と不名誉という、およそ耐えられぬ弱さを背負って生きているゆえ。汝、エリクスニーに御旗の破棄を告げませい。我々は互いに折れ、敵対関係を放棄すべきだと。さもなくば生き残ること能わずと。異種族の王子よ、死にゆく民に対してそれができるか?」
できるとも。捜索のための兵士と船と資源は手に入るのだから。いつものユルドレンらしく、すべてを賭けて生き残り、こうして彼らを自分の力で見つけたのだ。
心の中に彼女を感じる。まだそこにいる。かつてないほど、ユルドレンを必要としている。苦しみの穴の中で、彼女の声は鮮やかに響いた。かつて無重力空間の乱闘で、為す術なく叩きのめされている彼のもとへ現れた時のように。彼女はそこで待っている。だから大丈夫、彼女のために行こう。すべてうまくいく。
ファナティック|第1部 
彼女の声が途絶えてあまりに長い時が経った。
太陽系全体が、戦争の傷跡にうめき声をあげている。ユルドレンは、ひっきりなしに続く苦しみと無感覚、エーテルやもっと強い薬物なしでは耐えられない痛みの中で生きている。光が眩しすぎる。このように感じたことはなかった。このように深い痛みなど知らなかった。彼は何世紀もの間、彼女と一体となって生きてきたのに、いざ片側が失われたとき、これほど早く瓦解が訪れるとは。
なぜ語りかけてくれないのか。
リーフが周りで燃えている。粉々になった小惑星と、亀裂の入った居住区から、輝く瓦礫の破片がこぼれ落ちてくる。真空で太陽光に浮かび上がる漂流物ほど、荒涼としながらも美しいものはない。リーフはとてつもなく巨大だが、居住密度も高い。宇宙の広大さに反して、小さな星団に建造物も民も密集していた。ああ、トラウーグのブロークンリージョンはトロイの木馬だと、ペトラに伝えられていたなら。しかし自分の民をトラベラーに売り渡す「摂政」に、くれてやるものなどない。卑屈なペトラは、いつもマラの承認を求めていた。いつも取り入ろうとしていた。だが、マラが何に重きを置いているか、あの女は理解していなかった。マラの信頼を得るために、険しい道を歩もうという心意気がなかった。だからマラは、ペトラに語りかけないのだ。
しかし今や、ユルドレンにも語りかけてこない。
コルベット艦の船体を蹴りつける。ユルドレンとキングスは小惑星帯を急襲し、地球へ向かう船を撃墜して、リーフをさらなる混乱に陥れようとしている。ユルドレンは自らの民を殺した。初めは罪悪感に打ちのめされ、無味乾燥な独房で丸くなって寝ていたものだ。けれどマラも「より大きな善」のために——いまだに正体不明のそんなもののために、何千もの民を死に追いやったではないか。
彼女には常に、民を生け贄に捧げる意志があった。彼女の計画において、アウォークンは担保なのだ。ユルドレン次第で、その計画を再び軌道に乗せられる。
「マラ!」星の光に向かって叫ぶ。すでに懇願の段階は過ぎていた。やれることはやり尽くした。彼女に答えを要求する。「私は怒ってなどいない。君は彼らを救うために自分を犠牲にした...そのことは許そう。だが今すぐ答えてくれ!私は正しい道を歩んでいるのか?君のいる場所に近づいているのか?」
彼はハウス・オブ・キングスの支援を受けていた。彼がリーフを襲撃したことで、ペトラはガーディアンとの共同作戦を中断し、後退して守りを固めた。市民の防衛に集中せざるをえなくなったからだ。これは、マラに少しでも近づけたことになるのか?自分を信じてはみたが、本当にこのようなことをして良かったのか?今後もこれを続けて良いのか?
彼はいつも、マラにとって意外なことをしたかった。その驚きが、計画の再検討につながることを期待して。
一方でマラに少し先の未来が見えていることは、彼にとって大いなる助けとなった。正しい道を進んでいるのだと、確信することができたから。
「マラ!」まばたきをしながら叫ぶ。右目の痛みが治まらない。「きょうだいよ、私を見捨てたのか?」
そのとき、声が届いた。
ファナティック|第2部 
かすかな囁き、ほんの一瞬の安堵、わずかな震え...ユルドレン、私の救世主...
その声に彼はついてゆく。スラスターの炎に晒され、体が傷ついた。傾いだコルベット艦を降り、支配下に置いた小惑星の地を踏む。粉々のサービターとシャンクの残骸が見える。敗北の様相を呈しているのは明らかだった。ガーディアンがフォールンの一団に奇襲攻撃をかけたのだ。
スーツの化学受容器がエーテルの痕跡を検知する。彼はそれを追いかけた。
見つけた。フォールン・アルコンだ。砂埃の中でぐしゃりとつぶれている。射創の入り口と出口からエーテルがシューシューと音を立て、凶暴な太陽光に焼かれている。ゴールデンガンの印である。砂埃の中で点々と続くガーディアンの足跡を見透かし、嫌悪の溜息を漏らす。奴らは連れ立って、この場を急いで去ったに違いない。他の土地を我が物にしようとしているのは明らかだ。そこには採鉱者の一団を乗せた小型船が降り立ってきていたが...
とにかくアルコンの傷を調べる。致命傷だ。ユルドレンの腕の中でガタガタと震えている。何でもいい、何かしてやりたい。哀れな兵士に少しでも穏やかな最期を迎えさせてやりたい。民らが褒めそやしていたきょうだいの力が欲しい、この隣人を救うために。
いや、本当に自分はそれを願っているのか?この哀れな者を救いたいと願っているのか?
そうだ!願っている!
アルコンの傷を縛っている間、目が熱い同情の涙でいっぱいになった。素早く優しい手当てを終えると、すすり泣きが漏れた。このような仕打ちを行ったガーディアンが憎い。涙がアルコンの傷の上に染みを作る。ユルドレンの指の隙間から吹き出すエーテルが、徐々に重く、黒く、毒気を帯びてゆく。彼はそれに気づかない。
やっと彼は、手の甲で目をぐっとこすった。目が痛い、ずっと痛くてたまらない。無印のヘルメットの下で、4つの瞳が生気を取り戻し、驚きに見開かれていた。アルコンがしわがれた声で呼びかけた。ユルドレンに対してではない。死にゆく者が見る幻覚の、欠片のような名残だろうか。死後の世界で会いたいと、願っている相手かもしれない。「父さん...?」
断絶 
彼はやがて気づいた。何をすればよいのか分からないとか、本当に正しいことをしているのかといった疑問は、もはや問題ではない。大切なのは、何をしたいかだ。マラを探して救出したいなら、正しくあろうと必死で望んでいるのなら、彼の意志が善意から来ており十分に強いならば、道は開けるだろう。ただ、自分自身を信じていればよい。身がすくむような自己分析や、苦痛に満ちた後悔はもうやめよう——疑問など持たず、前に進まねばならないのだ。
アウォークンは美しい生き物だ。保護しなければならない。秘密は守られている。
「きょうだいよ...」彼は営舎の壁に問いかける。最近、極端な高揚感と、泥のように眠る時期が交互にやってくる。起床までに1時間かかり、アーマーを着込むのにもう1時間かかることがある。生きることはこれほど難しかっただろうか?次にしたいことがあれば、体は自然とついてきていなかったか?マラが自分を信頼している、その可能性に支えられていた、なけなしの生気が抜けてしまった。それを取り戻す必要がある。
壁が告げる——帰って来て。今こそ戻って、王位に就いて。
彼は飛び上がった。そうだ!ここで茫然と伏しているより、もう一度何かを目指したい。アウォークンの人々に顔を見せたい。彼の帰還を祝うファンファーレの音を聞き、王の座を授かり演説をぶち上げるのだ。マラを救うためならば蛮行も辞さないと人々に知らしめ、恐れと動揺を引き起こしてやろう。アウォークンは実に長く生き残ってきた。だから言おう、「もういい」と。終末が、長い計画の終わりが来ているのだと。
彼はケッチのブリッジへ向かった。「リーフから新しい知らせは?」声を張る。シャンクから通信が入る。
ペトラの声だ。取り替える必要のないものを、あえて取り替えようとするペトラ。「標的ケイドはクレーターにいるわ。私のファイアチームが阻止してるとこ。人手があるならどんどん寄越して」
ガーディアンども。奴らとペトラが協働している。以前のマラは、それを望んでいたか?そうは思えない。ひょっとして遅すぎたのだろうか?アウォークンは...もうアウォークンではないのか?きょうだいの不在のせいで、トラベラーの催眠術にかかってしまったのか?
「ベスタ基地にコース設定」目をこすりながら言い放つ。「小型船を用意しろ。カモフラージュして忍び込む。あの女に引導を渡してやる...」
「何をしている」キングスのキャプテンの声が耳を突いた。「ハウス・オブ・キングスはアウォークンの領土政策に感服しているよ。もしこちら側から介入すれば、ガーディアンを呼び寄せてしまう...?」
知るか。彼女ならきっと服従しない。「そうですね」注意深く、何気ない口調を保ちながら答える。「ガーディアンには要注意ですね」目の痛みが再発し、気づく。自身の中の新たな欲望に。それは激しく熱く燃えていた。
フィクルル 
彼が助けたアルコンは、名をフィクルルという。彼はユルドレンを、父親か神のように崇めている。2人の絆の根底にあるものが何なのか、ユルドレンは今になって理解した。2人とも、衰退した自分の種族の未来を見ているのだ...未来は、過去に縋ることでは手に入らない。フィクルルは、機械に頼り過ぎたフォールンがいかに不自由であるかをユルドレンに語った。彼らは伝統にしがみつくばかり——深淵に飛び込み絶滅を経て、新たに生まれ変わろうとする気概がないのだと。
「私も同じことを感じている」ユルドレンは、鉄の鋳塊から小型ガレー船の小さな模型を削り出しながら言った。「我々は光と闇の瀬戸際に存在しているのだ、フィクルル。だが私の民は、いつだって簡単に道に迷ってしまう」
「あなたはアウォークンにどのような未来を見ているのですか?」フィクルルが問いかける。
どのような未来...?マラを見つけて救った後は...どうでもいい、そう思っていることに気づいた。彼は何世紀もの間、アウォークン社会の周辺地域を偵察し続け、反抗する者を撃退し、スパイ活動をし、卑劣な真似をし、マラのために汚れ仕事を引き受けてきた。とうてい誇れぬ仕事ばかりだ、マラのためになる、という一点を除くなら。
彼自身にも価値などない。
「アウォークンの民は...勝手に死ねばいい」こぼれた声音は、自分でも驚くほど残忍に響いた。逆だ、そんな彼らを私は救いたかったのでは?...いや、違う。マラは目的のためなら、喜んで彼らを破滅に追いやった。アウォークンの存在価値は、彼女の計画の一端を担うこと。それ以外に無い。「もし生き残る民がいるなら...彼らはそれに値するということだろう」
私はアウォークンの滅亡を望んでいるのか?それが真の願いなのか?
「一緒に仕事をしないか」フィクルルに告げる。「ハウス・オブ・キングスは...そうだな、私の計画の邪魔なんだ。だから...」彼はナイフを振る。「取り除こう」
フィクルルはナイフから、すっと視線を上げた。その顔の周りで霧のごとく、ダークエーテルが飛沫を上げた。「時が来たのですね。今こそ彼らに未来を見せましょう」
結合 
「結局は名誉を失うわけか」元キングスのケルが喘ぐ。「ユルドレン・ソヴ、不実なペテン師め。貴様のきょうだいは我々を偉大なる機械から守ってくれたぞ。高貴な血筋の権限をもって、ウルブスと真っ向対峙した。しかしそのお前が...薄汚い闇の中で、こそこそと動き回るなど。ドレッグのように、傷を口実に隠れているのか」
「面白いな、お前がそれを言うか」ユルドレンは嘲笑する。とりあう価値のない相手だからこそ、あえて言葉を交わしてやるのだ。キングスのケルが、とどのつまり求めていたこと。それは過去に戻ることだ。サービターを増やし、機械を増やし、過去の遺物を増やす。今やユルドレンは、滅びが始まりに過ぎないと悟っている。たとい骨だけの身になろうとも、捨て去った肉体にこだわる者よりは生産的だ。
「フィクルル」
粉砕されたサービターとフォールンの死体が、フィクルルの後ろのエーテル凍結した土塁に累々と積まれている。ぞっとするような巨体が2本のショックダガーを携え、静かに前進する。火明りに照らされた格子状の頭飾りが、影と煙の塊に踏み入ってゆく。
「我々は種族最後の生き残りだ」ユルドレンがケルに告げる。「きょうだいは確かに姿をくらませた。お前が考えた偉大なる機械のアイディアも。私とお前の違いは何だと思うか?」前かがみになり、囁く。「マラは、戻ってくる」
バロンのアルコンは、キングスのケルを素早く4回切り刻んだ。ユルドレンは新たなドレッグのベルトにぶらさがっていたハウス・オブ・キングスの紋章を引き裂き、皆に見えるように掲げた。「キングスは死んだ」
「王様万歳」フィクルルの低い声が慇懃に響いた。
ペトラ 
その後、ユルドレンとフィクルルは一時的に別の道をゆく。
フィクルルは血の流れる仕事を請け負った。ハンマーでスパイダーを再形成するように、フォールン社会を再形成し、役に立つ引き出しを増やすのだ。
ユルドレンは単独で、マラの捜索を再開した。昔のことを思い出す。クロウや、「女王の怒り」以外には目もくれない若いコルセアと共に偵察任務に就いたこと...
もしかすると、ペトラも救えるかもしれない。
彼女は盗人の船着き場で見つかった。こんな所で何をしている...落ちぶれたものだ、最低の場所で犯罪者と情報交換をするなど。マラは決して許しはしなかっただろう。
彼は言った。「仲間はほとんど残っていないな」その瞬間、彼女の瞳に慙愧の念が浮かぶ。それを見て、彼女がすでに遠い存在であることに気づく。救いの手は届かない。
その夜、彼はペトラのために涙を流した。その嘆きを聞き、マラが暗闇から現れる。彼は驚いて顔を上げた——マラが見守ってくれている。彼女の意志と知恵とを以て。ならば何を憂うことがあろうか。
解放|第1部 
「認めろ!夢見る都市できょうだいを罠にかけたのはお前か!」
「そのようなことは、しておりません」イリンが言う。「王子。女王は罠にかかったのではなく、お亡くなりになったのです」
今やユルドレンは真実を知っている。物事を正したいという欲求がある。激しく切望するあまり、正しい事のために間違った事をしているかもしれないという発想が全くない。「嘘つきの魔女め」敵意をむき出しにして吐き捨てる。「女王は生きている!」
イリンはしばらくの間、黙って彼を見据えていた。「お越しになることは分かっていました」声には静かな反抗心が込められていた。「ご自分を見失われております。王子」
「私が来ると分かっていながら、探そうともしなかったと?きょうだいはお前の目を抉り出していただろう」
「女王はもう、私どもに何ら望んでおりません。王子...あなたにも」
怒りのあまり、もう少しで彼女を手にかけるところだった。もちろんマラは反対するだろう。彼女は今、彼と共にある。肉体はなくとも確かに実在しており、視界の隅で踊っている。もう少しよ、と彼女は囁く。この場所から解放して、ユルドレン・ソヴ...
「神経が衰弱されているようです」イリンが反発と同情の入り混じった口調で言う。「ご崩御の知らせに触れた時は、私も気が狂いそうになりました。なぜ、そのような...モノと、旅をされているのですか?ご来訪の目的は何ですか?」
率直に答える。「終わらせに来たのだ」冗談に聞こえぬよう、微笑む努力までしてみせた。彼は真実を語っている。「気づいたんだ。きょうだいを驚かせようだなんて、私は馬鹿者だったよ。我々は皆、彼女の計画のなかで存在しているのだから。イリン。彼女の同意があって初めて行動ができる。私は彼女を救いに行くが、それは彼女がそう頼むからだ。死んでほしいと言われたなら、死ぬ。そして、アウォークンのための偉大なる計画が完成したとき、アウォークンも死ぬ。すべてはマラのおかげだったのだから、そのために死ぬのは大いなる名誉だろう。目的を超えて生き続けることは、間違っているのだ。信じてくれ。彼女のいない人生は、どれほどの言葉をかき集めても嘆き足りない...」
そこで息が詰まった。言葉を継げない。視界の隅でマラが、悲哀を湛えた気遣いと、優しい思いやりに満ちた視線を注いでくる。今までずっと、そうしてほしかった。
その日の晩、彼はリーフに投降した。
解放|第2部 
ストライクチーム全体で彼を引き取った。引き渡し地点までユルドレンと看守を迎えに行った狙撃手のうち、1人が物言いたげに目を見開いていた。長いライフルを持ち、背が高く、顔立ちは端正で賢そうな細い目をしている。誰だ...?以前に何か頼み事をしたスナイパーだろうか?何か大切なことを忘れているか?彼はぼんやりと目をこすり、その男を見つめた。眉をしかめてみるが、やはり誰だか分からない。
エルダーズ・プリズンの低階層のうち1つに設置された、目立たない揚陸ドックへ連れて行かれる。監獄ユニットがシューと音を立てて開くと、白い光と霧の中に、目を青く輝かせたエクソと武器を抜いた女の影が現れる。ペトラだ。本物だ。
彼女は黙って立っている。やりたいことは分かっている。ユルドレンを殺したい。「よくやった」と言ってほしい。
「彼女はあなたに語りかけてくる?」ペトラの言葉はぶっきらぼうで、直接的だ。「何と言っているの?」
ユルドレンは目を閉じて、マラの言葉で全身を清める。彼は今、ペトラの勢力のど真ん中にいる。他のすべてが崩壊しても、慎重に維持され続けた監獄の中だ。彼は弱く、拘束されている。それは、きょうだいが決して持ち得なかった強さだ。屈辱に耐え、敗北の中で生き延びる強さ。
「彼女は言っている...」ユルドレンは面を上げ、ペトラと視線をかち合わせる。彼女がひるみ、1歩ずつ慎重に後退しながら、武器の照準を彼に合わせる。エクソが進み出て、黒い袋を彼の頭に被せた。「彼女は言っている...」
「解放せよ、と」

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ