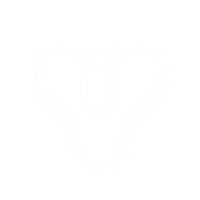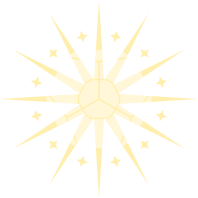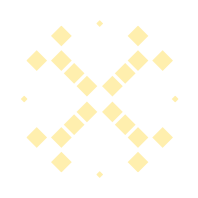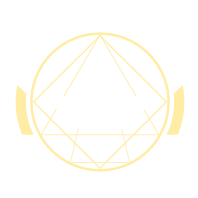▬
彷徨
- 「弾薬は太陽系の世界通貨だ。これからもそうであることをカバルは望んでいる」――カバルの女帝カイアトル
- 「これが最後に耳にする音になるかもしれません」――ペトラ・ベンジ
- 「この休戦協定を結ぶ条件はただ一つ。鉄の豪傑が協定を遵守することだ」――サラディン卿
- 「この声が聞こえたら、ヘルメットを脱いで一番近くにいるコルセアのほうを向きなさい。彼らは何をすべきか知っています」――マラ女王
- 「糸を強く張る必要はありません。その音で合っています」――ペトラ・ベンジ
- 「星々の間の道は、我々の脳内ニューロンと運命の浮き沈みを表すフラクタルの鏡」――アウォークンのテクナ・ウィッチ、スジャリ
- 「好きなように言えばいい。彼に直接伝える勇気があるならな」――エフリディート卿
- あ、あは。あははは。あははははははは。
- 「星々が激しい破壊の声を上げている。星の怒りを操るのです」――アウォークンのテクナ・ウィッチ、イライア
- 「私を信じろ」――オシリスのふりをしたサバスン
- 「しかるべき時が来たら、しっかりと爪痕を残してください」――ペトラ・ベンジ
- 突発的な怒りを兵器化したもの。
「弾薬は太陽系の世界通貨だ。これからもそうであることをカバルは望んでいる」――カバルの女帝カイアトル
女帝カイアトルは夢見る都市のホログラムを眺めて考え込む。地図には爆破位置、着地点、前線基地など、彼女の軍事顧問が緊急招集の末に決めた場所が記されている。あとは女帝が攻撃の指示を下すだけだ。
タウランがデータパッドを抱えて静かに部屋に入ってきた。自分の存在を示すために、軽く足踏みをした。カイアトルは顔を上げない。
そのまま女帝は口を開いた。「皇女として、父に仕える神話伝承者からアウォークンの物語をたくさん聞いた。時を超越した空間の物語や、現実を曲げる龍… 願いだけで建造された街の物語などな」
彼女は鬱陶しそうに牙で空を切る。「破壊するのはあまりにもったいない」
「ですが、戦略的に必要なことかもしれません」タウランが何かの発見を示すように、両膝をかすかに曲げてデータパッドを掲げた。「サラディン卿がバンガードの使いとして我々に接触してきました。私たちの推測が正しいと証明されました。ウィッチ・クイーン、サバスンは夢見る都市にいます」
「捕虜としてか?」カイアトルは顔を上げた。タウランは、支配者の声色に隠しきれない希望を感じ取った気がした。
「はっきりとは分かりません」タウランは曖昧さに歯を鳴らした。「地上の情報収集部隊によると彼女は身動きが取れないようですが、サイオンが言うにはシヴ・アラスから逃れるために彼女は自らの意思でそこまで行ったのだと」
「あえて囚われの身になったのか」カイアトルは渋い顔をした。「ハイヴの策略だな」
「同感です」女帝に合わせて、タウランは眉をひそめた。「ですが、マラ・ソヴは強力な力の持ち主。策略の対処もお手の物です。何らかの計画があると思って間違いないでしょう」
「それはサバスンも変わらない」カイアトルはホログラムディスプレイを切った。部屋に暗闇が広がる。
主の眉にこの決断の重さが現れているとタウランは思った。
突然、その重みが消えた――女帝は決断した。
「サラディン卿に言伝を依頼し、ザヴァラの元へ戻るように伝えろ」
「これが最後に耳にする音になるかもしれません」――ペトラ・ベンジ
アマンダ・ホリデイはエーテルタンクの底に取り付ける新しい液体容器の溶接を終え、満足げに唸った。回廊の方へ後ろ向きに這いずり、彼女の後ろでしゃがんでいた巨大なエリクスニーの脚にぶつかった。
「ミスラックス!」彼女は溶接ヘルメットを外し、叱った。
「アマンダ」ミスラックスが答えた。「いるとは思わなかったが、会えて光栄だ。エーテルタンクを改良しているのか?」
「うん、新しい液体容器を取り付けたの」アマンダは肩をすくめて道具をしまい始めた。「あなたたちにもできることだけど、たまたまここに寄ったからさ」
ミスラックスはしばしボッザ地区を見渡した。「それはどうかな」と、彼は苦笑いを浮かべて言った。
アマンダが笑った。「何言ってんの。貰いものにはケチをつけるなって昔から言うでしょ」
ミスラックスは頭をかしげた。
「気にしないで」と彼女が言った。「それで、皆元気にしてる? あれ以来…」彼女はそこから先を言いよどんだ。
「人間とベックスの攻撃が止んで以来、皆元気に過ごしている」ミスラックスはそう答えながら、しっかりと背を伸ばしてアマンダを立たせた。「果てなき夜が終わったことで資源が豊かになった。皆がお前たちと手を取り合い未来に向かって進んでいる」
「うん、いいことだよね」アマンダは同意した。「数か月前では考えもしなかったことが、今起きている。この間なんか、バザールでゴーストのシェルを選んでいるエリクスニーの集団を見かけたよ!」
ミスラックスの笑い声は低い唸りに似ていた。「ああ、空のシェルはなかなか美しい代物だ。お前のゴーストを紹介してくれるか、アマンダ? ぜひ会ってみたい」
「あら、ごめんなさい」アマンダはクスクス笑った。彼女は2本の指を手首に当てた。「脈はまだある。ゴーストは持ってないの」
ミスラックスはたじろいだ。「お前は光の戦士ではないのか?」
「まったく」彼女は答えた。「普通の人だよ」
ミスラックスはしばし考え込んだ。「光の賜物もなしに、そこまで人々を助けることができるとは…」彼はかぎ爪の手を胸に当てて、一礼する。「我々の仲間はお前から多くを学ぶべきだ」
アマンダは脚の重心を変えてもじもじし、首をかいた。「人に何かを教える立場には向いてないよ」と、静かに返事した。
ミスラックスは微笑んだ。「それはどうかな」
「この休戦協定を結ぶ条件はただ一つ。鉄の豪傑が協定を遵守することだ」――サラディン卿
壁にかかったアナログタイマーが、カチカチと時を刻んでいる。
圧力計が100パーセントに達した時、タイマーが最後にもう一度カチッと鳴り、ハンガーベイのエアロックが開いた。サラディン卿はヘルメットを脇に抱え、中へ入っていく。壁に飾られた青と白のバナーに、カイアトルの帝国、カバルの権勢の記章があしらわれている。
青いアーマーを着た2人組のファランクスが入口でライフルを掲げ、サラディンを迎える。しかし鉄の豪傑は一瞥もくれずに通り過ぎた。ファランクスはゆっくりとライフルを下ろし、ハンガーの反対側からやってくる重装備のバルスのほうを向く。
「1人でここへ?」バルス・オロークが、ヘルメットを脱ごうと手を伸ばしながら声を轟かせる。封止具が外れると同時に、加圧されたシューシューという音が漏れる。「勇敢だな、司令官」
「鉄の豪傑」サラディンは相手との距離を縮めながら訂正する。「私は鉄の豪傑だ」
バルス・オロークは立ち止まり、目を細めてサラディンを見下ろす。「鉄の豪傑サラディン」彼は歯ぎしりしながらその言い慣れない言葉を試す。「勇敢だな」
「ここへ来たのは、お世辞をもらうためでも、式典に出席するためでもない」サラディンは強く言う。もう腕を伸ばせばバルスに届く距離だ。サラディンは物怖じせずに彼を見上げる。「どうやって進めたい?」
バルスはサラディンの目をじっと見てから、大きく鼻を鳴らし、感謝の笑い声を響かせる。「作戦指令室がある」彼はより砕けた口調で言う。もはや自慢も、胸を叩くこともしない。「ハイヴ船の動きを追跡している。火星のアノマリー付近だ」
「夢見る都市で、シヴ・アラスに関する動きがあった。お前も知っておいたほうがいい」サラディンが答える。「案内しろ」
「この声が聞こえたら、ヘルメットを脱いで一番近くにいるコルセアのほうを向きなさい。彼らは何をすべきか知っています」――マラ女王
詐欺師の間で有名な言葉がある。「一番楽しいのは金を手にする前に、球を隠したカップの目印を明かす時だ」
サバスンはその意味を理解していた。クリスタルの牢獄の中で、彼女は自分が放った秘密の目配せや意味ありげな頷きを振り返った。冒したリスクと、自身を楽しませ、彼女のワームに餌をやる限界点について…
さらにその前…
オシリスがおぼつかない足取りでシティを歩く。ローブの下で何かが激しく躍動する。気を静めるために停止し、すぐに歩きだすが、黒い液体がボタボタと無造作に垂れ流している。
さらにその前…
オシリスはクルーシブルの戦いが繰り広げられるのを眺める。どちらのことも応援していない。倒された戦士をゴーストが蘇生している時に、オシリスはじっくり調べるように前かがみになる。セイントの手が彼の前腕に触れると、もう1人の男が何をするのか観察するためにオシリスは石像のように動きを止める。
さらにその前…
クロウとガーディアンが酒を交わすなか、オシリスはキャンプファイヤーの横に座る。魅了されたかのように2人を観察する。クロウは笑っている。彼にボトルを渡されて戸惑ったオシリスの手は痺れたかのように動かない。笑みをこぼしてからゴクゴクと飲み込み、骨の芯まで達した渇きを潤す。
さらにその前…
オシリスはぎこちなく前に進む。地下墓地で上級執行司祭が唸り、その唸り声の中に彼の妹の声が混じる。胸の鼓動が激しくなり、その感覚に飲み込まれるあまりに恐れることを忘れる。
さらにその前…
歪んだ幼虫期の姿のサバスンが、影より這い出て粉々に砕かれたゴーストのほうへ這いずる。そしてボロボロになった男の方へ身を寄せる。
さらにその前…
サバスンはアセンダントエネルギーの石灰化した流れに身を押し込み、ぶら下がるアハンカーラの頭がい骨の中で姿を現す。
網の真下に立っている男が彼女の出現を感じる。彼の光が燃え上がり、あり得ない速度で武器が引き抜かれた。
彼女には一瞬の猶予しかない。ロープの間から顔を下に出し、口を開けて、歌う。
男は動きを止め、ゆっくりと武器を収める。振り返り、腕を組み、何があったのか忘れる。
ぎこちなくも可能な限り頭がい骨の中に溶け込もうと戻るが、その細長い漆黒色の肘は収まりきらない。溝の向こう側にいる獲物の方へ意識を向け、自身をかくまうために優しく歌う。
やがて、下にいる男が彼女と一緒に口ずさみ始めた。
彼女の顔に笑みが浮かぶ。
「糸を強く張る必要はありません。その音で合っています」――ペトラ・ベンジ
這いずる暗闇が顔にひんやりと冷たく触れる。
喋ることも呼吸することもできず、サギラを求めて手を伸ばすが… 手を握っても何も感じず、拘束され、頭の中の映像に亀裂が生じる――
誰かが… アウォークンの王子だろうか? 彼が私を起こしてくれたが… 私はまだ暗闇の中でもがいている。すると私の… 私の声を使って、彼女が彼にお礼を言っているではないか――
彼女は私の姿かたちや声を奪ったが、きっと誰かが私のしくじりに気づき、彼女を追い出してくれるはずだ… そうでないと――
太陽の光… もうどのくらい経ったのだろう? ザヴァラが私――もとい、彼女を見て、彼女の言葉を、毒に覆われた知恵に耳を傾ける。彼に教えなければという一心で私は叫ぶ。ザヴァラ、聞け、聞くんだ、お前は私を知っている! この私を――
夜の花の香り… 私――もとい、彼女が月明かりに照らされた庭園を歩き、そこには話し、笑い、頷くイコラがいる… 見ろ、イコラ、私を見ろ! なぜ分からない――
よく見ろ、よく観察しろ! ちゃんと教えただろう――
エクソの女性が私の前に座っている。その体は揺れ、目は虚ろだ。やがて彼女の真の声が歌を口ずさみ… エクソは心の中でも沈んでいく。その揺れがますます速くなる――
彼の声が聞こえ、意識が表に引っ張られる。セイントだ。ダメだ、ダメだ、ダメだ、そう叫ぶが声が出ない。彼は彼女の目を見つめ、笑顔を見せ、私だが私じゃないそれに手を伸ばす。セイント、それは私じゃない、頼む、気づいてくれ――
泣いているが、泣くことができない。私は無だ。熱、憎しみ、病と恥だけの存在。
「私を信じろ」自分の声がそう言っているのが聞こえ、私は再び溺れる。
「星々の間の道は、我々の脳内ニューロンと運命の浮き沈みを表すフラクタルの鏡」――アウォークンのテクナ・ウィッチ、スジャリ
亜空間の瘴気を貫くフュージョンライフルの特徴的な音で、スジャリはパッと目を覚ました。
テクナ・ウィッチはもう2週間以上崩れかけた壁に寄りかかりながら座っていた。横には灰色の霧が容赦なく流れており、湿った空気が肌に張り付く。宿られた兵の異臭が彼女の鼻をつく。オゾン、銃の潤滑剤、そして魂の炎が燃える不快な甘い焦げの臭い。
今度は近くでフュージョンライフルの音が鳴った。射撃音の後に口を鳴らす不明瞭な音が聞こえ、宿られた兵が応戦して撃ち返した。
戦いを放棄した後、定期的に一帯を警備のために周回する宿られた兵に気づかれないよう、スジャリはなるべく動きを最小限に留めた。だが戦いはどんどん近づき、彼女が隠れている場所から十数メートルほどの所まで来ている。彼女は恐怖心を押し殺し、心を落ち着かせ、自身を見落としてくれることを願った。
彼女は時に数時間、心拍数を下げて瞑想で深いトランス状態に入ることで、詮索する宿られたサイオンの目を逃れてきた。だが、自分の身体に意識を戻すたびに、欲求がどんどん激しくなる。食料でも水でも何でもいい、身体がそれを求めていた。
あれほど訓練したにも関わらず、彼女はくじけそうになっていた。すると、その時――ある優しい、だがはっきりとした囁きが聞こえてきた。「信じるのです、私のテクナ・ウィッチたちよ。あなたたちは迷っていますが、忘れ去られたわけではありません。まもなく助けが来るでしょう」
マラ女王の約束がやっと果たされる時が来たようだ。まだ希望は残されている。
「好きなように言えばいい。彼に直接伝える勇気があるならな」――エフリディート卿
鉄の豪傑サラディン・フォージは、愚弄できる相手ではない。
もし彼を笑いものにした冗談を言ったのなら、それを聞いて彼が笑うことを祈るがいい――彼は決して笑わない。
鉄の豪傑サラディン・フォージは、軽視していい相手ではない。
もし彼を傷つけたのなら、こちらのことを忘れてくれるよう祈るがいい――彼は決して忘れない。
鉄の豪傑サラディン・フォージは、嘘をついていい相手ではない。
もし彼を欺いたのなら、彼が一生気が付かないことを祈るがいい――彼は決して見逃さない。
そして、何らかの不可解な理由で彼の友人や助言役を装い、彼の周囲に噂を流し、その耳に嘘を囁き、汚い偽りを余すことなく彼にぶつけることにしたのなら…
己の虫の神、剣と血の魔術、税と貢ぎ物、そして延々と重ねる交渉によって、脅威から守られることを祈るがいい。
だが鉄の豪傑サラディン・フォージの脅威から逃れられはしない。
あ、あは。あははは。あははははははは。
ザヴァラは机の上にばらまかれた紙をうつろに見つめた。
あらゆる報告が目の前に置かれている。夢見る都市に向かっているオシリスの目撃情報。セイント14とクロウの派遣。イコラからの大量かつ急ぎの調査依頼。
ページをめくっていくと、「オシリス」という名が目にとまった。そして、「サバスン」という名も目についた。
彼は古い報告書に手を伸ばした。ボッザ地区でのベックスの侵入による被害報告の下に埋もれていた、より簡素な内容だ。襲撃時の煙はまだ漂っているが、ずいぶん昔の出来事のように感じる。
果てなき夜についてのラフールの分析を見つけた。ネットワークから漏れ出るベックスのエネルギーがいかにして太陽を遮断し、シティの資源を枯渇させたのかについて触れていた。彼ら特有の周波数の波が市民を疑心暗鬼にし、外からの影響を受けやすくしたと書かれている…
ザヴァラは報告書をくしゃくしゃに丸めたい衝動を抑えた。その代わり、彼は立ち上がり、振り返った先にある高い壁に額を預け、目を閉じた。
オシリスのシティからの追放を取り消し、別館にとどまる許可を下した時を思い出した。サギラの死について彼と話した時のことを思い出した。クロウの処遇をどうするかを彼と相談した時や、カイアトルと会うために彼を助言者として連れていった時のことを思い出した。
どの時でも、太陽が燦々と輝いていたことを思い出した。
「星々が激しい破壊の声を上げている。星の怒りを操るのです」――アウォークンのテクナ・ウィッチ、イライア
夢見る都市の夕暮れが2人の周りを包みはじめる中、ペトラ・ベンジとイライアは中庭で一緒に座っていた。
「訓練を最初に始めたのは私のほうでしたが…」ペトラが説明を始めた。「難しかったです。身体で自然に覚えられるようなものではありませんでした。これのようにはいきませんでした」横に置いてあるグレネードランチャーに向かって彼女は頷いた。
「アイマーのせいで余計に難しくなりました。彼は一番年上の、私が出会った唯一の男性のテクナ・ウィッチでした。真剣に取り合ってくれたことなどない気がします」ペトラは考えるように、話を中断した。「もしかしたらとっくに未来を見て、私が失敗するのを見据えていたのかもしれない」
「姉が訓練を始めるまで、自分にどれだけセンスがないのか気が付きませんでした」ペトラが話を続ける。「すぐにピナールと私で、夢の中で長いこと語り合うようになりました。一晩中話しては、目が覚めてお互いに話したことをはっきり覚えているような日々を送りました。彼女がどれほど力をつけたのか、その時初めて気が付いたんです」
ペトラは視線を下にやった。「当然、ピナールはアイマーに気に入られていました。そして成長するごとに、私たちが共有する夢も鮮明になった。話す以外のことができるようになるまで、そう時間はかかりませんでした」
「彼女は場所や自分の姿形といった具合に、夢を操り始めました。私は彼女についていけなかった。自分の頭の中の助手席にいるような気分で、彼女の夢は私にとっては悪夢のようでした」思い出したくないことを振り切るように、ペトラは首を振った。「訓練を止めて、夢を見なくなったのはその頃です」
「やがて、私は自分の居場所をコルセアに見つけました」ペトラは物思いにふけった。「ですが、テクナ・ウィッチとして訓練を終えておけばよかったと思うこともあります。終えていれば、どこか夢の狭間で漂っているピナールを見つけることができるかもしれない」石畳の間から生えている雑草を抜き、風の中へ散らせた。
重苦しい空気がしばらく流れた後、ペトラは再びイライアに意識を向けた。「だから、私からのアドバイスはとりあえず訓練をやってみること。上手くいったなら、それでよし。ダメなら…」彼女は横にあるグレネードランチャーにポンポンと触れる。「やってもらう仕事は他にもたくさんあります」
「私を信じろ」――オシリスのふりをしたサバスン
天井の灯りが途切れる雑音とともにチカチカと点滅し、蛍光ピンクの光を放つ。壁にかけられた武器の棚に蛾が群がっている。
リード7は部屋にしゃがむように入り、背後の扉をかろうじて閉める。ここはクローゼットよりわずかに大きいほどの空間で、数多の武器が天井までびっしりと収納されていた。彼が通り過ぎた作業台には、オシリスの目の刻印が施された黒と金のプレートのフュージョンライフルが置かれている。
肩を前に丸めながら作業台の席に身を沈める。その体重により席が苦しそうな音を立てた。フュージョンライフルの周りには、友人シャユラの走り書きが目立つ紙が散らばっている。あらゆる物の表面を薄い埃の層が覆っていた。
リードはフュージョンライフルを手に取ってひっくり返した。オシリスの試練における功績を称えて、セイント14がこれをシャユラに贈った時のことを思い出す。その数か月後、シャユラは対戦中に制御を失い、他のガーディアンを殺しかけた。その顛末も、怒りも、苦しみも、全て覚えている。
「シャユラのことは案ずるな」オシリスはリードにそう言った。心の片隅で未だに彼の声がこびりついている。「こういったトラウマのことはよく知っている。彼女のことは任せろ。私が導き手となる」
リードの手がフュージョンライフルをさらにきつく握りしめる。
「彼女に明晰な思考を取り戻すための道を示そう」
彼の手が震える。
「私を信じろ」
「しかるべき時が来たら、しっかりと爪痕を残してください」――ペトラ・ベンジ
作業台でかがみながらロケットランチャーを組み立て直している時、異臭に気づいたペトラ・ベンジは顔を上げた。ガンオイルとゴムの臭いにに混じって、鼻を刺激する臭いが漂っている。まるで思い出したくない記憶のように、どこか馴染みはあるものの不愉快な臭いだった。
臭いをたどって夢見る都市の回廊へと進む。臭いが強くなるにつれ、彼女は足を速めた。
角を曲がると、長らく使われていなかった作業場へ続くドアから煙が漏れ出ていた。再び災いが降りかかる前兆のように感じたペトラは、部屋の中へ飛び込んだ。そこには床であぐらをかき、古い化学調合セットを広げたスジャリがいた。
新顔のテクナ・ウィッチが予期せぬ客人の方を振り向いた。「すみません」と彼女が口を開いた。「うるさかったですか?」
ペトラは咳込みながら顔の前で一生懸命手を振る。ドアが開いたことで、部屋の中の空気が少しずつはけていった。
「冗談ですか?」ペトラは糾弾した。「都市全体が煙まみれになっています。この臭いはなんです?」
「ああ」テクナ・ウィッチが気もそぞろに答える。「忘れていました。ごめんなさい」
ペトラは前かがみになってスジャリの顔をまじまじと見た。新顔のテクナ・ウィッチの瞳は輝いていて瞳孔が開き、目の中でごく小さな星雲が渦巻いているかのようだった。突如、ペトラは臭いの正体に気が付いた。
「クイーンフォイルを醸成しているのですか?」ペトラは笑った。
「はい」スジャリが答えた。「でも… 夢中になってしまって」
「私が来て運が良かったですよ」ペトラは叱った。「吸い込み過ぎると精神が亜空間を彷徨い続けることになります」
「レイラインを探さないと」当初の目的を急に思い出したかのようにスジャリが言う。「マラ女王を見つけなければ」
「ええ」ペトラの顔が急に曇った。「そうですね。クイーンフォイルは名案です。そのまま続けてください」
「でも、今度からは」鼻にシワを寄せながら彼女は叱った。「広場でやってください」
突発的な怒りを兵器化したもの。
ザヴァラはEDZ付近の荒々しい渓谷の近くにスパローから飛び降りた。低地の近くで、カバル・リージョナリーが小さなシャトルに寄りかかっているのが見える。近くに監視態勢のサイオンが立っている。
「お前がザヴァラか?」リージョナリーが呼びかける。
ザヴァラは失礼な対応を気にしないようにした。「ザヴァラ司令官だ」と、彼は返事をした。
リージョナリーは目を細めてゆっくりと頷いた。「確認したくてな」と答えた。「警備上の問題だ」
「さっさと終わらせよう」リージョナリーが太い指でサイオンを差した。「このサイオンがお前に質問をする。お前は答えを言う。その答えを私が女帝カイアトルに伝えて、終わりだ」
「どんな質問だ?」ザヴァラが尋ねる。
リージョナリーは肩をすくめる。「サイオンと女帝カイアトルしか知らない。それが一番安全だからだ」
ザヴァラは警戒しながらサイオンに近づく。単眼で見つめられたザヴァラの耳が鳴る。ピストルに手をかけたその時、鮮明に再現されたある光景が頭をよぎった。
ザヴァラは夢見る都市を見た。カバルの船が空にあふれ、油まみれの煙を吐き出していた。
突如、爆発が起きた――暴力的なほど赤く、惑星の殺人者への怒りを露わにする黒色が混じった爆発の連続。破壊者は少数精鋭で、目の前の任務をこなすのに十分な大きさだ。
彼は夢見る都市にいる者たちがクリスタルの宮殿にうつ伏せで死んでいる姿を見た。マラ・ソヴ、ペトラ・ベンジ、コルセア、無数のアウォークン。そして巻き添えになった多くの者たち。
クレーターの底には、クリスタルに捕らわれたハイヴの神が、最も弱体化した瞬間を狙われ、その身体は粉々に砕かれていた。お決まりの欺瞞を永遠に封じられて。
そして、恐らくだが、規模の小さな戦争が起きた。
後ろには血塗られた2組の手が見える。平和のためなら犠牲をいとわない、2組の手。
「断る」
ザヴァラがサイオンの眼差しから目をそらすと、先ほどの光景が急に消えた。リージョナリーが唸った。「それがお前の答えか?」
ザヴァラは平静を取り戻した。「私は断ると言ったんだ」とハッキリ言った。
リージョナリーは頷いた。「いいだろう」と返事をし、サイオンから半歩下がった。
サイオンは手首に設置された小さなスクリーンにコードを入力した。短い機械音、鈍い弾けるような音が鳴り、サイオンは地面に倒れ込み、頭の傷から血を流した。
ザヴァラは再び武器に手を伸ばしたが、リージョナリーは笑って手を上げた。「志願したものはこうなることを分かった上で引き受けた。これでお前と女帝以外に質問を知るものはいない。それが一番安全だからな」
「さて、答えを伝えに行かないとな」カバルはシャトルに乗り込みながらそう言った。「お前の判断が間違っていないことを祈る!」
船は空へ飛び立ち、ジェットの風圧によってザヴァラのブーツをサイオンの血が汚した。