戦術人形>〔 銃種別一覧 | 図鑑順一覧 | 所属別一覧 | スキル&陣形効果一覧 〕
基本情報
| No.110 |
|---|
 |
| No.110 |
|---|
 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 名前 | FG42 |
| ランク | ★2 |
| 銃種 | マシンガン |
| 製造時間 | 04:50:00 |
| 所属 | |
| CV | 伊藤あすか |
| イラスト | 叽困 |
| SD | |
 | |
| Lv.MAX時ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 87 | 8 | ||
| 28 | 4 | ||
| 33 | 745 | ||
| 121 | 8 | ||
| 1000 | 5% | ||
| 0 | 150% | ||
| ステータスランク | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
| 自己紹介 |
|---|
| ラインメタルFG42が着任しました。指揮官の下でもっと鍛えてもらいたいです。 |
| キャラタグ |
|---|
| Tag: ステータス強化 |
|
タグ説明を閉じる
|
スキル
| アイコン | スキル名 | 効果(Lv.10) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
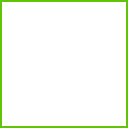 | 狩猟衝動 | 6秒間、自身の命中を60%上昇させ、攻撃が必ず会心になる | ||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 開幕CT | 3s | |||||||||
| CT | 18s | |||||||||
| 命中 | +22% | +26% | +30% | +35% | +39% | +43% | +47% | +52% | +56% | +60% |
| 持続時間 | 1.0s | 1.6s | 2.1s | 2.7s | 3.2s | 3.8s | 4.3s | 4.9s | 5.4s | 6s |
専用装備
| 画像 | 名前 | ZFG42 |
|---|---|---|
 | 種類 | アクセサリー |
| 能力最大値 | 命中+32 射速-1 会心率+30% | |
| 入手方法 | ブラックマーケット | |
| 説明 | ||
| ZF社がFG42のために生産したオプティカルサイト。百年の時を経て、黄銅の鏡筒はすでに光を失ったが、ガラスのレンズは未だに科学の国らしさを残してある。このスコープから覗く世界は、まさにマグナムの世界なのであろう。 | ||
セリフ
| 入手 | ラインメタルFG42が着任しました。指揮官の下でもっと鍛えてもらいたいです。 |
|---|---|
| 挨拶 | 指揮官、また遅刻です。残業2時間追加ね。 |
| 部隊編入 | 私がこのチームに入った以上、風紀を乱す真似は許しませんよ。 |
| 強化完了 | 武器の強化も良いですが、もっと実戦的経験が欲しいです。 |
| コミュニケーション1 | 指揮官、皆さん頑張って練習しています。ご安心ください。 |
| コミュニケーション2 | 気を緩めないで。まもなく作戦会議が始まります。 |
| コミュニケーション3 | 指揮官、軍紀を守ってください。これは許容範囲外です! |
| 出撃 | 行動開始です。足元に注意しなさい。 |
| 敵と遭遇 | 敵と遭遇しました。 |
| 重傷 | くっ!みんなとはぐれたか!?不覚です… |
| 勝利 | 勝利を収めたのもみんなのおかげよ。感謝します。 |
| 撤退 | こんな結果になるなんて…申し訳…ないです… |
| スキル1 | ふっ、チャンスだ。 |
| スキル2 | もっと恐怖を味わいなさい。 |
| スキル3 | !?…もう一遍、失敗作と言ってみなさい! |
| 後方支援開始 | 必ず、任務を完遂します。 |
| 後方支援完了 | 戻りました。完璧な結果です。 |
| 修復 | 戦場での経験が、まだ足りないです…訓練をもっと頑張らねば…! |
| 編制拡大 | ご安心ください。ダミーが増えても、訓練を怠るつもりはありません。 |
| 自律作戦 | 久しぶりに、本気を出す! |
| 誓約 | 指揮官が私を選んでくれたのですから、私はもう迷いません!あなたと共に戦います!あ、ありがとうございます…指揮官。 |
| コミュニケーション4 | 指揮官、今日のお菓子はどうだったでしょうか?……ですよね!手順にとらわれ過ぎていたら、サプライズは起きませんから! |
| ローディング | 指揮官、待機命令はまだ解かれていませんよ。 |
| 人形製造完了 | 私が、新隊員に軍紀を教えます。 |
| 口癖 | 直ちに実行します! |
性能
総評
実力はあるが不遇な優等生
- レベル上げの聖地、4-3eで大量に手に入る★2MG。
- 低レアながら平均以上の命中を持ち、やや低めの攻撃力はスキルの狩猟衝動でカバーしている。
しかし同レアで同じスキルを持ちながらキャリア任務ステージクリア報酬で入手可能でメンタルアップグレードも可能なLWMMGと比べると火力で大きく劣り、装弾数も8と致命的に少ない。
あえてLWMMGよりこちらを優先する理由はあまりないが、スキル自体は優秀なので他に優秀なMGが手に入らない場合は十分育成候補に入る。
スキル
- 詳しくはこちらを参照のこと。
- 効果時間中、攻撃が必ず会心(1.5倍)になる強力なスキル。
命中補正もマシンガンにとってはありがたく、大幅な火力アップが見込める。 - なお、装弾数が8と少ないため、スキル使用をオートにしていた場合、発動から1秒も経たない内にリロードに入ってしまうため、アサルトパックを装備して射撃時間を延ばす必要がある。
陣形効果/編成
- 左右の斜め前に命中30%を付与する。多くのSGにとって命中は火力より重要なので悪くはない。
- 火力が低めなので火力上昇の陣形や火力号令スキルを持つSGやHGと組むのが望ましい。
おすすめ装備
- 狙撃弾 or 特殊徹甲弾/オプティカルサイト or 予備サイト or ZFG42/アサルトパック
- 比較的火力が低めで序盤の運用が多いことを考えると狙撃弾が望ましいが、入手性を考えれば特殊徹甲弾のほうが現実的。
- ブラックマーケットで入手できるZFG42はアクセサリー枠で「命中+32 会心率+30% 射速-1」という★5ドットサイトの完全上位互換。
狩猟衝動持ちであってもオプティカルサイトや予備サイトのほうがDPSは上だが、
専用装備は入手や強化コストに見合うほどの差ではないので優先度は高くない。
キャラについて、小ネタ
- 設定画集掲載のキャラクター紹介
積極的だがシビアな性格、情け容赦なく、またお節介でもある。
人にも自分にもかなり高い要求を課す。
いったんルールを決めると、どんなに軽微でも違反者を許さない。
これも強い責任感から来るものだろう。
元ネタ
| 正式名称 | Rheinmetall Fallschirmjägergewehr 42 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 自動小銃 | 開発国 | ドイツ |
| 製造メーカー | Krieghoff GmbH | 生産対象 | 軍 |
| 生産期間 | 1942ー1945 | 採用国家 | ドイツ |
| 口径 | 7.92mm | 弾薬 | 7.92×57mmマウザー弾 |
| 装弾数 | 10/20(箱型弾倉) | 発射速度 | 900発/分(Ⅰ)600発/分(Ⅱ) |
| 初速 | 761m/秒 | 有効射程 | 550m |
| 全長 | 937mm(Ⅰ)1060mm(Ⅱ) | 重量 | 4500g(Ⅰ)4900g(Ⅱ) |
簡単な説明
- 第二次世界大戦中にドイツ空軍の空挺部隊であるFallschirmjäger(降下猟兵)*1向けにラインメタル社で設計・開発された自動小銃。
- 1941年5月、ドイツ軍はクレタ島へ大規模な空挺作戦を行ったが、この攻撃を行ったドイツ空軍の降下猟兵部隊である第7航空師団は占領に成功したものの、参加した約14000人の内、6600人程度が戦死、13000人程度が負傷する大損害を受けたのである。この損害の要因のひとつに降下時に携行できる武器の問題があった。
- 当時降下猟兵隊は陸軍と同じ装備を使用していたが、戦闘で主力となる小銃や機関銃などはコンテナに入れて投下し、降下後に回収するという方法をとっていた。それまでの間拳銃と手榴弾という非力な武装しか携行しておらず、クレタ島の戦いでは気流に流されてコンテナの落着位置が降下ポイントとずれ、武装を回収することが出来ずに壊滅する部隊が続出した。一部の隊員はC96に最大20発装弾が可能で木製のホルスターを連結してフルオート射撃が可能なマウザーM712やハーネルMP28を装備していたが、やはり拳銃弾では射程が短く焼け石に水であった。
- これを受けてドイツ空軍のヘルマン・ゲーリング国家元帥は「小銃・短機関銃・機関銃の役割を一丁で果たし、降下時に携行でき、更に当時最新鋭だったGew41やボルトアクションのKar98kと同等の命中精度を持つ自動小銃」を開発するよう命令した。開発中にさらに7.92×57mmマウザー弾使用の強制*2、光学照準器の標準搭載*3、さらにライフルグレネード発射機能と銃剣を装着可能で白兵戦にも耐えられる強度、そして1m以下の長さで従来の機関銃や小銃よりも軽い物をという無茶ぶりで、最終的にライフルグレネード発射機能は削除されたが、ワルサー社やマウザー社はじめどの小火器メーカーも匙を投げたほどの無理難題であった。
- 結局このトライアルに応じたのはラインメタル社とクリコフ社の2社だけでどちらも空軍と縁が深く機関銃や大砲などの重火器を手掛けてきたメーカーであった。
トライアルにおいて最有力とされたのはラインメタル社のルイス・シュタンゲ技師((機構が似ているといわれるルイス軽機関銃のアイザック・ルイスとは全くの別人である。またこちらの設計技師はサミュエル・マクリーン))が手掛けた設計案である。 - 動作機構ははロングストロークピストン・ロータリーボルトでセミオート時はクローズドボルト・フルオートではオープンボルトとなる非常に凝った機構を持ち、狙撃時の命中精度と連射時の連射速度、安全性を両立している。また銃身と完全に同一軸の直銃床とその端まで貫通するバッファーチューブを持ち、連射時にも銃身がぶれない構造を採用した。
銃床内部も機関部に取り込んだことによって全長はわずか937mm、重量も4200gとStG44より軽量であった。この後フランスのMAS36銃剣を参考にした*4スパイク型銃剣、光学照準器のマウントが追加されても4500gにとどまった。設計図にはライフルグレネード用の取り付け溝やレギュレーターなども描かれたものの、強度や重量の面で断念されている。またバイポッドも重心に近く設置型に匹敵する回転機構まで備えたものがデザインされた。フロントサイトも光学照準器の使用時やパラシュートの紐などに絡まらないように折り畳み式とし、Kar98に慣れた兵に合わせてピストルグリップの角度をライフルグリップに近いものにするなど細部まで兵士のことを考えたきめ細かな配慮がなされていた。 - しかしその複雑な加工を要求する設計に実際の製造技術や資材が全く追い付かず規格外の不良部品が続出し、またラインメタル社が小銃に不慣れで適切な工場を持たず量産を担当することになったクリンクホフ社の試作モデルも故障が多発し、機関部をスウェーデン鋼のフライス盤削り出しとすることでようやく試射に耐えるモデルが完成した。ゲーリングは感激し即座にFG42の正式名を与えて12万丁の生産を命じたが、すでに敗勢の濃いドイツにこんな手間のかかる銃の量産能力があるはずもなかった。結局1942年12月までにとりあえず5000丁とされたが、実際に生産できたのは明くる1943年1月に200丁がやっとであった。
- FG42の初陣は1943年、失脚したムッソリーニの救出作戦(グラン・サッソ襲撃)と言われているが、降下猟兵部隊指揮官のハラルト・モルスとオットー・スコルツェニー率いる精鋭の武装親衛隊の鮮やかな手腕でムッソリーニを救出しているものの、本銃は一度も発砲されなかった。
- ともあれ降下猟兵部隊に配備され、他の作戦にも投入された結果いくつかの欠点が指摘された。
フルサイズライフル弾を使用するため反動が大きく、固定されていないバイポッドが反動で折り畳まれてしまったり発射炎が大きく射撃の邪魔になる、左側面に弾倉右側面に排莢口がありバランスが悪いといったもので、いずれも小型軽量化の代償であった。特に弾倉は機関部*5の配置と光学照準器の関係で改良のしようがなく、横にいる弾薬手が装填しやすいという意図もあった。また1944年頃には大規模な降下作戦は行われなくなったため通常の歩兵部隊用として再設計が行われ、連射速度を2/3にし機関部の肉厚増加などによる強度の向上と質量増加*6による反動軽減、各部の材質変更が行われた。またマズル先端のフラッシュハイダーを大型にし、バイポッドをそのすぐ後ろに半固定式とした。ピストルグリップは近代的なMPやStGに合わせたほぼ垂直なものとし、材質も樹脂製となっている。小型軽量化にこだわる必要もなくなったため、ハンドガードやストックも大型なものとなった。それでも重量は4900gにとどまり、戦後のアサルトライフルと比較しても遜色のないものとなっている。 - 戦後、便宜上再設計前を(I)、再設計後を(II)と分類し、最終的な生産量はI型が2000丁、II型が5~6000丁と推定されている。ちなみに試作モデルはAからDまであり、ゲーリングに提出されたものがC型でI型の量産モデルがE型である。再設計後のII型も試作型のF型と量産型のG型があり、A~C型とF型はラインメタル内製、G型はクリコフに加えて占領下のフランスで自動車エンジンなどを製造していたロレーヌ・デートリッヒの工場でも製造された。
鹵獲したアメリカの技術者は本銃を高く評価し、MG42とあわせてのちのM60の基礎となった他、イギリスのEM-1にも強い影響を与えている*7。
- 1941年5月、ドイツ軍はクレタ島へ大規模な空挺作戦を行ったが、この攻撃を行ったドイツ空軍の降下猟兵部隊である第7航空師団は占領に成功したものの、参加した約14000人の内、6600人程度が戦死、13000人程度が負傷する大損害を受けたのである。この損害の要因のひとつに降下時に携行できる武器の問題があった。
コメント
- それまで冷静だったのに『もう一片、失敗作と言ってご覧なさい』ってガチ切れするのが草。トラウマなのかな(震え声) -- 2020-02-21 (金) 08:27:47
- この子は性能的に一線は引いたけど、基地で訓練教官としてバリバリ働いてて副官としても優秀な雰囲気が漂ってる -- 2020-03-23 (月) 22:06:27
- ドルフロとは全く関係ないんだけどさ…今日高校時代に戻って教室にいる夢を見たんだが、何故か机の上にFG42がバイポッドを展開した状態で置いてあったんだ…撃たずに夢から覚めたけど結局どういう夢だったんだろう…? -- 2020-06-12 (金) 18:43:21
- マジ全く関係なくて草。まあ、自動小銃でもぶっ放してストレス発散したい願望とか? その机が自分のか他人のかで意味は変わりそうだが、 -- 2020-06-12 (金) 19:18:17
- 夢占いだと教室は普段の環境を表していて、銃を見ている夢は誰かに対する敵対心或いは性的欲求の高まりを表しているそう -- 2020-06-12 (金) 19:43:23
- 教室と銃にそんな意味があったのか…全く関係ないのに調べてくれた人、ありがとう -- 枝主? 2020-06-12 (金) 20:21:09
- …いやまってこれフロイト先生構文 -- 2020-08-04 (火) 00:32:34
- 実はこの子、よく見たらハイレグなんだよなぁ… -- 2020-11-25 (水) 07:34:13
- MGでは一番デザインが好きなんだけどmod来ないかなあ -- 2020-11-28 (土) 23:57:21
- ヤンデレFG42さんに性活管理されたい -- 2020-12-29 (火) 11:03:35
- なるほど…良いな -- 2020-12-29 (火) 12:21:52
- FG42さん真面目だから指揮官が他の人形と楽しそうにしてても限界まで我慢してそうだし、指揮官が他の人形とスキンシップしてるのを見た後は「指揮官、私以外見てほしくないです…」って押し倒してくるんだ俺は詳しいんだ -- 2020-12-29 (火) 12:41:39
- 本気を出す、と言われるとゾクッとする -- 2021-07-30 (金) 01:16:30
- 1320万円の女と化したFG42ちゃん ※前期型の無可動実銃(しかも状態がかなり良い)が1320万円で入荷したから -- 2022-01-06 (木) 01:32:25
- ドイツもこいつもシュタイヤーシュタイヤー!なんで私を認めねぇ!! -- 2022-09-29 (木) 03:02:10
- フィクションでの活躍はヘルシングの吸血鬼大隊の皆さんが印象深いのではないか。 ヨーロッパ!ヨーロッパの灯だ!少佐殿!代行殿! -- 2023-06-10 (土) 02:26:33
- そうか、連中装備更新なんてできんからWW2の装備そのまま使ってるんか… -- 2023-06-12 (月) 17:10:54
製造・ドロップ報告用コメント
【過去ログ】
- 久々に沼った、資源が吹っ飛んだけど何とか新人形ゲット -- 2025-11-21 (金) 20:10:46
- 同じく沼った。IA2が出るまでにXCRの編成拡大が終わるほどに -- 2025-11-21 (金) 22:26:29
- 全てコンプしたけど、RFとARの闇鍋は胃が痛かった -- 2025-11-24 (月) 20:59:05
- 製造履歴見た感じ心なしかいつもよりPUの製造数が少ない感じがした -- 2025-11-24 (月) 23:15:05
- 今回も全コンプ。IA2が難産だったけど弾薬が7万減るくらいで出てくれた。新人形5人中3人が星4だったから気分的に楽だった -- 2025-11-26 (水) 08:47:19
- 各種資源ほぼMAXあるし余裕か~~~と思ってたら配給7万あたりまで減った時はオワッタかと思った。。。無事全員コンプです。。。 -- 2025-11-27 (木) 12:34:49
- イディーカムニェー… -- 2025-11-27 (木) 20:16:19
- 400位回して来ない…他の☆5の子達はぼちぼち来るのにscar-hだけ来ない… -- 2026-01-01 (木) 06:39:11
- ドルフロ無印ってまだ人いるのか…ストーリー読み返したいから再プレイしたいけど、工程が多すぎる -- 2026-01-06 (火) 12:41:13
- 板違いだけど新しくなったキャリア任務に沿ってやろうとだけ -- 2026-01-06 (火) 13:01:27
- でねぇ…でねぇよぉ…。大型製造(20枚)を数十回やったけどでねぇよぉ… -- 2026-01-20 (火) 18:46:09
- HK CAWSが出ないという話です(ただ単に萎えてるだけです) -- 2026-01-20 (火) 18:47:02
