参考:( 用語集 | 七国まとめ | キャラ・一族・団体 | 年表 | 神の目 | 言語 | ヒルチャール語 | 料理元ネタ考察 | 崩壊ネタ関連 | メインストーリー要約 | 中国語・英語まとめ | 誤訳 | 暗号解読 | 命ノ星座 | 考察総合 )
※食材-料理の早見、購入場所、バフ効果、効果性能比較は「料理」へ。料理の説明文を読みたい方は「食べ物」へ。
ゲーム中に登場する料理の元ネタと思われるもの。あまりにも自明なものについては省略。情報求む。
モンド料理 
モンド料理は元ネタとなった地域からドイツ料理を元ネタにした料理が比較的多いが、オランダやフランスなどドイツ近辺の国の料理もある。
| 画像 | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
 | 荒波パイ | エウルアのオリジナル料理。ターンオーバー という、パン生地やパイ生地などに具材を乗せ、折り畳んで三角形や三日月型にして調理する種類の食べ物だと思われる。具体的にどのターンオーバーかは不明だが、ドイツ語版ではイタリアのターンオーバーであるカルツォーネ という、パン生地やパイ生地などに具材を乗せ、折り畳んで三角形や三日月型にして調理する種類の食べ物だと思われる。具体的にどのターンオーバーかは不明だが、ドイツ語版ではイタリアのターンオーバーであるカルツォーネ 、スペイン語版ではガリシア発祥のターンオーバーであるエンパナーダ 、スペイン語版ではガリシア発祥のターンオーバーであるエンパナーダ と訳されている。カルツォーネは基本的にはピザ生地なので、どちらかといえばエンパナーダの方が相応しそうか。 と訳されている。カルツォーネは基本的にはピザ生地なので、どちらかといえばエンパナーダの方が相応しそうか。 |
 | エビのポテトカナッペ | カナッペ はフランスの食文化。ただし中国語版も英語版もカナッペという言葉は使用していないため、日本語版の訳者が説明文から意訳したものか。 はフランスの食文化。ただし中国語版も英語版もカナッペという言葉は使用していないため、日本語版の訳者が説明文から意訳したものか。 |
 | お肉と野菜のシチュー | 英語版によればグヤーシュ 。ハンガリー起原のスープ料理で、他の中央ヨーロッパ諸国やドイツなどでも食される。 。ハンガリー起原のスープ料理で、他の中央ヨーロッパ諸国やドイツなどでも食される。 |
 | 大根入り野菜スープ | 中国では蘿蔔湯(大根スープ)がよく食べられるのでそれだろうか。 |
 | テイワット風目玉焼き | 目玉焼きは国によっては両面焼きの方が人気の所もあるが、モンドの主なモデルと思われるドイツでは日本と同じく片面焼きが主流である。そもそもドイツ語では目玉焼きのことをシュピーゲルアイすなわち「鏡の卵」といい、片面焼きであることを前提とした上で、黄身のつややかさを称える名称となっている。 |
 | 鳥肉のスイートフラワー漬け焼き | 旅人なら誰もが知るモンド城門前ハト製の漬け焼き…冗談ではなく、図鑑の「白鳩」によれば鳩肉を使用するのが実際にモンドでの伝統である。(鳩肉ではないが)蜂蜜漬けのローストチキン は古代ローマの料理書『アピキウス』にも記される古い欧州料理であり、近年では『ゲーム・オブ・スローンズ』に登場したことで話題になったようだ。 は古代ローマの料理書『アピキウス』にも記される古い欧州料理であり、近年では『ゲーム・オブ・スローンズ』に登場したことで話題になったようだ。 |
 | 風神ヒュッツポット | ヒュッツポットはオランダの家庭料理で、野菜のつぶし煮。ちなみに中国語版では国を指定せず「杂烩菜」(ごった煮)だが、特に「荷兰杂烩菜」(オランダごった煮)=ヒュッツポットを指すこともある。一方、英語版ではフランス料理であるラタトゥイユ となっている。外観や文中の記述から、フランスやフランドル地方の煮込み料理であるオシュポ(Hochepot となっている。外観や文中の記述から、フランスやフランドル地方の煮込み料理であるオシュポ(Hochepot )とする説もある(余談だが全く別の料理にもかかわらず、フランスではヒュッツポットもオシュポといい、オランダではオシュポもヒュッツポットという)。 )とする説もある(余談だが全く別の料理にもかかわらず、フランスではヒュッツポットもオシュポといい、オランダではオシュポもヒュッツポットという)。 |
 | ホワイトソースポトフ | ポトフ はフランスの牛肉料理。ちなみに英語版では日本発祥の洋食であるクリームシチューとなっている。中国語版では「白汁时蔬烩肉」(季節の野菜と煮込んだお肉のホワイトソースがけ)。 はフランスの牛肉料理。ちなみに英語版では日本発祥の洋食であるクリームシチューとなっている。中国語版では「白汁时蔬烩肉」(季節の野菜と煮込んだお肉のホワイトソースがけ)。 |
 | 魚香トースト | クレーのオリジナル料理。魚香 (ユーシャン)とは中国の調味料・ソースの一種。ただしこのトーストはモンド料理であるため、ここでいうユーシャンは、公式レシピ (ユーシャン)とは中国の調味料・ソースの一種。ただしこのトーストはモンド料理であるため、ここでいうユーシャンは、公式レシピ でも使われているイタリア発祥(諸説有り)のトマトソースであるマリナーラソース でも使われているイタリア発祥(諸説有り)のトマトソースであるマリナーラソース (マリナーラはイタリア語で「船乗りの」という意味)のことを指していると思われる。余談だが、ゲーム中の料理も魚香(ユーシャン)も本来のマリナーラも、名前に反して魚介類は使用しない(ただし現在のイタリアではマリナーラにアンチョビを入れることが多い)。 (マリナーラはイタリア語で「船乗りの」という意味)のことを指していると思われる。余談だが、ゲーム中の料理も魚香(ユーシャン)も本来のマリナーラも、名前に反して魚介類は使用しない(ただし現在のイタリアではマリナーラにアンチョビを入れることが多い)。 |
 | 冷製肉盛り合わせ | 冷たいまま食べられる調理済み肉(ハムやローストビーフなど)を皿に盛る料理。コールドカットとも。欧米圏では珍しくない料理だが、モンドの主なモデルとされるドイツではアウフシュニットと呼ばれ、ヴルスト(ソーセージ)の質と多彩さで他国を遥かに圧倒する。 |
 | ムーンパイ | イングランド料理のビーフ・ウェリントン か。フランスの地方料理であるピティヴィエとする説もある。 か。フランスの地方料理であるピティヴィエとする説もある。 |
璃月料理 
璃月料理は元ネタとなった地域から中華料理を元ネタにした料理が多いが、日本人にとって馴染み深いものや逆に中国本国でしかわからない料理など多岐にわたる。
| 画像 | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
 | 揚げ魚の甘酢あんかけ | 中国語版ではそのまま蘇州の名物料理である「松鼠魚」(ソンシューユー)。中国東部に広く分布する淡水魚のケツギョ(桂魚)を用いることから松鼠桂魚とも言う。揚げて広がった切れ込み部分が松ぼっくりのように見えることから、松鼠(リス)が好きそうな魚という意味の名がつけられている。 |
 | 腌篤鮮 | そのまま腌篤鮮(イェンドゥシェン)。江南料理、特に上海の春節に食べられる料理。日本語にするなら「塩漬け肉(腌)と新鮮生肉(鮮)のじっくり煮込みスープ(篤)」だが、春の味覚である筍も肉と同じくらい重要な食材である。中国では冬になると、豚バラの塩漬け(地域によっては更に花椒などの香辛料を加えたり、塩ではなく醤油で漬けたりする)を家の軒先に吊るした「腌肉(咸肉とも)」を各家庭で作り、それを少しずつ切り出して食べながら寒さを凌ぐ。やがて冬が明けて春になり、新しく生えてきたたけのこと腌肉を合わせて腌篤鮮にすることで、寒さを乗り越えまた新しい春を迎えられたことを祝す料理とするのである。 |
 | エビのポテト包み揚げ | 中国語版ではそのまま「金絲蝦球」。エビマヨの金身包み。 |
 | 大椀のお茶 | 中国語版では大碗茶(「碗」の字が違う)。飲み物そのものは文字通り大碗(どんぶり)に入れたお茶なのだが、特に都市部の屋台で売られる庶民的なお茶を指す。大碗茶は1970年代から北京に進出したが、中国の経済的発展に伴い価格が数分(1円未満)から数元(数十円程度)へ100倍ほど上昇したため、庶民でもわかりやすい同国の繁栄の象徴的なものでもあるようだ。 |
 | お米プリン | ライスプディング 。作中では留雲借風真君の発明なので璃月料理としたが、中国のみならず世界各地に見られる料理であり、中国語版でも外来語を用いて米饭布丁(お米のプディング)となっている。 。作中では留雲借風真君の発明なので璃月料理としたが、中国のみならず世界各地に見られる料理であり、中国語版でも外来語を用いて米饭布丁(お米のプディング)となっている。 |
 | お食べくだ菜 | 盆菜(ぼんさい、広東語でプーンチョイ)。広東省、特に香港で旧正月に食べられる料理で、本来はゲーム中の解説文の通り「どうぞお食べ下さい」と大人数で取り分けて食べるもの。ちなみに原語版の名前は「来来菜」で、七七のオリジナル料理「アシタナシ(没有未来菜)」は「来来」を「未来」をかけた駄洒落である。 |
 | かにみそ豆腐 | 中国語版ではそのまま「蟹黄豆腐」(シエファンドーフ)。北京料理の代表だが、江蘇料理などでも食べられる。廉価な店では高級なかにみそではなく鹹蛋(シエンタン、アヒルなどの塩漬け卵)を使うことが多い。 |
 | 黒背スズキの唐辛子煮込み | 四川料理の水煮魚(シュイジューイウ)。「水煮」は四川料理の調理方法の一つである。白身魚を豚肉にする「水煮肉片」もある。余談だが、四川料理の「水煮」は文字通りのあっさりしたイメージではなく唐辛子や花椒を使った刺激的なもの。中国人でもよく名前で勘違いすることが多い。 |
 | 米まんじゅう | 中国語版では米窝窝。中国北部で食されるトウモロコシ製蒸しパンの窩頭(ウォートウ)に、コーンミールではなく糯米を用いたものと思われる。 |
 | 四方平和 | 八宝飯 (はっぽうはん、パーパオファン)。甘味のある点心で、上海料理を中心に慶事の際に食べられる。 (はっぽうはん、パーパオファン)。甘味のある点心で、上海料理を中心に慶事の際に食べられる。 |
 | 椒椒鶏 | 椒麻鶏(ジャオマージー)か。四川料理の口水鶏(コウシェイジー、日本では「よだれ鶏」とも)とする説もある。 |
 | 翠玉福袋 | おそらく翡翠白菜餃子。ゲーム中では緑色の部分は野菜を使っているようだが、現実ではホウレンソウなどの緑色の色素で色付けした生地である。……と思われていたが、小型の品種の白菜を使用してその内部をくり抜き、それを器として使って作るということが公式による再現料理動画、「【原神】グルメの旅——「璃月グルメ集」第五期 」で判明した。中華料理の深奥とは真に深いものである。このシリーズ動画はこのページを見るような旅人には最高の動画なので是非見てほしい。 」で判明した。中華料理の深奥とは真に深いものである。このシリーズ動画はこのページを見るような旅人には最高の動画なので是非見てほしい。 |
 | 水晶蝦 | 蝦餃 (ハーガオ)。広東料理のエビ蒸し餃子。 (ハーガオ)。広東料理のエビ蒸し餃子。 |
 | 絶雲お焦げ | 「お焦げ」の部分は中国語版ではそのまま鍋巴 (グオパー)。釜底のお焦げを乾燥してキツネ色に揚げ、せんべいのようになったところに中華あんをかけて食べる四川料理。ゲーム中のグゥオパァーの由来である。 (グオパー)。釜底のお焦げを乾燥してキツネ色に揚げ、せんべいのようになったところに中華あんをかけて食べる四川料理。ゲーム中のグゥオパァーの由来である。 |
 | 仙跳牆 | 佛跳牆 (ぶっちょうしょう)。福建料理の高級スープ。豚やアヒルなどの脂身の少ない赤身肉や干しアワビやフカヒレなどの海産物の乾物等を惜しげもなく煮込んだ一品で、油分が少なく透き通った見た目が特徴。名前の由来は肉が禁忌な仏僧ですら垣根を飛び越えてくるほどおいしいとされることから。 (ぶっちょうしょう)。福建料理の高級スープ。豚やアヒルなどの脂身の少ない赤身肉や干しアワビやフカヒレなどの海産物の乾物等を惜しげもなく煮込んだ一品で、油分が少なく透き通った見た目が特徴。名前の由来は肉が禁忌な仏僧ですら垣根を飛び越えてくるほどおいしいとされることから。原神では仏僧のかわりに菜食主義であるはずの半仙、甘雨が飛びつきそうになっている。 |
 | 天枢肉 | 東坡肉 (トンポーロウ)。杭州の名物料理。ゲーム中では璃月の政治家である七星の地位の一つ「天枢」に由来するとされるが、現実でも政治家・文学者の蘇軾(蘇東坡)に由来すると言われる。見た目からピンと来るかもしれないが、その後沖縄でアレンジされてラフテー、いわゆる豚の角煮として日本でも親しまれる料理となった。 (トンポーロウ)。杭州の名物料理。ゲーム中では璃月の政治家である七星の地位の一つ「天枢」に由来するとされるが、現実でも政治家・文学者の蘇軾(蘇東坡)に由来すると言われる。見た目からピンと来るかもしれないが、その後沖縄でアレンジされてラフテー、いわゆる豚の角煮として日本でも親しまれる料理となった。 |
 | 中原のもつ焼き | 雜碎 (チャプスイ)。広東料理やアメリカ式中華のモツ料理。ゲーム中では串焼きだが、現実だと基本的に炒め料理である。ちなみに他の言語版だと、名前を罵倒語と勘違いされることがあるという一文があるのだが、「中原」(「ちゅうげん」、ゲーム中では「なかはら」)が中国の雅称であるのに対し、「雜碎」の方は間抜けという意味も持っているので、そのことを指していると思われる。 (チャプスイ)。広東料理やアメリカ式中華のモツ料理。ゲーム中では串焼きだが、現実だと基本的に炒め料理である。ちなみに他の言語版だと、名前を罵倒語と勘違いされることがあるという一文があるのだが、「中原」(「ちゅうげん」、ゲーム中では「なかはら」)が中国の雅称であるのに対し、「雜碎」の方は間抜けという意味も持っているので、そのことを指していると思われる。 |
 | ピリ辛蒸し饅頭 | 中国北部で食されるトウモロコシ製蒸しパンの窩頭(ウォートウ)に、辛味の豚肉を合わせたもの。 |
 | 明月の玉子 | 焼売 (しゅうまい、シャオマイ、広東語:シウマイ)。言うまでもなく日本で最も有名な中華料理の一つ。料理説明文にも「卵と小麦の皮で具を包み」とある通り、点心の本場である広東や香港では生地に卵黄を混ぜているため皮が黄色い。日本中華街でも戦後の物資不足で小麦粉生地の代わりに薄焼き卵を使った「黄色い焼売」が開発され現在でも売られている。 (しゅうまい、シャオマイ、広東語:シウマイ)。言うまでもなく日本で最も有名な中華料理の一つ。料理説明文にも「卵と小麦の皮で具を包み」とある通り、点心の本場である広東や香港では生地に卵黄を混ぜているため皮が黄色い。日本中華街でも戦後の物資不足で小麦粉生地の代わりに薄焼き卵を使った「黄色い焼売」が開発され現在でも売られている。 |
 | モラミート | 肉夾饃 (ロウジアモー)。陝西省の料理で「中華ハンバーガー」の別名がある。白吉饃(バイジーモー:平たい渦巻の形をした蒸しパン)で臘汁肉(ラージーロウ:煮込んだ豚肉)の細切りを挟んで作る。 (ロウジアモー)。陝西省の料理で「中華ハンバーガー」の別名がある。白吉饃(バイジーモー:平たい渦巻の形をした蒸しパン)で臘汁肉(ラージーロウ:煮込んだ豚肉)の細切りを挟んで作る。 |
 | ミントの和え物 | 中国語版だとそのまま「涼拌薄荷」。雲南省の料理。薄荷(ミント)は薬としても用いられる。 |
 | 璃月三糸 | 中国語版だとそのまま「扣三絲」(コウサンスー)。上海料理。鶏肉、卵、椎茸の三種の食材を糸のように細切りにして作られることから名付けられた。 |
 | 岩港三鮮 | 元ネタは中国東北部で一般的な料理の「地三鮮(ディーサンシェン)」と思われる。ピーマン、じゃがいも、茄子を素揚げし、豆鼓などで味付けしたもの。言葉の意味は「大地からの3つのおくりもの」くらいの意味。余談だが、ピーマン、ジャガイモ、茄子はすべてナス科の野菜である。 |
 | 玉紋茶葉蛋 | 材料のお茶やたまごの殻にひびが入っている説明から「茶叶蛋」がモチーフだと考えられる。日本の煮卵と比べるとたまり醬油の色が濃く、お茶の香りがする。ちなみに卵は固茹でが一般的である。 |
稲妻料理 
稲妻料理は元ネタとなった地域から和食を元ネタにした料理が多い。伝統的な料理もあれば、中国から渡り日本で変化したラーメン、比較的近年に誕生したオムライスやキャラ弁等これまた多岐にわたる。
| 画像 | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
 | 真味茶漬け | 放浪者のオリジナル料理。シンプルなお茶漬け。スメール料理はインディカ米が使われているが、こちらはジャポニカ米である。つまりわざわざ輸入している。 「真味」とは素材本来の味という意味であり、説明文でも料理スキルを褒められている。 中国公式のレシピ*1によれば鰻は埋まっているそう。このスタイルの元ネタは島根あたりの郷土料理うずめ飯  だと思われる。 だと思われる。散々「放浪者がウナギだけ食った」とか「魚が嫌いで捨てた」だとかの風説が飛び交っていたが、実際は更に手間をかけて丁寧な料理にしていたという落ちであった。 |
 | 雨奇晴好 | 楓原万葉のオリジナル料理。秋刀魚の開きの干物を焼いたものに大根おろしを添えたものだろう。「雨奇晴好」は北宋の文学者・政治家の蘇軾の詩に由来する四字熟語で、どんな気候でも映えるような美しい風景を指す。 |
 | うなぎの蒲焼 | 美味しそうなうなぎの蒲焼。説明文を見るに、関東式のやり方のようだ(関東では蒸すが、関西では蒸すことがない)。 |
 | オムライス | なぜ稲妻料理欄に? と思われるかもしれないが、実は現実のオムライスも戦前の洋食店が由来の日本料理だったりする。発祥の店については大阪心斎橋の「北極星」や東京銀座の「煉瓦亭」など諸説ある。 |
 | オムライス・ワルツ | 久岐忍のオリジナル料理。こちらは「ドレス・ド・オムライス」。1958年創業の老舗洋食店「紅亭」によって、1997年~1998年頃に「特製オムライス」として考案されたもの。雑誌等を通じブームになったのは2010年代後半頃からだが、その歴史は意外と古い。 |
 | 活力にゃんこ飯 | キャラ弁 が元ネタと思われる。日本では弁当やたこさんウインナーなどはそれほど珍しいものではないが、海外では日本特有の文化として知られている。本格的なキャラ弁は70年代~90年代に料理研究家や料理評論家によって作られ始め、その後2000年代にブログの普及によって一般の主婦層の間で優れたキャラ弁が作られるようになったと言われる。 が元ネタと思われる。日本では弁当やたこさんウインナーなどはそれほど珍しいものではないが、海外では日本特有の文化として知られている。本格的なキャラ弁は70年代~90年代に料理研究家や料理評論家によって作られ始め、その後2000年代にブログの普及によって一般の主婦層の間で優れたキャラ弁が作られるようになったと言われる。 |
 | カニのバター添え | 中国語版は「黄油蟹蟹」となっており、香港名物の黄油蟹(イエロー・バター・クラブ)とほぼ同じ名前である。ただし、画像や稲妻(日本)料理であることを考慮すると、普通に日本で食されるカニのバター焼きのようだ。 |
 | 紺田煮 | 筑前煮 。ごった煮ともかかっているかもしれない。 。ごった煮ともかかっているかもしれない。 |
 | 「奇策」 | 珊瑚宮心海のオリジナル料理。茶巾寿司。ちなみに説明文中で形を喩えられている「袂落とし」は原文では「錦嚢」(錦の袋)となっており、『三国志演義』で孔明が立てる「錦嚢の計」が元ネタとなっていると思われる。 |
 | 強者の道のり | 荒瀧一斗のオリジナル料理。元の料理は焼きそば。説明文には料理の説明は書かれていないが、どう見ても焼きそばパン。不良が子分に買いに行かせる食べ物として有名だが元ネタははっきりしない。炭水化物に炭水化物をトッピングした見た目通り、値段のわりにボリュームがあり、金のない学生の食べ物として実際にポピュラーだったので、学校生活を彷彿とさせるモチーフとして自然発生的に使われるようになったのではないか、と言われている。 |
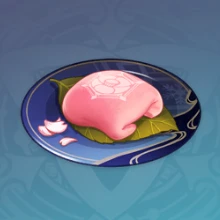 | 紅炉一点雪 | 神里綾華のオリジナル料理。長命寺風(関東風桜餅)の変種であるふくさ包みという形状の桜餅で、銀座あけぼのの季節菓子「さくらもち」が有名。白玉粉を入れた生地で包まれているため、しっとりとした食感なのが特徴と言われている。ちなみに「紅炉一点雪」(原典では紅炉上一点雪)は禅宗の語録『碧巌録 』の言葉で、戦国時代の武将・龍造寺隆信の辞世とされている(武田信玄が川中島の戦いの時に引用したとする説もある)。 』の言葉で、戦国時代の武将・龍造寺隆信の辞世とされている(武田信玄が川中島の戦いの時に引用したとする説もある)。 |
 | 魚とダイコンの煮込み | 魚と大根の煮付けは色々あるが、見た目からして富山県発祥の郷土料理ぶり大根と思われる。完璧版の「極寒、波、雷の試練を乗り越えた魚は鍋に飛び込み」という一文は、鰤起こし(11月半ば~12月に北陸の海岸で起こる雷で、この後にブリが豊漁になると言われる)やブリが出世魚であることを指したものであろう。 |
 | 獣骨ラーメン | 英語版ではそのまま「豚骨ラーメン」。 |
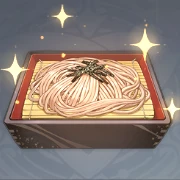 | そば | ゲーム上の事情で仕方ないのだが、小麦粉のみで作られた蕎麦、つまりゼロ割蕎麦…というかひやむぎである。 」(ソーキ=豚のスペリアブを載せてソーキそばと呼ばれることも多い)のことを単に「そば」「すば」と言い、逆に蕎麦粉を使用したそばの方を「ヤマトそば」等として区別する。 」(ソーキ=豚のスペリアブを載せてソーキそばと呼ばれることも多い)のことを単に「そば」「すば」と言い、逆に蕎麦粉を使用したそばの方を「ヤマトそば」等として区別する。 |
 | 団子牛乳 | 詳細不明。タピオカミルクティー の稲妻版だろうか? とか言われていたが、後に袖から本物を取り出すお兄様が実装されてしまった。 の稲妻版だろうか? とか言われていたが、後に袖から本物を取り出すお兄様が実装されてしまった。 |
 | 渡来鳥肉 | チキン南蛮 。南蛮漬けのように甘酢に漬けた揚げ鳥にタルタルソースをかけた一品。作中ではフォンテーヌ人によってもたらされた料理だが、現実のチキン南蛮は日本生まれ。発祥店こそ2つの説があるが、どちらも宮崎県延岡市の洋食店「ロンドン」で修行していた料理人が独立した際、当時提供されていた賄い料理(甘酢漬けにした衣つき揚げ鶏)をアレンジして売り出したという筋書きになっている。 。南蛮漬けのように甘酢に漬けた揚げ鳥にタルタルソースをかけた一品。作中ではフォンテーヌ人によってもたらされた料理だが、現実のチキン南蛮は日本生まれ。発祥店こそ2つの説があるが、どちらも宮崎県延岡市の洋食店「ロンドン」で修行していた料理人が独立した際、当時提供されていた賄い料理(甘酢漬けにした衣つき揚げ鶏)をアレンジして売り出したという筋書きになっている。 |
 | 緋櫻餅 | 桜餅 。桜餅には長命寺風(関東風)と道明寺風(関西風)の二種類あるが、こちらは東京・向島の老舗「長命寺桜もち」発祥の長命寺風の方(ただし本家のは桜色ではなく白い)。余談だが、神里綾華の伝説任務によれば、「ひざくらもち」ではなく「ひおうもち」と読む。 。桜餅には長命寺風(関東風)と道明寺風(関西風)の二種類あるが、こちらは東京・向島の老舗「長命寺桜もち」発祥の長命寺風の方(ただし本家のは桜色ではなく白い)。余談だが、神里綾華の伝説任務によれば、「ひざくらもち」ではなく「ひおうもち」と読む。なお、「餅」とはいうが長明寺の桜餅はもち米は使っておらず、小麦粉を水で溶いたものを焼いた薄い生地なのでどちらかというとクレープに近い。西日本で一般的な道明寺スタイル(内外が逆転したおはぎのようなほう)は道明寺粉という蒸したあとに乾燥させたもち米を石臼で粗く挽いたものを用いる。 |
 | 干物の網焼き | 日本語版では魚の種類がわからないのだが、中国語版では鮎と指定されている。 |
 | 唯一の真相 | 鹿野院平蔵のオリジナル料理。元の料理はカツサンド。説明文には料理の説明は書かれていないが、どう見てもカツ丼。材料に米も卵もなしでどうやって……? ちなみに、「刑事が取り調べ中にカツ丼を振る舞う」というイメージの源流は意外にもはっきりしていない。よく元ネタとして紹介される1955年公開の映画『警察日記』にあるのは、実際には取り調べ後に天丼を振る舞うシーンらしく、1963年の「吉展ちゃん誘拐殺人事件」の取り調べ中刑事がカツ丼を御馳走したという噂は刑事本人が否定している。ついでに言えば、日本国内の現行法では、取り調べ中の飲食の許可は自白の誘導に当たるとされ禁じられている。 |
 | 夕暮れの鯛焼き | 説明文の歴史は大体史実通り。1909年(明治42年)に東京で創業した浪花家総本店が発祥で、 最初はただの丸い今川焼きを販売したところ売れ行きが悪かったために鯛の形の鯛焼きを売り出したところ、大ヒットしたそうだ。画像では中身の「あんこ」は光沢のあるジャムに近いものになっているが、現実の小豆のつぶあんに似せたのか粒状の果実も見える。夕暮れの実の元ネタはカシューアップル (カシューナッツが取れる木の果実)説が最も有力だが、レンブ (カシューナッツが取れる木の果実)説が最も有力だが、レンブ (ジャワフトモモの果実)とする説もある。 (ジャワフトモモの果実)とする説もある。 |
 | ラズベリー水まんじゅう | 名前や画像、製法からして岐阜県大垣市の名物である水まんじゅうと思われる。中身に小豆餡ではなく、ラズベリーもしくはラズベリー餡を使用したタイプのようだ。 |
スメール料理 
スメール料理は元ネタとなった地域からインドや中東、エジプト料理を元ネタにした料理が多い。Ver3.1現在ゲーム内で調理できるものはあまり日本では馴染みがないものが多いため、それらの食文化を探究するのもいいだろう。
| 画像 | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
 | アアルコシャリ | 元ネタはコシャリ 。エジプトでよく食べられている混ぜご飯で、国民食的な存在。コシャリは混ぜるという意味を持ち、その名の通りご飯にパスタ、マカロニ、ひよこ豆などを加え、トマトソースをかけてごちゃ混ぜにした料理である。 。エジプトでよく食べられている混ぜご飯で、国民食的な存在。コシャリは混ぜるという意味を持ち、その名の通りご飯にパスタ、マカロニ、ひよこ豆などを加え、トマトソースをかけてごちゃ混ぜにした料理である。 |
 | 雨林サラダ | 中東のサラダは地域によって入れる材料が違い、バリエーションも名前も様々。その中でもこれに近いのがパセリを主体とした中東レヴァント地方のサラダダッブーレ 。パセリは料理の添え物としてのイメージが強いが、中東では主菜として食べられている。 。パセリは料理の添え物としてのイメージが強いが、中東では主菜として食べられている。 |
 | エルマイト鍋 | モロッコ料理のタジン。タジン鍋という円錐形の蓋が特徴的な土鍋を使う。ゲーム内説明文にもある通り、この蓋によって食材から発生した蒸気や香気を受け止め、上部で冷やしてまた水に戻すことで、少ない水で蒸し料理や煮込み料理ができる。日本で手に入るものは蓋も土鍋のものもあるが、収納時この蓋は非常に邪魔なため、蓋が耐熱シリコーンになっているものも多い。非使用時はシリコーンなので折りたたんで収納できる。 |
 | カレーシュリムプ | インド本国での名称は“プラウンマサラ”。シュリムプは英語のShrimp(エビ)の音写だがシュリンプと書くことの方が多い。 |
 | 決闘の魂 | セノのオリジナル料理、元はタフチーン。ピラミッド状の見た目だが、やはり直接の元ネタは『遊戯王』で登場する重要アイテム「千年パズル」の方だろう。実際、作中では主人公の魂、つまり決闘者(デュエリスト)の魂が封じ込められている為、名前も込みでネタと言える。これを食べれば、決闘の王になれるかも知れない。 |
 | 香味ミートロール | シリア・レバノン周辺の料理クッバ 。クッベやキッベなどとも書く。スパイスで味付けしたひき肉をブルグルと呼ばれる挽いた小麦で包んで揚げたもの。 。クッベやキッベなどとも書く。スパイスで味付けしたひき肉をブルグルと呼ばれる挽いた小麦で包んで揚げたもの。 |
 | タフチーン | 元ネタはイランの家庭料理タフチーン。タフチーンとはペルシャ語で「底に並べる」という意味。その名の通り鶏肉のヨーグルト漬けなどの具を鍋に敷き詰めたあと、その調味液と混ぜたご飯を流し込んで焼き上げる。最後は鍋をひっくり返してケーキ状に皿に盛り付けることが多いが、実際にニィロウが待機画面で頬張っている姿はケーキそっくり。 |
 | デーツナン | 元ネタはチャコールパンケーキ。ココナッツの殻の炭を練り込んだ黒いパンケーキで、ハワイで流行中。なおこの料理は中国語版では椰炭饼、英語版はCoconut Charcoal Cakeとあり、インド料理のナンに絡めた翻訳をしているのは日本語版だけ。 |
 | ナツメヤシキャンディ | 中東・南アジアの伝統的な砂糖菓子であるハルヴァ、もしくはその原型であるハビースが元ネタと考えられる。ちなみに、このハルヴァがフランスに渡りヌガーの由来となったとされる。 |
 | バターチキン | 日本では主にバターチキンカレーと呼ばれているが、インド本国での名称は“ムルグマカニ”。実は1950年ごろに発明されたかなり新しい料理。 |
 | パティサラプリン | 中東諸国で広く食されているプリンに似たデザート、トルコ語ではムハレビ、アラビア語ではムバッラビーヤと呼ばれている。ミルクに砂糖を入れて煮詰め、お米のデンプンで固めて、その上にバラの花のシロップをかけていただく。 |
 | マサラチーズボール | 元ネタはパニールコフタというチーズボール、インドではカレーの具として食される。パニールというインドのチーズを茹でたじゃがいもに混ぜて、丸く成形して揚げる。ちなみにこの場合のマサラはインドで用いる混合香辛料のこと(例:ガラムマサラ)であって、「まっさら」が由来のさよならバイバイされる町ではない。 |
 | シャフリサブスシチュー | 元ネタはゴルメサブズイ と考えられる。ドライハーブと豆類をたっぷり使って煮込んだイランやアゼルバイジャンのシチュー料理。ゴルメは煮込み、サブズィは香草を意味する。 と考えられる。ドライハーブと豆類をたっぷり使って煮込んだイランやアゼルバイジャンのシチュー料理。ゴルメは煮込み、サブズィは香草を意味する。 |
 | ピタ | そのまんまピタという名前で中東を中心に広く食べられている、ポケット状になったパンの一種。日本ではピタパンとも呼ばれ、ドネルケバブの屋台などで目にする事ができる。その歴史は古く、イタリアでピザの語源になったとも言われる。具を入れるのが前提の形状であるが単にピタと言った場合は具は含まない。 |
 | バクラヴァ | バクラヴァ とはギリシャやトルコ、イランなど地中海東部~中東あたりで親しまれる甘いお菓子。油と小麦粉で作るフィロ生地(パイのようなもの)の間にピスタチオやクルミなどの砕いたナッツ(原神のものは緑色なのでピスタチオのバクラヴァのようだ)を挟んで焼き上げ、焼き上がったところにローズウォーターやレモンなどを使用したシロップをたっぷりかけて染み込ませたもの。 とはギリシャやトルコ、イランなど地中海東部~中東あたりで親しまれる甘いお菓子。油と小麦粉で作るフィロ生地(パイのようなもの)の間にピスタチオやクルミなどの砕いたナッツ(原神のものは緑色なのでピスタチオのバクラヴァのようだ)を挟んで焼き上げ、焼き上がったところにローズウォーターやレモンなどを使用したシロップをたっぷりかけて染み込ませたもの。フィロ生地に染み込んだシロップが噛むと溢れ出し、とても甘い。 ちなみに、これに限らずイスラムのお菓子は本当に容赦なく甘いが、これはイスラムの戒律で飲酒は制限されているため、代わりにコーヒーとお菓子が嗜好食品の主役となったのが理由。 |
フォンテーヌ料理 
フォンテーヌは主にフランスとイギリスがモデル、従ってフォンテーヌ料理も主にフランス料理とイギリス料理が元になっている。料理まで二面性の国……フランス由来の繊細な料理とイギリス由来の素朴な料理、モンド地域とはまた違ったヨーロッパ料理に触れることができるだろう。
| 画像 | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
 | 鴨肉のコンフィ | 鴨肉のコンフィ。フランス料理の「コンフィ(confit)」は何かしらの液体に漬ける調理方法を指す。具体的な加工手順として全く異なる2種類が同じ名で呼ばれているが、この料理の場合は水鳥の肉等を低温の脂の中でゆっくり加熱する方法をしてコンフィと呼んでいる。もう一つの「コンフィ」は果物を砂糖漬けにしたもので、フランス南東端に位置するプロヴァンスの名物菓子としてよく知られている。 |
 | クレームクレープシュゼット | クレープシュゼット 。うす焼きにしたクレープを四つ折りにして、砂糖とバター、グランマルニエ(オレンジのリキュール)をベースにして作られるソースをかけたデザート。添え物としてアイスクリームや果物のコンポートなどを添える。名前の由来についてはイギリス皇太子だったエドワード7世の恋人シュゼットに由来するという説がある。ソースのアルコール分を飛ばす際にフランベすることが特徴で、提供する際には香りを保つためとパフォーマンスのため客の目の前で調理することも多い。 。うす焼きにしたクレープを四つ折りにして、砂糖とバター、グランマルニエ(オレンジのリキュール)をベースにして作られるソースをかけたデザート。添え物としてアイスクリームや果物のコンポートなどを添える。名前の由来についてはイギリス皇太子だったエドワード7世の恋人シュゼットに由来するという説がある。ソースのアルコール分を飛ばす際にフランベすることが特徴で、提供する際には香りを保つためとパフォーマンスのため客の目の前で調理することも多い。 |
 | 晶螺マドレーヌ | マドレーヌ 。ホタテの貝殻を模した型を使用する焼き菓子で、フランス北東部にあるロレーヌ地方コメルシーの名物。発祥は諸説あるが、雇われ料理人のマドレーヌ・シナモン、ロレーヌ公の召使マドレーヌ・ポルミエ、果てはマグダラのマリア*2など、いずれも「マドレーヌ」という女性の名前が関わる逸話に関係しているようだ。 。ホタテの貝殻を模した型を使用する焼き菓子で、フランス北東部にあるロレーヌ地方コメルシーの名物。発祥は諸説あるが、雇われ料理人のマドレーヌ・シナモン、ロレーヌ公の召使マドレーヌ・ポルミエ、果てはマグダラのマリア*2など、いずれも「マドレーヌ」という女性の名前が関わる逸話に関係しているようだ。 |
 | タルタルタワー | タルタルステーキ 。牛肉か馬肉をみじん切りにして味付けし、生肉のまま薬味や卵黄と混ぜて食べる料理。タルタルとは東ヨーロッパの人々がモンゴル帝国の遊牧民を指して言った「タタール」が訛ったもの。 。牛肉か馬肉をみじん切りにして味付けし、生肉のまま薬味や卵黄と混ぜて食べる料理。タルタルとは東ヨーロッパの人々がモンゴル帝国の遊牧民を指して言った「タタール」が訛ったもの。 |
 | ハギス | ハギス 。スコットランドの伝統料理。羊の内臓を香草や玉葱やオート麦と一緒に羊の胃袋に詰め、茹でたり蒸したりして作る。ゲーム内画像のように皿に盛り付ける前は非常にグロテスクな見た目だが、現地ではポピュラーな料理のようで、脂の効いた非常に濃厚な味わいは現地名産のスコッチウイスキーにとって最高のつまみになるらしい。ただ、オーツ麦の粘り気や内蔵の臭いなど、少なからず人を選ぶ料理であり、仏、独、露が会談中に当時の仏大統領が「あんなもん(ハギス)食ってる奴ら信頼できるわけない」と言ったところ、当の英外務大臣が「ハギスについてはごもっとも」と発言して外交問題を回避したという逸話すらある恐ろしい料理である。 。スコットランドの伝統料理。羊の内臓を香草や玉葱やオート麦と一緒に羊の胃袋に詰め、茹でたり蒸したりして作る。ゲーム内画像のように皿に盛り付ける前は非常にグロテスクな見た目だが、現地ではポピュラーな料理のようで、脂の効いた非常に濃厚な味わいは現地名産のスコッチウイスキーにとって最高のつまみになるらしい。ただ、オーツ麦の粘り気や内蔵の臭いなど、少なからず人を選ぶ料理であり、仏、独、露が会談中に当時の仏大統領が「あんなもん(ハギス)食ってる奴ら信頼できるわけない」と言ったところ、当の英外務大臣が「ハギスについてはごもっとも」と発言して外交問題を回避したという逸話すらある恐ろしい料理である。 |
 | ポワソンチャンティー・パイ | スターゲイジーパイ 。冗談みたいな見た目だが、16世紀のイギリス南西のマウゼル村の漁師トム・バーコックの伝説に由来するとされる伝統ある料理。ある年の冬、嵐によって長期間漁が阻まれて村全体が飢えに直面する中、バーコックはたった一人で荒れ狂う海に挑み、そして大量の魚を捕らえ帰還した。村人が歓喜する中、バーコックはちゃんと魚を捕ってきたことの証として、あえて魚が突き出すように整えた巨大なパイを焼き上げ、村民に振舞ったという。こういった伝承に基づき、現在でも毎年12月23日の「トム・バーコックス・イブ」という祭りにて、彼の勇気を称えてスターゲイジーパイが食されている。 。冗談みたいな見た目だが、16世紀のイギリス南西のマウゼル村の漁師トム・バーコックの伝説に由来するとされる伝統ある料理。ある年の冬、嵐によって長期間漁が阻まれて村全体が飢えに直面する中、バーコックはたった一人で荒れ狂う海に挑み、そして大量の魚を捕らえ帰還した。村人が歓喜する中、バーコックはちゃんと魚を捕ってきたことの証として、あえて魚が突き出すように整えた巨大なパイを焼き上げ、村民に振舞ったという。こういった伝承に基づき、現在でも毎年12月23日の「トム・バーコックス・イブ」という祭りにて、彼の勇気を称えてスターゲイジーパイが食されている。 |
 | フォカロルスのために | オペラ 。フランス発祥のチョコレートケーキ。ガトーショコラの一種。日本でも色々な洋菓子店で取り扱いがあるが、オリジナルはフランスでルイ14世のお抱え料理人だったダロワイヨ一族の系譜を引く食品メーカー「ダロワイヨ 。フランス発祥のチョコレートケーキ。ガトーショコラの一種。日本でも色々な洋菓子店で取り扱いがあるが、オリジナルはフランスでルイ14世のお抱え料理人だったダロワイヨ一族の系譜を引く食品メーカー「ダロワイヨ 」社の職人が開発したもの。レシピによって何層重ねるかはまちまちだが、オリジナルは7層らしい。 」社の職人が開発したもの。レシピによって何層重ねるかはまちまちだが、オリジナルは7層らしい。日本ユーザーの間ではどちらもコーヒーを使用したケーキなこともあり、「オペラ」説と「ティラミス」説が混在していたが、外見の特徴・材料・説明文などからほぼオペラで確定。 まず外見として、断面の層がクッキリと出ていることが一つ。ティラミスも層が出る、という意見については日本のティラミスはスポンジ生地にコーヒー味のシロップを吸わせて作った物が多いが、本来のティラミスはフィンガービスケットの一種であるサヴォイア風ビスケットを使用するので断面がきれいな層になることはない。スポンジを使用した日本でよくあるティラミスは厳密にはティラミスではない「ティラミス風ケーキ」である。 材料については、ゲーム内でアーモンド(杏仁)を使用するが、実際のケーキでもティラミスはアーモンドを使用しないがオペラはアーモンドを大量に使用する(ビスキュイ・ジョコンドという大量のアーモンドを練り込んだ生地を使うため。この生地はシロップを吸ってもスポンジのようにビチャビチャになりにくい)。 そして説明文で、「コーヒーとアーモンドの香り」とあるように、コーヒーの香りに負けないほどの量のアーモンドが使用されていることからも、これがオペラであるという証明になる。「絶え間なく展開する壮大華麗な過激に引き込まれたかのよう」という説明もオペラを連想させる。 |
 | フィッシュアンドチップス | フィッシュ・アンド・チップス 。イギリス定番のおつまみ、軽食、ジャンクフード。イギリスではあちこちで購入でき、深く生活に馴染んでいる。が、「白身魚(主にタラの仲間かヒラメ・カレイの仲間)の切り身に小麦粉を使った生地をつけて揚げたものにフライドポテト(キングス・イングリッシュではこちらがポテトチップス。日本人がイメージするポテチのほうはクリスプス等と呼ばれる)を添えたもの」以上の定義がないので店によってレシピは千差万別であり、またソースも原神ではタルタルソースが添えられているが、本国ではモルトビネガー(独特のクセとコクのある酢)だったりレモン絞ったりライム絞ったりとかなりまちまち。そして美味しさもピンキリだそうで……。幸い、根本的にレシピが破綻しているウナギゼリーなどとは違ってちゃんと調理すれば真っ当に美味しい料理なので、日本で食べるフィッシュアンドチップスが不味いということはそうそうないだろう。 日本だと近年店舗を増やしているHUB等で確実に食べることができる。 なお、イギリスでは本当にたくさん店舗があるぶん廃油も大量に出るため、この廃油をバイオディーゼル燃料の材料にしている。 。イギリス定番のおつまみ、軽食、ジャンクフード。イギリスではあちこちで購入でき、深く生活に馴染んでいる。が、「白身魚(主にタラの仲間かヒラメ・カレイの仲間)の切り身に小麦粉を使った生地をつけて揚げたものにフライドポテト(キングス・イングリッシュではこちらがポテトチップス。日本人がイメージするポテチのほうはクリスプス等と呼ばれる)を添えたもの」以上の定義がないので店によってレシピは千差万別であり、またソースも原神ではタルタルソースが添えられているが、本国ではモルトビネガー(独特のクセとコクのある酢)だったりレモン絞ったりライム絞ったりとかなりまちまち。そして美味しさもピンキリだそうで……。幸い、根本的にレシピが破綻しているウナギゼリーなどとは違ってちゃんと調理すれば真っ当に美味しい料理なので、日本で食べるフィッシュアンドチップスが不味いということはそうそうないだろう。 日本だと近年店舗を増やしているHUB等で確実に食べることができる。 なお、イギリスでは本当にたくさん店舗があるぶん廃油も大量に出るため、この廃油をバイオディーゼル燃料の材料にしている。 |
外部リンク(参考文献) 
- 「食欲の秋」テイワット料理再現コンテスト
 (原神公式、2021年9月~10月)
(原神公式、2021年9月~10月) - 〈原神の料理解説第一回〉 星5料理『仙跳牆』

- 〈原神の料理解説第2回〉 星3料理『四方平和』

- 〈原神の料理解説第3回〉 星2料理『鳥肉のスイートフラワー漬け焼き』

- 〈原神の料理解説第4回〉星3料理「風神ヒュッツポット」

- Genshin Impact Wiki: Food
 (英語)
(英語) - Genshin’s Liyue Food
 (英語)
(英語) - The Inn at the Crossroads: Honeyed Chicken
 (英語)
(英語) - Moon Pie from Genshin Impact (French Pithivier)
 (英語)
(英語) - 舌尖上的原神:来来菜、大碗茶、渔人吐司与满足沙拉
 (中国語)
(中国語)
コメント 
コメント投稿ルール
誰もが快適にコメント欄を利用できるように、他人を傷つけない投稿を心がけましょう。
不平不満は愚痴掲示板へ。
- リーク情報、キャラクターや他者に対する誹謗中傷、バグ悪用の推奨等は、投稿・編集ガイドラインで禁止されています。
- 不適切な投稿は、反応したり相手にしたりせずに、zawazawaにログインして通報
 (推奨)、または管理連絡掲示板で報告してください。
(推奨)、または管理連絡掲示板で報告してください。 - 悪質な場合は管理者より警告・投稿規制等の措置を行います。
- 不快なコメントに対しては、日付横の通行止めマーク🚫をクリックすることで、その投稿者のコメント全てを非表示にできます。
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ
・シャルロットはスポンジケーキやビスケット等を型に貼り付けてその中にババロアやフルーツなどを詰め、大きな平たいお皿に丸ごと盛り付けてリボンをかけるまさに帽子のような見た目のお菓子。フランス人シェフのアントナン・カレームがロシア皇帝アレクサンドル1世のに仕えている際に考案したもの。
・クグロフはシフォンケーキのように真ん中に穴の開いた王冠型のようなフランス・オーストリアなどで食べられる焼き菓子。マリーアントワネットの好物で、オーストリアからフランスに嫁入りする際に持ち込んだという説がある。
見た目的には圧倒的にシャルロットケーキなんですが背景事情考えるとクグロフがずっと捨てきれないんですよね…… -- 2024-02-01 (木) 04:46:09